http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1095.html
| Tweet | �@ |
(��: �ǂ����悤���Ȃ��_���X�s�[�J�[ JBL 4343 ���o�J���ꂵ�����R ���e�� ���엲 ���� 2019 �N 4 �� 10 �� 05:36:16)
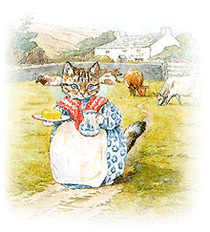
JBL �n�[�c�t�B�[���h �I���W�i��
JBL Hartsfield - YouTube ����
https://www.youtube.com/results?search_query=+JBL++Hartsfield
��������
�n�[�c�t�B�[���h
�͂��߂ĕ����I�[���z�[���V�X�e��(�n�[�c�t�B�[���h)�ł������A�ł���ۂɎc�����̂́A�J�U���X�̃x�[�g�[���F���ł�(Philips;�@�z���V���t�X�L�[�Ƃ����1958�N�̘^��)�B ����CD�͕��ʂɕ����Ƙ^�����Ȃ�Ƃ��������ŁA�J�U���X�̉����j���̂悤�ɕ������܂��B
�ꌾ�ł����ƁA���F�̕\���͂��������ł��B�͂����茾���āA����CD������ȉ��Ŗ�Ƃ́A���S�ɑz���͈̔͊O�̉��ł����B�J�U���X�͐������t�Ƃ��Ǝv���Ă��܂������A���̃V�X�e���ŕ������J�U���X�̐����Ƃ����̂͌��t�ŕ\������͕̂s�\�ł��B���͂ł͂Ȃ��A���̕\���͂̕��ł��B
�s�̂̃n�C�G���h�X�s�[�J�[�ɂ́A�N���V�b�N�����Ə̂���A�����ȉ����o�������\�̂Ȃ��悤�ȃX�s�[�J�[����������܂����A���̈�ۂł́A���̃z�[���V�X�e�������N���V�b�N�����ł��B�o�C�I�������t�Ȃ��܂������A�o�C�I�����̉��́A�t�҂̗͗ʂ𗇂ɂ���悤�ȃV�r�A��(���m��)�Đ����Ǝv���܂����B
�{���A�z�[���̉��t�ł́A�t�҂͗��ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B�ȑO����A(���ʂ̃V�X�e����)�^��-�Đ��Ƃ����ߒ����o��ƁA�Ȃɂ����ł����`���Ȃ����y�I�ȉ������������Ă��܂��Ɗ����Ă��܂������A���������������₷���������Đ������ۂł����B�܂��A�{�[�J�������ƁA�̎肪�}�C�N��ʂ��ĉ̂��Ă���Ƃ������Ƃ��A�͂�����`���܂��B
����ɁA�ǂ���Ă������܂������Af(�t�H���e)����Ap(�s�A�m)�ɕω������Ƃ��Ap���{����p�炵���������܂��Bp�ɂȂ��Ă������r�ꂸ�A�Z���͂����銴���ł��B
���ƃI�[�f�B�I�̊���
����͒m�荇���̊y��E�l�̕��ɕ������b�ł����A���̐E�l����̒m�l�ɐq��Ȃ炴��LP�}�j�A���I�[�f�B�I�}�j�A�̕������������邻���ł��B�V�Q�e�B��LP�����߂ă��[���b�p�ɂ܂ő����^�Ԃ悤�ȕ��ł��B�I�[�f�B�I�ɂ��������z��1000���~���Ă���A���̐E�l����͂��Ƃ��邲�ƂɁu�����̉Ƃŕ����Ă��������v�ƗU���č����Ă����Ƃ������b�ł����B
�ŁA����Ƃ��A���̃}�j�A�̕����E�l����̍H�[�ɖK�ꂽ�炵���̂ł��B���̂Ƃ��͂��傤�ǃ��@�C�I���j�X�g���H�[�Ŋy������t���Ă���Ƃ���ł����B��������}�j�A�̕����H���A
�u���킠�[�A���@�C�I�������āA����ȉ�������B���߂Đ��ŕ����܂����v
��ɏq�ׂ��n�[�c�t�B�[���h���O�́A���������āA�I�[�f�B�I�Đ��Ŋ��������߂�Ƃ������Ƃɉ������܂������̂������Ă��܂����B ���o�I�Ɍ����A�I�[�f�B�I�ŕ������y�ŕʂɊ����͂���Ȃ��A�I�[�f�B�I�͊��ɐ��̒��ɂ��Ȃ����j�I���t�Ƃ̈�[���u�m��v���߂̎�i�ɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
���A�n�[�c�t�B�[���h�ŁA�J�U���X�ɔ��Ɋ��������̂ł����A��Ɏ����̂킩��Ȃ��ߋ��̉��t�Ƃ́A������ł́u�^���炵�����́v��Nj����A���ʂƂ��ĕ����Ă��āA�܂�Ȃ����ɂȂ邮�炢��������A�����̕Ȃ����낤�Ƃ��A���邢�͉��Ɏ������֒����ꂽ���̂ł���\���������Ă��A���y�I�Ȋ������V�X�e���̂ق�����قlj��l������Ƃ����C�����܂����B
http://www.geocities.co.jp/MusicHall-Horn/3384/audio/favorite.html
��������
JBL_Hartzfield �`JBL�t�����̌���`
�����t�I�N�ɂāAJBL�̂��̃n�[�c�t�B�[���h���݂��܂����B
�n�[�c�t�B�[���h�́A�^���m�C�̃I�[�g�O���t�ƕ��сA���m����������\����R�[�i�[�^�I�[���z�[���V�X�e���ł��B
James B. Lansing����Ђ𗧂��グ���̂�1927�N�ł����A���̍��̓A���e�b�N�Ђɋz�����ꂽ��i�Ȃ̂ŃA���e�b�N�E�����V���O���Č�����ł��j�A�E�F�X�^���̉�������������肵�Ă��܂����B
1946�N��JBL�ЂƂ��ēƗ����܂��āA��ɏ��̉ƒ�p�t���A�X�s�[�J�[�ł���n�[�c�t�B�[���h���a�����܂��B�n�[�c�t�B�[���h��JBL���甭�����ꂽ���̂�1954�N�̂��ƂŁA55�N�ɂ̓��C�t���Ŗ��̋��ɂ̃X�s�[�J�Ƃ��ďЉ��܂����B���傤�ǃ}�����c�Ђ��ł���Model1���������ł��A���ł�50�N�ȏオ�o���Ă��܂��ˁB
�n�[�c�t�B�[���h�͔����ʃ��m�ł�������A���X�g�A����Ă�����A�I���W�i���ł�����^�ƂȂ�ƃz�[�����ȗ������ꂽ��ƁA�Ȃ��Ȃ������̃I���W�i���̂��̂�����܂��A����̂��̂͏����̃I���W�i�����������ł��B
���n�[�c�t�B�[���h�́A����JBL�ŊJ�����ꂽ���̂ł͂���܂���A���삪��̌������̃E�B���A���EL�E�n�[�c�t�B�[���h�����J���������̂ł��B�ނ́A���V���g��DC�ɂ��鐭�{�g�D�̕W���K�i�ǂɋΖ����Ă���A��ŃN���v�b�V���z�[����Ǝ��Ƀ��f�B�t�@�C�����R�[�i�[�^�z�[��������Ă��܂����B
���荇�킹�Ƃ͊�Ȃ��̂ŁA�������C�݂ɏZ��ł���JBL�̔̔��S���d���ł�����RayPepe��AES�œ��������ƂȂ����n�[�c�t�B�[���h�Əo��A�ނ̑g�X�s�[�J�[�V�X�e����m�邱�ƂɂȂ����̂ł��B����p�ň�ʂɔ�������Ă��Ȃ������A150-4C/38�p�E�[�n�A375�h���C�o���n�[�c�t�B�[���h���̎�ɓn��AD30085�n�[�c�t�B�[���h���J������邱�ƂɂȂ����̂ł��B
�^�Ԃ�D30085�Ƃ����̂͂́A30�Ԃ̃G���N���[�W����085�Ƃ������j�b�g�V�X�e�������߂����Ƃ��Ӗ����Ă��܂��āA085�Ƃ�150-4C�E�[�n�[�A375+537-509�z�[���AN400�܂���N500H�l�b�g���[�N�̑g�ݍ��킹�ԍ��̎��ł��B
���āA150-4C�E�[�n�[�Ƃ����̂́A���m��������̃n�[�c�t�B�[���h�Ɏg���Ă������j�b�g�ŁA�p���S���̏����^�ɂ������ł����̗p����Ă����悤�ł��BJBL�ł�1959�N�ɖ��E�[�t�@LE15A�����\����A1964�N�����LE15A�ɓ���ւ����Ă��܂��B�܂��A537-509�z�[���E�����Y�̓o�[�g�E���J���V�[���n�[�c�t�B�[���h�̂��߂ɓ��ʂɊJ�������Ƃ������ƂŁA�m���ɑ���JBL�V�X�e���ł͎g���Ă���̂͌������ƂȂ��ł��ˁB
�n�[�c�t�B�[���h��1964�N�܂Ő������������Ă����̂ł����A1959�N�ɂ͒��z�[�����ȗ�������Ă��܂����̂ŁA����̏o�i�͊ȗ����O�̋M�d�Ȃ��̂Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB1964�N�ɂ�075�����O���W�G�[�^������ɕt������3�E�F�C�V�X�e���ƂȂ�܂����B
�摜���画�f����ƃ��S��JBL�̃}�[�N�̂悤�ł����A�����^�ł̓W�������V���O�ƂȂ��Ă�����̂�����܂��B��Ђ�JBL�ɂȂ�O�̃W�������̍ŏ��̔N�ɍ��ꂽ�n�[�c�t�B�[���h�ő�ϒ��������̂ł��B��������̓��m�����ł̔̔��ł�������A�X�e���I�ŃV���A��No��������Ă���̂́A���肦�܂��A�A�B
�����ɂ��ẮA��������܂����A�����뒮�������Ƃ��Ȃ��̂łȂ�Ƃ������܂���B�z�[���Ȃ�ł͂̐L�т₩�������ቹ�ƁA�X�b�Ɛꖡ�̂悢�ቹ����������A�W���Y�̃o�X�h�����̃o�t�b�Ƃ������̂悤�Ȓቹ���A�畆���o�ŕ߂炦����B�Y�V�b�Ƃ����d�ʊ��̂���ቹ�ƑN�₩�������a�������������钆�����Ƃ��o�����X���ė��������鉹�B�Ȃǂƕ]�����������A���Ȃ��^�ł��˂��B
�R�[�i�[�z�[���^�ŁA�ǂƂ̋����ALR�̓����̕s���낢�Ȃǖ��̑����@��ł����A�Ȃ��Ȃ��ቹ���łȂ��ăp���[�A���v�𑊓��I�ԂƂ����b�������܂����A��肭�炷�ƁA�ǂ�������͐����悤�ł��ˁB
�����i�͊J�n���i��\300���ƂȂ��Ă���A���z�Ȃ���0BID�ł��ˁB�����^�n�[�c�̃y�A�ł͂���܂����A\250��������A\150���ő������Ƃ������Ƃ���ł��傤���B������ɂ͔����܂��炵���鎩�M������܂���˂��B�ł��A���̃n�[�c�ł���˂��A�A�n�[�c�A�~�����Ȃ��`�B
�R�����g
��E�E�E�悾�ꂪ�`�i��
�I���W�i�������ł͂���܂��A��x�����ߏ��̋i���X�Ŕq�������Ă��������܂����B
�R�V�T�ɍL����ቹ�́A�I�[���h�Ȃ炸�Ƃ��f���炵��������ł��B
�A���v�ɃN�������g���Ă����܂������A��͂�A�i���O���������܂��B�n�C
���X���镗�e�́w�p���S���x���l���ꍛ�ꂵ�܂��B
2009/1/25(��) �ߌ� 1:38
150-4C�̃p���S�������Ȃ�A�����^�n�[�c�t�B�[���h�ϐ��y�A�Ȃ�āA���̂܂����ł��ˁI�I
���`�ł��A��x�ŗǂ����璮���Ă݂����ł��B
2009/1/26(��) �ߑO 7:55 [ kt9*jp ]
ʰ�̨���ނ������݂̋ɂ݂��Ǝv���Ă���܂��B
�������Ȃ����Ɏ���ł��邽���߱�����킸�A�܂�375�̉������·������A��ڵ�͔��ɓ���̂������ł��B
�d�ቹ�͏o�܂����ް��̉��K�̕�����ቹ�͐��X�����A375�̐��\�ɕt���čs����B��̼��тƎv���܂��B�F�X�����Ď�����Ă��܂��܂������A�����̎c��SP�ł����B
2009/1/30(��) �ߑO 2:26 [ ���� ]
���͂悤�������܂��B���`�A�A�A�A�A�����Ă����̂ł����I�I�I�I���������������ł������A�A�B�������܂��A���Ȃ�A�������炽��̂����Ă��܂��܂��A�A�B�B�ł��T�X�K���[�U�̈ӌ��ł��˂��A
�X�e���I�ŃX�y�b�N�����낦��͖̂{���ɑ�ς��Ǝv���܂��ˁB���X�����x�[�X�Ȃ�āA�����ł��˂��A�ŋ߂ǂ����ŕ������Ƃ��ł�����肪�����̂ł����A�A�A�B
2009/1/30(��) �ߑO 8:38 [ �I�[�f�B�I�G�[�W�F���g ]
�m�l���A�Ԃ������Ă���A����������̂ŁA���̍ۂ͂Ƃ����Ă���܂��B
���̉Ƃɂ͒u���Ȃ��̂ŁA�Ȃ�Ƃ��A���肷��܂łɏꏊ���m�ۂ��Ȃ��Ɠs�s�����Ƃ���ł��B
�����̘A�Ԃ́A�A�����J�l�̃I�[�i�[���X�e���I�����\�����Ă��낦�����̂ŁA���j�b�g�S�����A�Ԃł����B���E�̃o�����X���悩�����ł��B
�����A�����̂��̂ł��A�ቹ�̕�����Ȃ��͂���܂����A������ӂ̓A���e�b�N�������悤�ɁA������y���ނ��̂��Ǝv���܂��B
���x�����̃I�[�g�O���t�������ɗ��Ă��������B���̓}�b�L����C20��MC60�܂���MC240�̑g�ݍ��킹�ŗV��ł��܂����A�N���V�b�N���Ȃ�A240�̂ق����悢�ł��ˁB
���䂩�W�܂��Ă��܂����}�b�L�������X�ɉł��ōs���Ă��܂��B���T���ɂ͂��傤��c22���ł��ōs���܂����B
�a�J�̃W���Y�i���̂��q����MC240�����_���Ă���Ă��܂��B
2009/6/7(��) �ߌ� 4:24 [ richard ]
�m�荇���̕������L���Ă���̂ʼn��������Ă��������܂���
�Ȃ��Ȃ��ł��� �ł��傫������...�W�����������܂��Ă��܂�����
�L���������~�����ł��ˁ�
2010/2/17(��) �ߌ� 7:46
�܂��A�m���ɂł����ł���ˁA�Ƃ��傫���̂ł��傤�ˁA�A�A�A�B�g�z�A�A�B
���̎���Ȃ̂ŁA�W�������͂�͂������Ǝv���܂����A�͂܂����Ƃ��̊������Ă̂͂ǂ��Ȃ�ł��傤���B�������H�H
2010/2/17(��) �ߌ� 9:53 [ �I�[�f�B�I�G�[�W�F���g ]
http://blogs.yahoo.co.jp/audio_agent/58428356.html
http://audioagent.wordpress.com/2009/01/25/jbl-hartzfield/
��������
D30085�n�[�c�t�B�[���h��JBL�̏����̍ō�����X�s�[�J�[�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B���̃X�s�[�J�[�ɂ��JBL�͐��E�I�ȃX�s�[�J�[�������[�J�[�Ƃ��Ă̖������m�����܂����B
�n�[�c�t�B�[���h�̐�����肪�����̂�JBL�̎�C�Z�t�ł���H�ƃf�U�C�i�[�ł������r���E�n�[�c�t�B�[���h�ł��B�@�P�X�T�S�N�AJBL�͌��X�v���t�F�b�V���i���p�̌���p�Ƃ��Đv�^�J�����ꂽ�R�V�TSIG�h���C�o�[�ƂP�T�O�|�S�b�E�[�t�@�[���A���̃V�X�e���̂��߂ɐV���ɊJ�����ꂽ�T�R�V�|�T�O�X�z�[���^�����Y�ƃt�����g���[�f�B���O�̒ቹ�z�[���^�G���N���W���[�ɑg�ݍ��킹�Ĉ�ʉƒ�p��D30085�n�[�c�t�B�[���h�Ƃ��Ĕ������܂����B�����ė�55�N�ɂ́u���C�t�v�ŁA�w���̋��ɂ̃X�s�[�J�[�x�Ƃ��ďЉ��AJBL�̖��͑S�Ē��ɒm��킽�邱�ƂɂȂ�܂��B
�n�[�c�t�B�[���h�͂��̌���A���j�b�g�d�l�ƃz�[���v�̗��ʂŔ��W�𑱂��邱�ƂɂȂ�܂��B�@
�܂��P�X�T�X�N�ɁA�ቹ�z�[���̍\�����V���v���ȍ\���ɍĐv����܂����B���̕ύX���R�Ƃ��Ă܂��\�������G�Ȑ܂�Ȃ��z�[���́A�����R�X�g�������������ƁA����ɏd�ቹ�̐L�т��s�����Ă������Ƃ��������Ă��܂��B�����̖��ɑΏ����ׂ��A�o�[�g�E���J���V�[�̓E�[�t�@�[�w�ʂ̃o�b�N�`�����o�[�����L������ƂƂ��ɁA�z�[���̊J�������g���āA�z�[���̒ʂ蓹���V���v���ɉ��P���A���̌��ʁA�d�ቹ�͖ڊo�������P����邱�ƂɂȂ�܂����B
1964�N�ɂ͍Ō�̉��ǂ��������O�V�T�g�B�[�^�[�Ƃm�V�O�O�O�l�b�g���[�N���lj�����ĂR�v�����V�X�e���ւƐ��܂�ς��܂����B�m�T�O�O�g�l�b�g���[�N���V�^�̂m�S�O�O�ɕύX����܂����B�@����ɃE�[�t�@�[�̂P�T�O�|�S�b�͂k�d�P�T�`�ɒu���������܂����B�G���N���[�W���[�̃`�b�v�{�[�h�̑������̂ɕς��܂����B
���������̔N�Ɍ��ǃn�[�c�t�B�[���h�͐������~�ƂȂ�܂��B���̗��R�Ƃ��ă��m�����Đ��ɕς��X�e���I�Đ������C���ɂȂ������Ƃ��������Ă��܂��B
���Ȃ݂�1970�N����ɂ��n�[�c�t�B�[���h�͏����Đ��Y����܂���������͊O�ς͂��Ȃ��ł������g�͑S���قȂ��Ă���ʏ�ʕ���������Ă���悤�ł��B���̃n�[�c�t�B�[���h��1959�N�`1963�N�܂łɐ��Y���ꂽ�����^�ƍl�����܂��B
http://island.geocities.jp/umanose8818/harts/hartsfield.html
��������
�i�a�k�n�[�c�t�B�[���h�̃N���t�c�}���V�b�v
�i�a�k���R���V���}�[�p�̃X�s�[�J�[���[�J�[�Ƃ��Ă̖������m������Ɏ����������͂ƂȂ������Џ����̍ō�����̂ЂƂB
�{���̓v���t�F�b�V���i���p�i�V�A�^�[��T�E���h�E�T�v���C�j�Ƃ��Đv�^�J�����ꂽ�R�V�T�h���C�o�[�ƂP�T�O�|�S�b�E�[�t�@�[���A���̃V�X�e���̂��߂ɐV���ɊJ�����ꂽ�T�R�V�|�T�O�X�z�[���^�����Y�ƃt�����g���[�f�B���O�̒ቹ�z�[���^�G���N���W���[�ɑg�ݍ��킹�Ă���B
�n�[�c�t�B�[���h�͂��̌���A���j�b�g�d�l�ƃz�[���v�̗��ʂŔ��W�𑱂����B
�@�܂��P�X�T�X�N�ɁA�ቹ�z�[�����S���̍Đv�ƂȂ����B���̕ύX�̗v���͂Q�������B
�@�܂��\�������G�Ȑ܂�Ȃ��z�[���́A���R�̋A���Ƃ��āA�����R�X�g�������������ƁB���G�ɂȂ������R�̂Ȃ��ɂ́A�i�c�Q�O�W�j����p�L�b�g�����t������悤�ɂ������Ƃ��������悤���B��ɓ���p�I�v�V�����𒆎~�ɂ������ƂŁA����ʓI�ȃz�[���v���ł���悤�ɂȂ����B
�@�Q�Ԗڂ̗v���́A�N���v�V���z�[���ɑR���ׂ��J�����ꂽ�͂��Ȃ̂ɁA���ۂɔ�ׂĂ݂�Əd�ቹ�̐L�т��s�����Ă������Ƃł���B�����̖��ɑΏ����ׂ��A�o�[�g�E���J���V�[�͐v�̌������Ɏ��|�������B�����āA�E�[�t�@�[�w�ʂ̃o�b�N�`�����o�[�����L������ƂƂ��ɁA�z�[���̊J�������g���āA�z�[���̒ʂ蓹���V���v���ɉ��P�����̂ł���B
�@���̉��ǂɌ��ʁA�d�ቹ�͖ڊo�������P���ꂽ���A�����܂ő����_���ɉ����邱�Ƃɂ��Ȃ����B�@���̘_���Ƃ͂ǂ���̒ቹ�z�[�������ۂɂ͑S�̂��猩���Ƃ��x�X�g�Ȃ̂��Ƃ����^��ɂ��������̂ŁA�ǂ���̐w�c�����̌�A�����̎^���҂��W�߂邱�ƂɂȂ����B
�@�������R���N�^�[�̊Ԃł́A�ŏ��̐v�ɂق��������l�i���t���X���ɂ���B�@������̂ق����I���W�i���̃n�[�c�t�B�[���h�����猾���̂���ȗ��R�ł���B
�@�Ō�̉��ǂ�������ꂽ�̂��P�X�U�S�N�ŁA����͑S���_�����ĂȂ������B
�@�n�[�c�t�B�[���h���A�i�O�V�T�j�g�B�[�^�[�Ɓi�m�V�O�O�O�j�l�b�g���[�N���lj�����ĂR�v�����V�X�e���ւƐ��܂�ς�����̂ł���B�i�m�T�O�O�g�j�l�b�g���[�N���V�^�́i�m�S�O�O�j�ɕύX���ꂽ�B
�@�i�O�V�T�j�����O���W�G�[�^�[�́A�s��ł̓������l��������ɓ�����ׂɒlj����ꂽ���̂��B�@�����A�����̃n�[�c�t�B�[���h�E�I�[�i�[���A�i�R�V�T�j�̍���̍Đ����E�ɑΏ�����ׁA�i�O�V�T�j�g�B�[�^�[�Ɓi�m�V�O�O�O�j�l�b�g���[�N��lj����āA�莝���̃V�X�e�����J�X�^�}�C�Y���Ă����̂ł���B�@�i�a�k�͒P���ɁA���̎d�l���X�^���_�[�h�ɂ��������ł������B
�ŔӔN�̕ύX�́A�i�P�T�O�|�S�b�j���i�k�d�P�T�`�j�ɒu��������ꂽ���Ƃ��B�i�a�k�̎Г��e�X�g�ŁA�n�[�c�t�B�[���h�Ɂi�k�d�P�T�`�j�����߂Ă݂�ƁA�c���ڂɌ����ď��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��킩�������߁A�Ō�̂P�N�̐������́A�i�k�d�P�T�`�j���X�^���_�[�h�̃E�[�t�@�[�ƂȂ����B
�@�P�X�U�S�N�ɉ������������~�̌���́A�X�e���I�Đ������m�[�����Đ��������̂��āA���ɘ^���t�H�[�}�b�g�̒��S�ƂȂ������ʂł������B
�@�i�ʍ��r�r���i�a�k�U�O�����@�`�����D���j
http://www.gokudo.co.jp/Vanguard/Hartsfierd/room1.htm
��������
JBL �n�[�c�t�B�[���h
�@���̃X�s�[�J�[�͖{���ɗǂ��o���Ă��܂��B���[�G���h�܂ŗǂ��L�тĂ��āA�Ȃ��������������̂ŁA������W�������̉��y���y���߂�I�[�����E���h�v���[���[�ł��B��ϊ����x�̍����X�s�[�J�[�ŁA����ł��������X�s�[�J�[�͌���Ă��Ȃ��Ƃ����Ă��ǂ���������܂���B
�@���R�[�h�v���[���[��LP12�A�v����JBL SG 520�A�p���[�A���v���}�����c�́�9��4��BCD�v���[���[�̓V���v���Ƀ�����CD12�ƂȂ��Ă��܂��B�������e�@��̉��ɂ̓��[�[���N�����c�̃C���V�����[�^�[���g���Ă��܂��B
�@JBL �p���S��
�@���̔������V���G�b�g�͕s�ς̂��̂ł��B'50��ɂ͂��������f���炵����i����R���܂�܂����B�A�����J�̉�������ŁA�f��ق̃X�N���[���Ō��邻�̖L���Ȑ����Ԃ��A���W�I���畷�����Ă��閣�͓I�ȉ��y�Ɏ����X���Ă͏����������̂ł����B
�@�v���[���[LP12�ƃv���A���vJBL SG 520�͑��̃V�X�e���ƑS�������ł��B�p���[�A���v��KT-88�v�b�V���v���̃}�b�L���g�b�V����275�Ńp���S�����h���C�u���܂��B
�@�ꕔ����2��̃X�s�[�J�[�Z�b�e�B���O�͓��
�@�n�[�c�t�B�[���h�ƃp���S���B���̓�̃X�s�[�J�[�͑�σ}�b�`���O�̗ǂ��g�ݍ��킹�ł��B���ʂ͈ꕔ����2�g�̃X�s�[�J�[���Z�b�e�B���O����͍̂�����ɂ߂܂��B
�@�������A�R�[�i�[�^�̃n�[�c�t�B�[���h�ƕ����̒����ɒu���悤�ɍ���Ă���p���S���ł�����A���݂����T�E���h�X�N���[�����ʂݏo���̂ł��̏�Ȃ��������ǂ��̂ł��B
http://www.rosenkranz-jp.com/kaiser/Visitor_visit%20(Trip%20of%20audio%20clinic)/Visitor_visit%20(Trip%20of%20audio%20clinic)/20061221_sh.html
��������
�p���S���ƃn�[�c�t�B�[��������� �G���F���X�g ������łȂ����R 12�� 11th, 2010
����ƌĂԂɂӂ��킵���I�[�f�B�I�@��Ƃ́A���������ǂ��������̂Ȃ̂��낤���B �ꗬ�i�A�����i�ƌĂ����̂��A����Ƃ͂�����Ȃ��B ����͈ꗬ�i�ł͂����Ă��A�K�����������i�i���z�i�j�ł͂Ȃ��B
����͖��킾�A�Ƃ��������Ƃ����ɂ��邱�Ƃ����邵�A���ɂ��邱�Ƃ�����B �[���ł���Ƃ�������A���ɏo���Ĕ��_�͂��Ȃ��܂ł�����X�������Ȃ�Ƃ�������B ��������Ƃ��Ă��郂�m���A����l�͂����͎Ƃ��Ă��Ȃ���������Ȃ����A�܂����̂��Ƃ�����B �����������m�́A�ʂ��Ė���ƌĂׂ�̂��B
�u����v�Ƃ����āA���������Ɏv�����ׂ�I�[�f�B�I�@��́A���łɐ������~�ɂȂ������̂���ł���B �ł��A����͎������̂��ƁA�Ƃ͎v�����A�u����v�Ƃ����āA�ŐV���i���v�����ׂ�l�͏��Ȃ��悤�Ɏv���B���Ȃ��Ƃ��I�[�f�B�I�ɂ����Ắu����v�́A�V���i�Ƃ��Đ��ɓo�ꂵ�āA���ꂩ�炠�钷���̊��Ԃ��o�����m�ł͂Ȃ����낤���B
���́A���钷���̊��Ԃ́A��̓I�ɉ��N�ƌ��܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B
���Ƃ��^���m�C�̃E�F�X�g�~���X�^�[��1982�N�ɓo�ꂵ�Ă���B��30�N���o���A���̊ԂɁA���x���̉��ǂ��ی삳��A�E�F�X�g�~���X�^�[�E���C����/SE�ƂȂ��Ă���B ����́A��������ƌĂ�ł����A�Ǝv���Ȃ�����A�Ȃ����A���̒��ł̓I�[�g�O���t�͖���Ƒf���ɌĂׂĂ��A�E�F�X�g�~���X�^�[�ɑ��ẮA��R���Ƃ܂ł͂����Ȃ�����ǂ��A�f���ɖ���Ƃ͌ĂׂȂ��̂͂Ȃ����ƁA�����ł��s�v�c�Ɏv���Ă���B
�E�F�X�g�~���X�^�[�ɁA�Ƃ��Ɍ��s�̃E�F�X�g�~���X�^�[�E���C����/SE�ɁA�I�[�g�O���t�Ɣ�r���ĉ]�X�A�Ƃ����P�`������Ƃ���͂Ȃ��B
�t�����g�V���[�g�z�[���̂���ɂ��Ă��A�I�[�g�O���t�͒����I�ȃz�[���������̂ɑ��āA�E�F�X�g�~���X�^�[�ł͎�Ԃ������ċȐ��Ɏd�グ�Ă���B ���ڂ���Ă���X�s�[�J�[���j�b�g���A�ŏ��̃E�F�X�g�~���X�^�[�̓t�F���C�g���̗p�ŁA���̓_�ł������������肵���̂������ȂƂ��낾���A�^���m�C�����̂��Ƃ͗������Ă����̂��A���݂̃��j�b�g�͌������Ɗ��S���Ă��܂��B
����ɃE�F�X�g�~���X�^�[�E���C����/SE��2006�N�o��Ƃ͂������̂́A�|�b�Əo�̐V���i�ł͂Ȃ��A���̎��_��24�N�̌������o�Ă��Ă���B�I�[�g�O���t�𖼊�ƌĂԂ̂ł���A�E�F�X�g�~���X�^�[�E���C����/SE���A����ƌĂȂ����R�͎v�����Ȃ��B
�ɂ��ւ�炸�A���������ӂ��ɏ����Ă����Ă��A�E�F�X�g�~���X�^�[�E���C����/SE�́A���ɂƂ��Ė���Ƃ��āA���܂̂Ƃ��둶�݂��Ă��Ȃ��B�E�F�X�g�~���X�^�[�E���C����/SE�𖼊�Ǝv���Ȃ��̂́A�Ȃɂ��E�F�X�g�~���X�^�[�����s���i������A�Ƃ����̂����R�ł͂Ȃ��B
JBL�̃p���S���́A���܂ł͐������~�ɂȂ��ĂЂ��������A�����I�[�f�B�I�ɊS�������͂��߂�����i1976�N�����j�͌��s���i�������B �����������̂͐��N��ł��������A�����̓p���S������͎������߂Ă��鉹�͏o�Ă��Ȃ��A�Ƃ����v�����݂�����������ǁA����ł��p���S���͖���ł���A�Ɗ����Ă����B
�����^���m�C�̃X�s�[�J�[�V�X�e���Ȃ̂ɁA�I�[�g�O���t�𖼊�Ƃ��Ċ����A�E�F�X�g�~���X�^�[�𖼊�Ƃ͎v���Ȃ��A
���s���i�ł����Ă��p���S���͖���ƒ��������̂ɁA�E�F�X�g�~���X�^�[�͂����ł͂Ȃ������B
����̂Ȃ��悤�ɂ��Ƃ���Ă������A�����ł����Ă���R�̃X�s�[�J�[�V�X�e���i�I�[�g�O���t�A�E�F�X�g�~���X�^�[�A�p���S���j�ł́A����Ƃ͎v���Ȃ��E�F�X�g�~���X�^�[�E���C����/SE�͊����x�������Ƃ���ɂ���Ƃ����邵�A�炵�Ă��������ł́A������N�Z�̏��Ȃ����E�F�X�g�~���X�^�[�ł���B
�E�F�X�g�~���X�^�[�E���C����/SE�͂悭�o�����X�s�[�J�[�V�X�e�����A�Ǝv���B
�Ȃ̂ɁA�ǂ����Ă��E�F�X�g�~���X�^�[�́A���ɂƂ��Ė���ł͂Ȃ��B
�I�[�g�O���t�Ɋ������ăE�F�X�g�~���X�^�[�Ɋ������Ȃ����́A
�p���S���Ɋ������ăE�F�X�g�~���X�^�[�Ɋ������Ȃ����́A
�܂�I�[�g�O���t�ƃp���S���ɋ��ʂ��Ċ���������́A�Ƃ͂��������Ȃ�Ȃ̂��B
�u�X�P�[���v���Ǝv���B
��N10��5���Ɏl�J�O���ځE�i������L�ōs�����H�ƃf�U�C�i�[�̍�씎�s����Ƃ́A�u�I�[�f�B�I�̃f�U�C���_�v����邽�߂ɁA�̒��� �p���S���̘b�ɂȂ����Ƃ��ɍ�삳��o���L�[���[�h���A���́u�X�P�[���v�ł���B
�^���m�C�̃I�[�g�O���t�ƃE�F�X�g�~���X�^�[�Ƃ̂������Ɏ��������Ă��邱�Ƃɂ��ẮA�Ⴄ�������������ł����̂����A��삳��̂���ꂽ�u�X�P�[���v���āA ����قNJȌ��ɕ\���ł���L�[���[�h�����������ƂɋC�������B
�����ł����u�X�P�[���v�Ƃ́A���i���̂��̂̃X�P�[���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B
���i���̂��̂̃X�P�[���ł����A�I�[�g�O���t�ƃE�F�X�g�~���X�^�[�Ƃقړ������A�ނ���E�F�X�g�~���X�^�[�̂ق����X�P�[���͑傫���Ƃ�����Ƃ��������B
����ǁA��삳�g��ꂽ�Ӗ��ł́u�X�P�[���v�ł́A���̉��߂ł̓I�[�g�O���t�̂ق����X�P�[�����傫���A�Ƃ������ƂɂȂ�B
��삳��́A���̂Ƃ��A�u�X�P�[���v�ɂ��ăp���S���Ƃ̑Δ�œ���JBL�̃n�[�c�t�B�[���h���ɋ�����ꂽ�B
�p���S���ƃn�[�c�t�B�[���h�́A�ǂ����JBL�̉ƒ�p�X�s�[�J�[�V�X�e���Ƃ��āA�A�����J�̂���Ή���������\���郂�m�i����j�ł��邯��ǁA�n�[�c�t�B�[���h�̓��m�[��������́A�p���S���̓X�e���I����ɂȂ��ĊJ�����ꂽ�X�s�[�J�[�V�X�e���ł���A�ǂ��炪�����Ƃ��A�f���炵���A�Ƃ��A������������r������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂����A���̂ӂ��̃X�s�[�J�[�V�X�e���ݏo�������z�́u�X�P�[���v�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�p���S���̕����n�[�c�t�B�[���h�����傫���A�Ƃ������ƂɂȂ�i�������͕����Ă����j�B
�n�[�c�t�B�[���h�ƃp���S���Ƃł́A�n�[�c�t�B�[���h�̂ق����������X�s�[�J�[�V�X�e�����Ǝv���Ă����������������B ���܂��A���̃X�s�[�J�[�������������̃R�[�i�[�Ɏ��߂�ꂽ�Ƃ��ɏ����o����镵�͋C�ɂ͖��������̂�����B
����ǃp���S���ɂ́A�X�e���I�p�X�s�[�J�[�V�X�e���Ƃ��č��E�̃X�s�[�J�[���ЂƂɂ܂Ƃ߂Ă��܂��Ƃ����A���������Ӗ��ł́u�X�P�[���v�̑傫��������A����Ɋւ��ẮA���m�[�����A�X�e���I�Ƃ�������w�i���W���Ă��邱�Ƃ͕S�����m�̂����ŁA�n�[�c�t�B�[���h�ɂ́A�d���̂Ȃ����Ƃ����A�p���S���I�ȁu�X�P�[���v�̑傫���͖R�����A�Ǝv���B
���́u�X�P�[���v���^���m�C�ł́A�t�]���ă��m�[��������ɐ��ݏo���ꂽ�I�[�g�O���t�Ɋ������A�X�e���I����ɂȂ��Ă���̃E�F�X�g�~���X�^�[�ɂ́A�Ȃ��Ƃ͂���Ȃ��܂ł��H���ɂȂ��Ă���B
http://audiosharing.com/blog/?cat=98
��̋L���Łu�X�P�[���v���u���i�v���́u�i�ʁv�Ɠǂ݊�����ƂȂ�ƂȂ����ӂ��`���܂��ˁB
��������
JBL ���s�̃X�s�[�J�[�V�X�e��
https://jp.jbl.com/premium-speakers
JBL ���X�s�[�J�[���j�b�g�ꗗ
http://audio-heritage.jp/JBL/unit/index.html
http://audio-heritage.jp/JBL/unit/index2.html
JBL ���G���N���[�W���[-�L���r�l�b�g�ꗗ
http://audio-heritage.jp/JBL/unit/index3.html
JBL ���X�s�[�J�[�V�X�e���i�����p�j�ꗗ
http://audio-heritage.jp/JBL/speaker/index2.html
JBL ���X�s�[�J�[�V�X�e���i�v���t�F�b�V���i���V���[�Y�j�ꗗ
http://audio-heritage.jp/JBL/speaker/index.html
�@
|
|
������@�@�@�@�@ �����C���� > ���o�C�o��3�f�����@���� �@�O��
|
|
- JBL �I�����p�X ���v���J ���엲 2020/11/18 17:48:53
(0)
�ŐV���e�E�R�����g�S�����X�g �@�R�����g���e�̓����}�K�ő����z�M �@�X�����Ĉ˗��X��
������@�@�@�@�@ �����C���� > ���o�C�o��3�f�����@���� �@�O��
|
|
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B