
�Ռ��I �L���b�V�����X�卑�E�����́u�m��ꂴ��Łv�@QR�R�[�h���g�����ޓ����������o��
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58098
2018.11.09�@�P�c ���ā@�t���[�W���[�i���X�g�@����r�W�l�X
�u�U�D�v�����܂���Ȃ��Ȃ����̂͂悩�������c
�u���܂ǂ��̒����l�͍��z�Ȃ�Ď����Ȃ��̂��v�\�\����ȃR�����g���悭�����B���{�ɗ��������l�ό��q�́A���z���J���ď��K�𐔂�����{�l���`�������āA�u�����͊��S�ɓ��{�����v�Ɨ����������Ă���炵���B
�����A�u���z�������Ȃ��v�Ȃ�ăz���g�Ȃ̂��A�u��������Ȃ��v�͒P�Ȃ錩�h����Ȃ��낤���H ���́A�����v�킴��Ȃ��u�L���b�V�����X���v�������ł͂��܂�����Ƃ���ŋN���Ă��邩�炾�B�قƂ�Ǖ��ĂȂ������L���b�V�����X���́u�Łv�ɂ��ă��|�[�g�������B

�X�}�[�g�t�H���ɕ\�����ꂽQR�R�[�h�i���m�N���̎l�p���摜�j���s�b�ƃX�L�����B��u�ɂ��đ���x����������QR���σT�[�r�X�������̐l�X�ɂ����炷�̂́u�ς킵������̉���v���B
���K�𐔂��Ȃ��ōςނ��A�ō��z�ʂ�100���D�ō��z��c��܂��Ȃ��Ă��ςށB�����U�D�����܂���Ȃ��Ȃ����B �g�g�����v�̃o�o�h��낵�����ʂ���j�Z�D�A���܂��ꂽ���̓��͖������Ȃ��Ƃ��������l�͐��̐��قǂ����B
��C�Ńu�e�B�b�N���o�c���鏗�����u�]�ƈ���������������܂����Ȃ��Ȃ����v�ƃj�R�j�R�炾�B������s��̂������́A�u����܂Ŋp�̒P�ʂ͋q�ɒl���Ă������A��������1�p�A2�p�̒P�ʂ܂ʼnۋ��ł���悤�ɂȂ����v�Ɗ��ł���B�x�T�w����̍����H�ޓX���u���K������Ȃ��Ȃ����̂ŋ�s�ɗ��ւɍs����Ԃ��Ȃ����v�Ƒ劽�}���B
2013�N�A�����́u�C���^�[�l�b�g�t�@�C�i���X���N�v���}�������A�ȗ��A��������QR�R�[�h���ς͒����s���̐����̒��ɒ蒅�������̂悤���B
QR�R�[�h�Łu�����x������鎖���v�����o���I
�����ɋ��_�����A�C���T�[�`�ɂ��A�����̃X�}�z���ς̋K�͂̓A�����J��50�{�B�����ł̓X�}�z���ς������I�ɐL�тĂ���A2017�N�ɒ����̏��Ƌ�s�����������X�}�z���ϋƖ���375�����i�O�N��46�����j�A���z�ɂ���202�����i�O�N��28�����A��3232���~�j�ƂȂ����B
���ꂪ�����̂́A���N���Ă���Q��܂�QR�R�[�h�ɃK�b�c���x�z����钆���̌���l�̐������B��C�E�Y���̋��Z�X�œ������i29�A�����A�����j��������̂ЂƂ�B�����͂�̒�ԁu��饼�����v���̂�QR�A�V�F�A�T�C�N���̊J����QR�A���i����̂�QR�ƁA���5�`6���QR�R�[�h��ǂݎ��̂��Ƃ����B�uQR�R�[�h�ƃX�}�z���ς͕֗������A����Ȃ��ɂ͐����Ă����Ȃ��v�i������j�炵���B
����ǂ�������͂ǂ����ł��́g�_���ρh���^���Ă���B���̗��R���u�������x�����ꂽ�j���[�X���₦�Ȃ�����v���Ƃ����B
�Ⴆ�A�ʔ̃T�C�g�̔��������ɁA���X������u���i���͂����v�Ƒ����Ă���QR�R�[�h��ǂݎ�����u�ԂɁA���o�C���E�H���b�g����18�����i��288���~�j�������ĂȂ��Ȃ����Ƃ��A�V�F�A�T�C�N�����J�����悤��QR�R�[�h���X�L����������f�|�W�b�g�̖��ڂ�299���i��4780�~�j���������Ƃ��ꂽ�Ƃ���������������B
�ꕔ�̃��f�B�A����̂́A2017�N�ɍL���ȂŋN�������{�~�ɂ���14���~�������܂�鎖�����B��C�ݏZ�̓��{�l������u�[�d�����u�ԂɎc�����Ȃ��Ȃ�Ƃ�����Q������炵���v�Ƃ����b���������B
QR�R�[�h�Łu�����x������鎖���v�����o���I
QR�R�[�h�𗘗p�����ƍ߂͎�ɂQ�̃p�^�[��������B�X�}�z�ɃE�C���X�����������邱�ƂŁA���p�҂̃E�H���b�g������𓐂ނƂ������̂ƁA���O�ō����QR�R�[�h���ォ�璣��t���āA�����̌����ɂ����𗎂Ƃ��������̂��B
�����S�y�ŃV�F�A�T�C�N���ɉ��t����2017�N�ɂ́A�����ɂ����O��QR�R�[�h�����S���ƈ�����A�钆�ɒ���t���ĉ��g�ޓ��c�h���o�������BQR�R�[�h���烊���N�����ǂ��Ă���������ŁA���[�U�[�̐g���ؔԍ��A�J�[�h�ԍ��A�g�єԍ��ȂǏd�v���𓐂ݎ�����Q�����o���Ă���B�Z�L�����e�B�̂�邢QR�R�[�h���ς���́u�����グ�v�Ȃǒ��ёO���B

�������A�ЂƂ��уg���u���ɒ��ʂ���ƁA�����Q���肷�邵���Ȃ��̂������Љ�B�A���y�C�̃E�H���b�g����5��2000���i��80���~�j�𓐂܂ꂽ�N�̓{��́A�g�����l�{�l�h�ł͂Ȃ��u���Q�����̋���v�Ɍ�����ꂽ���̂������B
���̐N�́A�A���y�C�ɑ��Q������\�����悤�Ƃ������u���Ȃ��̑����͑��Q�����͈̔͂ɂ͊܂܂�Ȃ��v�Ƃ�����ق��Ɉ�R���ꂽ�B�N�͖��n�ǂ��A���x�ƂȂ��A���y�C���Ɋ|�������A���̌���1�������₵�����̂́A���ǎ��߂����̂͂�����2000���i��3��2000�~�j�B
�����̕⏞�z�̓P�[�X�o�C�P�[�X���낤���A�N���l�b�g��Ō��J������̋L�^����́A�ی����|�������Ă����Ȃ��炢���ƂȂ�ΐ\����������悤�Ƃ���A��Ƒ��̑Ή��̗�W�����`����Ă���B
�M�҂̂��Ă̏�C�ł̐����������������悤�ɁA�����Љ�ł́g�������߁h���̗v�ł���B�g���u�������ɂ����₢���킹�����Ă��A�����K�C�_���X�ɂ���Ă��炢�ɂ���Ă��܂��B���Ƃ�����҂��P�Ӗ��ߎ��ł��A���̍��@�I���v�͂Ȃ��Ȃ��ی삳��ɂ����̂��B
�����C���^�[�l�b�g�l�b�g���[�N���Z���^�[�iCNNIC�j�ɂ��ƁA�����ɂ�����X�}�z���[�U�[��7��5300���l�A�X�}�z���ς̗��p�҂�5��2700���l�ɂ����Ƃ������A�{���݂͂�ȁg�k����w�h�ŃX�}�z�̌��σ{�^���������Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B
�u�����̍��Y�X�}�z�ő��v�Ȃ̂��v���
�u���Y�X�}�z���v���H�_�v������B
������7��5300���l�̃X�}�z���[�U�[�̂قƂ�ǂ��u�������v�̃X�}�z�𗘗p��������A��������イ����X�}�z�Ő���Ȏ�����ł���̂��Ƃ������̂��B
IT��咲�����IDC�ɂ��A2017�N�̏o�ב䐔�ł݂������s��̃X�}�z�̃V�F�A�̓t�@�[�E�F�C�i�؈ׁj����ʂł���A����ɃI�b�|�iOPPO�j�A���B�[���H�iVivo�j�A�V���I�~�i���āj�ƍ��Y�X�}�z�������B�ߔN�̍��Y�X�}�z�̃X�s�[�f�B�Ȕ��W�͂܂Ԃ������炢���B
�����A�P���������W�̗��ɂ͕K���u�Ђ��݁v�����݂���̂͒����Љ�̓S���B�s��V�F�A���D�݂̂ɖڂ�D���钆�����[�J�[�ɁA�ʂ����āu�s�Ǖi�v�ɑ����ӂ͂���̂��낤���B�����̃X�}�z���[�J�[�������Ɏ������ݏZ�̓��{�l���o��������Ȃ��Ƃ�b���Ă����B
�u�����̓d�q���i�ƊE�́A�s�ǂ��o��ΐV�������̂ƌ�����������Ƃ����F���������B���{�̃��[�J�[�Ȃ�O��I�Ɍ�����Njy�����P���悤�Ƃ����ł����v

�����������Y�X�}�z�̗��j�͖͑��i����n�܂�A�������̃A�b�v����T���\�����Ȃ��w�𒆐S�ɂ��̌ネ�[�G���h�ł��L�܂����B100���i��1600�~�j�̃X�}�z�ŗ��v���o�����Ǝv���A�g�ݍ��܂�镔�i�͈����Ȃ��̂ɂȂ邩��A���̏Ⴊ�N���Ă��s�v�c�ł͂Ȃ������B����������ȍ��Y�X�}�z�����͐́B���i�����̋Z�p�͂ƃV�F�A�g��ŁA�����̍������x������悤�ɂȂ����B
��C�ݏZ�ō��`�n������ЂɋΖ����闛������i38�A�j���A�����j�ɂƂ��ẮA���Y�X�}�z���g�g���̂āh���R�̂悤���B�������g���Ă���X�}�z�̓��m�{���ŁA2�����O��1300���i��2��2000�~�j�ōw�������B�g���S�n��K�˂�ƁA�u1300���̍��Y�i������ˁA���N�g�������ŏ\���v�Ƃ����B�{�̉��i1300���͎g�p���ɕs����o���Ƃ��Ă����߂������i���B
������̓������g���̂�1800���i��2��8800�~�j�̃V���I�~���B�z���C�g�J���[���x������V���I�~�Ȃ�A�M�҂��g���Ă݂������̂��B�����v���Ē��ׂ�ƁA2018�N��1�l�����A�V���I�~��14���̍����̏ᗦ�i���o�C���f�o�C�X�f�f��ƃu�����R���ׁj�������B
100�䂠���14�䂪����v�Z���B���M������A��ʂ��t���[�Y�����肷��炵���B������̂��ꂳ��i66�j�́u��ꂽ�甃���ւ���Ⴂ����v�Ƃ������A����ȕs����Ȓ[���ōs���u���ρv�Ȃ�Č����Ė����Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B
�l����s���u���S������r�I�Ⴂ�v�ƔF�߂��c
�����̓L���b�V�����X�Љ�Ɍ����Ď��g�݂����������Ă���B�ݕ��̔��s�����点�Η��ʃR�X�g�����点��킯�����A�o�ϊ����̓����x�����߁A�E�ł�}�l�[�����_�����O���Ȃ������߂ɂ��A�L���b�V�����X���͗L�����B
�����A�l����s�ł���u���S������r�I�Ⴂ�v�ƔF�߂�̂�QR�R�[�h���B����ł�����������𐄂��i�߂�̂́A�u�L���b�V�����X�Ƃ����Β����v�Ƃ����悤�ɁA�����́uQR�R�[�h�����̃L���b�V�����X�v�Ő��E�̃g�b�v�ɗ����������炾�B

���Ȃ݂ɕM�҂̓L���b�V�����X���ɂ͌����Ĕ��͂��Ă��Ȃ��B�����A�Z�L�����e�B�ɕs�����c��QR�R�[�h���ς����A�N���W�b�g�J�[�h��v���y�C�h�J�[�h�����̂܂܃X�}�z�ɓ��ڂ���A�b�v���y�C��A���h���C�h�y�C�̂ق��������ƈ��S����Ȃ����Ǝv���B
�܂��A������QR�R�[�h���ς͗��p�K��������イ�ς��B�ȂɂԂ�g�������̐^���������h�����璩�ߕ������ނȂ����낤���A�s����Ȃ��Ƃ��̏�Ȃ��B�������A�s��͓���Ɓi�A���y�C�ƃE�B�[�`���b�g�y�C�j���ǐ�A���p�҂��|�M����邱�Ƃ͂���͂��Ȃ����ƐS�z�ɂȂ�B
���āA�M�B�Ȃɂ́A�u13���Ԃ̃L���b�V�����X�����v�ɒ��킵���s��������Ƃ����B�ʂ����āu���S�L���b�V�����X�v�ɐ����������Ƃ����ƁA�ɂ��������̎s���́u2��5�p�v�������������Ă����B���{�~�ɂ��Ă킸��40�~���x�����A�X�}�z���ς����ۂ��ꂽ�X���������Ƃ������Ƃ��B���Ƃ����z�ł��낤�Ƃ��A����ς茻���͕K�v�������Ƃ������Ƃ��B
����A�����͑f���Ɏ]���悤�B�M�B�ȂƂ������ŋ߂܂Œ������\����g�n���ȁh�ŁA���{��ODA�����̑Ώۂ��������A���̋M�B�Ȃł��u����̓X�}�z���ρv�Ȃ̂��B���{�l�͏]���́g�����M�h����ڂ��o�܂��K�v������B
����ł��A�M�҂͂������q�˂����B
�d�r�ꂵ����ǂ�����́A�t���[�Y������ǂ�����́A���v������ǂ�����́\�\
�u�����Ȃ�Ă���Ȃ��v�͂���ς茩�h�ł��傤�A�ƁB
�x�m�R�[�́u�E�씪�C�v�A�x�m�R��K��钆���l���K���������ό��X�|�b�g�����A�r�̒�ŃL���L���P���̂͐��v�����X�}�z�Q���B�u�������͂��ꂩ��I�v�̖��̐��v�����B����ł������̐l�X�́u�����Ȃ�Ď����Ȃ��I�v�ƌ������̂��낤���B



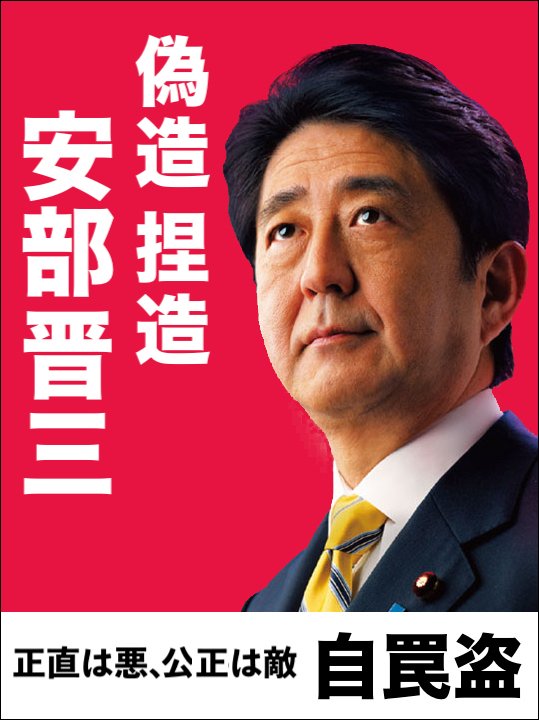




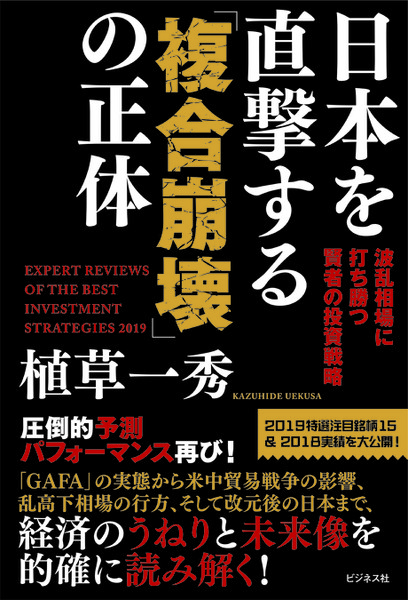
 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B