さらば、古舘伊知郎!〜視聴率大戦争が勃発。そしてテレビ朝日は、TBSに追い抜かれる
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47295
2016年01月13日(水) 週刊現代 :現代ビジネス
プロレスのアナウンサーから、日本一有名な報道番組のキャスターにまで登りつめ、その席に12年間も座り続けた。古舘伊知郎がついに「退場」する。『報ステ』抜きで、テレビ朝日は視聴率戦争を勝ち抜けるのか。足元を見ると、TBSがじわじわと距離を詰めている。
■裸の王様
「『古舘に早く辞めてほしい』と思っていた人が局内の大半でしたから、反応は冷たいですよ。古舘さんはテレ朝の中では『裸の王様』なんです。彼に意見を言えるテレ朝のディレクターはほとんどいませんでした。
毎晩、番組終了後には4階のスタッフルームに50~60人を集めて反省会が行われていましたが、これも古舘さんをヨイショするだけの会で、とてもじゃないけど、建設的な意見が言えるような雰囲気ではありません。深夜になればタクシー代が出るので、そのためだけに参加するスタッフもいるほどでした」(『報道ステーション』関係者)
テレビ朝日の「夜の顔」を務めた古舘伊知郎(61歳)が、今年の3月一杯で番組を去る。
突然の発表に、さぞ局の内外から名残を惜しまれているかと思いきや、意外にも冷めた声ばかりが聞こえてくる。「早晩こうなると思っていた」、「辞めてくれて清々した」という意見のほうが多いのだ。
古舘が煙たがられていたのは、前述の「裸の王様」状態に加えて、所属する古舘プロジェクトへの高額なギャラの問題も影響していたという。
「テレ朝から古舘プロに支払われる製作費は、一説には年間で30億円に上ると言われています。古舘さんの出演料が推定13億円で、残りの17億円は派遣スタッフや構成作家などに支払われるそうです」(テレ朝関係者)
コスト面からしても、古舘が降板するのは、時間の問題ではあった。だが彼が『報ステ』を去ることになった最大の理由は別にあるという。別のテレ朝関係者が語る。
「それはテレ朝の早河洋会長との『亀裂』です。反安倍政権の姿勢を打ち出したい古舘と、官邸を刺激しないよう穏便にことを進めたい早河会長の考え方に溝ができ、その溝がどんどん広がって修復不可能になってしまったのです。
さらに古舘プロの佐藤孝社長と早河会長の関係も悪化しました」
早河会長は、久米宏を司会に抜擢し、『報ステ』の前身である『ニュースステーション』を立ちあげた人物だ。そもそも、古舘を口説き、番組に起用したのも他ならぬ彼である。だが二人の関係は年月を追うごとに変わってしまった。
降板発表時の記者懇談で、早河会長と通じ合えなくなったことを、古舘自身が認めている。
「私は娯楽もので生きてきた人間なので、ずっとキャスター就任は固辞していました。でも早河さんが『自由にあなたの画を描いてほしい』と言ってくれたので引き受けたのです。ところがいざ始まってみると、言っていいことと、ダメなことの大変な綱渡り状態でした。苦しい12年間でした」
■もう疲れた
なぜテレ朝は、それほどまで古舘を縛りつけ、政治に関する発言を規制したのだろうか。
「テレ朝は'93年に起きた『椿発言』のトラウマを未だに抱えているんです。当時の取締役報道局長であった椿貞良氏が、『自民党政権の存続を阻止して、反自民の政権を成立させようと指示した』と発言したため、日本で初めて、放送免許取り消し処分が本格的に検討された事件です。その二の舞にならないためにも、政権に批判的な発言をしようとする古舘を監視せざるをえなかったのでしょう」(全国紙記者)
内部事情に詳しい関係者も続ける。
「表向きは古舘さんが自ら辞める形になっていましたが、実はテレ朝側が、彼に降板を迫ったようです。『もう支えられません』と暗に通告し、古舘さん自らが『辞める』と言わざるをえない状況に追い込んでいったのです」
本来なら守ってくれるはずのテレビ局から完全に見放され、後ろ盾を失くした古舘は、追い詰められていく。ここ数年、古舘の『報ステ』内での言動は、度々物議を醸してきた。
それがもっとも顕著に表れたのが、昨年の3月に起こった準レギュラーコメンテーター(当時)で元経産省官僚・古賀茂明氏の降板騒動だ。
古賀氏は「I am not ABE」と書かれたフリップを提示し「官邸から圧力を受けている」と発言。生放送中にもかかわらず、古舘と古賀氏の激しい口論に発展した。
「あの時、古賀さんに対して古舘さんは、彼をなだめつつ、もっと冷静に対処することもできたと思うんです。それをムキになって『そんな事実はない』と反論したことで、視聴者に対し、余計に『報ステ』がおかしくなっている印象を与えてしまった」(別の『報ステ』関係者)
政府と早河会長の間に挟まれ、古舘自身も次第に投げやりな気持ちになっていったという。
テレビ朝日報道局出身で『放送レポート』編集長の岩崎貞明氏が言う。
「『今後は新しいジャンルに挑戦したい』という言葉は本心だと思います。彼の中ではもう十分やりきった、という感じではないでしょうか」
彼を古くから知る人物によると、「古舘はとにかく真面目で、抱え込みやすいタイプ」だという。『報ステ』の放送終了後は、ネット上での批判や誹謗中傷に必ず目を通していた。本人もここ最近は、かなり「ナーバス」になっていたことを認めている。
「降板のニュースを見ていて一番印象に残ったのは、『古舘降板だぜ。やったぜ』というコメント。誹謗、中傷、非難、いっぱいありました。メールや電話には11年9ヵ月、全部目を通した。多い時は(一日)600本あり、へこんだこともある」
何を言っても、何も言わなくても、批判される。そんなプレッシャーに追われる毎日に、古舘はもう疲れ果てていた。
■最後までプロレスだった
だが一方で、彼には本当にニュースキャスターとしての「資質」があったのか、という疑問も残る。ある番組関係者は、「やっぱりプロレスの実況アナから、古舘さんは、抜け出せなかったんだと思う」と語る。
「結局この12年、いくら古舘さんが訳知り顔で政策を論じたり、反原発を唱えたりしても、視聴者はショーを見ているような『違和感』を拭えなかったんですよ。
古舘さんは彼なりに一生懸命に努力し、勉強もしていたはずですが、筑紫哲也さんのような豊富な取材経験に裏打ちされた説得力や迫力は出せず、かといって久米さんのような軽妙さもなく、最後までどこか空々しかった」
元フジテレビ報道局解説委員でジャーナリストの安倍宏行氏も語る。
「久米さんには自分はジャーナリストでないとの自覚があった。一方、古舘さんは自分がジャーナリストであるかのように振る舞い、反権力を装った発言をしていた。その結果、権力に付け込まれやすい状況を、自ら作ってしまったのです」
■下げ止まらない視聴率
古舘降板をきっかけに、2016年のテレビ業界の勢力図にも激変が訪れる。'13年にはゴールデン帯とプライム帯で視聴率2冠を達成し、現在年間視聴率2位のテレ朝が失速し、視聴率戦争はさらに激化していく。
「帯番組の成否は、局全体の視聴率を左右する問題です。夜の帯番組で『報ステ』のような手堅い番組があることはテレ朝にとって非常に安心感があった。その『視聴習慣』が崩れると、当然他の番組の視聴率にも影響する。『報ステ』は、テレ朝にとって『命綱』なんです」(放送記者)
もしリニューアルに失敗すれば数字はガタ落ち、テレ朝は、視聴率戦争で壊滅的な打撃を受けるだろう。
では、この機に浮上してくる局はどこか。今もっとも勢いのあるテレビ局といえば、間違いなくTBSだろう。
TBSメディア総合研究所『調査情報』の市川哲夫編集長はこう語る。
「昨年放送された『下町ロケット』は、TBSの復活を印象付け、ドラマが巷の話題になりました。視聴率争いのカギを握るのはドラマです。ドラマがいい局は全体も浮上する。1本の大ヒットドラマは他番組にも好影響をもたらし、局のイメージまでも変えるのです」
TBSの社員も鼻息は荒い。
「『半沢直樹』('13年)などをヒットさせた、福澤克雄ディレクターのブランドが確立されてきた。売り物になるブランドが今年は2つ、3つと増えていけば、瞬く間にトップに立てる。テレビはそういう仕組みの産業なのです」
事実、'70年代「民放の雄」と呼ばれていた頃のTBSには、大山勝美や久世光彦、石井ふく子らのドラマに、『8時だョ! 全員集合』などを生んだ居作昌果のバラエティーなど複数のブランドがあった。
一方、テレ朝は頼みの『相棒』の視聴率が、'07年以来の12%台にまで下がり危機に陥っている。
「さすがにシーズン14にもなれば視聴者も飽きますよ。バラエティーも含めテレ朝は『マンネリ化』が深刻です。でも上層部は過去の成功体験に縛られ、動こうとしない」(前出の放送記者)
現在、年間視聴率で2位のテレ朝だが、このまま一気にTBSに抜かれる可能性が高い。そして王者・日テレとTBSの一騎打ちになる。テレビ局の栄枯盛衰からも目が離せない一年になる。
「週刊現代」2015年1月16日・23日合併号より
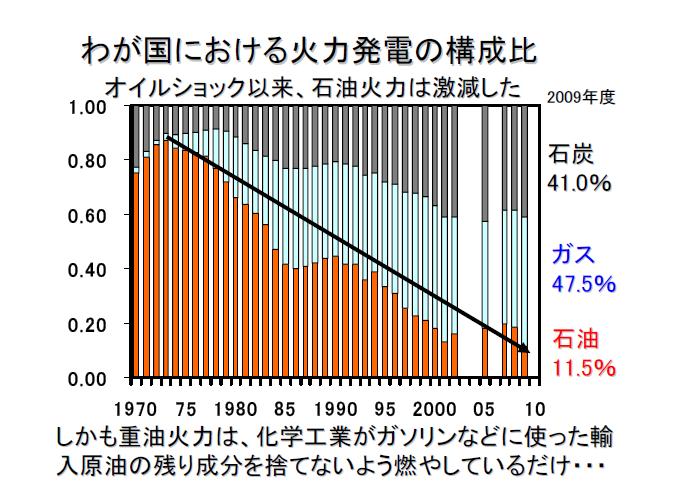

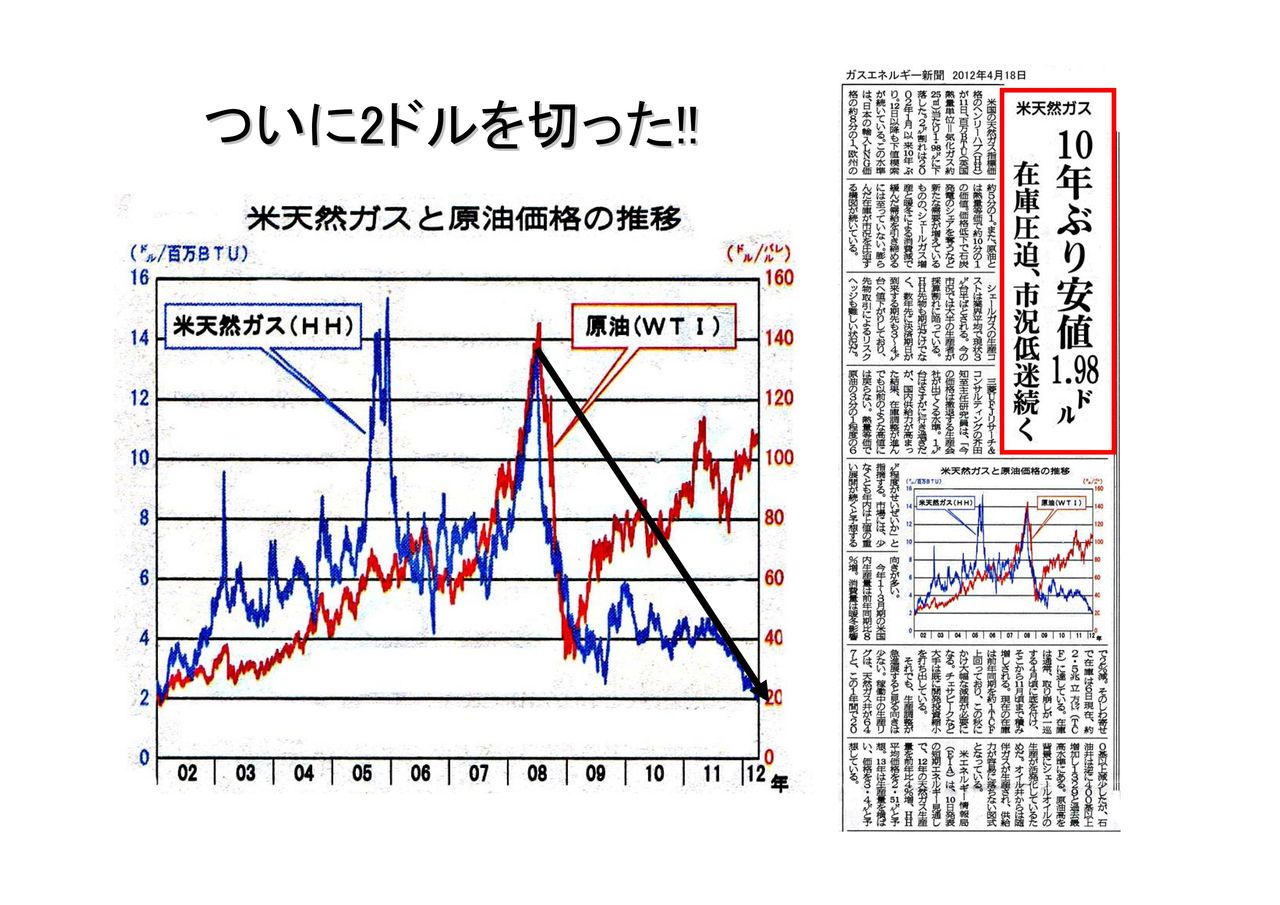
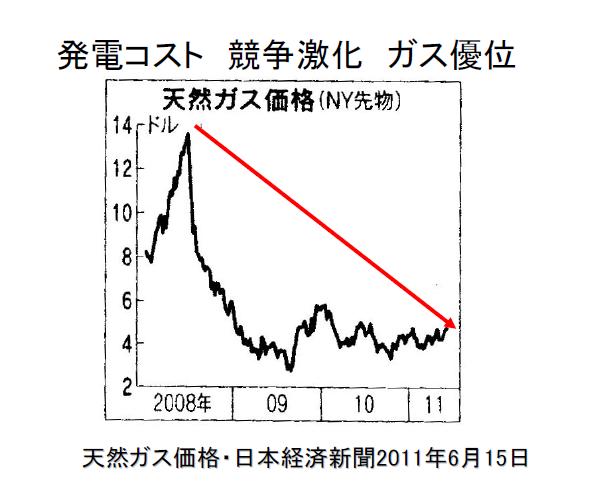

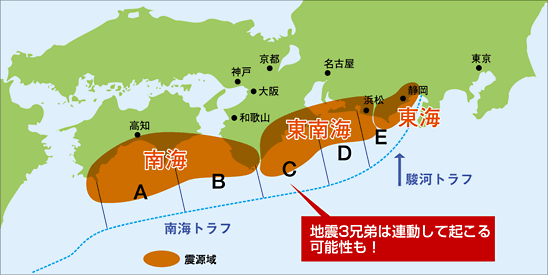
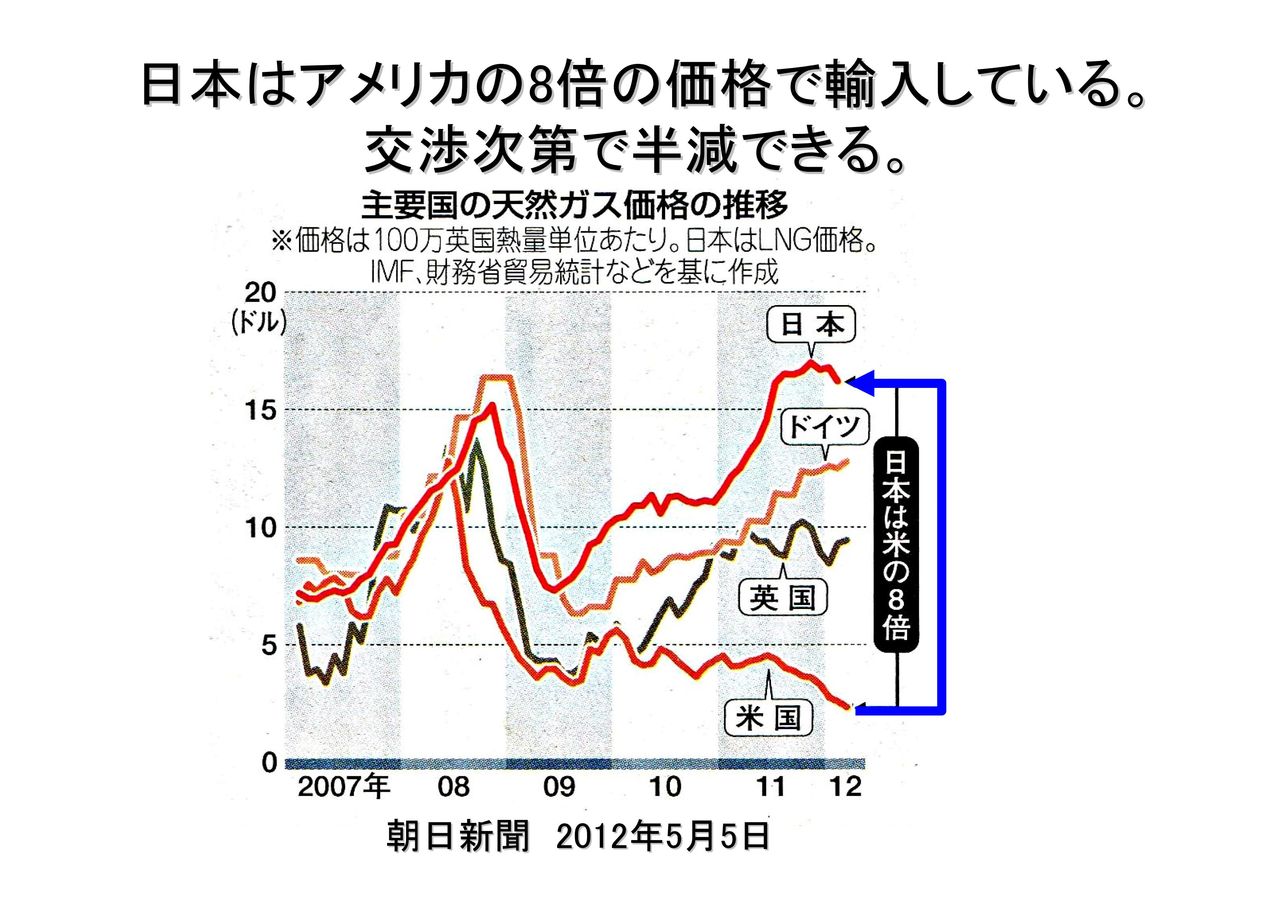
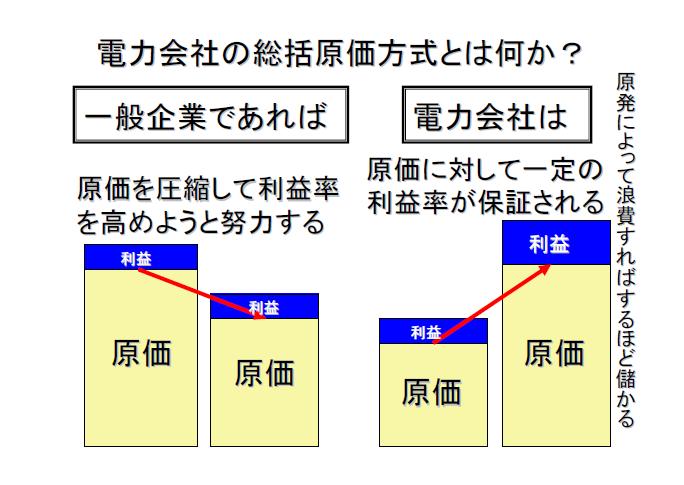
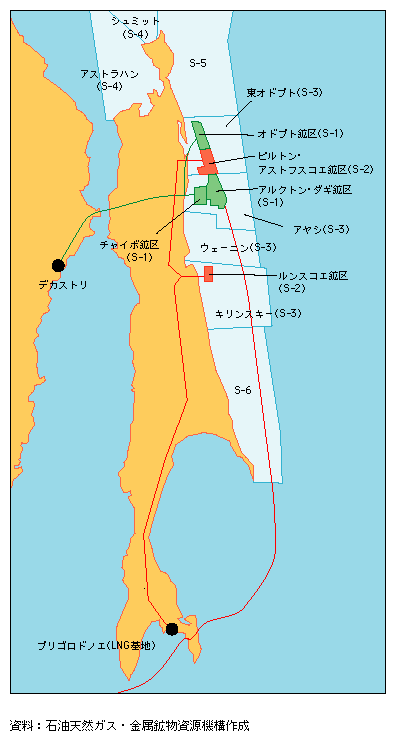
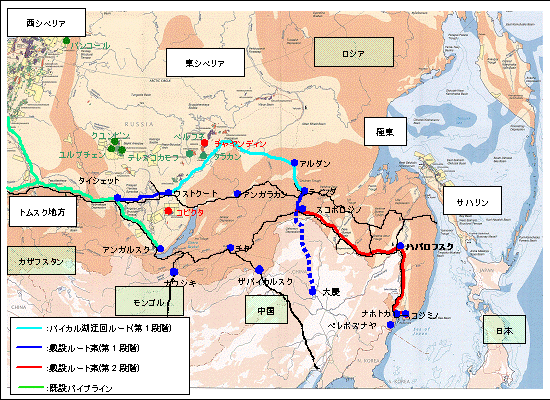



 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。