http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/170.html
| Tweet |
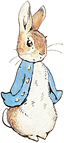
国家放送協会のこのニュースは、見出しでは「誰かが悪戯してるのだろう」と答えさせたいかのようだが。実際にコメントしている多くの人が知っているように、パブリックコメントはよほど大量に寄せられることでもないと「手続き」として冊子にまとめられ黙殺されるのが常だ。国などから「回答」があっても、其の殆どは国の立場を押し付ける「コピー&ペースト」のごとき類似文が並ぶだけとなる。さらに、記事中の「除染土利用」のパブコメなどは資料が難解で、どう書けばよいのか解らない問題があった。
問題なのは形骸化した制度のほうで、意見を寄せる市民ではない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー(ここから)
パブリックコメント20万件の衝撃 誰が何のために
2025年4月19日 17時36分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250419/k10014781621000.html
国が政策を決める過程で、国民から広く意見を募る「パブリックコメント」。
ふだんは数件から数十件というケースが多い中、ここ最近、ひとつの政策に1万件を超える意見が寄せられる異例の事態が相次いでいる。
政府は、一部の人たちが大量の投稿を行っていると分析。行政事務を妨げ、制度自体をゆるがしかねないと強い懸念を示している。
一体、誰が何のために大量投稿を行っているのか。
取材班はSNS上で繰り返し投稿を呼びかけていた複数の投稿者に話を聞くことができた。
そこで語られたこととは。
●対応省庁では夜まで残業も
先月、農林水産省の執務室では、多くの職員たちが夜遅くまで対応に追われていた。
食料不足などに備えた方針案についてパブリックコメントを行ったところ、およそ1万3000件の意見が寄せられたからだ。
これまでは数件から数十件程度というケースがほとんどだったが、一度に大量の意見が寄せられたことで職員らは読み込み作業に多くの時間を費やさざるを得なくなった。
意見の取りこぼしがないように、1つずつ丁寧に目を通し、内容ごとに仕分けして回答案を作成。上司の決裁も必要だ。
仕分けと回答にかかった時間は延べ500時間にも及んだ。
農林水産省によると、1か月の募集期間中にはXを中心に意見を提出するよう呼びかける動きが見られたという。
その影響か、特に最後の5日間には全体の半数以上にあたる7000件近くに急増。
しかし、寄せられた意見を分析すると、全く同じ内容のものが90%を占めていたことが明らかになったというのだ。
・農林水産省 河野研 企画官
「想定以上の件数が寄せられて戸惑っている部分もある。広く意見をくみ取って政策に反映させるためのパブリックコメント制度だが、職員が一つ一つ手作業でやっているので大量に意見が寄せられると、意見のくみ取りが難しくなるのではないかと課題を感じている」
●急増する1万件超のパブリックコメント
そもそも、パブリックコメント制度とは、国などがある政策やルールを決める際にあらかじめその案を公表して広く国民から意見を募集するものだ。
政策決定の過程に国民の意見を反映させる目的で2005年に今の形で導入された。
国が募集しているパブリックコメントでは、専用のホームページや郵送で誰でも意見を提出することができる。
1人が出せる意見の数に制限はなく、匿名でも提出が可能だ。
提出された意見は、募集した省庁が内容を検討した上で、反映すべきと判断すれば政策案を修正し、反映できない意見に対しては理由を回答することになっている。
自治体のケースだが、過去には川崎市がヘイトスピーチなどの差別的な言動を禁止する条例案について、パブリックコメントを踏まえて禁止する内容や期間などを修正するなど、実際に反映されたこともある。
国は毎年、数千件のパブリックコメントを募集しているが、2005年に制度が始まって以降、1つの案件に対する意見の提出数は数十件程度がほとんどで、ゼロという案件も少なくなかった。
中には、原発やエネルギー関係など賛否を二分するような政策案に対して、数千件や1万件以上寄せられることもあったものの、非常にまれだったという。
しかし、ここ数年で事情は大きく変わってきた。
*https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250419/K10014781621_2504181048_0418110254_02_08.jpg
2020年以降、1000件を超える意見が集まったケースが10〜20件ほどに増加。
2024年に入って、1万件以上を超えるケースも急増している。
●20万件の意見 96%が「コピペ」
特に意見が多かったのが、環境省が2025年2月15日までの1か月間に募集した、福島第一原子力発電所の事故後に除染で取り除かれた土の再生利用に関する基準案についてのパブリックコメントだ。
1か月で20万7850件の意見が集まった。
異例の多さで注目されたものの、農林水産省のケース同様、同じ文面の投稿が多く見られた。
句読点や改行なども含め一字一句同じだったものを1件として数え直したところ、意見の数は8277件になったという。
つまり、20万件余りのうち96%は、ほかの意見とまったく同じ「コピペ」意見だったということになる。
環境省によると、中には同じ投稿者の名前で1000件を超える意見が投稿されたケースもあったという。
・浅尾 環境相
「職員はすべての意見に目を通す必要があるが、同一の方から同一の意見が大量に送られると、行政事務の適正な執行の妨げにつながる可能性もあり、パブリックコメント制度のあり方自体に影響を及ぼしかねない」
●SNSで広がる呼びかけ
政府はこうした大量投稿が行われている事態が相次いでいる背景に、XなどSNS上での呼びかけがあると見ている。
X上では、パブリックコメントへの投稿方法を拡散したり、意見のひな型を共有しながら提出を呼びかけたりする動きが見られるという。
さらに、提出件数を競う動きや、意見を提出した際に発行される通し番号で「キリ番」と呼ばれる区切りのいい数字を得たことをアピールする投稿も見られ、政府内では一種のゲーム感覚で行っているのではないかという疑念も持ち上がっている。
私たちは、20万件を超える投稿があった除染土の再生利用の基準案について、SNS上での広がりを分析した。
すると、「パブリックコメント(パブコメ)」「汚染土」というキーワードを含む投稿が、意見募集期間の終了間際の数日間に急増し、1万件近く拡散されていることがわかった。
政府は、意見が多数寄せられること自体は問題ないとしつつ、同一人物による大量投稿はパブリックコメントの趣旨にそぐわない上、個々の意見について丁寧に対応することが難しくなっているとして、AIを使って意見を集約するなどの対応について検討を始めた。
●パブリックコメント呼びかける投稿者に取材
一体、誰が何のために大量投稿を行っているのだろうか。
取材班は、さまざまなパブリックコメントについて呼びかけを繰り返している複数の投稿者に取材を試みた。
なかなか取材を受けてもらえない状況が続く中、このうちのひとりから「対面でなければ取材に応じても良い」という意向が伝えられた。
会社員の男性で、活動を始めたのは、ある施設の建設に関するパブリックコメントがきっかけだったという。
Q. 活動を始めたきっかけや理由は?
きっかけは、政治ネタを投稿している仲間がスペース(音声チャット)で集まる中で「パブコメ」という仕組みを知ったことです。
当時、長崎大学にBSL4施設(エボラウイルスなど致死率が高いウイルスを使った実験施設)が建設されるという話題があり、「なぜ日本に必要なのか?」「長崎大学内に建設されるのはおかしい」「メディアが報道しないのはなぜか」といった疑問が原動力となりました。
Q. 同一の案件について、1人で複数のパブリックコメントを投稿することはあるか?
はい、同一の案件について複数回投稿したことがあります。
その理由は、投稿数を増やせば行政機関やメディアが振り向き、問題を認識してもらえると考えたから。
大量のパブリックコメントが投稿されることで行政機関側が騒ぎ出し、「パブコメ」という仕組みが世間に広まるきっかけになると期待したから。
件数が増えることで、参加する楽しさや背中を押される感覚が生まれるからです。
Q. 政策決定や行政機関の業務への影響についてはどう考えるか?
行政機関に与える影響は限定的であると考えます。
行政機関側には、もっとAIを活用していただき、件数が増えたくらいでへこたれないでほしいです。
Q. どのように文章を作成している?生成AIも使う?
基本的に、自分で文章を作成しています。
ただし、他の人の意見を参考にすることもあります。
具体的には、Xやグループチャットに投稿される文例を参考にしています。
また、AIについては、パブコメの意見募集に添付されている説明資料を解読する際に活用しています。
これらの資料は専門用語や役人言葉で埋め尽くされており、非常に分かりにくいため、AIを使って内容を理解しやすくする工夫をしています。
私たちの質問への回答からは大量投稿への問題意識は感じられず、むしろパブリックコメントという制度を知らしめることが目的だといった主張が繰り返し伝えられた。
●“政府のパブコメ運用に不信感”
取材を続けるうち、意外な申し出を受けた。
自分がパブリックコメントを始めるきっかけになったグループを立ち上げた中心人物にも、話を聞いてほしいという。
私たちは紹介を受けて、この人物とコンタクトを取ることができた。
除染土の再生利用の基準案や食糧不足に備えた方針案のパブリックコメントも主導したという。
Xでは、パブリックコメントの投稿手順や例文も紹介している。
メディアでの取り上げられ方に懸念があるとして、個人情報は明かさないとしながらも、取材は受けても良いという。
活動の狙いを聞いたのに対して語ったのは、政府によるパブリックコメントの運用に対する不信感だった。
・投稿呼びかけるグループの中心人物
「(パブリックコメントを)政策決定に反映していただければ良いと思うのですが、どんな内容の意見文でも、どんなにたくさんの意見文でも、結論ありきで強行されているのではないか?という疑念はあります。それではパブリックコメントを募集する意義とは何か?『とりあえず意見は聞きましたけど、反対意見はなかったですよ』そんなアリバイ作りに利用されないためにも、意見文を届けることは重要であると考えます」
その上で、何らかの規制が行われることへの警戒感も示した。
「(政府に)不利な投稿は『危険性を指摘する投稿』ということで制限される懸念があります。広く意見を募集するという姿勢と違うのではないでしょうか?今行政はこんなことをしようとしていて、それについて意見文を募集していると拡散する活動は『広く意見を求める』というパブリックコメントの趣旨と合致する活動と考えています。『数』に訴えるやり方に嫌悪感や危機感を持たれる方もおられると思いますが、『数』に頼るのが悪意ある人々と決まっている訳ではありません」
●“自分のことばで” 呼びかける人も
ただ、パブリックコメントを呼びかける人の中には、「コピペ」の投稿が増えている状況を快く思わない人もいる。
その1人、かおりさんは、微量の化学物質に反応して体調を崩す、メカニズムなどが不明の症状に悩まされていて、4年前から薬品関係や環境問題に関するパブリックコメントを投稿をしている。
かおりさんは、同じような経験を持つ人とSNSを通じてつながり、投稿を呼びかけているが、投稿者には自分たちの気持ちをそのまま伝えてほしいと話す。
かおりさん
「パブコメをみんなで増やしていく。私はこんな風に書きましたよっていう例が見られると、そこに着目すればいいのかとまた別の視点が加わってより内容が練られたいいものが送れるということもある。皆さん自分の言葉で書いてほしいので、私はコピペは推奨していないんです。こんな熱を持った内容を送ってきてくれるんだということで、省庁も意識が変わっていくんじゃないかという期待を込めているんですね」
●専門家“多数決の制度ではない”
パブリックコメントが大量に投稿される現象をどう見るか。
総務省の審議会の委員としてパブリックコメント制度の整備に携わった、学習院大学の常岡孝好教授に話を聞いた。
常岡教授は、多くの意見が寄せられること自体は望ましいとした上で、SNSを通じてコピペなどで大量投稿を呼びかける動きについては、制度の趣旨にそぐわないと指摘する。
・学習院大学 常岡孝好教授
「ある団体が構成員などに呼びかけて組織票のような形で投稿されるというケースはこれまでも多くあった。SNSで呼びかけるというのは、その形が変わってきたということだと思うが、パブリックコメントが多数決の制度ではないということがしっかり理解されていないことが、1人でたくさん出してしまうということにつながってるのではないか。パブリックコメントは民主主義的な意思決定を行うための制度だが、多数決とは違い行政がすくい上げきれなかった情報を吸い上げることに本来の趣旨がある。多くの人がそれぞれ意見を出すことによって大量の意見が寄せられること自体は関心の高さを示していると思うが、1人が同じ内容の意見を繰り返し送ることは制度の趣旨からも必要ない」
一方で、多様な声を政策に反映するというパブリックコメントの趣旨が必ずしも実現されてこなかったとも指摘した上で、政府が効率的に意見を収集、分析し、政策に取り入れる仕組みを整えることが必要だと話した。
「パブリックコメントによって内容が修正されるケースがあった一方で、行政側が提出された意見に対して通りいっぺんの回答しかせずぞんざいに扱っていたこともあった。また、パブリックコメントのタイミングが政策決定の最終段階になるケースが多いが、原案の策定段階で幅広い議論をして内容に反対する側の意見も検討しておけば、そもそも今回の大量投稿のようなことは起こらなかったのでないか。また、多くの意見が集まること自体は望ましいことなので、行政側には、今は文章を整理したり要約したりするソフトも発達しているので、大量に投稿があったとしても効率的に作業できる体制を整備してほしい」
●パブコメ大量投稿が投げかけることとは
相次ぐパブリックコメントの大量投稿を受け、政府は同じ内容の意見を複数投稿することに対して注意喚起を行ったり、「キリ番」獲得を競う動きへの対策として受付番号を受付順ではなくランダムに表示するなどの対策を始めた。
行政機関の事務に支障をきたすような事態は放置できないという危機感がうかがえる。
一方で、パブリックコメントの制度そのものに対する不満や不信感にどう対応するかが検討されている様子は見えない。
国民が直接政策に関与できる民主主義の重要なツールとして導入されたパブリックコメント。
今の制度になって20年、本来の役割を最大限果たすために何が必要なのか、考える時期に来ているのではないかと感じた。
(4月19日 サタデーウォッチ9「デジボリ」で放送予定)
(取材:科学文化部 橋口和門 島田尚朗/経済部 樽野章)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー(ここまで)
関連:
■万単位のパブリックコメントが届くからって…「AIで集約」アリなのか 数の重み「ガン無視」を心配する声
http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/159.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2025 年 4 月 18 日 03:26:44: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK297掲示板 次へ 前へ
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK297掲示板 次へ 前へ
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。