http://www.asyura2.com/24/gaikokujin3/msg/291.html
| Tweet |
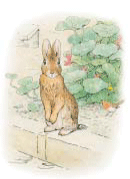
すでに「米軍基地化」が進んでいる自衛隊基地も...日本全土に存在する「基地問題」のリアル/ニューズウィーク日本版
池宮城陽子(東京科学大学特別研究員) アステイオン によるストーリー
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E3%81%99%E3%81%A7%E3%81%AB-%E7%B1%B3%E8%BB%8D%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%8C%96-%E3%81%8C%E9%80%B2%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%84%E3%82%8B%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E3%82%82-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%A8%E5%9C%9F%E3%81%AB%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%95%8F%E9%A1%8C-%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB/ar-AA1CZY9N?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=ede2b25db1a8462a9171880fa0b8c601&ei=13
<日本国民の防衛・安全保障に対する危機意識は高まっていると言われて久しいが、基地問題についての国民的議論は盛り上がらない。突破口はどこにあるのか──>
国民の防衛・安全保障に対する危機意識
SNSを通じて、目を覆いたくなるような戦争の残酷さを、日本に居ながらリアルタイムで目の当たりにするようになったからだろうか。 2022年2月に始まったロシアによるウクライナへの軍事侵攻以来、防衛・安全保障に対する日本国民の危機意識はかつてないほど高まっていると言われる。
例えば、2022年11月に実施された内閣府の世論調査では、「現在の世界の情勢から考えて、日本が戦争を仕掛けられたり、戦争に巻込まれたりする危険がある」、もしくは「どちらかといえば危険がある」と答えた有権者の総数は、全体の86%に達した。
だが実は、2018年の世論調査の時点で既に、「危険がある」「どちらかといえば危険がある」と答えた者の数は85%に達していた。背景には、北朝鮮の核兵器開発問題や、中国の軍備拡大および日本周辺地域における活動など、深刻化する日本の安全保障環境があると考えられる。
いずれにしても、防衛・安全保障に対する日本国民の危機意識が、現在極めて高い状態にあることは間違いなさそうである。
危機意識の高さ=国民的議論の活発化?
ところが、国民の危機意識が防衛・安全保障問題に関する国民的議論を活発化させたかといえば、必ずしもそうではない。そのような状況を象徴するもののひとつが、基地問題だろう。
「基地問題は沖縄だけの問題」──たとえばそういった考えが、基地を抱える地域が直面する問題への関心を遠ざける原因になっているのではないか。
基地問題が沖縄だけの問題でないことは、山本章子・宮城裕也『日米地位協定の現場を行く―「基地のある街の現実」』(岩波書店、2022年)が明らかにしている。「基地の現場」の人々の声をありのままに記し、日本各地の基地問題を考えさせてくれる1冊だ。
本書は、日米地位協定において認められた特権によって、米軍が米軍基地のみならず全国各地の自衛隊基地でも訓練を行えること、そのため日本に住んでいればどこでも基地問題に直面する、もしくはその可能性があることを指摘する。
すでに「米軍基地化」が進んでいる自衛隊基地もあるようだ。築城基地(福岡県)は、嘉手納基地の戦闘機訓練を受け入れているほか、新田原基地(宮崎県)とともに、有事の際に普天間飛行場に代わって米軍を受け入れることになっている。
築城基地周辺の自治体が、「沖縄の基地負担軽減」のための米軍再編に伴う基地負担を、再編交付金と引き換えに受け入れたためだ。再編交付金は、訓練が実際に行われた度合いに応じて自治体に払われている。
だが、「米軍基地化」によって、日米地位協定で取り締まれない米軍による騒音や事件・事故が起こるのではないか。基地周辺の住民の不安や懸念は強まっている。「沖縄の基地負担軽減」策が本土で新たな基地問題を生み出しているという、通常の報道では知り得ない「基地の現場」の実態だ。
また、基地に対して、賛成/反対のどちらか一方に立つわけではない各地の状況や、基地をめぐって存在する世代間の温度差を記しているところにも本書の特長がある。
こういった「基地の現場」の複雑な実情は、読者に基地問題の難しさを知らしめるものの、そのインパクトが問題への関心を喚起する。
東京にもまだある基地問題
基地問題は誰にでも起こりうる問題である。本書のこの指摘の重要性を、私は身をもって実感している。というのも、私自身が基地問題に直面しているからである。
現在の住まいは、10キロほど先にある横田基地(東京都福生市など)所属の軍用機の飛行経路下にあり、低空飛行している軍用機を頻繁に見かける。夜間には窓を閉め切っていても、軍用機が通過する際の騒音が嫌でも耳に届く。
横田基地には2018年から輸送機CV-22オスプレイが配備されており、事故を引き起こす可能性の高さを主な理由として、関係自治体に住む住民を中心にオスプレイの配備前から抗議活動が行われている。私が住む自治体でも、オスプレイが飛行経路を外れて飛行したことが問題になったことがある。
しかし、本書が指摘するように、日米地位協定では在日米軍の基地外での訓練に関する制限がない。そのため、飛行訓練はあくまで基地から基地への「移動」に過ぎないと米軍によって正当化されてしまう。
こうした事情ゆえに、飛行に関する自治体や住民からの要望が聞き入れられる可能性は低い。
関心をもつところから始める
横田基地の問題をめぐっては、抗議活動のほか騒音訴訟も行われているが、規模は概して小さい。2023年11月に、横田基地所属のCV-22オスプレイは屋久島沖で墜落事故を起こしたが、翌年7月には周辺自治体への事前通告もないままその飛行を再開させている。
だが、これらの問題が起こっても、横田基地の問題に対する人々の関心が高まっているようには見えない。
「米軍は危ないな」「何か大変なんだな」と思っていたが、思考がそこから先に進むことはなかった。基地問題よりも部活や友人関係など、自分の生活の範囲のことで頭がいっぱいの普通の学生だった。目の前でヘリが落ちたことで初めて、自分や身近な人の命の危険を感じ、日本の法律さえ守られない状況が自分の生活の延長線上にある、それが基地問題だと知らされた。(『日米地位協定の現場を行く―「基地のある街の現実」』、iv-v頁)
本書の執筆者のひとりであり、宜野湾市で生まれ育ち普天間飛行場が「日常」であった宮城氏のこの回想には、日本社会において基地問題に対する関心が高まらない理由が隠されているように思われる。
たとえ「日常」に基地の存在があり、漠然とした危険性や不安を感じていても、何か大きなきっかけがなければ、慌ただしい日常生活のなかで基地問題に関心を抱くことは難しい。「日常」に基地が存在しなければ、なおさらであろう。
本書のもうひとりの執筆者である山本氏は、日本に住む大多数の人が基地問題に関心を抱いていない現状が、問題の解決を難しくしていると指摘する。
そうであれば、まずは、誰でも基地問題の当事者になりうるという、日本の現状を知るところから始めてはどうか。防衛・安全保障に対する日本国民の危機意識が極めて高い状態にある今が、基地問題への関心を高める絶好の機会なのではないか。
日本の安全保障は岐路に立っていると言われて久しい。本書のような、日本の防衛・安全保障をめぐる問題の実態をありのままに伝える本が、問題への関心を人々に抱かせるきっかけとなり、国民的議論の活発化を促すのかもしれない。
池宮城陽子(Yoko Ikemiyagi)
慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得満期退学、博士(法学)。成蹊大学アジア太平洋研究センターポスト・ドクター、日本学術振興会特別研究員(PD)などを経て、現職。専門は日米関係史。主著に『沖縄米軍基地と日米安保―基地固定化の起源1945-1953』(東京大学出版会、2018年)がある。「戦後米国の沖縄基地政策―『二重の封じ込め』と沖縄基地の役割、1945~1951年」にて、サントリー文化財団2013年度「若手研究者のためのチャレンジ研究助成」に採択。
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。