【第102回】 2018年8月29日 浅川澄一 :福祉ジャーナリスト(元・日本経済新聞社編集委員)
日本が学ぶべき、介護費用を抑制するオランダとドイツの仕組み
ドイツの介護施設
ドイツの高齢者施設の様子。ドイツでは介護費用の抑制策が進んでいる。
高齢者の急増に費用が追い付かないため介護保険制度の介護サービスが縮減されつつある。現在70歳前後の団塊の世代が80歳を超えると、介護サービスへの需要はさらに高まる。他の先進諸国でも同様に、ベビーブーマー世代の高齢化に伴う財源難に悩まされ、効率的な運用に乗り出した。 介護保険を日本より早く制度化したオランダとドイツでは独自の総費用抑制策に取り組んでいる。 オランダは自治体への権限移譲で
交付金25%減、住民の力を借りる路線へ
1968年のナーシングホーム(日本の特別養護老人ホームに相当)から介護保険(AWBZ)の導入を始めたオランダでは、2007年に第一次の改革を始めた。介護保険サービスの中の掃除や買い物などの家事援助を地方自治体に権限を移し、その分国の負担を軽くした。受け皿となった自治体の制度(WMO)は、従来の社会福祉法と障害者法を統合したもので、住民主体の住民自治の力を効率的に発揮してもらおうという狙いだ。 これに先立ち、就任したばかりのウィレム・アレクサンダー国王が2013年9月に「オランダは、これまでの福祉国家から参加社会に転換しなければ」との声明を発表した。手厚い社会保障政策を続けてきたが、GDPに対する予算比率が年々高まり、もはや限界と判断。政府に頼るだけではなく、国民一人ひとりが地域社会への参加意識を持ち、助け合い活動に乗り出すように呼び掛けた。 元々ボランティア活動が浸透している国だけに、国王の呼びかけは好意的受けとめられた。AWBZの改革もその路線上で行われた。 次いで、2015年には第二次改革に挑む。AWBZの役割を高齢者施設だけに限定し、訪問看護やリハビリなど医療系サービスを医療保険(ZVW)に移すとともに、通所介護などの在宅サービスをWMOに全面移行させ、AWBZの名称もWLZと変えた。(図1) 「国から自治体へ制度を移行」図表
拡大画像表示
こうした地方自治体への権限移譲にともない、国から自治体への交付金も2015年から25%削減した。 介護教育部長が語る改革方針
医療者と近隣住民を繋ぐ「地域ケア」の重要性
首都のアムステルダムで、この2015年改革を担うデュオ・ステュールマン介護教育部長から具体的な方針を聞いた。 「大規模で単機能なサービス提供法を改め、小規模で多機能な方式に転換させようとしています。地域から疎遠な関係から地域に密着したやり方に変える。住民へのサービスがより行き届くようになります。そのために小さな組織を支援していきたい」 医療や介護のプロにすぐに頼るのではなく、市民ができるだけ自分たちの力を発揮できるようにと、仕組みを変えつつある。 「これまでは、税金を払っているのだからサービスは当然受ける権利があると多くの国民は考えていた。それを、自分たちでできることは自分たちで、と変えねばならない」 家庭医(GP)にも意識改革が及ぶ。地域との付き合いが深く、住民からの信頼度は高い。国民はすべて近所の家庭医に登録する制度が定着しているからだ。 「GPから2次医療機関への紹介状をすぐに出すのではなく、まず地域のケアサービスを活用することで対処できないか考えてもらう。できるだけ医療機関に頼らないようにしたい」 自治体が担うWMOの業務は広がった。住宅改修や車椅子の貸与のほか、美術館などへの同行ボランティアの派遣、ホームレスへの宿泊紹介、家庭内暴力への対応など高齢者だけではなく、「生活困難者」向けの業務を一手に担う。 強調したのは「地域ケア(バイクゾルフ wijkzorg)」という考え方だった。本人の左右に2つのグループを描いて説明する(図2参照)。右側に家庭医、訪問看護師、病院、保健センター、左側に家族、ボランティア、福祉施設、同伴者などがあり、両グループをまたぐように「地域ケア」と書かれている。右側の医療系の専門職集団と左側の近隣の住民集団という2つのグループを結びつけ、両グループが本人を支援するというのが「地域ケア」である。(図2) 「地域ケアは専門職と住民で」図表
拡大画像表示
右側の制度上の組織だけではこれからの介護施策は限界があるとみたのだろう。その限界を補完するために、左側の地域住民の関わりが求められる。この両グループの融合、即ち地域ケアを動かすために新たに設けたのが「地域チーム(バイクチームwijkteam)」だ。 そして、「従来の制度では、当事者への理解不足もあって、不必要なサービスを提供していたことも多かった。それを効率化させねばならない。必要ない人まで施設入居していた」とも話す。従来施策の基本的な見直しが始まっているようだ。 この2015年改革で、国から自治体に渡される交付金は25%も削減されたが、 「どの自治体からも不平不満の声は出ていません。利用者本位で動いてみると、この新しい予算内できちんとできることが分かったようです」 「国の制度から自治体・地域の自主事業へ」という大きな流れは欧州諸国に共通する。オランダでも同様だが、かなりドラスティックに進められているのは間違いなさそうだ。 ドイツは介護保険料を4回アップ、
総費用を抑制するための仕組みも導入
日本より5年早く介護保険をスタートさせ、日本が参考にしたのがドイツ。 高齢化率は22%で、日本より5ポイントも低い。それでも制度発足以来、保険料率を4回アップさせ財源を拡大させてきた。昨年1月には多くの認知症の人を対象者として迎え入れる大改革を断行した。 規模を拡大しているように見えるが、実は、総費用を抑制する仕組みを巧みに取り込んでいる。ひとつは「部分給付」と言われる基本的な考え方であり、もう一つは家族介護を広げるための現金給付である。 スタート時の保険料率は収入に対して1.7%だったが、昨年1月には2.55%まで上げた。経済成長が大幅な上昇を支えた。同時に3段階の要介護判定を5段階に広げた。(図3) 「2017年以降の給付」図表
拡大画像表示
認定基準も大きく変わった。「介護にどのくらい手間がかかるか」から「本人がどんな生活ができるか」になった。同時に身体介護中心だった制度に認知症など精神・知的機能面からケアが必要な人も要介護者に含めた。 度重なる制度改定の中で、近年、認知症の人向けに「要介護0」を設け、要介護1のほぼ半額の給付をしてきたが、昨年1月には本格的に取り込んで要介護2にアップした。 「確かに認知症の人への判定が緩やかになり、利用者が20%ほど増えた」「サービスを受けられる人が増えたのは良いことだと思う」と改定を評価する事業者が大半だ。 ベルリン在住のジャーナリストで研究者の吉田恵子さんは、「新たに約50万人の高齢者が要介護者と認定された。その大半は認知症の人になった」と言う。 なかには「とっても複雑で基準項目が15から144にも増えて大変。要介護度が低くされたと言う利用者のために、不服の申し立てをしようにも簡単にはいかない」(リュッセルハイム市のアルツハイマー協会)と嘆く声もある。 日本の介護保険でも、「認知症の軽度者は歩行や食事摂取など身体動作に問題がないことが多いため、要介護認定が軽くなってしまう」と苦情が寄せられ、認定基準の見直しを迫られたことがあった。もう10年ほど前のことだ。現地の施設視察の体験を踏まえても、認知症ケアへの取り組みは日本が一歩先行しているようだ。 ドイツ介護保険の財源は保険料のみ
「部分保険」によって総費用を抑制
ドイツの介護保険が日本と異なるのは、まず、利用者に年齢制限がないこと。医療保険と同じように国民すべてが保険料を払いサービスを受ける。労働者と経営者が折半の保険料だけが財源で、税の投入も利用者の自己負担もない。 保険制度の原則が貫かれており、さすがビスマルク以来の「社会保険の母国」だけのことはある。財源の半分に税が投入され、1割の利用料負担で始まった日本とは異なる。 そして、保険者は基礎自治体ではなく、「介護金庫」である。医療保険を運営する「疾病金庫」がそのまま2枚看板を掲げて運営している。 独立の公法人で日本の健康保険組合と似た組織だ。企業や同業者、地域などの単位で成り立ち、かつては全国で4ケタもあったが統合が進み、今では108に集約されている。最大手のAOK(一般地域疾病金庫)は、全16州に置かれ介護保険被保険者の半数近くが加入している。 介護保険法は1970年代から連邦議会で議論され「負担増になる企業側はずっと反対してきた。労働者側との妥協の結果が部分保険という決着になった」(フランクフルトの施設長)。 「部分保険」とは聞きなれない用語だが、要は介護保険だけでは十分でないと言うこと。例えば要介護5の人が施設に入居する際、1ヵ月の利用料が全国平均の40万3000円(3100ユーロ)とすると、介護保険では要介護5の場合で約26万円(2005ユーロ)しか給付されない。残りの約14万円は自己負担となり、年金や預金で補う。保険で賄うのは「部分」というわけだ。(図4) 「施設の利用料に届かない『部分保険』」図表
」
拡大画像表示
施設によって利用料はバラバラだから、自己負担額も異なる。地域差もある。南西部は高額で、旧東独地域は安い。職員の人件費や物価の格差による。 年金と預金が足りなければ、州自治体から「介護扶助」(生活保護に近い制度)を受給できる。従って、自己負担分が約14万円の場合に、年金や預金などで12万円分しか払えなければ、残りの約2万円を介護扶助で補うことができる。 日本では特別養護老人ホームの利用料は全国一律で、入居する際に要介護度に応じて利用料の1割だけ払えばいい。介護付き有料老人ホームでは、事業者に費用の一部が介護保険から「特定施設入居者生活介護」として給付が得られ、かつ、施設によって利用料がバラバラという点で、この「部分保険」と同様な仕組みと考えてよいだろう。 給付額を日本の制度と比べると、施設への給付費が要介護4と5で4〜5万円低く、その上利用料が高いので、利用者の負担は大きい。在宅サービスでは日独の差はさらに広がっている。総費用を抑える狙いからだ。(図3参照) 日本にはない「現金給付」も導入
家族介護の担い手を「労働者」と見なす
もうひとつ、日本と大きく異なるのは、家族介護者向けの「現金給付」が大きな役割を果たしていること。 日本では家族への現金給付で大議論があった。「家族が互いに助け合うのは日本の伝統であり美風」と言う推進派に対し、「嫁や娘、妻たちが介護を強いられてしまう」とする反対論が鋭く対立した。「介護の社会化」を掲げた介護保険の原則論が通り、現金給付は消えた。 ところが、ドイツでは当初から重視されている。何しろ在宅介護の過半がこの「現金給付」だ。「施設入居より在宅重視」とする基本施策は日本と同じだが、現物給付の半額以下の安い家族介護で総費用の圧縮を図っている。現物給付とは、訪問介護や通所介護(デイサービス)などの在宅サービスである。 実は、家族介護の担い手を「労働者」と見なしているところが肝心である。介護者の介護時間が週14時間以上あり、かつ、30時間以上は社会で働くことはできない状態であることが条件となっている。 労働者であるから、年金や労災保険、失業保険に加入できる。2年間の介護休暇を取得して、その後に元の職場に復帰する。 現金給付は要介護者の口座に振り込まれる。つまり要介護者が「雇用主」となり、子どもや親族、近隣者、あるいはファミリーヘルパーなどに介護費として渡す。このファミリーヘルパーは、散歩や掃除、洗濯などの生活支援を行う職業として定着している。諸団体が講習会を開いて資格を与えるが、国家資格ではない。 このほかに、ポーランド人を中心にした東欧やトルコなどからの移民を含めた外国人ヘルパー(家政婦)が大勢いる。その数は、40万人に達するとも言われる。低賃金労働者が多く、斡旋業者が介在する「闇労働」とも指摘されている。2011年からEU域内では労働者の移動が自由になったことが拍車をかけている。 24時間の継続した介護が必要な場合に外国人ヘルパーを住み込みで頼むと、現金給付の対象となるが、給付額が少なく大部分は持ち出しにならざるを得ない。 介護者がきちんと介護を受けているかのチェックが為されることもあり、今のところ現金給付制度への批判はほとんど聞かれない。 現金給付を設けた最大の理由は、できるだけ在宅介護を続けて、費用が高い施設入居を思いとどまらせたい政策判断がある。当初は、確かに現金給付の比率が高かったが、最近では大都市部を中心に独居者が急増しており、現物給付の比重が増えつつある。 現金給付と現物給付を組み合わせた「コンビネーション」と言われる使い方も広がっている。 (福祉ジャーナリスト 浅川澄一)
|
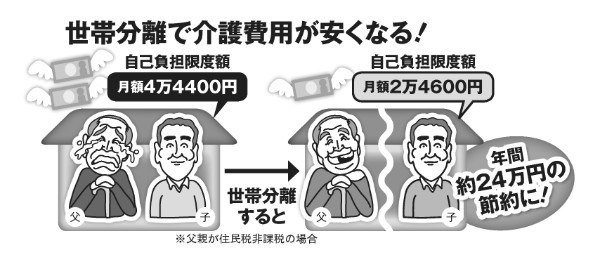
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。