����̊Ō�w�A���邢�͍ł�����ȋ����ϔO
http://yokato41.blogspot.jp/2014/02/blog-post.html
����Ȃ̋����ւ̏����s�Ɂw����x�̕��ɖ{���g�����N���Ԃ�œǂݕԂ����B�h�X�g�G�t�X�L�[�̍�i�̂Ȃ��ł͍D�݂̂��̂̂ЂƂł��Ԃ�l�ܓx�ڂ��炢�̍ēǂ��B���R���݂͊Ş��q�̗т̂������ɒ݂�ꂽ�n�����b�N�ɗh��Ȃ���A���邢�͍������̉Ƃ̔̊ԂŃe�g�j���̎��Ɠ��齂ɐ�ۂ������Ȃ���v���̂ق��M�����ēǂގ��Ԃ��������B
�Ƃ���Łw����x�̃_�[�����Ƃ������̓h�X�g�G�t�X�L�[�̍Ȃ����f���ł͂Ȃ����낤���B�`�L�I�����ɂ͑a���Ȃ���A�����ăC���^�[�l�b�g��ł��������ׂĂ݂Ă�����Ȍ����͌�������Ȃ��̂����A�A��ĞO�ȋL����T��悤�ɂ��ď��яG�Y�́w�h�X�g�G�t�X�L�C�̐����x��ㆂ��Ă݂�ƁA��Ԗڂ̍ȃA���i�E�O���S���G���i�E�X�j�g�L�i�̓h�X�g�G�t�X�L�[�̑��L�҂Ƃ��Ă̎d����^�����Ēm�荇���Ă���̂����A������h�X�g�G�t�X�L�[�̈ꕶ�����ɂȂ�܂ł�߂��Ȃ��q���Ȃɂ�鐶���̋����A���邢�͐�Ȃ���������Z�̎c���ꂽ�Ƒ��ւ̉ߏ�Ƃ�������S�z��A���Ƃ��ΌZ�̍Ȃ̊O�����o�����߂ɊO�������ɓ����ȂǂƂ������Ƃ܂ł��ċ����قǂ́u���g���v�ł���B������I���ł��ᒂ̔���̑����̂��ƁA���悩��F�l���̎莆�ɂ͂�������B
�l�̐��i�͌����a�I�Ȃ̂�����A�ޏ����l�̗l�Ȓj�ƈꏏ�ɂȂ���A���낢���J���邾�炤�Ƃ��v�Ă�B���۔ޏ��͖l���l�ւĂ��肸�Ƌ��������A�[���S�����������Ƃ��ӎ������ė����B�������낢��Ȏ��ɏo��Ėl�̎��_�ƂȂĂ��ꂽ�B���A�����ɔޏ��̂Ȃ��ɂ́A��������̏��Ȃ̂�����A�q���炵���Ƃ��낪��R����B��������������̂����A�K�v�Ȃ��̂����A�l�Ƃ��Ă͂ǂ��������炢���������������˂�B�Ƃ܂��������ӗl�Ȏ��͏o���̍ۍl�ւƂ�����B���ǂ��l�����A�ޏ��͍l�ւĂ���y���ɂ����肵���P�ǂȏ����B�����������S�͂Ȃ�Ȃ��v�i1867�N�A8��16���A�W���l�G�����}�C�R�t���j
�������h�X�g�G�t�X�L�[�̑n�������l���́A���ꂼ��ɂȂ�炩�̃��f��������̂��낤���A�A���i�����̂܂܃_�[�������Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ��B�d�������ҁA�c�������҂̃X�^�����[�M���̊Ō�w�u�������_�[���������łȂ��A�X�e�p�������u���g�I�Ɂv���b���郏�����[���v�l�̂Ȃ��ɂ��A���i������̂��낤�B
���w�҂͂ЂƂ��я����A���̍쒆�̏��l���́A�g�Ԃ�A�Ɠ��̂����A�꒲�́A�ǂ��Ƃ��āA�ނ̋L������ނ̗슴�������炳�Ȃ��������̂͂Ȃ��̂ł���B���肾���ꂽ�l���̖��̂ǂ��Ƃ��āA���n�Ɍ��Ă����l���̘Z�\�̖������̉��~���ɂ���Ă��Ȃ����̂͂Ȃ��A�����̈�l�͊�������߂邭���̃��f���ɂȂ�A���̈�l�͕Ђ߂��˂̃��f���ɂȂ�A�^�͔���I�ȕ���A�^�͂������r�̓����������A���X�̃��f���ɂȂ����B�i�v���[�X�g�u���o���ꂽ���v�j
�ȉ��͎G�R�ƈ��p�𒆐S�Ƀ����������̂����A���܂�ɂ������Ȃ����̂łЂƂ̂܂Ƃ܂�̂悤�Ȃ��́A���߂��Ƃɂ̂��قǐߑ�������B�ߑ�Ɠ��e�����܂荇�v���Ă��Ȃ���������Ȃ����A�C�ɂ��Ȃ��ł������B �y���_��ʂ��ēǂނ��Ƃ̕s�сz �s�l�Ԃ̐S���ɂ��ċ����Ă��ꂽ�ő�̐S���w�ҁt�ƃh�X�g�G�X�t�L�[���Ăԃj�[�`�F�̌��t��s�h�X�g�G�t�X�L�C�́A���_���͊w�����������^�����I�O�Ɍ���Ă���t�i�m�C�t�F���g�j�Ȃǂ̌��t���e�G�ɗ��p����āA�ꎞ���A�Ƃ��ɑO���I���t�O��A�h�X�g�G�t�X�L�[��S�����͂̋ɒv�̃e�L�X�g�Ƃ��āA���邢�͐��_���͊w�I�ϓ_����_�����]�����s�����͎̂��m�̂��Ƃ����A���̔����Ƃ��ā|�|����͂Ȃɂ��h�X�g�G�t�X�L�[�ɑ��Ă����łȂ����[�[�A�̑�ȕ��w�҂̃e�N�X�g�_���͗��_�ɂ���ēǂ݉����ȂǂƂ����u���疳�p�v�̒�����绂ɂ��肵�Ă݂���̂��u���w�ʁv�̏�����������������B �����̂Ȃ��ł����A���Ƃ��}���f�B�A���O�́w�C�̕S���xLe Lis de mer�i1956�N�j�͂ƂĂ��@�ׂȎ��I�ȃe�L�X�g�ł���ɂ�������炸�A���̏����̍Ō�ɁA��l���̐��Ȃ��A���_���͗��_�ɂ���Đ����ꂽ�肷��A���̐}���I�ȕ���I���Ƃ����݂ɋ����ߊ����o���Ă��܂��i���₻�̂悤�Ȃӂ�����Č��邾���ł������j�B����ȗނ̏����ɂ́A�������������ǂ݂ł͂Ȃ��킽���������x����荇���Ă���B�����Ă������Ƃ���ɏ��ւłЂƂ������߂Ă݂�����A���ԓ��Ř��߂����ċC����Ă݂���̂��A�����ǂ݂Ƃ��Ắu�C�L�v�ȐU�������Ɩ�Y����ȍ��o�ɕ������肦���u�K���v�Ȏ�����킽�����͂��������Ƃ�����B ���_�A�Ƃ��ɐ��_���͗��_��ʂ��ĕ��w��ǂނ��Ƃ��������锽�����ɂ́A�����́u�͂����Ȃ��v���ЂƂ͂Ƃ߂Ĕ�����悤�ɂȂ��Ă����͂����B�ނ��뗝�_�͕��w�ɂ���ēǂ܂��ׂ����[�[�s��]�͏����̉�Ǒ��u�ł͂Ȃ��A�������������u�ł���t�i�@���d�F�w�����̃G�`�J�x�u���Ƃ����v�j�\�\�Ƃ����ԓx�������ꂽ�����ւ́u�����ȁv�ڂ����ł���Ƃ���̂���\���I�㔼�́u�悫�v�ǂݎ�́A���Ȃ킿�������������Ȃӂ���������X�m�b�u�����̎p���ł��������낤�B
�y�h�X�g�G�t�X�L�[�����̃i�{�R�t�z ���ĂƂĂ��悭�ǂ܂ꂽ�h�X�g�G�t�X�L�[�����A���̐_�b�I�]�͂��̂܂ɂ����������Ă���i�����Ƃ�����͌ÓT���w�S�ʂɂ����邱�Ƃ�������Ȃ��j�B���яG�Y����]�Ƃł���������A���邢�͂��̖��c�肪�o�߂��Ȃ����A���Ȃ킿��w�����̎������ɂ����Ώ��яG�Y�̃e�L�X�g���g�p���ꂽ����ɂ́A���яG�Y�������Ƃ��͂����Ĕ�]�����Ώۂ̂ЂƂ�ł���h�X�g�G�t�X�L�[�ɂ������āA���w�ɊS�̂Ȃ����̂܂ł��f�p�Ȑ��q�A���邢�͂��̐S���`�ʂ̌������Ɏ]�Q���Ă݂���ȂǂƂ������Ƃ��������B �����ł�������蓹���āA�h�X�g�G�t�X�L�[��̍�ƂƂ���i�{�R�t�̎咣�����グ�Ă݂悤�B �������́w�������x�Ɓw���x�Ƃ���ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����I�Ȓj�͉ɂȎ��Ԃɂ͑S���̖�b�ɂȂ肩�˂Ȃ��B���̖L���Ȑl�Ԃ͌����Ďc���Ȑl�Ԃł͂Ȃ��B�c�c�h�X�g�G�t�X�L�[�� �����I�ȍ�ƂƌĂԏꍇ�A����́A�ǎ҂̑��Ɉ��P�I�ȓ���̔O���@�B�I�Ɏ�N���悤�ƁA ����ӂꂽ������|�p�I�Ɍ֒������ƁA�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł���B�i�i�{�R�t�w���V�A���w�u�`�x�j �h�X�g�G�t�X�L�[�Ɋւ��鎄�̗���́A��ł���A�܂����ł���B���̍u�`�̂��ׂĂɂ����āA ���͕��w�ɋ����̂���B��̊ϓ_���焟�����Ȃ킿�i������|�p�ƌl�̍˔\�Ƃ����ϓ_���當�w�� ����̂����A���̂悤�Ȋϓ_���炷��A�h�X�g�G�t�X�L�[�͈̑�ȍ�Ƃł͂Ȃ��Ăނ���}�f�� ��Ƃł���A�����ܐ▭�ȃ��[���A�̑M��������Ƃ��Ă��A�߂������ȁA�M���ȊO�̏ꏊ�͑啔�������w�I���蕶��̍r��ł���B�i����j
�s�i�{�R�t�̓`�F�[�z�t�������]�����A�ނ����̃��V�A��Ƃɗ^�����]���Ƃ��Ă̓g���X�g�C�̂`�v���X�Ɏ����`���v�[�V�L���ƃ`�F�[�z�t�ɗ^���Ă���B���̍�Ƃ̕]���́A�c���Q�[�l�t���`�}�C�i�X�A�S�[�S�����a�A�h�X�g�G�t�X�L�C�͂b�}�C�i�X�i���c�v���X�j�ŁA�u�`�F�[�z�t�����h�X�g�G�t�X�L�C���D���Ȏ҂ɂ̓��V�A�̐����̖{���͌����ė����ł��Ȃ����낤�v�ƃE�F���Y���[��w�̏��q�w�������ɘb���Ă����t�iHannah Green, "Mister Nabokov�j�B �i�{�R�t�̃h�X�g�G�t�X�L�C�����́A��Ƃ̑@�ׂȎ��I�\���������̗v�Ƃ���ނ̕]�_�⏬��������M���Ȃ��ł͂Ȃ��B�`�F�[�z�t�́w����A�ꂽ������x�ɂ�������̔��[�Ƃ��Ă̕��t�ዾ�i���[�l�b�g�j�̕`�ʂ�������A�A���i�E�J���[�j�i�u�`�̃i�{�R�t�̂Ȃ�Ƃ����ׂ₩�Ȏw�E��i�Q�ƁFPDF ���̐j�A�X�C�̂��݁\�\ �w�A���i�E�J���[�j�i�x��ǂݒ����\�\ �ᓇ�� )�B�������Ƀh�X�g�G�t�X�L�[�ɂ͂����������`�ʂ͋H�ɂ����Ȃ��B ���Ƃ��A�i�{�R�t�̏����̍�i�w���b�x�̎��̏��q�́A�s�A�j�b�V���̉��y�Ɏ������܂��悤�ɂ��ēǂނ��Ƃ𑣂��B �d�Ԃ���܂邽�тɁA��̂ق��ŕ��ɂ����ꂽ�}���j�G�̎��������ɂ������ĉ��𗧂Ă�̂����������B�R�g���|�|�����Ă�����A�e�ނ悤�ɁA�₳�����A�R�g���c�c�R�g���c�c�B�H�ʓd�Ԃ͏���炵�ē����o���A�G�ꂽ���K���X�̏�ŊX���̌����ӂ��U��A�ڂ��͋����h���т��K�����ƂƂ��ɁA���̉��₩�ȍ��������J��Ԃ����̂�҂����B�u���[�L�̋����A�◯���|�|�����Ă܂���A�ۂ��}���j�G�̎����������|�|�Â��ē�߂������A�����ɂԂ���]�����Ă������B�R�g���c�c�R�g���c�c�B�i�i�{�R�t�w���b�x�j �����̓h�X�g�G�t�X�L�[�̍�Ƃ̎����Ƃ͈قȂ�A�[�[���ׂĂ̍�i��O����ɓǂ킯�ł͂Ȃ��킽�����ɂƂ��āA�Ƃ����ۗ��͂����[�[�A�܂������߂��荇�������Ƃ̂Ȃ����I�`�ʂ̂悤�Ɋ�������B���������i�{�R�t�̓h�X�g�G�t�X�L�[�ɂ́u�`�ʁv�������Ȃ��Ƃ����咣�������Ă���B
�����ł́u�`�ʁv�Ƃ�����̈����ɂ͒��ӂ�v���邪�i���Ƃ��h�X�g�G�t�X�L�[�ɂ͐S���`�ʂ͂ӂ�ɂ���ł͂Ȃ����Ƃ����₢�͂������ܐ����邾�낤�j�A�i�{�R�t�����ł鑽���̕`�ʂ́A�\����]�C�̊��o�ł���悤�Ɏv���B�����Ƃ����Ƃ��J�t�J�́w�ϐg�x�̍����w�I���q�ɕΎ�����i�{�R�t�͒��o�����ł�̂Ƃ͂܂������ʂ́u�`�ʁv�������鑤�ʂ������Ă���i�Q�ƁF�i�{�R�t�ɂ��J�t�J�w�ϐg�x�̍����w�I���̈́����u����̓S�L�u���ł͂��肦�Ȃ��I�v�j�B ���������킽�����̓v���[�X�g�̂����悤�ȃh�X�g�G�t�X�L�[�̏Z�܂��̑n���́u�`�ʁv�����܂��\���ɓǂ݂Ƃ��Ă��鎩�M�͂Ȃ��B
�h�X�g�G�t�X�L�[�����̐��E�ɂ����炵���V�������ɗ������ǂ��Ă����A�t�F�����[���̊G�ŁA�z�n�̔z���╨�̏��݂���ꏊ�ɂ��āA����Ɠ��̍��̑n���A����Ɠ��̐F�ʂ̑n��������悤�ɁA�h�X�g�G�t�X�L�[�ł́A�l���̑n�����������ł͂Ȃ��A�܂��Z�܂��̑n��������Ƃ������Ƃł��B���Ƃ��w�J���}�[�]�t�̌Z��x�ɏo�Ă���E�l�̉ƁA�܂��Ԃ̂��邻�̉Ƃ́A���S�[�W�����i�X�^�[�V���E�t�B���b�|���i���E���A���̈Â��āA�����āA�V�䂪�����āA�Ƃ炦�ǂ��낪�Ȃ��ƁA�h�X�g�G�t�X�L�[�ɏo�Ă���E�l�̉Ƃ̌���Ƃ������ׂ����̉ƂƂ��Ȃ��悤�ɂ��炵���͂Ȃ��ł����H�@����Ƃ����A���̂����Ƃ���悤�ȐV�������A���̂���炪���A���̍������ꂽ�V�������A���ꂱ���h�X�g�G�t�X�L�[�����̐��E�ɂ����炵�����j�[�N�Ȃ��̂Ȃ̂ł����āc�c�i�v���[�X�g�w�����̏��x�j
�i�{�R�t�͂����ꂽ�v���[�X�g�ǂ݂����A���̎w�E���ǂ��~�߂Ă���̂��낤�B�\����]�C�̒��o���肪�A�����̑�햡�ł͂Ȃ��͂����B
�\���Ƃ������̂́A�c�c�܂��ɉ����͂킩��Ȃ����������m���ɑ��݂��悤�Ƃ��đ����Ђ��߂Ă���Ƃ������o�ł���B�ނ��������Ƃł͂Ȃ��B�Ă̂͂�����酉J�̗\���̂������߂�ЂƂƂ���z�����Ă������������B�i�c�c�j
�]�C�Ƃ͂������ɑ��݂��Ă��̂��邢�͏�Ԃ̎c���A�c�荁�ɂ��Ƃ����邪�A���݂������̂����������ł͂Ȃ��B酉J���߂�����������̑u�₩���ƈ��g�Ƌ���������ɂ��ނ��������̎v���Ƃł���B�i����v�v�u���E�ɂ���������ƒ���v�j
�܂��i�{�R�t�̓t���C�g�����Ƃ��Ă��m���Ă���B�h�X�g�G�t�X�L�[�ɐ��_���͓I�^�����������ꂽ�Ƃ��āA���ꂪ�����ƂȂ�̊W�����邾�낤�A�ƃi�{�R�t�Ȃ猾�����낤�B
�ӂ����уv���[�X�g�����p����A�h�X�g�G�t�X�L�[�ɂ̓v���~�e�B���h�̂����������̔�������Ƃ��Ă���B �ڂ��̓h�X�g�G�t�X�L�[�̂Ȃ��ɁA�l�Ԃ̍��́A�x�͂���ɐ[���A�������������̒n�_�ɌǗ����Ă���A�������̈�˂����o���܂��c�c���̓������҂������A�w��x�x�̐l�ԂƂ��Ȃ��悤�ɁA�Ɩ��ƕ����̌��ʂł������z�I�ł͂Ȃ��A�ق�Ƃ��͂ǂ��ɂł����镁�ʂ̐l�ԂȂ̂�������܂���B�c�c�����ڂ������肳����̂͂ˁA�l���h�X�g�G�t�X�L�[�ɂ��Č�����菑�����肵�Ă��邠�̌��I�������点�������߂����ł���B���Ȃ��͔ނ̏��l���̓��ʂʼn����Ă��鎩���S�ƌւ̖����ɒ��ӂ������Ƃ�����H�@�ނɂƂ��ẮA���Ɖߓx�̂ɂ����݂��A�P�ӂƂ��炬����A���C�Ƙ��ݕs�����A����Ύ����S�������Čւ������Ƃ�����̐���������킷��̏�Ԃɂ����Ȃ��̂ł��B����Ȏ����S�ƌւ��A�A�O���[����A�i�X�^�[�V����A�~�[�`�����{�Ђ����Ђ��ς��т�A�A�����[�V���̓G�������̃N���\�[�g�L���ɁA�����̂܂܂̎����́s���́t��l�Ɍ����邱�Ƃ��ւ��Ă���Ƃ����킯�Ȃ̂ł��c�c�h�X�g�G�t�X�L�[�Ƃ����ˁA�������͂ڂ��͂��Ȃ����v���قǔނ����]���ăg���X�g�C�̂��Ƃ�b���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�g���X�g�C�͂��͑傢�Ƀh�X�g�G�t�X�L�[���܂˂Ă���̂ł���B�h�X�g�G�t�X�L�[�̂Ȃ��ɂ́A�₪�ăg���X�g�C�̂Ȃ��Ŗ��ʂ̂ق���т���������̂��A�܂������߂��ʂ������A�s�������Ȋ�ŁA��������l�܂��Ă���̂ł��B�h�X�g�G�t�X�L�[�̂Ȃ��ɂ́A�₪�Ē�q�����ɂ���Đ���₩�ɂ����A�v���~�e�B���h�̂����������̕s�@����������̂ł��傤�ˁB�v�i�v���[�X�g�w�����̏��x��㋆��Y��j
�����A�s.�����ڂ������肳����̂͂ˁA�l���h�X�g�G�t�X�L�[�ɂ��Č�����菑�����肵�Ă��邠�̌��I�������点�������߂����ł���B�t�[�[���̔�]�́A�킽�����̌h�������Ƃł͂���Ȃ���A�X�L���̕�����w���O�ɏ㈲���ꂽ�Ꮡ���w�h�X�g�G�t�X�L�[�o���x�i1950)�ɂ����ěƂ܂�A�|�|�ƌ�������ɂ͂��̏����茳�ɂȂ��̂ł���A���Ƃ�掂��Ƃ�ʂ��낤�B
�{���́A�����ǂ���A�h�X�g�G�[�t�X�L�[�̍�i�ɂ��Ă̕n�����w�o���x�ł���B�����قȂ�A�܂��������������Ȃ������A���̂悤�ȁw�o���x�������ɂ��邱�Ƃ́A�͂Ȃ͂������؉z�ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ�������Ă���B�������A�̌n�I�ȃh�X�g�G�[�t�X�L�[�����ł͂Ȃ��B�����ɂ͑����̌�T��v���Ⴂ������ł��낤�B�������A���̐S�͂܂���������ɔc����ꂽ�B�_�ɂ��āA�l�Ԃɂ��āA�Љ�ɂ��āA����Ɏ��R�ɂ��Ă������A�h�X�g�G�[�t�X�L�[�́A���ɁA�܂������V�������_�I�������J���Ă��ꂽ�B����͋��Q���ׂ����߂ł����B���ɂƂ��āA�����ᔻ���邱�ƂȂ��A�܂������v�����y�Ȃ��B�����A����́A�����ׂ�����Ȃ�A�܂�����Ȃ��@�ׂȂ�A���̐[���A�Ɉ�����āA�������n�������݂�H��݂̂ł���B�i�X�L���w�h�X�g�G�t�X�L�[�o���x�u���Ƃ����v�j
���̃����N��ɂ́A�X�L���̓lj��Ɣ䂵�����Ƃł���T�R��v���̓lj�ᔻ������B��҂̓ǂ݂��ǂ����f����̂��́q���Ȃ������r�ɂ܂�����B
�y�S���w�I�ǂ݂̕����H�z
�Ƃ���ŁA�h�X�g�G�t�X�L�[�M���҂͋�����ɂ͂�������c���Ă���A�ŋ߂ł́A�h�X�g�G�t�X�L�[�̒���ȁw����_�x�i�j�R���C�E�X�^�����[�M���̋A���[�[�������́u����_�v�O����j�ȂǂƂ������̂�������Ă���炵���A�����ł̓X�^�����[�M���̌������u��e����̎����v�ȂǂƂ���u�S���w�I�ȁv�w�E������炵���i����������1949�N���܂�ł���A�킽�����̏\�N�قǏ�̐���̕��|�]�_�Ɓj�B
���Ƃ��A�������́A�u�j�R���C�E�X�^�u���[�M���v�̐��X�̗��\�T�S�A�܂� �u���v�ɂ��āA�u����`�b�N�v�u�傰���ȁv�Ə����Ă���B�u�j�R���C��_�b������悤�Ȍ�����������҂̈Ӑ} ���f����v�u�킴�Ƃ炵���v�ƌ����B�i�c�c�j
�@�����ŁA�������́A�j�R���C�E�X�^�u���[�M���́u���v�́A��e�ւ̔ƍs=���R�Ɠǂ݉����Ă���B�܂� �A�j�R���C�E�X�^�u���[�M���͕�e�̓M���̌��ň炿�A�܂����̕�e�̎��� ��E�������Ă��炸�A����̂ɕ�e�̊肢������āA�̋��X�N���@���[�j�V�L�ւƋA������킯�ł���A����Ɠ����Ɂu��e����̎����v�̎��݂Ƃ��Ă̐��X�̗��\�T�S�A���R(��)���J��Ԃ��Ƃ����킯���B
�ŋ߂̃h�X�g�G�t�X�L�[�_�ɂ��Ă͖��m�Ȃ̂ŁA�͂āA���Ƃ��ΎR��ނݎ��̕]���̍����_�͂Ȃɂ�����Ă���̂��i����ɂ��Ă̓C���^�[�l�b�g��ł͂����������̂͌�����Ȃ������j�A���邢�͚ʗ_�J�Ȃ̂���T�R��v���́w����x���߂͂ǂ�Ȃ������Ȃ̂��A�ȂǂƂ��������ׂĂ��邤���ɍs�����������_�]�Ȃ̂����A�u��e����̎����v�̎��݂Ƃ����͕̂ʂɃX�^�����[�M���łȂ��Ă��قƂ�ǒN�ɂł�����̂ł����āA�킽�����ɂ͎��Y�ɗނ���w�E�Ƃ��Ă����~�߂��Ȃ��A�|�|�Ƃ���̂͂��ẴX�m�b�u�̖��c�Ȏc�ƂƂ��Ă̒Z���I�ȋC���ł���ɂ͑���Ȃ��B�����������������̏���ǂ킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���R�ق��̏d�v�Ȏ����Ɨ���ł̌����ł���͂��ł���A�����ł́u��e����̎����v�ɂ��Ă����̈�ۂł���B
�������u��e����̎����v�́A���Ƃ��Ύ��̂悤�ȁw����x�̖`���߂��ɂ��鏖�q����A�N�ł����̋C�z�͓ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł���B
���N�́A��e��������M�����Ă��邱�Ƃ�m���Ă������A�ގ��g�͂���قǕ�e���D���Ă͂��Ȃ������B�v�l�͂��܂葧�q�Ƃ͌��������Ȃ��������A�߂����Ɏ��R�����邱�Ƃ��Ȃ��������A����ł����N�́A�����������������ƌ�����Ă����e�̎������A�a�I�Ȃ��炢�A�������Ɋ����Ă����B�i�w����x�]����@�V�����Ɂ@��@P59�j
���̖`���߂��̏��q�ȊO�ɂ��A�X�^�����[�M���̕�ւ̃A���r�o�����g�Ȋ���̗h��͂�����ł��w�E�ł��邾�낤�B�������ꂾ���ŃX�^�����[�M���Ƃ����l���̊������������ꂽ�犬��Ȃ��i�d�˂ď������A���������̘_�ւ̒Z�����]��ǂ����̈�a�ł���j�B
�y���w�Ƃ͖����̎����z
�����͏��Y���P�̎��̂悤�ȕ��͂�}�����āA�X�^�����[�M���̈�т������i���w����x�̃e�L�X�g����ǂ݂Ƃ�d���́A�u���w�Ƃ͖����̎����v�ł���Ƃ��Ă������B
���Ƃ��Ο��̏������߂����ď����ꂽ�����̖}�f�Ș_���Ȃǂɂ́A����o��l�������̉ӏ��ł͂���Ȃӂ��ɕ`�ʂ���A���̉ӏ��ł͂���Ȃӂ��ɕ`�ʂ���Ă��邪���̊Ԃ̐H���Ⴂ���ǂ��l������悢�̂��ȂǂƁA���ꂱ��^���Ɏv���Y��ł�����̂�����A�u���w�����v�̊w�k�Ƃ͉��Ɣn���n�������܂łɗ��V�Ȑl�X���Ƃ�������ꂳ�����ɂ����Ȃ��B���Ƃ�苕�\�̃C���[�W�ł����Ȃ�����̓o��l���ɂ��āA����͖{���͂��������ǂ������l�Ȃ낤�ƍl���l�߂悤�Ƃ��銯���I�Ȑ��^�ʖڂ��ȂǁA����w�Ƃ͂܂����������̎����ł���B�i�c�c�j
�w������x���w���Áx���v����ɂ����̊G�ł���A���̓���ĂƂ��ē������ꂽ�u�搶�v���́u�j�v���́u�Óc�v���́u���сv���̂́A����L���̑g�����ɂ���ĕ\�ۂ����z���I�Ȑl���C���[�W�̋Y��̐ϕ��I�ȑ��̂ɗ^����ꂽ�A���̖��O�ɂ����Ȃ��B�Ȃ�قǁA��l��l�̓o��l���Ɉ�т������ȓ��ꐫ�ƃ��A���ȑ��݊��^���悤�Ƃ����Ӑ}����Ƃ������Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��낤���A���������Ƃ������ł����Ă��A�n���́u���v�ɂ����ğ��́A���̂NJm���_�I�ȗh�炬�̒��ŁA�ނ���g�K���Ɂh�����Ă����͂��ł���B���̕M���^��������A���́u���v�̌���ɂ́A�ߌ���v���Ⴂ���������ӎ�������֒������Ɠ�����������A���������������ǂ��ɌĂт��܂ꂦ���̂ł���A�܂����������l�ԓI�g�����������h�ɑ�_�ɐg���ς˂邱�ƂŁA�ނ́u��i�v�ɂ�����^���͂��悢��L���ȁA�܂����C�ɖ��������̂ɂȂ��Ă������͂��Ȃ̂��B���̕��̂ɂ�����u���Ď��v�̖��Ȃǂ��A�ނ���u��i�v������_�I�Ìł���������������Ƃ����ނ̍�����݂̗~���̕\���Ƃ��ēǂ݉������ׂ��ł͂Ȃ��̂��B(���Y���P�u�\�ۂƊm���v�w���\�̓N�w�x�����@����P190)
���������w����x�́A�������肵���\�z�̌o�����Ƃɏ����ꂽ��i�ł͂Ȃ��i�����炭�h�X�g�G�t�X�L�[�̑����̍�i�Ɠ��l�Ɂj�B���M�����A���Ɂu���_�_�v�A���Ȃ킿�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̍\�z�������痣��Ȃ������悤���B
�ގ��g�u���ˁv�ɂ͑債���]�݂��|���Ă�Ȃ����B�����J�g�R�t�ւ̎؍����x�c��ਂ��P�V�Ȃ��d���ƍl���Ă�B�c���̔ނ̖�S�͂��̍�ɂ�萌W�̂Ȃ��召���ɂ����B�i���яG�Y�w�h�X�g�G�t�X�L�[�̐����x�u�W�@�l�`���G�t�����v�j
���Ȃ킿�A�����炭���̍�i�ɂ��܂��Ă��������̂��Ƒn���́u���v�ɂ����Ăނ���g�K���Ɂh�����ꂽ�����Ȃ̂ł���A�s���́u���v�̌���ɂ́A�ߌ���v���Ⴂ���������ӎ�������֒������Ɠ�����������A���������������ǂ��ɌĂт��܂ꂦ���t�̂��낤�B
�������h�X�g�G�t�X�L�[�̃e�N�X�g�̒f�Ђ���A���_���͗��_�I�Ȓf�Ђ��E�����Ƃ͂ł���̂�ے肷��킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ��t���C�g�̔j��~����狝�y�Ǝ����悤�ȏ��q������ȁA�Ƃ́u�����v���y���ނ��Ƃ͂ł���B��������͂Ȃɂ��h�X�g�G�t�X�L�[�Ɍ������b�ł͂Ȃ��B����̓t���C�g�̘_���̃V�F�C�N�X�s�A����̈��p�̖L�x����z���N���������ł悢�B
��̑�͐l�����炾�����Ɠ����ɁA�S����������悤�Ȍ��ʂ���ɐ��ނ��̂ł���B�ԉ͂��̌��ʂ����p�������̂��B�������ԉ̏ꍇ�́A���D���ȁA�K���������`�ɂЂ낪��A�����������̐g�͂܂��������S�Ȃ̂ŁA���傤�ǃV�����p���E�O���X���X�������Ƃ̂悤�ɁA�V�є����̌y�₩�Ȉ�ۂ����c���Ȃ��B�ق���̂̉Ύ��ƂȂ�ƁA�b�͕ʂł���B���̏ꍇ�́A��̉̐S��������������ʂ����邱�ƂȂ���A���|�S�ƁA��͂�킪�g�ɔ���Ȃɂ������̊�@���Ƃ��A�����l�Ƃ̊ԂɁi�������A�Ƃ��Ă���Ă��铖�l�����̊Ԃɂł͂Ȃ��j�����̔]�kṂ߂�����p���䂫�N�����A�ނ�̓��Ȃ�j��{�\���h������悤�Ȍ��ʂɂȂ�B�������A���̔j��{�\�́A�߂������ȁI�@�ǂ�Ȑl�Ԃ̐S�̒�ɂ��A�ތ��������̂��̂̂悤�ȉƑ������̋㓙���̐S�̒�ɂ����Ђ���ł�����̂Ȃ̂��c�c���̉B���Ȋ��o�́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�l��������X��������B�u�Ύ��Ƃ������̂𑽏��̖������Ȃ��ɒ��߂�����̂��ǂ����A�ڂ��͂��₵���Ǝv���ˁv�Ƃ́A���ăX�e�p�������A���܂��o���킵����̉Ђ���̋A�蓹�A�܂����̈��p���Ȃ܂Ȃ܂�����������ɁA���Ɍ�������t���̂܂܂̈��p�ł���B�i�h�X�g�G�t�X�L�[�w����x�@�]����@�V�����Ɂ@���@P272�j
�y���疳�p�ɋ����萸�_���͓I�ɓǂނ��Ɓz ���Ă����ł́u���w�Ƃ͖����̎����v�̂��̂̈�l�Ɗ����ċ������āA�t���C�g�̃h�X�g�G�t�X�L�[�_�����p���Ă݂悤�B
���e�L���Ȑl�i���������h�X�g�G�t�X�L�[��O�ɂ��āA�����͎l�̂��̂���ʂ��čl�������Ǝv���B���Ȃ킿���l�Ƃ��Ă̔ށA�_�o�ǎ҂Ƃ��Ă̔ށA�����ƂƂ��Ă̔ށA����эߐl�Ƃ��Ă̔ނł���B�����̓������������邩�������G�Ȑl�i��I�ɔc������ɂ́A���������ǂ������炢���̂ł��낤���B�i�t���C�g�w�h�X�g�G�X�t�L�[�ƕ��e�E���x�j
���̏��_��1928�N�ɏ�����Ă���A����t���C�g�ƌĂ�鎞��A���Ȃ킿�w�������̔ފ݁x1920�ȍ~�ɏ�����Ă���B
�u�l�̂��̂���ʁv���Ă���t���C�g�́A���̍ŏ��́u���l�Ƃ��Ắv�������߂����āA�t���C�g�́w�J���}�[�]�t�̌Z��x�́A�V�F�C�N�X�s�A�ɔ�r���Ă������ė���Ă��Ȃ��Ƃ��āA�Ƃ��Ɂu��R�⊯�v�̌��͐��E���w�ɂ�����ō�����̂ЂƂƂ��Ă���B�s�����c�O�Ȃ��ƂɁA���l�Ƃ�������O�ɂ��ẮA���_���͂͝i��T�ς�����ق��͂Ȃ��t�ƁB
���ꂪ���l�A�|�p�ƂƂ��Ă̍�Ƃ�O�ɂ����Ƃ��́A�����}�l�̑f���ȑԓx�ł��낤�B
�ЂƂ͂���ł��Ȃɂ������������Ȃ�̂������̏�ł���̂�����A�_�o�ǎҁA�����ƁA�ߐl�Ƃ��Ẵh�X�g�G�t�X�L�[���߂����ď����Ԃ炴��Ȃ���]�̌��t��S�ے肷��킯�ł͂Ȃ��B���̋@��ɏ��яG�Y�́w�h�X�g�G�t�X�L�[�̐����x��ǂݕԂ��Ă݂����A���яG�Y�̂��̟Ӑg�̔�]���ł������̗ނ́u��]�v�ł���Ƃ�����̂�������Ȃ��i�����Ȃ��Ƃ��i�{�R�t�I�ϓ_����́j�B
���ăt���C�g�ɖ߂��āA��Ԗڂ̋敪���A�u�����Ɓv�Ƃ��Ẵh�X�g�G�t�X�L�[�ɂ��ĂȂ�Ə����Ă��邩�B
�����Ƃ��[���߂̗̈��ʂ������Ƃ̂���҂݂̂��A�����Ƃ������ϗ��̒i�K�ɓ��B����Ƃ������Ƃ�_���Ƃ��āA�ނ�ϗ��I�ɍ����]�����悤�Ƃ���ԓx�́A�d��ȋ^�_���ʼn߂��Ă���Ƃ��킴������Ȃ��B���Ȃ킿�A�ϗ��I�Ȑl�ԂƂ́A�U�f�Ƃ������̂ɁA���ꂪ�S�̒��Ŋ�����ꂽ�Ƃ���ɒ����ɔ������A����������ɋ������邱�Ƃ̂Ȃ��l�Ԃ��w���Ă����̂ł���B���܂��܂ȍ߂�Ƃ��A������̂�������āA�����ϗ��I�v�����f����ɂ������Ƃ����悤�Ȑl�Ԃ́A�C�[�W�[�ȓ�����Ƃ�������Ƃ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������l�Ԃ́A�ϗ����̖{���I�����A���Ȃ킿�f�O�Ƃ������̂𐋍s���邱�Ƃ��ł��Ȃ������킯�ł���B�i�w�h�X�g�G�t�X�L�[�ƕ��e�E���x�j
�u�ߐl�Ƃ��āv�̃h�X�g�G�t�X�L�[�ɂ��ẮA���̂悤�ɏ������[�[�A�s�ނ́A����قǂ܂łɋ����l�X�̈������߂��ł͂Ȃ����B�܂��A���Ƃ��ŏ��̍Ȃ���т��̏�l�ɂ�������W�ɂ����Ă̂悤�ɁA���݂����Q���錠���������ɂ������ꍇ�ł���A�ނ͈������艇���̎�������L�ׂ���A���l�D��������ԓx�����鎦���āA�l��������\�͂̑傫�����ؖ����Ă���t�̂ɁA�ǂ����ās�ƍߎ҂̖{���I���F���Ȃ��A�������Ƃ�m��ʉ�~��A����Ȕj��I�X���A�\�\�⍓���A�܂�Ώہi���Ƃɑ��肪�l�Ԃł���ꍇ�j��]������ɂ������Ċ���̗v�f��������\�͂̌��R�t���h�X�g�G�t�X�L�[�Ɏw�E���邱�Ƃ��ł���̂��A�Ƃ܂��͗\������锽�_���������B�������̉ˋ�̔��_�ւ̉��������������B
���̋^��ɂ������铚�́A���̎��l�̑f�ޑI���̎d���ł���B���Ȃ킿�h�X�g�G�t�X�L�[�͂��̍�i�̑f�ނƂ��āA���\�ҁA�E�l�ƁA�䗘�䗘�S�҂Ȃǂ��A�Ƃ��ɍD��Ŏ��グ�Ă���A���ꂪ�A���l�ȌX�����ގ��g�̓����ɂ�����ł������Ƃ��@�m������̂ł���B���ꂩ��܂��A�ނ̐��U���̎�̎����A���Ƃ��Δނ̓q���Ȃ��������邵�A���邢�͂܂��A�����N�̏��������������Ƃ������̎����i���̎����ɂ��Ă͔ގ��g�̍���������j���A�����炭���̋^��ɂ������铚�ƂȂ�ł��낤�B���̖����́A�ގ��g�����₷���ƍߎ҂ɂ����˂Ȃ���������߂ċ����j��~�����A�h�X�g�G�t�X�L�[�̌����̐����ɂ����ẮA��Ƃ��Ĕގ��g�̐l�i�ɂ������āi���Ȃ킿�O�Ɍ������邩���ɓ��ɂ������āj�������A���̌��ʃ}�]�q�Y������э߂̈ӎ��ƂȂ��Ĕ����������Ƃ�������̂��Ɖ�������B������ɂ���A�ނ̐��i�̒��ɂ́A�T�f�B�X�g�I�ȗv�f�������ɂ����āA����͔ނ������Ă���l�X�ɂ������Ă����������Z�C�A�Ӓn���A�s���e�ȂǂɌ���Ă���A���邢�͂܂��A��ƂƂ��Ă̔ނ��ǎ҂���舵�����̂����ɂ�����Ă���B���������Ĕނ́A�����Ȏ����ɂ����Ă͊O�ɂ�������T�f�B�X�g�ł��������A�傫�Ȏ����ɂ����ẮA���ɂ�������T�f�B�X�g�A���Ȃ킿�}�]�q�X�g�ł���A�����Ƃ����l�D���ȁA�����Ƃ����ߐS�ɕx�l�Ԃ������̂ł���B�i���t���C�g�j
���̃t���C�g�̏��q�́A�s�����Ƃ����l�D���ȁA�����Ƃ����ߐS�ɕx�l�ԁt�Ƃ������ȊO�́A�w����x�̎�l���X�^�����[�M���̐��i�⌾�����قƂ�ǜf�i��������̂ł���A�X�^�����[�M���̌������u��e����̎����v�Ƃ��ēǂ݂Ƃ�͎̂��Y�ɗނ���Ƃ����̂́A���Y���P�́u���w�����ҁv�ւ̚}�ΈȊO�ɂ������������Ƃ��܈ӂ���B�t���C�g�͂��łɂ���ȏ�̂��Ƃ������Ă���B
���ăh�X�g�G�t�X�L�[�̑�l�Ԗڂ̋敪�A�u�_�o�ǓI�v�Ȗʂ́A�����ł͊�������B�ߐl�̌��Łu�}�]�q�X�g�v�Ƃ����ꂪ�o�Ă��Ă���̂�����B
�y�C���g���E�t�F�X�g�D���i�Ղ�̍Œ��j���߂����āz
�u�ᒎ����v�̃h�X�g�G�t�X�L�[�ɂ��Ă͖ؑ��q�ɂ��C���g���E�t�F�X�g�D���̎����̎w�E��z�N���邱�Ƃ��ł���B�ؑ��q�́A�l�Ԃ̐S���I���Ԋ��o���u�Ղ�̑O�i�A���e�E�t�F�X�g�D���j�v�u�Ղ�̌�i�|�X�g�E�t�F�X�g�D���j�v�u�Ղ�̍Œ��i�C���g���E�t�F�X�g�D���j�v�̎O�ɕ��ނ��Ă���B�Ղ�̑O�������a�I���Ԋ��o�A�Ղ�̌オ�N�T�a�I���Ԋ��o�Ƃ������Ƃ��������A�O�҂����m�Ȃ関���ɂ����鎩�Ȃ̉\���̒Nj��A��҂����m�̊��K��o���ւ̕ێ�I�Ȗ��v�Ƃ���A���҂Ƃ����Ԃ̐������i�����A���邢�͉ߋ��j�ɂ������a�����Ƃ���A�C���g���E�t�F�X�g�D���͎��Ԃ̐��������ł̓��퐫�̊����i����퐫�̌����j�Ƃ����B
�����Ă��̎w�E�ɂ����Ċ̗v�Ȃ̂́A�C���g���E�t�F�X�g�D���́A�ᒏǎ҂����ł͂Ȃ��A���N�l�̒N�ɂł��K�����̏u�ԁi��������a�҂�T�a�҂ɂ����Ă��j�Ƃ��āA�s���̜����A���Ƃ̒��ʁA���R�Ƃ̈�̊��A�@����|�p�̐��E�ɂ����钴�z���̑̌��A�ЊQ�◷�ɂ��������I��������̗��E�A��p�I�Ȋ����Ȃǂ̌`�ŏo����������́t�Ƃ���Ă��邱�Ƃ��B ���Ƃ��ΟT�a�e�a�C���Ɛ���������]���O�Y�́u��u���͂����炩���������ԁv�͂��̃C���g���E�t�F�X�g�D���Ǝ����悤�ȍ����������\���ɑ���Ȃ����A�����a�e�a�����Ƒz�肳���j�[�`�F�́u���߁v�����l�B
�܂��ɁA�����킸���Ȃ��ƁB�����������Ȃ��ƁA�����y�₩�Ȃ��ƁA������Ƒ���Ƃ����B��̑��A��̎���A��̂܂����[�[�܂��ɁA�킸���������A�őP�̂������̍K��������̂��B�Â��ɁB
�\�\�킽���ɉ������N�����̂��낤�B�����I�@���Ԃ͔�ы����Ă��܂����̂��낤���B�킽���͗����Ă䂭�̂ł͂Ȃ��낤���B�������̂ł͂Ȃ��낤���A�\�\�������点�I�@�i���Ƃ�����̂Ȃ��ɁB�i�w�c�@���g�D�X�g���x��l���u���߁v��˕x�Y��j �u�Ղ�̌�i�|�X�g�E�t�F�X�g�D���j�v�u�Ղ�̑O�i�A���e�E�t�F�X�g�D���j�v�u�Ղ�̍Œ��i�C���g���E�t�F�X�g�D���j�v�ɂ��āA�����ꂽ�O�[���h�V���[�}����A�v���[�X�g�_�Ȃǂ̒��ҁA�~�V�F���E�V���l�f�[���i�ނ͕����������ł�����A�܂������Ƃł����萸�_���͈�ł�����l���j�̎��̕����o���Ă������B
�c �s�A�m��������Ƃ����Ȃ�A���̂��߂ɂ́A�ʂ̎��ォ�����Ă��āA�˂Ɋ����`�Ō���Ă���悤�ȃA���g�D�[���E�׃l�f�b�e�B���~�P�����W�F���̃s�A�m�����邾�낤�B���邢�͂܂��ߔN�̃��q�e���̂悤�ɂ����̊��҂���������悤�ȃs�A�m������B���ҁA���Ȃ킿�ߍ����q�e�����o�ꂷ��ƁA�ꏏ�ɂ����ɂ�����邠�̖����̃m�X�^���W�[���i�h�A�͂��̂Ƃ��ЂƂ�łɂЂ炫�A�����ɂ���̂��킩��Ȃ�����������������B�j�������Ȃ��猻�`�ʼn��t����O�[���h�̎p�͌���I�Ȍ��������炵�A���C���邢�͓V�g�Ƃ����g���Â��ꂽ���O�ɂ̂ڂ点��B�i�w�O�����E�O�[���h�@�ǓƂ̃A���A�x�@�~�V�F���E�V���l�[�f����t���v��j
�������A�����Ń~�P�����W�F�����T�a�e�a�^�A���q�e���������a�e�a�^�A�O�[���h���ᒐe�a�^�ȂǂƂ�������͖ѓ��Ȃ��B���ꂼ��̉��t�Ƃ́A���ꂼ��̎d���ŃC���g���E�t�F�X�g�D���̐����ɗ����Ԃ̊��o��^���Ă���邾�낤�B��������ɂ��Ă��O�[���h�́u���ݐ��v�̜����̂Ȃ�ƍۗ����Ƃ�B
�����C���g���E�t�F�X�g�D���̋P�������ʂ�����������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�s�j�Ղ͂˂Ɏ��̌����ɂ���Ďx�z����Ă�����B���́A���ꎩ�̂Ƃ��Ă݂�Δ��킵���i�v���a���Ӗ�����̂ł��낤����ǂ��A�ʓI�����Ɏ���������퐫�̈ӎ��ɂƂ��Ă͋��|�̑ΏۈȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ����낤�B�E�l��ƍ߁A�v����푈�͂���Ȃ�ɐl�ނ̏j�ՂȂ̂ł���B�t�i�ؑ��q�@P161�j
���̌����ɂ͂��낢��ȕϑt�����邾�낤�B
�푈�̘_���͒P�������ł���B�l�Ԃ̉��[���������o�ɑi����B�ւ�ł���A���\���ł���A�o��ł���B�푈���N�I�j�ՓI�ȍ��g�ς������炷�B�i����v�v�u�푈�ƕ��a�ɂ��Ă̍l�@�v�w�����݂߂āx�����j
�����̋^��́A���Ƃ��u���̍m��v�A�u���̓��s�v�Ƃ��ăJ�[�j�o���I�ɂ����ꂽ���̂��K���t�@�V�Y���ɓ]������̂͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��B�j�[�`�F��x���O�\���̓t�@�V�X�g�ł͂Ȃ��Ƃ����Ă��͂��܂�Ȃ��B���͂⏃���ȃJ�[�j�o���Ȃǂ��肦�Ȃ��悤�ɁA�����ȁu���̓N�w�v�����肦�Ȃ��B����͂���������j�I�ȕ����ɑ��݂���₢�Ȃ�A�v�������ʔ��]��u������������̂��B�{���́A�u�\�͓I�Ȃ��́v�́s�ߑ�t�ɏo������̂��Ƃ����Ă��悢�B�i���J�s�l�w���j�Ɣ����x�j ���āA�h�X�g�G�t�X�L�[�̂̃C���g���E�t�F�X�g�D�����ɂ��ẮA���̂悤�ȏ��q������B �����̓h�X�g�G�t�X�L�[���瑽���̂��Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��ł���B�ނ̍�i�ɓo�ꂷ�鑽���̐l���́A���C�V���L����L���[���t�̂悤���ᒊ��҂����łȂ��A�S�������́u���݂̗D�ʐ��v�Ƃł������ׂ����������Ȃ��Ă���B�쒆�̐l�������ׂč�Ƃ̕��g�ł����Ă݂�A����͂����Ƃ��s�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B��Ⴞ����������A�w����x�ɓo�ꂷ����e�̗ߏ샊�U���F�[�^�c�c�ޏ��ɂƂ��āA�ߋ��E���݁E�����̈�т�������Ƃ��Ă̈�̐l���ȂǂƂ������̂́u���������Ȃ��v���̂Ȃ̂ł���B�ޏ��̓X�^�����[�M���Ƌ삯�������Ĉ��̏���o�����������A�u�ڂ��͂��܁A���̂��������݂������Ă���v�Ƃ����X�^�����[�M���Ɍ����āA�u�Ȃ�Ċ�Ȉ����������!���̂������̂��傤���̂ƁA�Ȃ�ł���Ȕ�r���K�v�Ȃ́H�v�i���@P281)�Ƃ����B�ޏ��́u�������ق�̈�u�Ԃ��������ł��Ȃ������Ƃ킩���Ă���̂ŁA�v�v�������Č��S���āu�S�l�������̈ꎞ�Ԃ�������k�̏�l�ɓq���Ă��܂����v�i���@P286-287�j�̂ł���B ��ʂɁA�h�X�g�G�t�X�L�[�̕`���l���͂���������l�ɑ��āA�Ƃ��ɂ͎����̐������������悤�Ȋ댯�ȑ���ɑ��Ă���s�v�c�ɖ��x���ŁA�����a�e�a�҂ɂ݂���悤�ȑ��҂̖��m���ɑ��鋰�|���͋H���ł���B�܂��A�������R���[�e�a�҂ɓ����I�ȁA�����̌^�̒��ł̖����I�ΐl�W���A�ނ̍�i�̂ǂ���T���Ă���������Ȃ��B�ނ̕`���ΐl�W�́A���ׂČ��݊�̑O�ɂ���l�Ƃ̌��݂̏u�Ԃɂ����钼�ړI�Ȑ[���A�ъ��ɂ���Ďx�����Ă���B �h�X�g�G�t�X�L�[�̈ӎ��ɂ����錻�݂̂��̖L�����́A�ނ��A�E���̌��ɂ����Ď��̑����琶�߂��Ƃ��̑s��Ȍ��i�ƁA�ǂ����Ő[���Ȃ����Ă���̂ł͂���܂����B���́A���̑����疢�m�̉\���Ƃ��Ē��߂�ꂽ�Ƃ��ɂ́A�g���k�܂鋰�|�̌��ƂȂ邾�낤�B�����������������ݒ��ڂɐ����邱�Ƃ��ł���Ȃ�A����͂��̏�Ȃ��P���������̂ł���ɈႢ�Ȃ��B�i�ؑ��q�w���ԂƎ��ȁxP150�j
����1982�N�ɏ����ꂽ�ؑ��q�̉��߂ɂ͍��ł��Ӗڂ�����Ȃ��̂ł����āA�t���C�g�̃h�X�g�G�t�X�L�[�̃}�]�q�X�g���ɔ�ׂĂ����F�͂܂������Ȃ��B�A�|�|�|�����Ƃ��A������ؑ��q�̘_��ǂݕԂ��Ȃ�������A�t���C�g�̓V�˂́A�h�X�g�G�t�X�L�[�̖��������Ȃ��܂܂ŁA���������h�X�g�G�t�X�L�[��X�^�����[�M���̎������߂����ď����Ă��邩�̂悤���A�Ƃ��Ă��܂��Ƃ��낾�����̂����B
�}�]�q�X�g�͏����ȁA����Ȃ��A�ˑ������A�ЂƂ�ł͐����Ă䂭���Ƃ̂ł��Ȃ��q���A�������Ƃ��ɂ��������Ȏq���Ƃ��Ď�舵���邱�Ƃ�~���Ă���B�t���C�g�́w�}�]�q�Y���̌o�ϓI���x�i�t���C�g����W�U�@P302�j
�}�]�q�X�g�́A�^���Ƃ������e�㗝�҂ɂ�锱�����邽�߂ɁA���v�Ȃ��Ƃ��d�o�����A�������g�̗��v�ɔ����čs�����A�����̐��E�̒��ɂ����Ђ炩��Ă���K���ɂȂ�\�����Ԃ��A���ɂ��Ύ������g�̐��������Ƃ������˂Ȃ��B�i����P308�j
��������Đ��_���͗��_��ʂ��ēǂ�ł��܂��킽�����͕��w�I�Ȏ������牓������Ă���B�����Ƃ����ꂪ�h�X�g�G�t�X�L�[�̂�����Ƃ̐��_�̓������������ł��ǂދ@���ɂȂ�K���ł���B
��i����Ƃ�����ƃ��@�����[�͂��������A���͂�͂��ƂƂ������̂�藣���č�i��_����C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���������̂����u��Ɓv�Ƃ́A��i������o����Ƃł͂Ȃ��A��i������o����ƁA���Ȃ킿��i�������Ƃ����ߒ���ʂ��Ă�����鐸�_�̓����Ƃ����悤�Ȃ��̂ł���B�i���J�s�l�j�|�|�u�s�Ԃɂ͂Ȃɂ�������Ă��܂���v�i�@���d�F�j���
�y�Ō�w�u��҂Ƃ��Ẵ_�[�����z �Ƃ���ŁA�w����x�̌����́A�_�[�����E�p���@�����i�A�[�[���ă������[���v�l�ɘA���ꂽ�K�ꂽ�X�C�X�ł̑؍ݒ��A�X�^�u���[�M���̊Ō�w�ɂȂ�Ɗ�]�����[�[���̔ޏ����X�C�X�̎R���ł̎₵�������ɓ��s�����߂�莆�̎����ꂽ���Ƃ̎�݂莩�E�̏��q�ŏI���Ă���A�s�j�R���C�E�X�^�����[�M�������݂�����v�Ȍ��R�́A���炩�ɂ��炩���ߋᖡ���ėp�ӂ���Ă������̂炵���A��ʂɂׂ��Ƃ�ƐΌ����h���Ă����B���ׂĂ��o��̎��E�ł��邱�ƁA�Ō�̏u�Ԃ܂ňӎ��������ɕۂ���Ă������Ƃ���Ă����B�t �_�[�����́A�j�R���C�E�X�^�����[�M���̕�e�������[���v�l�̗{���q�ł���A�v�l�̎��l���������e�������_�z�Ƃ��Đ��܂ꂽ�̂����A�ޏ��̂��C�ɓ���̖��ł���A�X�^�u���[�M���̃X�C�X�ł̃��U���F�[�^�E�j�R�t�@�G���i�Ƃ̗��������̐܂́u���k���v�Ƃ��Ă̖�����S���Ă���B
�c�c���[�U�������Ȃ����Ƃ�����ł��́B�܂�A�j�R���C����ɂ₫�������Ă����悤�Ƃ��āA�킴�Ƃ��̕��ƂȂ�Ȃꂵ��������ł��B�킽�����A������ǂ�������������͂���܂���̂�B�Ⴂ���ɂ͂��肪���́A�قق��܂����悤�Ȃ��Ƃł����́B�Ƃ��낪�j�R���C����́A�₫�������Ă��ǂ��납�A�������Ă��̐N�Ɛe���ɂȂ��āA�����C�����Ă��Ȃ��悤�ȁA�Ƃ������A����Ȃ��ƂȂǂǂ��ł������悤�ȑԓx���������ɂȂ�����ł���B���[�U�ɂ͂��ꂪ�Ђǂ��������܂����̂ˁB���̕��������ɔ����Ă������Ɓi�c�c�j�A���[�U�͉����Ƃ����j�R���C����ɓ˂��������Ă����悤�ɂȂ�܂����́B����ŁA�j�R���C���Ƃ��ǂ��_�[�V���Ƙb���Ă���������̂ɋC���������̂ł�����A�����A�����ƂȂ��Ă��܂��āA�킽�������A��e�Ƃ��āA����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����́B�i�w����x�@��P98�j
�X�C�X�ł̎���̑��q�ƃ_�[�����Ƃ̐e��������Ԃ̂��낤�������[���v�l�̋^���́u�\�ʓI�ɂ́v�������܉������ꂽ���ɂ݂���B
�����A�v�l�̋��ɁA�_�[�V���ɑ���^�������͐Ռ`���Ȃ��Ȃ��Ă����i�c�c�j�B�Ƃ������A����ȋ^�O�͂��Ƃ��Ƃ������͂����Ȃ������A�_�[�V���ɑ���v�l�̐M���͂���قǂɌ��������̂ł���B����ɁA�킪�j�R���X���A���Ƃ����낤�Ɂc�c�����́s�_�[�V���t����ɔM��������ȂǂƂ́A�v�l�ɂ͍l�����y�Ȃ����Ƃł������B�i�c�c�j
�u�_�[�V���v�ƃ������[���v�l�͂ӂ��ɘb�������������B�u���܂��A�����������ʂɂ킽���ɘb�������Ǝv���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������H�v
�u�������A�Ȃ�ɂ��v�_�[�V���͂�����ƍl��������A���̖��邢�ڂŃ������[���v�l�����グ���B�i�w����x��@P100-101)
�����������[���v�l�́A�Ȃꂪ��\�N���A�u�Ō�w�v�̖������Ă���Ǝ���C���Ă���A�w����x�̂�����l�̎�l���X�e�p���E�g���t�B�[���r�b�`�̍č��̑���Ƃ��ă_�[������Еt���悤�Ƃ���B
�u�킽���́A���l�A�ǂ��ł����܂��܂���A�ǂ����Ă����łɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł�����v�_�[�V���͂����ς�ƌ������B
�u�ǂ����Ă������āH�@���܂��A����͂Ȃ�̓䂾���H�v�������[���v�l�͂��т����ڂł����Ƒ�������߂��B �v�l���_�[�V���ɒp���������悤�Ȑ^��������킯���Ȃ��̂́A�ق�Ƃ��̂��Ƃ������B����ǂ��납�A���܂����v�l�͎��������̖��̉��l�Ȃ̂��ƍl���Ă����B�V���[�����H�D��Ȃ�����A�ޏ��̓��f���ȁA�����Ȋ፷���������ɒ�����Ă���̂��������Ƃ��A�ޏ��̐S�ɔR�����������̂́A����ɂ�����w��������邱�Ƃ��Ȃ������ȕ���̏�ł������B�v�l�͂ق�̎q���̎�������S��_�[�V���������Ă����B�i�c�c�j�ޏ��͂��̐Â��ȁA���ƂȂ������ŁA�h���Â悭�������]���ɂł��邵�A�����ŁA���͂���Č����ŁA�߂����ɂȂ��قǕ��ʂ�����A�����ĉ������A����Y��Ȃ��q���ƌ��߂���ł����B�i�w����x��@P107�j �X�e�p�����͂��̌����̍������߂����āA�X�C�X�ł́u���l�̕s�n���v�ƂԂ₭���ƂɂȂ邪�A�������[���v�l�̐\���o��f���킯�ł͂Ȃ��B�����Ƃ����̌����͕ʂ̗��R�ŕs����ɏI��B
���̌����b�Ƃ͕ʂɁA�����̌����߂��A�X�e�p�����́A�������[���v�l�Ƃ̂������Ɉ�㒅���������ƁA�v�l�̂��Ƃ���u�Əo�v���ĕ��Q���ď��Ղ��A���ꂪ�����ł̎��̊ԍۂɁA�����̃������[���v�l�ɂނ����Ď��̂悤�ɂԂ₭���ƂɂȂ�B
�u�{�N�n�E�A�i�^���E�A�C�V�e�C�}�V�^�A�C�b�V���E�K�C�c�c��\�l���J���I�v
�ޏ��͂�͂�ق��Ă����[�[�A�O���B
�u����A�ǂ����ă_�[�V���ƌ�������C�ɂȂ�����ł��A�����Ȃӂ肩���āc�c�v�ӂ��ɕv�l�͖��C���Ȃ����₫���Ō������B�X�e�p������䩑R�ƂȂ����B
�u�V�����l�N�^�C�܂Œ��߂āc�c�v
�ӂ����ѓ̒��فB
�u���̗t�����o���Ă��܂����H�v
�u�F��v���|�ɂ����Ĕނ͌��������B
�u���̔ӂ́A�t���A���̂��́c�c�����Ƃ��Ă����Ӂc�c�l���ł���������Ɓc�c�X�N���H���[�V�j�L�́c�c�o���Ă���́A�o���Ă���́H�v�ޏ��͂܂��͂������Ȃ𗧂��A�ނ̖��̗��[������ŁA�����Ƃ͂������ނ̓���h�������B�u�o���Ă���́A������ۂȁA���̂Ȃ��A�p���炵�ȁA�ӋC�n�Ȃ�����A�i���ɁA�i���ɂ�����ۂȐl�I�v�v�l�͑吺�ɋ��т����̂�����Ƃ��炦�Ȃ���A�����܂��������₫���Ō������B���ꂩ��A�悤�₭�ނ��͂Ȃ��ƁA����Ŋ���Ĉ֎q�̏�ɓ˂��������B�u��\�N�͉߂��Ă��������̂�B�������߂��Ȃ���B�킽�������Ȃ̂�v�i�w����x���@P499-500�j
�قƂ�Ǔ������q���A���˂��������q�����A���̏����̑O���ɂ�����B�X�e�p�����ɐ��U���z�̔N����^����̂ŁA�\�\�_���ȋ`���Ƃ��ā[�[�A�ʂ̏ꏊ�ŕ�炵�Ăق����ƃ������[���v�l���v��������ł���B
�u�����̊ԁA�܂������������Ȃ��̌�����A��͂蓯���悤�Ɏ��X�Ő��}�Ȓ��q�ŁA�܂������ʂ̗v�����`����ꂽ���̂ł����v�X�e�p�����͂������ƁA�߂����ȁA�������͂����肵�����t�Â����Ō������B�u�ڂ��͂��ƂȂ������������Ƃ���ɂ��āc�c���Ȃ��̂��]�݂ǂ���R�T�b�N�x���x���Ă݂��܂����B�\�E�A�R���i�E�q�J�N�K�E�J�m�E�f�X�l�B�{�N�n�E�W�u���m�E�n�J�m�E�G�f�E���������I�h�����E�I�h���E�ǂ�m���������_�b�^�B�Ƃ��낪���x�́c�c�v
�u���҂��ɂȂ��āA�X�e�p���E�g���t�B�[�����B�b�`�B�Ђǂ��������������Ⴀ��܂��B���Ȃ��͗x���x�����̂���Ȃ��āA�V�����l�N�^�C����߁A�V���̃V���c�Ɏ�܂Ƃ������ł����ŁA�|�}�[�h�����A�������ӂ����A�킽���̂Ƃ���ɂ�������������ł���B�͂�����\���܂����ǁA���Ȃ����g�A�����������Ă����������Ă��炵�����B���Ȃ��Ɋ�ɂ����Ƃ��������Ă���܂������A�f�����܂����ǁA����͂܂��i�̂Ȃ��\��ł�����B�v�i�w����x��P525-526�j
�����Ɂu�`���v�Ƃ������t�A�u�_���ȋ`���v�Ƃ����ꂪ�o�Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��Ă������B�����Ƃ��������[���v�l�̃X�e�p�����ւ̋`���́A�����ꂽ���Ƃ����肢�A���Ȉ���G�S�C�Y�����b�������ɂȂ������̂ł���A����͌����āu�_���ȋ`���v�Ƃ�������̂ł͂Ȃ��B
�����ꂽ���~�]�A����́A������Ώ�objet aimant ������Ƃ��đ�������A�ΏۂƂ��Ă̎������g�̐�ΓI�ʐ��̂����ɒ������Â����A�ꑮ��������~�]�ł��B������邱�Ƃ�M�]����l�́A�����̔��_son bien �̂��߈�����邱�Ƃɂ͂قƂ�ǖ������܂���B����͂悭�m���Ă��܂��B�ނ̊́A��̂��ʐ��ւ̊��S��subversion �ɍs���قLj�����邱�ƁA���̌ʐ�����������ł��s�����ōł�impensable �Ȃ��̂�subversion ����邱�Ƃł��B�l�͂��ׂĂ������ꂽ���̂ł��BOn veut être aimé pour tout.�ނ̎���̂��߂����ł͂���܂���B�f�J���m�͂��������܂��B�ނ̔��̐F�A��ȁA�コ�A���ׂĂ̂��߂Ɉ����ꂽ���̂ł��B �������t�ɁA���Ƃ��Ă͑��֓I�ɂƌ����܂����A�܂��������̂��߂ɁA�����邱�Ƃ͂�����������̂̔ފ݂ő��݂������邱�Ƃł��B���̔\���I���^�͑��҂��A���̓��ꐫ�ł͂Ȃ��A���̑��݂ɂ����đ��҂�_���܂��B�i���J���w�t���C�g�̋Z�@�_�x�j �������Ղɂ͌����܂��B�����Ń��J������鈤�̔\���I���^�̑��ʂ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̔��b�̓Z�~�l�[���ꊪ���炾���A����ɂ͍ŔӔN�̃��J���̓����P�́w�h�D�C�m�̔߉́x�I����������Ă���̂�����B�s���̉����k���炦�l�����߂Ă̋��т����ł͂Ȃ��A���͂₻�̂悤�ȌĂт����ł͂Ȃ��^�������Ă�����������ʐ��̂قƂ���A���ꂪ���܂��̋��т̖{���ł���B���܂��͒��̂悤�ɖ��C�ɂ����т����悤�A�^�c�c�t�i�����P�w�h�D�C�m�̔߉́x�j
�y��Ǒ��u�Ƃ��Ă̏����z
���J���̂��ꂼ��̎����ɂ����鈤���߂��锭�b�͋����قǗh�ꓮ���B�����̓��J���Ȃǂ́u���_���͗��_�v�ɂ���ď�������ǂ���K�v�Ȃǖѓ��Ȃ��B�ނ��냉�J���̌��t����������ǂނ悤�ɓǂނׂ����A���J�����t���C�g�̃e�L�X�g�����̂悤�ɓǂ悤�ɁA���Ȃ킿���������₢���߂��ė���Ƃ���A���˂̒��فA�S�O���Ȃǂ�₢�������Ƃɂ���āA�t���C�g�̊T�O�ɐV���Ȍ����Ǝ˂����悤�ɁB
�c�c���_�Ȉ�́A��O�ł�������������e�N�X�g�̂悤�Ȃ��̂̒��ɐg�������Ă���Ƃ����Ă��悢�ł��낤�B
���̃e�N�X�g�͕K���������t�ł͂Ȃ��A���t�ł����Ă����e�ȏ�ɉ����ł���B����̓t���b�g�ł��邩�A�}�g�ɕx��ł��邩�H�@�͂��݂����邩�H�@�J��Ԃ��́H�@�����߂��Ă���Ƃ���́H�@�����Č�����ǂ݂�A�ɂ킩�ɗY�قɂȂ�Ƃ���́H�@�i�c�c�j ���ׂȌ`�e���̕ύX�A���̂̑I���A�������̂Ă�ꂽ���e�A�u��������ꂽ�\���A�v�������폜�\�\�����ɂ���ăe�N�X�g����ς���B���̑O�̍��Ղ�����Ƃ킩��ʂقǂɂ݂��Ȃ���[�[�B����͂قƂ�ǎ������̐��_���̂��̂��B�i�c�c�j ���_�Ȉ�͐��lj�Liseur�ł͂Ȃ����A���߂炢�A�I�сA�̂āA�ނ��A�V���ȋǖʂ����A�ᖡ���āA�����Ď��Ɋ��p���A���Ɋ����D�ق��鐸�_�̉c�݁A���������e�N�X�g���������̉ߒ���g�߂Ȃ��̂Ɋ�����B�i����v�v�u�g�c��搶�́w�u����ꂽ�������߂āv���e�����x���߂����āv�j �����ŁA�s��]�͏����̉�Ǒ��u�ł͂Ȃ��A�������������u�ł���t�ƌJ��Ԃ��Ă������B�����Ƃ�����ȏ����ɂ͋H�ɂ�����荇���Ȃ��B
�`���I�ȏ������O�q�I�ȏ����ɂ���ׂĂ��̂킩��̂悳�����ȕ\����ׂĂ���Ƃ����̂ł͂���܂���B����N�������āA�������[�����āA���C���̈����قǂ��̂킩�肪�悭�A���̓_�ł͑���t���ƕς��܂���B����������A�̓��������́A�������݂����瑕�u�ł��邱�Ƃ��~�߁A�ǂ܂��ׂ����t�Ƃ��Ă��������Ǒ��u�ɐg���䂾�˂Ă��܂����Ƃ��炭����̂ł��B��]�Ƃ̎�ɂ��Ă�����̂���Ǒ��u�ł����āA���������̑��u�ɂ���ĉ�ǂ����Ώۂł����Ȃ��悤�ɂ��ׂĂ��i�s���Ă��܂��A���̂��ƂɁA�����Ƃ��A��]�Ƃ��^���̖ڂ������悤�Ƃ��炵�Ă��Ȃ��Ƃ������[�������������̂Ɏv��ꂽ�̂ł��B
�������A���̊W�͕s���N�ɓ]�|���Ă���B���u�ł���̂́A�ނ��돬���̕��Ȃ̂ł��B���u�ł���Ȃ���A���̑��u�����g�p�@���킩��Ȃ����̂Ƃ��ď��������݂��Ă���̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�����Ĕ�]�Ƃ́A���̖ړI��g�p�@��S�����l�Ԃł͂Ȃ��͂��ł��B�܂��Ă�A���u����ǂ��鑕�u����]�Ȃ̂ł��Ȃ��ł��傤�B�����Ƃ������u�́A�����炭�����ƂɂƂ��Ă����A���ꂪ���ɖ𗧂����������Ȃ��e�\�ȑ��u�ł���A�ł��邪�̂ɁA�����͎��R�Ȃ̂ł��B��]�Ƃ́A�g�p�@���킩��ʂ܂܂ɂ��̏������쓮������B���ꂪ�A������i�삷��Ƃ������Ƃ̈Ӗ��Ȃ̂ł��B�i�@���d�F�w�����̃G�`�J�x�u���Ƃ����v�j
�t���C�g��J���̗��_�̂����ꂽ��Ǒ��u�Ƃ��ăh�X�g�G�t�X�L�[����P������B�Ƃ���Ńt���C�g�̏����ւ̑ԓx�͎��̂悤�Ȃ��̂ł������B
�����̒��Ԃ̈�l���w�O���f�B�[���@�x�ɏo�Ă��閲�Ƃ��̉��߉\���ɊS���������i�c�c�j�B���̐l�����̍�Ƃɒ��ډ���āA���Ȃ��̍l���ɔ��ɂ悭�����w���̗��_�����邱�Ƃ������m�������̂��Ɛq�˂�݂��A�͂��߂���\�z�ł������Ƃ����A����ɂ������č�҂͒m��Ȃ��ƕԓ������A�����������ɂ͑����s�����Ȓ��q���������Ă����B�����āA�������g�̋�z���w�O���f�B�[���@�x�̃q���g���������Ă��ꂽ�̂��A�i�c�c�j���ꂪ�C�ɓ���Ȃ��l�͂ǂ������܂�Ȃ��ł������������A�ƌ������B�i�t���C�g�w�v�E�C�F���[���̏����w�O���f�B�[���@�x�ɂ݂���ϑz�Ɩ��x�j
�s��҂͂��̂悤�Ȗ@����Ӑ}��m���Ă���K�v�Ȃǂ܂������Ȃ����A������ނ������ے肵���Ƃ��Ă������ɔ��o�̉R���Ȃ��̂ł���t�A�t���C�g�͑����Ă��̂悤�ɏ����B
�����̕��@�̗v�_�́A���l�ُ̈�ȐS�I���ۂ��ӎ��I�Ɋώ@���A���ꂪ���Ȃ��Ă���@���𐄑����A��������ɏo���Ă͂�����\���ł���悤�ɂ���Ƃ���ɂ���B�����Ƃ̐i�ޓ��͂����炭����Ƃ͈���Ă���B�ނ͎������g�̐S�ɑ����閳�ӎ��I�Ȃ��̂ɒ��ӂ��W�����āA���̔��W�\���ɂ����Ǝ����X���A���̉\���Ɉӎ��I�Ȕᔻ�������ė}�����邩���ɁA�|�p�I�ȕ\�����������Ă��B���̂悤�ɂ��č�Ƃ́A����ꂪ���l���ώ@���Ċw�Ԃ��ƁA���Ȃ킿�����閳�ӎ��I�Ȃ��̂̊����������Ȃ�@���ɂ��������Ă��邩�Ƃ������Ƃ��A�������g���畷���m��̂ł���B�i����j �y���炸�̃��J���z ���_���͗��_�A�t���C�g��J����ǂނƂ��A�j�[�`�F�̎��̌��t��z�N���ĂƂ��ɓǂނ��Ƃ��K�v�ȂƂ�������B �s�����l���邱�Ƃ́A�������邱�Ƃ��Ӗ�����B �\�\��M�́A�����A���ɍl�@�����ƁA�����A���Ȃ��̂ɂȂ�B �t�i�j�[�`�F�w�����x76�ԁj ����͌����ăj�[�`�F���u�ʂ��āv�ǂނ̂ł͂Ȃ��A�u�Ƃ��Ɂv�ǂނ̂��B
������҂ƈꏏ�ɂ��āA���̂��Ƃ��l����B��������ƁA��Ԃ悢�l���������ԁB�d���ɕK�v�Ȓ��z����Ԃ悭������B�e�N�X�g�ɂ��Ă����l���B�����ԐړI�ɕ����悤�Ȃ��ƂɂȂ�A�e�L�X�g�͎��̒��ɍō��̉��y�����߂�B�ǂ�ł��āA���x����������A���̂��ƂɎ����X�������C�����ɂȂ�����̂��B���͕K���������y�̃e�L�X�g�ɑ������Ă���킯�ł͂Ȃ��B����͈ڂ�C�ŁA���G�ŁA�����ȁA�قƂ�Ǘ����������Ȃ��Ƃ�������s�ׂ�������Ȃ��B�v�������Ȃ���̓����B�����̕����Ă��邱�Ƃ͉����������A�����̕����Ă��Ȃ����Ƃ��Ă��钹�̓����̂悤�ȁB�i�o���g�w�e�N�X�g�̉��y�x�j
���邢�́s���҂����̐��̊҂���ނ̓V���������炳���c�傢�Ȃ�V�����c�Z�����A�����A�W�Q���A�ǂ��ɕs��v�����邩�ڐ������A�����ɋ�����A��藧�āA�����A���������邱�Ɓt
�u�j�Ə��̂������́A���܂����������v�A�t�@���X�͎n�I������J��Ԃ��Ă����c����͔ނ̋��`�̋��������B�ނ͂�������܂ł������Ɏ咣���Ă����c�ނ������̌�ō��{�I���h���������҂������ЂƂ�����Ȃ����Ƃ�]��ł����̂��v���A���y�̖v���A���y�͌��lj��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ̏ؖ��c�����A���ꂪ�u���܂������v�悤�ɂł��Ă���ƌ������҂����Ă����̂��낤���H�@�ʔ����̂́A���������ǂ����҂𗠐邱�Ƃ��ł�����Ă��Ƃ��c�������ł��܂��O�Ɂc�����Ƃ��A���ꂪ�ЂƓx�ق�Ƃ��Ɋ��҂𗠐����Ƃ�����A�����͂Ƃɂ��������͂��܂������Ă���c�����݂̂��������Œ��Ɏ��蒅���̂łȂ���c�ł����ꂾ���Ĕ����邱�Ƃ͂ł���c�ڂ��̈ӌ��ł́A�t�@���X�͏\���Ɋ��Ȃ������ȁc����͂��̂��Ƃł܂����Ă����̂��Ǝv���c�ǂ�ȏ����ނ̉�U�w�ɂ��т�Ȃ������̂��낤���H�@������������Ȃ��c���ۂɂ͂������c�C�Ⴂ���݂Ă����Ȃ������c��ɂȂ��āu���܂������Ă���v���A�����ĂȂ������Ă��Ƃ��ނɂƂ��Ăǂ��ł��悭�Ȃ�ɂ͏\������Ȃ������c�������瑼�҂����̐��̊҂���ނ̓V���������炳���c�傢�Ȃ�V�����c�Z�����A�����A�W�Q���A�ǂ��ɕs��v�����邩�ڐ������A�����ɋ�����A��藧�āA�����A���������邱�Ɓc�t�@���X���ڂ������̉Ƃł����������Ă������̂����̂��Ƃ��ڂ��͂�����x�l���Ă݂�c�ዾ�z���Ƀf�{���ɒ������ނ̒����፷���c�������ʂĂ���Y���c����͒ɂ܂��������A���ꂾ�����c�i�\�����X�w�������xp183�j
�[�[�\�����X�̏����̂Ȃ��́u�t�@���X�v�Ȃ�l���́A���J�������f���ł���̂͂悭�m���Ă���B
�y�ӂ����у_�[�V���z
�������ʂɃ������[���v�l�̃X�e�p�����ƃ_�[�V���Ƃ̍����̂����߂́A���[�U�Ǝ����悤�ȐU�镑���Ƃ��Ă��ǂ߂�����A�s���[�U�������Ȃ����Ƃ�����ł��́B�܂�A�j�R���C����ɂ₫�������Ă����悤�Ƃ��āA�킴�Ƃ��̕��ƂȂ�Ȃꂵ��������ł��t�\�\����u�₫�����v�ł͂Ȃ��A�X�e�p�����̈�����������߂邽�߂̐U�����Ƃ��āB
�����Ń��[�U������i��Ńj�R���C�ɐg���܂��������̂��Ƃ̌����ƌy�̂̓���܂��������b���o���Ă������B���ꂪ�������[���v�l�̐S��Ƃ��ʂ���u�M��Ȉ��v�A���Ȃ킿�i���V�V�Y���I���̓T�^�I�Ȍ������Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł���i�J��Ԃ��A�����Ƃ����邱�Ƃ��ł��邾���ŁA������u���Ղȁv��ʓI�Ȍ����ł���j�B�[�[�s�Ȃɂ����S�Ƃ�����́A�����ɂ����Ă������܂��ɋ��߂������[���ɂق��Ȃ�Ȃ��̂�����I�t�i�w����x��@P25) �u�ڂ����ꂵ�߂Ă���A�ڂ����Ă���A�ڂ��ɑ������Ԃ��Ă���v�ނ͐�]�ɂ�������ċ��B�u���݂ɂ͏\���ɂ��̌���������I�@���݂������Ă��Ȃ������ɁA���݂�j�ł��������Ƃ��A�ڂ��͒m���Ă���B��������A�w�ڂ��͏u�Ԃ������̎�Ɏc���Ă������x�B�ڂ��͊�]�������Ă����c�c�����ƈȑO����c�c�Ō�̊�]�������Ă����c�c���݂����̂���������A��l�ŁA�i��łڂ��̕����ɂ͂����Ă����Ƃ��A�ڂ��́A�����̐S���Ƃ炵�o���������ɂ����炤���Ƃ��ł��Ȃ������B�ڂ��͂ӂ��ɐM���Ă��܂����c�c���Ƃɂ��ƁA���܂ł��M���Ă���̂�������Ȃ��v �u����Ȃӂ��Ɍ����Ŗ����Ă�������̂Ȃ�A�킽�������Ԃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ���ˁA�[�[�킽���͂��Ȃ��̊Ō�w�ɂȂ�̂͂��߂�ł��B���������āA���傤���܂���Ɏ��˂Ȃ�������A�ق�Ƃ��ɊŌ�w�ɂȂ邩������Ȃ����ǁA���Ƃ������Ȃ��Ă��A���Ȃ��̊Ō�w�ɂ͂Ȃ�܂���B���Ȃ��ɂ������āA�ނ��A������̎�Ȃ��⑫�Ȃ��Ɠ����悤�Ȃ��̂ł����ǂˁB�킽���͂�������ȋC�����Ă�����ł��A�����Ƃ��Ȃ��͂킽�����A�l�Ԃ̔w��قǂ����鋐��ȓŒw偂̂���ł���悤�ȂƂ���֘A��Ă����̂ɂ������Ȃ��A�����ł킽�������́A���U�A���̒w偂߂Ȃ���A�т��т����ĕ�炷���ƂɂȂ�낤���āB����ȂȂ��ł킽�������̈���������Ă��܂���ł��B�_�[�V�F���J�ɂ��b���Ȃ����ȁA���̐l�Ȃ�A�ǂ��ւł����Ȃ��ɂ����Ă����Ă����ł��傤��v �u����ȂƂ��ɂ��A���݂͂���̂��Ƃ��v���o�����ɂ����Ȃ��́H�v �u���킢�����ȏ�������I�@���̐l�ɂ�낵���B���Ȃ��������X�C�X�ł��̐l��V��̂�����Ɍ��߂Ă��܂����̂��A���̐l�͒m���Ă���̂�����H�@�����Ԃ�p�ӎ����ȕ��ˁI�@��̐�܂Ō��ʂ��Ă���������I�@�c�c�v�i�w����x���@P288-289�j �u�`���Ƃ��Ă̈��v�Ƃ������t���g���Ȃ�A�_�[�V���A�j�R���C�E�X�^�����[�M���̊Ō�w�ɂȂ邱�ƂɌ��߂Ă��܂����_�[�V���̈��������́u�_���Ȉ��v�Ƃ��ēǂނ��Ƃ��ł��邩������Ȃ��B
�j�R���C�̌����A���Ȃ킿�����ł��܂��u�͂����Ȃ��v���_���͊T�O��K�p����Ȃ�A�ނ̃}�]�q�Y���I�Փ��Ƃ������邻�̏�ʂ̌�A���̂悤�ȃ_�[�V���Ƃ̖ʉ����B
�u�ڂ��͑O���炫�݂Ɖ�̂���߂悤�Ǝv���Ă��ĂˁA�_�[�V���c�c�����̂Ƃ���c�c�����́B���݂���莆�������������ǁA�䂤�ׂ͂��݂ɗ��Ă��炦�Ȃ������B�ڂ��̂ق�������莆���������������A�莆�͋��Ȃ̂łˁv�ނ͂��܂��܂����ɁA�Ƃ������ނ��낢�܂킵���ɂ������������B
�u�킽�����A�������̂͂�߂Ȃ���Ǝv���Ă��܂����B�������[�����܂��A�킽���������̒����Ђǂ��^���Ă�������Ⴂ�܂��v
�u�Ȃ��ɁA�^��̂͏��肳�v
�u���S�z��������̂͂����܂���B�ł́A���x�͍Ō�̂Ƃ��܂łł��̂ˁH�v
�u�܂����̍Ō�̂Ƃ��Ăɂ��Ȃ����Ⴂ���Ȃ��̂����H�v
�u�����A�킽���͐M���Ă���̂ł��v
�u���̐��̒��ɂ͏I��̂�����̂Ȃ�ĂȂ����v
�u����ɂ͏I�肪����܂��B���̍Ō�̂Ƃ��ɐ��������Ă�������A�킽���A�Q��܂��B���܂͂��ʂ�ł��v
�i�c�c�j
�u���Ȃ��͂�����l�́c�c�C�̈��������j�ł����͂Ȃ���Ȃ��ł��傤�ˁH�v
�u�C�Ⴂ���͔j�ł����Ȃ����A������A������l���ˁB���������C�Ȗ��́A�j�ł����邩������Ȃ��B�ڂ��͂ˁA�_�[�V���A�����낵���ڗ�ŏX��������A�Ђ���Ƃ�����A���݂������悤�ɁA�w�Ō�̂����܂��̂Ƃ��Ɂx�A�ق�Ƃɂ��݂��ĂԂ�������Ȃ��B�����Ă��݂��A����ȂɌ��������ɁA����Ă��邾�낤�ˁB�ǂ����Ă��݂͎����Ŏ�����łڂ����H�v �u�Ō�ɂ͂킽����l�����Ȃ��̂����Ɏc�邱�ƂɂȂ�̂��킩���Ă��܂�����c�c�����҂��Ă����ł��v�i�w����x��@P458-460�j �y�}�]�q�X�g���邢���ᒏǎ҂̃h�X�g�G�t�X�L�[�z �������O�ɖ߂��āA�X�^�����[�M���̌������A�}�]�q�Y���̌����Ƃ���̂͂����������}�����邩������Ȃ��B�����Ă����łӂ����іؑ��q�̃h�X�g�G�t�X�L�[�̃C���g���E�t�F�X�g�D�����̎w�E�����z�N���Ă��������B �w����x�̂Ȃ��ł������Ƃ��L���ȃX�^�����[�M���̍����̏͂ɂ͂��̂悤�ɏ�����Ă���B
����܂ł̐��U�ɂ��łɉ��x�����������Ƃł��邪�A���́A�ɓx�ɕs���_�ȁA���͂���ċ��J�I�ŁA�ڗ�ŁA�Ƃ��ɁA���m�ȗ���ɗ�������邽�тɁA���܂��Ă����A�x�͂���ȓ{��Ɠ����ɐM�����Ȃ��قǂ̉��������������ĂĂ����B����͔ƍ߂̏u�Ԃɂ��A�܂������̊댯�̔������Ƃ��ɂ������Ȃ̂ł���B����Ɏ����������݂��Ƃ�����A���͂��̓��݂̏u�ԁA�����̔ڗ̒�[�����ӎ����邱�Ƃɂ���āA�����������邱�Ƃ��낤�B���͔ڗ�������̂ł͂Ȃ��i���̓_�A���̗����͊��S�ɑS�����̂Ƃ��Ă������j�A�ł͂Ȃ��āA���̉����ꂵ���قLjӎ����铩���������ɂ͂��܂�Ȃ������̂ł���B���l�ɁA�����̏�ɗ����āA����̔��˂�҂���u�Ԃɂ��A���͂�������Ɠ����p�J�I�ȁA����������܂�ʊ��o�𖡂���Ă����B�Ƃ��Ɉ�x�͂��ꂪ���Ƃ̂ق�����ł������B����ƁA���͂����Ύ�������i��ł��̊��o��ǂ����߂����Ƃ�����A�Ƃ����̂́A���ꂪ���ɂƂ��Ă͂��̎�̂��̂̂Ȃ��ł������Ƃ�����Ɋ�����ꂽ����ł���B�i�w����x���@P550-551�j
�������������́A�h�X�g�G�t�X�L�[�����l�̏Փ��i�����y�j������Ă��Ȃ������Ȃ�A������͂��͂Ȃ��Ɩ}�f�ȁu�킽�����v�͙ꂢ�Ă݂�B���������y�g���V�F�t�X�L�C�����ɂ��ŋ��Ƃ��Ă̎��Y�̔����A���O�܂Ŏ��Y�������j�R���C�c��ɂ���ċp������Ă������Ƃ�m�炳��Ă��Ȃ������L���ȏo�����̐܂ɂ��A�h�X�g�G�t�X�L�C�͕��Âȗl�q�������炵���B
�y�g���V�F�t�X�L�C�A�����y���A�O���S���G�t�̎O�l���A�悸���ɔ�����A���l�̕��m���e���グ�����A�͖Ƃ̃n���J�`���|���B���������ꂽ���A�O���S���G�t�͔������Ă�B����ڌ��҂̌��ӂƂ���ɂ��A�h�X�g�G�t�X�L�C�͂܂��Ƃɕ��Âȗl�q�����B�f�����o�鑫�ǂ������Ă�Ȃ������A��F�������߂Ă�Ȃ��������ł���B�i���яG�Y�w�h�X�g�G�t�X�L�C�̐����x�j
�����Ƃ����яG�Y�͂��̂��ƁA�s��������Ȏ�����̉����Ӗ�����̂��炤�B�����̈����O�ɂ��l�Ԃ����ÂɌ����Ȃ��Ƃ�����Ȃ��t�Ƃ��Ă���B
�s�v�c�Ȃ��Ƃɂ��́A�܂��ɍŌ�̏u�ԂɋC�₷�邱�Ƃ͂߂����ɂȂ��̂ł��I ����ǂ��납�A���͂Ђǂ������������āA�@�B�������悤�ɗ͋����A�͋����A�͋��������Ă���ɂ���������� ����B�l�̑z���ł́A���̎����܂��܂ȍl�����Ԃ����Ă���̂ł��A�݂�Ȋ������Ȃ��A�����Ă����� ������A�������A���W�Ȃ���ȍl���ł��B�w�ق�A�������Ō��Ă���B���̊z�ɂ͂��ڂ����邵�A �ق�A���Y�l�̉��̂ق��̃{�^��������тĂ���E�E�E�x�ŁA���̊Ԃ����ׂĂ�F�����A���ׂĂ��L���� �Ă��܂��B�����ĖY��邱�Ƃ̂ł��Ȃ������_�������āA�C�₷�邱�Ƃ��ł����A���ׂĂ����̋� �����A���̓_�̋߂����A��]���Ă���̂ł��B�����čl����ƁA����͍Ō�̎l���̈�b�܂ł��̂� �܂ŁA���̎��ɂ͂�������f����ɂ̂��āA�����đ҂��Ă���A�����āE�E�E�m���Ă���̂ł��A �ƁA�ˑR��ɕ�������A�S�������Ă����I����͊ԈႢ�Ȃ��������܂��I�l�Ȃ�A�����������Ȃ�����A�l �͂킴�킴���܂��ĕ����ł��傤�I����́A������������ق�̈�u�Ԃ̏\���̈ꂩ������܂��� ���A�ԈႢ�Ȃ��������܂��I�i�h�X�g�G�t�X�L�C�w���s�x�j
������ɂ���A���̎ŋ��Ƃ��Ă̎��Y���s�̏u�Ԃ̐S�I�O�����L�����h�X�g�G�t�X�L�C�̏����̂Ȃ��ŌJ��Ԃ���邱�ƂɂȂ�B�ؑ��q�̂����h�X�g�G�t�X�L�[�̃A�E���̌��Ƃ͂��̂��Ƃł���B
�y�`���Ƃ��Ă̈��z ���Ă���������蓹�������Ă��܂������A�u�`���Ƃ��Ă̈��v�ɖ߂낤�B
�_�[�V���̃j�R���C�ւ́u�`���v�A�������[���v�l�̃X�e�p�����ւ́u�`���v�A�\�\�w����x�͂��ꂪ�J��Ԃ����e�L�X�g�ł�����B�����ăj�R���C�E�X�^�u���[�M�����X�e�p���E���F���z�[���F���X�L�[�������]�ނƂƂ��ɂ��Ƃ܂������v���w����������Ɏ����Ă���B
�Ƃ���ŁA�h�X�g�G�t�X�L�[�̓�Ԗڂ̍Ȃ��v�̔j���p�ȐU�����ɂ��ǂ낭�قǑς��鏗�����������Ƃ��m���Ă���B �A���i�́A�q�������̈���J���e�ׂɓ��L�ɔF�߂Ă��B�q������ЁA���爫���Ɣl��A��������T�����Ύ��̂ɒʂĂ����L�ɕ`���ꂽ�ނ̎p�́A�m���ɐ��C�ł͂Ȃ����A�ޏ��̔E�]�ɂ������ٗl�Ȃ��̂���������B�i���яG�Y�w�h�X�g�G�t�X�L�[�̐����x�u�V�@�����E�q���v�j
�ЂƂ͂������������̑ΏۂƂȂ����ꍇ�A�Ƃ��ɂ�����Ђǂ��d�ׂƂ���̂ł͂Ȃ����B�[�[�Ə����Ă��܂�����A���������́u��e����̎����v�Ƃǂ��Ⴄ�Ƃ����̂��낤�B��Ɏ��Y�ɗނ���Ɣᔻ�������A�킽�����̓ǂ݂���͂莙�Y�ɗނ���B
�t�ɂǂ�ȌǓƎ҂ł��ЂƂ�̈�����l���K�v���A�Ƃ��钆��v�v�̌��t���h�X�g�G�t�X�L�[���X�^�u���[�M���ɓK�p����̂Ȃ�A�J��Ԃ����u�`���Ƃ��Ă̈��v�́A�_�[�V���̃X�^�����[�M���ւ̖����̈��̏��q���肽�Ȃւ̊��ӂ́u�Ӑ}������\���v�Ƃ��Ă��ǂނ��Ƃ��ł��Ȃ��ł͂Ȃ��B
�n��̑S�ߒ��͐��_�����a�i���������ǁj�̔��a�ߒ��ɂ��A�_��Ƃ̊����ߒ��ɂ��A�����ߒ��ɂ����Ă���B�����ɂ����Ă����͗~���邢�̓L���X�g���Ɍ��������i�q���v���X�j�͍ő�̊��v�ł���B�t�ɁA�����̖����ȗF��͕ی�I�ł���B��Ƃ̓`�L�ɂ�����ǓƂ̋����ɂ�������炸�A���S�ȌǓƂőn���I���肦����Ƃ����͒m��Ȃ��B�����Ƃ��s�тȎ��ɔނ��u�����ϔC��v���ȂĐM�����铯�����邢�ِ͈��̗F�l�͂قƂ�Ǖs���ł���B�����̍�Ƃ́u�Â��v�̑Ώۂ�K���������Ă���B�t�ɁA���ꂾ���̐l�ԓI���͂��������Ȃ��A�����Â����Ȃ��l�͂��̎�����ʂ蔲���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�i����v�v�u�n���Ɩ��������v——�n��̐����w�Ɍ����āj
�w����x�̑�攪�͂́w�C�����c�q�x�̂������ƂɂÂ��͂Ƃ��ď����ꂽ�u�X�^�u���[�M���̍����[�[�`�z�����̂Ƃɂāv�A�|�|���ǁw���V�A��m�x�̕ҏW���J�g�R�t���G���f�ڂ�f��������߂ɗz�̖ڂ������A��N�i1921�N�j�h�X�g�G�t�X�L�[�̎���A���\�����̂����A�h�X�g�G�t�X�L�[���g�̍Z���łƃA���i�̎�ɂ��M�ʔł�����B���̓������ׂĂ݂�ƁA�ȃA���i�������ɍZ���ł̊j�S�������u��₁v���A�v�̗c���������߂���u�j���p�ȁv�e�N�X�g���B�����悤�Ǝ��݂��̂����킩��B�����A����ɂ��Ă͌����҂̐V�������������܂�����̂��낤���A�����m��Ȃ��҂��Ȃ�炩�̊��z�߂��������̂͂�߂ɂ��Ă������B �����_�[�V���ɂ�����镔���������o���Ă����B
����A�X�C�X�ŁA���́A���ď����̂���ɂ̂���ꂽ�̂Ɠ����悤�ȋ��\�ȏՓ��̈�ɂƂ��Ȃ�ꂽ�A�͂�������~�̔�����������B���͐V�����ƍ߂ɑ��鋰�낵���U�f���A���Ȃ킿�A�d�����s�����Ƃ����U�f���������̂ł���i���͂��łɍȑю҂ł��邩��j�B���������́A������l�̎Ⴂ���̒���������ē����������B�����Ă��̎Ⴂ���ɂقƂ�ǂ��ׂĂ��������A����قǂ܂Ŏ��������̂��̂ɂ������Ɩ]��ł��鏗�����A���͂܂����������Ă��Ȃ����ƁA�����������������邱�Ƃ��ł��Ȃ����낤���Ƃ܂őł��������B����ɂ��̐V�����ƍ߂��A�Ȃ�玄���}�g�����[�V������~���Ă���邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��������낤�B�i�w�߂Ɣ��x���@P574)
�t���C�g�́w�}�]�q�Y���̌o�ϓI���x�i1924)��w�h�X�g�G�t�X�L�[�ƕ��e�E���x(1928)�́A���̃X�^�u���[�M���̍�����ǂ�[�[���邢�͂Ђ���Ƃ��Ă��̏Ռ��ɂ��[�[�����ꂽ���̂��Ɛ�������B
�y���݂���y���ނ��Ɓz
�h�X�g�G�t�X�L�[�̃e�L�X�g�͂����Ȍ��ɒ��ڂ��邱�Ƃ��ł���B�킽����������̍ēǂŁA���Ƃ��璍�ڂ����̂́A�Ƃ�����M���_�[�V���̖�����ď������e�L�X�g�̒f�Ђ������B
�����ď�ɏ����ꂽ�悤�Ƀ_�[�V���̊Ō�w�Ƃ��Ă̋`���������ԓx�́A�����̈��̂ЂƂȂ̂��A����Ƃ��������l�ɂЂǂ��d�݂ƂȂ邩������Ȃ��u����Ȉ��v�Ȃ̂��A���邢�͂����Ƃ͂܂��ʂ̂��̂Ȃ̂��́A�u���݂�v�̂܂܂ł���B���܂͂��́u�����̒m�b�v���y����ł��̂悤�ȕ��������Ă���A�Ƃ��Ă����B
�A���i�E�J���[�j�i�����ʂ̖\�N�̋]���҂Ȃ̂��A����Ƃ��J���[�j�����s�����ȍȂ̋]���҂Ȃ̂��A���邢�͂܂��A�����ȃ��[�[�t�E�j���s���ȍٔ��Ŕj�ł��Ă��܂��̂��A����Ƃ��ٔ��̔w��ɂ͐_�̐��`���B����Ă��Ăj�ɂ͍߂����邩��Ȃ̂��A�c�ǂ��炪�������Ăǂ��炪�Ԉ���Ă��邩�B�G���}�E�{���@���[�͉䖝�̂Ȃ�Ȃ����Ȃ̂��A���邢�͗E���Ől�̐S�������Ȃ̂��B�E�F���e���͂ǂ����B�ނ͑����ŋC�����̂��B���邢�́A�̂ڂ��オ�����U���I�Ȋ���ƂȂ̂��B�����𒍈ӂԂ����ǂ߂ΓǂނقǓ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�B�i�c�c�j�����́��^�����͉B����Ă���A�\�����ɂ��ꂸ�A�܂��\�����ɂ��꓾�Ȃ����̂Ȃ̂ł���B�i�N���f���w�����̐��_�x�j
�l�Ԃ́A�P�ƈ��Ƃ����m�ɔ��ʂ��ꂤ��悤�Ȑ��E��]��ł��܂��B�Ƃ����܂��̂��A�l�Ԃɂ͗�������O�ɔ��f�������Ƃ����~�] �\�\�����I�Ō䂵�������~�]�����邩��ł��B���܂��܂ȏ@����C�f�I���M�[�̂���ė���b�́A���̗~�]�ł���܂��B�@����C�f�I���M�[�́A���ΓI�ŗ��`�I�ȏ����̌�����A���̕K�R�I�œƒf�I�Ȍ����̂Ȃ��Ɉڂ������邱�Ƃ��Ȃ�������A�����Ɨ������邱�Ƃ͂ł��܂���B�@����C�f�I���M�[�́A���ꂩ�����������Ƃ�v�����܂��B���Ƃ��A�A���i�E�J���[�j�i�����ʂ̖\�N�̋]���҂Ȃ̂��A����Ƃ��J���[�j�����s�����ȍȂ̋]���҂Ȃ̂������ꂩ�łȂ���Ȃ炸�A���邢�͂܂��A�����ȃ��[�[�t�E�j���s���ȍٔ��Ŕj�ł��Ă��܂��̂��A����Ƃ��ٔ��̔w��ɂ͐_�̐��`���B����Ă��Ăj�ɂ͍߂����邩��Ȃ̂��A�����ꂩ�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B ���́����ꂩ���ꂩ���̂Ȃ��ɂ́A�l�ԓI���ۂ̖{���I���ΐ��ɑς��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����\�����A�����́u�R���ҁv�̕s�݂����邱�Ƃ̂ł��Ȃ����\�����܂܂�Ă��܂��B�����̒m�b�i�s�m�����̒m�b�j������A�����Ă���𗝉����邱�Ƃ�����Ȃ̂́A���̖��\���̂䂦�Ȃ̂ł��B�i�N���f���w�����̐��_�x P7-9�j
���邢�́A�v���[�X�g��ǂރ������E�o���g�Ȃ炱�������A�s�R�^�[���́s�̑�t�ł��s�ڏ��t�ł��Ȃ��B���ɐ^��������Ƃ���A���̐^���́u���ҁv�̌��t���ނɗ^���铮�h�S�̂ɂ����킽�錾�q�̐^���ł���B�t
�o���x�b�N�s���̌y�֓S���̒��ŁA�A��̂Ȃ�w�l���w�����E�]�_�x��ǂ�ł���B�ޏ��͔��l�łȂ��A�����ł���B�u�b�ҁv�͔ޏ������Ƃ̏������낤�ƍl����B�Ƃ��낪�A���̗��s�̍ہA��Ԃɏ�荞��ł�����Q�̋q���u�b�ҁv�ɁA���̕w�l�̓V�F���o�g�t����܂��A���M�Ȑ��܂�ŁA���F���a�������Ƃ̃T�����̉Ԃ��A�Ƌ����Ă����B �܂������Η������̏�Ԃ�̑Ώۂ̒��Ō��т��A�O�������ꂩ�炭�������A���̔��Ε��ւƕς���A���������X�P�b�`�́w����ꂽ�������Ƃ߂āx�̒��ɂ悭�o�Ă���B�ŏ��̂�����������A�ǂޏ����ɉ����āA�������̗��������ƁA ��A�Q���}���g�Ƃ̓�l�̂��Ƃ��̂����A�z�C�ȕ����A���́A�����i���݁j�ŁA��W�ȕ��������Ȑl�i����j�ł���B ��A�I�f�b�g�E�X�����͎��͂̐l�̔��f�ł͂����ꂽ�����ł��邪�A���F���f�������Ƃł͂��҈����ɂ���Ă���B �O�A�m���|���́u�b�ҁv�̉Ƒ���|�C�Â����A�ނ�̑��q�ɂ͍˔\���Ȃ��Ɛ�������قLĵ����ɂ��Ă��邪�A�x���S�b�g�ɂ́A�ꌾ�ł������낳���i�s����͊Ԕ����ꂢ���t�j�B �l�A�����m���|���́A�M���ŁA���}�h�Ȃ̂ɁA�}�i�}���t�̓��h�O���g�߂������邪�A�s�����̔����I�ȃu���W�����ł�����ȓ��t�Ɏd����̂͋��ۂ����ł��낤���A�m���|�����̉ߋ���W�݂�l����m������A���t�̕��ł��S�z�ɂȂ����ɂ������Ȃ��B�t �܁A�X�����ƃI�f�b�g�́u�b�ҁv�ɑ��čׂ����C���g���Ă��邪�A���鎞�A�u�b�ҁv���������A�s����قǐ����I�ŁA�����ȁt�莆�ɕԎ����������Ƃ������Ȃ����Ƃ��������B�i�c�c�j �Z�A���F���f���������̓R�^�[���ɂ��ē�ʂ�̂�����������B�R�^�[�������̂��Ƃ肪���܂�m��Ȃ��ƌ��ĂƂ�ƁA�R�^�[���̂��Ƃ�J�߂��₷�B�������A���肪�m���Ă��鎞�́A�t�̕��@�����A�R�^�[���̈�w��̍˔\�ɂ��āA�����f�C�Ȃ��ԓx�������B ���A�����͐t���ɊQ������Ƃ������Ƃ����闧�h�Ȋw�҂̖{�œǂ���̎��A�u�b�ҁv�͂d���m�ɉ�B����ƁA�ނ́A�s������ʂɏo�邱�̏����G�߂̗��_�́A���ꂾ���t���̕��S���y�������Ƃ����_�ł���t�ƒf������B�ȉ��A���l�B�i�������E�o���g�u�����̍\�z�v�w�e�N�X�g�̏o���x�����j �����Ń������E�o���g�͑�ꊪ�u�X�����Ƃ̂ق��Ɂv�ɂ���킽�����ɂ͂����Ƃ���ۓI�ȃ��O�����_���̗�������Ă��Ȃ��B�X�m�r�Y���ɉ̂悤�ȓŐ��f���A�J�D��m������������A���v�킵���ȁA�����ő@�ׂȃ��O�����_�����A�M���Ƃ̈��A�Ɂu�ُ�Ȃ܂ł̊��C�ƔM�������킷�v�Ђǂ������ł��邱�Ƃ��B�������̂悤�ȗ�̓v���[�X�g�̏����ɂ͖����̂��Ƃ܂��Ȃ��B �y�ł�����ȋ����ϔO�z �Ō�Ɂu���疳�p�u�����ꂸ�A�d�˂Đ��_���͗��_����u�ł�����ȋ����ϔO�v�A�`���Ƃ��Ă̈�������r�I�Ⴂ���ɏ����ꂽ�W�W�F�N�̕������p���Ă������B
�c�c�������̋`���̓N�w�҂ł���J���g���m��Ȃ��������̂��A�ʑ��I�ŃZ���`�����^���ȕ��w�A�����̃L�b�`���͂悭�m���Ă���B���̂��Ƃ͕ʂɋ����ɂ�����Ȃ��B�Ƃ����̂��A�q�Ӓ��̕w�l�r�ւ̈��������̋`���ƌ��Ȃ��u�{������i�R�m�������j�v�̓`�������Ȃ������Ă���̂́A�܂����������������w�̐��E�Ȃ̂ł���B�R���[���E�}�b�J���E�́w����ȋ����ϔO�x�ɂ́A�{������W�������̓T�^�I�ȗႪ������B���̏����͂܂������ǂނɑς��Ȃ����̂ŁA���̂��߂Ƀt�����X�ł͑p���u�W�F�E�����i���͂����ǂ�ł��܂����j�v�̈���Ƃ��ďo�ł��ꂽ�B���̏����̎���͑���E���̖����A��l���́A�����m�݂ɂ��鏬���ȕa�@�Ő��_�a�҂̐��b�����Ă���Ō�w�ł���B�ޏ��͐E�Ə�̋`���ƁA�ЂƂ�̊��҂ւ̈��Ƃ̊����Ɉ�����Ă���B�����̌����ŁA�ޏ��͎����̗~�]�𗝉����A����f�O���āA�`���ւƖ߂�B�ꌩ����ƁA�Ȃ�̖ʔ��݂��܂Ƀ������Y���̂悤�Ɍ�����B�`������������ɑł������A�`���̂��߂Ɂu�a�I�ȁv�������f�O�����̂�����B�������Ȃ���A���̒f�O�ɂ����铮�@�̕`�ʂ͂����������G�Ŕ����ł���B�����̌��т͎��̂悤�ɂȂ��Ă���[�[
�ޏ��ɂ͂����ɋ`�����������B�i�c�c�j����͂���Ȃ�d���ł͂Ȃ������B�����ɂ͔ޏ��̐S���������Ă����B���������[���B���ꂪ�ޏ����{���Ɋ���Ă������Ƃ������B�i�c�c�j�Ō�w�����O�g���[�͂ӂ����ѕ����͂��߂��B�D�u�ƁA����邱�ƂȂ��A�ޏ��͂��Ɏ������g�𗝉������B�����āA�`�������A�ł�����ȋ����ϔO�ł���A���̕ʖ��ł��邱�Ƃ𗝉������B ���̂悤�ɁA�����ɂ���̂͐^�ɕُؖ@�I�E�w�[�Q���I���]�ł���B�`�����̂��̂��u���̕ʖ��ɂ����Ȃ��v�Ɗ������Ƃ��A���Ƌ`���̑Η����u�~�g�����v�B���̂ǂ�ł�Ԃ��[�[�u�ے�̔ے�v�\�\�ɂ���āA�ŏ��͈��̔ے�ł������`�����A�����I�ȑΏۂɑ��鑼�̂��ׂẮu�a�I�ȁv����p�����鎊���̈��ƍ��v���A���J���̗p����g���A���̂��ׂẮu�ӂ��́v���́q�N�b�V�����̒Ԃ��ځ@point de caption�r�Ƃ��ċ@�\����B�`�����̂��̂������I�������Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��o�������u�ԁA�`���ƈ��Ƃ̝h�R�A���Ȃ킿�`���̏������Ɨ�������̕a�I�����������邢�͈������Ƃ̝h�R�͉�������B �����̍ŏ��̂ق��ł́A�`���͏����ŕ��ՓI�ł���A��������͕a�I�ŁA�ʓI�ŁA����ł���B�Ƃ��낪�Ō�̂ق��ɂȂ�ƁA�`���������u�ł�����ȋ����ϔO�v�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�B���J���̃e�[�[�A���Ȃ킿�A�q�P�r�Ƃ͍����I�E��ΓI�q���r�̉��ʂɂ����Ȃ��A�q�����́@das Ding�r�A�܂�c�s�������ȁq�����́r�ɂ��u����ȋ����ϔO�v�̉��ʂɂ����Ȃ��A�Ƃ����e�[�[�́A���̂悤�ɗ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�q�P�r�̔w��ɂ͍����I�ȁq���r������A�q�P�r�Ƃ́u�q���r�̕ʖ��v�ł���B�q���r�͓���́u�a�I�ȁv�ʒu�������Ȃ��̂ł���B�q�����́@das Ding�r�A������Ȍ`�ł����Ɏ�芪���A�����̒ʏ�̐i�s�𗐂��O���I�Ȉٕ��Ƃ��ċ@�\���Ă��邨�����ŁA�����͎��g�ꂵ�A����̌����I�Ώۂւ́u�a�I�ȁv�������瓦��邱�Ƃ��ł���̂ł���B�u�P�v�́A���̎��ȁq�����́r�ɑ��Ĉ��̋�����ۂ��߂̗B��̕��@�ł���A���̋����̂������ł����́q�����́r�ɑς�����̂ł���B�i�W�W�F�N�w�߂��猩��xP299-300�j
�s����A���݁i�_�[�V���j�̖]�݂������A�����@�������Ȃ�������B���݂��ڂ��i�X�^�����[�M���j�ɊS�����̂́A���傤�ǔN�Ƃ����Ō�w���A�Ȃ��������l�̊��҂ɁA�ق��̊��҂����悯���ɊS�������Ƃ����邾�낤�A����A�����Ƃ��܂������A���������̑����ɗ�������Ă�������̔k���A��̂͂��낢�날��̂ɁA�ǂꂩ��̈�̂𖭂ɍD���悤�ȁA����Ȃ��̂��Ǝv���Ă�����B�Ȃ�����Ȗڂłڂ���������H�t�i�w����x�@��@P461)
�c�c�c�c
�����L
�y���яG�Y�w�h�X�g�G�t�X�L�[�̐����x�z
�s����l�͑��̂���l�ɑ������̐l�ԊW�ɂ����āA�P�l�ƂȂ�A�܂����l�ƂȂ�B�t�i�X�L���w�h�X�g�G�t�X�L�[�o���x�j �u���̌��ȂȓN�w��(�X�g���A�z�t�j�́A�h�X�g�G�t�X�L�C�̐��i�́u��ȕ���v�ɂ́A�]������Ă����炵���B�ނ̓g���X�g�C�Ɉ��ĂĎ��̗l�ɏ����Ă���B �u�ْ��w�h�X�g�G�t�X�L�C�`�x�A����艺�������Ǝv���܂��B���ɂ̐܁A���ǁA��ӌ������k����������K�r�ɑ����܂����A����ɂ��Ĉꌾ������\���グ�Ēu��������������܂��B���͂��̓`�L�����M���Ȃ���A�����ɗN���オ�錙���̏�Ɛ킢�܂����A�ǂ������Ă��̌��Ȋ���ɑł����������Ɠw�߂܂����B�i�����j�h�X�g�G�t�X�L�C�́A�Ӓn�̈����A���i�[���A�Ȃ̈����j�ł����B�������������̂����Ɉꐶ���߂����Ă��܂����Ǝv���A���m�ł��������ł����邪�A���̈Ӓn�̈����Ɨ��������v���A���̋C�ɂ��Ȃ�܂���B�i�����j�X�C�X�ɂ������A���́A�ނ��A���j���s�҂���l���A��̂�����Ɍ��܂������A���j�͊������˂āA�w�������Đl�Ԃ��x�Ƒ吺���o���܂����B�i�����j����Ǝ����l�ȏ�ʂ́A�₦���J�Ԃ���܂����B����Ƃ����̂��A�ނɂ́A�����̈Ӓn�̈�����}������͂��Ȃ���������ł��B�E�E�E�E������A���B�X�R���@�g�t�����Ęb�������ł����A���鏗�̉ƒ닳�t�̎�����ŁA���鏭���ɗ����Ŗ\�s���������b���A�ނɎ��������Ɍ���������ł��B�����̗l�ȓ��~�������Ȃ���A���̔��Ɋւ��āA�ނ������������������Ă��Ȃ��������ɒ��ӊ肢�����B�E�E�E�E�����ԕt�������Ă��邤���ɂ́A��������Ă��܂���l�Ȑl�����A����Ɍ����o�������o����̂ł��B�S����̑P�ӂ̓����Ƃ��A����̈�u�Ƃ��������̂́A�}�Ă𐅂ɗ������̂ł��B�t���I�h���E�~�n�G�C�����B�b�`�ɂ��āA������������v���o�ł���������A���͔ނ��������ł��傤���A�ނɑ��Ď��͖����Ȓj�ɂ��Ȃꂽ�ł��傤�B���ō��グ�����A���͂̏�̈����������ʐl�Ԃ��A�̐l���Ɛl�ɐM�������鎖�́A��̉��Ƃ������Ȃ��Ƃł��傤���B�v�i�P�W�W�R�N�P�Q���j �@������������l�Ԃ́A���̏����Ƃ̗ՏI���Ŏ��܂ŁA��\�N�Ԃ̃h�X�g�G�t�X�L�[�̗F�ł����������v�����A�N�̐S�̂����ɂ��A�₽�������ʂ�ł��낤�B�����ɂ���̂́A�}�f�Ȉ�v�z�ƂƓV�˂Ƃ̊Ԃɂ��閄�߂鎖�̏o���Ȃ��P�Ȃ�u�肩�B�X�g���A�z�t�̒��߂����̂́A�h�X�g�G�t�X�L�[�̈��锽�ʂ��낤���B�Ⴆ�A�g���X�g�C�ɁA�ǐl�̐��i�����₳�ꂽ���ɁA�h�X�g�G�t�X�L�[�̍Ȃ��������l�ɁA�u�ǐl�͐l�Ԃ̗��z�Ƃ������̂̑̌��҂ł����B�}���l�Ԃ̏���ƂȂ�l�ȁA���_��A�v�z��̔������A�ނ͍ō��x�ɔ����Ă��܂����B�l�Ƃ��Ă��A�C�̍D���A����ȁA���ߐ[���A�������A���~�ȁA�ׂ����v�������������l�ł����v�i�P�W�W�T�N�j�Ƃ������t���R�ł͂Ȃ��̂��낤���B�l�͍D��ň���l�̔��ʂƂ������t���g��������B���Ȍ��t���B�h�X�g�G�t�X�L�[���e�F�ƍȂƂɁA�I�����ʂÂ��������̂ł���B���B�X�R���@�g�t���A�X�g���A�z�t�Ɍ�����b�́A���̎������h�X�g�G�t�X�L�[���g�A�c���Q�l�t�̋��Ŝ��������Ƃ������`�̈�b���`�����Ă���قǗL���Ȃ��̂ŁA���̐^�U�グ�悤�ƁA���낢��w�߂Ă���]�Ƃ����邪�A���_�킩��Ȃ��B�킩�����Ƃ���ʼn��ɂȂ낤�B�P�Ȃ鎖������b���^�����Ƃ͌���Ȃ��B�E�E�E�E�E�E����ɂ��Ă��A���̕��w�n���̖��_�ɜ߂��ꂽ���̍�ƂɂƂ��āA�������̏�ł̎����̐��i�̐^���Ȃ��Ƃ������̂��A��̉����Ӗ������낤�B�ނ̓`�L��ǂނ��̂́A���̐����̗]��̗����Ɋ��������̂ł͂��邪�A�����R�Ɛ����āA������������悤�Ƃ����݂Ȃ������l�Ɍ�����̂��A���炭���w�n���̏�ł̒������M����ꂽ���ׂł���B�Ⴕ�ނ��������������_�̂Ȃ��������҂ł������Ȃ�A�ނ̕��w�́A����قǗ͋������̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ������낤�B�|�p�̑n���ɂ́A�����̋��͂�K�v�Ƃ���Ƃ́A���炭�ނɂ͎����̗��ł������B�Ⴕ�����Ȃ�A�X�g���A�z�t�͎����̎d�����������ׂ��d���ƌ����Ă��邪�A�h�X�g�G�t�X�L�C�́A�y���Ɍ������ׂ��d�����d�����Ď��Ƃ������悤�B�v�i���яG�Y�w�h�X�g�G�t�X�L�C�̐����x�u�U�����v�j ���̏��яG�Y�̕��͂́A�����قǑ����̂��Ƃ�����Ă��܂��Ă���B��������Ƀt���C�g�̌��t�A�h�X�g�G�t�X�L�[�́s�����Ȏ����ɂ����Ă͊O�ɂ�������T�f�B�X�g�ł��������A�傫�Ȏ����ɂ����ẮA���ɂ�������T�f�B�X�g�A���Ȃ킿�}�]�q�X�g�ł���A�����Ƃ����l�D���ȁA�����Ƃ����ߐS�ɕx�l�Ԃ������̂ł���t�̍I�݂Ȗ|���ǂނ��Ƃ��ł��悤�B���邢�̓j�[�`�F�̌��t�̖|����B
�킽���͌N�������鈫���Ȃ����邱�Ƃ�M����B����䂦�ɂ킽���͌N����P�����҂���̂��B
�܂��ƂɁA�킽���͂������̋���҂����������B�����́A�����̎葫����X�����ނ��Ă���̂ŁA������P�ǂ��Ǝv���Ă���B�i�j�[�`�F�w�c�@���g�D�X�g���x��˕x�Y��j ���яG�Y�́w�h�X�g�G�t�X�L�C�̐����v���������߂ɏ\�N�߂��������Ă���B�킽�����̔@�����N���Ԃ�̍ēǂ����������̎U���ȓǎ҂�������ɂȂɂ�珑���A���z���̂悤�Ȃ��Ƃ��������Ȃ��̂Ɍ����Ă���B�X�^�����[�M���̈�т������i���w����x����ǂ݂Ƃ�̂́u���w�Ƃ͖����̎����v�Ƃ������A�킽�������_�[�V���̈�т������i��ǂ݂Ƃ낤�Ƃ��铯���͂����Ȃ��^�������Ă���̂͏\���Ɏ��o���Ă���B
�c�c�c�c
�f�ГI�Ɉ��p�����X�^�����[�M���̌����̂��Ƃ̃_�[�V���Ƃ̉�b���������������t�L���Ă����B �u�ڂ��͑O���炫�݂Ɖ�̂���߂悤�Ǝv���Ă��ĂˁA�_�[�V���c�c�����̂Ƃ���c�c�����́B���݂���莆�������������ǁA�䂤�ׂ͂��݂ɗ��Ă��炦�Ȃ������B�ڂ��̂ق�������莆���������������A�莆�͋��Ȃ̂łˁv�ނ͂��܂��܂����ɁA�Ƃ������ނ��낢�܂킵���ɂ������������B �u�킽�����A�������̂͂�߂Ȃ���Ǝv���Ă��܂����B�������[�����܂��A�킽���������̒����Ђǂ��^���Ă�������Ⴂ�܂��v �u�Ȃ��ɁA�^��̂͏��肳�v �u���S�z��������̂͂����܂���B�ł́A���x�͍Ō�̂Ƃ��܂łł��̂ˁH�v �u�܂����̍Ō�̂Ƃ��Ăɂ��Ȃ����Ⴂ���Ȃ��̂����H�v �u�����A�킽���͐M���Ă���̂ł��v �u���̐��̒��ɂ͏I��̂�����̂Ȃ�ĂȂ����v �u����ɂ͏I�肪����܂��B���̍Ō�̂Ƃ��ɐ��������Ă�������A�킽���A�Q��܂��B���܂͂��ʂ�ł��v �i�c�c�j �u���Ȃ��͂�����l�́c�c�C�̈��������j�ł����͂Ȃ���Ȃ��ł��傤�ˁH�v �u�C�Ⴂ���͔j�ł����Ȃ����A������A������l���ˁB���������C�Ȗ��́A�j�ł����邩������Ȃ��B�ڂ��͂ˁA�_�[�V���A�����낵���ڗ�ŏX��������A�Ђ���Ƃ�����A���݂������悤�ɁA�w�Ō�̂����܂��̂Ƃ��Ɂx�A�ق�Ƃɂ��݂��ĂԂ�������Ȃ��B�����Ă��݂��A����ȂɌ��������ɁA����Ă��邾�낤�ˁB�ǂ����Ă��݂͎����Ŏ�����łڂ����H�v �u�Ō�ɂ͂킽����l�����Ȃ��̂����Ɏc�邱�ƂɂȂ�̂��킩���Ă��܂�����c�c�����҂��Ă����ł��v �u�ł��A�������ǂڂ������݂��ĂȂ��ŁA���݂��瓦���Ă��܂�����H�v �u����Ȃ��Ƃ͂���܂���A�Ă�ł��������܂��v �u�����Ԃ�ڂ����y�̂������������ȁv �u�y�̂����łȂ����Ƃ��������̂����Ɂv �u���Ă݂�ƁA�y�̂���͂肠��킯���H�v �u�킽���͂���Ȃ���ł͌����܂���ł����B�_���܂��������ł��B���Ȃ����������Ă킽���ȂǕK�v�Ɋ������Ȃ��悤�A�S�������Ă��܂��v �u���t�ɂ͌��t�̂��Ԃ������Ȃ�����ȁB�ڂ����A���݂�j�ł����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�Ɋ���Ă����v �u���Ȃ����킽����j�ł�����Ȃ�āA�ǂ��������Ăł���͂��͂���܂���A����͂��Ȃ������g����������悭�������̂͂��ł��v�_�[�����͑����ɁA�����ς�ƌ������B�u�������Ȃ��̂Ƃ���֎Q��Ȃ���A�킽���͊Ō�w�ɁA�t�Y���Ō�w�ɂȂ��āA�a�l�̐��b�����邩�A�{����ɂȂ��āA���������ĕ��������܂��B�킽���͂������߂���ł��B�킽���͂���̍ȂɂȂ邱�Ƃ��ł��܂��A���������ƂɏZ�ނ��Ƃ��ł��܂���B�킽���̖]�݂͂�������ł��c�c���Ȃ��͉��������������̂����Ɂc�c�v �u����A���݂̖]�݂������A�����@�������Ȃ�������B���݂��ڂ��ɊS�����̂́A���傤�ǔN�Ƃ����Ō�w���A�Ȃ��������l�̊��҂ɁA�ق��̊��҂����悯���ɊS�������Ƃ����邾�낤�A����A�����Ƃ��܂������A���������̑����ɗ�������Ă�������̔k���A��̂͂��낢�날��̂ɁA�ǂꂩ��̈�̂𖭂ɍD���悤�ȁA����Ȃ��̂��Ǝv���Ă�����B�Ȃ�����Ȗڂłڂ���������H�v �u�Ђǂ���������������ł��̂ˁH�v�Ȃ����܂��܂��Ɣނ̊���̂������݂Ȃ���A��������߂Ĕޏ��͂����˂��B�u�����I�@���ꂾ�̂ɂ��̐l�́A�킽�������Ȃ��Ă��������Ȃ�āI�v �u���������A�_�[�V���A�ڂ��͂��̂���悭���o���������B���̂��������Ȉ����߂��A���̏�ŁA���r���[�g�L���ƃ}�������E���āA�����̌����ɂȂ�������Ă��܂��A�ギ����̂Ȃ��悤�ɂ���A�Ƃڂ��Ɋ��߂�̂��B���̎���Ƃ��ċ�O���[�u���������ꂽ���ˁA���̍r�Î��͂����Ȃ��Ƃ���ܕS�ɂ͂��ƁA�����炳�܂ɓ��킵����B���炭���荂�������łˁI�@����W���I�@�́A�́I�v �u�ł��A���ꂪ���o�������ƁA�͂�����M���Ă�������Ⴂ�܂��́H�v �u���₢��A���o�ł��Ȃ�ł�����Ⴕ�Ȃ��I�@�����͒���l�t�F�[�W�J�Ȃ̂��A�k�Y���瓦����������������B�������A����Ȃ��Ƃ����Ȃ̂���Ȃ��B�����łڂ����ǂ������Ǝv���ˁH�@�ڂ��͎�����ɂ����������̋�����ɂ���Ă�����̂��A�������́A�ڂ�������������������̂Ǝv������ł��邾�낤���I�c�c�v �u���Ȃ��͖钆�ɂ��̒j�Ƃ���ɂȂ��āA����Ȃ��Ƃ����߂�ꂽ��ł��ˁH�@���Ȃ��ɂ͂��킩��ɂȂ�Ȃ���ł����A���̐l�����̒������Ԃɂ��Ȃ������������肱�܂�Ă���̂��H�v �u�ȂɁA�D���Ȃ悤�Ȃ����Ă������B�Ƃ���ŁA���݂̐�̐�͉����ڂ��ɕ����������Ƃ������āA�ނ��ނ����Ă���悤����Ȃ����A�ڂ�����킩���v���炾�������ȓŁX���������ׂāA�ނ͂������������B �_�[�V���͂�����ƂȂ����B �u�����������ƂȂ�Ă���܂���A�^��Ɏv�����Ƃ��Ȃ�ɂ�����܂���A������ق��Ă��Ă��������I�v�ޏ��́A���̕����������Ƃ��̂��悤�Ƃł�����悤�ɁA�s�����Ȑ��ŋ��B �u�Ƃ����ƁA�ڂ����t�F�[�W�J�ɉ�ɋ������ւȂs���Ȃ��ƐM���Ă���ˁH�v �u�����A�Ȃ�Ă��Ƃ��I�v�ޏ��͗�����炵���B�u�Ȃ�ł킽��������Ȃɂ��ꂵ�߂ɂȂ��ł��H�v �u����A�����̈�����k�������Ĉ��������A�����ƁA���̘A�����爫���Ȃ��������ˁB���́A�䂤�ׂ���₽��Ə������ĂˁA�x�݂Ȃ��Œ������Ƒ�������Ă݂����B�܂�ŏ���̂Ɏd�|����ꂽ�݂������c�c������I�@���ӂ��낪�A���Ă����ȁA���ӂ���̔n�Ԃ����ւɎ~��ƁA�������ł����킩��v �_�[�V���͔ނ̎�����B �u�_���܂����Ȃ����������炨�~�����������܂��悤�ɁA�����ČĂ�ł��������A�������������킽�����Ă�ł��������I�v �u�ӂ�A�ڂ��̈������ȂI�@�ق�̂����ۂ��ȁA�����Ȃ炵���A�ᜂ�݂̏������ŁA���܂��ɕ@���ׂ܂łЂ����ł������Ȃ����B�����ǁA�_�[�V���A���݂͂܂����������������˂Ă���ˁH�v �ޏ��͋�ɂƔ������߂Ĕނ����߁A�ˌ��̂ق����������B �u�҂Ă�I�v�ŁX�������Ɋ���䂪�߂āA���̂����납��ނ����B�u�������c�c����A�v����ɂ��������c�c�킩�邾�낤�A�܂�A�������ڂ����������֏o�����āA���̂��Ƃł��݂��ĂƂ�����A���݂͋������̂��̂��Ƃł����Ă���邩���H�v �ޏ��͐U�Ԃ�������A�����悤�Ƃ������A��𗼎�ŕ����ďo�Ă������B �u�������̂��Ƃł�����ȁI�v������Ǝv�Ă��Ă����Ԃ₢���ނ̊�ɁA���Ƃ킵���Ȍy�̂̕\����B�u�t�Y���Ō�w���I�@�ӂށI�c�c�����Ƃ��A����ɕK�v�Ȃ̂͂���Ȃ̂��������v�i�w����x��@P458-463�j
http://yokato41.blogspot.jp/2014/02/blog-post.html
|
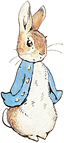
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B