| Tweet |
(回答先: 【非処罰プロジェクト:死刑廃止を超えて3-①】のアーカイブに添えて 投稿者 如往 日時 2008 年 1 月 28 日 02:56:48)
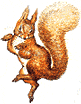
2006-07-21
第二部 死刑廃止の政治過程(一)
【1】序説
第一部では、死刑廃止論の新たな根拠付けについて、これまでの廃止論の論拠を再検討に付しつつ、やや抽象度の高い議論を展開してみたのですが、第二部では、より政治的な角度から、実際に死刑廃止はどのようにして可能であるのかを探求してみたいと思います。
このことは実際、死刑廃止論を採る者にとっては非常な関心事であるはずであって、いったい、他国ではどのようにして死刑廃止は進行・実現していっているのか、それにひきかえ、この日本ではまるで動く気配もないのではないかとため息も出るわけです。
この点では、近時、死刑廃止運動のメインストリームで起きている代替刑論の提案行動が注目されます。これは、要するに、死刑制度を廃止する代わりに、又は当面は廃止することなく、死刑に匹敵する代替的刑罰(多くは仮釈放なき終身刑)を制定して、死刑存置論者を説得せんとする取引的試みであり、かなりの支持もあるようです。注1
このような提案についてどう考えるかも大切ですが、この第二部ではこうしたいわば静態的な制度論的考察にとどまらず、実際に死刑廃止へ向けての動態的な政治プロセス的考察、つまり、実際にいかなるファクターが作用し、またいかなるアクターがいかに行動して死刑廃止へと実現するのかというダイナミズムを考察対象とするのです。
いまダイナミズムと言いましたが、これは決して大袈裟なことではなく、実際、死刑廃止とは、ある日突然惹起する出来事であるわけではありません。それは、たいてい相当に長いプロセスを経て実現に漕ぎ着ける歴史的なスパンを伴った政治過程であり、廃止へ至るには、様々な社会的・政治的及び経済的要因が作用するばかりでなく、死刑廃止運動のほか、宗教家や法律家、政治家、政党など様々なアクターが関与しつつ、一進一退を繰り返しつつ進行していきます。
たかが死刑という感もありますが、死刑にもいろいろな利害(産業的なものも含めて)が絡まっており、その廃止には激しい抵抗も見られます。政治過程の考察としては、こうした反廃止の力動を作り出すマイナス方向の要素を含めて分析対象とする必要があるでしょう。
死刑は、被害者、法確証、抑止などいろいろな口実(私はこれらを死刑口実と呼びます)によって正当化されますが、煎じ詰めれば国家の最高主権の作用であります。諸国の国家支配層が非常に長い間保持してきた伝家の宝刀であります。注2
死刑廃止論は、そのように歴史的に形成されてきた、そればかりか、民衆の脳髄にも深く刻印されほとんど身体化された権力でもある、そういう国権を奪おうと主張しているわけですから、廃止論者は本来自分がどんなに尖鋭な政治的主張をしようとしているか知らなければならないでしょう。
同時に、国家支配層の見地からみれば、死刑廃止とは、歴史的に保持してきた宝刀を放棄する決断を意味しますから、それには大いに未練がありましょう。出来れば手放したくないのも頷けます。そのために様々な死刑口実を援用します。
そういうわけで、死刑廃止の政治過程は非常に複雑で多くの時に不快な紛議をも含んだプロセスを辿ることが少なくなく、その展望を見通すことはなかなか困難でもあります。
このような分析は、死刑の政治的な分析であり、第一部が主として法理的分析であったのに対して、第二部では相当に生臭い政治的議論も展開されることになります。
また、第一部が、主として死刑囚の皆さんに向けられたものであったのに対して、第二部は―引き続き死刑囚の皆さんに加えて―死刑廃止運動に従事する方々に向けられています。時には忌憚なき批判も展開しますので、頁を閉じたくなるかもしれません。しかし、それは決して悪意からの攻撃ではなく、最近縮退を始めているように感じられる日本の死刑廃止運動に新たな活を入れ直そうという意図からのものなのです。
ここで予め結論的なことを先取りして述べておくと、日本における―というよりも、日本を含めて国連死刑廃止条約成立(1989年)からかれこれ二十年が経過しようとして未だ死刑廃止に至らない諸国における―死刑廃止運動は、すべてある種の民主化闘争の性格を帯びざるを得ないと考えており、その点で、現在の日本の死刑廃止運動には不足な面を感じます。現在の死刑廃止運動は未だ旧来の比較的保守的な社会改良運動の延長線上にあり、民主化闘争という自覚が希薄であるように思われるのです。
もっとも、このことは死刑廃止運動が内在的に持つ歴史的な制約でもあるのですが、そろそろそこから一歩抜け出る必要がありそうです。しかし、現状、少なくとも運動の主流では先の代替刑論の提案に見られるように、これまで以上に穏健なトレードオフ的ないし対案主義的な改良運動の方角へ向かおうとしているようであり、そこに懸念を持ちます。注3
これらに加えて、日本では裁判員制度と呼ばれる大衆の司法参加が予定されており、それが施行される2009年までに死刑が廃止されるかどうか、廃止されないとすれば、この制度は死刑判決に私どもを否でも巻き込むことになるのであり、そうした司法と政治の結節点のような場も設定されてきます。この問題についても、第二部で付随的に議論していく予定でおります。
注1
この代替刑論のイデオローグの役割を果たしているのが、菊田幸一であり、最近の著書『死刑廃止に向けて―代替刑論の提唱』(明石書店)はその集大成である。
注2
この点、ジャック・デリダも「主権者の主権に異議を唱えたりそれを制限したりすることなしには、死刑を根底的に、原理的に、無条件に検討しなおすことはできません。」と述べ(ジャック・デリダ&エリザベス・ルディネスコ/藤本一勇・金澤忠信訳『来たるべき世界のために』(岩波書店)208頁)、主権原理との対峙を強調する。それは、同時に「原理」だけの問題ではなく、国家主権と対決する実践的な政治行動の問題でもあるであろう。
注3
この点、日本の死刑廃止運動の中心的存在でもある安田好弘弁護士の講演「終身刑の導入と死刑廃止」は、近時の運動主流における方向性をコンパクトに整理して叙述しており、その個人的講演としての体裁にもかかわらず、ある種の綱領的意義を持つであろう。『年報・死刑廃止2005』(インパクト出版会)所収106頁以下参照。
2006-07-30
第二部 死刑廃止の政治過程(二)
☆前回記事
【2】死刑廃止のプロセス①
第2章では、死刑廃止がどのようなプロセスで進んでいくのかを考察します。その際の視点として、まずは歴史的・通時的な観点から見てみたいと思います。
そもそも死刑廃止とはどのようにして始まり、また現在どのような現象であるのかということが課題となります。
死刑廃止と言えば現在では社会運動を想起しますが、元々は啓蒙専制君主による制度改革として始まりました。
世界で初めて主権国家として死刑を廃止したのが、イタリア中部にあった自治国家・トスカナ大公国であるとされます。これは、当時の啓蒙的なトスカナ大公レオポルド一世(神聖ローマ皇帝としてはレオポルド二世)があのベッカリーアを新刑法編纂委員会の委員長に招き、実現されたものでした。同国では、1774年から死刑執行停止(いわゆるモラトリアム)に入り、1786年公布のトスカナ刑法典で正式に死刑が廃止されたのです。
残念なことに、民衆暴動をきっかけに、数年後には死刑は完全復活してしまうのですが、それでも、同国では復活後も死刑の執行はほとんどなされることはなかったとされます。
次いで、啓蒙専制君主の典型像とも言われるオーストリアのヨーゼフ二世(レオポルド二世の兄)は、トスカナでの経験に注目し、二度の秘密王令により死刑判決を原則恩赦とするモラトリアムの後、1787年に死刑を廃止しています。残念ながらこれも二代後のフランツ二世により覆され、死刑は復活してしまいますが、同皇帝自身、死刑の必要性を明示した勅令の中で、死刑廃止後も犯罪件数が増加していなかったことは認めざるを得ませんでした。
そのほか、ベッカリーアの著作の影響を受けたスウェーデンのグスタフ三世なども原則的な死刑廃止を打ち出したほか、ロシアのエリザベータ・ペトロヴナ女帝は、ベッカリーアの著作が出る以前に即位の宣誓で死刑のモラトリアムを宣言していました(これも、後継者のエカテリーナ女帝によって覆されてしまいます)。注1
このように死刑廃止の最初の起動力となったのは、いずれも啓蒙専制君主と呼ぶべき王たちであり、それは基本的に王の権威による上からの政治指導の結果として起きたことでした。言い換えれば、下からの民衆運動や、まして革命運動の結果ではなかったということは重要です。
むしろ、スウェーデンなどでは当時の農民層は死刑廃止に反対し、またドイツでも1848年のフランクフルト国民会議が原則的な死刑廃止を打ち出したのに対して、死刑存置を求める民衆運動が起きたりしているほどでした。注2
このように、思想でなく、現実の政治現象としての死刑廃止の出発点は体制内改良にあったということ、このことが死刑廃止の歴史的性格を基礎付けることになります。
実際のところ、啓蒙専制君主による死刑廃止はそう多かったわけでもなく(むしろ例外的)、啓蒙君主そのものも次第に消えていきますが、爾後19世紀から20世紀前半ころにかけての死刑廃止は比較的保守的な改良主義の知識人・政治家らがその主力となった啓蒙運動として展開され、またその枠内で死刑廃止が実現されてもいきます。注3
アメリカでは、1822年における革新的なリヴィングストン刑法典が死刑廃止を打ち出していましたが、これはまだ実現するに至りませんでした。その後、ニューヨーク・トリビューン紙創設者であったホラス・グリーリーが死刑廃止運動の先陣を切り、1845年には死刑廃止協会が設立され、爾後、1846年のミシガン州を皮切りに幾つかの州で死刑廃止の動きが続いていきます。注4
第一部で紹介したフランスのヴィクトル・ユゴーもまたそうした改良主義的知識人としてフランスで死刑廃止を熱心に唱道したわけですが、フランスでは1981年に至るまで死刑廃止は起きなかったことも周知の通りです。
日本はどうかと言えば、現在知られている限り、明治維新以前に死刑廃止を唱えた人は存在しなかったようですが、注5 明治時代の後半期になって、四度にわたり死刑廃止法案が提出されています。この頃の廃止運動の中心は行刑職員や弁護士でした。注6 遅れて近代化の波に乗った日本では、行刑職員など政府部内の開明的な層と在野知識人の啓蒙運動として死刑廃止が起動されたようです。
この傾向は戦後にも受け継がれ、検事出身の正木亮が音頭を取って死刑廃止の啓発に尽くした「刑罰と社会改良の会」に代表されるように、日本の死刑廃止運動では、保守的な社会改良主義としての性格が一段と濃厚に認められるのです。注7
こうして19世紀以降においては、啓蒙君主のように上からの権威的な形での啓蒙に代わって、より下からの死刑廃止運動が発生してくるわけですが、ここでもやはり、その基本は改良的保守主義とでも呼ぶべき立場にありました。その点では、上からの啓蒙という性格をも依然残しています。
ただ例外として、1917年のロシア革命時における死刑廃止が挙げられるかもしれません。しかし、残念なことには、世界で初めて刑罰を持たない革新的刑事法となった1922年の法で革命防衛のための保安措置として「銃殺」が復活してしまい、その後はスターリン治下での大量粛清に繋がっていったことはあまりに有名でしょう。注8
ところが、20世紀後半以降になると、今度は「人権」というものがクローズアップされます。20世紀前半における革命戦争や世界大戦での夥しい人的犠牲、体制護持のため死刑を多用した全体主義の経験への反省として、人権の価値が国連を中心に強く押し出されます。ファシズムの経験を持ったドイツとイタリア(戦時犯罪を除く)では戦後いち早く死刑が廃止されます。注9
20世紀後半以降の死刑廃止の特徴として、人権の価値の強調と同時に、民主化に伴って死刑廃止が起きることが挙げられます。ドイツやイタリアはその先陣でしたし、軍事独裁者フランコの死と共に民主主義が回復されたスペインでも1978年に死刑廃止が起きています。ポル・ポト派支配下で大虐殺を経験したカンボジアは死刑に否定的な国連主導の国家再建という事情もあり、アジアではいち早く死刑が廃止されました(1989年)。注10
また、1990年代以降、死刑廃止の動きが最も加速したのは、この間に民主化が進展した東欧と旧ソ連圏(ロシアはモラトリアム中)、そしてアフリカ地域ですが、これは死刑廃止が民主化に伴って生じる最近の特徴の証しとなっています。
このように20世紀以降の死刑廃止現象は、単なる啓蒙とか改良とかを超えて、人権と民主主義という価値を実現する一つの象徴的な出来事として現れるようになっていると言えます。それを後押ししているのは、国内外の人権運動体と共に、それと連携するより深化した死刑廃止運動です。注11 今日の運動はもはや一部知識人のみの社会改良運動にとどまらず、国境を越えた世界規模の社会運動に育ってきています。注12
同時に、政治構造の変動をきっかけとする死刑廃止が増えているのも事実です。しかも、それはロシア革命のようなドラスティックな政治変動ではなく、多くは合法的で民主的な結果を伴う政治構造の変化です。1981年のフランスのように変化の度合いはより小さいものの、民主的な政権交代を契機として死刑廃止が起こる例もあります。
こうした動きをいっそう後押しするのが、1989年の国連条約による死刑廃止の決定であり、また死刑廃止を加盟条件と位置づけるEUなどの外交的な攻勢であります。こうした国際的な死刑外圧とでも呼ぶべきものの生起も20世紀後半、とりわけ過去20年ほどの間の大きな特徴です。これは言ってみれば、国際法が人権の領域にも及んできた現代における一つの啓蒙的な力の再発現であるかもしれません。
こうした傾向は今後も一段と強まると見られ、21世紀の死刑廃止現象は、ますますもって、人権を武器とした民主化、また民主主義の深化を目指す社会運動としての性格を強めていくであろうと予測されます。このことはまた、死刑廃止運動の政治的なスペクトラムを、伝統の改良的保守主義から、自由主義的(リベラル)左派辺りにまで広げ、さらにはより急進的な左派にまで浸透することを促進していくであろうと思われます。
注1
ここまでの記述はジャン・アンベール/吉原達也・波多野敏訳『死刑制度の歴史』(白水社)67頁以下を参照。
注2
前掲『死刑制度の歴史』98-99頁参照。なお、この点では現代のいわゆる世論調査で死刑の「支持率」が高いことは、このように民衆レベルではなお死刑が愛好されやすいことを示唆している。
注3
他に最初期の死刑廃止の例としては、幾つかの南米諸国やポルトガル、オランダなどのほか、後に復活するとはいえ、イタリアも挙げられる。前掲『死刑制度の歴史』94頁以下のほか、法学セミナー増刊『死刑の現在』(日本評論社)87頁も参照。
注4
死刑が19世紀中に廃止された米国の州としては、本文で述べたミシガン州を皮切りに、ロードアイランド州(1852年)、ウィスコンシン州(1853年)、メイン州(1887年)があり、この四州は現在に至るまで死刑は復活していない。『年報・死刑廃止2003』(インパクト出版会)63頁参照[大山武執筆]
注5
ただ、本居宣長は死刑慎重論を開陳したことがあった。村井敏邦『民衆から見た罪と罰―民間学としての刑事法学の試み』(花伝社)第二話「『おそろしや』鈴ヶ森―死刑の残虐性」参照。
注6
明治時代の死刑廃止法案上程は、1901年、1902年、1903年、1907年と短期間に四たびなされている。『年報・死刑廃止96』(インパクト出版会)151頁参照。
注7
正木亮については、法学セミナー増刊『監獄の現在』(日本評論社)196頁以下参照[関哲夫執筆]。また、1956年の死刑廃止法案上程時における参議院公述人としての正木発言については、『年報・死刑廃止2002』(インパクト出版会)166頁以下参照。なお、明治期から正木亮に至るまでの日本における死刑廃止運動の行刑史的概観として藤岡一郎「日本行刑史の中の死刑廃止の思想と闘い」(法学セミナー増刊『死刑の現在』(日本評論社)197頁以下所収)も参照。
注8
前掲『死刑制度の歴史』108-109頁参照。
注9
同じくファシズムを経験した日本では戦後死刑廃止がなされなかったのは、戦後改革を占領下で主導した米国が死刑廃止に消極的であったことも影響しているのであろう。
注10
これより先、フィリピンではマルコス独裁体制を倒した1986年の革命を契機に翌87年に死刑廃止がなされたが、その後治安確保を名目に93年に復活した。その後執行も再開されていたが、2006年6月に再び廃止された。これについては、アムネスティ資料「フィリピン:死刑廃止」を参照。http://www.incl.ne.jp/ktrs/aijapan/2006/0606070.htm
注11
かねてより死刑廃止に力を入れているアムネスティ・インタナショナルを始め、日本でも国連死刑廃止条約の成立を機に結成された死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90の活動が死刑廃止運動の一つの転機となっている(ただし、後に述べるように筆者はフォーラム90に批判的である)。アムネスティのホームページ、特に「死刑廃止info!」は有益なサイトである。http://homepage2.nifty.com/shihai/
なお、上記フォーラム90の結成経緯については、座談会「徹底検証・死刑廃止運動―死刑廃止へ向けてどうするか この五年間の歩みと展望」(『年報死刑廃止・96』(インパクト出版会)106頁以下所収)を参照。ホームページはhttp://www.jca.apc.org/stop-shikei/index.html。
注12
2001年にストラスブールで開催された第一回死刑廃止世界大会の宣言に基づき、2002年にはローマで死刑廃止世界連盟(World Coalition against the death penalty)が設立された。ホームページは、http://www.worldcoalition.org/index.htmlまた、その設立総会出席の記録として 田鎖麻衣子「死刑廃止世界連盟の設立総会」(前掲『年報・死刑廃止2003』248-249頁も参照。
2006-08-04
第二部 死刑廃止の政治過程(三)
☆前回記事
【2】死刑廃止のプロセス②
この章では、死刑廃止のプロセスを共時的に見た場合に、そのプロセスにおいてはいかなるファクターがいかに働くのかということを検証してみたいと思います。
この点、まず、ごく大雑把に大別してみると、死刑廃止のプロセスにおいて作用するファクターとして、A政治指導 B体制変動 C国際外圧の三つを区分できます。
ところで、前回も述べたことですが、政治現象としての死刑廃止は元来、啓蒙専制君主による体制内改良から始まり、その後も体制内外の改良主義的な保守的知識人の社会啓発運動が起動力となったのでした。こうした意味からも、死刑廃止においては政治指導というファクターは非常に重要な要素を担っています。
日本でしばしば引証されるフランスの例でも、左右の政権交代という体制変動の要素もありましたが、その中にあっても、ミッテラン大統領自身の政治指導のもと、死刑廃止運動で名高かったロベル・バダンテール弁護士が法相に抜擢され、世論調査結果では死刑存置派が上回っていたにもかかわらず、死刑廃止に踏み切っているわけです。注1
また、英国では、19世紀から、政府主導で徐々に死刑制度の縮小が続けられてきたのですが、20世紀に入って、重大な死刑冤罪事件の発覚をきっかけとして、注2 死刑制度見直し論議が高まったのに乗じて、政府が死刑制度の調査を進め、1969年に通常犯罪での死刑廃止を実現したのでした。ここでも、世論の支持は芳しくなく、北アイルランド独立派のテロという治安問題もあって、その後、死刑復活法案の提出が何度かありましたが、いずれも失敗に終わっているのです。
また、国連死刑廃止条約の成立以降、条約を批准して死刑廃止に至る諸国が次第に増えていますが、これらも、条約批准という手続きの性格上、ほとんどは政府(又は議会)主導型の経緯をたどっているといってよいでしょう。世論調査で死刑廃止派が多数になったとか、死刑廃止要求デモが活発化して政府が押されて死刑廃止に至ったというような国は皆無ではないでしょうか。いずれも、政治指導の成果として、廃止が実現しているわけなのです。
ただ、ここでは、デモクラシーのあり方との関係で論点が生じるでしょう。政府が世論の多数意思に服従することをもってデモクラシーの本質だと解するならば、世論に反する政治政策は反民主的だということになるわけです。米国や最近の日本では、こうした議論がしばしば幅を利かせるようです。
日本政府なども、死刑問題では、事あるごとに死刑存置派が大多数を占める内閣世論調査の結果を持ち出して、それをあたかも国民投票の結果であるかのように見せかけています。しかし、こうした世論調査偏重のやり方は、「世論」なるものの曖昧さともあいまって、デマゴギッシュであることは否めません。この点では、本書でしばしば引用してきたフランスの法制史家、ジャン・アンベールも言うように、「死刑廃止に向かったのは、理性によって啓蒙された・・・・・・指導者たちだったのであり、トスカナ大公やオーストリアのヨーゼフ二世から現代の国会議員たちに至るまで、しばしば国民全体の意向に逆らってまでもそのようにした人びとなのである。」そこから、アンベールは、「民主主義というものは、選ばれた国会議員たちが選挙民たちの意向に添うことにあるのだろうか」という重い問いを投げかけて稿を閉じているのです。注3
この問いに関して、ジャック・デリダは、「議会制民主主義は世論にではなく選ばれた多数派に従うもの」という回答を与えています。注4 この問題については、デモクラシーに関する原理的側面から再度改めて検討してみたいと思いますが、さしあたり結論的に言えることは、デモクラシーにおいても、適宜適切な政治指導は否定されないどころか、非常に重要だということであります。とりわけ、死刑廃止のように、一般大衆を味方につけることがなかなか困難な課題を実現するには、政治指導が不可欠なのです。
たしかに現代のデモクラシーの中で、政治指導者が啓蒙専制君主として振舞うことはできないでしょう。しかし、「啓蒙的指導力」は発揮されねばならないのです。そうした役割を、さしあたり議会という合議機関に期待せねばならないという点に難しさはあるのですが、死刑廃止のような「票にならない」課題で、議会指導部が政治指導力を発揮できるかどうか、これこそ、議会制の質に関わってくることなのです。この点で、日本や米国の議会は、決して芳しい実績を示していないようです。注5
さて、前回も、20世紀後半以降では、体制変動、特に民主化に伴う死刑廃止が目立つと指摘しました。この体制変動というファクターも細分化すれば、a革命による場合 b敗戦による場合 c政権交代による場合とを区別できます。
まず、革命による場合としては、古くはロシア革命時、最近ではフィリピンのマルコス独裁政権を倒した1986年の「ピープル・パワー」直後の死刑廃止などがあります。ただ、このような非合法的な体制変動による場合には、しばしば死刑廃止は一時的なものにとどまりやすいようです。
ロシア革命の時は、1917年から5年間は死刑が廃止されていたのですが、その後、復活し、結局、ソ連解体まで廃止は実現しませんでした(現在も、廃止に至らないままモラトリアム状態にある)。フィリピンの場合も、革命で成立したアキノ政権時代の87年憲法で死刑廃止を明示したものの、議会決議による死刑復活の可能性を残した妥協的規定であったため、その後、治安確保等の観点から、後継のラモス政権時代の93年には早くも復活してしまいました(その後、2006年になってアロヨ政権で再び廃止)。
実際のところ、革命で死刑が廃止されることはあまり多くなく、近年では1989年のルーマニア革命がその一例かもしれません。ただし、ここでは、「最後の処刑」として、革命で打倒された独裁者・チャウシェスク大統領夫妻が杜撰な即決軍事裁判で銃殺刑に処せられ、その様子がテレビで放映されて世界に衝撃を与えるという経緯もありました。
これを見るに、革命的熱狂の中で、旧体制への反感から死刑廃止機運が高まっても、革命の道義的正当性を強調するため、あるいは革命後の新体制維持の必要性が死刑復活を要求してしまうようです。そのためか、中国やキューバ、イランなど、革命で成立した政権が今日まで永続化している諸国の多くは、むしろ強固な死刑存置国を成しているわけです。
一方、敗戦による場合は、広い意味で政権交代による場合に含め得るのですが、ドイツとイタリアという重要な二つの先例があるため、あえて別立てで考えてみたものです。この両国では、いずれもファシスト体制下で死刑が政策的に乱用されたことへの強い反省から、敗戦後の民主化過程で死刑廃止が重要な政治課題となり、迅速に廃止がなされました。ドイツでは、周知のとおり、憲法上、死刑廃止が規定されたのでした。
しかしながら、同じ敗戦を契機に軍国ファシズム体制から民主的転換が行われた日本の場合、死刑は廃止とならなかったのです。これには、連合軍の意向もあったと見られていますが、注6 このことは、日本の体制転換が占領統治下で受動的に実行されたことの証左でもあるでしょう。
ちなみに、2003年のいわゆるイラク戦争―あのような一方的軍事策動をなお「戦争」と呼び得るとして―では、日本とは逆の事態が生じ、米英占領当局は死刑のモラトリアムを導入したのですが、これは、日本占領当時と異なり、国連が明確に死刑廃止の立場であることや、やはり明確な死刑廃止政策を保持するEUのメンバーで自身も死刑廃止国である英国の意向を受けての措置であったと見られます。しかし、これも、政権を引き継いだイラク暫定政府によって覆され、死刑は復活されました。フセイン元大統領ら旧政権幹部を死刑に処するという政治的意図が指摘されています。注7
なお、厳密には敗戦ではありませんが、凄惨な内戦が終結した後、国連主導のもとに国家再建がなされたカンボジアでも、死刑が廃止されました。ここでは、クメール・ルージュ独裁下での大量粛清の経験が影響しているかもしれませんが、そうだとすると、これは、ドイツやイタリアと類似した事例ということになるかもしれません。注8
次に、政権交代による場合とは、普通にイメージされる合法的選挙を通じた政府構成の変動の場合のほか、非暴力的な体制変動の場合をも含みます。
前者の例としては、フランスのミッテラン社会党政権発足に伴う死刑廃止やフランコ死去後のスペイン民主化に伴う死刑廃止が挙げられるでしょう。これらは、合法的に行われたとはいえ、単なる政策面だけの政権交代ではなく、相当ドラスティックな政治構造の変動を伴う政権交代であったため、一つの変革の象徴として、死刑廃止が後押しされたと見ることができます。
後者の例としては、1990年代以降に進展してきた東欧や旧ソ連圏、ブラックアフリカ諸国の例があります。こうした地域では、この間、旧来の独裁的な体制が退場し、民主主義の定着が顕著であり、それに相伴って、死刑廃止も実現しています。その際、国連やEUの死刑廃止議定書の批准という形で、政府主導の死刑廃止が採られることの多いのが特徴で、その点では、先に述べた政治指導というファクターも相当に作用しています。
いずれにせよ、こうした体制変動に伴う死刑廃止は、死刑を多用する権威主義的体制からの変動期―総じて言えば、民主化移行期―によく見られます。この点で、フランスの死刑廃止例は最も穏やかな政権交代に伴うものですが、1981年のミッテラン社会党政権成立という出来事は、その後、同政権が支持者らに与えた失望にもかかわらず、フランス政治史では画期的出来事であって、従前ド・ゴール政権以来の保守権威主義的政治風土からの転換点になった―少なくとも、そうなると期待はされた―という意味で、やはり体制変動の要素は認められたといえるでしょう。
最後に、国際外圧ですが、これは、国連死刑廃止条約を始め、死刑廃止が条約上規定されるようになって以来高まっている新しい要素です。注9
例えば、トルコでは、外交政策として、EUへの加盟を悲願としてきましたが、EU加盟条件として死刑廃止が課されるため、嫌でも死刑廃止を行わなければならない責務が生じたのです。ただ、クルド人過激派によるテロという治安問題を抱えていることから、紆余曲折はありましたが、注10 モラトリアム期間からEU人権条約議定書の批准を経て、2004年に死刑は全廃されました。この例は、国際外圧が死刑廃止の決定打となった未だ稀有の事例として記録されるでしょう。
ただ、国連加盟国が国連死刑廃止条約を批准する形で廃止に至る場合、この条約はその本体部分である国際自由権規約の改正を目的とした選択議定書という形式を持つため、条約を批准するかどうかについては各国の選択権があり、批准の法的義務が生じるわけではなく、国連の加盟資格にも何ら影響しないことから、同条約の圧力は、EU条約と比べても弱いのです。
もう一つ、死刑存置国への逃亡容疑者引渡し拒否という外圧があります。これについては、国連の条約でも規定がありませんが、EUの犯罪人引渡し条約や、将来EU憲法条約に組み入れられる予定であるEU基本権憲章に定めがあるほか、国内法で定めを持つ国もあります。
この点で、日本は既にそのような国内法規定を持つスウェーデンとの関係で、外交問題を起こしています。日本国内での殺人容疑で手配中の逃亡犯がスウェーデンに潜入したため、同国に身柄引き渡しを求めましたが、死刑が科せられないことの公式保証を同国政府から要請されたため、引渡し請求を断念し、結局、同国で裁判が代行的に行われることとなったのでした。注11
現在でも、死刑存置論者の中には、死刑は国内の主権問題だとして、こうした国際外圧を批判する向きがありますが、前回も述べたように、死刑が普遍的な人権の問題として認識されるようになり、地球上のほとんどの諸国をカバーする国連の条約でも規定されるに至った現在、死刑という問題はもはや一国だけの国内政策問題ではなくなったのであり、国連条約の成立はそうした死刑=主権ドグマを崩す画期点でもあり、また、身柄引渡し拒否条項もいずれ死刑廃止国全域に広がるでしょうから、死刑問題は嫌でも外交問題の一角に席を占めるようになったのです。トルコの死刑廃止はその象徴的事例に過ぎません。
ただ、国際外圧がトルコのように決定打となることは珍しく、これは地理的にアジアと欧州の境界域に位置する同国独自の「脱亜入欧」政策とも関連しています。しかし、日本や米国がオブザーバー国である欧州評議会では、両国が迅速に死刑廃止に踏み切らない場合、オブザーバー資格を見直すという通告を発しており、もしその通りになれば、両国は外交上不名誉な扱いを受けることとなります。注12
以上見たとおり、死刑廃止のプロセスにおける作用因としては複数あり、どれがどう作用するかは諸国で違っているわけですが、基本的に政治指導は非常に重要であるということ、そして、その政治指導を補強し、俗に言えば追い風となり得るのが、政権交代を含めた体制変動という政治環境の変化であること、そして、近時は、これに国際外圧という新たな要因が加わってきていること、これらのことが理解されると思います。
その際、政治の民主化が進展するとともに、18世紀の啓蒙専制君主の如く、君主の個人的な思いつきで単純な政治指導による死刑廃止が実現することはなくなり、体制変動、特に、民主化という要素が重要性を帯びていることは留意されるべきです。そのため、死刑廃止運動も単に「社会改良」の域にとどまることができなくなっており、それは、一種の民主化闘争の色彩を帯びてくるのです。日本のように死刑廃止運動の改良運動的性格が濃厚なところでは、特にこの点を念頭に置く必要があるでしょう。
一方、国際外圧はそれだけで廃止が実現するというほどの決定力ではないとしても、非常に有力な側面支援効果を持つ要素となっています。今や、国際外圧を意識せずに死刑を存置し続けることのできる国は、一つもないと言ってよいからです。日本政府が、国連条約成立以降、それ以前にもましてことさらに「世論調査結果」を特筆大書して死刑存置を根拠付けようと躍起になっていることも、そのことの証しであると言えないこともないのです。注13
注1
フランスの死刑廃止の経緯については、伊藤公雄・木下誠編『こうすればできる死刑廃止―フランスの教訓』(インパクト出版会)を参照。
注2
英国における死刑冤罪問題については、本書第一部第三章を参照。
注3
前掲『死刑制度の歴史』140頁。
注4
前掲『来たるべき世界のために』225頁。
注5
冤罪の発覚を契機として執行停止中の全死刑囚に一括減刑をして論議を呼んだイリノイ州のジョージ・ライアン知事(当時)は、州議会が死刑制度の改革にいかに消極的であるかを嘆いている。ジョージ・ライアン/梶原絵美・柳下み咲訳「私は本日、全死刑囚を減刑する」、『年報・死刑廃止2002』(インパクト出版会)所収235頁以下参照。
注6
この点について充分論じた文献が見あたらないが、さしあたり、田中伸尚「「大逆罪」の存続を切望した吉田茂」、セミナー増刊『死刑の現在』所収173頁参照。マッカーサーは死刑存置論者であったと見られるとしている。
注7
イラク戦争後のイラクの死刑動向については、辻本衣佐「死刑廃止に向けた国際的動向2004」、『年報・死刑廃止2005』(インパクト出版会)所収144-145頁参照。
注8
ナチスやクメール・ルージュの大虐殺のような事態は、本来「死刑」に当たらない。それはまさに大量粛清であり、その実体は犯罪行為そのものである。しかし、それらが「合法」の衣を纏って行われる限りにおいては、「死刑」と同様な発現をしてくるのに過ぎない。
注9
現在、死刑廃止を定めた国際条約は、国連条約を含めて四本ある。国連条約以外では、欧州人権条約第六議定書及び第十三議定書、米州人権条約死刑廃止議定書である。このうち、あらゆる状況における死刑廃止(死刑全廃)を定めるのは、欧州人権条約第十三議定書のみである。
注10
トルコの死刑廃止では、クルド人過激派の首領、オジャラン氏への死刑判決がネックとなっていた。これについては、桑山亜也「死刑廃止に向けた国際的動向1999-2000」、『年報・死刑廃止2000-2001』(インパクト出版会)所収190-191頁参照。
注11
この件については、岩井信「死刑廃止に向けた国際的動向1990→1995」、『年報・死刑廃止1996』(インパクト出版会)274頁参照。
注12
欧州評議会の議員会議は2001年6月、日本及び米国が2003年1月までに死刑の執行を停止し、死刑廃止に向けた措置を取らない場合には、欧州評議会全体における両国のオブザーバー資格を問題にする旨の決議を採択した。駐日欧州委員会代表部「EUと死刑」参照。http://jpn.cec.eu.int/union/showpage_jp_union.death_penalty.php
注13
日本政府の死刑世論調査は、かつては不定期であったが、1989年の国連条約成立直前回以来、五年ごとに実施されるようになった。
2006-08-17
第二部 死刑廃止の政治過程(四)
☆前回記事
【3】死刑廃止におけるアクター①:議会・政党
本章では、死刑廃止のプロセスにおいて働く個々のアクターについて検討してみたいと思います。初めはまず、議会・政党です。
既に見たように、死刑廃止のプロセスには、革命などドラスティックな体制変動による場合もあったわけですが、ここでは議会制民主主義の枠内で死刑廃止が実現されるという想定のもとで考えてみた場合、やはり何と言っても、死刑廃止は議会(以下、特に断りのない限り、議会と国会を同じ意味で用いる)、しかも、その不可欠の要素である政党が決定的アクターとして作用してきます。
日本の場合に即してみれば、死刑廃止の方法として、死刑廃止は刑法改正によらねばなりませんので当然議会の多数決を要します。一方、国連条約を批准することは内閣の権限ですが、その場合原則として国会の事前承認が必要となります(憲法73条3号)。いずれにしても、議会の議決が不可欠です。それなくしては死刑廃止は不可能であるというほどの条件です。
そこで議会の指導的役割には期待がかかるわけですが、ここで前回も述べた世論との関係如何が問題となってきます。議会は世論の多数意見に追随すべきであるのかどうかという問題です。
結論からいけば、議会における多数決とは、世論の多数派ではなく、あくまでも国民代表機関である議会における多数派の意思決定を意味しています。このことは、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と規定する憲法43条が含意しているとされる自由委任原則からみても当然です。つまり、代議士は、ひとたび選挙されれば議場での行動に関して個々の支持者はもちろん、世論の拘束も受けることなく、自由に自らの良心に従って討議・表決すべきなのです。ドイツ憲法38条には「かれら(連邦議会議員)は、全国民の代表者であって、委任又は指令に拘束されることなく、その良心にのみ責任を負う。」という明文もありますが、日本国憲法においても43条のほか「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」とする51条もこのような趣旨を含むと解してよいでしょう。
従って、国会議員は世論調査結果に拘泥することなく、自由に死刑廃止について討議し、廃止の表決をしてもよいということになるのです。そうすると、フランスを始め、多くの諸国でそうであったように、世論調査結果に反してでも、国会の良心的決定として死刑廃止を実現することは何ら民主主義に反しないばかりか、むしろ議会の啓蒙的指導力の発現としてそれこそが期待されることなのです。
これを要するに、死刑廃止における議会の役割とは、世論に働きかけて死刑廃止論を多数派に押し上げるといういわば量的多数派を形成することではなく、議会内での多数派形成を工作していわば質的多数派を構築することにあると言えましょう。
これは、ある意味ではエリート名望家政治の表現でもある自由委任制の然らしめるところでもあって、これを自由委任制の政治指導機能と呼ぶこともできます。この点では、かつての啓蒙専制君主の働きに近い面もあります。もちろん、啓蒙専制君主はいくら啓蒙的であれ、「専制君主」に変わりありませんから、議会討議など無視するわけで、この点では議会制民主主義とはかけ離れていますが、政治指導という点では共通性があるわけです。
ところが、こと死刑廃止に関しては、おうおうにして国会議員はこのような質的多数派を構築することに非常に臆病です。これはどうしたことでしょうか。
その秘密はやはり選挙でしょう。いくら自由委任だといっても、選挙戦に勝利しなければ仕方がないわけで、その選挙ではどうしても世論の多数派からの支持調達ということが至上命題となりやすいのです。注1 それで、議員たちは、常に世論調査の多数意見は何であるかに敏感になるわけです。簡単に言えば、世論調査の多数意見に近い線で「公約」をまとめておくのが一番無難であるからでしょう。そうすると、死刑廃止など極少数意見を公約に掲げる勇気などとても出せないということになる。このことは選挙制議会の性質上理解できなくもないのです。注2
ですから、非常にリアルな「選挙戦術」というレベルで考えてみると、死刑廃止などは選挙戦の直接的争点には立てないほうがよい、もっと言えば、その問題は隠してでも別の争点で競うほうがよいということにさえなるでしょう。このような作戦は、死刑廃止のように、先の量的多数派という点では望み薄であるようなイシューにあっては、一つの秘訣になるでしょう。注3
もう一つ、議会の指導力を左右する要素として、政党制があります。すなわち、現代議会では政党の政策決定という憲法には必ずしも明示されているとは限らない決定プロセスが不可避であるところ、政党のイデオロギー分布状況が死刑廃止にもかなり色濃く反映されてくるという事情に関わってきます。
ここで大雑把に政党イデオロギーと死刑廃止の親和性を図式的に述べてみると、こうでしょう。まず、死刑廃止に最も親和性が高いのは、進歩的保守主義とでも呼ぶべき政党です。これは意外にも思えますが、以前に述べたように、死刑廃止は元々改良的保守主義者らがその中核になってきた歴史的事実と符合しています。つまり、伝統墨守でなく、漸進的社会改革を受容する保守主義の一派が死刑廃止の歴史的推進力でした。
この点では、急進的な社会変革を求める革命的左翼は、意外にも死刑廃止には消極か無関心です。おそらく、革命的左翼はその本性上、死刑のようなドラスティックな処罰法に親和的であるほか(しばしば革命運動内部の結束維持のために内部処刑も辞さない)、革命成就後に反革命勢力と闘争する際にも死刑を利用せざるを得ないという計算もあって、死刑廃止には少なくとも積極にはなれないのではないかと思われます。注4
これに対して、武力革命を放棄し、漸進的社会改革を志向する穏健な自由主義的左派になると、これは路線的に進歩的保守主義とも相当程度重なってくるために、死刑廃止のような刑罰改良策には積極的な傾向を見せます。進歩的保守主義と自由主義的左派は、死刑廃止に関する限り、ほぼ等価的でしょう。というより、今日では、フランスがそうであったように、自由主義的左派が死刑廃止では主導性を発揮することも少なくないようです。注5
これに対して、最も死刑廃止に消極なのが保守反動主義の政党であり、時に敵対的でさえあります。かれらは伝統墨守がその身上ですから、死刑制度のような歴史的に古い刑罰については、むしろ積極にこれの存置を主張することになりやすいのです。
以上のような布置状況からすると、現実の議会の議席分布上、最後の保守反動派が優勢であるような場合には、死刑廃止という課題を上程させることは極めて困難になることが判ります。残念ながら、日本の議席状況はこれに近いと言えます。注6 そのため、死刑廃止を議会で討議すること自体に高い壁が出来ているのです。後に詳しく述べますが、私が、日本の死刑廃止の道は、少なくとも政権交代によるしかないだろうと予測する理由の一つがここにあるのです。
さて、ここでいわゆる超党派的議員連携について触れておきましょう。これは、現に日本の国会内にも「死刑廃止を推進する議員連盟」という超党派グループが1994年以来設立されており、2003年には、このグループが「重無期刑の創設及び死刑制度調査会の設置等に関する法律案」なるものを国会へ上程しよういうところまで漕ぎ着けており、その活動はかなり活発です。注7注8
死刑のように高度に論争的なテーマに関しては、こうした超党派でシングルイシューの議員グループを形成することにも意義はあるでしょう。こうしたグループが核とならなければ死刑廃止のような「不人気」な政策はなかなか討議にさえ入れないという事情があるため、このようなシングルイシューでの横断的な一種の会派作りには意義を認めなければならないのです。
しかし、同時に、政党制のもとでは、こうした超党派の議員連携には限界もあります。超党派で法案を提出するにも各議員の所属政党の了承がなければ、実際に上程され、審議・議決まで至ることは事実上不可能に近いからです。これは国会をもって唯一の立法機関と宣する憲法上の建前(憲法41条)からすれば奇妙なことではありますが、政党制のもとでは、事実上政党単位で政策立案がなされる構造となるため、必然的に政党レベルの決定に優先権が生ずるわけです。従って、死刑廃止においても、否、このようなかなり大きなテーマにおいてこそ、政党レベルの決定は不可欠であって、超党派議員連携のみで死刑廃止をもたらすことは無理でしょう。基本的には、与党(現与党という意味ではない)の政策としてまずは決定されなければ現実の議決には結実しないのです。
そういう意味で、超党派議員連携の価値を過大評価することには慎重であるべきでしょう。このような連携は現実の死刑廃止の推進勢力というよりは、むしろ各政党内での議論を高めるための橋頭堡、さらには法務大臣の死刑執行への監視・抗議行動や死刑制度全般に対する国政調査、また国連条約の周知徹底など情報提供の部面でその力量を発揮することがより期待されると考えられます。
注1
特に、小選挙区制では一つの選挙区につき一人の当選者ということで、最多得票を得ることが当選への道であるから、なおいっそう多数意見への追従が生じやすい。
注2
ジャン・アンベールは、選挙民の意思に従うことをもって代議士の役割と捉えるアメリカの政治家を「デマゴーグ的」と非難するが(前掲『死刑制度の歴史』130頁)、このコメントはやや酷ではある。むしろ、「世論調査結果」を盾に持ち出す政府や「国民的合意」の欠如を死刑合憲論の論拠に据える裁判所の態度こそ、デマゴーグ的であると言えよう。
注3
選挙において、あらゆる問題を争点化する必要がないことは当然である。
注4
歴史的に著名な例では、フランス革命指導者のロベスピエールがある。彼は、元来死刑廃止論者であったが、革命後には、一転して、当面廃止に反対という立場に回り、周知のごとく、死刑を乱用する恐怖政治の当事者となった。
注5
例えば、自由主義的左派政党の国際組織である社会主義インターナショナルは、死刑廃止への政治的なイニシアティブを取ることを表明している。http://www.socialistinternational.org/7Campaigns/Deathp-e.html
注6
日本の議会政党では、公明党が本文で述べた進歩的保守主義に相応する政党であり、かねてより死刑廃止にも積極的な所属議員が少なくない。しかし、議会内勢力としては、少数派である。他方、民主党も進歩的保守主義に近いと言えるが、必ずしも明確ではない。
注7
議員連盟の設立趣意書については、『年報・死刑廃止96』(インパクト出版会)187頁「資料22」参照。また、本文で挙げた法案全文は、『年報・死刑廃止2002』(インパクト出版会)22頁以下参照。
また、http://www.jca.apc.org/stop-shikei/data/shikkouteishi.htmlにも掲載されている。
注8
同法案は、結局上程に失敗した。主要な理由は、与党・自民党法務部会で強力な反対があったためとされる。先にも述べた議会内における政党分布状況のなせるわざである。簡単な経緯については、http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/shikeimondai/02.html
2006-08-25
第二部 死刑廃止の政治過程(五)
☆前回記事
【3】死刑廃止におけるアクター②:政府
議会制民主主義においては、立法という形で政策の終局的決定権を持つのは議会ですが、政府は依然として政策決定上無視し得ない力を持っています。言うまでもなく、日本の場合には、内閣が政府の意思決定機関ですが(以下、断りのない限り、政府を内閣の意味で用いる)、刑罰政策では基本法制を扱う法務省も内閣の下で強い影響性を保持しています。
ただ、死刑廃止運動の側で、しばしば法務省を死刑存置の主要な牙城として主敵とみなす傾向がありますが、これは要注意です。刑罰政策が専門性を持った領域であり、また代議士らの関心度も低いことからして、刑罰政策面での法務省の影響力には相当なものがあることは否めませんが、実際のところ、法務省といえども内閣の下にある「行政各部」の一つに過ぎず、行政全体の要はあくまでも内閣です。従って、法務省の力能を過大評価することは運動戦術の誤りにも繋がりかねません。
日本国憲法上、内閣には条約批准の権限が与えられています(73条3号)。ですから、内閣が国連死刑廃止条約を締結する方針を固めて、それが国会で承認される公算となれば、法務省はお手上げなのです。一行政官庁には条約批准に関して拒否権などないからです。
国連条約成立以降は、政府主導での条約批准による死刑廃止というこれまでにない有力な廃止プロセスが確立されたのであって、この点で、政府には大きな指導性を発揮する余地があるわけです。ところが一方、日本でも採用されている議院内閣制においては、内閣は通常、議会における多数党派がこれを担います。従って、この多数党派が死刑存置論であれば、内閣としても条約批准のプロセスを主導しないため、動きは出ないことになります。この場合には、政府が死刑廃止を議会に上程させない、争点潰しの妨害アクターとして活動することにもなります。
従来の日本はこういう状態になっており、要するに、内閣を掌握している議会の多数党派である自民党があくまでも死刑存置論である以上、内閣の指導性は期待できないことになります。注1 そこで、法務省を死刑廃止の主敵と見るのは必ずしも適切でなく、与党=支配政党こそが、その支配権維持のため死刑を必要としているのだと理解すべきです。比ゆ的に言えば、法務省などはせいぜい地獄の門番に過ぎません。門番としての強い権限は任されているにせよ、閻魔大王ではないのです。この点を見間違えないようにしたいと思います。
けれども、翻って、国連条約成立以降、政府の役割は重要性を増しており、議会単独での内発的な死刑廃止プロセスの起動が難しい場合には、条約批准から入っていくやり方は有望ですし、これが「正攻法」であるとさえ言えます。この点は後に詳述しますが、国連条約の最大意義は、死刑廃止を一国の政策問題という狭い枠組みから解放し、これを国際社会における共通課題に押し上げ、国際的土俵のうえで解決する道筋をつけたところにあるからです。
この正攻法を踏むうえで、政府の役割には大きなものがあり、プロセスとして見たときの死刑廃止に政府というアクターが一切関与しないことはあり得ないでしょう。しかし、議院内閣制の場合には、内閣が議会の多数派に大きく依存する形になるため、とりわけ多数党派との緊密な連携が不可欠であり、条約批准に当たっても国会の承認が必要ですから、死刑廃止を政策として取りまとめることのできる党派が議会で多数派となって内閣を担わなければならず、結局、現状では政権交代という民主主義なら当たり前のことが実現するかどうかにかかっていると思うわけですが、これについても改めて述べることとします。
さてここでやや視点を変えて、法務大臣の死刑執行命令権について考察します。日本では、死刑の執行は法務大臣の命令によるとされており(刑事訴訟法475条1項)、形のうえでは一大臣の単独権限で死刑執行がなされるという、これまた非常に非民主的な構成です。注2
しかし、この権限を逆手に取れば、大臣が命令を保留し続けることで、事実上死刑執行がなされない状態を長期間継続する、すなわちアムネスティ・インタナショナルの基準でいえば「事実上の死刑廃止」を導くことも可能となるのです。実際、日本で1990年から1993年にかけて死刑執行が「休止」されたときには、注3 合計四人の法務大臣が執行命令を出さなかったわけですが、このうち仏教者としての信条から意識的に執行命令を出さなかったことを明言している左藤恵氏を除くと注4 特に意識的な保留であったという証跡はありません。
それでは、法務大臣が意識的に死刑執行を拒否して「事実上の死刑廃止」を実現するということが果たして許されることなのでしょうか。これは、職務と良心という観点からも倫理学的争点となります。
この点に関しては、法務大臣の死刑執行権限を高度の政治的な権限とみなして、個人の信条、政治家としての政治哲学からの執行保留も許されるという考えもあります。注5 けれども、このように死刑執行を大臣の信条によって左右させることを認めると、逆に死刑を肯定する信条、哲学に基づき、ためらうことなく大量執行するということも認めなければならなくなります。信条によって執行しないことは許されるが、執行することは許されないという理屈は通りにくいでしょう。そうすると、結局、法務大臣は自己の信条のみを理由として死刑執行を保留することはできないということになります。
しかし、正式に死刑執行停止のモラトリアムを宣言するならば別です。モラトリアム法が制定されればこれは法に基づいて執行が凍結されるわけですから、当然執行はできなくなりますが、そのような法律によることなく、政府の宣言によるモラトリアムも認められますから、それで初めて執行保留とすることができるのです。注6
これはやや厳しい見解で、93年に死刑執行を再開した当時の後藤田正晴法相が吐露した考えと似ている感もありますが、注7 私見のポイントは、死刑執行を大臣個人の信条に委ねることは死刑制度を恣意的なものとすること、また、公式のモラトリアムを導くためにも、大臣個人の信条にのみ依存した主観的執行停止ではなく、あくまでも客観的な指針に基づく執行停止を実現したいということにあるのです。
そうすると、死刑廃止論者は死刑制度が存在する限り、法務大臣に就任してはならないのか。前述の後藤田はそういう趣旨まで踏み込んで示唆していたのですが、これは謬論であると思います。しかし、死刑廃止論者であるならば、法務大臣としての最初の仕事として、少なくともモラトリアム宣言発効を取りまとめる決意で就任すべきであり、それが不能な状況であるならば就任すべきでないと考えます。就任したうえで個人的信条のみによって執行保留とすることは許されないと考えますし、まして単なる心情的な執行忌避は違法な責任放棄となります。
かといって、死刑廃止論者でありながら、制度が存在する以上は執行するとして命令を出すことは自己の良心に対する背信であり、やはり一種の責任放棄です。これは違法ではないものの、倫理的な信用失墜行為であって、相応の非難に値する挙措です。
続いて、より深刻なレベル、死刑執行の最前線にいる刑務官は死刑執行職務を自己の信条によって拒否できるでしょうか。もしも刑務官たちが集団で死刑執行拒否をするならば、それは死刑制度のうえに非常に重大な波紋を投げかけ、インパクトは強いでしょう。
ここで重要なことは、そもそも死刑執行の命令ではなく実際処置、つまり死刑囚を死刑台に吊るして殺害することを実際に誰が行うのかにつき、法律は何も定めていないということです。しかし、実務上は、拘置所の刑務官が執行に当たっています。これは、「刑務官職務規程」という命令に基づくものと考えられ、国会が制定した法律ではありません。注8 本来、刑務官の任務は受刑者を抹殺することではなく、矯正することですから、当然のごとくに刑務官が死刑執行業務に当たるべき理由はないのです。しかし、かれらは職務としてそれを押し付けられているのです。
こうした特異な状況下で、従来から刑務官(退職者を含む)の中には、明確に死刑廃止を訴える人もありました。注9 これは、秩序維持に関わる職能の中では異例のことで、類似の職能である警察官や、同じ法務省系列の検察官などには見られない特色です。もっとも、韓国の調査事例では、刑務官の間での死刑存置論の割合が80%台と、検察官と並んで“死刑支持率”が高いというデータもありますので、注10 日本でも大方の刑務官は死刑を肯定しているのかもしれませんが、そうであっても、紛れもない殺人処置である死刑執行を嬉々として行うという人はおそらく稀であり、「死刑執行人の苦悩」は現在する問題なのです。注11
こうした点からみて、刑務官に関しては、良心的執行拒否を正面から認めることをためらう必要はありません。刑務官は、その本来的な職務でない、単に命令で突如として割り当てられる忌まわしい執行処置注12 を拒否できるし、また拒否した者を処罰することも許されません。それは、良心の自由を保障する憲法19条に違反し、また同法18条が禁止する「意に反する苦役」に相当する場合もあるでしょう。刑務官が執行を拒否するということは、たとえそれが単独行動であってもインパクトを持ちます。それのみで死刑廃止への決定打にはならないとしても、そのことは死刑制度史上の記録に残り、制度の不正を告発する材料となります。ですから、それだけに、刑務官の死刑執行業務服従へのプレッシャーは強く、懲戒権を振りかざした脅しがかけられるでしょう。注13
最後に蛇足となりますが、面白い提案があります。それは、死刑執行を無作為抽出で選ばれた市民にさせてみよという挑発的提案です。注14 世論調査で80%が死刑に賛成であるというならば、市民は自ら死刑執行に当たるべきではないか。なぜ、それを刑務官に押し付けるのだろうか。おそらく、市民が裁判に参加する裁判員ならぬ、死刑執行に参加する「執行員」の制度ができれば、死刑廃止の意見が増加するかもしれません。死刑存置論とは、一面、無関心の表現でもあるからです。忌まわしい殺人処置を他人任せにする無関心こそが、死刑制度をあっさりと肯定させるのです。
注1
前章でも紹介した死刑廃止議員連盟の提案した「終身刑導入及び死刑制度調査会設置等に関する法律案」が主として自民党法務部会の大反対によって上程さえされなかった経緯について、亀倉弘美「死刑廃止議連の提案する法案の経緯と顛末」、『年報・死刑廃止2004』(インパクト出版会)所収184頁以下参照。
注2
法務大臣の単独権限といっても、法務大臣が所属する内閣が個々の死刑執行に全く責任を負わないとは考えられない。憲法上、内閣は一般的に「法律を誠実に執行」する権限(責任)を持つほか(73条1号)、恩赦の権限をも持つ(同条7号)以上、死刑執行に関しても一定以上の責任を負うはずであり、閣議において事前に執行の当否を確認することは最低限すべきである。
注3
本文で述べた死刑の「休止」とは、公式のモラトリアム宣言によることなしに、事実上死刑執行がなされないことを言う。
注4
海部内閣で1991年に約10ヶ月間法相を務めた左藤恵氏は、「私は浄土真宗の寺の住職でもありますので、宗教人として人の命の大切なことを人一倍感じている立場からもサインを拒否いたしました・・・」と明言している。この発言からすると、法務省は、死刑が休止していた前記の期間中にも大臣に対して執行命令を具申はしていたことが示唆されている。『年報・死刑廃止96』(インパクト出版会)155頁、「資料6」参照。
注5
「法務大臣の執行命令は、政治家として憲法の理念、取り巻く国際社会の動向、死刑に対するヒューマニズムといった視野の中で判断することが求められる」とする見解もその一つである。佐々木光明「死刑「執行」の論理を問う」、『年報・死刑廃止2000-2001』118頁参照。
注6
法律によらないモラトリアムをどのような形式で発するべきかは難しい問題だが、最も簡便なものは、内閣のモラトリアム声明に基づき、総理大臣がその配下たる法務大臣に対して執行命令を保留するよう指揮することである。
注7
後藤田法相発言の要旨は、「法務大臣になる者は死刑執行命令という重大な責務を承知で就任すべきで、命令を決済したくなければ辞職すべし」というまことに単純素朴な意見である。参照、『インパクション80』(インパクト出版会)12頁参照。
注8
明治時代に制定された「看守職務規程」45条に「看守ハ上官ノ指揮ヲ承ケ死刑ノ執行ニ従事スヘシ」という規定があるという。清水反三「死刑を強制される刑務官 私の死刑廃止論」、法学セミナー増刊『死刑の現在』(日本評論社)所収126頁参照。ただし、1991年に新たに「刑務官職務規程」が制定された。内容は上記旧規程条項を継承していると思われるが、この点同規程原文を公開資料で確認できなかったため、本文の叙述は推測にとどまる。
注9
戦後では、1956年に参議院で死刑廃止法案が上程・審議された際、拘置所長時代に46人の死刑囚の死刑執行に立ち会った経験を持つ現職刑務所長、玉井策郎氏が、公述人として死刑廃止の立場から意見を述べている。『年報・死刑廃止2003』207頁参照。玉井氏には、『死と壁 死刑はかくして執行される』(彌生書房)という著書もある。また、比較的近時では、注8でも引用した清水反三「死刑を強制される刑務官 私の死刑廃止論」、法学セミナー増刊『死刑の現在』(日本評論社)所収122頁以下も元刑務官の立場からの廃止論である。そのほか、インターネット上では戸谷喜一氏のコメントも参照。http://homepage2.nifty.com/shihai/message/message_toya.html
注10
韓国国家人権委員会の「死刑制度に対する国民意識調査」によると、刑務官では、死刑存置が88.7%、廃止は11.3%に過ぎない。ちなみに、検察官では、同じく83.3%と16.7%である。『年報・死刑廃止2004』(インパクト出版会)211頁参照。
注11
大塚公子『死刑執行人の苦悩』(角川文庫)はまさにこの問題を実証的に扱った好著である。なお、この本を単に死刑廃止論の一亜種としてのみ読む(存置論者にありがちである)のはあまりに予断に満ちた表層的読みだろう。この本の最大意義は、死刑廃止論一般ではなしに、死刑を考えるときに通常はほとんど無視されている、実際の死刑執行=殺人処置の最前線にある問題を主題的に提起したことにある。
注12
大塚前掲書によると、担当刑務官には執行当日の朝に立会いを命ずるという。「前日に知らせるとみんな休んでしまうからだ。」同書19頁参照。そうだとすると、日本の死刑は、執行される死刑囚にとっても執行する刑務官にとっても、「突然」降りかかるように仕組まれているということを意味する。
注13
前掲清水論説によると、「看守職務規程」には刑務官が死刑執行従事を拒否した場合の罰則はないという。ただし、国家公務員法上の服従義務違反で懲戒される可能性はあるものの、その場合の根拠は単なる配置拒否であって本来の職務放棄ではないから、せいぜい戒告か軽度の減給で済むだろうともいう。だが、刑務官社会にも見られる階級制の特性から、上司に反抗的な刑務官が事実上排除される構造があり、そうしたインフォーマルな制裁を恐れて、実際に死刑執行従事を拒否できる可能性は乏しいであろうことも指摘している。
注14
これを提案しているのは、作家の森巣博である。長いが面白いので引用してみよう。
「現在の死刑執行は、拘置所の刑務官によっておこなわれている。いわば、殺人の代行だ。これを止めればよろしい。自分が殺したい人間を、だれか他の者にやらせて涼しい顔をしている、なんてまるでヤクザの親分である。「日本国民」は、そんなに破廉恥ではない。「つくる会」の「のすたるじじい」たちが主張するように、日本人は誇り高いのである。だから、殺したい奴を自分たちの手で殺すように制度を改めよう。一回の死刑執行につき、100人くらいを選挙人名簿から無差別に抽出して、死刑執行官とする。もちろんこれは、死刑制度を容認する「日本国民」の義務である。拒否はできない。拒否するなんて、それは「非国民」というものだろう。
「おめでとうございます。貴殿、貴女はO月OO日に予定された******の死刑における執行官に当選いたしました。戦争以外で合法的に殺人ができる唯一の機会です。どうぞこの僥倖(ぎょうこう)を存分にお楽しみ下さい」
なんて通知の手紙を送ったら、いいのじゃないかしら。その通知の手紙は、血の赤がよろしい。新アカガミ、ですな。その死刑執行に喜んで駆けつける「のすたるじじい」たちも居るかもしれないが、まあ、これでだいたい「8割の世論」は、ひっくり返せるのではないのでしょうか。付け加えると、「絞首刑」なんて、一見「汚くない」殺人方法も廃止しよう。選ばれた死刑執行官は、千枚通し、あるいは文化包丁を使って刑の執行をおこなおう。やってやろうじゃないのさあ。上等じゃないのよ。そして、じっくり考えよう。「文化包丁は文化的か?」と。」
http://homepage2.nifty.com/shihai/message/message_morisu.htmlを参照。
ただし、「のすたるじじい」ならぬ「のすたるにいちゃん/ねえちゃん」も増加している昨今、森巣提案は逆効果になることはないだろうか・・・。
2006-08-31
第二部 死刑廃止の政治過程(六)
☆前回記事
【3】死刑廃止におけるアクター③:司法部
死刑廃止におけるアクターとして、司法部を検討します。ここで司法部とは、最も典型的な司法裁判所はもちろん、憲法判断のみを担う憲法裁判所(日本には存在しない)をも含めて総称します。
今日の共通認識では、死刑といえども法的刑罰である以上、必ず司法裁判に基づいて適用・執行されるということはほとんど定言命法であることからして、司法部は、死刑の法的手続き上は決定的役割を持ちます。すなわち、司法裁判で死刑判決が言い渡され、それが確定しない限り、絶対的に死刑は執行できないわけです。注1 ということは、司法部が死刑判決を止めてしまえば、死刑制度は事実上停止状態となります。
一方、司法部とは、元来、既成の法律を大前提に、提訴された具体的案件の法的解決を託された公権力部門であって、死刑であれば、死刑が規定された刑法を大前提に、犯罪構成要件に該当する事実の存否と死刑を科することの当否についての判断を求められます。このように、司法部の役割はすぐれて消極的であり、一般的に死刑制度の廃止を決定付けることができるような形でアクターとなることはできません。
しかし、憲法判断の権限を持つ裁判所(日本などでは通常の司法裁判所)であれば、死刑が憲法に違反するか否かの判断をすることもでき、ここで違憲となれば、そもそも判決で死刑を言い渡すことができなくなります。このように、違憲判断が示されれば、以後司法部で死刑を適用することができなくなるため、運用において死刑制度が停止される、いわゆる事実上の死刑廃止を導けるのです。近年の実例としても、ハンガリーや南アフリカ、ウクライナ、最近ではアメリカのニューヨーク州で、死刑違憲の判決が出されています。注2
しかし、それらは、ほとんどの場合、立法府において死刑廃止の機運が生じてきた状況の中で、いわば援護射撃的に下された判決であって、何の徴候もないところに突然、司法部の違憲判断が現れたというようなサプライズではないのでした。注3 後述する1972年のアメリカ連邦最高裁判所の死刑違憲判決も、既に継続していたモラトリアム状況の中で下されたものでした。ただ、憲法問題のみを審理する憲法裁判所の場合には、通常裁判所に比べてよりアクティブな司法行動を取り得るように思えますが、例えば、韓国の憲法裁判所では、逆に死刑合憲の判決が出されており、死刑廃止にとっての阻害的アクターとなってしまっています。注4
この点で、死刑史に記憶されるべきは、アメリカにおける司法部の行動です。アメリカでは、1972年の有名な「ファーマン判決」において、死刑違憲の判断が5:4の僅差で出されたことをきっかけに、1968年から継続していた全米規模の死刑モラトリアムに追い風が与えられました。注5 この判決では、「気まぐれかつ恣意的に適用される死刑は、合衆国憲法の残虐かつ異常な刑罰の禁止と公正な裁判を受ける権利を保障した条項に違反する」ということになったのですが、上記のとおりの僅差であり、また、多数意見の論拠も一致せず、死刑制度そのものの違憲性を述べたのか、その「運用」の違憲性を述べたのか不明瞭な点が残りました。そこで死刑存置州では、多数意見の中でも死刑の適用基準が不明確で濫用の余地が大きいという点に重点をおいたものに着目しつつ、死刑条項の明確化などの法改正を施して、あくまでも死刑存置を目指したのでした。その結果、再び死刑の合憲性が争点となった事件では、一転して、死刑合憲の判決となりました。これが、1976年の「グレッグ判決」です。この判決では、先例である「ファーマン判決」について、死刑基準の不明確性を指摘したものだという理解に立って、基準が明確化された死刑であれば合憲という論理を取ったのです。ファーマン判決からわずか四年後のこの逆転判決をきっかけに、翌77年以降、全米で死刑は再開され、モラトリアムは約十年で覆されました。注6注7
では、死刑の適用基準は果たしてグレッグ判決の期待どおりに明確化されたのかといえば、このグレッグ判決では多数意見に加わったハリー・ブラックマン判事が退官直前の判決で少数意見を述べ、死刑適用基準の明確化を目指した試みは挫折したとして、「今日という日から、私は死の機械と決して関わらない」と宣言したことからも明らかなように、期待どおりにいっていないようです。注8
このように、司法部の憲法判断がしばしば積極的になされる米国でさえ、死刑制度に関しては決然たる態度を示さないため、司法部は死刑廃止においてプラスのアクターとしては機能していないのです。まして、司法部の官僚主義的保守性が徹底している日本においては、そもそも死刑違憲の判決自体がわずかであれ期待できず、注9 1948年の古い合憲判決が全く見直されることなく、維持されています。日米ともに、司法部が、憲法判断を通じて死刑廃止に向けてアクティブに活動することは極めて困難な状況にあると言えるでしょう。
しかし、このことは、司法部が本質的に持つ消極的性格からしてやむをえないところもあります。元来、司法部は既成の法を大前提として判断するため、憲法判断においても、合憲違憲の判定が微妙である場合には、合憲の判断に傾斜していく性向を排除できないわけです。
ところで、司法部にとってはもう一つ、死刑の適用基準を厳格化することで事実上死刑を適用しない状況を作り出すという方策も可能です。これは、違憲判決というある意味で立法府への介入となる劇的な手段を講じなくても、既成の法の適用基準という司法部本来の領野でもって死刑制度を事実上停止させることですから、司法の消極的性格とも整合するのです。
この点では、本書第一部で参照した死刑囚作家・永山則夫の裁判が好例となります。この裁判ではまさに死刑の適用基準が主要な争点となったのですが、控訴審では、非常に厳格な判断が示され、死刑の適用は「如何なる裁判所が衝にあっても死刑を選択したであろう程度の情状がある場合に限定される」という趣旨の判決でしたが、最高裁ではこれが覆され、「死刑制度を存置する現行法制の下では、・・・・・・・・その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許される」というより緩やかな判断となりました。この判決以降、下級審のレベルで死刑判決が増加する傾向を示すようになり、この永山事件最高裁判決は、いわば下級審向けのゴーサインとなり、現在に至っているわけです。アメリカにおける前出グレッグ判決のような位置づけにある先例と言えるかもしれません。
しかし、元々日本刑法では、例えば、殺人罪の規定は、単に「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」(刑法199条)とされており、いかなる場合に死刑となるのか、その加重事由が全く不明であり、アメリカの判例基準であれば違憲とされるのではないかと思われるのですが、永山判決の基準自体、決して明確とは言えないわけで、注10 法と判例と二重の上塗りで不明確な死刑運用をしているのが日本のお寒い状況であります。
ここで考えるに、日本刑法のように、同じ殺人で下限は懲役五年から上限は死刑までと、とてつもなく広い法定刑が用意されているということであれば、被害法益の個数は重要な基準であるはずで、極例を挙げれば、100人殺害も3人殺害も同じ死刑であるということは奇妙なことです。少なくとも、1人や2人の殺害での死刑はあり得ないと言えます。3人でも法定刑の幅の広さからして死刑はバランス上妥当でないでしょう。このような議論に対しては、むしろ法定刑の幅の広さは、動機や犯行手段、付随的状況等の幅広い考慮を許すもので、被害法益の個数こそ重要な要素ではないことを示す(つまり、被害者1人でも死刑があり得る)という全く逆の理解があり得るのですが、そうだとすると、そうした死刑を決定付ける考慮要素が法に明記されていないことは恣意的な運用を許すもので、憲法違反(おそらく、適正な手続きによらない処罰を禁じる31条違反)の疑いを生じるでしょう。注11
当初は死刑合憲判決に加わり、アメリカのモラトリアムを破ることに手を貸したブラックマン判事も最後には認めたように、死刑の適用基準の明確化は至難のことです。しかし、唯一、基準を客観的に明確化できるのが、被害法益の個数、すなわち、被害者の数なのです。例えば、「人を十人以上殺した者は、死刑に処する。」というような規定は極めて「明確」です。
しかし、このように被害法益の個数を死刑の重要な適用基準と考えると、個数は数学上無限大にあるわけですから、「極刑」と規定される死刑が適用されるべき極限的場合を厳密に同定していく限り、被害者2、3人ではもちろん、10人でも、否、100人でもそれを極刑に相当するとは言えないことになるはずであり、事実上死刑を適用できる場合はなくなってしまうのではないかと思います。
このような発想に対しては、いや、生命は崇貴なものであって、その侵害の個数は問題でない、たとえ1人であろうとも残酷凶悪な殺人ならば死刑に処すべしといった反論があり得るところでしょう。それは、抽象的な生命倫理学としては理解できます。しかし、実際の法の適用という場面では、先ほどから問題としている基準の不明確性という問題に逢着します。「残酷凶悪」といったところで、それを文学的な描写でなしに、法的な準則として立てるのは至難なのです。ブラックマン判事の指摘を待つまでもなく、そのような試みは初めから挫折する運命にあったのではないでしょうか。
しかしながら、日本の司法部では、このようなことを縷々思索すること自体、裁判官の間ではタブーとなっているようで、「悩まなくなった裁判官」というような悲観的な指摘もなされています。注12 実際、ここ数年はとりわけ死刑判決の急増が目立ち、死刑判決ラッシュというべき事態になっています。注13 日本の司法部は、ブラックマン判事が峻拒した「死の機械」の王国となりつつあるのでしょうか。
ここに、一つ困難な問題があります。それは、死刑判決文では常套句となっている「死刑の選択もやむをえない」という言表の問題性です。「やむをえない」というのは、より通俗化した表現では、「仕方がない」という意味になるでしょうが、ここには、「死刑にしたくはないが、仕方がない」という含意があります。この言表は、先の永山事件最高裁判決の文言に既に現れております。
しかし、この「やむをえない」ということが、他に選択の余地がないのであれば、まさしくやむをえないのですが、日本の刑法では、殺人罪などでは、死刑は選択刑の一つに過ぎず、他に選択肢がないわけではない。従って、この「やむをえない」という言表は、きわめて無責任な決断回避の言い訳となっています。本来、死刑になどしたくないが、自己の良心に反して死刑にするのであるという含みがあるのです。
しかし、憲法には、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」という規定もあります(76条3項)。代議士の場合における審議・表決に際しての良心の問題を前々回記事で指摘しましたが、裁判官については、憲法明文で良心規定が定められているわけです。そうすると、先の「やむをえない」というような決断回避の文言は、この良心に従う裁判官責務に反している疑いさえあります。注14
こう申せば、たいていの裁判官は、おそらく、上記条項の後半で「法律に・・拘束される」とある箇所を指摘しつつ、死刑制度がある以上は適用しないわけにいかないと反論するのでしょう。しかし、裁判官が、法律が不存在であるのに、又は法律の文言を曲げて、自己の良心のみに従って一定内容の判決を言い渡すことは許されませんが、自己の良心に従い、法律の適用要件を厳格に解して実際上適用の余地をなくすことは問題ないのです。死刑に関しては、永山判決の控訴審判決が、(それでも相当に曖昧ではありますが)そうした方向の判断であったわけですが、それを覆して、法律が存在する以上は良心に反してでも必ず法を適用しなければならないというように、先の憲法条項に反して裁判官の良心にタガをはめ直したのが、永山事件上告審判決であった、そのことの一つの表現が、「やむをえない」ということなのであると考えます。
私はこのような司法政策を不当と考えますが、しかし、日本のように司法部が高度に官僚主義的に構築されているところでは、司法の消極性が際立ち、司法部の構成要員に過ぎない裁判官の良心などは吹き飛んでしまうのであろうと思わざるを得ません。一方、アメリカのように多くの州で裁判官が選挙で選出され、また、連邦では大統領の政治任命となる状況では、裁判官が一種の「政治家」となってしまうために、結局、ここでは裁判官も代議士同然に“世論”の風向きに配慮せざるを得ないという点で、死刑違憲に関しては消極判断になりがちだということでしょう。注15
こうして、司法部が死刑廃止において果たすアクターとしての役割は、これを過大評価することはできません。結局のところ、確実に死刑判決を出させないためには、さしあたり死刑の言い渡しそのものを暫定的に禁止するモラトリアム法を制定しなければならないということになるでしょう。
注1
司法裁判によらない司法外処刑(extra-judicial execution)が横行する国もあるが、日本ではこの問題は除外して考察してよいだろう。 なお、私見では、司法裁判と死刑は整合し得ないと考えるため、死刑そのものが司法外のものと考えるが、これについては第一部第7章②「死刑の不能性(ⅰ)」を参照。
注2
ロシアの憲法裁判所は、99年2月に、すべての国民が陪審裁判を受ける権利を享受するまでは、死刑は適用されないという論理で、死刑のモラトリアムを後押しした(『年報・死刑廃止2000-2001』(インパクト出版会)185頁参照)。これは、完全な違憲判決とは異なるが、特定状況における死刑の適用を違憲とする限定的な違憲判決とみることもできる。
注3
例外として、欧州唯一の死刑存置国(本稿執筆時点)となっているベラルーシでは、憲法裁判所が、03年3月、「刑法上の死刑条項は、生命に対する権利を保障し、不法な権利侵害から人命を保護することを国家に要請する憲法条項に違反する」という決定を下した。『年報・死刑廃止2005』(インパクト出版会)144頁。
注4
ただし、韓国では、独立行政機関である「国家人権委員会」で、2005年5月、「死刑廃止」の勧告がなされた。同委員会は司法部ではないため、この勧告に判決のような強制力はないが、正式の国家機関でこのような「意見」が出されたことは、韓国で98年から継続されているモラトリアムに追い風となるだろう。韓国の状況については、パク・ビョンシク「韓国の死刑廃止法案と国家人権委員会の死刑廃止意見」、注3文献所収78頁以下参照。
注5
ファーマン判決とそれ以降のアメリカの死刑事情については、井上大「人種差別と死刑」、法学セミナー増刊『死刑の現在』(日本評論社)所収188頁以下参照。
注6
アメリカの例からは、司法部の中途半端な介入の問題性とともに、モラトリアムが必然的に最終的な死刑廃止に結実するとは限らないというモラトリアムの限界性を学び取ることができる。
注7
2004年にニューヨーク州の控訴裁判所(最上級審)で出された違憲判決は、全員一致制の陪審評決で、一致がなされないと、死刑のほか、仮釈放のない終身刑も言い渡しができないという州の規定は、陪審員に死刑反対意見を述べにくくし、死刑評決を強いることになるという趣旨で違憲とした。これは基準の明確性とは異なる論点であるが、やはり規定の修正によってクリアできる余地を許している点で、連邦最高裁判決と同様の中途半端さが残る。この判決については、以下を参照。
http://www.aclu.org/capital/general/10605pub20040713.html
注8
ブラックマン判事は、本文で引用した箇所に続けてこう述べる。「私は、死刑の実験は終焉したと、道義的にも知的にも認めなければならないとひたすら感じる。手続法と実体法のいかなる組み合わせも、決して死刑からその特有の憲法的欠陥を救うことができないということは、私にとってほとんど自明のことである。」また、「私は、こうした死刑事件で貧困か人種を理由とした違法性の存在しなかったケースを見ることはできない」とも指摘する。参照、http://people.freenet.de/dpinfo/judges.htm
なお、アメリカの死刑評決における人種差別という特有の問題に関しても、前掲注5井上論文を参照。
注9
既に永山事件判決に前後して、死刑事件を扱う弁護士の間では、「現在の裁判所に死刑違憲判決を期待することは不可能である」という共通認識が形成されつつあったという指摘がある。座談会「死刑廃止へ向けてどうするか」、『年報・死刑廃止96』(インパクト出版会)所収114頁、安田好弘発言参照。
注10
永山最高裁判決では、考慮要素として、「犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察」するというが、このような雑然とした羅列的基準では、あってなきがごとくである。
注11
唯一、かすかな期待を持てる死刑違憲の主張としては、「死刑を選択すべき加重事由が不明確な規定は憲法31条に違反する」というものであろう。ところが、裁判官の中には、永山判決にさえとらわれずに「自由に」死刑を言い渡したいという願望を抱く者さえあると指摘されるが(飯室勝彦「悩まなくなった裁判官」、法学セミナー増刊『死刑の現在』(日本評論社)所収113頁)、このような発想は裁判官の主観的判断のみによって死刑を決定しようという恣意的・専制的な裁断への愛着を示すもので、驚くべき時代錯誤であると思われる。
注12
前掲注11飯室論説を参照。
注13
特に、2000年代に入ってからすべての審級で死刑判決が増加し、それに伴い、死刑確定者も急増、近い将来100人突破もあり得る状況である。最近の資料として、「最近の死刑判決と執行数」、注3文献所収141頁(菊池さよ子執筆)。また、永井迅「重罰化傾向を考える」http://www.jca.apc.org/stop-shikei/news/82/2.htmlも参照。
注14
前回記事で取り上げた刑務官の良心的執行拒否と比べると、刑務官には憲法上は権利条項である19条(又は18条)でしかその保護が与えられていないのに対して(従って、その立場は弱い)、裁判官には司法の構成を規定する76条の3項で、その良心への忠誠が責務としても与えられている点に重大な相違があり、裁判官の良心保持は、単に権利であるのみならず、制度的責務にも組み込まれているのである。
注15
第一部第4章「死刑制度の転回①」でも述べたように、近代法における法のシステム化という一般的現象もまた、ブラックマン判事の言う「死の機械」化の原因を形成するだろう。法=死刑がそこに在る以上、その管理人たる法官はそれの作動を自己の所存では止めることができないようになってしまうのである。
2006-09-09
第二部 死刑廃止の政治過程(七)
☆前回記事
【3】死刑廃止におけるアクター④:運動体
前章までは、死刑廃止におけるファクターとして、国家セクターに属するものを見てきましたが、ここからは、非国家セクターに属するアクターを検討します。まずは何よりも、最も肝心な死刑廃止運動体についてです。
ここで、いきなり肩透かしをしますと、死刑廃止において死刑廃止運動体は、必ずしも必須のアクターではありません。つまり、啓蒙専制君主の統治する体制ならば、君主の命令のみで死刑廃止は実現し得るからです。注1 皮肉にも、運動体は啓蒙専制君主の消滅に伴って呼び出されます。つまり、民主化が一定は進展することで、死刑制度がかえって「民意」の衣を被るようになると、運動体が必要になってくるのです。死刑存置を国是とする独裁国では、運動体の存立そのものが許されません。たとえ欠陥ありとしても、民主主義が形式的であれ一応存在していることが運動体のアクター性を基礎付けると言ってもよいでしょう。ただ、運動体がアクターとしてどれだけ強力に働けるかは、民主主義の質に関わる問題になります。
ところで、死刑廃止のためには、死刑廃止という「問題」を社会的な関心事として公共の場へ持ち出し、目標に向けての公論を作り出していくという過程が不可欠であると考えられています。その際、その公論過程を開拓するのが、運動体であります。このような局面における運動体の活動を、啓蒙行動と名づけてみます。これを日本の死刑廃止運動の歴史に鑑みれば、正木亮たちの「刑罰と社会改良の会」の活動が戦後の代表例であると思います。注2
こうした啓蒙行動の重要な目的は、「常識を揺さぶる」ことにあります。死刑とは、一つの刑罰であると同時に、民衆の意識に潜り込み、牢固とした常識とも化し、観念化された権力態でもあるのです。注3 ですから、死刑廃止はしばしば社会的に「非常識」とみなされ、それを唱えること自体が強い攻撃的非難の的となるのです。死刑廃止論の特徴は、国家支配層自体からよりも、一般社会から激越な攻撃を招き寄せるというところにあります。
従って、死刑廃止という「問題」を社会的な関心事として公共の場へ持ち出すには、そうした常識との対決という過程を経なければならないのであって、そのために、ここでは知識人を中心とした啓蒙ということが不可欠なのです。この啓蒙という語はやや時代錯誤的に聞こえるかもしれませんが、ここで意味している啓蒙とは、先に述べた「常識を揺さぶる」ということを意味しているに過ぎません。注4
しかし、このような啓蒙行動のみでは、現実の死刑廃止には到達しませんので、ともかく公論を喚起した後は、実際の死刑廃止を国家セクターに働きかけるという過程が必要となります。このような運動体の活動を請願行動と名づけます。
このような請願行動を組織化する前提として、まず廃止論者たちが社会的にカムアウト(登場)するということが必要です。この過程は、日本の死刑廃止運動の歴史に鑑みれば、1990年における「死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90」(以下、フォーラム90と略す)の結成を一つの画期とするでしょう。この出来事は、フォーラム90の重要な主導者であった安田好弘弁護士が端的に述べていたとおり、「15.7%もの多数の死刑廃止を考えている人たちが一堂に集まって、これだけ世間に存在するんだということを、社会的にアピールする」ということを主眼としていました。注5
このような局面での死刑廃止運動体は、もはや啓蒙にとどまらず、国家セクターとの交渉能力を身につけることによって、実践的な行動力を高めていきます。ここで重要なことは、議会制民主主義のもとでは、議会・政党との連携を強めることです。死刑廃止はその旨の立法によって初めて実現されますから、議会・政党への架け橋なしには、死刑廃止は単に公論の枠内にとどまってしまいます。
この過程における運動体は、あくまでも死刑廃止を国内刑罰政策の変更要請という相で捉えて行動するのです。上記フォーラムでも、93年3月に死刑執行が3年4か月ぶりに再開されるまでは、法務省交渉などを通じた請願運動を展開していたようですが、これは日本におけるそうした請願行動の一例であったでしょうし、執行再開を受けて94年に設立された「死刑廃止議員連盟」はそうした請願行動の結実であると同時に、その足がかりにもなり得るものです。注6
こうした請願行動においては、国際的な連帯も強化されています。域内での死刑廃止が一段落した欧州では、EUのような国家セクターも一種の運動体となって、「死刑廃止の輸出」のため、日本をはじめ、存置各国に廃止の働きかけを強めていますし、また、強力な国際的運動体も存在しています。注7
さて、国家の政治構造が柔軟で、政権交代にも開かれている体制では、こうした請願行動だけでも死刑廃止が開けてくることもあり得ますが、そうでないところでは、事態は動きません。そこで、運動体としても、請願行動を超えたより強力な行動に出る必要が出てきます。これを、抗議・変革行動と名づけてみます。ただ、厳密に言えば、抗議と変革は区別されます。
抗議は、死刑制度に対する異議表明を意味します。典型的には、死刑執行に対する抗議行動のようなものです。これは、あくまでも死刑廃止というシングル・イシューに係留されつつ、請願行動を超えて、死刑を維持する体制への異議を申し立てるより強硬な行動ということになります。日本では、93年3月の死刑執行再開により政府から裏切られる恰好で、爾来前記フォーラムもこの抗議行動の段階へ入っていかざるを得なくなりました。注8
一方、変革行動は、抗議行動をも超え出て、死刑制度を維持する政治体制そのものの変革(場合によっては、転覆)まで目指す行動であり、運動体の活動展開としては究極的で最もラディカルな領野に突入します。
次章で詳論しますが、現在、死刑が残されている諸国は、多かれ少なかれ、非民主的な政治構造を温存しています。もちろん、必ずしも死刑存置国=独裁体制でないことは、例えばアメリカやカリブ海諸国の例が示していますが、それでも、死刑という強権に依存しようとする衝動が強い国は、質の高い民主主義の構築に失敗している国なのです。そうした諸国では、表面上、民主主義が存在しているように見えても、上記の請願行動、あるいは抗議行動をもってしても死刑廃止の道は見えてこない、それどころか、逆に死刑制度強化の反動さえ惹起するという事態もあり得るのです。
そこで、こうした状況下では、運動体は、もはや死刑廃止というシングル・イシューに自己を繋ぎ止めず、より広い視野で、所与の政治構造そのものを変革する事業に乗り出さざるを得ないことになります。このようなことが、変革行動の意味であります。
変革の方法としては、超法規的な革命から、選挙を通じた合法的な政権交代に至るまで様々のレベルがありますが、いずれによるかは、それぞれの国における政治構造上の条件によるでしょう。一般的には、民主主義の度合いが高いほど後者であり、逆であれば前者に傾きます。現在のところ、死刑廃止運動体がここまでの行動に至った事例は提示できないようです。というのは、これまでに死刑廃止が実現した実例では、ほとんど請願行動ないし抗議行動までのレベルで実現に至っているからです。しかしながら、条約成立から20年を経ようとして、いまだに廃止見通しが立たない諸国では、運動体も変革行動の域に進む必要が出てくるでしょう。そういう意味では、93年以降、まさに死刑反動の真只中にある日本では、運動体の存在理由が改めて試されているように思います。この点、日本の廃止運動体は、非常に穏健な請願運動の域を超え出ることに慎重で、「存置論者との出会い」を重視するように見えます。注9 元来、第2章でも見たように、死刑廃止運動は尖鋭な革命派ではなく、改良主義的な保守派によって唱道されてきた歴史からして、廃止運動が尖鋭な対決・転覆型の運動へ動き出すことには不安や異論も出るでしょうが、これは、死刑廃止へ向けた過程の中で、運動体が直面しつつある新たな段階として、避けて通れないことであるように思えます。
注1
最近でも、(啓蒙専制君主どころか暴君と呼ぶべき)ニヤゾフ終身大統領が支配する中央アジアの悪名高い個人独裁国家であるトルクメニスタンでは、(一見奇妙にも)1999年に死刑廃止が実現している。『年報・死刑廃止2000‐2001』(インパクト出版会)181頁参照。この詳しい経緯は不明であるが、地理的に近い欧州からの厳しい人権批判をかわす狙いもあると見られる。
注2
正木らの運動を事実上引き継ぐ形で、菊田幸一の「犯罪と非行に関する全国協議会」(JCCD)が登場する。座談会「徹底検証・死刑廃止運動 死刑廃止へ向けてどうするか」、『年報・死刑廃止1996』(インパクト出版会)所収115頁以下菊田発言参照。なお、同座談会は、戦後から近年に至る日本の死刑廃止運動を、(近年の)運動当事者らが同時代史的に概観するもので、日本の死刑廃止運動の欠陥や拙劣さを知るうえでも大変参考になる。
注3
安田好弘弁護士は、「国家権力の面からすれば、死刑は根本的な権力意識構造なんです。それは、具体的な権力作用ではなくて、むしろ国民の意識のなかに権力の支配・被支配を貫徹させる、ものすごく象徴的なものだと思います。」と指摘する。座談会「死刑は、なぜなくならないのか」、法学セミナー増刊『死刑の現在』(日本評論社)所収19頁参照。
注4
自らが常識と信じていることに揺さぶりをかけられると、人は衝撃とともに不快感を催し、攻撃的な反論に出る傾向がある。死刑廃止の啓蒙活動は、最初にそれを公言したキリスト教ヴァルド派以来、社会からの強烈なリアクションに直面する宿命を免れないのである。
注5
前掲注3座談会26頁安田発言参照。
注6
日本の死刑廃止運動は、行政府に属する法務省を主敵とみなす傾向があるが、これは日本の政治構造に対する通俗的認識(=官僚主導)を前提とするものであり、適切でないと考えるが、これについては後の章で言及する。
注7
アムネスティ・インタナショナルが、いち早く1977年のストックホルム宣言で、国連をはじめとする国際社会へ死刑廃止を訴えかけ、国際的レベルでの請願行動を開始している。これに関する経緯を簡潔にまとめたものとして、以下を参照。
http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-background-eng
注8
安田弁護士によると、「(執行のなかった)三年四か月の間に作られてきた、死刑廃止運動を担う人たちの感覚の中で育ってきたのは、一日でも長く執行しない状態を継続させることによって、事実上の死刑執行停止状態が生まれてくる。それがやがては法律上の死刑執行停止になり、そして死刑廃止になる。いわゆるソフトランディングの考えであったわけです・・」と述べている。前掲注2座談会130頁参照。このように驚くほど素朴な楽観論で「死刑の死滅」を空想していたのだとすれば、日本の死刑廃止運動は、日本の政治と法の特殊な構造についてほとんど何の予備的省察もしていなかったに等しいことになる。
注9
安田弁護士は、最近の死刑廃止運動の戦術(特に、「仮釈放なき終身刑」の導入を唱道する方向)について、「不服従で直接行動的なものをきれいにそぎ落としてしまったところにある運動論」と端的にまとめている。座談会「終身刑導入は死刑廃止への近道か」、『年報・死刑廃止2000‐2001』(インパクト出版会)所収17頁参照。最近の安田弁護士の発言ではさらに進んで、少数派である死刑廃止論者が低姿勢を取り、多数派である死刑存置論者との接点を探っていくべきことが強調されており、「わたし達のもっとも大切なものは命。そのためには自由を犠牲にすることもやむを得ないという苦渋の選択」をしなければならないとまで述べている。安田好弘「終身刑の導入と死刑廃止」、『年報・死刑廃止2005』(インパクト出版会)所収111頁参照。このくだりは、そのまま「テロとの戦い」のために自由を犠牲にする必要性を説く米国のブッシュ大統領ら、治安優先主義者の言説に置き換えても通用しそうである。しかし、この問題については後に言及する機会を持ちたい。
2006-09-19
第二部 死刑廃止の政治過程(八)
☆前回記事
【3】死刑廃止におけるアクター⑤:社会諸団体(ⅰ)
○在野法曹界
在野法曹界、すなわち弁護士会は、刑事事件において被告の弁護人を務める弁護士の職能団体である同時に、死刑問題を含む刑事司法上の問題についても社会的に意見を提起することが期待されていますから、死刑廃止においても決して無視できない影響力を発揮し得る立場にあるはずです。
しかし、実際には(残念ながらと言いたいところですが)、腰が重いのが実情であります。例えば、日本弁護士連合会(以下、日弁連と略す)は、戦後初めて死刑廃止法案が参議院に出された1956年当時には時期尚早として廃止に反対していますし、注1 その後も死刑廃止を打ち出すべきという内部の意見に執行部は消極であり、今日に至っても、会として死刑廃止を明言はしていません。注2 おそらくは、弁護士会は強制加入団体であり、内部には死刑に賛否あるため統一的立場を打ち出せないということが理由とされるでしょう。けれども、他の問題では(例えば、代用監獄の問題)、日弁連はしばしば一定の立場を打ち出し、制度廃止を唱えることがありますから、なぜ、死刑に限って特定の立場を打ち出せないのかは明確でありません。
たしかに、職能団体としては党派的問題に対して特定の立場は示せないということは理解できますが、死刑は弁護活動をしばしば無効にしてしまうという点で、まさに弁護士の職能に関わると思います。死刑事件では(求刑事件も含む)、しばしば裁判所の審理が偏頗・拙速に流れ、弁護人の活動が制約されます。また、(全く不当なことに)弁護活動そのものが社会的糾弾にさらされ、脅迫等の業務妨害を受けるほか、評判も損ないます。被告側も絶望、羞恥、あるいは死刑願望から、弁護人にも心を閉ざし、依頼人とのコミュニケーションにも困難をきたすこともあると言われます。注3 さらには、依頼人の確定死刑囚が執行されれば、再審弁護活動を全く不能にします。注4 このように、死刑という制度は弁護活動と根本的に矛盾する、というのが言い過ぎであれば、弁護活動に対して本質上敵対的な刑罰です。死刑該当者が適切に弁護されることを許さない刑罰と言い換えてもよいでしょう。このことは、まさに弁護士という職能の存在理由に関わることであり、そうした観点からも、死刑廃止を明確に提起すべきです。
もっとも、米国の法曹界ではかねてより死刑モラトリアム・プロジェクトに乗り出しており、近時日弁連もこれに倣って死刑執行停止法を提案しているようです。注5 モラトリアムは、廃止とは異なり、さしあたり執行を停止するという過渡的制度ですが、これだけを独立して主張しても廃止の契機とはなりません。全く不充分です。明確に弁護士という職能を擁護するという観点から、死刑廃止を打ち出すことが要請されます。このことは一見して業界利益を優先する利権的発想に見えますが、死刑問題においては、弁護士の職能を護ることが同時に死刑廃止への重要な一里塚となり得るのです。
それはまた、弁護士会自身の死刑事件への組織的取り組みを活発化させます。現状では、死刑が求刑されるおそれある刑事事件の第一審ではほとんどが国選弁護人により弁護されますが、弁護不充分のケースが相当数あると考えられますので(特に弁護士過疎地区)、注6 死刑事件の特殊性からも、弁護士会として特別に取り組むことが要請されます。一審から充分な弁護を提供して、死刑判決をできる限り阻止するための対応を強化することが必要です。この点、日本では死刑事件に関心を持つ弁護士の非公式的な会が存在しているようで、この点は評価できますが、それが依頼人の側にとって、実際にどの程度活用性(availability)を持っているかというとやや疑念もあります。注7
○法学界
法学界、わけても刑法学会は、死刑制度の根拠法でもある刑法を専門的に研究する専門職の団体であり、このような刑法学者集団による理論面からの死刑制度の批判的分析は、死刑廃止のプロセスにおいて、知的な影響力を及ぼします。まさに、18世紀のベッカリーアも、まだ学問が未分化であった時代の超域的学究であったとはいえ、死刑廃止を初めて理論的に提言して、現代にまで至る大きな影響力を発揮してきた刑法学者でした。
けれども、当時の主流派刑法学者らはベッカリーアに対して敵対的態度も辞さない構えの人が多かったのです。注8 刑法学者にもいろいろスタンスはありますが、最もスタンダードなのは今も昔も応報刑論です。応報刑論は、要するに、刑罰とは犯罪行為に対する返報であるということから出発していますから、究極的重罪には極刑たる死刑で報いよという発想に傾きます。それで、刑法学者には今日でも死刑存置論者が少なくないわけです。戦後日本でも、一般的には自由主義的な学風で知られた平野龍一と現在でも極めて有力なその系列学派がおおむね死刑存置論であるのも、応報刑思想を前提とした一般予防論という理論を採用するからにほかなりません。
これに対して、刑罰を犯罪行為への返報というよりも犯罪を犯した人間への教育であるとみなす教育刑論の学派は、かねてより死刑廃止論を主張していました。注9 今日では、この学派はほぼ廃れてしまい、その代わりに刑法解釈よりも刑罰制度全体のあり方を研究する刑事政策学と呼ばれる刑法学の応用分野に色濃く継承され、この分野の研究者には死刑廃止論者が少なからず存在する状況となっています。注10
特筆すべきは、応報刑論者でありながら死刑廃止論を提起する団藤重光です。団藤は応報刑論に立ちつつも、研究者としては人間人格の事後的可変性を認める刑事責任論を提唱してきたことと、最高裁判事となった経験から冤罪の深刻さを身をもって体験したことなどから、過去十数年にわたり、著書の改定を重ねて丹念に死刑廃止論を唱道し、相当の影響力を発揮してきました。注11
しかし、日本の刑法学会では、依然として死刑存置論が大勢を占めているようであります。そういう中でも1994年に団藤を含む有志刑法学者たちが、死刑廃止を求める共同声明を発していますが、研究者のこうした集団的社会介入はユニークであり、高く評価できるように思います。注12 こうした学会介入が継続的になされることは、死刑廃止のプロセスにおいて必ずしも決定的ではないものの浸透的とでも言えるような遅効性の影響を及ぼしていくでしょう。
○人権団体
ここで言う人権団体とは、専ら死刑廃止を目的に活動する死刑廃止運動体を除いた一般的な人権団体のことです。広い意味では、死刑廃止運動体も人権団体に含まれますが、その問題は特別に前回取り上げましたので、ここでは重複を避けます。
さて、人権団体は、死刑廃止が「人権」の問題であるという認識が高まるにつれて、死刑廃止における在野での重要なアクターとして台頭してきました。国際的なレベルでは、アムネスティ・インタナショナルを嚆矢として、今日では、内外の多くの人権団体が(人権団体を仮冒する政府系又は保守的政治団体などは別として)、死刑廃止を少なくとも活動方針の一つに掲げています。注13 人権団体は、在野法曹、とりわけ弁護士が有志的にその設立や運営に関わっていることも多く、弁護士会等の職能団体としては統一的な行動が取りにくい死刑廃止のような問題を人権団体の枠組みの中で取り組んでいく足がかりとなることも少なくないようです。
この人権団体は、通常、請願行動の領野で死刑廃止運動体と連携しつつ力量を発揮します。有力な人権団体は各国政府のみならず、国連へも働きかけて国内法や条約の制定を請願し、場合によっては、立法過程そのものへも関与していきます。この点で、現代の人権団体は、旧式な「人道団体」とは異なり、立法過程におけるアクターとしても機能するようになっています。ここから、人権団体が支配層に取り込まれていく危険もないではありませんが、通常、人権団体は「政治的中立原則」を掲げその危険を回避しようとしています。注14
しかし、「政治的中立原則」を掲げるゆえに、運動体に関して述べたような政権交代を目指す変革行動は人権団体の活動範囲には含まれないでしょう。ただ、近時は、変革行動に至らない抗議行動において人権団体の活動が拡大しています。アムネスティの緊急行動(Urgent Actions:UA)はその一例で、人権侵害の危険が差し迫っている場合に、当該国政府機関等宛に手紙やファックス、メールなどで集中的に抗議を寄せる活動で、単純でありながら一定の「抑止効果」はあるとされています。注15 死刑廃止運動体自身もこうした活動を取り入れる場合があります。また、各種の集会開催などの行事設営能力を持つ団体も少なくありません。
しかし、残念なことに、こうした人権団体は、日本ではあまり発達していません。例えば、NPO法人というカテゴリーの社会団体がありますが、ここでも「人権擁護」を定款上の活動目的とする団体は全体の15.3%とそう多くないのが実情であり、注16 また、専従スタッフもほとんどいないなど、資金面をも含めた活動基盤に脆弱性が見られます。こうした団体に関わることが直接に弾圧されるようなことはないようですが、公安監視下に置かれる可能性は残っており、日本における人権団体の発展はこれからの課題でありましょう。現在のところ、日本の死刑廃止過程においては、アムネスティに代表されるような海外の人権団体からの一種の外圧的介入を期待することが精一杯のようです。注17
注1
安田好弘「国家と死刑」、『現代思想2004年3月号』(青土社)所収45頁参照。
注2
安田弁護士の見解によれば、日弁連が死刑廃止を明言しない背景として、刑法「改正」の問題が絡んでいるという。つまり、「死刑について弁護士会が取り組むということは、刑法「改正」問題に新たに大きな論点を付け加えるというということで、これを避けて通ろうという政策的な思惑があった」という。座談会「死刑廃止へ向けてどうするか」、『年報・死刑廃止96』(インパクト出版会)113頁安田発言参照。ただし、現在では、既に刑法の法定刑引き上げ等の刑法典制定以来の大改正が実現済みであり(2004年)、もはや状況は異なっている。また、十歩譲って、死刑廃止を弁護士会が提起すると「「改正」問題に新たな論点を付け加える」のだとしても、刑罰権を縮小化する方向の論点付加であり、日弁連が懸念していた厳罰化方向の論点付加ではない。理由にならないように思う。
注3
弁護人とのコミュニケーション遮断が如実に現れたのが、オウム事件のいわゆる麻原裁判であったろう。この事件でも主任弁護人であった安田弁護士は、死刑事件の被告の独特な心理として、「強い心理的抑制」を指摘する。すなわち、「受罰的な観念の中にいて・・・・主体的な事実の見直しとか、あるいは主体的な事件に対する理解、解明・・・が欠如した状態が長く続く」ということである。死刑を意識するところから来るこのような特有の被告心理もまた、弁護活動を制約するだろう。座談会「司法改革と死刑」、『年報・死刑廃止2004』所収121頁安田発言参照(インパクト出版)。
注4
1999年には、小野照男死刑囚の弁護人が再審請求を提起した直後に執行されるという不埒なケースがあった。この件に関しては、菊池さよ子「執行された二人のこと」、『年報・死刑廃止2000-2001』(インパクト出版会)所収140頁以下参照。それによると、再審請求を出した日と法務大臣が執行命令を出した日が同日であったという。執行はその4日後であるから、この間に再審請求提起のことは知りえたはずである。再審請求も執行を阻止し得ないということを示威する意図的な執行と見てよいだろう。このように、再審制度、わけても再審弁護と死刑制度とは決定的に矛盾するのである。
注5
アメリカ法曹協会(ABA)の「死刑モラトリアム導入プロジェクト」については以下を参照。
http://www.abanet.org/moratorium/home.html
日弁連の「日弁連死刑執行停止法制定等提言・決議実現委員会」については、次のページを参照。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/shikeimondai.html
なお、この日弁連提言の経緯と趣旨については、対談「死刑執行停止に向けて」、『年報・死刑廃止2003』(インパクト出版会)所収4頁以下の金子武嗣弁護士発言も参照。
注6
一審限りで死刑が確定しているケースを見ると、多くが、東京・大阪などの大都市圏を離れた地方での事案である。弁護過疎地区とほぼ重なる。
注7
1983年に「死刑事件担当弁護士の会」として開始され、後に「死刑を考える弁護士の会」と改称したという。注2座談会における安田発言(前掲書114頁)。しかし、弁護士サイドの非公式的な研修会にとどまっているようで、本文で述べたような依頼人にとってのavailabilityがないのは、実践的でない。
注8
これについては、第一部第6章で若干言及した。そこに掲記の文献も参照のこと。
注9
既に紹介してきた正木亮はこのような教育刑論の代表者であり、また、死刑廃止法案を審議した1956年の参議院法務委員会で正木とともに公述した木村亀二も教育刑論の巨匠であった。木村の公述については、『年報・死刑廃止2003』(インパクト出版会)158頁以下参照。
注10
その最近の論調について本書では批点的に扱っているものの、日本の刑事政策学分野で死刑廃止論を長くリードしてきたのが、菊田幸一である。
注11
団藤の『死刑廃止論』(有斐閣)は現在、第6版(2000年)まで改定が重ねられている。
注12
93年の死刑執行再開を機に、翌94年に「死刑廃止を求める刑事法研究者のアピール」のメンバー280人によって出されたもので、佐伯千仭・団藤重光・平場安治編『死刑廃止を求める』(日本評論社)として公刊されている。
注13
例えば、アメリカの国内最大規模の人権団体である、ACLU(「アメリカ自由人権協会」と訳されているが、本来は「アメリカ市民的自由協会」である。)は死刑廃止を掲げ、公式ホームページでも専用コーナーを設けて情報提供を行っている。
http://www.aclu.org/capital/index.html
しかし、同組織と姉妹的関係にあり、国連経済社会理事会の特別協議資格をも持つ日本の自由人権協会は、死刑廃止を掲げていない。日本の人権団体の弱さの一例である。
http://www.jclu.org/index.html
注14
アムネスティ・インタナショナル規約では、第2条の「中心的価値」で、「不偏・不党性と独立性」を掲げる。
http://secure.amnesty.or.jp/statute/ai_statute.shtml
注15
緊急行動の内容と効果に関しては、以下を参照。
http://www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=250
http://www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=259
注16
内閣府国民生活局ホームページ参照。
http://www.npo-homepage.go.jp/data/bunnya.html
注17
日本の死刑制度に関するアムネスティ・インタナショナルによる最近の調査報告として、以下参照。
http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=155
http://web.amnesty.org/library/index/engasa220062006ただし、アムネスティ等の国際団体のウォッチは基本的に人権状況が最も劣悪な諸国に集中するため、日本など一般的に「先進国」とみなされる諸国に対しては手薄になりがちな感もあり、基本的に日本人スタッフが運営する日本支部事務所の拡充とともに、UAをはじめ、今後は抗議行動の面での効果をより強める必要がある。
2006-09-29
第二部 死刑廃止の政治過程(九)
☆前回記事
【3】死刑廃止におけるアクター⑥:社会諸団体(ⅱ)
○宗教界
霊的な問題を専ら扱う宗教界は、死刑廃止におけるアクターとして大いに期待できるでしょうか。そうありたいところですが、宗教界も死刑問題では微妙で両義的な立場にあります。その理由として、まず、ほとんどの宗教が備えている教義体系に照らしても、死刑に関しては一義的に明確でなく、賛否いずれも導出され得ることが挙げられます。注1
また、歴史的には、総体として、キリスト教も含めほとんどの宗教が死刑制度に賛成でありましたが、次第に廃止運動に与する宗教が増えてきたと言えるようです。政教一致制が人間社会でまだ色濃く残存していた時代には、宗教界は統治者とほとんど一体であったのであり、その時代には、キリスト教の異端審問などの例に見られるように、宗教裁判が死刑を多用・乱用したことさえありましたが、政教分離が進展するにつれて、宗教界は死刑廃止へ傾斜していった感があります。注2 その意味で、政教分離という憲法原理は、間接的ながら死刑廃止を促進する効果を有するとさえ言えるように思います。あえて大胆に一般化すれば、支配的権力に近い宗教界ほどに死刑存置への傾斜が濃厚に見られ、その反対に遠いほど死刑廃止に傾くということになるでしょうか。注3
この点、現在の日本は言うまでもなく憲法上政教分離を採用しており、宗教の地位は個人の信仰を媒介とした精神指導的なものにとどまり、宗教界と支配的権力との距離は相対的に遠いと言えるでしょう。そうした中で、キリスト教団や天台宗、真宗大谷派、また神道系の大本教などがかねてから死刑廃止運動にコミットしてきています。注4注5注6 近時は、こうした宗教系の廃止運動が緩やかに連携するようにもなってきました。キリスト者の側には、「死刑廃止キリスト者連絡会」があり、2003年には、このグループを含む「「死刑を止めよう」宗教者ネットワーク」という多宗教横断的グループも結成されました。注7
けれども、日本の宗教界も決してこぞって死刑廃止運動を領導しているわけではなく、全体としては低調であるなか、各派宗教者の個人的なネットワークで廃止運動が展開されているようであります。注8 このことの背後には、歴史の古い教誨師制度の問題が潜んでいると考えられます。教誨師は死刑制度にとって不可欠の機構となっており、近年の例では、教誨師が死刑執行過程に相当深くコミットしていることが報告されています。注9 実際、死刑を死刑囚に積極に受容させるという日本式処刑では霊的な教導の需要は高く、円滑な執行確保という便宜的な目的からとはいえ、ほとんど政教分離原則違反寸前の形で教誨師が執行過程にコミットすることになりやすいのです。ただ、教誨師の側でも、死の強要に関与することに宗教者として個人的な悩みは抱えているようですが、注10 一方で教誨師を送る教団側では、教誨活動への配慮から死刑廃止を明示的に打ち出せないといった、教義とは別次元での考慮が働き、運動に参加しにくい事情も窺えます。注11
ここで韓国における興味深い例を挙げておきましょう。韓国では死刑廃止運動そのものが宗教的であるとさえ言われるほどに、宗教界の影響力が顕著に見られます。例えば、韓国における二つの主要な死刑廃止運動体がいずれも宗教者によってリードされています。これは、韓国において、宗教を持つ人の割合が高く、宗教者の社会的影響力が強いためとも言われています。ただ、基本的には韓国も政教分離体制であり、宗教界が直接に支配的権力と結ばれているわけではなく、むしろ在野の立場での影響力行使であるという点では、日本と似た状況にあるでしょう。しかし、その韓国においても、宗教界こぞっての死刑廃止運動ではなく、主としてカトリックがその中心にあり、他の宗教では個人単位での参加が多いとされています。注12
結局のところ、宗教界はその教義の点からも、また一種「政治」的な立場(日本における教誨師の問題も一種の「政治」問題である)からも、死刑廃止に対して明確な態度を示すことが難しいようですが、ひとたび廃止に与する場合であっても、宗教界の役割は、主として啓蒙的なもの、しかも精神指導的な支柱という意味合いが主となるでしょう。その点では、宗教界は、死刑廃止論がしばしば攻撃を招き寄せ、そのアキレス腱にもなっている被害者救済問題でも一定の影響力を持ち得るという強みはあります。一般的な見方によれば対立的に捉えられる死刑廃止と被害者救済とを跨ぐ活動をする余地の最も広いことが宗教界の特質であります。この点でアメリカの修道女、ヘレン・プレジャンの活動は注目されます。同氏の運動は今のところ単独行動的ではあるようですが、映画化されて話題を呼んだ『デッドマン・ウォーキング』に見られる著作をはじめ、世俗的な運動とも連携しながら被害者支援にも及ぶ活動を展開しています。注13
ただ、カトリックであるプレジャンについても言えることですが、宗教的な観点から「生命の尊重」ということを絶対化していくと、妊娠中絶反対などの保守的な道徳運動と死刑廃止運動がリンクしていくこともあります。注14 これは、宗教界が死刑廃止運動で果たすアクターとしての役割の危険性でもあります。宗教界は、歴史的・現在的に、自由のブレーキ役でもあり続けています。私見では、宗教界のアクターとしての役割はなるべく限定的な精神指導的なものにとどめ、在野の廃止運動の主体は世俗主義の運動体等であるべきです。
○被害者団体
被害者団体は、死刑廃止のプロセスにおいて、これを最も阻害するアクターとみなすべきでしょうか。そう考えたくもなりますし、実際、死刑廃止に強く反対する団体もあることでしょう。しかし、近年はそれほど単純ではなくなってきています。死刑制度が、果たしてその宣伝どおりに被害者のいかなる権利をいかにして擁護していると言えるのか、これを冷静に省察しようとする被害者たちが現れ始めているのです。
その最先端はアメリカにあります。アメリカでは、死刑に反対する殺人被害者団体というものが複数存在しており、文字通り遺族の立場で死刑に反対し、また一部では収監中の死刑囚の家族や執行された死刑囚の遺族もメンバーに加わり、活動をしています。注15 こうした運動が具体的にどの程度成果を上げているかとなるとはっきりしませんが、最近、ある州の検察官は、死刑要求をしない遺族が増加していることについて、「たとえ死刑に非常に賛成であれ、その大方が、決してそれで幕引きではないし、死刑システムが約束するような結果を必ずしも保証するものでもないとみるプロセスを進んで経験しようとする人は少数である」とコメントしています。注16 これからすると、アメリカの死刑存置州においても、遺族による死刑反対論が広がっているかに見えます。
しかし、一方で、死刑を「普通に」求める「良い遺族」と遺族でありながら死刑を求めない「悪い遺族」のふるい分けがアメリカで盛んであるという指摘があります。注17 たしかに、残酷な殺人事件の被害者遺族は、通常、強い怒りや憎悪を示し、被告に対する死刑を当然に要求するはずだと理解されてきました。実際、現在でも法廷でそのように陳述する人は少なくないでしょうし、それは検察側にとっても死刑求刑論告の説得性を補強するうえで不可欠であり、結局のところ、検察側の求刑政策・方針に協力的な遺族が、配慮に値する「良い遺族」であるのです。注18 日本では、法廷であえて遺族が死刑を求めないと明示的に陳述したという話は、被告が親族でもあるような場合を除けば、あまり聞かないのですが、1956年に参議院で死刑廃止法案が上程・審議されたときには、その直前に妻と娘を強盗に殺害された磯部常治弁護士が公述人に立ち、死刑廃止論を展開するという昨今では想像できないようなハイライトシーンがあったのでした。注19 最近の事例では、保険金殺人で弟を失った原田正治さんが、犯人である死刑囚の死刑執行に反対し、死刑囚との対話を継続することを当局に要請するも空しく執行が強行されたことがあります。これなどは、死刑維持の国策に協力的でない「悪い遺族」への見せしめ的な要素も込められた早期執行であったとも言えます。注20
日本の場合には、こうして単独行動的に死刑に反対する遺族も散見はされますが、私の知る限り、アメリカのように団体を結成して活動するまでには至っていません。ここで再び宗教の問題が提起されるかもしれません。死刑に反対するアメリカの被害者団体も基本的には世俗主義の団体ではありますが、キリスト教信仰の影響がゼロであるとも言えないでしょう。ちなみに、キリスト教も決して一枚岩で死刑廃止論なのではなく、むしろ保守的キリスト教徒の中には死刑存置論者も少なくないわけで、キリスト教信仰を持たない限り遺族の死刑反対論は成り立たないというように結論づけるわけにはいきません。注21 ただ、キリスト教に限らず、宗教一般に見られる寛容とか救済のモチーフは、遺族が怒りや憎しみを乗り越えて死刑に反対する意見に傾くときの助けになるでしょうし、またそうした遺族たちが結集する際の旗印にもなりやすいでしょう。この点では、仏教国とされながら、仏教の精神指導性が弱く、「葬式仏教」と揶揄されるような世俗主義が強固であり、また古来の神道にしても「お宮参り」などの世俗的な願掛けのレベルでしか浸透していない日本の状況はやや不利であり、今後も遺族が集団的に死刑に反対するということは期待薄かもしれません。
そのためか、日本の文脈では、死刑廃止運動体も、遺族感情というものを怒りや憎しみの相だけで狭くとらえ、それへの配慮として死刑と価値的に変わらない終身刑の創設等が不可欠であるといった議論に走りがちですが、むしろ遺族の立場で死刑判決または執行に反対するという人たちを掘り起こし、支えていくという活動こそ重要であります。注22 これは、そうした異論を持つ遺族が自主的に結集するだけの社会的な基盤が脆弱で、アメリカ以上に少数派遺族が片隅に追いやられるか、社会的な圧力に負けて、結局死刑要求に向かう以外なくなるかという状況に追い込まれやすいことを考慮してのことです。
いずれにせよ、遺族の立場での死刑反対運動は、死刑存置勢力が死刑の最大顧客と想定し、自らその理解者をもって任じている者たちの「反逆」という意味を持ちますから、これはインパクトが大きいでしょう。そうした運動が全国的に発生・展開されていけば、死刑制度はその存在理由の主要な柱が大きく揺らがされ、危機にさらされます。それだけに、存置勢力側でも、マスメディアを利用し、それと一体となって、遺族らの激怒・憎悪感情を扇動するという術策に出ることでしょう。残念なことに、日本ではこの術策が過去十数年にわたり、かなりの程度成果を収めてきたのです。
注1
主要な宗教と死刑問題の関連については、以下を参照。
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_and_capital_punishment
注2
18世紀に死刑廃止論を展開したベッカリーアも、宗教界からの攻撃を意識していた。例えば、『犯罪と刑罰』の「前言」でも、自分の理論が反宗教的であると烙印を押されないよう繰り返し念を押している。『犯罪と刑罰』(岩波文庫)11頁以下参照。
注3
仏教では殺生を禁忌とするにもかかわらず、仏教界の政治的影響力の強いタイやスリランカでは仏教界が死刑存置側にある。タイの状況について、『年報・死刑廃止2002』73頁(ロブ・スチュワート報告)参照。1976年以来死刑が休止しているスリランカでは、死刑再開の政治的動きに仏教界やイスラム教の聖職者・団体などが賛意を表明しているという。『年報・死刑廃止2000‐2001』189頁参照(桑山亜也執筆)。
注4
日本基督教団は、第22回教団総会(1982年11月16日~18日)において「日本基督教団は、日本国家による死刑執行の中止を求め、死刑制度の廃止を訴え、裁判所は死刑判決を下すことのないよう求める」との決議を採択している。
参照、http://www.jca.apc.org/~haikiren/framepage1.html(「キリスト教会の声明文集」欄)
注5
天台宗は、1999年の「死刑制度に関する特別委員会」最終答申で、死刑廃止を打ち出している。
参照、http://www.tendai.jp/shuchou/02.html
真宗大谷派は、2003年以来、毎年死刑廃止を求める声明を出している。
参照、http://www.tomo-net.or.jp/info/news/news.html
注6
大本教は、2003年に「死刑廃止に賛同する教団見解」を公表している。
参照、http://www.oomoto.or.jp/Japanese/jpOpin/030612.html
注7
柳下み咲「「死刑を止めよう」宗教者ネットワークの発足」、『年報・死刑廃止2004』202頁以下参照。
注8
ネットワークの設立趣意については上掲注7報告を参照。
注9
2000年11月に執行された藤原(勝田)清孝への執行に真言宗教誨師が深く関与していたことについて、安田好弘「執行をめぐる状況」、『年報・死刑廃止2000‐2001』157頁以下参照。
注10
大塚公子「死刑囚教誨師の嘆き」、法学セミナー増刊『死刑の現在』(日本評論社)130頁以下。
注11
上掲注7報告参照(204頁)。
注12
パク・ビョンシク「韓国における死刑廃止の動きと行方」、『年報・死刑廃止2002』所収105‐106 頁参照。
注13
ヘレン・プレジャンは公式ホームページを開設している。
http://www.prejean.org/
注14
実際、プレジャンは、上掲ホームページ上で、「私は、殺人には、道徳的に強く反対の立場である。すなわち、戦争、死刑、老人・精神錯乱者殺し、胎児であろうとなかろうと子殺し。」と述べ、明確に死刑と妊娠中絶ともに反対する。
注15
主要なものと挙げると、次のようである。
和解のための殺人被害者家族会
http://www.mvfr.org/index.htm
人権のための殺人被害者家族会
http://www.murdervictimsfamilies.org/
希望の旅―暴力から癒しへ
http://www.journeyofhope.org/pages/index.htm
注16
以下の拙稿参照。
http://turedure-sisaku.blogzine.jp/sophia/2006/09/post_f0ec_2.html
(英文出典はhttp://people.freenet.de/dpinfo/quotes.htm)
注17
坂上香「「被害者」の声を聴くということ」、『現代思想』2004年3月号(青土社)所収76頁以下参照。そこでは、殺された父が死刑に反対していたことから、遺志を継ぎ、法廷で死刑を望まない旨の証言をしようとしたところ、判事から制限され、量刑段階で死刑という語を発したら拘留または罰金刑に処すという通告まで受けたフロリダ州の遺族の例が紹介されている。
注18
上掲坂上論文によると、アメリカでは被害者関係の団体を検察が所管し、検察に被害者認定権がある州も存在することから、検察側が死刑を求刑する事件で、それに反対する「悪い遺族」は不利な立場に置かれ、「被害者」と認定されず、被害者としての権利行使も制限されるといった事例が発生しているという。
注19
磯部弁護士の公述と質疑応答については、『年報・死刑廃止2003』140頁以下及び152頁以下参照。
注20
詳しい経緯は、原田正治「弟を殺した加害者と僕」、『現代思想』2004年3月号(青土社)所収64頁以下。なお、上掲注17坂上論文(76頁)によると、原田さんは、弟を殺害した長谷川敏彦死刑囚の死刑執行反対を求めてビラ配りなどをしていた時に、「国が加害者を死刑にしてやっているのに反対するのは悪い被害者だ」という趣旨の嫌味を浴びせられたという。なお、長谷川死刑囚に対する死刑執行直後の原田さんの発言として、同「被害者感情を踏みにじった執行」、『年報・死刑廃止2002』所収137頁以下も参照。
注21
例えば、古くから遺族の立場で死刑に反対してきたカトリック教徒の米国人、マリエッタ・イェーガーさんは、来日した際の講演で次のように言っていた。「たしかに、さきほど私が許すという言葉を使っていたときに、背景として私の宗教的なものがありました。けれども、同時にそれは、世俗的・心理学的にみても、心を癒していく過程で重要な意味も持っているのです。」(同「復讐からは何も生まれない」、法学セミナー増刊『死刑の現在』(日本評論社)所収95頁[訳・篠崎知子])
なお、イェーガーさんの簡単な紹介と近況について、以下も参照。
http://www.journeyofhope.org/pages/marietta_jaeger-lane.htm
注22
死刑囚への個別支援が重要であるのと同時に、死刑に反対ないし懐疑的な被害者遺族への個別支援も死刑廃止運動体の活動として位置づけるべきであるが、これについては後に詳論したい。
2006-10-07
第二部 死刑廃止の政治過程(十)
☆前回記事
【3】死刑廃止におけるアクター⑦:メディア
メディア、とりわけ、マス・メディアは死刑廃止における最大の妨害要因であるとまず断言します。といっても、これは決してマス・メディアがその本性上そうだというのではなく、(特に日本の)現状においてそうだというにとどまります。
そういう点からすれば、昨今のマス・メディアは社説等で死刑廃止を唱えることなど全く期待薄であるばかりか、注1 1989年の国連死刑廃止条約成立という死刑史における画期的出来事もこれを詳細に伝えたマス・メディアは当時ありませんでしたし、注2 今日でも条約にはほとんど触れられることはありません。さらに日々の犯罪報道では、事件の感情的な側面を執拗に描写し、死刑存置論の「識者」や「コメンテーター」を並べては死刑を当然視する糾弾的で偏頗な報道に終始しています。特にワイドショーと呼ばれるテレビの犯罪報道の偏頗さには大変なものがあります。明らかにマス・メディアが正式公判前に事実上有罪・死刑「評決」まで下し、有罪・死刑を「世論化」してしまうメディア・トライアルの世界最先端を、日本は走っているとしか言いようがありません。この国では近現代司法の鉄則である、何人も刑が確定するまでは無罪と推定される「無罪推定原則」など、ほとんどジョークでしかないでしょう。
ここにマス・メディアのマス(大衆)という語は、元来必ずしも「多数派」を意味しませんが、現代日本のマス・メディアでは、マスがますます「多数派」を指し示すようになっています。つまり、多数意見を偏重しつつ少数意見を取るに足らないものとして切り捨て、事実上存在しないものとして扱うのです。このような傾向は、やはりオウム事件の頃から過激化したように思われます。注3 もちろん、ここには商業メディア特有の「情報の商品化」という問題も含まれています。株式会社として運営される商業メディアは公論の提起よりも利潤追求に傾斜しがちですから、必然的に売り上げ部数や視聴率至上主義になります。売り上げや視聴率を伸張させるには、当然ながら、社会の多数派が見聞したいと思っていることを報道するのが一番です。その逆はあり得ません。オウム事件で言えば、「オウムの連中がいかに極悪で死刑相当か」を執拗に描くことです。あるいはまた、「被害者遺族がいかに筆舌に尽くし難い苦しみを味わっているか」を“涙そうそう”と伝えなければならないのです。死刑廃止論もお呼びでないことはないのですが、それは憤慨した読者・視聴者からの「抗議殺到」を招くことを覚悟のうえでということになるでしょう。
このようにして多数意見に寄り添い、それを助長するために製造される情報商品は、大袈裟なセンセーショナリズムと狭量で凡庸な道徳的教説をこね合わせたような奇怪な化合物になります。ワイドショーのキャスターやゲストたちは、一種道徳の教師として振舞います。注4 聞いているほうが赤面するような凡庸な言葉使いで「加害者」を糾弾し、悪魔化し、場合によってはその「熱心すぎる弁護人」にまで―しかも、弁護士ゲストの口を借りて―矛先を向けていきます。弁護人は悪魔を手助けする背徳者とみなされます。ワイドショーはほとんど現代の異端審問・魔女裁判と言ってよいでしょう。
結果として、大衆は冷静な判断力を喪失します。よほど意識の覚醒した人以外は、いわゆるモラル・パニックに陥るでしょう。注5 統計など無視して、まるで同種凶悪事件が「激増」しているかのような錯覚を起こします。統計上は敗戦直後のほうがよほど治安が悪化していたにもかかわらず、「最近は治安が悪化した」とか「モラルが崩壊した」などの信念を持つに至ります。統計に基づかない単なる気分に過ぎない「体感治安」なる用語も派生しました。実は、オウム事件以降に激増したのは、「凶悪事件」ではなく、こうしたマス・メディアを通じて人工的に発動されるモラル・パニックの頻度なのです。マス・メディアが狙いをつけた事件が報道されるたびに、モラル・パニックの痙攣的連鎖反応が惹起されています。このような状況の積み重ねが、近年における「死刑支持率」の上昇という見かけの現象にもつながっているでしょう。注6
それでも、私はマス・メディア全否定論には与しません。マス・メディアは、本来、「独立性」「公平性」「啓発性」の三つの原理を掲げて公論を提起する任務を負った言論専門機関であると考えます。死刑廃止との関係で言えば、まず、与党・政府(検察も含む)・司法部からも独立して独自の立場を保ちつつ、少数意見である死刑廃止論や運動をも公平に紹介し、かつ国連条約の存在と内容を丁寧に解説し、また毎年死刑廃止国が増加している国際社会における死刑廃止の動向をも常時伝える。こういうことを日頃着実に実行していけば、マス・メディアは直接に死刑廃止におけるアクターとはなり難いにせよ、少なくとも死刑廃止過程を現状のように阻害する妨害アクターにはならなくて済むのです。注7 なぜ、それができないのでしょうか。それは、結局のところ、利潤確保という活動目的に沿わないからにほかなりません。商業メディアとは、まこと、その存在理由と活動目的とが自己矛盾的に食い違った奇妙な資本主義的産物なのです。注8
私は、マス・メディアを全否定はしないとはいえ、現代マス・メディアにもはや死刑廃止の論陣を張ることを期待もしません。 それでもせめて、死刑情報、わけても死刑執行の日時・場所・対象者とその関連情報(健康状態や再審請求の有無等)を政府に開示させることは実行して欲しいと思います。これはマス・メディアとしてなし得る最低限の仕事です。死刑は正義だとマス・メディア自身確信するなら、正義の顕現たるはずの死刑執行がなぜ秘密裡なのか追及する気にならないのでしょうか。それさえも政府への配慮から事実上自制し、自己検閲を課しているならば、日本のマス・メディアはいよいよ終焉を迎えるでしょう。
ところで、メディアと言ったときには、マス・メディアばかりでなく、ミニ・メディアも含まれます。死刑廃止におけるアクターとしては、マス・メディアよりもミニ・メディアのほうが有望です。このミニ・メディアには、死刑廃止運動体や全くの個人が発行する雑誌やパンフレット、電子上のウェブ・サイト等も含まれます。これらのメディアは、マス・メディアと異なり、死刑問題に特化したものですから、当然発行部数やアクセス数には限界を抱え込むことになり、なおかつテレビ放送というコストのかかる手段はミニ・メディアではほぼ不可能です。それでも、これらのメディアにはマス・メディアが日頃伝えない出来事や観点からの報告・論評などが豊富に含まれますから、マス・メディアとは異なる固有の役割を果たしています。
こうしたミニ・メディア一つ一つは非常にか弱い存在ですが、いわばゲリラ的メディアとして死刑廃止過程には欠かせないものです。ミニメディアはその弱さという限界ばかりに目を向けると、運営者自身が幻滅し挫折しかねないのですが、ゲリラ活動の価値を過少評価はできません。もちろん、言論の自由が体系的に抑圧されている国では、こうした死刑廃止メディアも存在自体が許されないということになりますから、この場合にはどうすることもできないのですが、そうではないところでは、ゲリラ戦的メディア活動はむしろ死刑廃止論の重要な拠点になり得ます。この点では、日本の死刑廃止運動体などはまだ不充分であると思います。注9 個人の立場でもブログなどの簡便な電子ツールを使用して、いつでもミニ・メディアを作成できます。日本の最新世論調査でもなお6%は死刑廃止を支持しています。単純に人口1億と仮定すれば死刑廃止論者が600万人は存在する計算になります。ミニ・メディアはもっと盛んであってもおかしくありません。おそらく、少数意見をことのほか発信しにくい社会的な風土も影響しているのでしょうが、ミニ・メディアは死刑廃止論の裾野を広げるという意味でもその役割は過少評価できないということを再度強調しておきます。
注1
約半世紀前の朝日新聞社説(1956年1月16日社説)では、格調高く死刑廃止法案賛成論が展開されていた。『年報・死刑廃止2003』76頁以下。特に、「いかなる権力も、いかなる理由も、人を殺してはならぬという制度が確立してはじめて、人の生命に手を触れてはならぬという信念が、すべての人の心に芽生えてくるのである。」という一文は、死刑が廃止されて初めて死刑廃止論が多数意見になるという死刑廃止におけるパラドクシカルな真理を言い当てている。これを書いた記者の50年後の後輩たちにはもはや同じことを期待できないであろう。この退化が現代マス・メディアのありようをよく物語っている。
注2
山口正紀「死刑制度維持に加担するマス・メディア」、法学セミナー増刊『死刑の現在』(日本評論社)所収145頁以下。
注3
山口正紀「死刑とマスメディア90~95」(『年報・死刑廃止96』276頁)の分析によると、90年から93年にかけての執行休止・再開という出来事の間はマス・メディアの死刑関連報道が活発化し、特に93年の執行再開当時は社説等でも再開に疑問を滲ませ、議論の必要を主張する新聞もあったが、地下鉄サリン事件後初の死刑執行があった95年5月以降は報道が縮小していき、「「死刑の日常化」の中で、真先にニュース感覚をマヒさせてしまった」という。
注4
ピエール・ブルデューは、「テレビ関係者のモラリズム」について手厳しい指摘をしている。「彼らは、シニカルでありながら、しばしばまったく驚くべきほどの順応主義的モラルの言葉を述べます。我らがテレビニュースのキャスターたち、討論番組の司会者たち、スポーツ・コメンテーターたちは、良心の小指導者になっています。彼らは、他人からほとんど強いられる必要もなく、自分たちを小市民的(プチ・ブルジョア)モラルの代弁者にして、自分たちが「社会の問題」を呼んでいること、例えば郊外での犯罪や学校での暴力について、「考えるべきこと」を語るのです」、ピエール・ブルデュー/櫻本陽一訳『メディア批判』(藤原書店)80-81頁。
注5
モラル・パニックの問題も含めて、「死刑のある社会」の問題を刑罰の根底まで遡って問う論考として小野坂弘「<死刑がある社会>と<死刑がない社会>」、上傾注2『死刑の現在』38頁以下参照。
注6
各方面でよく引かれる数値であるが、2004年の内閣府調査によると、死刑制度に関して、「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」と答えた者の割合が6.0%、「場合によっては死刑もやむを得ない」と答えた者の割合が81.4%となっている。このように、政府が自己の政策について独立した世論調査機関に委託せず、自ら「世論調査」するというのはそれ自体が政策の一環であって問題含みであるが、このことは後に検討したい。さしあたり、政府調査における死刑支持率は過去最高、廃止論の割合は同じく過去最低であることは間違いない。以下を参照。
http://www8.cao.go.jp/survey/h16/h16-houseido/2-2.html
注7
死刑廃止運動を効果的に展開するうえで、マス・メディアを活用することが無益であるわけではない。2006年6月に死刑を廃止したフィリピンの経験でも、廃止運動体は、「死刑問題に対する関心を高めるため、ドキュメンタリービデオの製作や路上での演劇、地域での討論会、展示会、論説委員への書簡やテレビやラジオのインタビューをはじめメディアへの積極的な働きかけ」を展開したという。以下を参照。
http://homepage2.nifty.com/shihai/report/adpan/report.html
注8
NHKという特有の非商業的メディアが存在するが、死刑問題に関する限り、商業メディアと大差ない。犯罪報道でも近年は商業メディアに追随するようなセンセーショナリズムの傾向が見られる。
注9
日本の幾つかの死刑廃止運動体もインターネット上にウェブ・サイトを開設している。ただ、まだ数的にも少ないうえ、一般に更新ペースが遅く、内容も最低限度のものにとどまることがほとんどで、日本の死刑制度の実情や廃止運動の日々の動きがなかなかヴィヴィッドに伝わってこない。ウェブ・サイトは比較的低コストでミニ・メディアを運営できる有力な手段であるから、もっと活用されてよい。この点では、全米で非常に多くの運動体がウェブ・サイトを開設し、活発な情報提供を行っているアメリカの状況を見習う必要もあるだろう。
|
|
- 【非処罰プロジェクト:死刑廃止を超えて3-②(下)】 如往 2008/1/28 04:17:15
(3)
- 【非処罰プロジェクト:死刑廃止を超えて3-③】 如往 2008/1/28 04:26:16 (2)
|
|
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
|
|
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。
|
|
|
|
|
|
|
|