2019�N10��31��
�Љ��`�͂���ȂɈ�����
From ���l��Y@�]�_��/���m�ڑ�w�q������
https://38news.jp/politics/14856
�u�Љ��`�v�Ƃ����Ă��A�����₩�Ẵ\�A���m�肵�悤�ȂǂƂ����b�ł͂���܂���B
�ꕔ�ň��]���̍����V���R��`�C�f�I���M�[�́A�ȉ��̏����ڂ����`�Ƃ��Ă��܂��B
(1)�����Ȑ��{
(2)���R�f�Վ�`
(3)�K���ɘa
(4)���ȐӔC
(5)�q�g�A���m�A�J�l�̈ړ��̎��R�i�O���[�o���Y���j
(6)�Ȃ�ł����c��
(7)���������`
�����݂͌��ɗ��ݍ����A�e����^�������Ă����̒����ւƎ��ʂ��Ă����܂��B
���̒����Ƃ́A���z�̃J�l�����܂��������ҁA���ۃ��[��������ҁA���ƒ�����j��҂���������Ƃ����I���Ȓ����ł��B
(1)�́u�����Ȑ��{�v�_�҂́A(3)�́u�K���ɘa�v�����ɂ������Ƃƍl���A(6)�́u�Ȃ�ł����c���v�𐄐i���A(7)�̋��������`���m�肵�܂��B
���̌��ʁA�ߓ����������܂�A���E�͗D����s�̏�ԂƂȂ�܂��B
�s�҂͂��ׂ�(4)�́u���ȐӔC�v�Ƃ������ƂɂȂ�A�N���~�ς̎�������L�ׂ܂���B
�܂��A(2)�́u���R�f�Վ�`�v�́A�o�ϗ̝͂h�R���Ă��鍑�ǂ����ł���A�������삯�����̏�ƂȂ�܂��B
�������ӂ��͋��オ�����������܂��Ă���̂ŁA�����́u���R�v���㏬���́u�s���R�v�Ƃ��Č���܂��B
��������(5)�̃O���[�o���Y�����҈Ђ��A���{�ړ��̎��R�����Z���{���剻�����A���̌o�ς́A�����������Z����ɕ�d����悤�ɂȂ�܂��B
���ԑw�͒E�����A�J���҂̒����͗}������A�n�x�̊i���͊g��̈�r�����ǂ�A�Y�Ǝ��{�Ƃ͐₦�����Z�����Ɓi�劔��Ȃǁj�̊�F���M���悤�ɂȂ�܂��B
�P�C���Y���A�Y�Ǝ��{�ƊK���ƁA����ł��铊���ƊK���Ƃꎋ���Ȃ��������R�������ɂ���܂��B
�Ƃ���ŁA�Љ��`���Ƃ�W�Ԃ��Ă����\�A�����Ă���Ƃ������́A�Љ��`�Ƃ����Y��`�ƕ����A�厸�s�̎����ł��������̂悤�Ȋ��o�����E���ɍL�܂�܂����B
���̔����Ƃ��āu���R�v������̌o�ϗ��O�Ƃ���C�����x�z�I�ƂȂ�A���ɎЉ��`�v�z�͂��ׂă_�����Ƃ������u�Љ��`�A�����M�[�v��������O�̂悤�ɒ蒅���Ă��܂��܂����B
���̊��o���A�o�ςɂ�����V���R��`�̏����̉����Ɉ���Ă��܂��B
���X�ɔᔻ���͂��u�l���v���đS�̎�`���Ƃ𐬗��������̂̓X�^�[�����ł���A���̊�b�ƂȂ郍�V�A�v�����N�������̂̓��[�j���ł���A���̃��[�j���̓}���N�X�̎v�z�ɂ��ƂÂ��ĎЉ��`���������������A������A�X�^�[���������[�j�����}���N�X�ƘA�z���͂��炩���āA�����̍����̓}���N�X�̎Љ��`�v�z�ɂ�������A�Ƃ����b�ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�������{���ɎЉ��`�͂��̌o�ϗ��O���炵�ă_���Ȃ̂ł��傤���B
���������A�z�Q�[���ŕ����f����̂́A���j�̎��������悤�Ƃ��Ȃ��A���܂�Ƀi�C�[�u�Ȏv�l��H�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�M�҂́A���낵���ϓ]���鐢�E�j���A�l�ƌl���Ȃ��A�z�Q�[���I�Ȏv�l�ʼn��߂�����@�ɂ́A�傫�Ȍ��������A�ƒ��N�l���Ă��܂����B
�\�A�́A�Ȃ������̂��B
�ł��傫�ȗ��R�́A�u���Y��`�v�Ƃ����C�f�I���M�[���f�����������ƍٌ��͂������ɋ�����A�l�X�̌o�ϊ����ւ̈ӗ~��r������������ł��B
1956�N�A�t���V�`���t���X�^�[�����ᔻ���s�Ȃ����ɂ�������炸�A�ނ̎��r��A���̊����I�d���͂������Đ[�܂�܂����B
�܂肱�̗��j�̓����́A�n�n�҂̌o�ώv�z�̌��ɂ��̍��������Ƃ������́A�������̃C�f�I���M�[���u�_�̒��v�Ƃ����������͂̑̎��ɂ�������Ƃ݂�̂��Ó��Ȃ̂ł��B
�M�҂́A���Ƀ}���N�X�ʂ���킯�ł͂���܂���B
�ނ̎v�z�ƍs���̒��ɂ́A�\�㐢�I�I�ȁi���܂͒ʗp���Ȃ��j�ߌ��ȗ��z���m���ɂ���܂����B
���̑傫�Ȃ��͓̂����܂��B
���Ƃ̔p��Ǝ��L���Y���̔ے�ł��B
���̐l�����킫�܂��Ȃ������v�������`���Ƃ��Ă��m�肷��킯�ɂ͂����܂���B
�������A�Љ��`���͂̌����I�Ȍn�������ǂ��Ă݂�Ƃ������̔���邱�Ƃ��킩��܂��B
����܂����ɁA�n�n�҂��ǂ�Ȍ����F���Ɗ�{�\�z�������Ă������ɖډB�������邱�Ƃ́A�v�z�I�ɂ͋�����܂���B
�}���N�X�́A�傽�銈���̕�����A�������̏o�̐����Ŕe�����ƂƂ��Ă̒n�ʂ��m�����������C�M���X�̎�s�E�����h���ɒu���Ă��܂����B
�����Ŕނ��������̂́A�N���̎q�ǂ������܂ł��ߍ��ȘJ���ɒǂ���鐭���o�ϑ̐��̂��тȎp�ł���A�����ɑ�ʐ��Y�ɂ���ċ����ׂ����Y�͂����������鎑�{��`�̗͂ł����B
�}���N�X�̓����߂Ă����̂́A�O�҂̉ߍ��Ȏ��Ԃ����Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����e�[�}�ł������A�����ł́A��҂̋���Ȑ��Y�͂�ے肷�邱�Ƃł��̉ۑ���������ׂ����Ƃ͂������čl���܂���ł����B
���̋���Ȑ��Y�͂̔閧�ł��鎑�{��`�̐����̍\����ے肷�邱�Ƃ́A���n�����ւ̉�A���A�����������q�̓I�Ȓ����ւ̋t�߂���Ӗ����܂��B
�ނ͂����l���܂����B
���{��`�̐��Y�͂͐l�ނ����グ���x�̈�Y�ł���A���������ɔ��W�����āA���Y��i���ꈬ��̎��{�Ƃɐ�L�������A��葽���̐l�X�ɕ��z���邱�Ƃ������A���̉����Ɍ��т��A�ƁB
�}���N�X�́A���{��`��ے肵���̂ł͂Ȃ��A���{��`�Ƃ�����Y�l�ɂƂ��Ă̂��̂ɂ���ɂ͂ǂ�����悢���ɓ���Y�܂����̂ł��B
���̍\�z���������邽�߂̐����I��i�Ƃ��āA���Y�ҊK���̒c���ƁA�\�ԓI�ȃu���W���A���Ƃ̎~�g���Ăт������킯�ł��B
���̍\�z���n���邽�߂ɂ́A�ނ��A�����h���Ƃ��������̐��E�o�ς̍Ő�[�ŁA���̖��Â̗��ʂ��ώ@����Ƃ����������K�v�ł����B
���Đ��E���́u�Љ��`�v���v�������������Ƃ���郍�V�A�́A�����ǂ̂悤�ȏ�Ԃɒu����Ă����ł��傤���B
�c�@�[���̈����̂��ƂɁA�命���̖��w�Ȕ_�z�������Љ�ӎ��ɖڊo�߂邱�Ƃ��Ȃ��A�����n���̂����ɖ��荞��ł����̂ł��B
�Y�Ƃ͂قƂ�ǔ��W���Ă����A�}���N�X���v���̕K�{�����ƍl���Ă������{��`�I�Ȑ��Y�l���͂܂������������Ă��܂���ł����B
�}���N�X�́A���V�A��x�ꂽ���Ƃ��Čy�̂��Ă��܂������A���̍��Ŕނ̍\�z����Љ��`�v�����N����ȂǂƂ͖��ɂ��v���Ă��܂���ł����B
�x��ēo�ꂵ�����[�j���́A�܂�Ɍ���C���e���ł������A���V�A�̌�����Ƃт���J���Ă��܂����B
���̍��������ł��ǂ�����ɂ́A�g�D�I�Ȗ\�͊v�����N���������Ȃ��A�Ɣނ͍l���܂����B
���̎��ނ̖ڂɁA���ꂱ���g����Ɖf�����̂��A�}���N�X�̎Љ��`���_�ł����B
���������V�A�̌���͑��ς�炸�ŁA�}���N�X���Љ��`�����̕K�{�����Ƃ��Ă������{��`�̍��x�Ȕ��W�Ƃ����i�K�ɂ͎����Ă��Ȃ������̂ł��B
���[�j���́A���̎Љ�����̃M���b�v�����܂����B
�C�Â��Ă��Ȃ������͂��͂Ȃ������Ǝv���܂����A�����I���@�̏Ք����A���̃M���b�v�ɂ��Ă̔F����}������ł��܂����̂ł��傤�B
�܂胍�V�A�v���Ƃ́A���{��`���܂��n���Ă��Ȃ��������V�A�Ƃ������y�ɂ��������Ȋv���A�Ƃ������̓N�[�f�^�[�ƌ����Ă��悢���̂ł��B
���E�̃C���e�������́A���̃N�[�f�^�[�ɏՌ����A�x�z�w�͐[���ȓ��h�Ɋׂ�܂����B
�J���ҊK���͂����ɑ傫�Ȋ�]�����o���A���{�ƊK���͑傫�ȘT�����B���܂���ł����B
�ނ�͓����̃��V�A�̎��Ԃ�������ƕ��͂����A��l�ɁA���E���̎Љ��`�v�������������A�ƍ��o�����̂ł��B
���̏؋��ɁA���肱�����_�������́A�v������Ȃ��킩��Ȃ��܂܂ɁA��ւ����V�������͂ɏ]���������ł��B
�܂����[�j���̎���A���͂��������X�^�[�����́A�ꍑ�Љ��`���f���A�����̎��{��`�����Ɉꍏ�������ǂ������ƁA�S�̎�`�I�Ȑ����̐��̉��ɁA���X�ɋ����ȎY�ƌv���i�߂Ă����܂��B
���Ύ҂̑�ʂ̏l���A�����J���A�������e���Ȃǂ̉��_�́A�������Đ��܂ꂽ�̂ł��B
���ǁA���V�A�v���Ƃ́A�x�ꂽ�Љ�̐���ł��āA�ߑ㎑�{��`���Ƃ����݂��邽�߂̂��̂������̂ŁA�}���N�X�̍\�z�Ƃ͂͂������ʂ����ׂ����̂Ȃ̂ł��B
������u���V�A�E�}���N�X��`�v�Ƃ�������Ȗ��ŌĂт܂��B
���Ă����l���Ă���ƁA�����������ă\�Η����A���̌������Ƃ͈���āA���R��`�u�r�Љ��`�Ƃ����C�f�I���M�[�Η��ł͂Ȃ��A�܂��o�ϑ̐��̈Ⴂ���߂���R���ł��Ȃ��A�ނ���A�����Ԃɔe�����ƂȂ����A�����J�ƁA�ƍِ����ɂ���ċ}���ɗ͂�L�����V�����{��`���\�A�Ƃ́A�P�Ȃ鐭���I�Ȕe�������ł���Ƃ������Ԃ������Ă���ł��傤�B
���ܖ��ƂȂ��Ă���Ē��f�Ր푈���A�����悤�Ȏ��{��`���Ƃǂ����̗͂Ɨ͂̌��˂ɉ߂��Ȃ��ƌ��Ȃ��K�v������܂��B
�������������Ɏs��o�ς�������Ĉȗ��A���̍��́A���O�����͎Љ��`���f���Ȃ���A�����I�ɂ͒��؉�������Ɠ����ƍّ̐����̂�A�o�ϓI�ɂ͍Ő�[�ƌ����Ă��悢���{��`�̐����̂��Ă��܂��B
���[�j�����ł��|���Ώۂƍl�����u���ƓƐ莑�{��`�v���܂��ɒn�ōs���Ă���킯�ł��B
�ł́A�`���Ɍf�����V���R��`�̏����́A�ǂ�����Η}������̂ł��傤���B
����ɂ́A��̕��@���l�����܂��B
��́A�L�͍��Ƃ����c���āA����}�Ȍo�ϓI�u���R�v���K�����郋�[������邱�Ƃł��B
���{��`��ے肷��̂ł͂Ȃ��A�s��̎��R��m���̈ړ���בւɂ��Ẵ��[�������������������ꂽ���̂ɂ��܂��B
����������́A���ɉ����Ă��鍑�ێЉ�̌����A�O���[�o���Y���ɏ�������Ē鍑��`�������ɐi�߂Ă��钆���̂��Ƃ��l����ƁA���ӂ�̂��ɂ߂ē���ł��傤�B
����Ɠ��ʁA������̕��@�ɗ��炴��܂���B
����́A���ꂼ��̍��Ƃ��A�����̌o�ς̔\�͂ƌ��E���悭���͂��A���ꂼ��Ɍ��������`�ŁA����}�Ȍo�ϓI�u���R�v�̐N���ɑ���h�g��ƂȂ邱�Ƃł��B
���ē��{�͏�k�����Ɂu���̎Љ��`�����v�ƌ����Ă��܂����B
����́A�K�v�ɉ����āA���{���K�Ȋ֗^�����A�܂���Y�Ƃ͍��L��Ɓi���Ёj����������ł��B
���܂̐�����������قƂ�ǂȂ��������Ԃ́A���ƂƂ��Ă̎��E�s�ׂƌ�����ł��傤�B
�o�ς�����قǐ��ނ��A���S�̂̒�������R�Ƃ��Ă��邢�܁A���܂��܂ȕ���ł̌���������ϋɓI�ɑ��₷�K�v������܂����A���{���o�����X����R���g���[�����Ƃ��Ă����K�v������܂��B
���̂��߂ɕn���⎸�Ƃ��Ȃ����i��������Ƃ����A�Љ��`�����Ƃ��Ǝ����Ă�����{���@�̂����Ƃ�����������K�v������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����́A�ŋߘb���MMT�ɂ����Ȃ����̂��ƕM�҂͊m�M���Ă��܂��B
���Q�l�F�ْ��w13�l�̌�����ꂽ�v�z�Ɓx
�摜
https://www.amazon.co.jp/dp/4569826822
�y���l��Y����̂��m�点�z
�����ƗR�I���ꎁ����ɂ���u�v�z�m�E���j��v�̑̐������Ȃ�[���������̂ƂȂ�܂����B
��x�A�ȉ��̂t�q�k�ɃA�N�Z�X���Ă݂Ă��������B
https://kohamaitsuo.wixsite.com/mysite-3
���w�ϗ��̋N���x�i�|�b�g�o�Łj�D�]�������B
�摜
https://www.amazon.co.jp/dp/486642009X/
���w���{��͓N�w���錾��ł���x�i���ԏ��X�j�D�]�������B
�摜
https://www.amazon.co.jp/dp/486642009X/
https://38news.jp/politics/14856
��������
�@���āu�ԋ��|(Red Scare)�v�Ƃ����錻�ۂ��������B�P�X�T�O�N��̃}�b�J�[�V�Y���̂��Ƃ͂悭�m���Ă��邯��ǁA�P�X�P�O�N��́u�ԋ��|�v�ɂ��Ă͂���قǒm���Ă��Ȃ��B
�@�P�X�P�V�N�Ƀ��V�A�v�����N����ƁA�A�����J�ł��A�i�[�L�X�g�����ɂ�镐���������n�܂����B�P�X�P�X�N�̓����������e�e���ł́A�p�[�}�[�i�@�����̎���܂Ŕ��j���ꂽ�B���{�͂���ɂ���āu�����I�N�͋߂��v�Ƃ����S���`�������B
�@���ܕ����Ɓu�o�J�o�J�����v�Ǝv���邾�낤����ǁA���̓�N�O�A�܂�������ȂƂ���ŋ��Y��`�v�����N����͂����Ȃ��Ǝv���Ă������V�A�Ń��}�m�t�����������Ƃ����ԂɊ��������̂ł���B�����͖��̒��ł���B�A�����J�ł����ĉ����N���邩�킩��Ȃ��B
�@�Ȃɂ���A�P�W�V�O�N��́u���҂�����v�����A�A�����J�����͂��̕��s�̋ɂɂ���A���{�Ƃ����̎��D�Ԃ���܂���l���I�Ȃ��̂ł��������炾�B���[�j���͈��ꔪ�N�����Ɂu�A�����J�̘J���҂����ւ̎莆�v�̒��ŁA�u�����オ��A������Ƃ�v�Ǝ��q�Ⴕ�A�����N�O���ɂ́A���E�R�V�����̘J���ґg�D�̑�\�҂��������X�N���Ɍ��W���āA�R�~���e�����̎w�����ɐ��E�v����簐i���邱�Ƃ����Ă����̂ł���B
�@�\���v�����_�ł̃��V�A�����̃{���V�F���B�L�̎����͏\���l�B�����N�ɃA�����J�����ɂ͊m�M�I�ȉߌ��h���Z���l�����B���������A�A�����J�̃u���W�����������u�v���߂��v�Ƃ������|�S�ɑ�����ꂽ���Ƃɕs�v�c�͂Ȃ��B
�@�P�X�N�ɐ��肳�ꂽ�@���ł́A�}���N�X��`�҂��A�A�i�[�L�X�g���A�g�������Ƃ��A�i�@�Ȃ��u���A�����J�I�v�Ɣ��肷��A�s�������܂��擾���Ă��Ȃ����͍̂��O�Ǖ��A�s�������擾���Ă�����̂͂������Ɏ��Ă���邱�ƂɂȂ����B���̎d���𐋍s���邽�߂Ɏi�@�ȓ��Ɂu�Ԏ��iRed Hunt�j�v�ɓ��������Z�N�V�������ݗ����ꂽ�B�p�[�}�[�����̔C���ς˂��̂��A�ႫJ�E�G�h�K�[�E�t�[���@�[�ł���B
�@���̃t�[���@�[�͊v���g�D������Z�N�܌�����ɑS�Ăň�ĖI�N����Ƃ����s�m���ȏ����p�[�}�[�ɏグ���B�t�[���@�[�́A��蒲�ׂ����������Ƃ������ނ�̋@�֎��ɏ����U�炵�Ă����ߌ��Ȍ��t�i�u�R�c�X�g����n�܂�A����𐭎��X�g�A����ɂ͊v���I��O�s���Ɋg�債�āA�ŏI�I�ɍ��ƌ��͂�D�悷��v�j�ɂ����قǂ̐����I���͂ȂǂȂ����Ƃ�m��Ȃ���A�p�[�}�[�ɕ����I�N���ؔ����Ă���Ƃ������|�𐁂����݁A����ɂ���Ď����̃Z�N�V�����ւ̗\�Z�z���Ɛ��{�����ł̃L�����A�`�����͂������̂ł���B
�@�t�[���@�[�̂����₫��M�����p�[�}�[�͌܌�����ɁA�j���[���[�N�A���V���g��DC�A�t�B���f���t�B�A�A�V�J�S�ȂǑS�đ�s�s�̑S�����{�݂Ɨv�l�����̎��@�Ɍx�@���������Č����Ԑ��𖽂����B�����A�����N����Ȃ������B�S���̐V���̓p�[�}�[�́u�܌��v���v��}���A�E�b�h���[�E�E�B���\���̎��̃z���C�g�n�E�X�����L�͎�����Ă����p�[�}�[�͂��̑s��ȋ�U��Ő����������������̂����A����͂܂��ʂ̘b�B�@
�@�������������̂́A�A�����J�l�͈ӊO�Ɂu�|����v���Ƃ������Ƃł���B
�@�A�����J�l�͋v�����\�A������Ă����B��킪�I�������̓C�X����������Ă����B�����āA���܂͒���������Ă���B
http://blog.tatsuru.com/2019/10/28_0831.html
��������
���{�l�̔����ɋ��ꂨ�̂̂��Ă��������V�c
���{�{�ɓs�q�܂̓��L
���{�{�ɓs�q�܂̓��L�����㔭�\���ꂽ�B���{�{�ɓs�q�܂͏��a51�N�܂Ő����A����A���̓��L�͔��\���ꂽ�B�悭���\�������Ǝv���B�v���C�x�[�g�ɏ����Ԃ������̂��⑰�����\�����̂��B�����܂ŏ����Ă����畁�ʂȂ甭�\���Ȃ��B���邢�́A���̕����͏ȗ����邩�A���邢�͔��\����O�ɔj��̂ĂĂ��܂����B��������Ȃ������̂͑�ςȗE�C���Ǝv���B
�ɓs�q�܂��A�u���{���������߂��v�ƍl�����̂����a33�N11��27�����B���̂S�����O�A���̍c���q���܂��A��]�I�ȋC�����ɂȂ��Ă����B�u�����Ƃv�͂������B
�@�w���a33�N�V��14���B
�@���݁A�����ƁA���ꂪ�l�̉^�����ˁB
�@���m�c���q�x
�@�ǂ�ȉ^�����Ƃ����ƁA�u�ÎE�����^���v���B���c�́u����v�ɂ́A��������B
�@�w���̓��A�C���N�����t�@�C�T���́A�R���̃N�[�f�^�[�Ɩ��O�̖I�N�ɂ��ÎE���ꂽ�B���w�F�̋��{���������܂��܌䏊�ɏ�����Ă��āA�ꏏ�ɂ���������ł���ƁA���]������������Ƃ����B
�@�u�c���q�͂��̏u�ԁA�����ɂȂ�A��ɂ��Ă����g�������������q��G�̏�ɗ��Ƃ��āA���b���������A�����������ɂȂ�Ȃ������v���A���������߂��Ă����������ꂽ�������B�܂����q�q�܂̎��ƁA���c�Ƃ�������Ŏ����Ă��������B��\��˂ňÎE���ꂽ�����̕s�K�𑼐l���Ƃ͎v���Ȃ������̂��낤�x
(3)�u�_�{�̑�ōŌ�ɂȂ�̂��낤���v�Ɣ߂��������Ƃ�
�@���a33�N�Ƃ����̂́A1958�N���B60�N���ۓ����̒��O���B�����̗͂��������������B�u�V�c���œ|�I�v�����Ԑl�X�����������B�����������{�̕������m���Ă����̂��B�����ɃC���N�����̈ÎE�̕B
�@�������A���w�F���V�тɗ��Ă鎞�ɂ킴�킴�A����Ȏ������Ȃ�āA���]�����������B���c�͂���ɂ��������Ă���B
�@�w�̂��ɁA��㏉�̍��o�Ƃ��ė������A���Őڑ҂����G�`�I�s�A�c��n�C���E�Z���V�F���S���Ȃ�A�C�����̃z���C�j�v���ɂ��p�[���r�������œ|����A�A�W�A����͑��X�A�����������Ă䂭�B
�@���j�_�{�����܂��ƁA���m�c���q�͊w�F�����Ɂu�_�{�̑�ōŌ�ɂȂ�̂��낤���v�Ƃ������Ƃ����x
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2005/shuchou0822.html


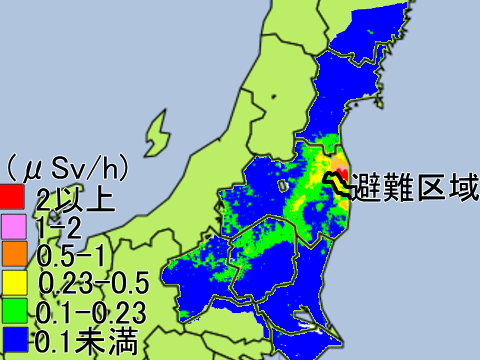
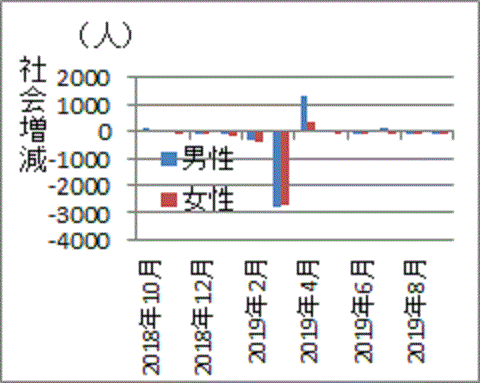
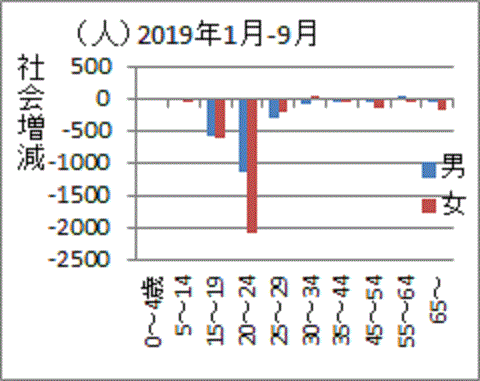
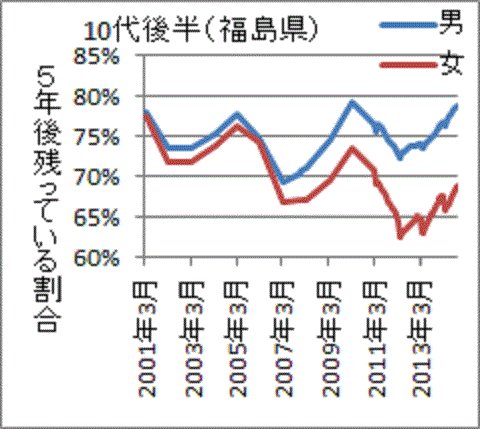
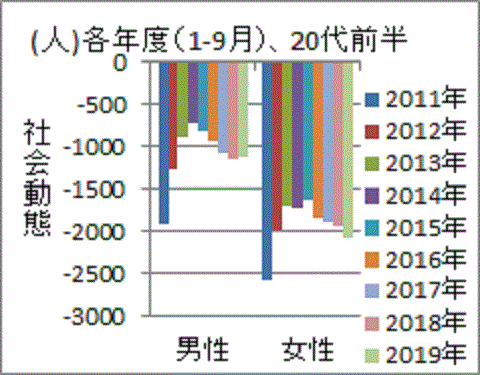
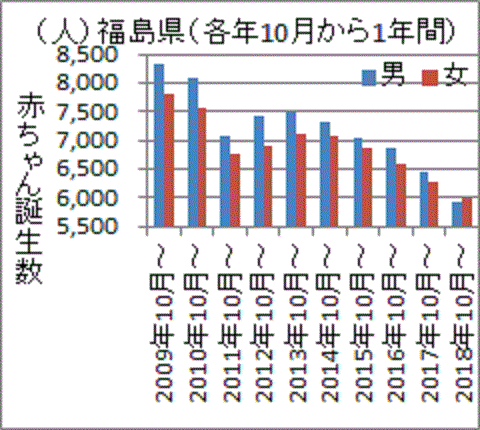

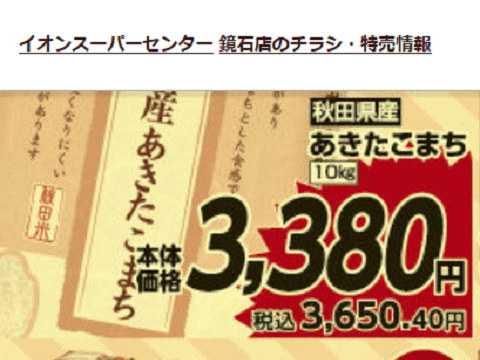
 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B