2019�N09��21��
Craig Stanford�w�V�����`���p���W�[�w�@�킽�������͂��܁u�אl�v���ǂ��܂Œm���Ă���̂��H�x
https://sicambre.at.webry.info/201909/article_48.html
�@�N���C�O�E�X�^���t�H�[�h�iCraig Stanford�j���A�I��m�V��ŁA2019�N3���ɐy�Ђ�芧�s����܂����B�����̊��s��2018�N�ł��B
�{���͂܂��A�`���p���W�[�ώ@�̓���ƁA���̕���ɂ�����O�h�[���iDame Jane Morris Goodall�j���̌��т��������܂��B���ł͓��R�̂悤�ɍl�����Ă���A�`���p���W�[��������g���A�����s�Ȃ��A�W�c�ōU������Ƃ������s���̃O�h�[�����ɂ��́A�����̃`���p���W�[�ς�傫���ς��A���������̎�҂��z������͍̂���ł���A�Ƃ����킯�ł��B
�@�`���p���W�[�͎����s�Ȃ��܂����A�{���I�ɏn�����ʎ��̃X�y�V�����X�g���Ɩ{���͕]�����Ă��܂��B�`���p���W�[�͕��n�I�ȎЉ���`�����܂����A�����R�~���j�e�B�̗Y�̌����x�͂��قǍ����Ȃ��A��������ł������͂�⍂�������ł��B�ŋ߂ł͍Č������i�߂��Ă�����̂́A��ʓI�Ɏ��͗Y�قǎЉ�I�ł͂Ȃ��A�����̃R�~���j�e�B�ɏ������Ă���\��������A�Y�͎����x�z���邽�߂ɓ�������A�Ɩ{���̓`���p���W�[�Љ�̍\����c�����Ă��܂��B�`���p���W�[�̃p�[�e�B�[�T�C�Y�����肷��̂͂����ɐH���Ǝ��̔ɐB�T�C�N���j�ŁA��҂̕����e���͂͑傫���悤�ł��B�`���p���W�[�̎Љ�s���ɂ��ẮA�L�����z��S�̂ő��̗쒷�ނ�����l�ƕ]������Ă��܂��B
�@�O�h�[�����̑傫�Ȍ��тƂ������A�ȑO�̃`���p���W�[�ς�ς����̂́A�`���p���W�[�̖\�͐��ł����B�{���́A�`���p���W�[�̖\�͂��A���܂��܂Ȋ������ɂ����čP��I�ɐ�����Ƃ����Ӗ��ŁA����߂āu���R�v�ƕ]�����Ă��܂��B�`���p���W�[�̃R�~���j�e�B�Ԃ̖\�͂́A���͂��s�ύt�ȏꍇ�ɋN���₷���Ȃ��Ă��܂��B��ʓI�Ƀ`���p���W�[�́A���̃R�~���j�e�B�������ŗD���Ȏ��ɂ͍U�����d�|���܂����A�݊p�Ȏ��ɂ͖\�͍s�g�ɐT�d�ɂȂ�܂��B�R�~���j�e�B�Ԃ̖\�͂Ŏ����Y�ɎE����邱�Ƃ�����܂����A����́A�H�����Ƃ̌��ˍ�������A�R�~���j�e�B�ɂ����ď��ʂ̍����Y�ɂƂ��āA�V���Ȏ����}��������꒣����g�債�ĐH�������[������������A�K���x���グ���邱�ƂƊ֘A���Ă��邾�낤�A�Ɩ{���͎w�E���܂��B�`���p���W�[�̖\�͐��̕\��Ƃ������ɂ͋G�ߐ�������A����͏����l�ނƓ������A���G�ɏW�����Ă��邻���ł��B�������A���G�ɂ͗t�������Ċώ@���₷���Ƃ����肪�����Ă���\�����w�E����Ă��܂��B���̒��S�͗Y�ł��B
�@�`���p���W�[�̎��͂����ނ�11�ΑO��ōŏ��̐���c�����o�����A1�`2�N��ɏo���R�~���j�e�B���o�Ă����܂����A�אڃR�~���j�e�B�Ő������߂�������A�o���R�~���j�e�B�ɖ߂�ꍇ������܂��B�������A13���܂łɂ͏o���R�~���j�e�B�Ƃ͕ʂ̃R�~���j�e�B�ɗ��������A�����ňꐶ���߂����܂��B�`���p���W�[�̎��̓S�����̎��Ƃ͈قȂ�A�ŏ��̈ڏZ�̌�ɍēx�ڏZ���邱�Ƃ͋H�ł��B�ŏ��̎q�����n����m����50%�����ł��B���͂����ނ�5�N�Ԋu�ŏo�Y���A����ɂȂ�قǔD�P���ɂ����Ȃ�܂����A�q�g�̂悤�ȓˑR�̕o���}���邱�Ƃ͂���܂���B�����`���p���W�[�Љ�ł́A���Ƃ��ďo���R�~���j�e�B���痣��Ȃ��������݂��܂����A����͍����ʂ̉ƌn������Ɛ�������Ă��܂��B
�@�`���p���W�[�̑I���ɂ��ẮA�������ڂ���Ă��܂������A�ߔN�ł͗Y�̑������ڂ���Ă��܂��B�`���p���W�[�̗Y�́A�q�g�Ƃ͈قȂ�A�N���̎����D�ތX���������܂��B���̗��R�ɂ��Ċ��S�ɉ𖾂���Ă���킯�ł͂���܂��A�`���p���W�[�̎��̒n�ʂ͍���̂̕����Ⴂ�̂����������ƂƊ֘A���Ă���A�Ƃ̌���������Ă��܂��B����I�Ƃ����`���p���W�[�ł����A�ߔN�A����ِ̈��Ԃ̒������J���m�F�����悤�ɂȂ��Ă��Ă���A�q�g�Ƃ̗ގ������w�E����Ă��܂��B
�@�`���p���W�[�����͐l�ސi�������ɗL�v�ł���A�Ɩ{���͋������܂��B�������{���́A�`���p���W�[�������l�ނƂ�������Ǝ咣���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�`���p���W�[�͏����l�ނ̐i���̓K�ȃ��f���ƂȂ蓾��A�Ǝw�E���Ă���킯�ł��B�܂��{���́A����������v��Ȑ��͗쒷�ނɂ����đ��̚M���ނ�葽��������Ƃ͂����A�����������ł���A�ŏ����l�ނ���v��Ȃł͂Ȃ��������낤�A�Ǝw�E���܂��B���������A�{�����w�E����悤�ɁA����l�������ɂ͈�v��ȂƂ͌����Ȃ������ł��B�l�ސi���j�ɂ�����z��`�Ԃ̕ϑJ�ɂ��āA����I�ȏ؋���͓̂���ł��傤���A����������͐i�W���Ă����ł��傤����A���ڂ��Ă��܂��B
�@�{���̓A�t���J�암�Ŕ������ꂽ�z���E�i���f�B�iHomo naledi�j�ɂ��āA�ŏ����z�����ł���n�r���X�iHomo habilis�j�Ƃ悭���Ă���A�A�E�X�g�����s�e�N�X���ɕ��ނ��錤���҂������邱�Ƃ���A�i���f�B�ɂ���[�u�����v�̉\����S�ے肵�Ă��܂��B�������A�����A�{���̓i���f�B�̔N��ɂ���100���N�O���̉\���������Ƃ��Ă��܂����A���������ɂ�335000�`236000�N�O���ŁA�����l�ށiHomo sapiens�j��l�A���f���^�[���l�iHomo neanderthalensis�j�n���Ɍ�����h���I�����������邱�Ƃ���A�n���I�ɂ��P���Ƀn�r���X�Ɗ֘A�Â��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��悤�Ɏv���܂��i�֘A�L���j�B�܂��A�i���f�B�̑��݂����N��ɂ͏��������l�ނ������͌����l�ނ̒��߂̑c��n�����A�t���J�암�ɑ��݂����ƍl�����邱�Ƃ���i�֘A�L���j�A�i���f�B����[�A�̉��[���ɉ^�̂ł͂Ȃ��A���������l�ނ��֗^���Ă����\��������Ǝv���܂��B�������A����͂܂��v�����ɂ������A�\���͒Ⴂ��������܂��A1�����̋ɏ��Ȃ��Ƃ�15�̕��̃i���f�B�̈�[�����邱�Ƃ���A�{���̑z�肷��悤�ȋ��R�̒~�ς̉\�����Ⴂ�̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B
�Q�l�����F
Stanford C.��(2019)�A�I��m�V��w�V�����`���p���W�[�w�@�킽�������͂��܁u�אl�v���ǂ��܂Œm���Ă���̂��H�x�i�y�ЁA�����̊��s��2018�N�j
https://sicambre.at.webry.info/201909/article_48.html
http://www.asyura2.com/18/reki3/msg/635.html
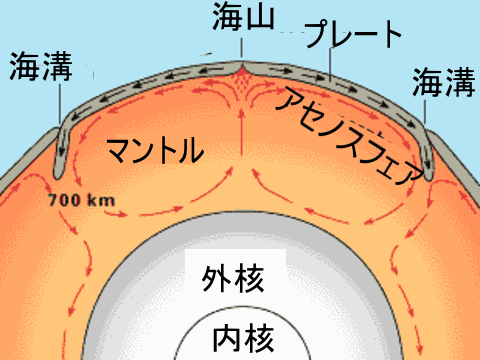

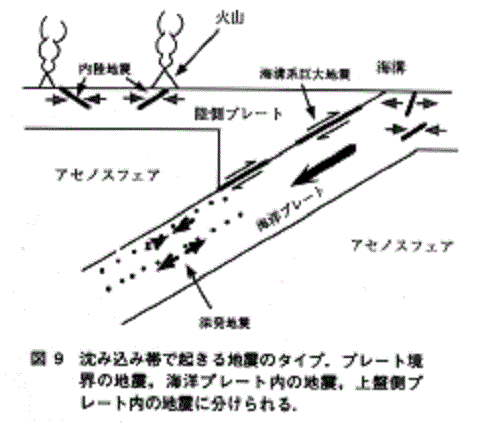
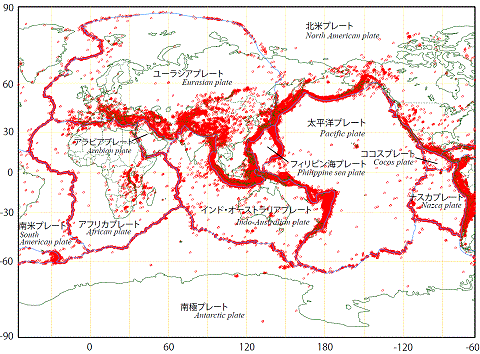
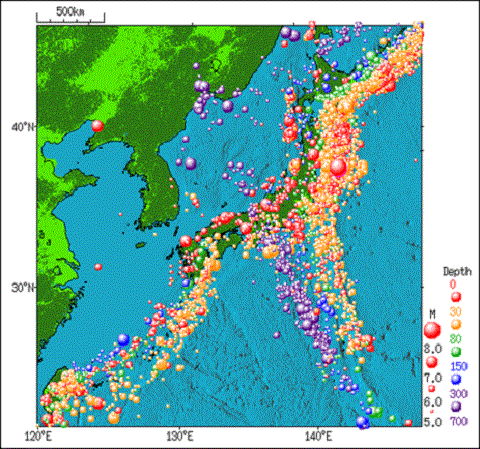
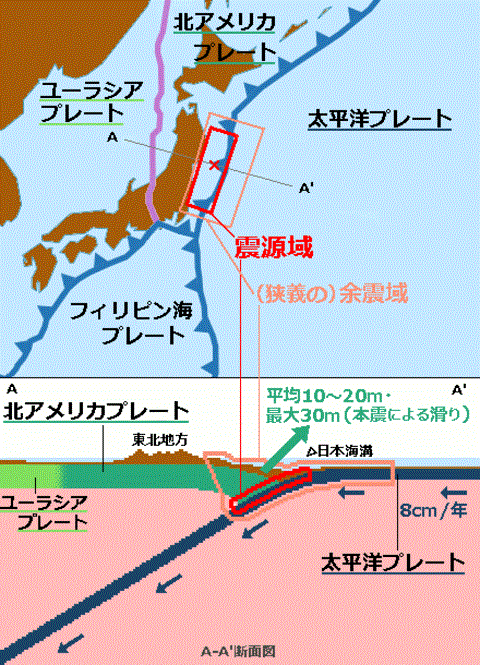


 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B