�܂��Ȃ��A��]�́u�告���Ŏ���v������Ă���@�Ƃ�������Ă������ł������Ȃ�
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53323
2017.12.26�@�T������@�@�F����r�W�l�X
��800���l�����̍�����p�������\�\�B�l�����������A�Ƃ���������Ȃ��łȂ��ߏ�ɍ����Z��B�قƂ�lj��l�̂Ȃ��Ȃ����c��̐���̎����Ƃ́A�����ň�C�Ɂu�����Y�v�Ɖ����Ă����B
�}�C�z�[���Ƃ������̏I���
2028�N����A�c��̐����80�ΑO��ƂȂ�A���̎q������ƂȂ�u�c��W���j�A�v��50�㔼����㔼�A�؎��ɘV��̐������l���Ȃ���Ȃ�Ȃ������ɍ���������B
�������Ă����̂ɏ\���ȔN�������炦��̂��A�V��̈�Ô����ی��͂�������x������̂��B
�Љ�ۏႾ���łȂ��A���{�o�ς̐�s�����̂��s�����ŁA��N�܂ʼn�Ђɂ����邩���킩��Ȃ��\�\���̂悤�Ȑ���ɒǂ��ł���������悤�ɖK���̂��u�����v�Ɋւ����肾�B
�u���t�{�ɂ�镽��25�N�Łw����Љ���x�ɂ��A�c��̐���̎����Ɨ���86.2���Ɣ��ɍ����B1947�N����1949�N�܂ł�3�N�Ԃ̏o������806���l�ł��邱�Ƃ��l����ƁA���ꂩ����{�͐��S�����т̋K�͂Ŏq���e�̎��Y���p���w�告������x�ɓ˓�����̂ł��v�i���c�R���T���e�B���O��\�̎R�藲���j
������ی��E�،��ɉ����āA��⎩���ԂƂ��������z�ȕi���ȂǁA�����̑Ώۂ͑���ɂ킽�邪�A����܂ʼn�X�́A�e�Ɏ؋��ł��Ȃ�����A��������Ί�{�I�Ƀv���X�ɂȂ�Ƃ̎v���Ŏ��Y��e������p���ł����B
���{�̏ꍇ�A�قƂ�ǂ̑����ł����Ƃ����z�Ȃ̂��u�s���Y�v�ł���B
���x�o�ϐ���������o�u���܂ł��o�������c��̐���́A�݂ȁu�Z����낭�v�����ꂼ��ɕ���ł����B�P�g�̃A�p�[�g����X�^�[�g���A��t����ˌ��Ă���ɓ���邱�Ƃ��ЂƂ́u������v�������B
�O��̃}�C�z�[������q���������������Ă����̂�������A�ȂƘV����߂����B�₪�Č��������q�������������߂�A�����̖ʓ|�����Ă���邱�Ƃ�S�̂ǂ����Ŋ��҂���B
���肵�����������邽�߂ɁA�Ȃ��u�E�ɂȂ炦�v�Ŏ�ɂ����c��̐���̖����A���܂ƂȂ��Ă͂��͂⌶�z�ɂ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�Ƃ����̂��A2028�N�ɂ́A���������邱�Ƃɂ���Ēc��W���j�A�����Y����ɓ����ǂ��납�A�ނ���傫�ȏo��𔗂��邱�Ƃ�������O�ɂȂ邩�炾�B���̍ő�̌������A�ق��Ȃ�ʕs���Y���i�̉����ɂ���B
�u�R�▃�z�Ƃ������s�S�̒��ꓙ�n���s�s�̈ꕔ�������A����s���Y���i�͑S���I�ɉ������Ă����܂��B�l����'08�N���s�[�N�Ɍ����������Ă���ɂ�������炸�A�������Z�������������ꑱ����A�Ƃ����~�X�}�b�`���s���Y�ƊE�ŋN�����Ă��邱�Ƃ�����ł��B
�Z��̋����ߏ肪�i�ނƁA���i�̉��������łȂ��ƕ����̑����ɂ��Ȃ��邱�ƂɂȂ�܂��v�i�s���Y�R���T���^���g�E�����玖������̒����C���j
���|�́u�����Y�v�X�p�C����
�Z��i�̉����ƂƂ��ɁA�c��̐��オ�Z��ł�����ʂ̏Z��A�ނ�̎��ɂ���Ė��p�̒����Ɖ����B
�����l�K�͂Ől�������������n��̃C���t���͗��A�Y�Ƃ����ނ���B�₪�Ď�҂͐��݂��Ȃ��Ȃ�A�f�x���b�p�[���ĊJ���ɏ��ɓI�ɂȂ�B�������āA�s���Y���i�͗ւ������ĉ������Ă����̂��B
��������Ƃ̉��i�́A���̓y�n�̘H��������ɍ��肳���B���݁A�s�s���̕s���Y���i�͂킸���ɏ㏸�X���ɂ��邪�A�s�ꂪ�ЂƂ��ю������ĕ����̔��l��������A�����ō���̕]���z�Ɣ��l�Ƃ̂������ō����傫���o�āA�Ԏ��̑����ɂȂ�P�[�X��������B
�s���Y�炸�ɂ��̂܂܂ɂ��Ă����A�����łɉ����Ė��N�̌Œ莑�Y�ł�ێ���d���̂��������Ă���B�Z��ł���킯�ł͂Ȃ��ɂ�������炸�A�ł���B���Ȃ킿�A�������邾���ő�������u�����Y�v���A�c��̐���̍�����^�[�j���O�|�C���g�Ƃ��ċ}�����Ă����̂��B
�c��̐��ォ�瑊�����邱�ƂɂȂ�c��W���j�A�́A���łɓs�s���ɏZ������L���Ă��邱�Ƃ������B���e�̉Ƃ����Z�n���痣�ꂽ�Ƃ���ɂ���A���̊Ǘ��܂łȂ��Ȃ��肪���Ȃ����낤�B
�����͕����Ă��������ɗ��A�l�ɑ݂����Ƃ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���������đ����l�́u�����ɔ��邩�A���čX�n�ɂ��邩�v�̓���𔗂��邱�ƂɂȂ�B
�������㕨�������ƂȂ������ɔ����肪���������A�z���\�N���߂��Ă���ł��낤�c��̏Z��ł́A�������܂������Ƃ͌���Ȃ��B�Ƃ͂����A�Ƃ���̂���ɂ�150���`300���~�Ƃ��������z�Ȕ�p�̕��S���K�v���B
�E�`�ɂ͂���ȗ]�T�͂Ȃ�����A�����̍ۂ͂������Č��ʂӂ�����邵���Ȃ��\�\�B
�e�q����̌o�ώ�������܂��āA�ꑰ���猩�̂Ă�ꂽ�Ƃ����{�S���ɂ��킶��Ƒ��B���邱�ƂɂȂ�B
���̎��Ԃ��d���������{��'15�N����u�Ƒ����ʑ[�u�@�v���{�s���A�Œ莑�Y�ł����������B�Z����Ă��Ă���y�n�́A�Œ莑�Y�ł̕]����͍X�n��6����1�ƂȂ�̂��ʗႾ���A������A�����̂���u�����Ɓv�ƔF�肳�ꂽ�y�n�Ɋւ��ẮA�X�n�Ɠ��l�̉ېłƂȂ�B
�܂�A�Ƃ���u���Ă��܂��ƁA�Z��������������6�{���̉ېł��y�n�ɂ����悤�ɂȂ����̂��B
�}���V�����͂����Ɛ[��
��ʓI�Ȉꌬ�Ƃ̕����ł��A�Œ莑�Y�ł�20���~�߂�������B����Z�ނ��Ƃ��Ȃ������̔��莞�́u���܁v�Ȃ̂�������Ȃ��B�����������A���łɔ�����͏��X�Ɍ�����ɂ����Ȃ��Ă���B
���̋Ɩ��͈ꌬ�Ɠ��L�̂��̂ł͂Ȃ��A�����}���V�����ł����l�̎��Ԃ��N�����Ă���B
�x�m�ʑ�����Ȍ������̕ĎR�G�����͎��̂悤�Ɏw�E����B
�u���L�҂��s���ɂȂ��������́A���̔����肪������܂ŊǗ����C�U�ϗ������}���V�������ɓ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B��������Ƃ܂��܂��Ǘ��̏�Ԃ͈����Ȃ�܂����A���đւ��Ȃǂ̑���c�ɂ��x�Ⴊ�o��B
���ʓI�Ƀ}���V�����S�̗̂̃X�s�[�h�����܂�A���i�͉�����A������������l�͂�������������Ƃ������̃X�p�C�����Ɋׂ�̂ł��v
���łɃ}���V�����́u�����Y�v���͊e�n�Ō��o���Ă��āA���Z�҂����Ȃ��Z�����Ǘ��g�������������������ĐԎ��o��Ŕ��p���A�Ǘ����C�U�ϗ������m�ۂ������o�͂��߂Ă���B
���x�o�ϐ������Ɍ��Ă��A�z50�N���o�߂��Ă��C�U���܂܂Ȃ炸�V�����̈�r�����ǂ�u���E�}���V�����v�ɓs�s���ł����o���킷�悤�ɂȂ������A������ƂƓ��l�ɉ����x�I�ɍ��㑝���Ă������ƂɂȂ�B
�s�S���ɃA�N�Z�X�̂����s���Y�������Ă���l�Ԃɂ͊W�̂Ȃ��b���A�ƍ����������Ă���l��������������Ȃ��B��������͌�肾�B
�u���łɓ�������̃x�b�h�^�E���A�s�S����1���ԂŒʋΉ\�Ȑ_�ސ�̃j���[�^�E�����ӂł��A������i�݁A�w�Ɨ\���R�x�ƂȂ��Ă��܂��B2030�N�ɂ��������邱��܂łɁA�����c��̐���ɐl�C�����������n�悪�܂Ƃ߂āw�����Y�x�Ɖ����\��������̂ł��v�i�O�o�E�������j
�쑺�����̎��Z�ɂ��ƁA2028�N�ɂ͑S�Z��6899���˂̂����A25�����ɂ̂ڂ�1772���˂��ƂɂȂ�Ƃ����B�܂��V���K�|�[��������w��'15�N�ɔ��\���������ɂ��A���{�̏Z��i��2010�N����2040�N�܂ł�30�N�Ԃ�46����������Ǝ��Z�����B
�܂�A��X���������Ă���s���Y�́A�u�告������v�ɂ�4����1���ƂƉ����A������߂�������ɂ͏Z��i�����z�ɂȂ��Ă���̂��B��X�������M���Ă���s���Y�̉��l�́A�قƂ�ǖ��Ӗ��ɂȂ��Ă��܂��ƍl���Ă����ׂ����낤�B
�d�����鑊���łɋꂵ�މƑ��́A�u�����j�Y�v������邽�߂Ɂu���������v�������́u���[�v�����邱�ƂɂȂ�B
��������������\�������ꍇ�A�s���Y�����łȂ�������ی����ȂǁA�����鎑�Y�̑�������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂���܂ł́A����Ȏ؋���e�������Ă���Ȃǂ̎���Ȃ�����A�����������s�����Ƃ͂Ȃ������B
��������͕ς���Ă��邩������Ȃ��B�ЂƂ̗v���Ƃ��āA2028�N�ɂ́u�V�V���v�����[�������Ă��邱�Ƃ��l�����邩�炾�B
�����ی������Z���^�[�ɂ��'15�N�x�̒������玎�Z����ƁA1�l�ɂ��������p�͕���547���~�ɂ̂ڂ�B
����p���ƌv�ɋ����A�e�̒��������łȂ��q�����オ���Y�������o���Ă��鐢�т��������낤�B����ł��A�e���瑊�������Ƃ�u�s���ė����v�Ŏ��߂���Ǝv���������B
�Ƃ��낪�A�������҂��Ă����ɂ�������炸�A�u�����Y�v�𑊑����邱�ƂɂȂ�����ǂ����낤���B�����l�ł���Ȃ��獂��҂ƂȂ�ƁA�V����������������đ��������U���邱�Ƃ��قڕs�\���B��������Ƒ����������A�I�����̈�Ƃ��Ă��܈ȏ�Ɍ�������ттĂ���B
�u���[�v���ł��Ȃ�
�����Ă��̑����l���₪�ĉ�삳��鑤�ɉ��Ƃ�������B����̉���p�ɉ����A�����ł̐Ԏ��Œ�����傫�����茸�点�A�c��W���j�A�̎q������Ɏc��̂͂��ꂱ���u�����Y�v�̂݁B�������ĉߋ��̕����ꑰ�������p�������邱�ƂɂȂ�̂��B
�u���[�v�͕s���Y�p�����A���̂܂܍��ɍ��Y�Ƃ��Ĕ[�t������@�����A���͕��[�͂��Ȃ�n�[�h���������B�Ƃ����̂��A�גn�Ƌ��E���������܂��ȓy�n��A�����ʐς��o�L��ʐςƈ�v���Ă��Ȃ��y�n�͕��[���F�߂��Ȃ��B
���̂��ߎ��ӏZ���Ƃ̌����W�̒����⑪�ʁA���m�ȓo�L��������ƍς܂��Ă����K�v�����邪�A�����ɂ������p�͂��ׂđ����l�̎����o�����B
�����u�����Y�v�������ł�����͂������̍ۂɂ����Ă��A�����l����������ꍇ�́A�u�����v���u�����v�����Ă��܂����Ƃ����O�����B
�u�s���Y�̑����ő�������P�[�X�������Ă����Ȃ��ŁA�s�v�Ȏ��Y�́w�����������x���Ƒ��Ԃő������邱�ƂɂȂ�ł��傤�B�w�����͂��邯�ljƂ͂���Ȃ��x�ƒN���������o������Ō�A���������͂���܂ňȏ�ɓD��������̂ł��v�i�ŗ��m�@�l�^�b�N�X�E�A�C�Y��\�̌\�����F���j
�{�A�ڂ̑�3��ł͏��L�҂��s���ɂȂ��Ă��܂����u���L�n���v�����グ�����A���������≟���������������A�s�����Ƒ���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��s���Y���������Ă������ƂɂȂ�B
��x�u�����Y�v�̃X�p�C�����Ɋ������܂��Ύ��Ԃ��̂��Ȃ����ƂɂȂ�B��]����Ԃ��Ȃ������ɁA�������̉ƌv�����������܂��܂Ȗ�肪�ꋓ�ɂ̂��������Ă���B���ꂪ2028�N�ɑ҂��錻���Ȃ̂��B
�u�T������v2017�N11��4�������


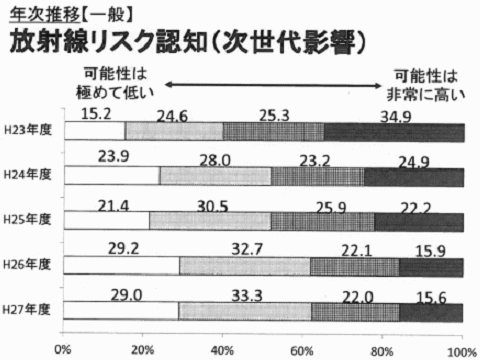
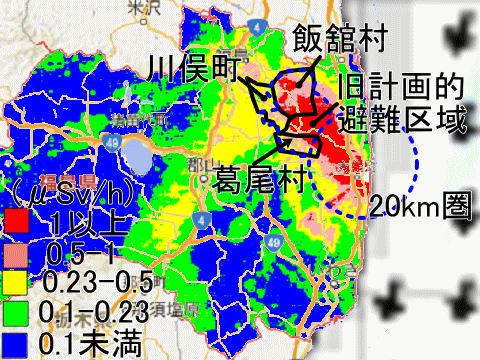
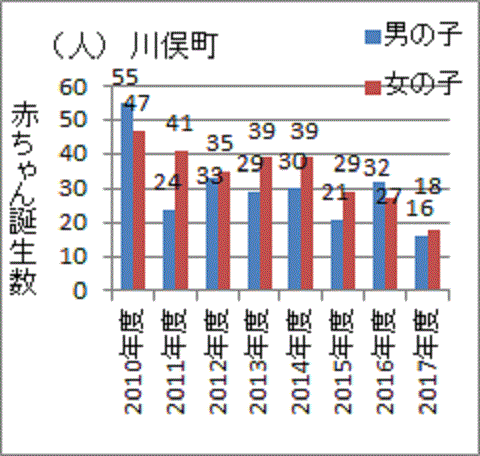

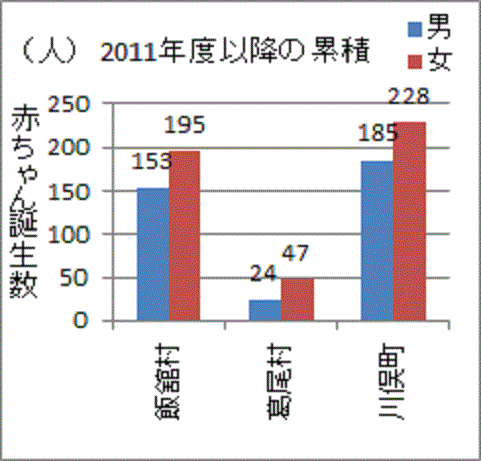
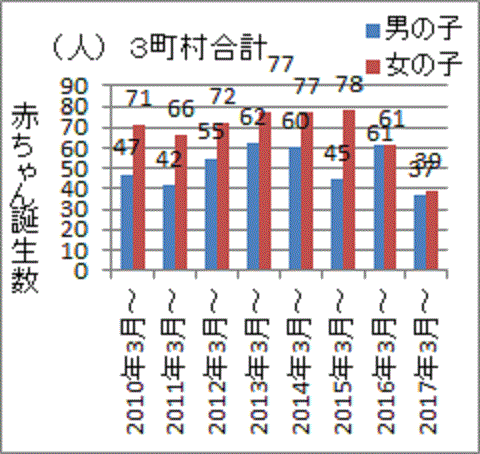



 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B