�u�Ɍ��̖����`�A���r�A�V�q���v�{������^�����V���Ёf�W�Q�N�@���甲��
�i1965�N�A6�`7���j
��T�o�N�̎�s�����h��
�@�����h�̒��̊O�ς̕ϗe�͂��Ă����A���{�̂悤�ȍ����痈�����s�҂ɂƂ��ẮA���̎�s�͂�͂�܂��ٗl�Ȓ����Ǝv���B�啔���̃C�X���������ł́A���ꂭ�炢�傫�Ȓ����ƁA���F�[���i�u���J�j�����Ԃ��Ă��Ȃ������݂��邵�A�g���R��C�����͖@�I�ɔp�~���Ă��邪�A�����h�ł͏��̂��ƂȂ��P�O�O�����F�[�������Ԃ��Ă���B�f����݂��Ă���̂́A���q�@�̃X�`�����f�X�ƊŌ�w�������Ƃ������A
�X�`�����f�X���Ō�w���A�p���X�`�i��o�m�������肩��h�A���h���ꂽ�w�l�������B�T�E�W�o�g�̕w�l�ł́A���Ɉ�l�Ƃ��đf����o�����҂����Ȃ��������ƂɂȂ�B
�@�܂��A���Ƃ��ƃC�X�����Љ�ł́A�����Ƃ��ď@���E�����E�@�����������Ă��Ȃ��B�C�X�����@�͋ߑ�@�ƈقȂ�A���߂ӂ����������܂˂��A���[�́A�͂��肵��ʈӎu�ɂ�鋳���̈ꕔ�ł����āA�A���[�̈Ӑ}������ł���ɏ]�����Ƃ����@����邱�Ƃł���B���������l�����Ɠ��R�֘A���āA�C�X�����@�ł͌��@���s���S�ł���A�c�B
��e�ŐT�ݐ[���x�h�E�B�������`������������
�@�i�����̃x�h�E�B������[�H�̏��҂��A�o������ƁA���ҋq��菭�Ȃ��q�W�܂��炪�O�B����������ĉ��X�Ə��荇��������j
�Ᏽ�҂̉h�_��
�@�u�^�[���A�^�[���i�ǂ����A�ǂ����j�v�ƁA���������H���̍��ɁA���Ƃł����ƌ݂��ɑ��������������́A���̌��Ɍ���ꂽ�B
�@�݂�Ȃ̐H�����̃X�s�[�h�����݂��Ă������Ǝv���ƁA�˔@�Ƃ��ĐH���͒��f����A���������B�p�ӂ���Ă������ŊȒP�Ɏ��ƁA�ӂ����Ȃ��ƂɁA�q�����͂��̂܂܃h���h���A�肾�����B���Ҏ҂Ɂu�����������܁v�Ƃ����Ƃ����킸�A���Ƃ������������Ȃ��B
�@���ƂȂ��ςȋC������̂ŁA�ʖ�ɕ����ƁA�������͏��Ҏ҂Ɂu���҂���h�_��^���Ă�����v�̂ł������B
�������ǁ�
�@�����h���o�������Ƃ��A���{���ǂ̓K�C�h��ʂ��Ď������ɂ������������[�u�x�h�E�B���̏��ɂ͋߂Â��Ȃ��悤�ɁB�ʐ^���Ƃ�Ȃ��悤�Ɂv�B�c
�@�G�X�L���[��j���[�M�j�A�̎�w�����́A�����̔�ׂ��牽�Ƒ����C�S���m�ꂽ���Ƃ��낤�B���̌����č������F�[���́A���{�l�Ƃ��Ă̎������ƁA�ł��A���r�A�I�A���r�A�l����x�h�E�B���Ƃ́A������ǂ��ے����Ă��邩�̂悤���B�x�h�E�B�����G�X�L���[��_�j���i�j���[�M�j�A�j�ƌ���I�ɈႤ�_�́A�����镶���l�ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A���n�����A���邢�͖��J�l�ł͌����ĂȂ����Ƃ��B

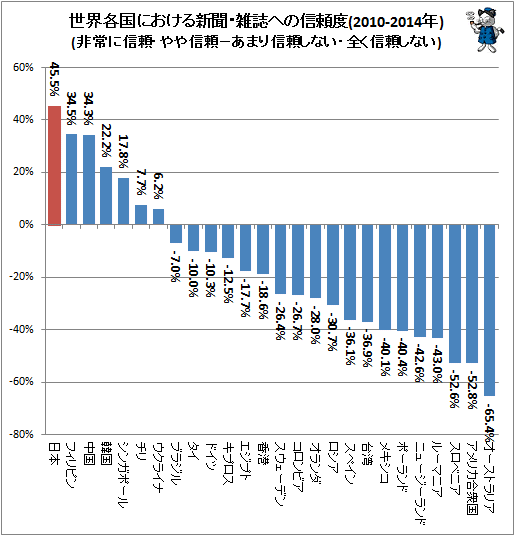
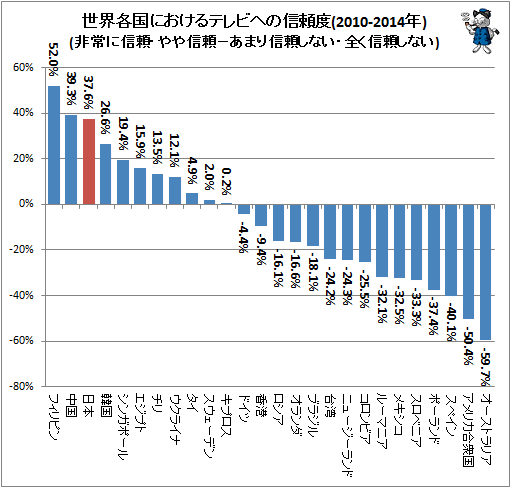





 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B