大企業にも負けない技術力を持っている町工場は、数多くある(写真はイメージです)〔PHOTO〕gettyimages
これぞリアル『下町ロケット』だ! 大企業のイジメに負けなかった「町工場の物語」世界のグーグル相手に戦った男もいる
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/46490
2015年11月23日(月) 週刊現代 :現代ビジネス
阿部寛演じる町工場の社長が、巨大企業に立ち向かう姿が感動を呼んでいる。だが、大企業との戦いはドラマだけの話ではない。技術屋のプライドを守り続ける小さな町工場は、現実にも存在する。
■膨大な注文、そして裏切り
北海道札幌市から東へ約100km。赤平市という小さな町にある植松電機は、主にマグネットの製造・販売を行う、従業員18名の町工場だ。
先代の父から実務を受け継ぎ、同社で専務を務める植松努氏が語る。
「『下町ロケット』、僕も毎週観ています。でも一般の方とは、感想が違うかもしれません。大企業から訴えられたり、理不尽な難題を突きつけられたり……。そんな主人公の姿を観ていると、『うちと同じだなあ』と思ってしまうんです。いまでこそ事業は順調ですが、ここまで来るには、苦労の連続でしたから」
植松電機が設立されたのは、'62年。その後、地道に事業を続け、'90年代には実用的なバッテリー式マグネットシステムの開発にも成功した。
だが、そこから苦難の時が始まったと、植松氏は言う。
「工事現場で鉄板を運ぶ際に使うマグネットシステムの独自開発に成功しました。すると、ある大手企業が、興味を示してくれたんです」
声をかけてきたのは、トラック搭載型クレーンのシェア50%を占め、全国に500ヵ所の営業所を持つ、植松電機とは比べ物にならない大企業。その担当者から、植松氏はこう伝えられたという。
「『開発したマグネットをぜひ我が社で独占販売させていただきたい』と言われ、実際にとてつもない数の注文書を出してきた。事業拡大のチャンスですから、快諾しましたよ。
ただ、その膨大な注文に応えるのは、僕と父さんの二人だけではとても無理。そこで、注文書をもとに銀行から融資を受け、工場を二棟建設し、本社も新築、従業員もどんどん増やしていきました」
だがその翌年、事態は急変する。
「社長が交代したので、方針が変わりました。もう植松電機のマグネットは不要です」
担当者から、そう宣告されたのだ。
「勘弁してください! こっちは借金したばかりなんですよ!」
必死に食い下がる植松氏に、担当者は続けてこう言い放った。
「おたくが勝手に拡大路線を取っただけでしょ。ウチは知りませんよ」
植松氏のもとに残ったのは、2億円もの莫大な借金だけだった。
「とにかく借金をどうにかしなきゃいけないので、日本中を駆けずり回って営業をしました。そして、飛行機に乗るたびに『今日こそ落ちてくれ』と祈った。落ちれば保険金で借金が返せるから、と。僕の子供がもらってきたお年玉を全部取り上げて、支払いに回したこともありました」
■特許を盗もうとする大企業
地道な飛び込み営業を続けたものの、努力は実らなかった。なんとか倒産だけは免れていたが、借金はいっこうに減らなかった。
それでも、転機は訪れた。ある大手建機メーカーが、同社のリサイクル用マグネットに注目。「我が社で使いたい」という申し出があり、共同開発することになった。
だが、またしても予期せぬ苦難が降りかかる。今度は特許侵害問題が起きたのだ。
「仕事を横取りされたと思ったんでしょう。昔からその建機メーカーと付き合いのある会社が訴えると言ってきて、『植松電機が特許侵害をしている』と書いたビラをうちの取引先にばら撒いたんです。すべての取引先が、『もう植松電機からマグネットは買えません』と言ってきました」
植松電機の経営は完全に行き詰まった。だがそれでも、植松氏の心は折れなかった。
長年、マグネットの独自開発を続けてきた植松電機が、特許を侵害しているわけがない——その自信が、植松氏を支えた。
「うちは'70年代からマグネットを作っていました。僕は小学生のときから父を手伝い、その姿を見てきた。だから先に技術開発をされているわけがないと確信していました。
そこで、向こうの特許をよく調べてみたら、やはりうちが先に開発した技術だった。昔の資料や販売実績の書類など、証拠をかき集め、提出しました。それを見て勝てないと思ったんでしょう。相手は訴訟を断念した」
その後は、離れていた取引先も戻り、植松電機は軌道に乗った。現在の売り上げはマグネットだけで約4億5000万円にのぼり、近年はロケット開発などの宇宙関連事業も始めたという。
「苦労から学んだのは、『どうせ無理』と思っては絶対にいけないということです。だからこそ、僕もロケット開発を始めました。皆が諦めてきたロケット開発にうちみたいな小さな町工場が成功すれば、世の中が変わるかもしれないと思ったんです。
いまはマグネットの売り上げが全体の8割で、宇宙関連は2割ですが、いずれこれを五分五分にしてみせます」
■俺たちにしかできないこと
長野県小諸市にあるコイルメーカーのセルコもまた、大企業に苦しめられてきた町工場だ。
'99年に社長に就任した、小林延行氏が言う。
「'70年の創業以来、ずっとうちは大手の下請けだった。それだけに、私を含めて、我が社には『下請け根性』が染み付いていました。元請けがいないと仕事が来ないという『常識』があり、彼らの言うことなら何でも聞いてしまっていたんです。
そのために大企業から技術を盗まれたケースは、思い出せばきりがありません。工場を視察したいと言われて見せてあげると、いつの間にか、彼らがうちの模倣品を製造している。その繰り返しです」
小林氏が社長になったとき、すでにバブルははじけ、元請けである大手も海外に活路を見出している時期だった。盗まれた技術を海外に流され、国内下請けの受注は激減。セルコも窮地に立たされた。
「売り上げが1億円から3000万円に下がると、どこの銀行も融資をしてくれなくなりました。ドラマと同じですよ。『おたくのような経営難の会社に貸せるわけないでしょ』。それで終わりです」
残された選択肢は、社員のリストラしかなかった。45人ほどいた技術者は13人に。平社員時代から、数十年にわたり共に働いてきた仲間のクビを切る。小林氏はその悔しさが、いまでも忘れられない。
「リストラする社員の前で挨拶をするとき、涙があふれて何も言えなかった。『社長として何をしていたんだ』と、情けなくてしょうがなかった」
小林氏は「脱下請け」を決意。発注を待つのではなく、自らトラックを運転して製品の営業を始めた。
ただ現実は甘くはなく、受け入れてくれる企業はほとんどなかったという。
「たまに仕事をくれるのは、開発を行う技術部の人だけ。しかも大量生産する製品の受注ではなく、試作品を作る手伝いですから、注文の難易度が非常に高く、人がやらないようなものばかり。でも結果的に、これがよかった。2~3年必死にやっている中で、うちの技術力はどんどん高くなっていったんです」
そんな中で生まれたのが、セルコの代名詞でもある「高密度コイル」だった。コイルは巻けば巻くほど高性能になるが、密度の限界は約70%とされていた。だがセルコは、ほぼ100%の密度を持つコイルを開発してみせたのだ。
大企業が真似しようと思ってもできない、技術力の結晶。専門誌などにも取り上げられるようになり、セルコには仕事が次々と舞い込んでくるようになった。
「特許も取りましたが、うちみたいな小さな町工場が大企業の製品すべてを監視するのは不可能。もしかしたら、どこかの企業がうちのコイルを真似しているかもしれません。
でも、セルコにかつて『下請け根性』があったように、元請けにもまた、下請けに厳しく自社に甘い体質が染み付いている。だから、うちと完璧に同じものは作れないと思っています。
一方で、うちの技術を認めてくれて、対等に付き合ってくれるメーカーさんもたくさん出てきました。ドラマでもそうでしたが、町工場が生き残るには、『そこでしかできない技術』を生み出すしかないんです」
東京都大田区大森にある、精密板金加工業の金森製作所。「戦う経営者」として知られる同社社長の金森茂氏は、大企業にも町工場の気持ちを汲んでくれる人間がいることを、身をもって知っている。
「'78年に設立した頃は、下請けどころか、うちは3次、4次請けの仕事しかなかった。安いカネで発注を受けて、文句でも言おうものなら『じゃあ他でやってもらうからいいよ』と。それが当たり前でした」
普通の経営者なら、「仕方ない」と諦めるところだろう。だが、金森氏は違った。4次請けだったにもかかわらず、ピラミッドの頂点に位置する大手メーカーへ、直談判するという手段に打って出たのだ。
「ツテもなにもないから、当然、守衛に止められる。いくつもある入り口を全部回ってもダメ。でも諦めずに、7回くらい通い続けた。そうしたら、根負けしたのか、とうとう守衛が入れてくれたんです。
ただ中に入っても、まだ問題はあった。何とか資材課の偉い人を見つけ出したんだけど、やっぱり怒り出すわけですよ。『何なんだお前は! なぜここにいるんだ!』と。
でも、うちの現状を訴えたら、コーヒーをごちそうしてくれて、きちんと話を聞いてくれた。俺は製品を見せて、どれだけの技術力があるかを示した。そうしたら、『じゃあ直接仕事をしましょう』と言ってくれたんだ」
ドラマでは吉川晃司演じる帝国重工・宇宙航空部部長の財前道生が、佃製作所を陰に陽に支えてくれたが、町工場の技術力を認めてくれる大企業の社員は、確かに存在するのだ。
■グーグルに立ち向かった男
たとえ高い技術力を持っていたとしても、大企業と正面から戦い、勝利を収めるのは難しい。だが中には、それをやってのけた稀有な例もある。
東京都千代田区にある、社員8名のIT企業・イーパーセル。同社は、世界売上高約8兆円の「超」巨大企業・グーグルから、開発した技術を守ることに成功した。
'04年から社長を務める、北野譲治氏が語る。
「'96年の設立以来、我が社が獲得してきた特許は、これまでに13件。中には、『自分あてにデータが届いたことを画面上で知らせる仕組み』など、いまでは誰もが当たり前に使っているサービスもあります。
しかし、これは日本企業の体質だと思うんですが、欧米と違い『新しいもの』はなかなか受け入れてくれない。大手企業はやはり大手システム会社と結びついていて、我々が入り込む隙間がない。いくら素晴らしい技術だと説明しても、信用してもらえなかった」
この状況に甘んじれば、開発した技術が陽の目を見ないまま、イーパーセルは潰される。悩んだ末、北野氏が考えだしたのが、グーグルに対する特許侵害訴訟だった。
「グーグルが我々の技術を勝手に使っていることはわかっていました。もちろん巨大な相手であることは承知していましたが、彼らに特許侵害を認めさせれば、世界中に我々の技術力を知ってもらえると考えたんです」
'11年3月に始まった裁判は1年以上続いたが、'12年7月、ついにグーグルが白旗を揚げた。北野氏が言う。
「結果は和解でしたが、これでいいんです。特許ライセンス料が欲しかったわけではなく、技術を認めてほしかっただけですからね。
それからというもの、『買収したい』、『提携したい』といった申し出は無数に来ています。でも、すべて断っている。我々は自力でビジョンを実現し成功したい。カネではないんです」
たとえ会社の規模が小さくても、誇りはどこにも負けない。そんな熱い経営者たちが、日本の技術力を支えている。
「週刊現代」2015年11月28日・12月5日号より






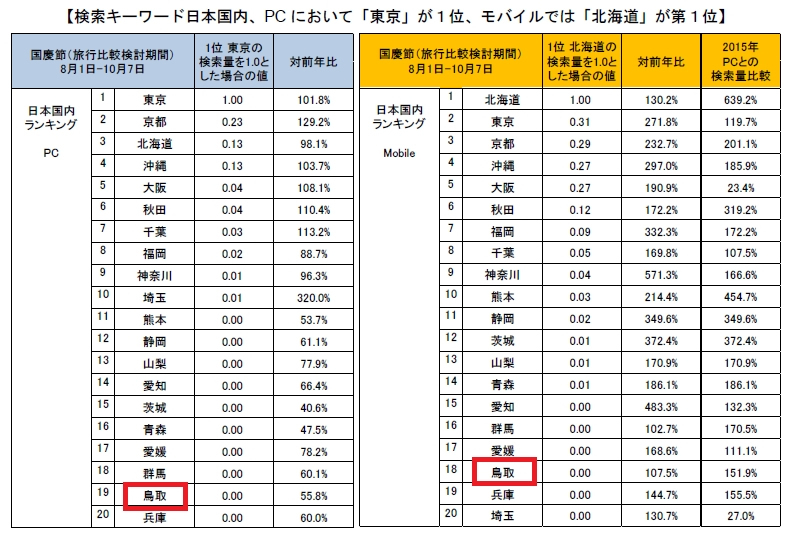

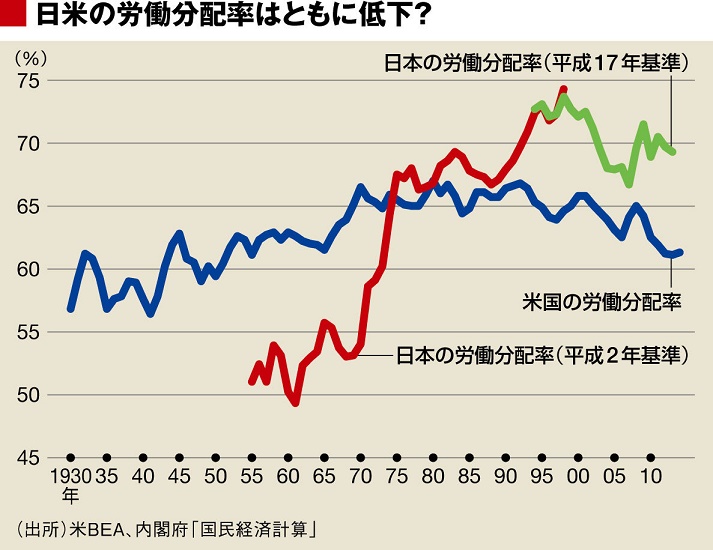
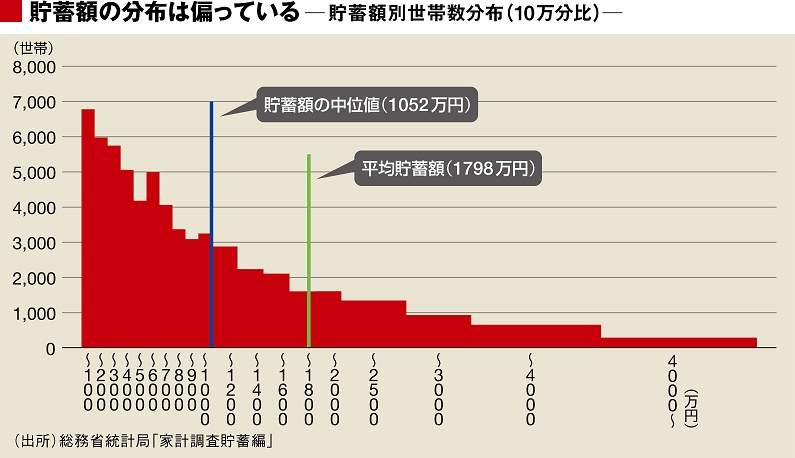
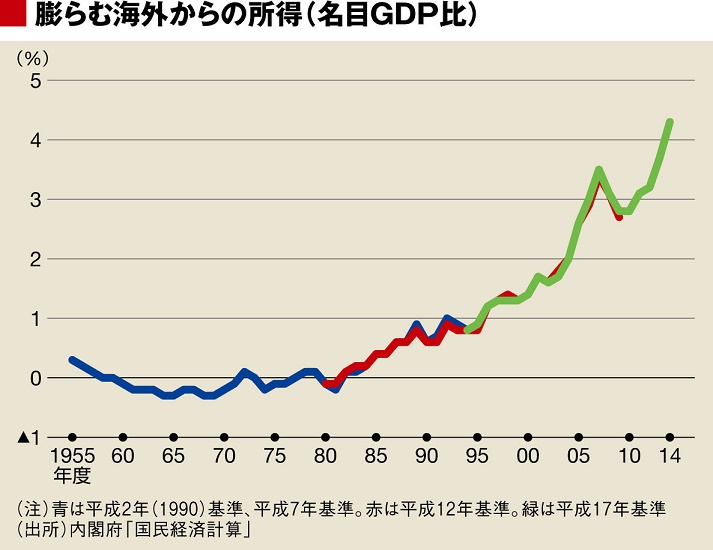
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。