�ė̃v�G���g���R�̃M���V�����̎S���@
2015.7.1�i���j Financial Times
�i2015�N7��1���t �p�t�B�i���V�����E�^�C���Y���j
����������ɂ��f�t�H���g�A���}�ɍ����Ƃ�
�v�G���g���R�͐��N�O���������@�����O����A�u�J���u�C�ɕ����ԃM���V���v�Ƃ���������Ă��� (c) Can Stock Photo
�@�v�G���g���R�ƃM���V���̔�r�͑傰����������Ȃ��B���z�̍���������Ď����̃v�G���g���R�͕ăh�����̂Ă�Ƌ����Ă���킯�ł��Ȃ���A�č����痣�E����Ƌ����Ă���킯���Ȃ��B����Ɋ낤���Ȃ��Ă����M���V���̃��[�����A���B�A���iEU�j�����Ƃ͑ΏƓI�ɁA�ǂ���̃V�i���I���l�����Ȃ����Ƃ��B
�M���V���Ƃ̗ގ��_
�@�����A���ȗގ��_������B�ǂ�Ȏړx�Ō��Ă��A�v�G���g���R�̍����S�͎����s�\���B�����10��5000���h���̗������̃f�t�H���g�i���s���s�j�́A�������7��1�����j���ɂ��N����B
�@����ɁA�v�G���g���R�ɂ͍������X�P�i�J�艄�ׁj���閾�m�ȃ��J�j�Y�����Ȃ��B�č��̏B�ł͂Ȃ����߁A�S��50�B�����p�ł���A�M�j�Y�@9���i�`���v�^�[9�j�̑[�u���s�g���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��B
�@�M���V���ƃ��[�����̂悤�ɁA�v�G���g���R�͕č��o�ς̂��������ȃV�F�A������߂Ă��Ȃ��B�v�G���g���R��������720���h���̍��́A�u�~���j�v�ƌĂ��3��7000���h���K�͂̕Ēn���s��̂����ꕔ���B�����A����ł��č��̒n�������̎j��A�ő�̃f�t�H���g�ƂȂ�B
�@�č��̑S�̓I�Ȏ����R�X�g�\�\����ɂ́A�����グ���ׂ����Ƃ����ĘA�M����������iFRB�j�̌��f�̃^�C�~���O�\�\�ɑ��Ĉ��e���������郊�X�N�������ł��Ȃ��B
�@�o���N�E�I�o�}�哝�̂�������Đ����͍��T�A�v�G���g���R�ɋ~�ϑ[�u��^���Ȃ��ƌJ��Ԃ����B����͐������X�^���X���B�f�g���C�g�s��2013�N�ɔj�Y�鍐�������ɂ́A�A�M���{���珕���������A�~�ϑ[�u�͎Ȃ������B
�@�Đ��{�̋~�ϋ֎~�̌����́A���\�N������Ă����B�����ł��������ɂ߂���A���z�̍�����������̕č��n�������̂Ɋ댯�ȑO�������Ă��܂����ƂɂȂ�B
�@�����A�v�G���g���R�͓Ɠ��Ȍ�����������������قȃP�[�X���B���}�ɉ������p�ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�N�ԏ�����100�������ɏ��v�G���g���R�̍��́A��G�c�Ɍ����ĕč��̏B�̕��ς�10�{���B
�@�č��{�y�Ɣ�r�����v�G���g���R�o�ς̏́A�唼�̃��[���������Ɣ�r�����M���V���̂���Ɠ������炢�����B
�@�l��350���l�̂����J���͂ɂȂ��Ă���̂�4�����x�ŁA�c��č��̖�6�����Ⴂ�B�č��{�y�ɏZ��ł���v�G���g���R�l�̐��́A���ɏZ��ł���v�G���g���R�l���������B�l���͔N�Ԗ�1%�̃y�[�X�Ō������Ă���B
�@�����āA�v�G���g���R�́u�W���[���Y�@�v�̉��ŁA���ׂĂ̐��i��č��Ђ̑D���ŗA�����邱�Ƃ��`���Â����Ă���B����͔�ނȂ��قǍ����A������v�G���g���R�o�ςɉۂ�����x��̖@�����B
�@�v�G���g���R���͂邩�ɋ��͂Ȋό��Ƃ̊�Ղ����n���C�������ƁA����قǍ����A��������Ƃ��������Ă���č��̏B�͑��݂��Ȃ��B
��剻�������I����̓O����v�ƈ��������ɍ����Ƃ�
�@���ےʉ݊���iIMF�j�̌��`�[�t�G�R�m�~�X�g�A�A���E�N���[�K�[����6��26���t�̃��|�[�g�ŏq�ׂ��悤�ɁA�v�G���g���R�̔�剻�������I����̓O����v�̌��Ԃ�ɍ����Ƃ��s���ȊO�ɑI�����͂Ȃ��B
�@�����I�ɂ́A�Đ��{�͊��S�ȏB�̒n�ʂ����߂�v�G���g���R�̗v�����čl���ׂ����B51�Ԗڂ̏B��n�݂��鍢����l����Ɓ\�\���ɁA�R�����r�A���ʋ�i���V���g��DC�j�̓��l�ɓ��قȒn�ʂ�����_�����ĔR�����邱�ƂɂȂ�\�\�A�Z���I�ȉ����K�v�ɂȂ�B
�@�ł������ȍ�́A�ċc��v�G���g���R�Ƀ`���v�^�[9�̋��c�ɓ��邱�Ƃ�F�߂�@���������邱�Ƃ��B
�@�����A�@�Ă͋��a�}�̎x���Ȃ��Ő��i�ł��Ȃ��B���Δh�́A����Ȃ��Ƃ�����A���ۗL�҂��v�G���g���R�Ɏ�����݂���������k�y�I�ɕύX���邱�ƂɂȂ�ƌ����B�M���V���̍��҂��A����ƂقƂ�Ǔ����c�_����g���Ă���B
�@�������A����ȊO�̉\���̕����͂邩�Ɉ����B�S�ʓI�ȃf�t�H���g�́A�č��S�y�̎����̂̎����R�X�g�������グ�邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B�������č��̍������Ƃ̂�����4����3���v�G���g���R�ɑ��ĉ��炩�̃G�N�X�|�[�W���[�i���Z���c���j������Ă���B
�@���̂��߁A�O�i���铹�͂͂����肵�Ă���B�ċc��̓v�G���g���R���f�g���C�g�̂�������Ɓ\�\�����ăM���V�����܂������������Ȃ����Ɓ\�\��^����̂�F�߂�ׂ����B�v�G���g���R�͍����Č��ƈ��������ɁA���̍Č������邱�Ƃ��������ׂ����B
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/44195
�q�s�N�s�̐��E���Z���]
�C�O�@�֓����Ƃ̍ő匜�O�͉��� �M���V�A�ł��č����グ�ł��Ȃ��x���ޗ�
2015�N7��1���i���j�q�s �N�s
�@6���ȍ~�A�s��̘b��̒��S�͐R���̓����ߕt�����M���V�A�ƁA�č����グ�c�_�����ڂ��ꂽFOMC�i�A�M���J�s��ψ���j�̓�ɍi���Ă����B�ǂ�����u�D�荞�ݍς݁v�ƌ����Ȃ���A�������̌����������܂�ɂ�āA�ב֎s��⊔���s��Ȃǂ̕ϓ������g�傳����v���ƂȂ��Ă������Ƃ͎��m�̒ʂ�ł���B
�@���ɁA��T�����[���������������x���ł����鍐���ꂽ�M���V�A�́A���T�͂��߂̊e���s�������ɗh���Ԃ����BECB�ً͋}�������x���̑��g�����₵�āA�����͍��T�͂��߂Ɏ��{�K��������]�V�Ȃ����ꂽ�B6������IMF�ւ̎x�������s�\�ƂȂ�A�����Ȋ��Ҋ������������āu�f�t�H���g�E���[�������E�v�̉\���ɒ��ʂ����s��́A���h���B���Ȃ��B
�@�m���ɓ����̃��[�������E�̌������͔ے�o���Ȃ��B�A���AEU�����ŐM�����[���ƂȂ����̂̓`�v���X�����ł����ăM���V�A���Ƃ��̂��̂ł͂Ȃ��BEU�������̐�������҂��Ă���̂͌��R�̔閧�ł���B7��5���̍������[�́A�������x��������m��Ȃ��܂܍s����Ƃ��������Ԃ�ł��邪�A�����I�ɐ����x���E�s�x����₤���[�ɂȂ�\�������낤�B
���[�������E�O�ɋN���蓾��h���}
�@���f�B�A��6������IMF�ւ̕s�������u�f�t�H���g�v�ƌĂсA���ꂪ���[�������E�ւ̔����J�����˂Ȃ��A�ƕĂ��邪�AIMF�́u�f�t�H���g�v�Ƃ���������������Ă���A�i�t����Ђ�IMF�ւ̕s�����̓f�t�H���g�ƔF�肵�Ă��Ȃ��B���[�������E�̑O�ɁA�܂��h���}�͋N���蓾��B
�@�����I�Ȗ��́A7��20���ɖ�������������ECB�ۗL�̃M���V�A���̍s�����낤�B����܂łɃ`�v���X�������ސw���A�b�萭���̉��Ŏx���Č����s���Ƃ����̂�EU�̑_���ł͂Ȃ����B���Ԃ͌����Ă��邪�A���B�ψ���̃��X�R�r�b�V�ψ����u���̑����͊J���Ă���v�Əq�ׁAECB�̃h���M���ق��u�ً}���������g�c�_�̍ĊJ�͗L�蓾��v�Əq�ׂĂ���̂́A���̕������낤�B
�@EU�ɂƂ��āA������Ƃ��Ẵ`�v���X�͌��̂Ă邱�Ƃ��o���Ă��A���V�A�Ƃ̑Η��W����������ANATO�����o�[�Ƃ��ẴM���V�A���ȒP�Ɍ��̂Ă��ɂ͂����Ȃ��B���������[�����ɗ��߂邽�߂̒�����́A�o��̏�ł���B
�@�����ǂ�ȃh���}���N����ɂ��Ă��A�M���V�A�̉ߑ�ȕ�����EU�̏d�ׂƂ���7���ȍ~���i�����邱�Ƃ͊m���ł���B���[���Ƃ������ʒʉ݂̍\���I�ȐƎ㐫���A���炽�߂ĔF������邱�ƂɂȂ����B�s�ꂪ�M���V�A����Y�������́A�����ȒP�ɂ���ė��Ȃ��B����̃h�^�o�^���́AEU�̒����I�ۑ肪�I�悵�����̂Ƒ�����ׂ����낤�B
�@�܂��č��̗��グ�Ɋւ��ẮAFRB�̃C�G�����c����FOMC�J�Ì�̋L�҉�Łu���グ�͊ɖ��ȃy�[�X�ɂȂ�v�Ƌ������Ďs��s����a�炰�邱�Ƃɕ��S�������A�u�[����������̗����v�͒N�ɂƂ��Ă����m�̑̌��ł���B�ǂ�ȃx�e���������Ƃł����Ă��A�s���̎�͐s���Ȃ����낤�B
�@���グ�̃y�[�X���C�G�����c���̂�����ʂ�u�ɂ₩�Ɂv�i�ނ��ǂ����́A�W���J���Ă݂Ȃ��Ɖ���Ȃ��B�ɂ₩�ȗ��グ�ł������A���Y�o�u�����������Ƃ���FRB�̖ڕW�͑t�����Ȃ��Ƃ�������������B
�@�č����͊��Ɋ����Ƃ������]���蒅���Ă��邪�A���グ�Ɍ����č��͔������A�M���V�A��������i������A�ނ���FRB����i�C�g��Ƃ������n�t���������s�ꂪ�ߔM���A�Ăуv�`�E�o�u���ւ̓�����ݎn�߂�\���͏������Ȃ��B
�u2007�N�����Ɠ���㩂Ɂv�Ƃ̌x��
�@�����̐Ԏ��x���`���[��Ƃɑ���n�C�y�[�X�̎����������A2000�N������IT�o�u�����霂�������̂ł���B�A�N�e�B���B�X�g�Ƃ��ėL���ȓ����Ƃ̃A�C�J�[�����̓W�����N�̉ߔM���Ɍx����炵�u����̑�O��2007�N�����Ɠ���㩂ɛƂ����v�ƌx�����Ă��邪�A���������ւ̌��O���z��ȏ�ɗ��グ�y�[�X������������A���Y���i�̋}����U�����Ƃ��l������B
�@�i�C�ɑ���FOMC�̌��������C�ɌX���n�߂Ă���͎̂������B�m���Ɏ����Ԕ̔��͍D���ł���A�Z��s�������P���Ă����B�l�����ݔ�������������ł���B�����[����������E�o�������ƍl����͓̂��R���낤�B�f�[�^����Ƃ͌����Ȃ���A�������퉻���}���C�G�����c����嗬�h�́A�����E�����㏸�ɑ��Ă��Ȃ�̊��Ҋ������߂Ă���悤�Ɍ�����B
�@�A������ŁAFRB��������͎��R���Ɨ��̒ቺ�Ɋւ��镡���̌x���V�O�i�����o�Ă���B�܂��C���t�����N����悤�Ȍٗp���ł͂Ȃ��A�Ƃ����w�E���B����FRB�̃��T�[�`���[�́A���ɒ������㏸���n�߂Ă������㏸�ɂ͌q����Ȃ��\���������A�Ƃ��������[�����|�[�g�����\���Ă���B
�@�܂��������N�Ԃ�0.5�����x�ɂ܂Œቺ�����č��̐��Y���́A���ݐ������̒ቺ���������Ă���B������ʂ�FOMC�Ŏ����ꂽ�����������͐��Y�����}�㏸���邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���A�ǂ������{�̌o�ύ��������c������̍������S���v��Ŏ������u���b�v�Ɏ��Ă���悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��B
�@���ɕč��o�ς��u���グ���������v�̈ʒu�ɋ���Ƃ���Ȃ�A�N�����グ��������n�߂��i�C�̍���܂��Ă��܂����X�N������B����ɁA���グ�ɔ����h�����̐i�s����ƋƐтƃC���t�����҂ւ̋t���ƂȂ郊�X�N���������悤�B�č����グ���܂��A�u�D�荞�ݍς݁v�ƍς܂�����悤�Șb�ł͂Ȃ��̂ł���B
�M���V�A�ł��č����グ�ł��Ȃ����ړ_
�@�A���A�C�O�̋@�֓����ƂɂƂ��Ă��������M���V�A��č����グ�Ƃ����ޗ��́A�K�������ő�̒��ړ_�Ƃ�����ł͂Ȃ��炵���B���̏������Ă���̂��A�p�����Z�̃o�[�N���C�Y��6�����{�ɖ�900�Ђ̐��E�̋@�֓����Ƃ�Ώۂɍs���������ł���B
�@���̃A���P�[�g�̏W�v���ʂɋ���A���O�ޗ��Ƃ��čł������������A�S�̖̂�20�����߂��u�����y�ѐV�����̌o�ϐ����v�ł������B���炭���̒��S�͒�����肾�낤�B������16�����u�s�ꗬ�������v���ő�̌x���v���ɋ����Ă���B�u�M���V�A���v�͎O�Ԏ�ł���A�u�č����グ�v�́u�n���w���X�N�v�Ɏ����ܔԎ�̃��X�N�v���Ƃ����F���ł������B
�@���݂Ɂu�M���V�A��肪�ǂ�قǐ[�����v�Ƃ����₢�ɑ��ẮA�ŏ����̃l�K�e�B�u�ȉe���ɗ��܂�Ƃ̉���50�����߂Ă���A�O���[�o���ȍ����������N�����Ƃ�����20���̔ߊϘ_��傫�������Ă���B
�@�܂��v�ȋ@�֓����Ƃ́A�M���V�A��č����グ�͋C�|����ȍޗ��ł͂��邪�����o�ς�s�ꗬ�����̕�����قǃC���p�N�g�̑傫����肾�A�ƌ��Ă��邱�Ƃ�����B�i�C�݉��y�[�X���N���ɂȂ�A��C���̍s�����������Ȃ��Ă��������ɂ��ẮA���͂��������K�v���Ȃ����낤�B�����ł́A��Ԗڂɋ�����ꂽ�s�ꗬ�����ɂ��ď����⑫���Ă��������B
���s��ɂ�����ߏ�������
�@���{�s��ɂ����闬�������́A���ĉp�Ȃǂ̒�����s���ʓI�ɘa��Ƃ��č��̑�ʔ�������J�n����������u���ʎs��̋K�͏k�����v�Ƃ��Ďw�E����Ă������A���ꂪ��N�����牢�Ďs��ɂ�����傫�ȉۑ�Ƃ��ĕ��サ�Ă���B
�@��̓I�Ȏ��ۂƂ��Ē��ڂ��ꂽ�̂́u30���N�Ɉ�x�v�ƌ���ꂽ2014�N10���̕č����������̗�������A���N4�`5���ɋN�����h�C�c10�N�����̖��\�L�̋}���ł���B�����������I�ȋ����ϓ��ɑ��AIMF��FSB�i���Z���藝����j�Ȃlj��Č��I�@�ւ́A�ቺ�X���������Ȏs�ꗬ�����ɑ��Ă��ĂȂ��قǂ̊�@����\�����Ă���B�����č����ł́A���̗ʓI�ɘa�����{����FRB��ECB�܂ł����A�����������������X�N�Ɍx������悤�ɁA�Ƃ����J�Ɏs��ɌĂт����Ă���B
�@�j���[���[�N��w�̃��[�r�j�����́A������u�ʓI�ɘa�ɋ���ߏ藬�����ƍ��s��ɂ�����ߏ��������̃p���h�b�N�X�v�ƌĂсA�댯�ɂ܂�Ȃ��������e��������s��ɖ��ߍ��܂�Ă���A�ƌx�����Ă���B���{�����A�����ė�O�Ƃ͌����Ȃ��B
�@���[�}���E�V���b�N��\���������ƂŒm���铯���������ɁA���̌x���Ɏ����X���铊���Ƃ����Ȃ��Ȃ��悤���B���݂Ƀ��[�r�j�����́u�}�N���ȗ������ƃ~�N���Ȕ����Ƃ�����Ȍ������ŏI�I�ɂ͐[���Ȏs��ۑ�ɔ��W���邾�낤�v�ƁA�V���Ȃ��������Ă���B
�@����ɉ����āA���Z�K�������ɂ���ē�����s���u�M�v�Ƃ��ċ@�\���Ȃ��Ȃ������Ƃ𗬓����ቺ�̗v���Ƃ��Ċ뜜���鐺�������B���E�ő�K�͂̎��Y�^�p�z���ւ�ău���b�N���b�N�́A�ŐV�̌ڋq�������|�[�g�̒��Łu��債�������Ƒw�Ək�����钇��@�\�̃A���o�����X�͎s��̃����g�_�E���������N�������X�N�����߂Ă���v�Ǝw�E���A�s�ꗬ�������ቺ���钆�Ń��o���b�W�������n�܂�u�ʓI�ɘa�������ׂĂ��������̃{�[�g����Ăɒ��v����\��������v�ƌx�����Ă���B�č��ł���A���͂���S���Y�Ƃ͌ĂׂȂ��Ȃ��Ă��܂����̂��B�����������|�����A��q�����@�֓����Ƃ̉ɋÏk����Ă���̂��낤�B
�@����ŁA�s�ꗬ�����Ƃ͞B���ȊT�O�ɉ߂����A����ɑ��錜�O�͎��݂��Ȃ����z����������Ă���悤�Ȃ��̂��A�Ǝa��̂Ă����������B�����ē�����s�̎M�@�\���ቺ���Ă���Ƃ̎w�E�ɑ��Ă��A���Ƃ��Ɣޓ��͎��痦�悵�Ĕ��铊�@�I���݂ł���A�ɒ����͂��ߑ�]������Ă���A�Ƃ̔��_������B
�@�܂����E�̎��{�s�ꂪ2013�N5���ɋN�����o�[�i���L�E�V���b�N�i���Ďs��ł́u�e�C�p�[�E�^���g�����v�ƌĂ��j�ȍ~�A���������ɑ���w�K���ʂ�ς�ł������Ƃ͎����ł���B���i���}�������Ƃ���ł́A�N����ۂȂǂ́u�ҋ@�}�l�[�v��������z������\���������B
�@�����A�s�ꗬ�����̖��͍��Ɍ��肳��Ȃ��B�ނ���W�����N��V�����Ŗ�肪�������A���ꂪ�e���̍��s��⊔���s��ɔg�y���ăO���[�o���Ȗ��ɔ��W����A�Ƃ��������[�g��z�肵�Ă����ׂ����낤�B���̊ϓ_���璍�ӂ��˂Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�ߔN�̋��Z����̎�����]���̏��Ƌ�s���玑�Y�^�p��Ђɕς����邱�Ƃ��B
�@�܂��ƗZ������Ѝ��s�ɁA�V�����Z�����V�������s�ɂƕω����邱�Ƃɂ��A�����̒S���葦���M�p���^�̎�̂��u�o���N�v����u�m���o���N�v�ւƈڂ��Ă���̂ł���B�����ɂ́A�u�o���N�v�ɑ���K�����d���L���|�����Ă���B
�@��s�ƈ���Ď��Y�^�p��Ђ́A�ڋq�������������g����Ί����ׂ̈ɕۗL���Y������˂Ȃ�Ȃ��B����͔���̈��z���`�������˂Ȃ��B���������͌����ċ�z�����o�������O�ł͂Ȃ��A���݂��鋰�|�Ȃ̂ł���B
�@�e������̗ʓI�ɘa��́A�u�|�[�g�t�H���I�E���o�����X�v�Ƃ���搂�����œ����Ƃ��u����g���[�h�v�ƌĂ�銔������Ѝ����ȂLj���I�Ȏ���ɓ����Ă����B����͒�����̉��Ŋ����㏸�������Ă�����{�������ł���B
�@��ꂽ�}�l�[�́A��荂�����^�[�������߂ė������̖R�����s��ɂ��Q�����Ă�������Ȃ��B���ꂪ��x�t�����n�߂�A���G�����f��قő�k�Ђ��N�������̂悤�ɁA�����o���Ɍ������ĎE�����邱�ƂɂȂ�B���ʂ͗e�Ղɑz���o���邾�낤�B
�u�f�t���v����u�C���t���v�Ɉڂ鎋��
�@�O�q�����o�[�N���C�Y�̒����̒��ŁA������_���ڂ��ׂ��_������B����́A���E�̓����Ƃ̎������u�f�t���v����u�C���t���v�Ɉڂ�n�߂����Ƃł���B����1�`2�N�ԂƂ������Ԏ��̒��łǂ���̃��X�N���d�����邩�A�Ƃ����₢�ɑ���́u�f�t���v��40���A�u�C���t���v��60���ƂȂ�A���N3���̑O���܂ő����Ă����u�f�t�����O�v�D�ʂ̃V�F�A���t�]���Ă���B
�@���ۖ��Ƃ��āA��i���ɂ����鑫���̕����㏸�����ڗ����Ă����Ƃ͎v���Ȃ��B���{�̃R�ACPI�̓[���ߕӂŐ��ڂ��Ă���A�č��̃R�APCE��1.2���ƒᐅ�����ꂸ�A���[�����͑Q���f�t������E�o��������ł���B�s��ŃC���t������莋����Ă���C�z�͂Ȃ��B�����ł̓f�t�����O���琶���Ă���B
�@�����A��i���Ɋւ������f�t���Ƃ������|�������X�ɔ���Ă����̂͊m���ł���A���ꂪ������č��݂̂Ȃ炸���B����{�̋��Z����܂ł��C���𑣂��̂ł͂Ȃ����A�ƊC�O�@�֓����Ƃ��g�\���n�߂��Ƃ���A��������F����ς��˂Ȃ�܂��B
�@���{�ł́A�����㏸�����[���ߕӂ̏œ��₪�o����͍����锤���Ȃ��A�Ƃ����̂��吨�̈ӌ����낤�B�����㏸���҂͎c���Ă���Ƃ͂����Ă��A2���̎������͗y���ޕ��ł���B�����A�č��̓R�APCE��2���ɓ͂����ʂ����������ł����グ���J�n����p���������Ă���A���[�����ł��C���t�������}�C�i�X����E�o�����u�ԂɗʓI�ɘa�k���Ƃ������v�f���o�n�߂����Ƃ��l����A�m���ɓ��{���������܂ł���O�Ƃ͌����Ȃ���������Ȃ��B
�@�����������O�ɑ��A���₾���łȂ����Z�E������u���{���̗������͉��Ăƈ���đS�����Ȃ��v�Ƃ��������悭���ɂ���B�{���ɂ����Ȃ̂��낤���A�Ƃ����̂��M�҂̍ŋ߂̋U�炴��v���ł���B
���̃R�����ɂ���
�q�s�N�s�̐��E���Z���]
���{�A�����Đ��E�̋��Z��ǂ݉����R�����B�M�҂͂�������Z���i�̐�삯�ł���f���o�e�B�u�Y�̓��{�����ƁA���E�ł̎s����ɂ��ǂŏ��̐���̓��{�l�B2008�N7���ɏo�ł����w������s�o�u���̏I���@�T�u�v���C�����̃��J�j�Y���x�ŁA�T�u�v���C�����[������\�������B���������łȂ��A����������M�҂Ȃ�ł͂̋��Z���]�B
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/230160/063000002
http://www.asyura2.com/15/hasan98/msg/372.html

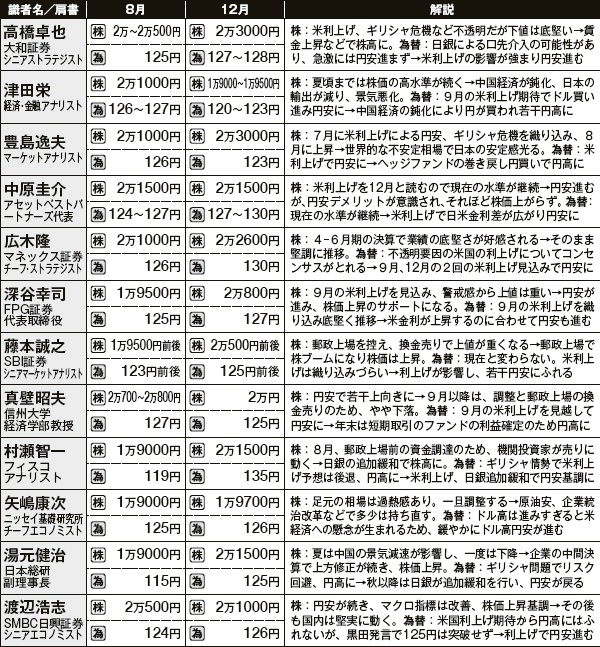
 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B