『日本国民に告ぐ』 一学究の救国論
藤原正彦(お茶の水女子大学名誉教授)
(転載了承済)
二つの戦争は日本の侵略だったか
核心は、日中戦争および日米戦争が日本の侵略であったかなかったかということに帰着する。これが実に難しい。
侵略という言葉の定義がはっきりしないからである。軍事学においては、侵攻と侵略は区別されている。まず、侵攻とは、目的を問わず、相手方勢力や相手方領域を攻撃する行動である。この定義、は明確と言ってよい。一方、侵略とは、相手の主権や政冶的独立を奪う目的で行なわれた侵攻のことである。この定義は不明確である。例えば領土紛争に見られるように、相手国領域か自国領域かどうかということ自体が、紛争の争点だからである。このように不明確ではあるが、ニュールンベルグ裁判や東京裁判ではこの定義が用いられた。日本の行った二つの戦争がこの定義における侵略戦争でなかったことは以下に述べるように明らかである。
日本が盧溝橋事件(昭和十二年)以来の日中戦争で、中国の主権や政治的独立を奪おうとしたことはなかったからである。そもそも発端となった昭和十二年七月七日の盧溝橋事件において、最初に発砲したのは中国側であることが明らかとなっている。一九〇〇年の北清事変の後で結ばれた北京議定書に基づき、合法的に駐留していた日本軍に対し、中国側から夜陰にまぎれた断続的な銃撃が何度かあったのだが、断続的であったため敵の意図がつかめず、牟田口連隊長は防衛の姿勢に入らせただけで自重を命じていた。明け方になって迫撃砲を射ってきたのを見て初めて、明確な攻撃と断じ反撃を命じたのである。初めの発砲を受けてから反撃開始まで七時間もたっていた。この衝突に関し日本側は、政府も参謀本部もそろって不拡大方針であった。当然である。日本陸軍の仮想敵国は明治の頃から一貫してソ連であり、何の得にもならない中国との本格的戦闘をこの時期に始めることなどは誰もが避けたかったからであった。従って間もなくこの戦闘は停止された。
ところが中国軍は引き続き北京の通州で日本人居留民を襲撃し婦女子を含むニ百三十名を虐殺したうえ死体に凌辱を加えたり、上海では米英仏伊などと共に、租界居留民を守るためにやはり合法的に駐留していた日本軍を一方的に包囲転攻撃したりした。この結果、ついに国民も激昂し、近衛内閣は不拡大方針を見直し、上海派遣軍を送るなど本格的戦闘に入って行ったのである。
一九三五年のコミンテルンで宣言されたように、ソ連にとっての仮想敵国はヨーロッパではドイツ、アジアでは日本であった。ソ連にとって、予想されるナチスドイツの侵略に備えるには、アジアでの憂いを解消し、ソ満国境のソ連軍を西部戦線に移動させることが非常に望ましい。憂いを解消するには日本と中国を本格的な戦開状態におとし入れることが一番だ。そのために、コミンテルンの支部である中国共産党に働きかけ、国共合作と抗日民族統一戦線の形成を画策したのである。壊滅寸前だった共産軍と蒋介石率いる国府軍との戦いを止めさせ、共同して抗日戦争をするよう企図したのである。
日中戦争を始めさせるために、中国共産党を通し、日本軍に対するありとあらゆる挑発を行なった。スターリンに入知恵された毛沢東率いる中国共産党は、国府軍と日本軍の共倒れを図り漁夫の利を得ようとしたのである。主敵ソ連による画策などとは夢にも思わず、日本は挑発に乗り、何の目的もない泥沼の戦争へずるずると引きこまれて行ったのである。正規軍による大会戦などのない、もぐら叩きをしながら奥へ奥へと引きずりこまれて行くような、無目的で、無意味で、惨めで、徹底的に愚かな戦争であった。
日米戦争も、アメリカの主権や政治的独立を奪おうなどと考えた人は日本に無論一人もいなかったから、この定義での侵略ではない。アメリカは、日本軍による一九四〇年のインドシナ(べトナム、ラオス、カンボジア)北部への進駐に対し屑鉄や銅の禁輸、翌年七月の南部インドシナ進駐に対しては在米日本資産の凍結や石油の禁輸を行なった。許せぬ非人道的行為に対する懲罰ということだった。
日本軍のこの進駐は、宗主国フランスのヴィシー政権の許可という一応の体裁を整えた上で、アメリカなどによる蒋介石支援のための軍事援助ルート(援蒋ルート)を遮断する目的で行ったものであった。実はアメリカは、武器援助ばかりでなく、中国にフライイング・タイガーズという空軍部隊を派遣するなど、対日戦争に秘かに参戦することで中国がすぐに降伏せずなるべく長く戦い続けるよう目論んでいたのである。
一九三〇年代からアメリカ政府にはソ連スパイが入りこんでいて、四〇年代にはアメリカ共産党員を含め数百人が紛れこんでいたのである(『ヴェノナ』中西輝政監訳、PHP研究所)。日本の石油備蓄は当時、二年分しかなく、鉄なども七〇%はアメリカに頼っていたから、このままでは日本経済の破綻は時間の問題ということになったのである。アメリカが日本の仏印進駐を人道上許されないと言ったのはアメリカ得意のダブルスタンダードである。日本の南インドシナ進駐のたった一カ月後の一九四一年八月末に、イギリスとソ連は共同で、イランの石油確保およびアメリカからソ連への軍需物資輸送ルートの確保のため、イランに進駐した。驚愕したイラン国王はルーズベルト大統領にこの侵攻を中止させるよう嘆願したのだが、ルーズベルトはこれを冷たく断ったのである。在米日本資産凍結という強盗行為や、英蘭を引きこんでの日本に対する石油や鉄などの全面禁輸は、非人道的な侵略を許さぬ、という表向きとまったく異なる目的をもつものであった。こうなっては野垂れ死にするか、勝算のない戦いを始めるか、の二つしかない。日本はもっともしたくない対米戦争を準備しつつ、最後の日米交渉に全力をつくすこととなった。
事実上の宣戦布告だったハル・ノート
和平を求める日本案を拒否したルーズベルトは、十一月二十六日にハル・ノートを日本側に提示したのである。日本軍の、インドシナばかりか中国からの撤退をも要求するていた。
しかしながら、議会はもちろんアメリカ国民の八割以上は参戦に反対であり、ルーズベルト自身、前年の大統領選拳で「アメリカの若者の血を一滴たりとも海外で流させない」と公約して当選していた。この世論の厭戦気分を一掃し公約を破棄するには、日本に「最初の一発」を撃たせ、国民を憤激のるつぼにおとし入れるしかない。ルーズベルトは知恵をしぼりにしぼり、日本が手を出さざるを得ないように仕向けたのである。
なお、ハル・ノートを起草したハリー・ホワイト財務次官補は、戦後解読されたヴェノナ文書(米の情報機関がソ連とアメリカの間で交された暗号を解読したもの)によると明白なコミンテルンのスパイであった。ハリー・ホワイトは終戦の三年後、共産主義者として告発され非米活動委員会に召喚された後、自殺した。ホワイトなどソ連工作員達は、ソ連の生存はアメリカの参戦に依存し、アメリカ参戦は日本軍のアメリカ攻撃に依存すると捉え、日米交渉決裂のため必死の工作を行なっていたのである。
要するに、日米戦争は、自身、社会主義者に近く、ソ連に親近感を持つルーズベルト大統領が、権謀術数をつくして日本を追いこみ、戦争の選択肢しかないように仕向けたものであった。
日本が追いこまれ追いこまれ、国中が呼吸も苦しいほどになっていたからこそ、開戦の報を聞いたほとんどの国民という驚くべき内容のものだった。インドシナからの撤兵だけなら恐らく合意に至ったろうが、中国からの撤兵となると、一九三三年の国際連盟で満州国建設は「日本による中国主権の侵害」と認定されているから、当然満州からの撤兵も含まれることになる。これは日本が、日露戦争の頃から東アジアで営々と築いてきた権益のすべてを放棄することを意味し、とうてい呑める話ではない。
アメリカ側もそれを熟知して出しているはずだから、日本側はこれを当然ながら最後通牒と受け取った。事実上、アメリカ側の宣戦布告だったから、アメリカは直ちに臨戦態勢に入り、日本は十二月一日の御前会議で苦渋の開戦決定をした。アメリカを侵略しようなどと誰一人考えなかったどころか、昭和天皇は最後まで強い反対意見を述べられていた。天皇のお気持をよく知っていたからこそ、開戦前夜、東條首相は寝室で皇居に向かい正座して号泣し続けたのである。
ハル・ノートは、東京裁判での日本側弁護人ブレイクニーが「こんな最後通牒を出されたらモナコやルクセンプルグでも武器をとって立つ」と言ったほどの高圧的かつ屈辱的なものであった。ドイツの勢力拡大を憂えるルーズベルト大統領は、モスクワ陥落という所まで追いつめられているソ連、および気息奄奄(きそくえんえん)のイギリスを救うため、ヨーロッパへの派兵を望んでいた。チャーチルや蒋介石夫人、それに政府内の要所にいたソ連スパイなどが必死に参戦を促しは、勝敗について不安を一様に抱きながらも、「すっきりした」のである。開戦の三週間後の正月、左翼文芸評論の青野季吉までが日記にこう書いた。「じつに四海波静かと云いたい明らけき日。天地も亦、この戦勝の新年を歓呼するが如し。日本は神国なりと云う感が強い」。軍部ばかりでなくすべての国民が、在米日本資産の凍結、全面禁輸、ハル・ノートと愚弄され続け、鬱屈していたから、息苦しさから一気に解放されたような気分になったのであった。祖国の存亡と名誉をかけて、世界一の大国に対し敢然と立上ったことに、民族としての潔さを感じ高揚したのである。
この戦争に関しては、東京裁判を開廷し日本を侵略国家と断罪した当の本人マッカーサーが、一九五一年の米国上院軍事外交合同委員会で次のように答弁している。「日本は絹産業以外には固有の産物はほとんど何も無いのです。彼らは綿が無い、羊毛が無い、石油の産出が無い、錫(すず)が無い、ゴムが無い。その他多くの原料が欠如している。そしてそれら一切のものがアジアの海域には存在していたのです。もしこれらの原料の供給を断ち切られたら、一千万から一千二百万の失業者が発生するであろうことを彼等は恐れていました。したがって彼らが戦争に飛び込んでいった動機は、大部分が安全保障上の必要に迫られてのことだったのです」(『東京裁判 日本の弁明』)。すなわち、日本にとって自衛の戦争であった、と証言したのである。これはドイツに、明確な世界制覇の意志と共同謀議があったのと対照的である。日本の陸海軍は終始いがみ合ってそんな上等な野望のかけらも持ち合わせていなかったのである。
すでに見たように日中戦争も日米戦争も、軍事学上の侵略とは言えない。すなわち、第二次大戦までの定義による侵略ではない。東京裁判はまったく一方的な裁定と言えよう。それでは侵略の現代的定義とは何か。他国の国民あるいは国民を代表する政府に歓迎されずして軍隊を進駐させること、と私は考える。この現代的定義を採用した場合、日本は朝鮮、中国などを侵略したことになる。広い視野に立った場合、朝鮮や満州や中国に日本の大軍が歓迎されぬまま駐留しているということは、いかに国際法に則っていようと、他国の主権をないがしろにした行為である。
ただ、この現代の視点を基に考えると、日本だけでなく当時の列強はすべて、文句なしの侵略国である。米英口独仏蘭中と、十九世紀二十世紀の列強は例外なくそうである。そして侵略国は倫理的に邪悪な国ということにはならない。この二世紀を彩った帝国主義とは弱肉強食を合法化するシステムだったからである。侵略しなかった国は単に弱小国でその力がなかっただけのことだ。
今から考えると侵略を合法化するシステムが生きていたなどとは信じられない話だが、一九〇〇年の時点でこれを疑う人は世界にほとんどいなかった。強国は当然と思い弱国は仕方ないと諦めていた。十九世紀来の帝国主義は第一次大戦において史上空前の犠牲者を出したことで終焉するはずだったのだが、そうはいかなかった。終戦後のパリ講和会議で反省に立って国際連盟まで作ったが、そこで採択された民族自決はヨーロッパだけにしか適用されなかった。その時に生れた国際連盟規約の「委任統治」に触れた箇所には、「自ら統治できない人々のために、彼らに代って統治してあげることは、文明の神聖なる義務である」という趣旨のことが書いてある。「文明の神聖なる義務」という美しい言葉が必要だったのは、帝国主義の矛盾に人々が気付き始めた証拠なのだが。その会議では日本の提起した「人種平等法案」も、人種差別をしつつ植民地をたらふく抱えた英米などの反対で否決された。かくして帝国主義は二千万の犠牲者を出した後でも生き残ったのである。
一九二〇年以降、かろうじて生き残った帝国主義勢力に加え、できるだけ多くの国を赤化しようとするソ連、世界制覇の夢を見るナチスドイツ、恐慌後の米や英によるブロック経済化を見て大東亜共栄圏を目論んだ日本、という新たな膨張勢力が列強として登場した。陣取りゲームとも言える帝国主義は、地球の表面積が限られている以上、いつかは大混乱となる。帝国主義のごとき内部矛盾をはらんだイデオロギーは必らずいつかは破綻し、大清算される運命にある。それが第一次大戦であり第二次大戦であった。同様に矛盾を内包した共産主義は、一九九〇年前後にベルリンの壁やソ連の崩壊とともに七十四年の大実験の後に大清算されたし、やはり矛盾だらけの新自由主義すなわち貪欲資本主義は、世界を二十年ほど跋扈した後、リーマンショックから現在のギリシア危機、ユーロ危機へと、未だ大清算が続いている。
独立自尊のために戦争は不可避だった
日本はこの大きな世界史の流れに明治維新とともに放りこまれてしまったのである。独自の、人類の宝石とも言うべき文明を生んで来た日本は、その気高い自負ゆえに、他のアジア諸国とは異なり独立自尊を決意した。日本のような後進の小国にとって実に大それた望みであった。明治の日本人が満腔にこの決意を固めたと同時に、その後の流れはほぼ決まってしまったのである。
ロシアの恥も外聞もないあからさまな南下政策から自衛するためには、富国強兵を早急になしとげ、朝鮮に拠点を確保した上で、満州をめぐり大国ロシアと生死をかけた戦いに挑む以外になかった。昭和の世界恐慌では、列強のブロック経済化により日本の輸出が閉め出され、失業者は国中にあふれ、東北の農村などでは一日一回の食事もできない欠食児童が大量に現れ、若い娘たちが身売りされる中、朝鮮をこえ、中国の主権を踏みにじって満州に新らしい市場を求めざるを得なかった。これはコミンテルンの謀略により日中戦争までに発展し、アメリカの謀略により袋小路に追いこまれ、ついにはアメリカとの悲劇的戦争に至ったのであった。
その間に多くの致命的間違いを犯した。人種差別撤廃を否決された禍根や、日本を孤立化させようとするアメリカの陰謀もあって、大正十年に命綱の日英同盟を放棄したこと。昭和二年の南京事件で幣原外相が、蒋介石軍が明確に国際法を犯したにもかかわらず、「日支友好」を優先し英米と共同行動をとらなかったため、英米に「抜け駆け」と見られ、以後敵視されてしまったこと。昭和八年に、満州国に関するリットン調査団が「満州には中国主権下の自治政府を作る。そこでの日本権益は尊重する」、というごく妥当な結論を出したのに、これを不服として国際連盟を脱退したこと。
昭和十五年に海軍の猛反対にも拘らず日独伊三国軍事同盟を結び、米英と完全な敵対関係に入ってしまったこと。
などなど日本外交の拙劣さが悔まれる。しかしこういった大失策がなくとも結局は、明治の初めに独立自尊を覚悟した以上、帝国主義の潮流に乗らざるを得ず、この潮流の衰退とともに、小国日本は斜陽の列強として静かに沈むしかなかったであろう。日米戦争はなくとも、いつかは満州、朝鮮などの人々による、大国からの支援を受けた、独立を目指す正当な戦いが始まり、日本は権益を守るため甚大な犠牲を彼我に出しながら、恥ずべき戦争を進行せざるを得なかったろう。そして歴史の流れにより敗北し、恐らく現在の四つの島に、史上一度も外国勢に征服されたことがない、という名誉だけにすがり、ひっそりと生きていたことだろう。
アジアの小さな島国日本は、帝国主義の荒波の真只中で、ほとんど不可能ともいえる独立自尊を決意した。これがすべてであった。この独立自尊を守るため、二千年近い歴史の中で、海外出兵は白村江の戦いと朝鮮出兵だけという、また江戸時代には二百六十年の完全平和を築くという離れ技をやってのけた、世界でも際立った平和愛好国家は、帝国主義の荒波に乗るしか他なかった。荒波に抗して呑みこまれ粉々に砕け散るよりは、荒波に上手に乗るしか他に道はなかったのである。
過去の出来事を、当時の視点でなく、現代の視点で批判したり否定したりするのは無意味なことだ。十九世紀までの人類社会を、人間の平等すらなかったひどい時代と否定してみても何も生まれないのと同様だ。帝国主義は現在の視点から見れば、無論、卑劣な、恥ずべきものである。従ってこの観点からは、日本も他の列強がそれぞれの征服地でしたごとく、朝鮮や中国の人民に言語道断の振舞いをし甚大な迷惑をかけたことになる。弱肉強食は帝国主義時代の唯一の国際ルールだったとは言え、自省と遺憾の念を持つべきなのは当然である。
しかし人間はその時代のルールで精一杯頑張って生きるしかなく、未来のルールで生きる訳にはいかない。すべての列強と同じ誤ちを日本も犯してしまったのは仕方のないこととしか言いようがない。一方、この帝国主義の荒波の中で、日本人はそれぞれの時代の最強国ロシアそしてアメリカに、独立自尊を賭け身を挺して挑むという民族の高貴な決意を示した。無謀にもロシアとアメリカに挑んだことは、別の視座から見ると、日本の救いでもある。日本の基本姿勢が他の列強とはまったく違い、弱肉強食、すなわち弱い者いじめによる国益追求、という恥ずべきものでなくあくまで独立自尊にあった、ということの証左にもなっているからである。そして日本人は、これら大敵との戦いの各所で、民族の精華とも言うべき自己犠牲、側隠、堅忍不抜(けんにんふばつ)、勇猛果敢などの精神を十二分に発揮したのである。
日本が追求した穏やかで平等な社会
歴史についての叙述が多くなったのは、明治、大正、昭和戦前を否定する東京裁判を、形式ばかりか内容についても拒絶するためであった。日本は恐ろしい侵略国であった、などというフィクションを信じこまされているから、日本人自ら、「自分達は一人一人はよいのに集団になると暴走しやすい危険な民族である」と自己否定してしまい、自国の防衛にすら及び腰になるのである。そして何より、明治以降が占領軍と日教組の都合に合わせて否定されたままにしておいては、いかに江戸期までに素晴らしい文明を創り上げた日本があっても、祖国への誇りを持ちにくいからである。
それでは日本文明を特徴づける価値観とはどんなものであったか。一つは、欧米人が自由とか個人をもっとも大事なものと考えるのに対し、日本人は秩序とか和の精神を上位におくことである。日本人は中世の頃から自由とは身勝手と見なしてきたし、個人を尊重すると全体の秩序や平和が失われることを知っていたのである。自分のためより公のためにつくすことのほうが美しいと思っていた。従って個人が競争し、自己主張し、少しでも多くの金を得ようとする欧米人や中国人のような生き方は美しくない生き方であり、そんな社会より、人々が徳を求めつつ穏やかな心で生きる平等な社会の方が美しいと考えてきた。
このような独得の価値観はかろうじてながらまだ生きている。高校生に関する日本青少年研究所の統計データを見ても、「お金持は尊敬される」と思う人はアメリカで七三%なのに対し、日本では二五%しかいない。「自分の主張を貫くべきだ」と思う人はアメリカで三六%、日本では八%である。「他人のためより自分のためを考えて行動したい」に強く同意する人はアメリカで四〇%、日本で二%に過ぎない。
思えば、帝国主義とは近代日本人の発想から生まれるものではなく、欧米のものであった。右で、自分を自国に置きかえて見れば一目瞭然だ。国家が国際秩序とか平和より、自国を尊重し、自国の富だけを求めて自由に競争する。まさに帝国主義である。リーマンショックに始まり現在のギリシア危機、ユーロ危機へつながり、まだまだ続きそうな国際経済危機は新自由主義によるものである。これまた欧米のものである。
万人が自由に、自分の利益が最大になるように死に物ぐるいに競争し、どんな規制も加えないですべてを市場にまかす。どんなに格差が生まれ社会が不平等になろうとそれは個人の能力に差があるのだから当然のことだ、というのは、日本のものではない。日本人が平等を好むのは、自分一人だけがいかに裕福になろうと、周囲の皆が貧しかったら決して幸せを感じることができないからだ。仏教の慈悲、武士道精神の側隠などの影響なのだろう。
日本は、帝国主義、そして新自由主義と、民族の特性にまったくなじまないイデオロギーに、明治の開国以来、翻弄され統けてきたと言える。
今こそ、日本人は祖国への誇りを取り戻し、祖国の育くんできた輝かしい価値観を再認識する必要がある。座標軸を取り戻すのだ。これなくしては根無し草のようなものであり、目前の現象にとらわれどんな浮足立った改革をしてみても、どうなるものでもない。どの選挙でどの政党が勝ち、誰が首相になりどんな政策を打ち出そうが現代日本の混迷は解決するどころかひたすら深まるだけである。
祖国への誇りと自信が生まれて来れば、日本を日本たらしめてきた価値観を尊重するだろう。アメリカが、アメリカンスタンダードである貪欲資本主義をグローバルスタンダードと言い含めて押しつけようとしても、「日本人は金銭より徳とか人情を大事にする民族です」と言い抵抗することができたはずである。規制なしの自由な競争こそが経済発展に不可欠と主張し強要してきても、こう切り返せたはずである。「日本人は聖徳太子以来、和を旨とする国柄です。実際、戦後の奇跡的経済復興も、官と民の和、民と民の和、経営者と従業員の和でなしとげました」。これを言わずアメリカ式を無批判にとり入れたから、日本特有の雇用が壊され、内閣府によるとフリーターは四百万人を超え、完全失業者は三百万人を上回ることとなった。
占領軍の作った憲法や教育基本法で、個人の尊厳や個性の尊重ばかりを謳ったから、家とか公を大事にした国柄が傷ついてしまった。これはGHQが意図的にしたことだった。家とか公との強い紐帯(ちゅうたい)から生まれるそれ等への献身と忠誠心こそが、戦争における日本人の恐るべき強さ、と見抜いたからである。占領の一大目的である日本の弱体化には、軍隊を解散するばかりでなく、そこから手をつけなければならなかった。そこで個人ばかりを強調したのである。
東京裁判のおまじないが解けない日本人は、公への献身は軍国主義につながる危険な思想、などと自らに言い聞かせ、個人主義ばかりをもてはやした。個人主義の欧米が、日本など比較にもならないほどの争いに彩られた歴史を有することを顧みなかったのである。この結果、家やコミュニティーとの紐帯を失った人々は浮草のようになってしまったのである。困った時には家や近隣や仲間が助けの手をのべる、という美風を失ったのである。実はこの紐帯こそが、幕末から明治維新にかけて我が国を訪れ日本人を観察した欧米人が、「貧しいけど幸せそう」と一棟に驚いた、稀有の現象の正体だったのだ。日本人にとって、金とか地位とか名声より、家や近隣や仲間などとのつながりこそが、精神の安定化をもたらすものであり幸福感の源だったのだ。これを失った人々が今、不況の中でネットカフェ難民やホームレスとなったり、精神の不安定に追いこまれ自殺に走ったり、「誰でもいいから人を殺したかった」などという犯罪に走ったりしている。
少子化の根本原因もここにある。家や近隣や仲間の有難さが失われ人々との繋がりが稀薄になったこの社会で、苦労して育てた子供は本当に幸せになれるのだろうか。なれそうもないのなら子育てにエネルギーを使うより、自らの幸福を追い求めよう。自分を支えてくれた社会へ恩返しするより自己実現、となるのである。「個の尊重」「個を大切に」を子供の境から吹きこまれているからすぐにそうなる。だから少子化は出産費用の援助や「子ども手当」で解決する問題ではない。馬車馬の尻を鞭(むち)で叩くような、勝者と敗者を鮮明にする成果主義にもとづく競争社会でなく、祖国への誇りと自信の上に、日本の国柄としての家とか公をはじめ、人々の濃密なつながりを大事にしたうるおいのある社会を取り戻さない限り、社会に漂うとげとげしさややるせない不安、少子化などの諸問題は解決しない。
学級崩壊や学力低下なども、個人を尊重し過ぎた結果、先生と生徒、親と子供が平等となったことが大きい。基本的人権を除けば、先生は生徒より偉く、親は子供より偉い、という古くからの明確かつ当然な序列が薄くなったため、子供達が野放図となった。厳しい鍛練すらできなくなったから、学力は低下した。今では、教師は教授する者でなく子供の学習の援助者、などということになっている。日本に昔からある「長幼の序」や「孝」を幼いうちから叩きこまないとどうにもなるまい。自殺にまでつながる除湿ないじめなども、「朋友の信」や「卑怯」を年端のいかぬうちから叩きこまない限り、いくら先生が「みんな仲良く」と訴え、生徒や親との連絡を緊密にしようとなくならない。
要するに現代日本の直面する諸困難は、各党のマニフェストに羅列してあるような対処療法をいくら講じてもどうにもならないということだ。戦前から始まり、戦後には急坂を転がるように進んだ体質の劣化が原因だからだ。体質劣化の余り、体質を改善する能力さえすでに失ってしまっている。人々はうすうすそれに気付き始めている。何をしてもうまく行かないからである。
そのためか国民の視線が内向きになり下向きになっている。思考が萎縮し始めている。大人達は将来を悲観し、若者は夢や志さえ持たなくなっている。筑波大学のグループが日中韓の中学生を調査したところ、「将来に大きな希望を持っている」は日本二九%、韓国四六%、中国九一%である。祖国への誇りが世界最低のことは先に述べた。GHQと日教組による日本弱体化計画が偉大なる成功を収めたのである。
日本文化が持つ普遍的価値
実は今、頽廃に直面しているのは日本ばかりでない。欧米をはじめ世界的規模で変調が起きている。産業革命以来、世界は欧米の主導下にあった。それは、論理と合理と理性を唯一の原理として進む文明であった。帝国主義も共産主義も新自由主義もその原理から生まれたモンスターであった。二十世紀になってから世界中で一斉に噴出し始めた困難は、この原理の行き詰まりを意味する。論理、合理、理性は無論、最重要のものであり断じて否定さるべきものではない。ただそれだけで人間社会を仕切るのは不可能ということが露呈したのである。帝国主義と共産主義の誕生から滅亡への過程で人類は恐ろしい犠牲を払った。現在は新自由主義の破綻で苦しんでいる。リーマンショックから現在のギリシア危機、ユーロ危機に至る一連の危機は一言で言うとデリバティブ(金融派生商品)によるものだ。確率微分方程式というかなり高級な数学を用いた経済理論にのっとった論理の権化と言えるものだ。五年前に出版した拙著『国家の品格』の中で次のように記した。「(デリバティブは)現状では最大級の時限核爆弾のようなものとなり、いつ世界経済をメチヤクチャにするか、息をひそめて見守らねばならないものになっています。しかもなぜか、これに強力な規制を入れることも出来ない。そもそもマスコミはこれに触れることすら遠慮している。資本主義の論理を追求していった果てに、資本主義自身が潰れかねないような状況に、だんだんなってきているのです」。
エコノミストから大分批判された部分であったがその通りになってしまった。そしてやっと今頃になって、アメリカや欧州で規制が言われ始めている。現在の経済危機はまだまだ続く。世界は誤った新自由主義による金融不安や不況に苦しめられているものの、未だ各国が打ちのめされていないからだ。人間は一つの原理にどっぷり浸っていると、本質が見えなくなるのである。ここ一世紀間に次々とモンスターは破局を迎え人類は悲惨を味わったにもかかわらず懲りない欧米は未だに原理を疑おうとせず、同じ原理で物事を進めようとしている。欧米は他の原理を持ち合わせないからだ。欧米以外の諸文明に生きる人々は、この原理から適切な距離を置きつつ、自らの文明を少しずつ取り戻すことである。効率、能率、便利、快楽、なかんずく富、こそが幸福と大いなる勘違いをし、それらばかりを求めるグローバリズム、大きくは欧米文明への追随に訣別し、各国はその国柄を大事にすることである。新しいローカリズムである。
とりわけ我が国は、真に誇るべき文明を青くんだ国である。それに絶大な誇りを持ってよい。十九世紀に書かれた『Character』の中でスマイルズは、「国家とか国民は、自分達が輝かしい民族に属するという感情により力強く支えられるものである」(藤原訳)と言った。祖国への誇りを持って初めて、先祖の築いた偉大なる文明を承継することができ、奥深い自信を持つことができ、堂々と生きることができる。アメリカの横暴やロシアの不誠実を諌め、中国の野卑を戒め、口角泡を飛ばし理屈ばかり言う米中に「論理とはほとん常に自己正当化にすぎないものですよ」と諭すこともできる。世界を動かすシステムに日本の視点から堂々と注文をつけることもできる。
「過去との断絶」「誇り」を回復せよ
日本人が祖国への誇りを取り戻すための具体的な道筋は何か。日本人は「敗戦国」をいまだに引きずり小さくなっている。戦争は勝つか負けるかのゲームだ。ユーラシア大陸の国々は有史以来、どの国も勝ったり負けたりだから、勝敗は時の運と思い長期間うなだれたりはしない。日本は負けなれていなかったからショックが大きかっただけだ。
ユーラシア人のように「時の運」と割り切ることだ。WGIPで植えつけられた罪悪感を払拭することだ。そして作為的になされた「過去との断絶」を回復することだ。
すなわち、「誇り」を回復するための必然的第一歩は、戦勝国の復讐劇にすぎない東京裁判の断固たる否定でなければならない。その上で第二は、アメリカに押しつけられた、日本弱体化のための憲法を廃棄し、新たに、日本人の、日本人による日本人のための憲法を作り上げることだ。現憲法の「前文」において国家の生存が他国に委ねられているからだ。独立国でなくなっているからだ。そして自衛隊は明らかな憲法違反であり、「自衛隊は軍隊でない」という子供にも説明できぬ嘘を採用しなければならなくなっているからだ。国家の軸たる憲法に嘘があるからだ。「嘘があってもいいではないか。戦後の経済発展は軍備に金をかけず経済だけに注力したからではないか」という人もいる。これも真赤な嘘だ。戦前のドイツ、日本、戦後の韓国や台湾、近年の中国など、毎年GDP比一〇%、あるいはそれ以上の軍備拡大をしながら目覚ましい経済発展を遂げたからだ。軍備拡大とはある意味で景気刺激策とも言えるのだからむしろ当然なのである。
次いで第三は、自らの国を自らで守ることを決意し実行することだ。他国に守ってもらう、というのは属国の定義と言ってもよい。屈辱的状況にあっては誇りも何もないからだ。一時的にでも自らのカで自国を守るだけの強力な軍事力を持った上で、アメリカとの対等で強固な同盟を結ばねばならない。
日本人の築いた文明は、実は日本人にもっとも適しているだけではない。個より公、金より徳、競争より和、主張するより察する、側隠や「もののあはれ」などを美しいと感ずる我が文明は、「貧しくともみな幸せそう」という、古今未曾有の社会を作った文明である。戦後になってさえ、「国民総中流」というどの国も達成できなかった夢のような社会を実現させた文明である。今日に至るも、キリスト教、儒教、その他いかなる宗教の行き渡った国より、この美的感覚を原理としてやって来た日本で、治安はもっともよく、人々の心はもっとも穏やかで倫理道徳も高いのである。この美的感覚は普遍的価値として今後必らずや論理、合理、理性を補完し、混迷の世界を救うものになろう。日本人は誇りと自信をもって、これを取り戻すことだ。これさえあればわが国の直面するほとんどの困難が自然にほぐれて行く。さらに願わくばこの普遍的価値の可能性を繰り返し世界に発信し訴えて行くことだ。スマイルズは前述の書で次のように言った。「歴史を振り返ると、国家が苦境に立たされた時代こそもっとも実り多い時代だ。それを乗り越えて初めて国家はさらなる高みに到達するからである」(藤原訳)。現代の日本はまさにその苦境に立たされた時代だ。日本人の覚醒と奮起に期待したい。p-119 (おわり)
http://www.asyura2.com/10/senkyo90/msg/633.html
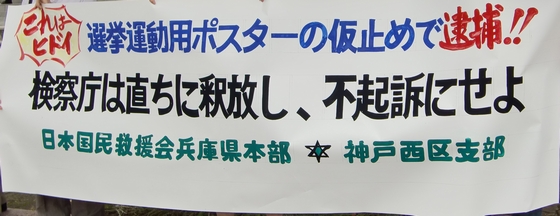

 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。