http://www.asyura2.com/24/kokusai35/msg/482.html
| Tweet |
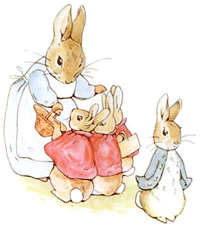
いよいよアメリカの景気後退懸念が高まってきた/東洋経済オンライン
松本 英毅 によるストーリー
https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E3%81%84%E3%82%88%E3%81%84%E3%82%88%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%AE%E6%99%AF%E6%B0%97%E5%BE%8C%E9%80%80%E6%87%B8%E5%BF%B5%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F/ar-AA1CWQvk?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=8fd24d3232d0491288094d19e19a3e66&ei=21
アメリカのトランプ政権に対して、金融市場が「株式・債券・通貨のトリプル安」という形で「NO」を突きつけている。
4月9日、アメリカ国債の急落懸念などから、ドナルド・トランプ大統領は発動したばかりの相互関税について、「大部分を一時停止、各国と90日間の交渉期間を設ける」と発表。同日のS&P500種指数などは過去最大の上げ幅となった。
だが、米中両国の関税応酬が続くとわかった10日は一転、株価は大幅に下落。11日も続落していたが、その後、ボストン連銀のコリンズ総裁が「金融市場が混乱した場合、FRB(連邦準備制度理事会)は対応する手段がある」などと発言したことが報じられ、結局同日のS&P500種指数は前日比95ポイント高の5363ポイント、ナスダック総合指数も同337ポイント高の1万6724ポイントまで値を戻した。
それでもアメリカ債券売りは完全に止まったとは言えず、景気悪化を織りこんで4%を割っていたはずの10年債の利回りは、4.5%前後でなお高止まりしている。
トランプ政権は関税政策を本当に続けるのか
改めて、足元の市場の混乱は、トランプ政権の関税政策をめぐる不確実性に起因しているのは間違いない。
そもそも、トランプ大統領は、連邦政府支出の大幅削減なども打ち出している。筆者が住むアメリカでは、関税政策導入でインフレが進み、雇用も悪化して景気が急速に冷え込む「トランプリセッション」(景気後退、2四半期連続でGDPがマイナス成長に陥ること)になるという観測が急速に高まっており、市場も景気減速を示唆するデータに、極めて敏感になっている。
景気後退入りを予想していたゴールドマン・サックスは9日、トランプ大統領が相互関税についての一部停止措置などを行ったことから、「今後1年間以内にアメリカがリセッション入りする確率は45%」と、従来の予想に戻しているとはいうものの、人々は疑心暗鬼だ。果たしてアメリカ経済は今年中にリセッションに陥るのだろうか。
もちろん、それには一連の強硬な関税政策が今後どうなるかにかかっているといえそうだ。トランプ大統領は関税によってアメリカに富を還元させることで、経済が成長するとの信念を曲げていない。
しかしながら、関税が税金である以上、その賦課が経済成長の足かせとなることは不可避だ。かつて増税によって、経済成長が上向いたことはない。関税でインフレ圧力が改めて強まれば、すでに悪化の兆しが見え始めている消費者心理を更に落ち込ませることになり、GDPの7割を占めるとされている個人消費の減速にながることは避けられない。4月11日にミシガン大学が発表した4月の消費者マインド指数は50.8と、市場予想を大幅に下回っただけでなく、1年後の予想インフレ率は6.7%と、3月の5.0%から1.7%ポイントもはね上がり、1981年11月以来、約43年ぶりの高水準となっている。
DOGEによる連邦政府職員の人員整理の影響はこれから
もう一つの懸念材料は、イーロン・マスク氏率いる政府効率化省(DOGE)による連邦政府支出の大幅な削減や、職員の人員整理だ。4月3日に人材派遣大手のチャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社が発表した3月のアメリカの企業・政府機関の解雇予定数は、27万5240人と前年同月比の約3倍に急増、2020年7月以来の高水準となった。前月比でも60%増という異常な高水準となった。
27万5240人のうち、約8割の21万6215人が政府部門の予定数であり、DOGEの推進する政策の影響が出ていることは明らかだ。翌4日に発表された3月の雇用統計では、非農業部門の新規雇用数(NFP)は2月比22万8000人増加し、事前予想をやや上回った。だが、これは大手スーパーでストライキを行っていた従業員が職場復帰したことや、政府部門でも、有給休暇中や退職金を受け取っている職員はカウントされないことなどが影響しているとみられる。
相互関税やDOGEによる人員削減の影響は、いよいよ5月に発表される4月雇用統計で明らかになりそうだ。とくに政府部門での雇用大幅削減は、人々の消費行動を抑制するという、直接的影響にとどまらず、政府と契約している民間業者の業績悪化や、連邦政府職員の消費に依存している首都ワシントンDCの小売業者の売り上げの減少など、間接的な影響もかなりの大きさになると見られる。インフレの高止まりと相まって、やはり個人消費の落ち込みにつながる恐れは、かなり高そうだ。
こうした状況下、アメリカでは、トランプ政権の政策で景気が刺激され、ドル高が進むという市場の観測は、急速に後退しつつある。
株価や強いドルの元での健全な金利上昇に期待したトランプトレードは姿を消す一方、足元ではトランプ政権の迷走で株式、債券、通貨市場すべてから資金が流出する危機にある。これは、トランプ政権が大幅減税などの景気刺激策の実施を後回しにし、関税や連邦政府支出の削減、不法移民の強制送還といった、景気を悪化させる政策を積極的に進めていることが、その背景にあるのは間違いないだろう。
その中でも、最大のリスクは、やはりインフレとFRBの金融政策だ。今のところ、ジェローム・パウエル議長をはじめ、FRB高官の多くは現時点で金融政策の変更を急ぐ必要はないと、トランプ政権の政策の影響を見極めるまでは様子見の姿勢を維持している。
利下げ環境整わなければ、不況に陥る可能性が高まる
FRBが今後年内に利下げする可能性は高いとしても市場が大いに期待しているように、景気悪化につれて利下げのペースを再び速めるかは、なお微妙だ。逆に、この先、もしインフレ圧力が改めて強まるようなことがあれば、利下げの再開が遅れるだけにとどまらず、再利上げの懸念が浮上するシナリオはなお消えていない。
10日に発表された3月のアメリカ消費者物価指数(CPI)は、前年比2.4%上昇、エネルギーと食品を除外したコア指数は同2.8%上昇と、ともに市場予想を大きく下回った。
確かに、インフレに対する懸念はひとまず後退した格好だが、関税の影響はむしろ今後遅れて表れてくることを考えれば、まったく手放しで喜べるような状況ではない。
特に、今後コア指数の伸びが前年比で再び4%を超えてくるようなことがあれば、FRBの対応も変わってくると思われる。もし、再利上げを迫られるようなことになれば、アメリカ経済はいよいよリセッションに陥る可能性が一気に高まりそうだ
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。