http://www.asyura2.com/24/kokusai35/msg/431.html
| Tweet |
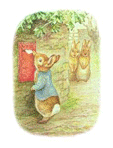
相変わらずトランプ発言に揺れる原油価格、イラン・ベネズエラ産への制裁強化で上昇したが下落基調は変わらない/JBpress
藤 和彦 によるストーリ
https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E7%9B%B8%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%9A%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E7%99%BA%E8%A8%80%E3%81%AB%E6%8F%BA%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%8E%9F%E6%B2%B9%E4%BE%A1%E6%A0%BC-%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%B3-%E3%83%99%E3%83%8D%E3%82%BA%E3%82%A8%E3%83%A9%E7%94%A3%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%88%B6%E8%A3%81%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%81%A7%E4%B8%8A%E6%98%87%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E4%B8%8B%E8%90%BD%E5%9F%BA%E8%AA%BF%E3%81%AF%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84/ar-AA1BSJlf?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=9e187b91fa914115b592920ed58543ef&ei=46
原油価格がまたも、トランプ大統領の発言によって上昇した。ベネズエラやイランの原油を購入している中国をターゲットにした制裁強化の発表を受けて、原油価格は3週間ぶりに一時70ドルを超えた。だが、この上昇は長続きせず、原油価格の下落基調は変わらない。そのワケは?
(藤 和彦:経済産業研究所コンサルティング・フェロー)
米WTI原油先物価格(原油価格)は今週に入り、1バレル=68ドルから70ドルの間で推移している。トランプ米政権の制裁強化の発表を受けて、原油価格は3週間ぶりに一時、70ドルを超えた。
まず、いつものように世界の原油市場の需給を巡る動きを確認しておきたい。
ロイターは3月24日、「石油輸出国機構(OPEC)とロシアなどの大産油国で構成するOPECプラスは5月も4月に続いて増産を実施する公算が大きい」と報じた。
OPECプラスは20日、「合意水準を超えて生産された超過分を相殺するため、7カ国が追加減産を行う」と発表していた。月次の減産幅は日量18万9000〜43万5000バレルで、来年6月まで継続される。イラクが減産の大部分を担う。4月から予定される増産幅(同13万8000バレル)を上回る規模だ。
この決定を踏まえ、OPECプラスは「2022年以降進めてきた有志国による協調減産の巻き戻しを2カ月連続で実施しても、原油価格が下落することはない」と判断しているようだ。OPECプラスの次回の閣僚会合は4月5日に開かれる。
一方、「世界の原油供給が大幅に増加する」との観測は根強い。
米金融サービス企業レイモンド・ジェームズ(RJ)は21日、「多数のプロジェクトが年内に稼働し始めることで増加する原油生産量は日量約290万バレルと昨年(約80万バレル)の3倍以上となり、過去10年で最大となる。今年末の世界の原油市場は供給が需要を日量28万バレル超過する」との予測を発表した。
RJが指摘するプロジェクトは、カザフスタンのテンギス油田やブラジル沖のバカリュウ油田、サウジアラビアのベリ油田やマルジャン油田などの拡張工事だ。
原油価格の下落でこれらのプロジェクトに遅延が生ずる可能性はあるが、OPECプラスにとって頭の痛い問題だ。
スイスのローザンヌで25日に開催されたイベントに出席した国際商品取引企業も「今年の原油価格は軟調に推移する可能性がある」とみている。OPECプラスが増産に転じる一方、需要サイドが弱いというのがその理由だ。
市場ではウクライナ紛争の停戦協議の行方に関心が集まっている。
またもトランプ発言に揺れる原油市場
ロシア大統領府は25日、「米国の仲介で合意されたロシアとウクライナのエネルギーインフラへの攻撃の一時的な停止は3月18日から30日間にわたって有効であり、双方が合意すれば延長も可能だ」と明らかにした。
「米国が対ロ制裁を緩和する」との観測が原油価格の上値を抑えているが、ロイターは25日、「国際商品取引企業はロシア産原油の取引に極めて慎重な姿勢を示している」と報じた。米国が制裁を解除しても、欧州が制裁解除に難色を示す可能性が高いからだ。
中東地域ではイエメンの親イラン武装組織フーシ派と米軍との戦闘が続いており、イランを巡る情勢も不透明のままだが、市場はこれらに反応しなくなっている。
今週の原油市場の主役はまたもトランプ大統領だった。
トランプ氏は24日、ベネズエラ産原油を購入した国からの輸入品に25%の追加関税をかけるための大統領令に署名した。4月2日に発効する。貿易相手国に関税を課すことでベネズエラに対して不法移民の受け入れ圧力を高める狙いがあると言われている。
二次的関税の対象国は明確に記載されていないが、中国に関税が課された場合には香港やマカオにも適用されると明記されている。
中国が名指しされたのはベネズエラ産原油の主な買い手だからだ。ロイターによれば、中国は日量約50万バレルの原油を輸入している。
ロイターは25日、「中国の取引業者や製油所は大統領令がどのように実施されるか様子見をしており、ベネズエラ産原油の輸入は停滞し始めている」と報じた。
トランプ政権は20日にもイラン産原油を購入している中国山東省の民間製油所を制裁の対象に追加している。制裁のせいで割安となったイランやベネズエラの原油を積極的に購入し続ける中国に対し、米国はついに「待った」をかけた形だ。
「中国が他の産油国からの代替調達に走る」との憶測から原油価格は上昇しているが、「今回の措置で原油価格が持続的に上昇することはない」というのが一般的な見方だ。
逆に中国の原油輸入量が減少するかもしれない。
原油価格の下落基調は変わらない理由とは
中国国有石油大手の中国石油化工集団が23日、「新エネルギー車への切り替えが進み、粗利益率が大幅に下落したため、昨年の純利益は前年比16.8%減の503億元(約1060億円)となった」と発表したように、中国の原油需要は頭打ちとなっている。新たな輸入先を急いで確保する必要は乏しく、今後、中国の原油輸入が減る可能性は十分にある。そうなれば、原油価格の下押し圧力は間違いないだろう。
トランプ氏はさらに新たなカードを切った。26日に「輸入自動車と基幹部品の一部に25%の追加関税を課す」と発表したのだ。完成車への追加関税は4月3日を予定している。
これに対し、欧州連合(EU)やカナダが強硬姿勢で臨むことを明らかにしており、貿易戦争が激化し、世界経済が下振れすることが現実味を増している。
自動車関税についての金融市場全体の反応が限定的だったことから、27日の原油価格は下落しなかったが、予断を許さない状況が続くだろう。
トランプ政権の不確実性に対する不満は世界全体で高まっていると言っても過言ではない。この悪弊が改まらない限り、原油価格の下落基調は変わらないのではないだろうか。
藤 和彦(ふじ・かずひこ)経済産業研究所コンサルティング・フェロー
1960年、愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。通商産業省(現・経済産業省)入省後、エネルギー・通商・中小企業振興政策など各分野に携わる。2003年に内閣官房に出向(エコノミック・インテリジェンス担当)。2016年から現職。著書に『日露エネルギー同盟』『シェール革命の正体 ロシアの天然ガスが日本を救う』ほか多数。
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。