http://www.asyura2.com/16/iryo5/msg/608.html
| Tweet |

深刻な後遺症、植物状態…死ぬより怖い「投薬ミス」の実態 病院で、薬局で、老人ホームで続出!
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51648
2017.05.10 週刊現代 :現代ビジネス
投薬ミスで死期が早まったり、後遺症が残ったりすることは実は珍しいことではない。表沙汰になっていないだけで、あなた自身や家族にも起こりうる医療事故の実例を追った。
薬剤師からかかってきた電話
「申し訳ございません。お薬を渡し間違えておりました。今からお宅に取り換えにうかがってもよろしいでしょうか?」
上野光三さん(仮名、72歳)のもとに、慌てた声の薬剤師から電話がかかってきたのは今年の始めのことだった。
数日前に上野さんは、かかりつけの病院で処方箋を受け取ったが、普段行く薬局ではなく、出先の初めて行く薬局で薬を受け取っていた。電話をかけてきたのは、この初めて訪れた薬局だった。
よくよく聞けば、いつも上野さんが飲んでいる降圧剤のアテレックをアレロック(花粉症でよく使われる抗ヒスタミン剤)と取り違えて出してしまったのだという。
「なんていい加減な薬局だと腹が立ちました。幸い、たいした副作用が出るような薬ではなかったので、大事には至らずに済んでよかった。処方箋やお薬手帳もちゃんと出したのに、こんな初歩的なミスが起きるのかと驚きました」(上野さん)
実はこのようなミスは、日々、いたるところで起きている。薬局に行けば、薬剤師たちが何重にもチェックしていて、ミスなんか起こるはずがないと思っている人も多いだろう。だが、病院や薬局を盲信してはいけない。
上野さんのケースは健康被害もほとんどなく、医療事故と呼べるようなものではないかもしれない。だが、ミスが重なれば、重篤な副作用が出て、後遺症が残る可能性もある。最悪の場合、投薬ミスが死に至るケースだって考えられるのだ。
実際に投薬ミスで、深刻な状態にいたったケースがある。
「妻は優しい人でした。友人も多く、亡くなったときには約550人の方がお通夜・告別式に参列してくれました。副作用のせいであのような形で最期を迎えることがわかっていれば、絶対に薬を飲ませなかったでしょう」
こう語るのは川崎市在住の長濱明雄さん(42歳)。妻の裕美さんは'14年に東京女子医大病院で脳腫瘍の治療中に、大量の抗てんかん薬を投与され死亡した。
明雄さんは今年3月28日に大学病院と担当した医師2人を相手取り4300万円の損害賠償を求める訴訟を起こしている。
「脳腫瘍がわかったのは、'13年の9月でした。別の病院で手術を行い、治療をしていましたが、悪性の脳腫瘍であったため、通常の医療に加えて先進医療が受けられるという東京女子医大に移ったのです。
妻は長年サンバを趣味にしていて、再発が発覚した後も、'14年の8月23日のカーニバルに出たいと言っていました。そしてカーニバル後の9月3日か4日に手術を受ける予定でした」
ところが8月20日、裕美さんは職場でてんかん発作を起こして倒れてしまった。運ばれた外来で点滴を受け、発作は収まったが……。
「外来担当の脳外科医師から『主治医に連絡したところ、サンバに出るためには、抗てんかん薬の血中濃度を上げたほうがいいということになった。通常徐々に量を増やすところ、最初から最大量を処方する』と告げられました。それで処方されたのがラミクタールでした。
その時は、命を落とすリスクも重大な皮膚疾患が出るリスクについても、まったく説明がありませんでした。承諾書にサインすることもなかった」
ミスを闇に葬る病院
明雄さんが処方箋を持って薬局に行くと、「本当にこの量と言われたのですか」と聞き返されたという。そして薬剤師が担当医に連絡し、確認したうえで薬が処方された。23日のカーニバルにはなんとか出られたが、そのころからふらつきがひどくなり、ろれつが回らなくなったという。
「29日早朝、ふらつきが強く、うまく歩けずに転倒したため、緊急入院しました。入院後も39度の熱が出たり、顔が赤くなったりしました。その後皮がむけるなどの重大な皮膚疾患が出て、深刻な状態になった。中毒性表皮壊死という症状でした。点滴を止めるテープをはがすときも、皮膚がめくれて痛みで叫ぶほどでした。
結局、全身麻酔をかける前に『頑張ります』と言ったのが妻の最後の言葉になりました。最後まで生きる努力をしていたんです。一進一退が続きましたが、9月9日の昼、妻は亡くなりました。
主治医は、発症時の説明で『100万人に1人の割合の発症だ』と妻の体質のせいにして、自身の責任を認めませんでした。斎場でも『力及ばず申し訳なかった』と口にはしましたが、責任を認めたわけではなかった。
妻のことがあった半年前にも、東京女子医大では薬の誤投与で小さな子供が亡くなっています。私たちのように一縷の望みを抱いて女子医大に行く患者さんも多い。責任の所在を明らかにして再発を食い止める努力をしなければ、患者さんにまた同じ思いをさせることになります」
こうした悲劇を生む、投薬ミスがいま、全国で増加している。
医療事故に関する情報を収集している日本医療機能評価機構によると、'16年に全国の医療機関から報告があった医療事故は、前年比228件増の3882件で過去最多を記録した。このうち薬剤による事故は229件だった。
投薬ミスによる事故は増加傾向にあるが、長濱さんの例のように訴訟沙汰になったり、機構に報告されているものは、氷山の一角に過ぎない。
著書に『医療事故はなぜ起こるのか』がある医師で法医学者の押田茂實氏が語る。
「労災事故が起こる確率を予測するのに有名なハインリッヒの法則というものがあります。私は、これは医療事故にも応用できると考えています。
1つの重大な事故の背後には29の軽微な事故があり、さらにその背景には300のヒヤリとするようなミスがあるという法則です」
つまり、仮に表面化している重大事故が年間200件あるとすれば、5800の軽い事故があり、さらには6万件の事故寸前のミスがある。自分自身や家族にも、かなりの確率で起こりうるのだ。
都内の病院に勤務する看護師が語る。
「うちの病棟は30床ほどで大きな規模ではありませんが、毎日のようになんらかの事故は起きています。
原因は医師のミス、看護師のミス、患者さん自身の問題などさまざまですが、トラブルが起きたら必ず『インシデント・レポート』が作成され、回覧することになっている。月に20〜30ほどのレポートが回ってきますね。
実際、薬の副作用で転倒し、それが原因で出血し、数週間後に亡くなった高齢の患者さんはけっこういます。
医師も看護師も、『あのときの薬が間接的な原因だ』とわかってはいるのですが、直接の死因には違う病名がついているのであえて蒸し返したりはしない。患者の家族にも、転倒したのは薬のせいだとは絶対に言いません。
このような表沙汰にならず、闇に葬られた投薬ミスはものすごく多いと思いますよ」
後遺症で寝たきりに
ナビタスクリニックの佐藤智彦氏が語る。
「いちばん起こりやすい基本的なミスは、医師が似た名前の薬を取り違えること。
私が見たことのある例では、高血圧の患者に本来出すべき降圧剤(アルマール)の代わりに糖尿病薬(アマリール)を出してしまったケースです。
実際、アルマールとアマリールの取り違えは頻繁に起きていたようで、患者が寝たきりになった事例も報告されています。その結果、'12年に事故防止のためにアルマールはアルチノロール塩酸塩と改名されました」
'11年に神戸の薬局で誤ってアマリールを処方された80代女性は、服用後、低血糖脳症のために意識不明に陥り、寝たきりになるという重い後遺症を残した。この件では、薬局側が患者に8000万円を支払うことで和解が成立している。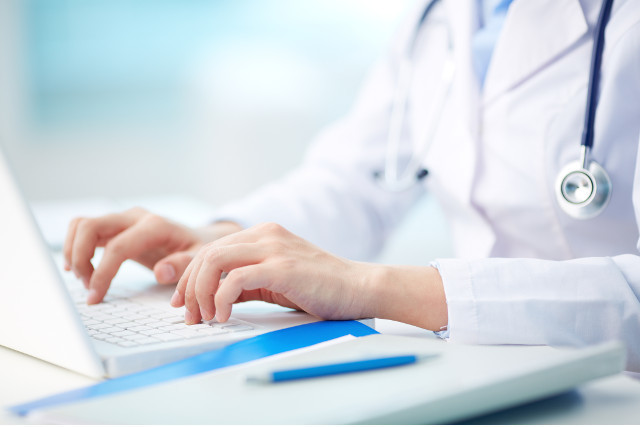
名前が似ているため起きた処方ミスの例は他にもある。'08年にはサクシゾン(抗炎症剤の副腎皮質ホルモン)を投与するはずだった患者(70代男性)に誤って「サクシン」(筋弛緩剤)を投与してしまい、死亡に至った事故が徳島県健康保険鳴門病院で起きている。
処方した医師は電子カルテで「サクシ」とだけ入力したが、その病院ではサクシゾンは取り扱いがなかったため表示されたサクシンを選択、点滴を担当した看護師から「本当にサクシンでいいのか」と確認されたが、そのまま点滴時間だけを指示したという。
「いまはコンピュータ上で投薬指示を出すことが多いのですが、頭から数文字を打つと自動的に候補が表示される予測変換があるため、このようなミスが起こりやすいのです」(佐藤氏)
前出の押田氏が語る。
「間違いやすいから名前を直せというのは簡単ですが、実際にはこれが難しい。本来であれば、後から出てきたサクシゾンを変更すべきなのですが、サクシゾンはサクシンの何倍も売り上げがあるメジャーな薬。だからサクシゾンの製薬会社は、名前を変えられないと主張しました。
急に名前が変われば、医療界も混乱して薬の売り上げが落ちますからね。最終的にサクシンが『スキサメトニウム』という名前に変わりました」
他にも間違えやすい名前の例としては、アモリン(ペニシリン系抗生物質)とアモバン(睡眠導入剤)、テオドール(気管支ぜんそく)とテグレトール(てんかんの発作薬)など色々ある。
「小さな個人病院などで薬品についての知識が乏しい医者が薬を出しているとミスが起こりやすい」(大手薬局勤務の薬剤師)
だが、実際には大学病院のような大きな病院でもミスはしばしば起きている。
「都内の大学病院で降圧剤のノルバスクと抗がん剤のノルバデックスを取り違えた事故がありました。まだ1年目の新米ドクターが処方したということですが、降圧剤の代わりに抗がん剤を出すなんて、あまりにひどいミス。
患者さんは高齢で言われるがままに薬を飲んでいたそうですが、数日後に家族が『いつもの薬と違う』と気付いたため、深刻な事態に陥る前に発覚したのです」(大学病院勤務の看護師)
投薬ミスは、他にもいろいろな原因で起こる。
多いのは点滴などで薬の容量や投与時間を間違えてしまう事例だ。自身も看護師として多くの医療事故の現場を見てきた、医療ガバナンス研究所の樋口朝霞氏が語る。
「たとえば、本来は24時間かけてゆっくり点滴投与しなければいけない薬を間違えて2〜3時間で投与してしまうようなミスです。それが痛み止めのための麻薬だったり、鎮静剤だったりしたら大変なことになります。ふらつきや意識障害、そしてひどい場合には呼吸停止にいたることもある」
特に点滴による投薬は、看護師による裁量が大きい。しかし、同時に多くの患者の世話をする激務のなかで、点滴薬をセットし、投薬の分量を調整するのは煩雑な作業だ。当然ミスも起こりうる。
「大病院では3交代制の8時間勤務のところが多い。なかでもミスが起こりやすいのは夕方から真夜中にかけての準夜勤といわれる時間帯です。昼間だと医師や看護師長などスタッフの数も多いためチェック機能が働きますが、どうしても手薄になる夕方から夜間はミスが起こりやすい『魔の時間帯』なのです。
専門病院で使う薬がある程度決まっているところはいいのですが、総合病院でいろいろな科を異動する場合は、使う薬の種類も膨大。なかには計算の苦手な看護師もいて、多忙だと1時間あたりの点滴の量を正しく計算できない人もいます」(樋口氏)
老人ホームはもっとひどい
投薬の量に注意が必要なのは、点滴薬に限ったことではない。高齢者もよく服用している慢性便秘薬の酸化マグネシウムも、とりわけ服用量に注意が必要な薬だ。横浜市立大学大学院・肝胆膵消化器病学教授の中島淳氏が語る。
「適正な量をはるかに超えた量を漫然と服用している患者さんがいます。酸化マグネシウムは、大人なら普通2g以内が限度です。酸化マグネシウムを過剰に飲むと不整脈が起こって、ときに死亡してしまうこともあります。実際にそのような事例が報告されています」
まさか便秘薬で患者が不整脈になるとは予想していない医者も多いだろう。だが、このような身近な薬でもさじ加減一つ間違えれば、大事故につながるのだ。
多忙に追われたスタッフがミスを犯すのは老人ホームも同じこと。東京都内の介護施設スタッフが語る。
「老人ホームでは単純な投薬ミスが多いですね。病院では患者さんの手首にバーコードをつけて、投薬ミスのないようにチェックするシステムなどが普及していますが、老人ホームではそこまでやりませんから。
特に多いのは、同じ苗字の患者さんの薬を誤って飲ませてしまうパターンです。私の施設で起こったのは、84歳の女性でアルツハイマー型認知症と多発性脳梗塞を患っている方の事故です」
その患者は脳梗塞予防のワーファリンとアルツハイマーの進行を抑えるアリセプトを服用していた。その薬を飲んだ上に、スタッフが間違えて同じ苗字の人の糖尿病薬(オイグルコン)と降圧剤(ラシックス)を飲ませてしまった。
「ラシックスは効き目の鋭い血圧降下剤なので低血圧を引き起こしやすい。またオイグルコンとワーファリンを併用するとオイグルコンの血糖降下作用が増強されて、低血糖になることもある」(介護施設スタッフ)
結局、その女性は意識障害で病院に搬送されてしまい、一命は取り留めたものの、植物状態になってしまった。
「高齢者、特に認知症患者への投薬ミスは、それが原因で転倒しても、薬が原因だったと追及されないケースも多い。遺族も薬の副作用と気付かないし、そうと疑っても『仕方ないか』とあきらめがちなので、示談になるのです」(介護施設スタッフ)
実際、裁判に持ち込んだとしても、必ずしも遺族の思った通りの展開にならないのが投薬ミス裁判の難しいところ。医療過誤を専門に扱うALG&Associatesの岡本祐司弁護士が語る。
「医療裁判の難しさは二つあります。一つは証拠がすべて病院側にあること。二つ目は医学的判断の複雑さと専門性。病院はそもそも患っている人が行くところですから、病気が原因で亡くなったのか、誤投薬のせいなのか判断が難しいのです」
「なんとなく薬を出す」医者
高齢者の場合は、投与する薬の量も多くなる。さじ加減を調節するのが下手な医師にかかると、死に直結する場合も多い。関西の総合病院内科病棟に勤務する看護師が語る。
「昨年暮れ、脳梗塞のリハビリで入院していた76歳の男性が風邪を引き、高熱を出しました。解熱鎮痛剤のアスピリンと抗生物質を投与しました。風邪には抗生物質は効かないのですが、高齢者の場合は肺炎の予防の意味もあって抗生物質を出すのです。
しかし、担当医がまだ研修を終えたばかりの若い医者で、次々と新しい薬に変えたがる。抗生物質も最初はペニシリン系でしたが、どんどん強くしていき、最後はマクロライド系の抗生物質を使った。
最初から便が少し緩くなっていたので、『これは抗生物質の副作用じゃないでしょうか』と進言したのですが、聞き入れてもらえず、マクロライド系を投与した晩にすごい下痢と嘔吐をくりかえして脱水状態になり、結局3日後に亡くなりました。
絶対、抗生物質の誤投与が原因だと思うのですが、その医師は肺炎が原因だと遺族には説明していました。せっかくリハビリで病院の廊下を歩けるまで回復していたのに、本当に残念です」
このように医者の力量不足が原因で起きる投薬ミスもある。そして、さらに悪質なのは、その薬が本当に患者のためになるかどうかも不確かなのに使おうとする医者までいることだ。医療過誤原告の会会長の宮脇正和氏が語る。
「投薬ミスの背景には、新しい薬がどんどん開発されていることもあります。医者自身も新薬についての正確な知識がなく、臨床経験が少ないままに、なんとなくの感覚で処方してしまう。
特に儲け主義の製薬会社と関係が深く、意図的に新薬拡大に加担しようとする医者は危険です。本来は投薬に関するあらゆる情報が医療スタッフのあいだで共有されるべきなのですが、そういう医者は独断で処方してしまうことが多いのです」
では、私たち患者が投薬ミスから身を守る術はあるのか?
「普段と違う薬を出されたり、薬の色や形が違っていれば、面倒であってもきちんと医師や薬剤師に確認することです。また、ケアレスミスが多い病院は、重大な事故が発生する確率も高い。日頃からちょっとしたミスが多い病院は避けたほうがいい」(前出の押田氏)
前出の樋口氏が続ける。
「病院が医療事故を減らすための安全対策を取るためには、それなりの費用がかかります。経営状態が悪いと、安全対策にかける予算が削られることが多い。
予算が足りないからといって、安全に点滴を注入するポンプを買ってもらえず、病棟でポンプが奪い合いになる病院もあると聞きます。入院する前に病院の経営状態を知っておくことも、大切です」
注意をしていても、ミスはどうしても起きるもの。少なくとも、ミスを防ごうとする姿勢がない病院には近寄らないほうがいい。
「週刊現代」2017年5月6日・13日合併号より
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。