http://www.asyura2.com/16/hasan114/msg/443.html
| Tweet |
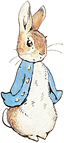
1972年まで「360円/ドル」(固定相場)だったのに異次元金融緩和マイナス金利でも360円には戻らず103円ですね、なんで円は高くドルは安くなったのでしょう、
特に、円高の日本の「GDP/人」は世界26位と低迷、ドル安の米国の「GDP/人」は世界6位とかなり上なのです(2015年、名目)
日本の技術競争力はトップクラスなのです、1972年以降日本国民は政治の貧困で犠牲になっている、これに気付いて頂きたい
▼円高ドル安の根源は何か、日本の対外純資産は366兆円と世界ダントツに膨れ上がった根源は何か、考えて頂きたい
重要な経済課題なのに国会でも新聞テレビでも一切話題にすらならない、なんでなのか不思議でならない
この事実に見向きもしないで、異次元金融緩和マイナス金利などは国民犠牲になるだけで景気が良くなる理由は全くないのです
そもそも消費低迷しているならデフレになって当然ですね、それを金融でインフレにするとは消費はさらに低迷し景気が良くなる根拠は全くないのです
▼日本企業が労働力に見合う賃金を払っていたら対外純資産はゼロで、360円/ドルのままだったはず、
最低時給を上げれば輸出に不利だが、日本の対外純資産は膨れ上がっている、外貨準備高は1兆ドル以上もある、従って輸入には全く問題ないのです
そもそも輸出は国民生活にマイナス、プラスになるのは輸入なのです、これも認識して頂きたい
▼「360円/ドル」に戻るまで最低時給をどんどん上げて頂きたい、数倍になるでしょうね、円高メリット還元です
「360円/ドル」に戻れば、デフレも解消し、GDP/人は世界一、財政赤字も解消、農業も林業も漁業も問題は完全に解消します、
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 経世済民114掲示板 次へ 前へ
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。