http://www.asyura2.com/16/hasan108/msg/248.html
| Tweet |
世界2冠同時受賞! なぜマツダ「ロードスター」は世界で愛されるのか
http://president.jp/articles/-/17732
2016年5月3日 PRESIDENT Online
ニューヨーク国際自動車ショーで、3月24日、マツダの「MX-5」(日本名 ロードスター)が「2016年世界カー・オブ・ザ・イヤー」とデザイン部門の「世界カーデザイン・オブ・ザ・イヤー」を同時受賞という史上初の快挙を成し遂げた。さらにそのおよそ1カ月後の4月22日には生産累計100万台を越した。なぜマツダ「ロードスター」はこのように世界で愛されるのか、ロードスターの開発現場を徹底取材した。
■世界2冠同時受賞は自動車の歴史に残る快挙
3月24日、マツダ・ロードスターがワールド・カー・アウォード(World Car Awards)主宰の自動車賞で、最高の栄誉となる「2016ワールドカー・オブ・ザ・イヤー(WCOTY)」を与えられた。現在米国で開催中のニューヨーク国際オートショーで発表、同時にその授賞式が行われた。ロードスターはこれに加えて「2016ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー(WCDOTY)」も同時に受賞。

3月24日、ニューヨーク国際自動車ショーで、マツダの「ロードスター」が「2016年世界カー・オブ・ザ・イヤー」とデザイン部門の「世界カーデザイン・オブ・ザ・イヤー」を同時受賞という史上初の快挙を成し遂げた。
同賞の対象は直近の1年間に誕生した乗用車。したがって、ロードスターが総合的に最も優秀と認められたばかりでなく、そのデザインに対しても最高の評価が与えられたことになる。
同賞が創設されたのは2004年という。それ以来昨年の2015年までにカー・オブ・ザ・イヤーを獲得した11のモデル(実際の授賞は2005年から)を振り返ってみても、このふたつの賞を同時に手にしたモデルはない。ダブル受賞は、昨年5月に発売されたオープン2シーターの軽量スポーツカー、ロードスターが初めてなのだ。その意味で、これは日本の自動車の歴史に残る快挙、と言っても決しておおげさな表現に過ぎることはないだろう。
日本の自動車の歴史という観点からすると、日本がこれまでに生み出した“グローバル・カー”の双璧は、トヨタのセルシオ、そしてこのマツダのロードスターではないかと筆者はかねてから考えている。前者はその精緻な仕上がりで世界の高級車メーカー・市場に衝撃を与え、その後トヨタが高級ブランド“レクサス”を生む礎となり、レクサスの旗艦モデルであるLSへと発展進化している。後者は、1980年代当時“絶滅危惧種”と思われ開発意欲をなくしていたオープン2シーターの軽量スポーツカーのメーカー各社に大きな衝撃を与えることによって、そのマーケットを世界的に甦らせ、活性化に貢献した。
両者(車)とも誕生と同時に世界的な評価を得て、ともにグローバル・カーとしての立場を確立していった。発売されたのが同じ年、1989年、というのも偶然の一致とは言い切れない何か因縁のようなものを感じてしまうのは、筆者だけだろうか。というのも、昨年このロードスターが発売されるわずか1週間前の5月13日、トヨタとマツダの両社は業務提携に合意したことを発表しているのだから。
■マツダのクルマづくりの考えがわかるデザイン
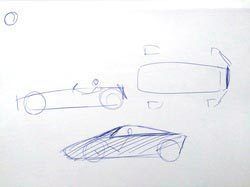
ロードスターのチーフデザイナー、中山雅さんのスケッチ画。
初代ロードスターの発売から四半世紀あまり、本年4月22日、ロードスターの生産累計はついに100万台を突破した。1989年の生産開始以来、27年間で積み上げてきた数字だ。名実ともに“グローバル・カー”と呼ばれる資格十分だ。とはいえ、今回の受賞には、このグローバル・カーに新しい勲章がもうひとつ加わった、というだけでは終わらない、もっと重要な意味があるのだ。
それは、今回のロードスターの受賞によって、マツダが、独自技術のスカイアクティブを核としてこの数年(とくにスカイアクティブの第1号車CX-5を発売した2012年2月以降)展開してきたブランド戦略が成功をおさめ、さらにそれを次の段階に移行できる状況をつくりだしている、この事実が国際的、客観的に証明されたことが、マツダにとって非常に重要なのではないか。
言うまでもなく、ロードスターは現在、マツダのブランドを象徴するいわば“ブランド・アイコン”として位置づけられており、それだけにその戦略を展開発展させるという大きな役割を担っている。この役割を全うさせようと、実は、マツダの経営陣は、今回のロードスターを開発するにあたって、デザイナーに次のような命題を与えた。
「マツダのクルマづくりの考え方がわかるようなデザインにしろ!」
ブランド・アイコンである以上、しごく当然の要求だと言えるだろう。
確かに、今でこそ、ロードスターはマツダのブランドを象徴するモデルと一般的にも捉えられてはいる。しかし、27年前にこのモデルが誕生したときには、マツダ自身に、これを“ブランド・アイコン”にするという明確な意図が必ずしもあったわけではない。
ロードスターが初めて誕生した(エンジニアやファンの間ではその型式からNAと呼ばれている。ちなみに、それ以降の世代はNB、NCとなり、今回受賞した最新モデルはND)のはすでに述べたように1989年。このとき、このオープン2シーターの軽量スポーツカーに与えられていた位置づけは、当時マツダが推進していた販売チャンネルの拡大路線によって生み出された5種類のブランド(マツダ、アンフィニ、オートラマ、オートザム、ユーノス)のひとつ、「ユーノス」のいわば目玉的なモデル、だった。
これが世界的な大ヒット製品となり、1998年の2代目NB(ユーノス・ブランドが廃止されたためマツダ・ロードスターに名称変更)、2005年の3代目NCへとモデルチェンジをしていく過程で、エンジンの排気量はNAの1.6Lから1.8Lそして2.0Lへと拡大していく。デザインも基本的に初代からの流れが継承されていった。
■「ガラパゴス的な存在」から脱却する意味

ロードスターのチーフデザイナーの中山雅さん(左)。(2月27日マツダ本社ショールーム、ロードスターサンクスデイ)
ロードスターのファンからすれば、モデルチェンジしてもデザインはオリジナルのイメージが残されていくことに真っ向から反対する人はあまりいないだろう。その意味で保守的だ。しかし、この流れをマツダの乗用車全体の視点から見てみると、果たして同一ブランドとしての総体的な統一感が意図されていたのかという点に関しては疑問符がつく。逆に言えば、マツダにとってもあるいはファンにしてみても、スポーツカーだからという理由で、マツダの全体のデザインからいわば“はみ出て”いても許されたのではないか。つまり、“総体としてマツダ乗用車の枠の中におさまっていない”ことが、むしろかえってロードスター特有の存在感だと肯定的に受け取られていた側面もあるだろう。
2011年の10月にロードスターのチーフデザイナーに指名されたデザイン本部の中山雅(まさし)は、“マツダのクルマづくりの考え方がわかるデザイン”に関してこんなコメントをしてくれた。
「“ロードスターだから”といったガラパゴス的な存在からの脱却を果たせ、ということですよ。今までは、マツダ車のラインアップの中で、いわば末っ子的な存在だったかもしれない。だから、名実ともにブランド・アイコンと認められるデザインを生み出そうとしたわけです」
もはや、末っ子だからと甘えてばかりはいられない、マツダ車ファミリー全体を牽引する立場へと脱却するのだ。確かに過去3代の所有者の中には、ロードスターのファンではあっても、マツダのファンとは限らない人も存在していたのは事実だった。彼らはときとしてロードスターを“マツダ”から切り離して見ていたこともある。ボディーからマツダのバッジを取り去ってしまうオーナーもいた。こうした“切り離されていても構わない末っ子”的な印象を完全になくしてしまわなければ、ロードスターがマツダ・ブランドの包括的な象徴にはなりえない。そう考えたとき、ロードスターのデザインの方向性は自ずと決まってくる。
こうしたデザインの構想をまとめあげようとしているまさにそのとき、開発部門ではスカイアクティブ技術の開発が佳境に入っていた。しかもそこでエンジニアや企画部門が標榜する“新世代のマツダ車”の特長はスカイアクティブ技術を活かした“人馬一体”という、もともと四半世紀にわたってロードスターの開発エンジニアが掲げていた“走り”の目標だった。
つまり、スカイアクティブを核としたマツダ特有の“走り”の、将来を見据えた方向性を明確に表現する、これがロードスターのデザインに与えられた課題だった。これができれば、言うまでもなく、“ガラパゴス”からの完全な脱出が完成する。
■制約のおかげでロードスターのデザインが完成
中山は次のように言った。
「人馬一体を標榜するマツダ車としての統一感を、単なるグラフィックの面で追求するのではなく、ボディー全体のいわば“体形”で表現しようと心がけ、それに邁進したのです」
たとえばラジエーターグリルの形をモデル間で類似にするといった単なる“見た目”の統一感を演出する、といった手法はとらない。それよりも、全体の骨格や体形といった全体的総合的な造形によってマツダの走りを表現し、マツダ車の総体的な統一感を演出し表現する、という意味だろう。言い換えれば、セダンやSUVといった乗用車のカテゴリーが違い、またエンジンの排気量やボディーの大きさが異なっても、マツダのバッジがついたモデルなら、道路上を走っているその姿をひと目見ただけで「マツダ車だ」と認識され、静止時にもその走りが予感されるデザインを彼らは目ざすことになる。
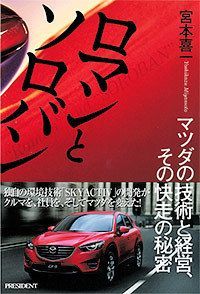
『ロマンとソロバン』(宮本喜一著・プレジデント社刊)
しかも、もともとはロードスターの個性とされた“人馬一体”が、しだいにマツダが掲げたZoom-Zoomという走りを印象づけるキャッチフレーズと融合し、マツダ車共通の個性として定着し始めていた事実が、強く彼らの背中を押していた。
「エンジンは1.5Lのみ、と決められたことがよかった」と中山は振り返ってくれた。
エンジンの排気量が決まった瞬間、タイヤ+ホイールのサイズ、ホイールベース(前車軸と後車軸の間の長さ)の上限が決まる。ボディーの大きさにも制約ができる。具体的にはホイール径は16インチ、ホイールベースは2300ミリ前後、車体の全長は4メートルまで。車重は1トン以下。結果として、エンジンの排気量の1.5Lはこれまでで最小、全長も最短の3915ミリ(従来最短だったNAより55ミリ短い)におさえられた。中山に言わせれば、この制約があったおかげで新しいロードスターのデザインが完成した、という。
通常、セダンやワゴン、SUVといった乗用車には屋根があり、中に乗っている人間は外からながめる人の目にはほとんど入ってこない、つまり意識されない。したがって、乗員の“見た目”がクルマのデザインに大きく影響することはない。しかし金属製の屋根のないオープンカーの場合、人間の体がいわば“むき出し”になるために、人間の姿そのものもデザインの一部にならざるを得ない。と言うよりむしろ、見た目の人間の姿をその一部として溶け込ませてはじめて、オープンカーのデザインは完成する。人間もそのデザインの重要な要素なのだ。
(文中敬称略)
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 経世済民108掲示板 次へ 前へ
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。