http://www.asyura2.com/15/hasan97/msg/737.html
| Tweet |
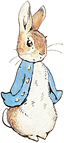
「コネ採用」は制限されるべきか?
2015年6月17日(水) 五十嵐 洋介
経済学者が創造する架空の世界を「モデル」という。実際の経済で政策をあれこれ実験すると国民に迷惑がかかるので、政策担当者はモデルといういわば「実験室」で税率を変えたり、規制を変えたりして、政策の効果をシミュレーションする。経済学者はモデルの予測力を上げるためにデータを用いてその妥当性を検証し、必要あれば改良する。
モデルの中には、現実を模してたくさんの消費者や企業が存在する。政策が変わると彼らも自分の得になるように行動を変え、その結果異なる均衡状態が生じる。政策担当者は少なくともモデルの中において最も効果的な政策が何か見極められるというわけだ。
筆者の最近の研究もやはり政策の効果を簡単なモデルを使ってシミュレートするものだ。政策の標的はずばり「コネ」。親戚や大学の先輩を頼って企業に就職したというような話を読者の方も聞くことがあるだろう。そういったコネの存在が格差社会の温存の一因になっているという議論は米国でも以前からある。筆者の研究の問いは、「コネを通じた採用を禁止/制限すれば、コネを持たない人の厚生は向上するか」どうか、である。
コネ禁止政策が、コネなし組にもデメリット
結論は、コネの禁止政策がコネのない人に常にプラスになるとは限らず、場合によってはマイナスになる可能性がある、というものだ。そんなバカな、と思う人がいるかもしれない。例えば毎年10人雇う企業があったとして、この企業はうち5人を現従業員の友達や学校の後輩など、いわゆる「コネ」で採用し、残りの5人だけを正規のルートで採用しているとしよう。
ある日「コネ」採用を制限する法律が実施されたとする(例えば企業は採用に際して最低1カ月間は求人情報をおおやけにしなければならない、求人1件当たり最低4人は時間をかけて面接しなければならない、人種、出身地、出身校などに関してバランスよく採用しなければならない、コネ採用の疑いがある場合は訴えることができる、など)。
そのような法律ができれば、企業にとってコネ採用のうま味が減り、代わりに正規ルートによる採用が促進され、コネを持たない人の道が広がる、というように感じるかもしれない。
そのように感じるのは、10個なら10個という決まった数の仕事の口があって、コネのある人とない人がそれを取り合いしている、というイメージがあるからだ。しかし話はそう単純ではなく、実際の経済では他にも様々な要因が絡み合っているから、コネ採用禁止後もこの企業が毎年10人雇えるとは限らない。
つまり、労働市場の様々な要因を同時に考慮して政策の総合的な影響を予測する必要がある。そのための強力な経済学モデルが、近年マクロ的労働経済学の基本的な枠組みになっているサーチ・モデル(Search Model)だ。
サーチ・モデルは、 新古典派のモデルと一線を画し、単純な賃金調整によって労働の需給が均衡するとは仮定しない。むしろ均衡においてすら 労働の過需要(求人)と過供給(失業)が併存し続けると考える。理由は「労働者」や「企業」とひとことに言ってもその中身は千差万別であり、しかもお互いの中身が見えにくいため、両者がベスト・パートナーを見つけてマッチングするのには多分に時間がかかるからだ。これを労働市場の摩擦(Friction)という。
労働市場の摩擦の存在を出発点として認めたサーチ・モデルは、労働市場の様々な現象を直感的に説明できることから広く応用され、2010年、サーチ・モデルの3人の先駆者にノーベル経済学賞が授与された。このサーチ・モデルの重要な仮定は以下のとおりだが、どれも非常に直感的で納得のいくものばかりだ。
仮定1. 企業の求人にはコストがかかる(ここで「求人」とは単なる求人情報の公開だけではなく、履歴書の選考や面接等、採用に関わる実際的な活動を指す)。
仮定2. 労働者と職のマッチには時間がかかる(すなわち企業がコストをかけて求人しても適任者はすぐには見つからない)。
仮定3.失業者がどれだけすぐに適職を見つけられるか、企業がどれだけすぐに適任者を見つけられるかは、現在失業者と求人とのどちらがどれだけ多いかに依存する。人が多ければ企業の人材探しは楽だし、求人の方が多ければ労働者の仕事探しは楽である。
仮定4. 賃金は企業と労働者の交渉力の大きさによって決まる。
仮定5. 企業は求人することによる期待利得が正であれば求人するし、負であれば求人をやめる。
サーチ・モデルは、これらの仮定の下でどんな均衡状態が起こるかを予測するためのたくさんの方程式からなる。もちろん、どんな均衡状態が起こるかは労働市場の環境によっても変わってくる。
ここで労働市場の環境とは、たとえば企業の生産性や採用コスト、労働者の賃金交渉力や失業利益(家事生産や失業手当)のことで、これら環境変数の値は国や時代ごとに異なる。そこで、今仮にある国の労働市場の環境変数がこれくらいだとしたら、という値を選んでインプットすると、それをもとにコンピューターが複雑な連立方程式を解き、どんな均衡状態が起こるかを数字で予測してくれる。サーチ・モデルで予測できるのは、失業率、求人数、賃金などだ。
サーチ・モデルは、例えば、失業利益が高いと失業率の景気変動が大きくなること、労働者の賃金交渉力は高過ぎても労働者のためにならないこと(企業の収益性が下がり、求人数が減って失業者が増えるため)などを、数字で予想してくれる。
「コネ」に関する筆者の研究はそんなサーチ・モデルの拡張版のひとつだ。拡張のポイントはただひとつ、労働者の中に「コネのある人」と「コネがない人」の2種類が存在し、コネのない人が正規のルートでのみ企業とマッチできるのに対し、コネがある人は正規のルートと知り合いの紹介との2種類の方法で企業とマッチできる、という点だ。
モデルを実行してみると、当然コネあり組の方がコネなし組より失業率は低くなる。また、コネあり組の労働者はその有用な人脈ゆえに、また失業の心配が少ないという強みも相まって、均衡において受け取る賃金がコネなし組よりも高くなる。
このような世界において、ある日突然、企業によるコネ採用が政策によって禁止されたらどうなるか?
モデルがはじいた結果は、「コネのない労働者の厚生は必ずしも上がらない」というもの。特に、労働者の賃金交渉力がもともと低い経済では、コネ禁止政策の結果、コネのない労働者の失業率が上がり、同時に賃金も下がって、コネのない労働者の厚生が0.2%〜1.5%程下がる可能性があることが示唆された。
これは裏を返せば、 コネあり組の一部がコネで仕事を見つけることが、コネなし組にもメリット(専門用語でいう「正の外部性」という)を与え得るということを意味する。一見甚だ納得しがたい話だが、実はこの結果、あり得ない話ではない。
コネは必ずしも悪いものではない
コネという言葉には身内びいき(nepotism)や学閥(old-boy network)などの負のイメージが伴う。採用者が自分に近いという理由で必ずしも生産的でない人を採用する一方、コネを持たない人への門が閉ざされ、多分に不公平であるという観念だ。しかしこのような観念にはいくつもの但し書きが存在する。まず、コネの利用が、限られた人の特権という考えは必ずしも正しくない。
少なくとも米国では、収入や業種・職種によらず、たくさんの人が親戚や友人などの知り合いを通じた職探しをしていることが、様々な調査で明らかになっている。米ジョージタウン大学のホルザー博士が1980年代に国の調査に基づいて行った研究では、16〜23歳の青年男子のうちおよそ85%が知人友人の「つて」を職探しに利用していたことが報告されている 。また米ライス大学のエリオット博士の90年代の研究でも平均77%の人が知人友人のつてを職探しに利用し、その利用率は貧しい地区ほど高かったことが報告されている。
「知人に頼むだけなら誰でもできる。実際に知人から仕事を得られるかどうかは別問題だ」と思う人もいるかもしれない。では「現在の会社から仕事を得るために、会社内部にいる知人の助けを得たか」という質問をした調査結果はどうか。米ミシガン大学が70年代後半に行った調査では35%の人が助けを得たと答えているし 、1980年代初頭にニューヨークに住む男性399人に尋ねた調査では、実に59%の人が助けを得たと答えている。
上述のエリオット博士の90年代の研究でも56%の人が知人を介して仕事を得たと答えている。その他様々な研究調査から、「少なくとも半数くらいの人が知人友人の紹介で仕事を得る」というのがこの分野における共通の認識となっている。
第2に、労働者が人づてで職を探す、あるいは会社が従業員の人づてで人材を探すということにはもう1つ重要な側面があって、社会学者や経済学者はずいぶん前からこれに気付いている。それは「情報提供」という側面だ。
例えば、ある企業X社の現従業員であるA氏が、知合いのB氏を会社に紹介するという状況を考えてみよう。X社はB氏のことをよく知らない。履歴書や面接で分かることには限界がある。一方B氏にとっても、X社で働くことに関しては未知な部分がある。会社は自分たちのいいことしか宣伝しないから、中に入ってから悟ることも少なくない。
その点、A氏はX社の内部の人間であるから、X社がどんな場所で、どんな仕事があって、どんな人材を求めているかよく知っている。さらに知り合いのB氏がどんな能力を持っていてどんな性格をしているかもよく知っている。
従って X社とB氏がいいマッチであると仮にA氏が思うのであれば、 これはかなり有用な情報である。X社がいくらたくさん面接を行ってもなかなか得ることのできない情報だ。X社とB氏の双方をよく知るA氏だからこそ果たせる役割がここにある。
米プリンストン大学のアルバート・リーズ博士は、企業が労働力を買うことは、石油や食糧の購入よりもむしろ中古車の購入に似ていると言った。石油や食糧のように質が比較的均一な財であれば、できるだけたくさんの売り手をチェックし、一番安い売り手から買うというのが得策である。
ところが中古車のように質が千差万別で判別の難しいものとなると、たくさんの店を覗くよりもむしろ少数の売り手の品を時間をかけて吟味するのが得策になってくる。そして企業にとって労働力を買うということはまさに後者なのだ。労働力は本質的に不均一なものであり、企業は候補者の能力、性格、相性を多面的に見極める必要がある。企業はそのために多大な採用費をかけるわけだ。
正規ルートの採用には多大なコストがかかる
そう、正規のルートによる採用には多大なコストがかかる。さらに、人は雇ってすぐには役に立たない。実際に会社の利益になるまでには簡単な業種でも数週間、複雑な仕事であれば数カ月かかるかもしれない。企業はその間、資源を投じて研修・教育する。しかし労働者と仕事との相性が思っていたほど良くなく、結局半年で辞められてしまうということもあり得る。
そんなときにA氏が「実はうってつけの奴を知っている。有能な奴で、この職場のカルチャーにも合っていると思う。本人にもここの仕事のことを話したのだが、彼も乗り気だ。採用を考えてもらえないだろうか」と言ったなら、これがいかに強力なことか気づくだろう。
ここではA氏はいわば仲人(なこうど)役をしているのだ。十人十色の労働者と千差万別の企業が限定された情報の中で相手探しに苦労している状況において、「コネ・つて」は人と会社の質の高いマッチを円滑に生み出す役割を果たす。専門的な言い方をするなら、労働市場の摩擦を軽減する役割を果たすのだ。
ここまで来ると、筆者がサーチ・モデルを使ってシミュレーションして得た結果もそれほど驚くには値しないことが分かってくるだろう。「コネは良くない」という信念から多大な政策費をかけて「コネによる採用」を制限し、「正規のプロセスによる採用」だけを押し進めると、労働市場の仲人たちが排除され、企業はコストのかかる正規のプロセスだけに依存せざるを得なくなる。
企業の収益性も下がるかもしれない。政策の結果、たしかに求人数は増えるだろうが、仕事が見つからない「コネあり組」の失業者の数も増える。求人数と失業者数が同じだけ増えると思い込みたくなるが、 相手探しに時間のかかる摩擦だらけの労働市場においては必ずしもそうとは限らない。求人数よりも仕事がなかなか見つからない労働者の方が圧倒的に増え、その結果「コネなし組」の職探しがむしろ難しくなる可能性があるのだ。
ところで、「コネ禁止がコネの無い人にも悪影響を与えるかもしれない」という主張は、誤用されれば労働市場における公平性の追求を阻害しかねない。だから最後に以下の2点を強調しておきたい。まず第1に、一般に経済モデルの示唆することは、当然ながらモデルのいろいろな仮定に依存している。
モデルの予測力を上げるためには、それらの仮定の妥当性を実証的に検証し、必要ならモデルを改良することが求められる。第2に、仮にモデルが妥当だとしても、そのシミュレーション結果はモデルへのインプット次第で変わってくる。 筆者の用いたサーチ・モデルでも、コネ禁止政策の効果は、労働者の賃金交渉力などインプットする内容次第で異なってくる。
政策で不必要に摩擦を増やさないために
日常的な感覚や経験則に従うだけでは見落としてしまういろいろな影響を、モデルを使って可視化することが重要である。そうすれば、政策が意図する正の効果と意図せざる負の副作用とのどちらがどれだけ上回るか、様々なシミュレーションを通じてある程度予想することが可能になる。労働市場の摩擦を増やしてしまう副作用を持つ政策に関しては、特にそのような総合的分析が欠かせない。
参考文献
執筆に際して九州大学工学部の野澤亘先生に有益なコメントを戴きました。なお文章の内容・間違い等に関する責任は筆者に帰属します。
Harry Holzer (1987) “Job search by employed and unemployed youth,” Industrial and Labor Relations Review
James Elliott (1999) “Social isolation and labor market insulation: network and neighborhood effects on less-educated urban workers,” The Sociological Quarterly
M. Corcoran, L. Datcher and G. Duncan (1980) “Most workers find jobs through word of mouth,” Monthly Labor Review
N. Lin, W. Ensel and J. Vaughn (1981) “Social resources and strength of ties,” American Sociological Review
Mark Granovetter (1995) Getting a job―A study of contacts and careers
Albert Rees (1966) “Labor economics: Effects of more knowledge,” American Economic Review
このコラムについて
「気鋭の論点」
経済学の最新知識を分かりやすく解説するコラムです。執筆者は、研究の一線で活躍する気鋭の若手経済学者たち。それぞれのテーマの中には一見難しい理論に見えるものもありますが、私たちの仕事や暮らしを考える上で役立つ身近なテーマもたくさんあります。意外なところに経済学が生かされていることも分かるはずです。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20150609/284085
「好き嫌い」で決まってしまう人事評価をなくすために
湧永製薬・湧永寛仁社長×石田淳対談 第2回
2015年6月17日(水) 石田 淳
湧永寛仁社長(右)と石田氏(写真:皆木優子)
前回に続き、滋養強壮剤「キヨーレオピン」で有名な製薬会社、湧永製薬の社長である湧永寛仁社長との対談をお送りします。湧永製薬では私が提唱する行動科学マネジメントを導入し、成績向上の兆しが見えてきたそうです。「好き嫌い人事をなくしたい」と語る湧永社長の思いと、「チェック・アンド・フォローシート」などの現場における具体的な活用法を聞きました。
(聞き手は石田淳、構成は高下義弘=課長塾編集スタッフ/ライター)
(前回からの続き)
湧永:実は、どの社員がきちんと頑張っているのか、逆に誰がその場の立ち回りだけで乗り切っているのかを一番よく分かっているのは、現場の人たちなんです。
「あの人、大して結果を出していないのに何で評価されるのかな。あの人は声の大きい部長の誰それさんと仲がいいもんな」といった不満の声が組織に蔓延してきたとすれば、それは相当会社が弱っている証拠だと思います。
逆に、結果を出す行動を特定し、それを実行しているかどうかという観点から評価するという仕組みを整えれば、ちゃんと頑張っている人に報いることができますし、しかも結果が出る組織に変えていくことができる。繰り返しになりますが、石田さんのご講演を聞いたときに、これだと確信したのです
石田:行動科学マネジメントに基づいた評価の仕組みを営業部門に展開したということで、現場の反応はどんな雰囲気でしょうか。
湧永:たまたま、評価の仕組みを導入したタイミングで部長に昇進した社員がいました。その部長がしきりに言っていたことが印象的でした。「私が部長になった時、チームをどう運営すればいいか、なかなかつかむことができなかった」と。けれども、「経営本部から具体的な行動内容に基づいた評価項目が提示されたので、それがチームを運営する際の指針となり、非常によかった」と。
石田:なるほど。日本企業でよくあるのは「お前は次から管理職だ、後はよろしく」ですからね。
湧永:そうなんです。私の経験からも言えることですが、管理職の仕事とは何かというのは、意外に誰もきちんと答えられない(笑)。
気合いのマネジメントから脱却できた
湧永:3つの評価項目を使って日々の業務を回していくと、現場の管理職には「行動の記述のうち、この内容は成果にはあまり結び付かないかもしれない」とか「こういった行動のほうが大事だ」といったことが見えてきたそうです。
2015年度にはそれまでの9項目から3項目に変更しましたが、変更した際にはそのような現場の意見を反映させました。
このような具合に、定めた評価項目に従って現場の行動を促すことで、いろいろな芽が出てきました。
行動科学マネジメントを評価の仕組みに取り入れてよかったことの一つは、仮説の域を出ていなかったとしても、社員一人ひとりは何をすればいいかという指示が具体的に出せる上に、その行動が結果に結び付いたかどうかを検証できる体制が整ったことです。
石田:結果に結び付くであろう行動が明確でないと、ついつい「気合いのマネジメント」が蔓延します。とりあえずやれ、気合いだ、といった号令レベルのマネジメントですよね。これだとなかなか結果が出ないまま社員は疲弊し、次の手が打てなくなる。泥沼ですよね。
湧永製薬さんのように、社員の昇給や昇格の材料にするという目的の下、社員の行動に着目し、行動した結果を記録するというサイクルを回せる体制にすれば、このような事態を食い止められるはずです。
湧永:社員の行動の量は、毎月集計されて本部に報告される仕組みになっています。ある支店のメンバーからは、行動の量と営業成績の関係性がつかめてきたそうで、支店の士気が上がってきたと聞きました。実際、その支店の行動量を見ると伸びているんです。
お店でのカウンセリングに適用
湧永寛仁(わくなが・かんじ)
湧永製薬社長。1973年、同社創業家の長男として生まれる。1997年慶応義塾大学経済学部卒業後、ソフトバンクに入社。1999年湧永製薬に転じ、取締役に就任。取締役国内営業副本部長、常務取締役営業総括などを経て、2007年から現職。グロービス経営大学院経営学修士(MBA)。
湧永:営業部門の評価の仕組みだけでなく、別の領域でも行動科学マネジメントの考え方を導入し始めています。
当社は医薬品や健康食品を製造・販売しておりますが、お店ではカウンセリングを通じて販売していただくという理念を共有いただき、お取引させていただいています。
来店されるお客様はいろいろな健康上の悩みを抱えておられます。そこで「どうしましたか」とカウンセリングを通じて悩みを引き出し、それに対して適切な製品を提供できれば、それだけお客様も喜ばれるし、お店も信頼度が上がるという考え方です。
石田:カウンセリングというスタイルには、来店客の悩みに柔軟に対応できるというチャンスもある一方で、難しさがありそうですね。
湧永:店頭に立つ薬剤師や登録販売者の先生方の対応がカギを握っています。同時に、お取引先を訪問する営業担当者の活動も重要です。
2011年に、「チェック・アンド・フォローシート」を用意しました。これはお店のコンサルティング活動を支援するものです。このシートには、お店における理想と思われるコンサルティング活動を行動分解し、記述してあります。当社の営業担当者はこれを使って店頭でご説明を差し上げて、その結果をチェックして、それをまた上司がフォローします。
まさに石田さんが行動科学マネジメントで推奨しているチェックシートを適用したものです。
石田:お店の方々も理解しやすいですよね、こういうのがあると。
店舗のコンサルティング支援に活用している「チェック・アンド・フォローシート」
湧永:そうですね。もう少し中身を紹介しますと、お店におけるコンサルティング活動を複数のフェーズに分けて、それぞれのフェーズにおいて、適切と考えられる行動を記述しました。行動の項目数としては合計で数十あります。
シートを最初に作る際、許可をいただいた店頭では、先生方の動きをビデオに撮らせていただきました。リアルな現場の動きを記録にとって何度も観察していると、効果が見込める行動をピンポイントで抽出するのに役立ちます。その後は売り上げが高いお店を複数調べて共通点を特定し、逆にあまり影響のない行動を見つけて省く、といった作業を通じてブラッシュアップしました。
やはり、売り上げが高いお店の先生の行動には共通点があるんです。その共通点が見つかると、当社としてもお取引先には自信をもって「こういう行動が重要なんです」とアドバイスできるわけです。
石田:以前はどうやってお店にアドバイスしていたのですか。
湧永:具体的な資料はありませんでした。先輩からのいわゆる伝承のような形で教わっていました。
営業担当者の行動の質が上がった
石田:チェック・アンド・フォローシートを使い始めてから、お店の反応はいかがでしょうか。
湧永:チェック・アンド・フォローシートには、コンサルティング活動がうまくいっているお店のノウハウが入っています。このような説明を差し上げますと、やはり興味を持ってくださるお店は多いですね。また、実際に中身をお伝えすると、お店の中で気付きが生まれてきたというお声をいただいています。
石田:店舗を訪問する営業担当者の反応はいかがですか。
湧永:行動の質が上がりました。例えば、業務の漏れが減りました。これは大きいです。人間ですから、やはりうっかり特定の手順を忘れたりとか、お取引先にお願いすべきことを忘れてしまったり、ということが起きますよね。これが極少化されました。最低限やるべきことはみんなできている、という体制ができました。
管理職の視点からメリットを挙げますと、チェックシートを使って業務の完了状況が可視化されていますから、部下の仕事で何がどこまで進んでいるのかが把握しやすくなりました。管理職の仕事でよくあるのが、準備が終わってやれやれと思っていたところで、部下からあれがまだ終わっていませんと相談を受けてバタバタとフォローに回る、という状況ですが、これが減りました。
石田:行動科学マネジメントに基づいたチェックシートを用意するメリットは、標準化や業務品質の底上げということが挙げられます。まさに、御社でもそのようなメリットを体感されたということですね。
非常に力を入れて取り組んでおられる様子がうかがえます。行動科学マネジメントのことを知った企業はどこも、具体的な行動内容まで記述したチェックシートは大事だとおっしゃる。けれども、実際にここまで踏み込んで実行に移すケースはそれほど多くありません。
湧永:自社で取り組んでみて、やはり作成するのは相応の労力がかかりました。私は業績を上げている大企業はもうみんな作っているのかと思って、焦りながら取り組みました(笑)。
石田:企業や部署によって差がありますが、体力のある大企業ほど、意外にチェックシートやマニュアルを整備していません。その理由は、マンパワーで何とか回せてしまっている現状があるからです。日本の大企業は幸か不幸か現場に非常に優秀な社員やパートの人たちがいて、その人たちの力量で支えられているようなものなのです。
その一方で、マニュアルやチェックシートが存在し、それに基づいた評価制度が作られている企業でも、機能していないケースが多い。その理由は先ほど(前回の記事を参照)湧永さんがおっしゃった通りで、項目が「積極性」とか「コミュニケーション」という抽象的なレベルにとどまっているからです。現場の社員からすれば結局どう行動すればいいんだ、となるわけです。
やはりマニュアルやチェックシートは、それを使う現場の人たちを巻き込むか、現場経験が豊富な人を中心メンバーに入れて作らないといけません。
「好き嫌い」で決まる評価をなくしたい
湧永:経営者として一番の悩みは、現場の仕事の質を上げたくて、また社員のモチベーションを上げたくてマニュアルや評価制度を作るのに、むしろ社員のモチベーションが下がってしまうということなのです。そして評価については結局、上司の「好き嫌い」に基づいたものになってしまう。当初の意図に反する状況が、現場で起きてしまうのです。
当社が行動科学マネジメントに基づいた評価の仕組みを作り始めるとき、私はいろいろな会議のときに重ねて、「『好き嫌い評価』は会社を弱くする。だから新しい評価の仕組みを検討し始めるのだ」という話をしていきました。
石田:御社だけでなく、どこの企業も同じ問題に突き当たっています。おしなべて人材採用に苦労しており、いい人材を獲得し、引き留めるために社内の制度を改革しようとしているのですが、なかなか打ち手がないという状況に陥っているのです。
湧永:大手も苦労しているのですか。
湧永社長と対談する石田氏
石田:はい。いわゆる有名な企業ですと新卒はたくさん応募があるのですが、課題は中途採用です。いろいろな方面から聞いた話を総合すると、募集しても優秀な人が来ないという悩みで一致しています。
同じく苦労しているのがパートやアルバイトの採用です。産業界全体で人手不足の折、スキルが高い人が採れなくなっている。だからスキルが低い人を雇ってとにかく教育しなければならない。しかし、現場の社員は、雇ったパートやアルバイトの人に何をどう教えればスキルの底上げが図れるかが分からない。結果、現場が混乱して、ますます現場の社員が忙しくなる。つまり悪循環が起きているわけです。
この悪循環はなかなか抜け出すのが大変です。こうした経緯から、行動科学マネジメントに着目する現場も多いです。
経営トップの関与が成功要因
石田:御社の場合は、湧永社長という経営トップ自らが、行動科学マネジメントの導入に関与されました。どんな施策でもそうですが、やはり経営トップがコミットすると強い求心力が働きますから、うまくいきます。特に中堅や中小企業の場合は、経営トップが号令をかけるとそのメッセージが組織中に行き渡りやすいので、スムーズに導入が進むといえるでしょう。
大企業の場合は、事業部単位や人事部が主導で導入する形がほとんどです。ある事業部で実績が出てきたらそれを横展開する、といった格好が典型的です。
湧永:2007年頃に行動科学マネジメントを初めて知ったのですが、その1年後に自社内で研修を実施しました。当社では管理職向けの研修や勉強会を定期的に開催しているのですが、その1つとして行動科学マネジメントを選びました。1年ほど継続しながら、「このような考え方に基づいたオペレーションマネジメントを導入しましょう」というメッセージを社内に送り続けたのです。
石田さんがよく著書で例示されているような、料理の手順を行動に分解するという実習もやってもらいました。その中で「自分のチームの仕事に適用してみたい」と申し出てくれる社員もいましたので、そういう人には現場の仕事を行動科学マネジメントの考え方に従って分解してみる、という課題を与えることもありました。
石田:なかなか本格的ですね。
湧永:研修や勉強会を通じて、行動科学マネジメントの考え方をある程度定着させることができたと思っています。もしかしたら、これが現場で抵抗感なく使われている要因かもしれません。
マニュアルがあるから進歩する
石田:ちょっと話題が変わります。今多くの企業で問題になっているのは、仕事の引き継ぎです。特に専門性が高い仕事だと起きやすいのですが、人事異動が起きた際に、後任の社員が前任者からうまく引き継げず、現場が混乱するという事態が以前よりも頻繁に起きています。
昔から同様の課題はあったのですが、市場の変化スピードが今ほど早くないし、現場の人手にも余裕があったので、社員の頑張りで何とかなっていた。ところが今は変化が早いし、人数は少ないし、前任者も新しい職場で忙しいので、昔以上にきつくなっているのです。
この点、御社では行動科学マネジメントを導入し始めてどう変化しましたか。
湧永:いくつかの現場では、それぞれの業務に応じたチェックシートを作成して使っています。
例えば弊社ではお客様向けのイベントを定期的に開催しています。イベントの経験者はともかく、初めて担当する社員にとっては、何をすればいいか分からない。しかし、チェックシートがあれば、何をすればいいかが把握できるのでスムーズに準備が進められます。
最近、専門性が高い部署でも、チェックシートを整備し始めました。石田さんがおっしゃる通り、人数が少なく専門的な部署ですと、異動が発生した際に混乱するという状況が少なからずありました。
最初に行動分解して記述するのは大変ですが、あとはそれをベースに改良していけばいいですから、比較的スムーズですね。やはりチェックシートがあると便利です。完ぺきな内容ではなかったとしても、記述内容が手がかりになりますから、ゼロベースよりは断然いい。
石田:私は今、ある大手企業の部長から相談を受けています。その人は以前から私の知人で、外資系企業からスカウトされてその企業に移ったのですが、マニュアル類が何もないということで嘆いていました。前の外資系企業では業務マニュアルが整備されていて、社内のドキュメントを開けば、何の仕事をどんな手順ですべきかが一覧になっていたそうです。
その大手企業にはなぜマニュアルがないかというと、「マニュアルがあるとそれに頼りっきりの社員が出てくるのでダメだ」という価値観が定着しているそうなのです。それも考えてみたら極端な話ですよね。マニュアルには仕事の品質を底上げし、それで生まれた社員の余力をより高度な活動に振り向けさせるという目的もあります。マニュアルがあると社員が考えなくなるという図式は必ずしも成り立たない。
話を戻しますと、その知人の前任者は地方の支社に異動になってしまい、直接聞けない。仕方がないので電話をしたら、「いきなり教えてくれと言われても困る。本当に困ったときに、分からないところだけ聞いてくれ」と言われたそうです。しかし、手の付けようがないから困っているわけですよね(笑)。
「今までどうやってこの会社はやってきたんでしょう」とその部長は嘆いていましたが、恐らく伝統的な日本企業でよく見られる光景であるはずです。
でも、今こそ、そういう状況は変えなければいけない。特にこの大手企業は海外への事業展開が弱い。実はその知人は海外展開の強化をしたいということでスカウトされてやってきたのですが、恐らくマニュアルに対する重要性が認識されない限り、海外展開は難しいかもしれません。海外の人の場合は文化や考え方にばらつきがありますから、ますますマニュアルの整備が欠かせません。
(次回に続く)
このコラムについて
輝く課長の行動科学マネジメント
日本の現場を支えているのはミドルマネジャー、すなわち課長です。課長が輝いてこそ、現場が元気になり、企業は発展します。課長の目の前に課題は山積しています。目標達成、新事業の立案、部下の育成から子供の教育、生活習慣の改善まで。様々な課題に対し、対策は提示されていますが、その実行と継続は容易ではありません。自分の行動を自分で改善し続けられる「行動科学マネジメント」で、輝く課長を目指しましょう。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20150605/283971
社長が考える「優秀な若手」が意外に伸びない理由
第1回:3歳児になったつもりで学べますか?
2015年6月17日(水) 井上 高志
「平凡なサラリーマン家庭に生まれて、学校の成績もスポーツもずっと“中の中”。特に誇れるものもなければ、バネにするほどのコンプレックスもない、普通過ぎるほど普通の若者だった」という、ネクストの井上高志社長。東証1部上場後も成長を続けるベンチャーの旗手とは思えない自己分析だ。普通の人でも謙虚に学び続ければ、ビジネスで成功をつかめる。そんな持論を、現役経営者が実体験から説き明かします。第1回は、自己紹介と心構え。伸びる若手に共通するメンタル面の特徴とは?
「井上社長は、理論派ですね!」
そんな編集者さんの一言から、このコラム企画は始まりました。ただ実のところ、もともとの私は、理論派にはほど遠かった。あまりに理論を知らない自分を自覚して勉強して今があります。
はじめまして。ネクスト社長の井上高志と申します。
1995年、26歳で起業。その2年後にネクストを設立し、不動産・住宅情報サイト「HOME'S」を立ち上げました。現在、株式を東証1部に上場しています。2015年3月期の業績は売上高179億円、経常利益23億円となりました。
こう説明すれば、「すごいですね」と言ってくれる人もいます。が、謙遜抜きで、私はいたって普通の人間です。
平凡なサラリーマン家庭に生まれて、学校の成績もスポーツもずっと“中の中”。青山学院大学に進学し、サークル活動とアルバイトを中途半端に楽しみました。特に誇れるものもなければ、バネにするほどのコンプレックスもない。強いて挙げれば、学校の成績もスポーツもずっと“上”で、慶應義塾大学から総合商社に就職した兄に、ちょっとしたライバル心をくすぶらせていたくらいでしょうか。
平凡な若者の転機は「就活惨敗」&「失恋」
そんな私が変わったのは、就職活動を始めた大学3年生の春でした。
腕試しのつもりで受けた小さなベンチャー企業の集団面接で惨敗したのです。不採用の通知を受けるまでもなく、その場でダメだとはっきり分かりました。あえてベンチャーに就職しようとする学生はやはり意識が高い。中途半端に遊んでいた私とは、学生時代の“実績”に差があり過ぎました。「こいつらはホンモノ。オレはニセモノ」――。
打ちのめされた矢先、追い打ちをかけるように恋人に振られました。「米ニューヨークに留学して、現地でニュースキャスターを目指すの」――。そんな理由で、彼女は私のもとを去りました。「日本人が米国でニュースキャスターになろうだなんて、無謀だよ!」と、批判することもできたかもしれません。けれど、そのときの私は、就活で受けたショックもあって、彼女の「志の高さ」に圧倒されてしまいました。自分の人生にビジョンがないことが心底、恥ずかしくなったのです。
著者。上場企業をつくったベンチャー起業家にして、読書家
そこで、起業を考え始めました。「入社5年以内に独立する 。一生かかっても一大事業をつくる 」と公言して、不動産デベロッパーのリクルートコスモス(現コスモスイニシア)に入社。そして宣言通り、4年後に退職し起業しました。
起業したといっても、本来がいたって普通な人間です。お金もなければ、知識もスキルもない。経営者に必要な資質で備えていたのは情熱くらいでした。
これではいけない。ビジネスの戦場で戦うには自分はあまりに丸腰過ぎる。こんなことでは志半ばで倒れてしまう。何より自分の夢についてきてくれた社員たちに責任を果たせない。
そんな思いから、ビジネス書を次々に読み、そこで知ったビジネス理論やフレームワークを実践に移すようになりました。
まずは、私が今までに会社経営に活用してきたビジネス理論をざっとご紹介しましょう。以下に列挙した用語の内容については次回以降にご説明したいと思いますが、「理論を学びながら経営する」ことの雰囲気だけでもざっくりと感じていただければ幸いです。
【2002年ごろ】営業改革を断行した時期
・PUSH型営業からPULL型営業へ
【2008年ごろ】「日本一働きたい会社」を目指し始めた時期
・マッキンゼーの7S
【2009年ごろ】大手ライバル企業への対抗策を練った時期
・ポーターの競争戦略(5フォース)
・マーケティングの3C、4P
【2010年ごろ】マスプロモーションの活用と効果測定に取り組んだ時期
・ファネル分析
・PDCAサイクル
・メディアミックス
【2012年ごろ】海外市場など、新しい投資領域を探った時期
・アンゾフのマトリクス
パッション先行の新入社員が起こした騒動とは……
自社の戦略を社内外に向けて話すときにも、こうしたビジネス理論を使って説明することが多いので、「理論派」と見られるようになってきました。
けれど、最初に申し上げた通り、起業したころは理論派にはほど遠かったのです。むしろ、感性と感情で突っ走る“右脳”派で、“左脳”はほとんど空っぽでした。
パッション先行型の私を象徴する、若いころのエピソードがあります。「HOME'S」を立ち上げる、直接のきっかけにもなった事件です。
リクルートコスモスに入社して1年目の春、新築マンションのモデルルームに常駐し、営業を担当していました。そこに若いご夫婦が訪れ、この物件をとても気に入ってくださいました。さっそく購入の手続きをしたのですが、残念なことにローンの審査が通りませんでした。
ご夫婦はひどく落胆されました。
ただ、営業の社員としては「仕方ない」で済ませるべき場面です。
けれど、まだ新入社員だったせいもあるのでしょう。私はご夫婦に心を寄せてしまいました。このご夫婦のためにいい物件を探して差し上げたい。純粋にそう感じて、行動に出ました。
ご夫婦の希望に合って、ローンの審査も通りそうな別の物件を探し始めたのです。自社物件はもちろん、他の会社の物件情報もかき集めて40件ほど候補を選んで、ご紹介しました。その中からライバル会社の物件を気に入ってくださり、契約に至ったそうです。
上司に怒られても“ハッピー”をつくりたい!
上司にはこっぴどく叱られました。「競合他社を利するだけで、1円の利益にもならないことをしやがって。何のために、お前を雇っていると思っているんだ!」と。もっともです。
けれど、ご夫婦はとても喜んでくれました。後日、菓子折りを持っていらっしゃいました。
「本当にありがとうございました!」
そうおっしゃったときの満面の笑顔! 自分の全身が幸福感で包まれました。「ああ、こういうハッピーな笑顔をつくり続ける仕事がしたい」。これが私の起業の原点です。
この一件で、不動産業界の問題点も見えてきました。買い手にとっては一世一代の大事な買い物なのに、市場に流通する商品すべてをワンストップで網羅的に見る手段がないのです。いわゆる「情報の非対称性」です。この問題を解消する情報インフラをつくれれば、業界を変革できる。そして、誰もが安心納得の住まい選びができるようになる。そう考えて、 ビジネスモデルを練り始めました。ときは1990年代半ば、インターネットが日本で広がり始めたころ。そこで「不動産の情報インフラ」というアイデアを、「不動産情報サイト」という形で具体化したのが、今の主力事業「HOME'S」です。
この連載では、次回以降、私が実践で使ってきた理論をご紹介していく予定です。本を読んで学んだフレームワークを、ネクストというベンチャー企業で実践し、活用してきた私のケーススタディーが、ビジネスパーソンの皆さまに役立つよう、頑張りたいと思います。
ただ、その前に2つお伝えしたいことがあります。
1つは、理論とは理論だけでは役立たないということ。
理論を学んでも、実践しなければ意味はありません。スポーツと同じです。がむしゃらにウサギ跳びをしても体を傷めてしまうから、最新の知見に基づく正しい身体の動かし方を学ぶ。本を読んで学びながら、理論通りに身体を動かす自分をイメージし、実践の後、結果を検証する。こんなプロセスを繰り返しながら、心技体がそろった自分を極めていく。経営、スポーツに限らず、能や狂言といった伝統芸能や音楽など、あらゆる学びに共通する真理でしょう。
理論を実践するには、情熱や感性が必要です。左脳と右脳、両方を鍛えなくてはなりません。起業したときに情熱が先行していた私は、理論に重点を置いて勉強を始めました。けれど、逆の順序がいい人もいるかもしれません。
さらに、ビジネスパーソンが学ばなければならないのは、理論だけではありません。
経営者が学ぶべき4象限
ビジネス理論を学ぶとは、歴史を学ぶことだと思います。リーダーシップ論にしろ、マーケティング論にしろ、およそ理論とは、過去に先人が実践してうまくいったことを整理し、まとめたものです。そして「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」。理論をまったく学ばないのは愚かなこと、ですよね? 私も、松下幸之助さんや盛田昭夫さん、井深大さん、稲盛和夫さんや西郷隆盛さんなど、偉大な先人の生き方に本を通じて触れることで得たものが多くあります。
しかし、過去の歴史である以上、未来永劫、この理論が通用するわけではない、ということも忘れてはいけないと思います。今、使おうとしている理論が、これからの未来に通用するかどうかは、自分で判断するしかありません。
となると、自分のビジネスに関わる未来について、学ぶこともが必要です。IT業界に身を置く私なら、ビッグデータやセンサー技術、ライフログの進化が、世の中をどう変えるかなどについて、目配りしなければならない。さらに、人工知能や再生医療の進化に、人間が倫理的にどう向き合うべきかといったことにも、自分なりの意見を持つべきです。だから、倫理学や哲学の本も読みます。
私は、経営者が学ぶべき領域について、下図のようなイメージを持っています。おおまかに「左脳(理性)と右脳(感性)」、そして「過去と未来」という2軸で区分される4象限がある。これが全体像。これらをバランスよく網羅するように学び続けることを、いつも心掛けています。
(図版制作:新藤真実/HORO DESIGNS)
もう1つお伝えしたいのは、理論を学ぶときの心のありようです。そこで再びこの図です。
(図版制作:新藤真実/HORO DESIGNS)
私のスタート地点は、上図にSで示したポイントです。起業したときに持ち合わせていたのは、使命感と情熱くらいでした。
ほどなくして、そんな自分に危機感を覚えました。最初に気づいたのは、たまたまビジネス誌かビジネス書で「3C、4Pは、マーケティングの基本中の基本」といった記述に出くわしたときだったと思います。「えっ、オレはそんなことも知らないや」と。
今思うと、こんな具合に「オレは何も知らない」「オレは何もできない」というところからスタートしたのが、かえって良かった気がします。
私は今、就職活動や起業の準備をしている若者と話す機会が多くあります。学生時代に勉強もスポーツもできて、新しい学生団体を立ち上げた経験もある。そんな優秀な若者たちの間で、その後の明暗が分かれるポイントがある気がします。それは、「自分はデキる」と思いこんでしまうタイプか、「いろいろやってきたけど、自分はまだまだ発展途上。これからもっと頑張ろう」と思えるタイプかです。小さな自分に満足して、狭い世界に留まるのか。あるいは、もっと大きな自分を目指して、広い世界に飛び出していけるか。その差です。
私がマーケティングの4Pや3Cについて一生懸命、説明しても、「ああ、アレね。知ってる、知ってる」と聞き流してしまう人は多い。一方で、「内容は知っていたけど今まで実践したことはなかったな。良い機会だから、改めてしっかりと理解して実行してみよう」と、興味を持ってくれる人もいます。そこでつく差は、とてつもなく大きいと思います。
3歳児のつもりで学べば伸びる
こんな話をしていたら、「自分が何も知らないと思うと自信を失い、動きが鈍りませんか」と、尋ねる人がいました。
それなら、こうイメージしてください。知らないことがたくさんある自分は今、3歳児のようなものなのだ、と。
3歳の子どもは、知っていることもできることもとても少ない。だからといって、愚かだと思う人がいるでしょうか。そんなことはありません。3歳児は何も知らないからこそ、猛烈なスピードで知識を習得します。朝できなかったことが午後にはできているといった勢いで、スポンジのように新しいことを吸収していく。社会人になってはじめてビジネス理論を学ぶときとも、それと同じ。何も知らなかったからこそ、伸びしろが大きいのです。
伸びる人というのは、「自分は何もできない」と自覚すると同時に、「やればできる」と思っているものです。それも「自分だからできる」ではない。「やれば誰にでもできる。だから自分にもできる」です。そんな肩の力の抜けた感覚で、淡々と学び続ける。実際、ビジネスの理論やフレームワークは、学びさえすれば誰にでも分かるものです。やる気さえあれば、誰にでも使いこなせます。
さて、前置きはここまで。次回からは本編です。いたって普通の人間である私が、いかにビジネス理論を武器に変え、大企業と戦いながら市場を切り拓いてきたかをご説明したいと思います。
(構成:小野田鶴)
日経BP社は、書籍『稲盛流コンパ〜最強組織をつくる究極の飲み会』を発売しました。稲盛和夫氏が生み出した新しい飲み会のスタイル「稲盛流コンパ」は、最強組織をつくる経営手法として広まりつつあります。コンパがなければ、稲盛経営の代名詞とされるアメーバ経営もフィロソフィ経営も成り立ちません。これまで解明されずにいた稲盛経営の深部にもぐり、初めてコンパ経営を解き明かしたのが本書です。企業の経営者はもちろん、あらゆる組織のリーダーに必見の究極の飲み会ノウハウが詰まっています。詳しくはこちらをご覧ください。
このコラムについて
普通の人が上場企業をつくるための超実践講座
「平凡なサラリーマン家庭に生まれて、学校の成績もスポーツもずっと“中の中”。特に誇れるものもなければ、バネにするほどのコンプレックスもない、普通過ぎるほど普通の若者だった」という、ネクストの井上高志社長。普通な人でも謙虚に学び続ければ、ビジネスで成功をつかめます。では、どう学べばいいのか。ゼロから起業して、東証1部上場企業をつくった現役経営者が、実体験から説き明かします。http://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20150603/283864
|
|
|
|
- 「偏差値50のバラ色人生を考えよ!」 ニーズ至上主義の本末転倒 実学重視の教育が凡人を生む rei 2015/6/17 08:53:58
(0)
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。