http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/251.html
| Tweet |
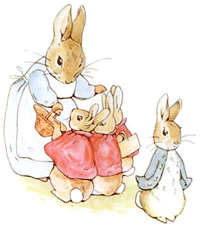
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20131020/plt1310200722001-n1.htm
2013.10.20
15日召集された臨時国会の課題の1つは、東京電力福島第1原発の汚染水漏れ問題だ。この問題の本質を突き詰めると、現在の東電救済スキームを根本的に見直すことになると私は考える。
2年前の2011年8月に成立した原子力損害賠償支援機構法(支援機構法)は、支援機構を通じた公的資金投入で東電の破綻を回避し、原発事故の賠償が滞らないようにすることが目的だった。
なぜ当時の民主党政権は東電の破綻処理を回避したのか。
東電が発行する電力債は当時5兆円にも上っており、かつ、電気事業法では、電力債保有者は優先して弁済を受けられることになっている。つまり、東電を法的整理しても、資産の売却益は賠償原資に回すことができなかったのだ。
しかし、今や東電は、事業継続と事故処理の間で深刻なジレンマに陥っている。事故処理はしなければいけないが、企業として存続するために赤字を垂れ流すわけにもいかない。その結果、汚染水対策費をケチり、対策が後手に回ってしまうという悪循環が続いた。
安倍晋三首相は「汚染水問題は東電任せにせず、政府が前面に立つ」と宣言したが、9月10日の閣議決定では、政府が汚染水対策に予備費を投入できるのは「技術的に難易度の高いもの」に限られている。
安倍政権が進める凍土遮水壁は前例がなく、この基準に該当する。だが、汚染水対策には多重防御が必要で、粘土壁による「第2壁」も同時に作るべきだ。この粘土壁は在来工法で、「技術的に難易度が高い」とは言えない。つまり、民間会社である東電に国費を投入できる根拠がないのだ。
そこで、私は東電の救済スキーム見直しを提案したい。
事故処理や廃炉に関しては国が関与する新組織(廃炉機構)を作り、東電から切り離す。そこに内外から人材・技術を集め、資金を投入する。東電の法的整理・発送電分離を同時に行い、発電部門・小売部門の売却益や、送電会社として生まれ変わった東電の収益は賠償に回すという枠組みだ。2年前には債券市場の混乱が懸念されたが、すでに原発を持つ他の電力会社8社の社債発行が復活するなど、市場は安定している。
支援機構法とその付帯決議では、2年をめどに枠組みを見直すとされているが、安倍政権は着手していない。安倍首相は2020年東京五輪に向けて「抜本的なプログラムに着手し、実行することを約束する」と国際公約した。東電救済スキームの見直しこそ、踏み出さなければいけない大きな課題である。 (民主党選対委員長)
| 拍手はせず、拍手一覧を見る |
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
(タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明)
(←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)
↓パスワード(ペンネームに必須)
(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証

( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。