http://www.asyura2.com/13/ban6/msg/421.html
| Tweet |
(回答先: ムラヴィンスキー 世紀の名盤 投稿者 中川隆 日時 2014 年 1 月 29 日 21:24:18)
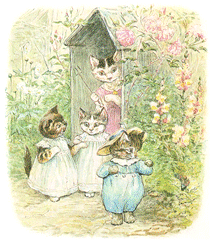
Sofronitsky - YouTube
http://www.youtube.com/results?search_query=Sofronitsky&sm=3
ソフロニツキー -ニコニコ動画GINZA
http://www.nicovideo.jp/tag/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%83%84%E3%82%AD%E3%83%BC?sort=n&order=d
スクリャービン 詩曲「炎に向かって」 ソフロニツキー
http://www.nicovideo.jp/watch/sm13868328
【ロシアのショパン】スクリャービン神曲集【左手のコサック】
http://www.nicovideo.jp/watch/sm7339816
ソフロニツキー:スクリャービン演奏集
http://www.nicovideo.jp/watch/sm22607683
http://www.nicovideo.jp/watch/sm22607922
スクリャービン ピアノソナタ第5番 作品53 ソフロニツキー
http://www.nicovideo.jp/watch/sm13868591
スクリャービン ピアノソナタ第9番「黒ミサ」 作品68 ソフロニツキー
http://www.nicovideo.jp/watch/sm13868450
Sofronitsky plays Beethoven Sonata No. 32 , Op. 111
http://www.youtube.com/watch?v=nA6veYrhjts&list=PL47127B65CB7ED537
Vladimir Sofronitsky plays Schubert Sonata B flat major
Live recording 1960
http://www.youtube.com/watch?v=5XwPT5jz-9k&list=PL47127B65CB7ED537
http://www.youtube.com/watch?v=sa7vJunPTno&list=PL47127B65CB7ED537
http://www.youtube.com/watch?v=GFVymVw2DQI&list=PL47127B65CB7ED537
http://www.youtube.com/watch?v=iv4yYc5_QCs&list=PL47127B65CB7ED537
Vladimir Sofronitsky plays Schubert Impromptu Op. 90, No. 1
http://www.youtube.com/watch?v=WnfOr8AolhM&list=PL47127B65CB7ED537
Vladimir Sofronitsky plays Schubert Impromptu Op. 90, No. 3
http://www.youtube.com/watch?v=PL6gZ0vMIlQ&list=PL47127B65CB7ED537
Vladimir Sofronitsky plays Chopin Ballade no.3. op47
http://www.youtube.com/watch?v=HM0E4Vqb508&list=PL47127B65CB7ED537
Vladimir Sofronitsky plays Chopin Mazurka Op. 41 No. 2
http://www.youtube.com/watch?v=m5NHeauBtTM&list=PL47127B65CB7ED537
Vladimir Sofronitsky plays Chopin "Barcarolle" Op. 60
http://www.nicovideo.jp/watch/sm7301407
http://www.youtube.com/watch?v=G6dKMCofOrE&list=PL47127B65CB7ED537
シューマン クライスレリアーナ 作品16 ソフロニツキー(p)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm10925478
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。