http://www.asyura2.com/12/senkyo128/msg/905.html
| Tweet |
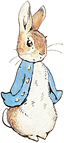
■ 消費税(付加価値税)と経済成長
● 消費税(付加価値税)増税は経済成長抑制策
消費税増税法案が閣議決定に至る前の民主党内議論で、増税反対派は、実施に移される直前でも実施を阻止できるよう、景気弾力条項の増税実施条件に経済成長の具体的な数値目標を書き込もうとした。
その戦術的意義はともかく、97年の消費税増税政策の“顛末”を思い起こせばわかるように、景気が上向いた経済状況でも消費税の税率をアップすれば、元の木阿弥どころか、ダイエットのリバウンドのように前よりひどい落ち込みになる。
財務省やメインストリームの経済学者は認めようとしないが、現在に至る日本経済のデフレ不況を確固たるものにしてしまった最大の要因(失策)は、97年に実施された消費税の増税なのである。
バブル崩壊後も緩やかながら増加していた名目の給与総額が一転して低下に向かったのは、97年の消費税増税で企業経営が深刻なダメージを受けた直後の98年からである。
そして、総需要の要である給与総額が減少する荒波をかぶった日本経済は、99年からはっきりとデフレ基調に移行したのである。
03年のはじめには明瞭になった「異常円安景気」でデフレ圧力は緩和されたが、99年から02年までの日本経済は、まさにデフレ・スパイラルと言える推移を見せたのである。
消費税増税が実施された97年は幸いなことに給与総額が対前年比で2%増加していたので、増税の悪影響が少し緩和された。
しかし、拓銀や山一証券の破綻に象徴される金融危機の再燃からは逃れることができなかった。金融危機はその後も拡大し、翌98年には長銀・日債銀が破綻に至った。
(※ 財務省などそれらを「アジア通貨危機」に結びつけようとする人たちもいるが、金融危機は、アジア通貨危機が要因ではなく、以前からの国内融資の焦げ付きが一気に拡大したことが主要因である。消費税増税と金融危機の関連性は後述する)
【消費者物価指数と給与総額の対前年比対照表】
(単位:%・CPI:消費者物価指数)
年度: CPI:給与総額:
88: 0.7: 3.5:
89: 2.3: 4.2:★3%の消費税導入
90: 3.1: 4.7:
91: 3.3: 3.5:
92: 1.6: 1.7:
93: 1.3: 0.6:
94: 0.7: 1.8:
95:−0.1: 1.8:
96: 0.1: 1.6:
97: 1.8: 2.0:★消費税2%税率アップ(地方分を含む)
98: 0.6:−1.4:
99:−0.3:−1.4:
00:−0.7:−0.3:
01:−0.7:−0.9:
02:−0.9:−2.9:※戦後最長の「異常円安好景気」開始
03:−0.3:−0.1:
04: 0.0:−0.8:
05:−0.3: 1.0:
06: 0.3: 1.0:
07: 0.0:−0.9:
08: 1.4:−0.5:※リーマン・ショックで円安と好景気終了
09:−1.4:−4.8:
10:−0.7: 1.4:
消費税がGDPそのものである付加価値に課される税であることを考えれば、それまでの経済状況がどのようなものであれ、その増税が経済成長を抑制してしまうのは当然である。
政府も、増税一辺倒という非難を避けようと、11年度から20年度にかけて、平均で名目3%程度・実質2%程度のGDP成長率を目指す総合政策を行うという内容を消費税増税法案に盛り込んだ。
消費税増税の根拠である税収不足額の見積もりが名目成長率1%台を前提として算出されていることとの整合性や想定GDPデフレーター+1%に伴う金利上昇の問題などはさておき、名目3%という年平均成長率は、「戦後最長の好況期間」を含む01年から10年までの年平均名目成長率がマイナス0.6%という事実を考えると、とてつもなく高いハードルであることがわかる。10年の名目GDPは479兆円と、01年の名目GDP498兆円に比べて3.8%も減少している。
信頼性から多くの企業が経営計画の基礎データとして利用している日本経済研究センターの中期経済予測では、11年から20年の年平均名目成長率は0.2%・年平均実質成長率は0.9%となっている。
日本経済研究センターの中期経済予測に消費税の税率5%アップが織り込まれているのか不明だが、5%という消費税の大型増税が現実のものになると、政府の目標よりずっと低い日本経済研究センターの予測値でさえ達成できないと断言する。
97年は表面的には金融危機の再燃にとどまり、GDPに深刻な悪影響が現れたのが翌98年からだった前回の消費税増税とは異なり、14年と15年に給与総額が前年比で増加するとは思えない現状を考えると、3%アップされる14年も、2%アップされる15年も、その年からすぐにGDPに多大な悪影響が現れると予測する。
さらに、総需要変移と供給力変化の連関性から、14年の3%アップは15年及び16年のGDPにも多大な影響を与え、15年の2%アップは16年及び17年のGDPにも多大な影響を与える。
消費税増税の衝撃的影響が一段落し増税が経済活動に馴染み始める18年以降も、大規模の財政出動があれば別だが、外需に大きな改善がなければ、低迷したままじりじりと下押し圧力にさらされることになる。
上の表でも、輸出に支えられた「異常円安好景気」が顕著になった03年から指標に改善の兆しが見えているが、それも時間外手当や一時金(賞与)の増加を反映した限定的なものでしかなかった。
増税がGDPに及ぼす甚大な悪影響が重なる15年と16年の2年間は、それこそ、“想定外”で“未曾有”の経済的苦境が日本に満ちることになるだろう。
「それじゃあ、何のためにわざわざ消費税を増税したのか!?」という非難を恐れずに、バラマキと雇用創出に徹する大規模な財政出動に踏み切らない限り、経済的苦境がどれだけ緩和されるかという問題は、ユーロ圏や米国・中国の経済が回復してどこまで活況を呈するかという外需任せの話になる。
ユーロ圏の緊縮財政や貸し渋りがEU諸国やその他の地域の経済活動に深刻な影響を与えるのは今年後半から来年にかけてだろうから、消費税増税が予定されている14年や15年の時点で大きな回復が見られるとは考えにくい。
米国や中国の経済状況もふらふらした足取りでしかなく、EU諸国がより深刻な不況に向かえば、その影響を受けて低迷に陥ってしまう。
たんなる話だけだが、政府が法案に盛り込む名目3%の経済成長が達成されれば、20年の名目GDPは613兆円ほどになり、国税の税収水準が現在と同じ対GDP比8.5%としても、52兆円ほどの税収が見込める。
景気回復期の税収弾性値は大きく、名目GDPの拡大は同時に名目所得や企業利益の増加につながるので、所得税の累進性や法人税納税企業の拡大を考えると、税収は少なくとも対GDP10%の61兆円には達するだろう。
税収の対GDP比は、バブル崩壊後でも、97年度までは10%超を維持していた。
消費税増税法案を成立しやすくするために気をひく数値を並べただけというのなら別だが、本気なら、尋常ならざる政策の発動しか実現の道がないような数値である。
法律の条文に加えるからには、政府は、14年・15年にかけて消費税税率を5%アップしてもなお、11年から20年の年平均名目成長率を3%程度・年平均実質成長率を2%程度に引き上げられる政策の中身を提示する義務がある。
デフレ脱却のためにこれまで採られてきた数々の政策と違うどのような政策を実施するつもりなのかを示さないまま、法律の条文に「11年度から20年度にかけて、平均で名目3%程度・実質2%程度のGDP成長率を目指す総合政策を行う」といった文言を加えるというのはゴマカシやマヤカシでしかない。
消費税増税を実現するためならなりふり構わず、条文までデタラメな文言で彩るといった対応は、「大東亜戦争」の轍を踏むようなもので、とうてい認められない。
経済の現状と有力企業の姿勢を考えると、名目3%・実質2%の経済成長を持続的に達成するには、対前年比15%程度の歳出拡大を続けなければならないだろう。11年GDPを基準として名目3%は14兆円、11年度歳出を基準として15%は14兆円ほどになる。
“総合政策”として必要な歳出規模は、12年度で109兆円、13年度は125兆円・・・という具合になる。そして、14年・15年には消費税の5%増税という大きな経済成長阻害要因が発生する。5%の増税で13.5兆円の増収を見込んでいるのなら、それを補うだけの歳出拡大を追加的に行わなければならない。消費税増税の影響が、設備投資の増加など経済拡大に伴う自律的拡大を吹き飛ばす可能性が高く、消費税増税の直接的影響が落ち着く17年以降も、毎年度15%ずつの歳出拡大が必要となるだろう。
(※ 12年度予算の一般会計は90兆3千億円だが、東日本大震災の復興経費は特別会計で管理されている。歳出規模は、特別会計や補正予算を含めたものがベースとなる)
歳出の拡大に伴い、税収も、初年度で3〜4兆円ほど増え、以降も8%程度の率で持続的に増加するが、景気対策で拡大させた財政赤字の1/4程度を回収するに過ぎない。このため、政府債務残高はぐんぐん膨らんでいくことになる。
名目3%の経済成長を達成するために、14兆円から20兆円もの財政赤字拡大を辞さないというのなら、他の税目も増税せず据え置いたままで、10兆円程度の税収である消費税を廃止したほうが、国民生活の安定にとっても経済成長にとってもより効果的な政策である。
日本経済に活力を取り戻したいのなら、まず、消費税の廃止から手を付けるべきである。それにより落ち込む?税収をカバーするための税制改革は、経済に活力が戻ってから論議すればいい。
日本経済はそれくらいの余力がある。別の言い方をすると、それくらい余力があるからこそ、赤字国債の発行が税収を超え歳出の半分近くを占めるような財政運営が続いても、デフレからインフレに転換しないのである。
「とんでもない、ただでさえ財政が苦しく社会保障制度の維持さえ難しい状況なのだから、これ以上赤字を増やす政策を採るわけにはいかない」というのなら、歳出の拡大を伴わずに名目3%の経済成長を達成する“秘術”を開陳してもらいたい。
名目3%成長をめざすという総合政策が、法案を可決させるための戦術的な“美辞麗句”でしかないというのなら国家犯罪である。
日本経済の潜在力や需給ギャップを考えれば、有力企業と政府そして日銀が強い意志でスクラムを組み進み始めることで、名目3%・実質2%というレベルの持続的な成長は達成できるだろう。
しかし、14年、15年と消費税の税率アップを実施すれば、それを契機に経済が落ち込み、赤字財政の拡大など追加的な政策を行うか経済成長を諦めるかの選択をしなければならなくなる。
● デフレ下での消費税(付加価値税)増税は愚の極み
国民経済がデフレ基調にあるなかで、付加価値税(消費税)の導入や付加価値税の税率アップという政策を選択する政府は愚の極みである。
デフレ基調にある日本が14年4月から15年10月にかけて5%もの消費税増税を実施すれば、その後の日本の推移は、壮大でリアルな社会実験として経済学の貴重な考察対象になってしまうだろう。
付加価値税(消費税)は、インフレ基調の国民経済に導入されたり、インフレ基調のなかで増税されたことはあっても、デフレ基調のなかで導入されたり増税されたことはないからである。
欧州諸国が付加価値税(VAT)を競って導入した70年代は、スタグフレーションさえ経験した高いインフレの時代である。
日本以外の先進諸国は、その後もデフレとは無縁でインフレ基調が続き、付加価値税の税率アップもインフレ基調のなかで行われてきた。
97年の消費税増税も、日本経済がデフレ基調に転換する契機にはなったが、増税時点はごく緩やかなインフレ基調だったのである。
消費税(付加価値税)の負担増加は、インフレ基調にある国民経済にも大きな悪影響を与えるが、デフレ基調にある国民経済にはよりいっそう深刻な打撃を与え、国民経済をデフレ・スパイラルの深みに引きずり込むトリガーとなる。
それが国民生活にどのような苦痛をもたらすかは、ここ15年の日本を思い返し、現在の日本を見ればわかることだ。
民主党では、木内孝胤代議士に続き平山泰朗代議士も、消費増税関連法案の国会提出に抗議して離党届を提出した。平山泰朗代議士は、離党してまで法案に反対する理由について、「デフレ下で消費税率を引き上げることは困窮者や自殺者を増やすことになる」と説明したという。
経済成長とは、その国民経済から生み出される付加価値の総計が増加していくことである。
ストックではなくフロー(付加価値の生成と移転)への課税は、どれもが付加価値への課税とも言えるが、事業者の最終利益に課税される法人税や個人の所得レベルに応じて課税される所得税とは違い、付加価値そのものに生で先行して課税される消費税(付加価値税)は、炭素発生ならぬ経済成長を抑制する税であり、経済成長を罰する税とも言える。
デフレ経済と消費税(付加価値税)の関係をかいつまんで説明する。
どの企業もマージン(付加価値)が多くなるよう少しでも高く商品を売ろうと動くのに、それができないどころか、逆に価格が下がっていくというのがデフレである。
そのようなデフレ状況では、値上げの目的が何かにかかわらず、販売価格を引き上げることは困難である。消費税に引きつけて言えば、増税で増加した消費税の負担を販売先や最終消費者に転嫁することは、インフレ基調の経済状況に較べてずっと難しくなる。
値上げの目的が儲けを増やすことなのか税負担を転嫁することなのかといった供給サイドの都合は、需要サイドが根源的に規定する値上げのしやすさやしにくさに影響を与えるものではない。
内税制度の現在ではなおさらであるが、転嫁しやすそうに思える外税制度でも、値上げで販売数量が減少してしまうのなら、値上げは困難と判断しなければならない。
とにかく、(利幅×数量−消費税負担額)の値が増税前より小さければ、消費税増税に伴う負担増の転嫁は十分にはできなかったことになる。
消費税の負担増加分を第三者に転嫁できなければ、事業者は自身のマージン(付加価値)を削って消費税の納税に充当するしかない。
最終利益が出ていれば利益の減少で済むこともあるが、余裕があまりない状態で事業を営んでいるのなら、経費を削るか人件費を削るかして、増加した消費税を納付しなければならなくなる。
すでにぎりぎりの経費と人件費で事業を営んでいるところなら、事業を縮小するか畳むかしかないところまで追い込まれる。
日本商工会議所などが昨年実施した調査では、売上高5千万円未満の企業のおよそ70%が消費税増税分を「販売価格に転嫁できない」と答えたという。
百貨店大手の高島屋社長も、「消費税率が第一ステップの8%に引き上げられた段階で、300億円の減収要因になる」と語っている。
増加した負担の転嫁が十全にできるのなら、その分だけ税込売上が増加するから売上は変わらない。高島屋の売上は8600億円ほどなので、300億円の減収は、消費税の3%アップで3.5%の減収に相当する。
(※ ただし、百貨店業界共通の問題として、高島屋も、今年度も1.3%の減収という長期減収傾向に身を置いているから、その傾向を織り込んだ上での予測数値であろう)
さらに、借入金の利払いや元本返済も稼いだ付加価値が原資だから、消費税の負担増加で手元に残る付加価値が減少すれば、利払いの滞りや倒産といった事態が多く発生するようになる。
この論理が現実にはっきりと現れたのが、消費税導入の翌年90年から始まった「バブル崩壊」であり、消費税税率が2%アップした97年に再燃した金融危機なのである。
(※ ただし、「バブル崩壊」はあくまでもバブルの形成自体が崩壊の主因であり、消費税の導入は、一因でありトリガーでしかない)
次に、デフレのなかでも増加した消費税の負担を最終消費者に転嫁できる企業(業界)が存在する場合を考えてみる。
デフレ基調にある国民経済は、これまでの日本経済の推移でわかるように、名目ベースの総需要やGDPが縮小する傾向にある。
そのような経済状況で、ある企業(業界)が増加した消費税負担を最終消費者に転嫁すると、別の企業(業界)は、そのしわ寄せで、消費税の転嫁がいっそう難しくなる。
それどころか、転嫁に成功した企業(業界)にただでさえ減少傾向にある総需要を多くとられることになるから、販売価格の低下や販売数量の減少に見舞われ、増税前に得ていたマージン(付加価値)さえ得られなくなる可能性が高い。
増税で消費税の負担が増加するだけでなく、限られた総需要のなかで負担の転嫁に成功した事業者の余波をかぶることで、増税を上回るレベルで負担を背負う事業者まで出てくるのである。
離党届を提出し、「デフレ下で消費税率を引き上げることは困窮者や自殺者を増やすことになる」と語った平山代議士は、消費税増税で起きる日本の変化がリアルにイメージできているのだろう。
日本の全産業平均の名目賃金は月ベースで、2000年の36万円弱から11年の32万円弱までじりじり減少してきた。このような変化が、名目GDPを縮小に向かわせる動因であるとともに、デフレ基調が続く基本要因であり、増加した税負担が転嫁できない土壌でもある。
日本の名目賃金は95〜10年のあいだに11%も減少した。一方、付加価値税(消費税)の増税が何度か行われたユーロ圏の名目賃金は、同じ期間で40%も増加している(米国は72%の増加)。
このような差異が、円がドルやユーロに対し高くなる基礎的要因でもある。
インフレ基調なら、名目では所得が増加しているが実質では減少という変動もある。
実際、00年から10年にかけてドイツの平均給与は、名目では12%増加しているが、物価上昇を加味した実質では4%減少している。
ドイツでは中間層(単身世帯で月間名目収入861〜1844ユーロ)の割合が00年の66%から10年には60%まで下がっている(ドイツ経済研究所調査)ことを考えると、名目所得が増加しても、中所得層にいたある部分は、名目と実質のズレのために低所得層に落ちるものであったことがわかる。ドイツの製造業も、日本と同じように、賃金上昇を抑えつつ派遣労働者への依存を増やしている。
日本は逆だが、実質賃金より名目賃金の増加率のほうが高い経済状況なら、付加価値税(消費税)の負担が増加しても最終消費者に転嫁しやすい。
増税分の転嫁で値上げが行われても、名目所得の増加を支えに高くなった商品やサービスが買えるのなら、消費者は生活レベルを下げずに、事業者は付加価値を減らさずに、付加価値税増税の衝撃をなんとかかわすこともできる。
それでも、企業は利益を追求しているのだから“便乗”という非難は当たらないのだが、価格の引き上げを税負担増加分より多くできる事業者と負担増加に見合うほど価格の引き上げができない事業者という差異は生じる。
日本の財務省は、インフレ基調でもやるべきではない付加価値税増税を、愚かにも、絶対やってはならないデフレ基調の日本でやろうとしているのである。
かつて小泉元首相の政策をののしるほど批判したが、遅ればせながら、小泉元首相が消費税増税を政策の選択肢から遠ざけていたことを高く評価したい。
消費税増税に猪突猛進の野田首相のおかげ(笑)だが、これをもって、野田政権に、小泉政権を超える国民経済破壊者の称号を贈る。
消費税の税率アップは、経済状況が悪ければその度合いをさらに深くし、経済状況が良くても悪化に転じさせてしまう論理を内包しているのである。
消費税増税は、15年も続いているデフレ基調経済をさらに悪化させ、中小零細を中心に企業や商店の経営を疲弊させ、低中所得者を中心に国民の生活を困窮に向かわせる破滅的政策である。
けっして愚かではない財務省の官僚たちは、それが分かっていながら、菅―野田政権に消費税増税の実現を必死に働きかけてきた。
野田政権は、恒久かつ多段階の消費税増税の“お墨付き”を手に入れる“代償”として(身を切る姿を見せるため)、国家公務員給与の“2年間限定”7.8%切り下げや国家公務員の採用人数の大幅削減という異様で誤った“総需要縮小政策”まで持ち出した。
さらに、消費税増税で得られる増収分は、社会保障や少子化対策以外には使わないという意味のない“目くらまし”の文言を法案に盛り込んだ。
増税に“社会福祉目的”というお為ごかしの話をことさら持ち出さなくとも、社会保障費だけで既に歳出規模が26兆円に達し、今後も毎年1兆円ずつ増大していく。社会保障や少子化対策が使途と言えなくもない文教関連予算6兆円や地方交付税交付金16兆円まで加えると、社会福祉と言ってもおかしくない歳出規模は既に48兆円に達している。
このような歳出構造を前提にすれば、1%で2.5兆円の税収と仮定しても、20%までの消費税増税なら、「社会保障&少子化対策(社会福祉)目的」と言えてしまう。
社会保障財源は、その規模からわかるように、道路特定財源とはわけが違うのだ。
続く投稿で、消費税増税が国民生活や経済社会に及ぼす弊害や消費税増税が「財政再建」の手段として無効であることを知りながら、消費税増税に向けしゃにむに走る財務省官僚の意図が何かを探っていきたい。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
- Re: 名目GDPと実質GDPの関係 佐助 2012/4/16 21:52:18
(0)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK128掲示板
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。