| Tweet |
(回答先: ≪野党の皮を被った傾国の張本人 谷垣禎一総裁、柴山昌彦議員、茂木敏光議員、後藤田正純議員らの正体&水谷建設の醜聞≫ 投稿者 Roentgenium 日時 2010 年 1 月 23 日 03:39:11)
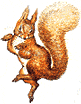
(まえがき)
コメントにも寄せられたとおり、本文の題名とは一見かなり乖離?した内容ですが、
「独身税」の部分に関する≪補足≫として、参考になるようにアップしておこうと思います。
たしかに政治の動きを追ってそれを解き明かしたり、糾弾することも重要です。
しかし、いっぽうで大きなテーマについて俯瞰的に捉え、試行錯誤することも必要なことではないかと
考えるのです。
「独身税」に関連して、と先に書きましたが、ここで≪補足≫として追記する内容は、
じつは「永住外国人参政権」の問題などにも無関係ではないと思います。
---------------------------------------
≪補足≫ 「人口論」と、優生学について
---------------------------------------
人口増加=納税者拡大、経済発展・税収増加に繋がるとは必ずしも思えない。
それよりも、今ある民間の雇用を安定させ、生活基盤を与える。その整備を着実に進めていくことが、持続的な社会を設計する上での基本だと思う。
戦争の為の兵力確保、平時における奴隷として、或いは淘汰していく中で優生学の実験をするのなら話は別だが・・・・
■トマス・ロバート・マルサス Thomas Robert Malthus 「人口論」~概略 その1
(以下、P.72~P.73 一部引用転載)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
「集団殺戮に関する覚え書き」
人口を一定に保つ為に、必要な数を超えたすべての子供たちは、大人の死によって空きが出た時を除いて必ず消滅させなければならない。
愚かにそして無益に人口増加を遅らせる努力をするよりも、死ぬ運命を生じさせる大自然の働きを促進させるべきである。
もし、忌わしい形の大飢饉の訪れが怖いならば、我々は殺戮の為に自然を服従させる他の手段を熱心に促進するべきである。
それにもまして、
病気を治癒する特別の治療法や薬品、特定の病気を根絶する方法を研究することによって、人類に貢献していると勘違いしている
慈悲深い男たちを拒絶するべきである。
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
※参考1 「大量殺りくの慶賀:戦争と集団的健忘症-Chris Hedgesのコラム」
http://eigokiji.justblog.jp/blog/2010/01/-chris-hedges-a.html
※参考2 「人々が目にしてはいけないことになっている戦争写真-Chris Hedgesのコラム」
http://eigokiji.justblog.jp/blog/2010/01/-chris-hedges-1.html
(以下、一部引用転載)
戦争は残虐で、人間味の無いものだ。個人の勇気ある行動といった夢想や、民主主義といった夢想的な目標のばからしさを嘲笑うものなのだ。
産業技術を駆使する戦闘は、攻撃してくる相手など見たこともない何十人、いや何百人もの人々を、一瞬で殺害出来る。
こうした高度な工業生産による兵器の威力は無差別で、信じがたいほどだ。瞬く間に、団地にいる全員を生き埋めにし、粉砕することが可能だ。
そういう兵器は、村々を破壊し、戦車や、飛行機、船舶を灼熱の爆発で吹き飛ばすことが可能だ。
生き残った人々にとって、傷は、酷い火傷や、失明や、四肢切断や、一生続く痛みやトラウマとなって残る。
こうした戦闘から戻ると、人は変わってしまうものだ。しかもこうした兵器が使われてしまえば、人権にまつわるあらゆるあらゆる論議も茶番劇と化する。
生き残った人々を、絶望と自殺が、とらえて離さない。戦争中に亡くなった人数より多くのベトナム戦争退役軍人が、終戦後に自殺した。
戦時に、兵士や海兵隊員に叩き込まれた非人間的な資質が、平和時に、彼等を打ち破るのだ。
これこそが、戦争に纏わる偉大な書物『イーリアス』と、職業的殺人者の回復に至る長い旅を描いた偉大な書物『オデュッセイア』の中で、
ホメロスが我々に教えてくれていることだ。
多くの人々は、決して再適応することが出来ない。彼等は、妻や、子や、両親や友人達と、再び意思を通じ合うことが出来ずに、
自己破壊的な苦悶と憤激という、孤独の地獄に引き篭もる。
「連中は、兵士がいかなる感情も持たないよう、条件づけるのです。隣に座っている誰かが殺されても、黙って自分の仕事をやり続けるという具合に」
フォークランド戦争に従軍したイギリスの退役軍人スティーブ・アナベルは、グリンカーに、こう語っている。
「退役した時に、そういう状況から戻った時に、退役した人間の感情を、押すだけで、よみがえらせることができるボタンなどありません。
そこで、退役兵士は、ゾンビーのように歩き回ることになるのです。連中は、感情を殺すように条件づけした退役兵士を、条件づけから解除出来ないのです。
退役兵士が厄介者になると、連中はそうした人物を隠してしまうのです」
■トマス・ロバート・マルサス Thomas Robert Malthus 「人口論」~概略 その2
Wikipediaより
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E8%AB%96
【人口の原理】
先ず、マルサスは基本的な二個の自明である前提を置くことから始める。
①第一に食糧(生活資源)が人類の生存に必要である。
②第二に異性間の情欲は必ず存在する。
この二つの前提から導き出される考察として、マルサスは人口の増加が生活資源を生産する土地の能力よりも不等に大きいと主張し、
人口は制限されなければ幾何級数的に増加するが生活資源は算術級数的にしか増加しない、という命題を示す。
人口は制限されなければ幾何級数的に増加するという原理は理論上における原理である。
風俗が純潔であり、生活資源が豊富であり、
社会の各階層における家族の生活能力などによって人口の増殖力が完全に無制限であることが前提になっている。
この理論的仮定において、
繁殖の強い動機づけが社会制度や食料資源によって一切抑制されないならば、人口増は現実の人口状況より大きいものになると考えられる。
ここでマルサスは米国において、より生活資源や風俗が純潔であり、早婚も多かった為に、
人口が25年間で倍加した事例を示し、この増加率は決して理論上における限界ではないが、これを歴史的な経験に基づいた基準とする。
そこで人口が制約されなければ25年毎に倍加するものであり、これは幾何級数的に増加することと同義である。
“生活資源は算術級数的にしか増加しない”という原理は、次のような具体的な事例で容易に考察出来る。
ある島国において生活資源がどのような増加率で増加するのかを考察すると、先ず現在の耕作状況について研究する必要がある。
もし最善の農業政策によって開拓を進め、農業を振興し、生産物が25年で2倍に増加したという状況を想定する。
このような状況で次の25年の間に生産物を倍加させることは、土地の生産性から考えて技術的に困難であると考えられる。
つまり、このような倍加率を指して“算術級数的な増加”と述べることが出来る。
この算術級数的な生活資源の増加は人口の増加と不均衡なものであると考えられる(注.1)。
◇ ◇ ◇
(注.1):
マルサスは人口と生活資源の増加が不均衡であることについて、次のような具体的な状況を想定している。
ある島国の人口は約700万名で、生活資源となる生産物がこの人口を充足させる分量だけ存在すると仮定する。
25年ごとに、人口は幾何級数的に1400万、2800万、5600万と増加するが、食物は算術級数的に1400万、2100万、2800万としか増加しない。
1世紀の終わりには人口が1億1200万名で、生活資源は3500万名分の不均衡が発生することになる。
この議論は地球全体にも適用出来る議論であり、仮に全世界の人口が10億名であり、生活資源は充足しているという状況を想定すると、
225年後の人口と生活資源の比率は512対10となり、3世紀後には4096対13まで拡大する。
【貧困の出現】
次にマルサスはこのような人口の飛躍的な増加に対する制限が、どのような結果を齎すかを考察している。
動植物については、本能に従って繁殖し、生活資源を超過する余分な個体は場所や養分の不足から死滅していく。
人間の場合には、動植物のような本能による動機づけに加えて、理性による行動の制御を考慮しなければならない。
つまり経済状況に応じて人間は様々な種類の困難を予測していると考える。
このような考慮は常に人口増を制限するが、それでも常に人口増の努力は継続される為に人口と生活資源の不均衡もまた継続されることになる。
人口増の制限は人口の現状維持であり、人口の超過分※の調整ではない。
このような事実から、人口増の継続が、生活資源の継続的な不足を齎し、したがって重大な貧困問題に直面することになる。
何故なら、人口が多い為に労働者は過剰供給となり、また食料品は過少供給となるからである。
≪≪このような状況で結婚することや、家族を養うことは困難である為に人口増はここで停滞することになる≫≫。
安い労働力で開墾事業などを進められることで、
初めて食料品の供給量を徐々に増加することが可能となり、最初の人口と生活資源の均衡が回復されていく。
社会では、このような人口の原理に従った事件が反覆されていることは、注意深く研究すれば疑いようがないことが分かるとマルサスは述べている。
このような変動がそれほど顕著なものとして注目されていないことの理由は、
≪≪歴史的知識が、社会の上流階級の動向に特化している≫≫ことが挙げられる。
社会の全体像を示す、民族の成人数に対する既婚者数の割合、結婚制度による不道徳な慣習、社会の貧困層と富裕層における乳児の死亡率、
労賃の変化などが研究すべき対象として列挙出来る。
このような歴史は、人口の制限がどのように機能していたのか?を明らかに出来るが、現実の人口動向では様々な介在的原因がある為に不規則にならざるを得ない(注.2)。
◇ ◇ ◇
(注.2):
介在的原因とはある産業の開始や失敗、農業の衰退や農業の豊凶、戦争、労働力の節約、労賃と物価の相違などである。
※参考1 「人口可容論」
人口可容論(じんこうかようろん)とは、将来の地球上に想定できる可容人口数を算出するもので、地理学を中心に発展してきた。
ドイツのペンクは、人類の総数(Z)は地表単位の平均生産(P)に全陸地(L)を乗じた数に、各人の平均食料需要量(n)で割ったものから算出されると考案。
Z=LP/nはペンクの基本公式と呼ばれる。
ペンクは、ケッペンの気候区分を利用して、地球上の最大可容人口数を159.04億人と算出。理想可容人口数を76.89億人と算出した。
フィッシャーは、政治区画を単位とした可容人口は60億人と算出。
ホルスタインは、世界を40近くの農業区域に分け、土地評価と人間の要求熱量などを考慮に入れた可養日数を算出し、そこから132.9500億人と想定した。
※参考2 「人口増加による窮乏化のメカニズム」
http://phrik.misc.hit-u.ac.jp/Asami/Jugyo/2005/socdev/week2/malthus1.html
■トマス・ロバート・マルサス Thomas Robert Malthus 「人口論」~概略 その3
CiNii - 上武大学経営情報学部 佐藤 宏さんという方が書いたもの
http://ci.nii.ac.jp/naid/110007150648/
(以下、引用転載)
【マクロ経済学におけるマルサスの位置づけ】
1939年、「雇用・利子および貨幣の一般理論」をケインズが著したことでマクロ経済学は誕生した。
そのケインズは、マルサスを自らの先駆者として位置づけた。
しかし、マルサスをしてケインズ学派の先行者と見なすかどうかは、未だ決着をみた議論となっていない。
マルサスからケインズへの流れを探求しようとする時、多くの場合、
「古典派」経済学大系とケインズ経済学大系のように二分し、マルサスがどちらの領域に属するかという議論となっている為である。
例えば、貯蓄と投資の認識の相違、或いは、「有効需要論」の相違例が挙げられる。
本稿はこれに疑問を持つ。何故なら、ケインズが最も大きな関心を持ったのは失業問題であった。
従って、マルサスとケインズの理論的親近性を論じる際、「失業」を両者がどのように見ていたかを論じる必要があるだろう。
本稿の狙いは、マルサスとケインズの「失業」への認識を整理し、「不完全雇用状態」の発生プロセスを明らかにすることにある。
そして、不完全雇用均衡論理から有効需要原理への展開とした時、マルサスをケインズの先行者として考える道筋を提起することにある。
本文は下記※pdf
http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0009101604
■トマス・ロバート・マルサス Thomas Robert Malthus 「人口論」~概略 その4
マルサスの「人口論」の概略は、一橋大学教授・斉藤 修さんと言う方が下記のサイトに詳しく書かれているので、参考に。
長くなりますので、ここでは転載を省かせていただきます。
第1章.人類史の見方示す - 「人口と経済」から人類の歴史をみる
http://blog.goo.ne.jp/chorinkai/e/64e31dd0ace179ea7a2796fa5b01b6c2
第2章.原理による批判 - 「人口の原理」を知らない進歩主義を批判する
http://blog.goo.ne.jp/chorinkai/e/dcceb2a4ed5e1fd384467ebe60302685
第3章.2つの制限 - 経済は人口とのレースに勝てない
http://blog.goo.ne.jp/chorinkai/e/1bcfa315cbe6d60751afefc20fd7d126
第4章.歴史的な意味 - 第二次世界大戦後、明示的にマルサス的な歴史解釈が登場する
http://blog.goo.ne.jp/chorinkai/e/467db6a167930d6ce50bd9de955c7727
第5章.政策的な意味 - 労働市場に不必要な介入をする救貧法は廃止すべき
http://blog.goo.ne.jp/chorinkai/e/bce6ffaad180ae7f8a904cc387e19a17
第6章.実証へ姿勢の変化 - 新たな資料と観察事実を求めての探索の旅に出る
http://blog.goo.ne.jp/chorinkai/e/1385b602a18a44b001f5fa07fe8afd82
第7章.兎と亀 - 人口を「兎」に、生活物資の採算を「亀」に見立てる
http://blog.goo.ne.jp/chorinkai/e/fc4404619afe1ea9568313141b16e9e5
第8章.21世紀へのヒント - 成長する経済と縮小する生態環境とのギャップ拡大をマルサス的に憂える
http://blog.goo.ne.jp/chorinkai/e/c93d8ba442ae33250c8d6267d17488f7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(第5章から以下、引用転載)
16世紀以来、英国には救貧法と呼ばれる公的な貧困者救済制度があった。
とくにマルサスの時代(18世紀後半-19世紀前半)には、
寡婦や障害者らに加え、働く能力を持った労働者に一種の失業手当を支払うといういう仕組みが広まっていたのである。
マルサスは、人口原理による理想主義批判の応用問題として、この制度を攻撃する。
救貧がいかに善意に基づく制度であっても、その結果は意図とは違ってしまう。
失業者に手当てを支給するのは、一時的に積極的な人口制限(貧困など)を解除させるので、結果は労働者階級の人口を増加させるだけだ。
人口が増えれば、失業者はさらに増え、賃金は上がらず、労働者自身にとって良くない状況を招くだけである。
しかも、家族を養うだけの稼ぎがないにもかかわらず結婚する者を増やすことから、労働者の独立心を弱め、予防的な制限(主に結婚の延期や非婚)の作動を鈍らせる。
結局、救貧法は貧困者を増やすだけである。
それゆえ、労働市場に不必要な介入をする救貧法は廃止すべきである。これが彼の批判であった。
このマルサスの処方箋は経済学者だけではなく、政策担当者にも甚大な影響を与えた。
その結果、救貧法は1834年に大改正され、支援が大幅に制限された。「人口論」は、自由主義的な経済政策思潮の支柱となったのである。
このような論法は、現代の労働市場改革論議を想起させる。
同時に、その論拠が、労働者家族への手当てが人口増加を促したというところにあったことも、少子化が進んでいる日本ではとくに興味を引く。
ただ、この種の家族補助は、出生率を引き上げるのに本当に有効だったのであろうか?
現代の英国経済史家は様々な資料からその検証に取り組んでいるが、明確な結論は得られていない。
手当て支給の死亡率低減効果ないしは出生率上昇効果はゼロだったのかもしれない。
仮に多少の効果はあったにしても、極めて弱いか、或いは相当に長いタイムラグがあった為に、他の要因の影響に掻き消されてしまったとも考えられる。
いずれにしても、救貧法の人口増加効果は確認出来ていないのである。
マルサスの同時代人には強い説得力をもった演繹(えんえき)論法であったが、実証的な根拠は意外に不確かだったといえよう。
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
■優生学について
優生学
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%84%AA%E7%94%9F%E5%AD%A6
(以下、Wikipediaより一部抜粋)
①積極的優生学・・・・子孫を残すに相応しいと見なされた者がより子孫を残すように奨励する。
②消極的優生学・・・・子孫を残すに最相応しくないと見なされた者が子孫を残すことを防ぐ。
プラトン「国家」より、
「最も優れた男性は、意図して最も優れた女を妻に娶ったに違いない。そしてその反対に、最も劣った男性についても同じことが言える」
フランシス・ゴルトン「遺伝的天才」より、
「多くの人間社会は経済的に恵まれない人々と弱者を保護に努めてきた。それ故にそれらの社会は、弱者をこの世から廃絶するはずの自然選択と齟齬を来してきた」
「人間は動物に対して様々な形質を際立たせる為に人為選択の手段を用いることが可能であり、そのようなモデルを人間に対して応用するなら、
同様の結果を期待することが出来る」
「私は本書に於いて、人間の本性の持つ才能はあらゆる有機体世界の形質と身体的特徴がそうであるのと全く同じ制約を受けて、
遺伝によって齎されることを示したいと考える。
従って斯様な様々な制約にも拘らず、注意深い選択交配により、速く走ったり何か他の特別の才能を持つ犬や馬を永続的に繁殖させることが、
現実には簡単に行われている。従って、数世代に亘って賢明な結婚を重ねることで、人類についても高い才能を作り出しうることは疑いない」
ゴルトンは、社会は既に知的に劣った者の出生率が知性に優れた者に勝る状態(即ちダーウィンの用語で言うところの「カタストロフィー」の状態)にあるとして、
逆淘汰(Dysgenics)の状況に進んでいると主張した。
ゴルトン自身は如何なる形での選別方法をも提示することはなかったが、もし人々が子孫を残すことの重大性を認識することで社会的規範が多少なりとも変わるならば、
いつの日にか解決方法が見つかるであろうことを願った。
優生法は、ほとんど全ての非カトリックの西ヨーロッパ諸国によっても採用された。
1933年、ドイツにおいて、遺伝的かつ矯正不能のアルコール依存症患者、性犯罪者、精神障害者、
そして子孫に遺伝する治療不能の疾病に苦しむ患者に対する強制断種を可能とする法律が立法化された。
スウェーデン政府は40年の間に優生計画の一環として6万2千人の「不適格者」に対する強制断種を実行している。
スティーヴン・ジェイ・グールドなど様々な著述家達が、米国において1920年代に成立し、1960年大幅な改正を受けた移民制限が、
自然の遺伝子プールから「劣った」人種を排除することを意図した優生学的目標によって動機付けられたものであったと主張している。
20世紀初頭、米国とカナダは、南欧と東欧から膨大な量の移民を受け入れるようになった。
ロスロップ・スタッダードやヘンリー・ラフリンの様な影響力を持った優生学者たちは、
もしこの先移民が制限されないとするならば、国の遺伝子プールを汚染することになる劣等人種が国中に満ち溢れることになるとする議論を立ち上げた。
これらの議論によってカナダと米国は、民族間の序列化を行う様々な法の立法化へと向かうことになった。
これらの法律では、
最も上位にアングロ・サクソンとスカンジナビア人が位置付けられ、下に向かって事実上移民から完全に閉め出された日本人と中国人に至る格付けが行われた。
しかし、フランツ・サムエルソン、マーク・シュナイダーマン、リチャード・ヘアンスタインらは、
移民政策に関する議事録を詳細に調査した結果、連邦議会は実際にはそれらの要素を考慮に値するものとは見做していなかった事実を明らかにした。
一般的に優生学の概念に同意しない立場においても、優生学的立法は、依然として公益性を有すると主張している人々が存在した。
当時、優生学は科学的かつ進歩的であり、人間の生命の領域に、産児に関して自然な知見を応用するものであると多くの人々から理解されていた。
第二次世界大戦の強制絶滅収容所以前、優生学がジェノサイドに繋がる恐れがあるとする考え方は真剣には受け取られなかった。
それらのネガティヴな優生学とは区別して、シンガポールは限定的な「ポジティヴな優生学」を実施した。
シンガポール政府はあらゆる人種の平等を明確にし、明らかに他国とは全く違った優生学的見解を表明した。これは多くの左翼知識人から絶賛を受けた。
【優生学的思想の各国・各政権による採用様態】
ドイツ(ナチス政権)・・・・
20世紀、優生学の信奉者で著名な人物はアドルフ・ヒトラーだった。
彼は「ドイツ民族、即ちアーリア系を世界で最優秀な民族にする為」に、「支障となるユダヤ人」の絶滅を企てた(民族浄化)以外に、
長身・金髪碧眼の結婚適齢期の男女を集め、強制的に結婚させ、「ドイツ民族の品種改良」を試みた。
インド・・・・
ヒンドゥー至上主義政党の中で最も過激として知られるシヴ・セーナーが、
カースト制度最上位階層の多くを占めると言われるアーリア系について優生学的擁護を訴える政策をしばしば提言し、じわじわと支持を広げている。
米国・・・・
ドイツと共に、優生学思想を積極的に推し進めた国はアメリカである。
優生学に基づく非人道的な政策を採っていた、と来れば、一番に想起されるのはやはりナチスだが、実は、アメリカの方が優生学的な政策を実施していた期間は長い。
また、そのような政策を始めたのも、アメリカの方が早い。優生政策の老舗は、アメリカだと理解した方が事実に沿っているのである。
しかし、ナチスのようないわゆる「積極的駆逐」(=組織的殺害)は全くおこなっていない。
断種法は全米30州で制定され、計12000件の断種手術が行われた。
また絶対移民制限法(1924年)は、「劣等人種の移民が増大することによるアメリカ社会の血の劣等化を防ぐ」ことを目的として制定された。
この人種差別思想をもつ法は、公民権運動が盛んになった1965年になってやっと改正された。
日本・・・・
日本への優生学の影響は、1905年頃には既に現れた。例えば雑誌『人性』(1905-1918)に欧米優生学(民族衛生学)の紹介が見られる。
また1910年代には、海野幸徳「日本人種改造論」(1910)、澤田順次郎「民種改善 模範夫婦」(1911)、氏原佐蔵「民族衛生学」(1914)が書かれた。
1919年には、市川源三を中心に大日本優生会も結成された。
尚、この間、1916年に保健衛生調査会が内務省に設置され、ハンセン病者への隔離を実施し、断種政策とも関連が深いらい予防法の制定へ向けて、
政府関係者自らが「民族浄化」を叫ぶなどした。
1924年には、後藤龍吉を主幹として雑誌「ユーゼニクツス」(のち「優生学」)が刊行された。
また池田林儀は、1920年~1924年にドイツ国でワンダーフォーゲルや民族優生学に影響され、1926年日本優生運動協会を設立、雑誌『優生運動』も創刊した。
1930年には、永井 潜を中心に日本民族衛生学会が結成された。これまでにない大規模な優生学者の団体である。
「民族衛生」を刊行し、形態を変えつつも現在に至っている。
この団体は、通俗講演会も積極的に行った他、優生結婚相談所の開設や映画「結婚十字街」の製作など注目すべき事業も行っている。またアイヌの調査も有名である。
1938年(昭和13年)、戦争に対応するため厚生省が作られ、予防局優生課が「民族優生とは何か」など優生政策を進めた。
1940年(昭和15年)、“中絶条項”は国会の反対で大幅に修正されたものの、遺伝性精神病などの断種手術などを定めた国民優生法が公布された。
しかし、厚生省の意図とは異なり、当時の「産めよ増やせよ」の国策に加えて、天皇を中心とする家族的な国家観が“強制断種”と馴染まなかったなどの理由から、
優生的な政策は必ずしも実効を結ばなかったとされる。
日本において優生学的なイデオロギーが政策的に色濃く反映され、実効されたのはむしろ戦後の優生保護法の施行の後である。
優生保護法(1948年)は、優生学的見地からの強制断種が強化されたことも特筆される。
元日本医師会会長でもある谷口弥三郎参議院議員を中心とした超党派による議員立法で提案された同法は、
当時必須とされた人口抑制による民族の逆淘汰を回避することを提案理由として、子孫を残すことが不適切とされる者に対する強制性を増加させたものとなった。
同法は、ハンセン病を新たに断種対象とした他、1952年の改正の際に新たに遺伝性疾患以外に精神病、精神薄弱も断種対象とした。
これを消滅させるべく1997年に法改正がなされ、名称も母体保護法と変更された。
|
|
|
|
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
|
|
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。
|
|
|
|
|
|
|
|