http://www.asyura2.com/10/hasan70/msg/732.html
| Tweet |
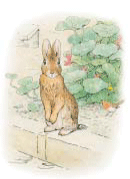
株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu232.html
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
--------------------------------------------------------------------------------
日本人は転勤というのは当たり前だと思っているだろうが、外資ではトップ
クラスの幹部を海外法人に派遣するような戦略的な人事にしか見られない
2011年1月22日
◆無気力は終身雇用に対する最大のテロリズムである 2010年12月24日 大石哲之
http://www.tyk2.info/2010/12/blog-post_497.html
横須賀の市役所で異動を拒否して前の職場に居座り、出勤後は本を読んで一日をすごしていた職員(40)が停職一ヶ月をくらったようだ。仕事は一切していないが、給与やボーナスはちゃんと支払われる。
市によると、主任は4月1日付で発令された港湾部への異動に従わず、2年近くいた市民部にそのまま毎日通った。上司や同僚らが迷惑がる中で、空いた席に陣取って職務に関する本を読んでいたという。一方、港湾部では主任の異動拒否の影響で職員が1人少ないままになっている。
無気力は終身雇用に対する最大のテロリズムである。
終身雇用というのは、解雇規制もあいまって、絶対にクビにしないかわりに、会社のいうことはなんでもきくという一種の血の契約である。
異動、配置転換は拒否できない、単身赴任だって、地方転勤だって、10年間のタジキスタンの工場暮らしだって、定年までマニラで過ごせといわれてもNoとはいわない。人が足りないときにはサービス残業もいとわず、社畜となって、すべてを会社に捧げるのが暗黙のルールだ。そのかわり、会社側は株主利益よりも雇用を優先し、どんなことがあっても定年まで賃金を払い続けるというのが裏の約束だ。
要するに、手足が吹っ飛んだりしても一生恩給をだすし、戦死したら家族の面倒は軍が見るから、国家に忠誠を誓ってほしい、そういう約束に近い。
これには、前にもいったように、若いうちに貢献度よりも低賃金で会社に貯金をし、50代以降に出世とポストを以て報いるというものがセットであった。
しかしながら、昨今では40代で賃金が頭打ちになる。ポストも用意されない。若いうち働いて会社に貢献しても報われる保証はないのだ。
この主任の場合、ちょうどその40歳であり、移動先が港湾部というからには、おそらく左遷人事である。将来が見込めず、ポストも用意されないことがわかった主任がとった行動が、無気力という最大のテロリズムだ。
終身雇用+解雇規制の世界では、将来の出世の見込みがない人にとって最も合理的な行動は、一切働かないことだ。それでもクビにできないのだから、働かなければ働かないほど、ROIは上昇する。
将来にわたって賃金が上昇することがないなら、労働投入量を減らすことによって労働/賃金のROIを上昇させることができる。これが無気力労働のからくりだ。
サービス残業を拒否し、自分のパフォーマンスが悪くても「スキル向上の機会がなかった」といって開き直る。究極は、この主任のように、空いた席に陣取って職務に関する本を一日中読むことだろう。今後は、このような行動をするひとはめずらしくなくなるだろう。あと10年もゼロ成長がつづけば、会社内のサボタージュや、無気力によるテロが普通になるのは時間の問題だ。
これに対抗するには会社が解雇できるようにする以外にない。そのかわり、適正な賃金を適正なタイミングでキャッシュで払う。つまり、若いうちの賃金を適正な水準まで上昇させ、サービス残業は廃止し、他部門への異動や地方転勤は当然拒否できる。異動による社内ローテーションで出世するのではなく、専門能力によってキャリアを積み上げそれに応じて処遇する制度に変わっていかざるを得ない。
その変化の臨界点がいつになるのかは分からないが、職場の1割がこのような無気力テロの状態になった時点で変わると思う。
無気力で革命をおこすという、なんとも笑えることが起きようとしている。
◆日本の会社はなぜ転勤が多いのか 2011年1月15日 池田信夫
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51665871.html
きのう「たかじんのそこまで言って委員会」という東京では見られない番組で話題になったことだが、放送に出るかどうかわからないので、ちょっとメモしておこう。
日本の政治報道が「政局報道」でしかないのは丸山眞男以来、指摘されていることだ。その一つの原因は政治が政策で動いていないからだが、もう一つは記者が政策を理解していないからだ。記者クラブのローテーションは半年単位で、1〜2年でクラブを転々とし、5年ぐらいたったら地方に転勤する。40歳すぎると管理職になるので、取材しているのはほとんど政治に素人の30代のサラリーマンなのだ。
これはマスコミだけではなく、日本のほとんどの会社と同じだ。日本人は転勤というのは当たり前だと思っているだろうが、外資ではトップクラスの幹部を海外法人に派遣するような戦略的な人事にしか見られない。IBMは例外的に転勤があり、社名は"I've Been Moved"の略だという冗談もあった。その原因は、一時期までのIBMは社員を解雇したことがなかったためだ。長期雇用と転勤は補完性があるのだ。
その第1の理由は、業務がなくなっても解雇できないため転勤で対応しなければならないこと、第2は処遇を平等化することだが、第3の理由は社内の人間関係を定期的にリセットすることだ。サラリーマンなら誰でも経験すると思うが、いい上司にめぐりあうことは少ない。たいていは1年ぐらいすると上司の顔を見るのものいやになるが、「こいつと付き合うのもあと数年だ」と思うから我慢する。転勤は、長期雇用によるストレスの安全弁になっているのだ。
記者の場合には、取材先との癒着も問題だ。特に政治部や経済部の記者は毎晩のように高級料亭で接待を受け、かなりきわどい付き合いをする。このため一つの派閥にずっとついていると、読売の某主筆やNHKの島元会長のように派閥の構成員になってしまうので、定期的に持ち場を変えるのだ。だから深い取材ができず、政策について勉強もしていないので、政治家の噂話を記事にするしかない。
このように長期雇用の都合で専門知識を犠牲にする人事システムが、日本企業をだめにした大きな原因だ。IBMも80年代に倒産の一歩手前まで追い込まれて終身雇用をやめ、ピーク時に40万人いた社員を転勤ではなく解雇して、20万人まで減らした。おそらくそれぐらい強烈なインパクトがないと、日本の会社も変われないだろう。
(私のコメント)
最近の新人社員はアジアやアフリカといった海外勤務を嫌がる人が増えてきたというニュースを良く見ますが、その反面では長期雇用を望んでいる。長期雇用体制ならば転勤は避けることが出来ず、地方勤務や海外勤務を避けることが出来ない。長期雇用年功序列体制は日本企業の強みでもあったのでしょうが、経済状況が変われば弱みにもなりうる。
大石氏のブログで紹介されている記事も、横須賀市で転勤を拒否した職員の記事ですが、市役所も長期雇用体制だから転勤は避けることが出来ない。アメリカでもIBMのように長期雇用の時は転勤で人員体制を整えてきましたが、現在の職場で骨を埋めたいと思っていても、会社は転勤で望まない部署に配置をされてしまう。欠員が出れば転勤で穴を埋めなければならないからだ。
最近ではテレビでも新卒の求職難がニュースになっていますが、若い人は大企業志向で長期雇用の安定した企業を求めている。しかし海外勤務を嫌がる傾向も出ていて、10年間のアフリカ勤務や終身東南アジア勤務を命じられても文句は言わない覚悟があるのだろうか? 最近の日本企業は国内市場の行き詰まりで海外に市場を広げる企業が多くなってきている。
メーカーや商社ばかりでなく、流通や小売といった国内企業でも中国進出など盛んだ。だから順応性の高い新人社員は真っ先に海外勤務を命ぜられる可能性が高い。場合によっては英語力が堪能だと終身海外支店に回されるかもしれない。終身雇用体制ならばそうしなければ人員配置がままならなくなるからだ。それを覚悟で新卒の就職希望者は一流大企業を望んでいるのだろうか?
最近では海外勤務を命じても二人に一人が拒否をするといいます。これでは海外支店に欠員が生じても転勤もさせられず、東京の本社には転勤を拒否した社員だらけになってしまう。これでは長期雇用は成り立たなくなり、韓国などのハングリーでガッツのある企業に新興国市場で負けてしまう。一流大企業ほど海外で活躍が出来るような有能でやる気のある社員の需要が高まっていますが、長期雇用体制は会社の命令ならどんなことでも従う社員が前提だった。
これからは海外ばかりでなく国内でも転勤を拒否する社員が増えてくるようになり、特に女子社員は転勤を命ずることが不可能に近くなっている。最近では「転勤の無い総合職」も女子社員用に作ったところもあります。日本企業は解雇規制と転勤拒否の増加に頭を悩まし、無理に転勤させれば仕事への士気も低下して、海外の市場でも韓国企業に破れるケースも増えてきている。
長期雇用制度から能力給制度にして、人材の中途採用でも不利にならないような制度にしていかないと、転勤拒否の問題が大きくなって、社内の膿が溜まってきて、仕事をしない、終身雇用にあぐらをかいたような無能社員だらけになって会社も傾いていくのだろう。会社に欠員が出来たら現場の部門で採用して移動させなくても人員を維持できる体制に切り替えないと成り立たなくなるのではないだろうか?
株式日記でも同一労働同一賃金にしないと、中途採用もままならなくなると書いてきましたが、社会状況が終身雇用と年功序列ではグローバル競争に勝てなくなってきている。終身雇用年功序列にも長所はあるが、転勤を嫌がるような社員が増えてくると社内に膿が溜まり、人間関係も逃げ場が無くなり最悪の環境になってしまう。
池田氏が書いているように日本企業に転勤が多いのは長期雇用のなせる業であり、会社に絶対的な忠誠心がある社員があって始めて成り立つ。しかし最近では海外勤務を二人に一人は拒否するようになり、転勤もままならなくなれば人事も停滞してしまう。ならば能力給に切り替えて解雇をしやすくして、同一労働同一賃金で中途採用で人事の穴を埋めていくようにしなければ組織が成り立たなくなる。
私自身も銀行員を14年ほど経験したが、支店を三度変わり、支店内でも毎年のように担当が変わった。何でこんなに転勤や移動が多いのだろうと思いましたが、事情は大石氏や池田氏が書いているような長期雇用によるものだろう。しかし社員が終身雇用と解雇規制に安住して仕事をしなくなり転勤も拒否では、日本経済の停滞の原因は、社員の長期雇用による無駄遣いにあるのではないだろうか?
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
- Re: 引用記事の内容もコメントも一読の価値があるが、現実を知らないボンクラの(私のコメント)にはウンザリだね metola 2011/1/22 17:24:40
(0)
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。