| Tweet |
(回答先: 『売国者たちの末路』紹介に深謝します(植草一秀の『知られざる真実』) 投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 8 月 31 日 11:15:02)
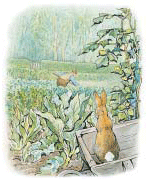
森田実のホームページより
http://www.pluto.dti.ne.jp/~mor97512/
渡邉良明●現代日本政治論 より
http://www.pluto.dti.ne.jp/~mor97512/
http://www.pluto.dti.ne.jp/~mor97512/WA2-63.HTML
2009.6.15
植草一秀著『知られざる真実―勾留地にて―』を読んで
――植草氏の一日も早い名誉回復を祈りたい
--------------------------------------------------------------------------------
◆はじめに――植草氏は「無実」である/あの事件は謀略だ
腐敗した自公政権が日本政治を牛耳るいまの邪悪な世の中では、心ある正義の士は葬り去られる。たとえば、彼らは、自殺を装った他殺や犯してもいない罪をでっち上げられて、社会的に抹殺される。日本の検察や裁判所、それに警察が「正義」だなどというのは、まさに“幻想”でしかない。むしろ彼らは、単に政府(=政権担当者)の走狗にすぎない。
無論、なかには真実・無私の検察官や裁判官、それに警察官もいよう。だが、これらの心ある方々は、自らの心に矛盾や憤懣を感じながら、日々勤務しているのではあるまいか。組織特有の自らに甘い“内向き”の体質が、これらの人々の良心や正義感を時に萎えさせ、時に麻痺させる。
なぜなら、組織で働く人々は、妻子や家庭生活を人質にとられている弱い存在でしかないからだ。それゆえ、いきおい彼らは、自ら感じる怒りや正義感を封印し、日頃、無理難題を負わせる上司の命令に服することになる。ひたすら無念の涙を流しながら、じっと家族のために耐えている人々が、わが国には一体どれほどいるのだろうか。私は、いまの日本にはこのような人々の怒りや憤懣が充満していると感じるのだ。
しかし、このような時の政権の不正や腐敗を座視できず、自ら信じる持論を堂々と展開する勇気ある人もいる。だが、それをなしたがゆえに時の政権担当者たちから憎まれ、罠にはめられた識者も決して少なくはない。植草一秀氏がその代表的な人物だと思う。
植草氏は世に言う「手鏡事件」で不当に逮捕された。そして、2回目など東京拘置所に132日間も勾留された。だが、さまざまな情報を渉猟し精査すれば、誰でもそれらが明らかな“冤罪”、つまり“でっち上げ”だったことがわかる。
では、どのような人々がそんな酷いことを仕組んだのか? それは誰よりも植草氏が名誉を剥奪され、社会的に葬られて、最も喜ぶ人であろう。人に「理性」というものがあるならば、あの事件が謀略だったと確信することだろう。
植草氏は、「天地神明に誓って、このような罪は犯していません」と言明された。私はこの言葉を100%信じる者である。この思いは、私が言うまでもなく、すでに数多くの心あるブロガー(ブログ主宰者)や知識人たちが表明している。
ところで、植草氏は、ご自分のブログ[知られざる真実]の〈財界による「日本郵政私物化」を拒む改革が必要〉(5月21日)と題する論考の冒頭で次のように記している――《政権交代を実現する意義は、日本の政治をこれまでの、「資本の論理」、「官僚の論理」、「中央の論理」に基づく姿から、「生活者の論理」、「国民の論理」、「地域の論理」に基づく姿に転換することである》と。
実に明快だ。まさにそのとおりだと思う。今日、野党勢力はこの視点で選挙運動を展開している。だが、この植草氏の言葉は何度強調されてもされ過ぎることはない。
たしかに、今日の自公政権は「資本」「官僚」、そして「中央」の論理なのだ。とりわけ財務官僚を主にした“霞が関”が自らの保身や職場の権力拡大のために政府の要所を押さえている。だが、この「昔軍人、今官僚」の悪弊を打破し、彼ら(=官僚)の力を国民のために活用することこそが、民主党主体の新政府には何より求められると思うのだ。
◆竹中平蔵氏の“欺瞞”を最もよく知る植草氏
最近、植草氏の著書『知られざる真実―勾留地にて―』(イプシロン出版企画)を読んだ。これは後世に残る名著だと思う。実に内容の濃い気高い“魂の書”である。
同氏のブログのなかには同書を説明してこう書かれている。「小泉竹中経済政策の深い闇を抉る戦慄の告発書」「満身創痍にひるまず、権力に立ち向かう著者が小泉竹中経済政策を一刀両断に斬る救国の告発書」と。「満身創痍」という言葉は決して大袈裟ではない。
小泉・竹中経済政策がいかに売国的で国民を裏切るものであったかは、年々歳々、明白なものとなっている。「郵政民営化」がその典型だ。無論、植草氏をはじめ心ある識者には、小泉政権が邪悪な従米主義を本質としたものであることは自明のことだった。加えて、同政権がどれほど財務省の言いなりであったかということも周知のことだった。その小泉政権の売国的体質を最も深く認識していたのが、実は植草氏だったように思うのだ。
竹中氏にとって植草氏はちょうど10歳下の経済学者だ。竹中氏は、同業の植草氏に異常なほどの羨望と脅威を感じたことだろう。そのことは容易に想像できる。というのは、植草氏の客観的な経済分析能力は竹中氏をはるかに凌いでいると思うからである。なぜなら、竹中氏はミルトン・フリードマンの「新自由主義(=市場原理主義)」なる欺瞞的な経済理論の“単なる信奉者”に過ぎなかったからだ。簡単に言えば、竹中氏の経済理論なるものは単なる“屁理屈の受け売り”に過ぎないと思う。
私は竹中氏を学者だとは思わない。本来、学者は「真理」に対して謙遜、かつ公平でなければならない。また、自らの持論を「多の中の一」と考えるだけの客観性がなければならない。だが、彼は微塵もそのような謙遜さや客観性を持ち合わせていないと感じる。
いまでも竹中氏は性懲りもなくテレビ朝日系の番組に出演している。だが彼は、人と議論しても、同じ土俵で論じ合うというよりもむしろ自分で勝手に土俵をつくってしまい、そこで自ら覚えた(?)議論をまくし立てているように感じる。換言すれば、彼は学者というよりもむしろ欺瞞的で偏狭な宗教家(=原理主義者)に近いように思うのだ。だが何より問題なのは、彼がアメリカ大資本の悪辣な“手先”の一人だということだ。 これに対して、ジョン・M・ケインズを敬愛する植草一秀氏は、日本国内の現実を直視した正当な経済理論を展開する。その卓越した経済分析はまさに超一流である。2004年4月、彼が不当に逮捕される前、テレビ番組『ウェークアップ』などでのコメンテーターとしての活躍は目を見張るものがあった。植草氏には、単に優れた分析能力だけでなく、むしろ人一倍の正義感とヒューマニズムが感じられた。それゆえに魅力的だったのだ。
私は、植草氏と竹中氏は「月とスッポン」「提灯と釣鐘」だと思う。「太陽」と「月」ぐらいの違いさえあろう。端的に言えば、“ホンモノ”と“ニセモノ”の違いがある。竹中氏が“ニセモノ”であるゆえに、同じ“ニセモノの政治指導者”小泉純一郎氏に重用されたのだと思う。私は、両者は同じ“ニセモノ”であるゆえに“波長が合った”のだと感じる。
竹中氏の欺瞞を最もよく知っているのが植草氏ではあるまいか。それゆえ彼は、虐げられた日本国民を覚醒するために、本著を書かずにはいられなかったと思うのだ。
◆本書は、絶望の淵から生還した植草氏の清冽な“魂の書”
読書には大まかに言って速読と精読の二つがある。若い頃の私は精読派だった。昔は一頁の一行目から丹念に読み始めたものだ。大学時代(ほぼ40年前)、杉浦明平氏(作家、評論家、1913〜2001)の晴耕雨読の合間に「1日に4、5冊読んでいます」という文章を読んだことがある。内心、“嘘だろう”と思った。だが近年、同氏と同じ立場になってみて、1日、4〜5冊の読書が可能だと感じる。
書物には必ずキーワードや要点、要約が潜んでいる。それらを自分なりに見出し、著者の心や執筆意図に共感できれば、文章をまるで一幅の絵のように読み進むことができる。ただ、文章や言葉自体の“情感”を重んじる文学の場合はそうはいかないかもしれない。
だが、若い頃から読み慣れている論説文や社会科学系の論文などはだいぶ速読できるようになった。つまり、各所の要点や要約を掴み、それを最終的に自分の頭の中で統合あるいは“再構成”できれば、筆者の執筆意図はだいたい把握できると思うのだ。
しかし、今回の植草一秀氏の著書は謹んで精読しようと思った。なぜなら、本著には単に植草氏の経済理論や経済分析だけでなく、彼が経済学を志した経緯や彼の思想や価値観、それに先年の“でっち上げ事件”の詳細が丹念に記述されているからだ。
著者が渾身の思いで書いたものを安直な気分で読み流すことはできない。この種の著書に対して、速読は何の意味もない。むしろ読む方も魂を込めて読まなければならない。それほどに本著は植草氏の魂のこもった作品なのだ。同書を日本の全国民に読んでほしいと思う。それと同時に、私自身、自ら何度でも読みたいと思う名著である。
本書はプロローグ、第一章〜第三章、エピローグ、巻末資料からなる。その各章の合間に、著者は先人とご自分が書いた和歌を付している。それは次のとおりだ。
「かくすれば かくなるものと 知りながら やむにやまれぬ 大和魂」(吉田松陰)
「世の人は 我を何とも ゆはば言へ 我がなすことは 我のみぞ知る」(坂本龍馬)
「ひと挿しの 野に咲く花の 香ぐはしき かをりがわれに いのち与へり」(植草一秀)
私自身、何冊かの本を書き、そのなかに吉田松陰の上記の和歌をとり上げたことがある。それゆえ、植草氏の思いがよく理解できる。同氏は、政治的謀略による不当な逮捕・勾留を通じて絶望の淵に落された。まさに“地獄を見た”とも言えよう。あの聡明・明晰な植草氏が、その耐え難い絶望の淵で自殺さえも試みた。よほどのことがあったのだろう。
しかし、家族、親族、恩師、同級生たちが彼の無実を信じた。また、彼を支援する人も多く出た。彼らの愛と支援を一輪の花に託して詠んだ「かをりがわれに いのち与へり」のなかに植草氏の万感の思いがある。本書は、絶望の淵から生還した同氏の“魂の書”だ。
第一章のタイトルは「偽装」とある。これは、姉歯秀次建築士による耐震構造偽装事件だけでなく、小泉構造改革自体が国民を欺き、日本の国富をアメリカの金融資本に売り渡す国家的規模の詐欺(=偽装)だったと論じる。
第二章のタイトルは、「炎」である。ここで彼の青春時代のエピソードが披瀝される。
第三章は「不撓不屈」である。地獄のなかで“光”を見た彼が、雄々しく“身の潔白”を訴える。各章が植草氏の“涙の結晶”だと思うのだ。
◆今日の日本の偽りのない姿
私事だが、1993年から2年間、私は、ハワイ大学のスパーク・マツナガ平和研究所で客員研究員として過ごした。帰国後、時折、妻と語り合った。妻が言う。「なんだか日本が急に悪くなった感じね。昔(出国前)の日本はこんなにひどくはなかったわ」と。私も「同感!」と答えずにはいられなかった。 何も昭和30年代にまで遡らなくても、かつての日本人はもっと情に厚く健康的だったように思う。それに何より、はるかに“精神的”だったような気がする。だが、最近はひどく物質的かつ拝金主義で、何だかギスギスした感じだ。
“日本は貧しくなった”と言われる。だがそれは単に経済的な意味だけでなく、はるかに精神的に貧しくなったように感じる。つまり、すべてが劣化したというか、劣悪になった感じだ。より端的に言えば、日本人もずいぶんと“悪辣”になったように思うのだ。たしかに、ホノルルやシアトルでの生活において妻と私は多くのカルチャーショックを体験した。だが帰国後の日本では時系列的というか、時間的な意味でのショックを味わった。
ところで、私は先ほど「悪辣」という言葉を挙げた。私が30年以上も愛用している岩波の『国語辞典(第三版)』には、「自分の目的を達するためには、どんなひどい事でも平気でするというように、たちが悪い仕方・性質であるさま」とある。言い得て妙である。ほかに、「わるくてすごいこと。非常にたちのわるいこと」と書かれた『広辞苑』よりははるかに具体的で説得力がある。
実は、植草氏の本著を読んだ後、彼を拘束した神奈川県警鉄道警察隊の巡査部長や取調べにあたった刑事ならびに検察庁の検事たちの言行を読んで感じた思いが、この「悪辣」という言葉だった。“よくもまあ、こんな悪行ができるものだ”と心底、怒りを覚えた。
ちなみに、「6月4日午後7時50分ごろ、岡山市の路上で、買物に行こうと歩いていた同市の無職女性(75)に近づき、追い越しざまに胸に抱えた現金1万円入りの財布をひったくる」事件が起こった(熊本日日新聞、6月5日付夕刊)。ところが、この犯人というのが実は愛媛県の盗犯係の刑事だった。その犯人を取り押さえたお手柄の高校生(2人)の一人が犯人が本来「捕まえる人(=刑事)」だったことを聞いてもらした言葉が、「世も末だと思います」だった。まさにそのとおりだ。
最近、私は庭仕事で祖父母が生前使っていた大きな甕(かめ)を移動する作業をした。すると、動かした甕の底には蟻、ダンゴ虫、ワラジムシ、ムカデなどの虫たちがウヨウヨしていて思わずギョッとした。だがそのとき、警察も検察庁も裁判所も、実はこんな状態ではないかと思った。それゆえに鳩山民主党代表が言う“大掃除”が必要なのだ。
植草氏はよく「悪徳ペンタゴン」という言葉を使う。植草氏のいうペンタゴン(五角形)とは、政治屋(政)、特権官僚(官)、大資本(業)、米国(外)、御用メディア(電)であり、国民を誘導して政権交代を阻止し、既得権益=悪徳権益の甘い蜜を独占しつづけようと企てている悪の軍団のことである。彼らによって、植草氏は貶められた。だが現在、植草氏や彼を支援する心ある愛国者たちが彼らに果敢に挑戦している。これが今日の日本の偽りのない姿だと思うのだ。
◆“直感と経験則”で確信する植草氏の無実
私は植草氏の貴著を3日間かけてじっくりと読んだ。読了後、“心の涙”を禁じ得なかった。かつてフリードリッヒ・ニーチェは「書物は汝の血をもって書け」と語った。若い頃、私はこの言葉の意味がまったく理解できなかった。長じて感じるのは、ニーチェは“書物は汝の命を賭けて書け”と言いたかったのではないかと思うのだ。
植草氏は2年前、名実ともに“命を賭けて”本著を物したと思う。彼が“命を賭けて”書いた著書ゆえに、読む者は心から感動するのだと思うのだ。本著は今後、“ロングセラー”として、きっと日本国民に愛読され、読者に多大の好影響をもたらすことだろう。
それに何より、植草氏は当時、本著を“書かずにはいられなかった”のだと思う。“何か”が彼を動かしたと感じる。私は、その“何か”とは、日本の「神」ではないかと思うのだ。
読了後感じたことは、植草氏がいたって正直かつ誠実な人だということだ。それに彼は天才的な記憶力の持主だと思う。その記憶力の素晴らしさは並外れている。私は日本の知識人のなかでも彼ほど聡明な人を知らない。だが、卓越した分析能力以上に、彼は正義感の強い有徳の士である。正直言って、植草氏はワイセツ事件を起こすような人物ではない。
なぜそう思うかといえば、それは、私の“直感と経験則”にもとづいている。私はいままで、年齢とともに、中学、高校、短大、大学、塾などで数多くの生徒や学生に教え、彼らと接してきた。その経験からして、個人の人柄や価値観・思想がどんなものかが全体的に把握できる。少なくとも、その人が“心根のよい人か悪い人か”、容易に察しがつく。
6月5日(金)の夕方、テレビ番組『Jチャンネル』を観ていると、足利事件で逮捕され17年ぶりに釈放された菅家利和氏について報じていた。スタジオで菅家氏の弁護団の佐藤博史弁護士が、キャスターの小宮悦子氏から次のように問われた。「いつ頃から(菅家さんを)無罪とお考えでしたか?」と。それに対して、佐藤弁護士がきっぱりと答えた。「いや、初め(=17年前)から犯人じゃないと思っていました」と。佐藤氏がこう言い切ったのは理屈ではなく、むしろ彼の“直感と経験則”によるものだと感じた。つまりこの“犯人じゃない”という思いは、人間の真心から発する“直感”だと思う。今日、日本人はこのような真心や良心、つまり“神の小さな声”をあまりにも軽んじていると思うのだ。
それに、いまも植草氏は奥様やお子さん、それにご両親、親族、同級生、支援者から信頼され愛されている。考えてもほしい。もし植草氏が世人に陰口される「ミラーマン」(?)なる常習の性的変質者なら、とうに家族は崩壊し、親は同氏を見離し、同級生が支援などするわけがないではないか。むしろ事実は逆である。実際、植草氏の“冤罪”を強く確信する国民が日に日に増えているのが現状だ。そしていまや、彼のブログは日本で最も信頼され人気がある。かくいう私も彼のブログの大ファンである。正直、私が毎朝起きて何をするかと言えば、まず植草氏のブログを読む。それがわが日課の始まりである。
腹蔵なく言えば、私は植草氏の復権(=名誉回復)と彼の重用こそ、民主党主体の新政権の責務だと確信する。彼ほどの真の愛国者がマスコミが流した“害毒”で国民に誤解されたままでいるのは、まさに日本国の損失であり、われら日本国民の恥とさえ思うのだ。
◆青少年期に培われた植草氏の正義感と深い思想性
植草氏は1960年(昭和35年)12月18日に江戸川区で生まれた。彼は書く。「生家にはそこそこの敷地があったが、父親は企業勤務の平均的な家庭だった。普通の家庭で普通に育てられた。父の躾は厳しかった」と。最後の「父の躾は厳しかった」の言葉に、真実と正義を重んじ何より正直と誠実を植草氏に教え込んだ父親の姿が垣間見られる。
だが、父親は決して厳しいだけでなく、休日には一秀少年を魚釣りに連れて行ったり、夏休みには幻灯機を使って近所の子どもたちを集めて怪談映画の上映をするような優しい人だった。家庭内では「家族会議」が行われ、子どもたち(姉と植草少年)や両親が意見を述べ合った。この家庭内で彼の“民主的な性格”が形成されたように思われる。
何より植草氏がご両親から受け継いだものは“正義感”だったように思う。ご両親(とくに父親)は「不正」なことが大嫌いだったのではあるまいか。「父は若いころに両親を亡くし、働きながら大学を卒業した苦労人だった。先祖を大切にして仕事ぶりは謹厳だった」との彼の言葉のなかに、私は父親の誠実な“正義感”を感じずにはいられないのだ。
ところで事件後、植草氏を支援する同級生たちのブログに[一秀くんの同級生のブログ]がある。そのなかに、本著で植草氏が引用したある女性の次のようなブログがある。
《小学校の低学年の頃、植草さんはクラスのみんなに「かずちゃん」と呼ばれていたので、ここでもそう呼ぶことにする。
全校生徒数は約千人だったが、休み時間になると大半の生徒が遊んでいた。ごちゃごちゃと入り組んで、各々好き勝手に走り回っていた。
三年生の時だったと思う。校庭で友達と鬼ごっこをしていた。前をよく見ないで走っていたためだと思うが、「ゴツン!」と頭を強くぶつけて倒れた。野球をしていた他のクラスの男の子と鉢合わせしたのだった。 起きあがる間もなく、「オマエのせいで、アウトになっただろう!」と、すごい剣幕で怒鳴られ、ぶつけた頭の痛みもあって、気の強い女の子だった私もべそをかきそうになった。
そこへ一緒に鬼ごっこをしていたかずちゃんが現れ、「お前こそあやまれ!」と助けてくれた。
かずちゃんは、決して腕っ節が強いわけではなかった。やせていて、背も低い方だった。それでも、その怒り狂っている男の子を相手に、私を守るようにして、しばらくの間、押し合いをしてくれた。
力ずくのケンカではない、彼らしく正しい理屈を言っていた。どちらにも非があるのだから、この子だけを責めるのはおかしいと。
授業開始のチャイムが鳴って、みんな遊びをやめて下駄箱へと走り、その争いもそれっきりになった。泣きそうになるのをこらえていた私は、泣き顔を見られたくなくて、そのままみんなに紛れて下駄箱へと走った。 この時のお礼をかずちゃんに言いそびれたまま、今に至っている。こんなふうに私を守ってくれた男の子は、今までの人生の中でもかずちゃん一人だった。
もしも再会することがあったら、遅ればせながらお礼が言いたい。「かずちゃん、あの時は本当にありがとう」と。》
このブログの書き手の「こんなふうに私を守ってくれた男の子は、今までの人生の中でもかずちゃん一人だった」との言葉が重い。
人には人生において“変わるものと変わらないもの”があると思う。たしかにかつての紅顔の美少年もいつかは老醜を湛えた老人になろう。だが、人間の根源的な「気質」や「人格」がそんなに簡単に変わるものだろうか? 私は“変わらない”と思うのだ。
このときの植草少年は、フェミニストというより、むしろ正義感の強いヒューマニストだったと感じる。植草氏のこの“正義感”はいまもまったく変わらない。とりわけ欺瞞的、かつ売国的な「小泉政権」の時代、彼の正義感はその正当な批判精神と同様に最も充実していたと感じる。たぶん彼の正義感は今後、彼が瞑目する瞬間まで変わらないだろう。まさに「三つ子の魂、百まで」なのである。
私は、読者の方々の心、とりわけその魂にあえて問いたい。“あなたはこのような正義感の強い潔癖な植草一秀氏が、安直に痴漢行為をするようなそんな軽薄な輩と考えられますか?”と。
むしろ安直かつ邪悪なのは、彼を拘束した当時の神奈川県警鉄道警察隊の志賀博美巡査部長と末永巡査、取り調べに当たった高輪署の松田警部補や古旗警官、それに彼らの上役たち、さらには彼らの上位にいてまさに“狙い撃ち”の形で植草氏を社会的に葬り去る謀略を企てそれを冷酷に実行した竹中氏ら当時の政府関係者たちではあるまいか。
ところで植草氏は、都立両国高校でたいへん濃密かつ充実した高校生活を過ごした。彼が最も熱心に取り組んだ科目は「倫理・社会」だった。彼は次のように記す。
《教師が熱心だった。板書の時間を節約するため、模造紙に丁寧に書かれた資料を毎回数十枚も用意した。教科書を使わず、授業はアルキシス・カレル『人間―この未知なるもの』から始まった。ヴィクトール・フランクル『夜と霧』、ロロ・メイ『失われし自我を求めて』、ディヴィッド・リースマン『孤独な群衆』と進んでいった。ナチス・ドイツの優性政策にも時間が費やされた。その後、自我、エゴ、エス、アガペー、エロスなどのさまざまな概念が説明された。授業は儒教、旧約聖書、新約聖書へ続き、般若心経の詳細な解説に重点が置かれた。
夏休みにはグループ研究が課題になった。私のグループでは『新約聖書』を研究した。私たちが得た結論のひとつは、「新約聖書の言葉は論理を超えている」というものだった。
新約聖書には論理的な矛盾が随所に発見される。新約聖書は論理を超えて全体として伝えるものがあると解釈した。そんな発表をした。
この理解は私の考え方に影響を与えた。人はすべてを「理屈」=「論理」で考えてしまいがちだ。理屈の通ることは正しく、理屈の通らないものは間違いだと思いがちだ。だが、理屈を超えたところに真実が存在することもある。「もうひとつの真理」を忘れてはならないと思う。説明が難しいが論理を超えた真理がありうることを忘れずにいたい。
東京拘置所で読んだ『村上春樹はくせになる』に興味深い引用があった。ブルガリア出身の記号学者ツヴェタン・トドロフの著書『象徴表現と解釈』からで、アウグスチヌスが神の言葉について『三位一体論』で述べた言葉だ。「神のことばは、直接に理解できる思想ではなく、心の底で探究し、内奥から引き出すべき神秘をわれわれに提示している。」
グループ研究の結論がこれに近かったのかは分からない。私は永く新約聖書に関心を持った。この素地の上で映画『エデンの東』に遭遇した結果、新しい価値観が形成された。 後期の「倫理・社会」は仏教の講義が大半を占めた。『般若心経』が詳述された。のちに『般若心経』に関する著作を多く読んだ。教師は鈴木大拙禅師の流れを組む禅宗の専門家だった。授業は道元禅師の『正法眼蔵』の講義に進んだが難解だった。平井富雄著『瞑想と人間学のすすめ』を真剣に読んだことを思い出す。
高校での最大のイベントは体育祭だった。全校が六色の対抗チームに分かれ、競技、立て看板、殺陣(たて=応援団)、踊り、神輿を競う。立て看板はベニヤ板を20枚もつなぎ合わせて描く巨大絵画だった。
神輿も体育祭が終わると町会から寄進願いが申し入れられるほど立派で本格的なものだった。毎年、六基の神輿が作られた。学区域内に「三社祭」で有名な向島、本所があった。生粋の江戸っ子が多数を占める学校だった。
私は応援団員を務めた。6月から10月初めにかけて学校は体育祭一色に染まる。夜遅くまで近くの公園で練習が続けられた。青春映画のような風景だった。後夜祭では六色対抗で製作した見事な神輿や立て看板を燃やしてしまうチームが多かった。サンタナの「哀愁のヨーロッパ」がBGMに流れた。燃える炎を見つめて感慨にふけった。皆、燃焼し尽くした。》
引用が長くなって恐縮だが、皆さんに、植草氏が青少年期にいかに正義感と深い思想性を培っていたのかを知っていただきたかった。人それぞれに青春時代がある。植草氏は自らの青春時代をまさに燃焼し尽くしたのだ。きっと、悔いはなかったことだろう。 第二章の「炎」というタイトルも、実は高校の後夜祭で神輿や立て看板を燃やしたときの炎によって具象化されたものだった。
ところで、私は、上記の「論理を超えた真理がありうることを忘れずにいたい」という彼の言葉に注目したい。彼は単なるエコノミストではない。むしろ、彼の経済分析の根底にはこのような深い思想性と哲学がある。そこが竹中氏と本質的に異なるところだ。
私は植草氏が高校時代に培った深い思想性と哲学を自分なりに“実感”(あるいは“共感”)できる。なぜなら私自身、都立両国高校で倫理と政経を教えた経験があるからだ。
両国高校の生徒たちは実に優秀、かつ人間的にも魅力的な若者たちだった。とくに植草氏のような江戸っ子は気風がよくて、何より“曲がったことが大嫌い”なのだ。そんな江戸っ子の代表みたいな彼が、マスコミ(ネット上では「マスゴミ」と呼ばれる)が流布した「痴漢行為」などするわけがないではないか。むしろ、正義感の強い彼はいま、いままで彼を不当に貶めかつ辱めた輩に対して、正々堂々と反転攻勢に出ているのである。
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK70掲示板
フォローアップ:- 渡邉良明氏書評:植草一秀著『知られざる真実―勾留地にて―』を読んで 続き1 クマのプーさん 2009/8/31 11:27:54
(1)
- 渡邉良明氏書評:植草一秀著『知られざる真実―勾留地にて―』を読んで 続き2 クマのプーさん 2009/8/31 11:29:55
(0)
- 渡邉良明氏書評:植草一秀著『知られざる真実―勾留地にて―』を読んで 続き2 クマのプーさん 2009/8/31 11:29:55
(0)
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。