プリンスの長年のパートナーが語る『パープル・レイン』をめぐる狂騒、ワーナーとの確執
By DAN HYMAN 2016/05/22 16:30
http://images.rollingstonejapan.com/articles/25944/410x618/336cd6c81a25c6cbdd8281bcae3ff0b2.jpg
プリンスが絶大な信頼を寄せたアラン・リーズが語った、『パープル・レイン』の桁外れの成功がもたらした混乱、そしてレコード会社との対立(Photo:Getty)プリンスの黄金期をツアー・マネージャーとして支え、後にペイズリー・パーク・レコードの代表を務めたアランが・リーズが、プリンスとの思い出について語る。 アラン・リーズはプリンスが全幅の信頼を寄せた数少ない人物の1人だ。ツアー・マネージャー、そしてペイズリー・パーク・レコードの代表を務めたアランは、プリンスのキャリア最盛期の1983年から1993年の10年間において、あらゆる面で彼を支え続けた。60年代後半にジェームス・ブラウンのチームの一員となり、後にマックスウェルやディアンジェロのマネージメントも務めるアランは、『1999』のリリースツアーをきっかけにプリンスと出会い、その後の『パープル・レイン』をめぐる狂騒、そして彼とワーナー・ブラザース・レコードとの確執を目の当たりにしている。 2人はビジネス面におけるパートナーでありながら、互いに信頼を寄せ合う良き友人同士でもあった。「面と向かって彼に感謝の気持ちを伝えられなかったことを、私は後悔しているんだ」プリンス逝去が報じられた翌日に、ローリングストーン誌の取材に応じたリーズはそう話す。「彼と過ごした10年間で私が経験したこと、それは何物にも代えられない宝物だ」約1時間に及んだ本誌のインタビューで、彼はプリンスとの思い出について語ってくれた。 ―あなたはキッスのツアーマネージャーというポストを降り、『1999』のワールドツアーの中盤にプリンスのチームに加わっています。彼との出会いについて話していただけますか? 彼のチームに加わって数週間が過ぎた頃、当時のツアーマネージャーだったスティーヴン・ファーグノリ、そしてボディガード兼アシスタントの「ビッグ・チック」ハンツベリーからこう警告されたんだ。「彼の信頼を得たければ、無理に距離を縮めようとしないことだ」それまでに私が仕事をしたアーティストはみな積極的で自己主張が強かったが、プリンスはその対極にあるような人物だった。「彼が君のことをチームの一員として認めるまで、じっと待つことだ」そう言われたんだよ。 当時のツアーマネージャーから彼を紹介してもらった時、プリンスは軽く握手して頷いただけだった。ツアーに加わってから2、3週間経ったある日の夜、私はバンドのメンバーたちと一緒にホテルのバーで酒を飲んでいた。そこにチックに付き添われたプリンスがやってきて、バンドのメンバーが全員一瞬にしてかしこまった。まるで王様を前にした家来のようにね。私の目には奇妙に映ったが、みんな演奏のミスなどを指摘されることを恐れていたんだろう。バンドのメンバーがあんな風にアーティストと接するのを、私は見たことがなかった。彼がその場に加わった途端、ただならない緊張感が漂うのを感じたんだ。 幸か不幸か、たまたま私の隣の席が空いていて、そこにプリンスが座った。私はチックに席を譲ろうとしたが、彼は座ろうとはせず、着席するようにと手振りで示した。重たい空気が流れる中、私は何か話そうと言葉を探していたが、先に口を開いたのはプリンスだった。彼は私のほうを向き、どこか無邪気な様子でこう言った。「ジェームス・ブラウンの話を聞かせてくれ」何の前触れもなく、ただそう言ったんだ。あまりに急で、私は何を話すべきか考えを巡らせなくてはならなかった。バンドのメンバーも皆、私の緊張を感じ取ったようだった。話せば長いが、その時に私はプリンスと初めて会話らしい会話を交わしたんだ。 http://images.rollingstonejapan.com/articles/25944/wysiwyg/f865a3c225ceb4658fcd0e5a24827639.jpg
『彼は私のほうを向き、どこか無邪気な様子でこう言った。「ジェームス・ブラウンの話を聞かせてくれ」』―アラン・リーズ(Courtesy of Alan Leeds) ―あなたがチームに加わった時、彼のマネージメントは既に撮影に入っていた『パープル・レイン』の配給契約を取り付けようと奔走していたと言われています。 そのとおりだ。当時の私はまだマネージメントチームとは関わりがなく、そのことを知ったのも『1999』ツアーが終わってからだったがね。だが彼がノートに何かを書き留めている姿は度々目にしていた。曲や歌詞のアイディアだろうと思っていたが、実際には映画のストーリーに関するものだったんだ。 ―『パープル・レイン』撮影時のエピソードについて聞かせてください。周囲の人々は映画の出来に期待していましたか? していなかったね(笑)撮影に携わっていた人間の多くはアマチュアだった。ハリウッドで本場の撮影を経験したことがない、B級映画専門の人間の集まりといった感じだったんだ。音楽に基づいた映画というコンセプト自体がまだ一般的ではなかったから仕方ないがね。ミュージックビデオをはじめ、現在でこそ映像はミュージックビジネスの重要な一部となっているが、当時はそうではなかった。撮影チームの人間の多くは、「この素人たちに映画を作らせるなんて、音楽業界はどうかしてる」って思っていたはずだよ。プリンスが誰かもよくわかっていない様子だったから、彼らの仕事に対するモチベーションも低かった。当時は映画産業と音楽業界の間に、それぐらい大きな隔たりがあったんだ。『1999』の成功とワールドツアーはプリンスの名前を世界中に轟かせたが、それはあくまで音楽ファンの間に限られていた。映画の世界では、彼は全く無名の新人に過ぎなかったんだよ。 ―先見の明を持っていたんですね。 彼は音楽におけるビジュアル面の重要性を深く理解していた。マドンナやマイケル・ジャクソンと同じくらいね。彼は両者を結びつけた先駆者の1人だったんだ。その数年後、私がツアーマネージャーとして彼と共に世界中を飛び回っていた頃、彼はペイズリー・パーク・レコードを設立し、そこにオフィスを構えることになった私は、文字どおり四六時中彼と行動を共にするようになった。ある日私がオフィスで仕事をしていた時、プリンスから電話があった。その日はプリンスにとって典型的な1日で、朝10時か11時頃にノートを片手にスタジオにやって来て、自分のオフィスで軽く仕事を済ませ、午後1時頃からスタジオでレコーディングを始めた。彼はアルバムの制作に2ヶ月もかけるような平凡なアーティストとは違い、毎日必ず何かしらレコーディングしていた。たとえその曲の用途が決まっていなくともね。そしていつも夕方5時か6時頃になると私のオフィスに電話してきて、得意気にこう言うんだ。「今日録ったやつ、少し聴いてみるかい?」残念なことにその時スタジオで耳にしたのがどの曲だったか思い出せないんだが、ものすごくファンキーな素晴らしい曲だった。その曲は後にアルバムに収録されたかもしれないし、もしかしたらスタジオのどこかに眠ったままになっているかもしれない。私がファンク好きだということを彼はよく知っていたから、きっと気に入ってもらえると思ったんだろう。互いの声が聞こえないほどの大音量で曲が流れる中、私は彼の耳元でこう尋ねたんだ。「本当にこれを今日1日で録ったのか?」曲の出来は言わずもがな、ミックスもほぼ完璧に近い出来だったからね。彼はこう答えた。「昨夜書いたばかりで、今日早速録ってみたんだ」私は信じられないといった様子で首を横に振った。それだけでなく、彼はその曲のミュージックビデオのアイディアについてまで話してくれた。彼は既に明確なコンセプトを考えついていて、ストーリーボードを用意すればすぐにでも撮影に入れるほどだった。恐るべき才能だと思ったよ。彼と仕事を始めて数年が過ぎていたが、凄まじいペースで優れた作品を生み出し続ける彼に、改めて感服せずにはいられなかった。「まさかビデオのアイディアまで考えついているとはね、驚いたよ」私がそう伝えると、彼はこう言った。「分かってないね。君はオールドスクールな男だから仕方ないかもしれないけど、近頃のキッズは曲を聴くだけじゃ物足りないんだよ。ミュージックビデオはもはや曲の一部なんだ」 ―『パープル・レイン』はリリースと同時に世界中を席巻しましたが、あなたとプリンス本人は、それが時代を象徴する作品になると当時から確信していましたか? そうだね。ただ状況を飲み込むには少し時間がかかったよ。というのも、あれほどまでの成功を収めたアーティストを、私はビートルズ以外に知らなかったからね。両者を比較するわけじゃないが、キャリア最盛期のジェームス・ブラウンですら、あれほどの狂騒を経験したことはなかった。あの作品はそれまでのプリンスのファンを熱狂させただけでなく、新たなファン層を大量に生み出したんだ。映画に登場する台詞をすべて暗記しているという人もいれば、ウェンディやボビーZといったキャラクターのコスプレでコンサートに足を運ぶファンもいたよ。 あの作品の途方もない影響力を肌で実感した時のことは、今でもはっきりと覚えているよ。ツアーの3日目はワシントンDCで、我々はウォーターゲートホテルに宿泊していたんだが、プリンスが髪を切りたいと言い出してね。どこに滞在していようとも、彼がそう主張するたびに、私たちは場を提供してくれる街のサロンを探さないといけなかった。店をまるごと貸し切られせてくれるところをね。従業員を休ませ、窓をすべて新聞紙で覆うことに同意してくれるという店には、彼らが希望する額を支払った。店主の中にはプリンスの大ファンで、サインとコンサートのチケットだけで十分だっていう人もいたよ。その日、彼のスタイリストはジョージタウンにあった店と話をつけた。私は同行せず、ホテルに残って仕事を片付けていたんだが、テレビでジョージタウンの街が大混乱に陥っているというニュースを目にしたんだ。プリンスが車から出てきてそのサロンに入っていくのを目撃した人間が騒ぎ立てたせいで、近隣の店にいた人々や噂を嗅ぎつけたファンたちが大量に押し寄せ、警察がウィスコンシン・アベニューを閉鎖する事態になってしまった。その様子をテレビで観ながら、私は思わずこう呟いた。「我々の手には負えないな」 http://images.rollingstonejapan.com/articles/25944/wysiwyg/187d4a78697d3299f8280d78aafa9473.jpg
『パープル・レイン』でのプリンス 「キャリア最盛期のジェームス・ブラウンですら、あれほどの狂騒を経験したことはなかった」―アラン・リーズ(Photo:Getty) ―1985年頃、プリンスはツアーに出ることをやめ、次作からはミュージッックビデオも制作しないと公言しました。あなた方は彼が本気だと思っていましたか? 最初はただの気まぐれだろうと思っていた。というのも、私は彼が毎日のようにスタジオで曲を作っていることを知っていたし、それがいずれアルバムとしてリリースされると確信していた。
それに、彼はステージで新曲を演奏することに何よりも喜びを覚えていた。私がやめろと言っても、彼は決して耳を貸そうとしなかった。当時私は彼の発言をあまり深刻に受け止めていなかったが、実際のところ彼は『パープル・レイン』によってもたらされた途方もない名声にうんざりしていたんだ。何万人もの前で演奏することにもね。8、9ヶ月もノンストップで演奏し続けて、消耗してしまっていたのかもしれない。『パープル・レイン』のツアーはすべてが緻密に計画されていたために、毎晩何かしらのアレンジを加えるということができなかったんだ。映画のストーリーと連動している以上、セットリストを変えることはできないし、結果的にライティングやプロダクションもすべて固定せざるを得なかった。期待どおりの内容にファンは熱狂したが、アドリブやアレンジが許されないショーの連続は、プリンスにとっては苦痛だったんだ。 その解決策として彼が思いついたのは、アンコールで好きな曲を好きなだけ演奏することだった。必然的にショーの時間が長くなり、会場使用費は膨れ上がった。ツアー日程の半分を終えた時点で、そのコストは既に何千万ドルにも達した。毎晩0時30まで演奏していたんだから当然さ。とにかく、そんな彼がステージに立つことをやめるなんて私は信じなかった。ファンの前で演奏する喜びを、彼がそう簡単に諦めるはずはなかったからね。 ―いま振り返ってみても、『ダーリン・ニッキー』に対するティッパー・ゴアの主張のような、彼のセクシャルな内容の歌詞に対する世間の過剰な反応は馬鹿げていたと思います。 同感だ。彼の歌詞はカルチャーが大きく変貌しつつあった当時のムードを風刺していたんだ。アル・ゴアの妻だったティッパー・ゴアのような、どちらかというとリベラルな人物があんな風に反応したことが、時代がいかに大きく変わろうとしていたかを物語っていると思う。プリンスの影響力を考えれば、彼はそのムーヴメントの一端を担っていたと言っていいだろうね。メディアの前では常に動じないふりをしていたが、実際にはそういう馬鹿げた主張にうんざりしていたと思うよ。 ―『ウィー・アー・ザ・ワールド』への参加を拒否したことも大きな話題となりました。当時の状況について、印象に残っていることを話してもらえますか? あの日の夜は外出を控えてくれと懇願したよ。彼は夜のロサンゼルスの街を出歩くのが好きで、カルロス・アンド・チャーリーズ・オン・サンセットというクラブがお気に入りだった。エディー・マーフィーやジム・ブラウンもよく出入りしていた、ロサンゼルス随一のセレブ御用達のクラブだったんだ。私やバンドのメンバーもよく足を運んでいたよ。プリンスが『ウィー・アー・ザ・ワールド』に参加しなかった理由はただひとつ、彼が自分のやりたいことだけをやりたいようにやる一匹狼だからだ。プロジェクトのコンセプトに賛同していなかったからじゃない。その証拠に、彼は自身の曲を提供している。彼は集団に混じって行動するタイプじゃない、ただそれだけだよ。 プリンスは自身の作品にゲストを参加させることはあっても、その逆のケースはほとんどなかった。あったとすれば、それは個人的な繋がりか、あるいはそのアーティストをサポートしたいという強い思いからだろう。当時メディアが毎日のようにマイケル(・ジャクソン)とプリンスの確執を記事にしていたことも関係していたかもしれない。マイケルとクインシー(・ジョーンズ)が主導していたあのプロジェクトに参加すれば、自分は引き立て役にさせられると感じていたんだろう。あまり知られていないが、それが彼が参加しなかった理由のひとつだと私は思っているんだ。 とにかく、私は彼にこう言ったんだ。「今日は外出を控えてほしい。あのプロジェクトへの参加を断って外で遊んでいたと報じられたら、君のイメージが著しく傷つくことになる」彼がホテルの部屋から出ないように、私たちは見張っていないといけなかった。夜中の1時か1時半頃、彼がさすがに諦めたようだと判断した私は、妻のグウェンと共に自分たちの部屋に戻り、バンドのメンバーたちもそれにならった。しかし夜中の3時頃、プリンスのボディガードのビッグ・チックが電話してきたんだ。「寝てる場合じゃないぞ。俺たちの仲間がムショに送られた」私は蒼ざめた。今となってはよく知られていることだが、私たちが引き上げた後にプリンスは外出し、出先で大勢のパパラッチに取り囲まれてしまった。あまりにしつこかったフォトグラファーに肘打ちを食らわせた彼のボディガードは投獄され、我々は翌日に保釈金を支払うはめになった。その後は私たちが懸念したシナリオどおりになってしまった。アフリカの子供たちを飢餓から救うという素晴らしいコンセプトに賛同した音楽業界の大物たちがスタジオに集まっていた頃、参加を断ったプリンスはナイトクラブで羽目を外し、ボディガードがパパラッチに暴力を振るって刑務所に送られたという、大衆が飛びつきそうなストーリーがあらゆるメディアのトップを飾った。実際にはその事件と彼があのプロジェクトに参加しなかったこととは無関係だったが、私は頭を抱えずにはいられなかった。 ―ヒット・アンド・ラン・ツアー、そしてパレード・ツアーの直後に、彼はザ・レボリューションを解散させてファンを驚かせました。その背景にはどういう事情があったのでしょうか? あの頃、彼はミュージシャンとして日毎に成長を遂げていたんだ。その背景にはウェンディ(・メルヴィン)、リサ(・コールマン)、そして私の弟(エリック・リーズ)との出会いがあった。彼らはそれぞれ、プリンスとはまったく異なる音楽的バックグラウンドを持っていたからね。私の弟はジャズに精通していたし、シーラはジャズとラテン音楽に造詣が深かった。プリンスと出会う前、彼女はハービー・ハンコックやジョージ・デュークのツアーに参加していたんだ。エリックは子供の頃からジャズに夢中だったよ。プリンスは彼らとの出会いを通じて、自身の音楽的バックグラウンドを広げていったんだ。当時の彼はすごく生き生きとしていたよ。 そういった新たなインスピレーションは、作曲、パフォーマンス、楽曲アレンジなど、彼の音楽のあらゆる面に大きな影響を及ぼした。結果として、彼はより多様なニーズに応えられるミュージシャンを必要とするようになっていったんだ。ザ・レボリューションのオリジナルメンバーたちは、お世辞にも経験豊富とは言えなかった。プリンスを除けば、めぼしいアーティストとの共演歴もほとんどなかった。新たなヴィジョンを具現化するために、プリンスはより優れたミュージシャンたちを必要としていたんだ。アーティストとして進化するための前向きな決断だったと私は思っているよ。プリンスだけでなく、バンドのメンバーや彼のファンにとってもね。 『パープル・レイン』の熱狂的なファンにとっては残念な出来事だったかもしれないが、新たなフェーズを迎えようとしていた当時のプリンスにとって、彼らでは役不足だったんだ。進化には変化がつきものだからね。夢を壊されたと感じたファンもいただろうけど、結局のところ、プリンスのファンと『パープル・レイン』のファンは、それぞれ求めることが違っていたということだよ。後者の中にはプリンスの他の作品をまったく知らないという人も多いはずさ。 ―その後の数年間で、プリンスはドリーム・ファクトリー、カミール、クリスタル・ボールといった複数のプロジェクトを手がけています。3枚組のアルバムをリリースするという彼の希望にワーナーが反発し、結果的に2枚組として発表されたのが『サイン・オブ・ザ・タイムズ』でした。あの出来事がワーナーとの確執の始まりだったのでしょうか? そのとおりだ。もちろん過去にも意見の食い違いはあったが、後にしこりを残すような対立はあれが最初だった。何らかの理由でお蔵入りとなったドリーム・ファクトリー、カミール、そしてクリスタル・ボールという3作の集大成といえる『サイン・オブ・ザ・タイムズ』は、皮肉にもワーナーとの摩擦から生まれたということだよ。彼は全面的に争ったが、最終的にはレーベルに屈したんだ。 『アラウンド・ザ・ワールド・イン・ア・デイ』と『パレード』の2作は、商業的には『パープル・レイン』で収めた成功に遠く及ばなかった。だから当時ワーナーの人間が考えていたのは「もう一度1300万枚売れるレコードを出す」ということだけだった。アート性の強い難解な作品ではなくね。内容よりもセールス重視というわけさ。『サイン・オブ・ザ・タイムズ』からもヒットシングルは生まれたが、マーケティング戦略がもっと優れていれば、あの作品はより大きな成功を収めることができたはずだと私は思っている。今となっては言い訳のようにしか聞こえないだろうがね。とにかく、ワーナーとの確執の発端があの作品であったことは紛れもない事実だ。 ―アメリカでは『サイン・オブ・ザ・タイムズ』のツアーが行われませんでした。その決定をめぐり、多くの議論が交わされたことは容易に想像できます。 我々はもちろんアメリカでツアーを行うべきだと考えていたが、彼は首を横に振り続けた。ヨーロッパツアーを経て、彼はショーに対するモチベーションを既に失ってしまっていたんだ。シングルカットされた『イフ・アイ・ウォズ・ユア・ガールフレンド』が、期待したほどの反響を得られなかったことも関係していたかもしれない。我々がプリンスの決定に口を挟むことは許されなかったように思われているかもしれないが、そんなことはなかった。彼の考えが正しくないと思った時には、我々は必ず話し合いの機会を設け、それによって彼が考えを改めることもあった。しかしあのツアーにおいては、彼は我々の意見を決して聞き入れようとしなかった。『パープル・レイン』が収めたとてつもない成功に比べ、『サイン・オブ・ザ・タイムズ』のツアーが見劣りすると感じていたのかもしれない。 ―『ブラック・アルバム』の制作において、印象に残っているエピソードはありますか?プリンスが罪悪感を理由に、同作のリリースを直前に中止したことは広く知られています。 あの判断が直感的なものだったことは確かだ。あとは出荷するだけという段階での決定だったからね。彼は『ブラック・アルバム』をプリンスの作品ではなく、サイドプロジェクトのひとつとして捉えていたんだ。ジャズ寄りのインスト作品を発表していたマッドハウスや、ピュアなR&B
やファンクを追求したザ・タイムと同じようにね。ゲットー出身のR&Bアーティスト、そんな風にカテゴライズされることを、彼は何よりも嫌っていたんだ。 『ブラック・アルバム』は、プリンスが『パープル・レイン』でセルアウトしたという黒人層からの批判に対する回答だった。実際『プレイス・オブ・ユア・マン』のような、ストレートなロックンロールをよしとしないブラックミュージックのファンは少なくなかった。だが彼はブラック系のラジオ曲でかかるような、典型的なR&Bアーティストになるつもりはまったくなかった。また当時、メインストリームの音楽として認識されるようになったヒップホップがチャートを席巻していた。スタジオで過ごしていたある日の夜、彼は床に転がっていたビルボード誌を指差してこう言ったんだ。「ヴァニラ・アイスやMCハマーのような、ロクに歌えもしないやつらの曲がチャートのトップを飾り、人生をかけてアートを追求し続けているアーティストの曲がトップ10にすら入らないなんて、どうかしてると思わないか?」彼は当時の状況に大きな不満を抱えていたよ。 当時は誰もがパブリック・エネミーのようなアーティストに夢中になっていたが、我々はそうは感じていなかった。プリンスはエリックB&ラキムのことも気に入らない様子だった。彼らはブロンクスのゲットーではなく、プリンスと同じミネアポリス出身だったからね。「やつらはただ喋ってるだけじゃないか。詩人としてはまぁまぁなのかもしれないけど、少なくともミュージシャンと呼べるような存在じゃない。DJと大差ないさ」彼はそう話していた。『ブラック・アルバム』は彼のそういう思いを形にした作品であり、同時に「プリンスはもうファンキーじゃない」という批判に対する回答でもあった。こんなのは俺にとって朝飯前なんだよと言わんばかりのね。 しかし彼はあの作品が怒りから生まれたことに罪悪感を感じ、直前になってリリースを中止した。今振り返ってみても、それが正しい判断だったと私は思っているがね。 http://images.rollingstonejapan.com/articles/25944/wysiwyg/df421bec021258ef54a401642be184e3.jpg
「彼は毎日欠かさずレコーディングしていた。とてつもない数の作品が未発表のままになっているんだ」―アラン・リーズ(Bertrand Guay/Getty) ―その後プリンスとワーナーの関係は目に見えて悪化していきました。両者の確執について話してもらうことはできますか? 喜んで話すさ!プリンスは自身の新たな方向性を受け入れようとしないワーナーの態度に不満を感じていた。80年代半ばから終盤、彼の創作意欲はとどまるところを知らず、次から次へと作品を生み出していった。当時彼は毎日欠かさずレコーディングしていたんだ。とてつもない数の作品が、今でも未発表のままどこかに眠ってるはずだよ。作品の新鮮味をとても重要視していた彼はこう話していた。「完成した曲をできるだけ早くファンに届けたいんだ。レコード会社に任せていたら、リリースされる頃には古臭くなってしまっているだろう。今すぐこの作品を世に出すにはどうすればいいと思う?」 ペイズリー・パークで彼が不満を爆発させた時のことは今でもよく覚えている。1990年のことで、彼がワーナーの傘下に立ち上げたペイズリー・パークの運営に専念するために、私はツアーマネージャーという役割を降りたばかりだった。ペイズリー・パークがヒットシングルを出せずにいたことで、ワーナーとの関係が悪化する一方だった当時、プリンスは自身の作品の扱いについても不満を募らせていた。90年代初頭といえば、インターネットが音楽業界に及ぼす影響について議論され始めた頃だ。彼はこう話していた。「君はレーベル運営の経験がある。2人で新しいレーベルを立ち上げようじゃないか。いいアイディアがあるんだ。(ロン・)ポペイルがテレビショッピングで皮むき器を売っているのと同じ要領で、出来上がったばかりの作品をファンに届けるんだ」私はこう答えた。「プリンス、ワーナーとの契約が続いている以上、そんなことが許されないのは君もわかっているだろう。我々がそんな行動に出れば、作品はすぐに差し押さえられ、間違いなく裁判沙汰になる。君だって何十万ドルも無駄にしたくはないはずだ。冷静に考えよう」すると彼はこう言った。「じゃあプリンスの名を使わなかったらどうだ?」私はこう答えた。「不可能ではないかもしれない。だがペイズリー・パークの代表である私の給料の半分は、親会社であるワーナーから支払われているんだ。そんなことをしたら、やつらは私を監禁しかねない」 彼は私の目をまっすぐ見てこう言った。「よし、じゃあレーベルの名前はグウェン・レコーズにする」グウェンは私の妻の名だ。「彼女が代表を務める。作品のどこにもプリンスの名前は一切クレジットされない」そう話す彼に、私は何と返せばいいかわからなかった。今になって思えば、レコードショップで買えない音楽をインターネット上で流通させるという、現在では当たり前となったダイレクトマーケティングという手法を、彼は当時の段階で思いついていたということだよ。もちろん青写真に過ぎなかっただろうが、そういう時代がくることを彼は予想していたんだ。 ―ペイズリー・パークの商業的失敗、そしてワーナーとプリンスの板挟みという状況は、あなたがプリンスと袂を分かつきっかけとなったのでしょうか? 彼もそう捉えていたようだった。「あんたもあっち側につこうってわけか」そう話す彼に、私はこう答えた。「そうじゃない。私はただ両者にとって最善の選択肢を選ぼうとしているだけだ。ペイズリー・パークは私だけの会社じゃないんだ。私がこのプロジェクトに関わったのは、君がアーティストのプロデュースを手掛け、ヒットシングルを生み出すと信じていたからだ。しかし率直に言って、君はその役割を果たすことができていない」ペイズリー・パークがメイヴィス・ステイプルズ、そしてジョージ・クリントンというレジェンド2人と契約したことは私も誇りに思っているが、残念ながら結果を出すことはできなかった。彼らを過去のアーティストとみなしていたワーナーは、最初からあまり前向きに捉えていなかった。レーベルの新人アーティストにプリンスが提供した曲も、決して優れているとは言い難かった。自分の彼女のレコードに手抜きの曲を提供しているようでは、成功など望むべくもない。プリンスと袂を分かつことを決意した私は、彼にこう伝えたんだ。「プリンス、我々は追い詰められてしまった。この状況を打開するにはやり方を変えるしかないが、君が首を縦に振らないことはよく分かっている。残念だが、これ以上君との関係が悪化する前に、私は降りることにする」 ―タッグを解消した後、プリンスとの関係はどうなりましたか?あなたが最後に彼と話したのはいつ? 彼と最後に話したのは2、3年前だ。ディアンジェロのことで、彼から連絡があったんだ。まだ『ブラック・メサイア』がリリースされていなかった2012年に、ディアンジェロは長い沈黙を破ってツアーに出ることを発表した。そのニュースを耳にしたプリンスが、ディアンジェロが彼のコンサートの前座を務めるという話を持ちかけてきたんだ。残念ながら実現には至らなかったがね。彼と話したのはその時が最後だ。過去にどこかの会場で偶然出くわしたことはあったけどね。マックスウェルかディアンジェロか、どちらだったか忘れてしまったが、コンサートの会場にプリンスが来ていたんだ。あと93年か94年に、日本ツアーの企画に関することで連絡をもらったこともあった。でも常に仕事に関することだったよ。「やぁ、奥さんとの調子はどう?久々にピンボールでも一緒にどうだい?」彼はそんな電話をかけてくるタイプじゃないんだ。 彼に伝えたいことはたくさんあるよ。妻にもよくこう話していたんだ。「どこかでプリンスと出くわすことがあればいいんだがね。もう随分長く顔を合わせてないんだ」彼と何時間も音楽の話をしていた頃が懐かしいよ。ああいった形でタッグが解消され、自分の思いを面と向かって伝えられなかったことが心残りになっているのかもしれない。だからここで言葉にしておくよ。彼と過ごした10年間は、私の人生において最も輝かしい時間だった。彼と出会わなければ、今の私は決してなかったはずだ。彼がこの世を去ったというニュースを耳にした私の弟が、昨日電話でこう話していたんだ。「プリンスのような存在は不死身のはずなんだ」人々はマイケル・ジャクソンに対しても同じ幻想を抱いていたが、もしかするとそのとおりなのかもしれない。プリンスやマイケル・ジャクソンは、人々に幸せと喜びをもたらすためにこの世界に降り立った、人間を超越した存在だったのかもしれないね。 Translation by Masaaki Yoshida
http://www.rollingstonejapan.com/articles/detail/25944/1/1/1
http://www.rollingstonejapan.com/articles/detail/25944/2/1/1
http://www.rollingstonejapan.com/articles/detail/25944/3/1/1
http://www.rollingstonejapan.com/articles/detail/25944/4/1/1
|
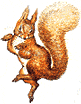
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。