http://www.asyura2.com/09/jisin16/msg/793.html
| Tweet |
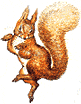

まだ大勢の人が避難所生活を強いられている(写真は岩手県陸前高田市の避難所で、おにぎりを配るボランティア)
大災害の爪痕 ~FT現地ルポ(3) ~2011.04.01(Fri) Financial Times
この日、大船渡の瓦礫の中で、持ち帰れる物がないか探している人はサトウさんだけではなかった。
少し離れたところで、足を引きずりながら線路に沿って歩いている2人の中年女性の姿が目にとまった。この単調な風景の中で生き物が動いている、と一瞬ショックに近い感覚が走る。
1人は赤い杖をつき、毛糸で編んだ帽子を被っている。ほおの色はりんごのように赤い。もう1人は白いマスクをつけている。2人ともリュックサックを背負い、寒さに備えてしっかり着込んでいる。
恐らく50代のシモダテ・ヒロミさんは喫茶店のオーナーだ。少なくとも、この間まではそうだった。
この辺りにお店があったんですよ、と彼女は手を振りながら教えてくれた。「うちのものが何かないかと思って探してるんです。その、ほら、イスとかそういうもの」。何か申し訳なさそうな口調でシモダテさんはそう話す。
地震が起きた時、2人ともこの喫茶店にいたという。連れのキムラ・ヤスコさんが、スマートフォンに収めてあった店の写真を見せてくれる。ピンクが基調の内装で、額に入った写真が何枚か飾られている。つい数日前の、別の時代に撮られたものだ。
お店はすごく揺れた、とキムラさんは言う。津波警報が聞こえたので、大急ぎで車に乗り、海から離れたのだという。
チリ地震の記憶があり、逃げなかったお年寄り
「ここではお年寄りがたくさん亡くなりました。逃げなかったんです。この辺りのお年寄りはみなさん、昭和35年のチリ地震を覚えていますから」。1960年のチリ地震は観測史上最大の地震であり、地球の反対側にある日本にまで津波をもたらした。
「あの時は、ここまでしか津波が来なかったんです」。キムラさんはそう言って指さしたが、この辺りは荒れ果てた光景がずっと続いており、海岸に多少近いほかの荒地と区別がつかない。「お年寄りは、こんなところまで水が来るはずないと思ってたんですね。だから動かなかったんです」
シモダテさんは言う。「この辺りの人は、家族を全員亡くしました。それに比べたら、私の被害なんか何てことない。隣の入り江は、もっともっとひどかったから」
食料事情は自衛隊の活動のおかげで改善されつつある。筆者もこの後、自衛隊のトラックが何台か通るのを見かけた。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/5777
「何日か前、自衛隊の人がおにぎりをくれたんですね。でも、1つのおにぎりを2人で分け合わないといけなかった。ガソリンもないんです。だから歩かないといけない」。シモダテさんはそう言って、マンガのキャラクターをまねて、ひじを伸ばしたまま腕を大きく振って歩いてみせた。そして、「これ、健康にいいのよ」と大きな声で笑った。
こんなことで町が有名になるなんて・・・
「彼女の友達がニューヨークからメールしてくれたのよ」とシモダテさん。彼女とは、隣にいるキムラさんのことだ。「大船渡がテレビに映ってたんですって。私たち有名になっちゃったのよ。でも、こんなことで有名になってもねぇ」。シモダテさんは、あたかも後から思いついたかのようにそう付け加えた。
「あっ、何かある!」 シモダテさんが甲高い声で突然叫び、前方に飛び出した。見ると、彼女は小さな、金属製の平らな漉し器を握りしめていた。みそ汁を作る時などに使う道具だ。以前の生活の残片と再会した彼女は、うれしさ半分悲しさ半分といった表情をしている。
「うちのだって、すぐに分かった。毎日使ってた物だから」。シモダテさんはそう言って、荒涼たる風景の真ん中で、小さな漉し器を改めて見つめた。「何か哀れな感じがするわね」
翌日、大船渡の北東に位置する泊(とまり)という海辺の集落に足を運んだ。筆者には、前日訪れた大船渡とこことの見分けがあまりつかない。大船渡と同じように、ここにも人がいて作業をしている。
サガワ・ヒデオさん(62歳)は青いスポーツジャケットを着て野球帽をかぶっている。側にいる妻のクミコさん(57歳)は、ひざ丈の青いスモックに明るい赤のコートという身なりだ。
クミコさんは瓦礫の様子を杖でつついて調べており、ヒデオさんは住宅に使われていた材木をのこぎりで切っている。「たきつけにする」のだそうだ。
サガワ夫妻は、避難所がある近くの丘の方を指し示して教えてくれた。逃げてきた70人ほどの住民がとりあえずそこに寝泊まりしているのだという。行ってみると、古い縫製工場に東地区の避難所の本部が設置されていた。
避難所の光景
駐車場には、牛丼チェーン「吉野家」のトラックが1台止まっている。支援物資を届けに来たのだ。温かい食事を食べるのはあの地震の日以来だという人も多いかもしれない。
一番大きな部屋に入ると、20世帯あまりの人たちが小さなグループに分かれて過ごしている。入り口の引き戸のそばには、靴や長靴が畳に沿ってきれいに並べられている。室内は暖かく、ストーブの上に置かれたブリキのやかんから湯気が出ている。誰もが床に座って、小さな声で話をしたり、テレビで原発の最新ニュースを見たりしている。
子供たちは走り回っている。最愛の家族を失ってしまったのだろうか、ただぼんやりと宙を眺めている人も何人かいる。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/5777?page=2
部屋の一番奥にはフェルトの赤い敷物が敷かれている。その上には折りたたみ式の長いテーブルがきれいにセットされており、何人かが手分けして緑茶のペットボトルを一定の間隔で置いていく。やがて、その隣にスチロール製の容器に入った牛丼が並べられる。
午後6時半きっかりに「夕食です」というアナウンスが入る。誰もが静かにテーブルまで移動し、それぞれに両手を合わせて「イタダキマス」と言う。「謹んで受け取ります」という意味の言葉を食事の前に唱える、日本の習慣だ。食事が始まると、部屋はとても静かになる。きっと、すごくお腹がすいている人が多いのだろう。
この避難所で筆者が最後に話しかけたクマガイ・トモヤさんは58歳の漁師で、地震が起きた時には自分の船に乗っていた。
「船はいつも揺れている。当たり前だがな。だが大きな地震の時は水の動き方が違う・・・三角というか、ギザギザの波になるんだ。あれで大きいやつが来たと分かったんで、大急ぎで港に引き返した」
クマガイさんは夫人と義理の母親を見つけて、車で安全なところに避難した。丘の上からは一部始終がはっきり見えたという。彼の話は、筆者がこれまでに耳にした津波の描写の中で最も生々しいものだった。
何度も何度も襲ってきた波、これからは高台で暮らしたい
「最初の波は高さが7メートルくらいだった。こいつは防潮堤を越えなかった。ところが、波は一度引いてからまたやって来た。水の量は倍に増えていて、堤防をぶちこわした。その後も、波は何度も何度もやって来た。大きいやつも4回来た。いったん陸に上がった水は引かなかった。次から次へと海から押し寄せてきたからだ」
クマガイさんはリアリストだ。この地区で再び漁業ができるようになり、住民が新しい住まいを見つけて元の暮らしを取り戻すには、非常に長い時間がかかるだろうと考えている。避難生活が何年も続く恐れもあるという。
ご自身はどうするのか尋ねてみた。住んでいた場所に戻って、家を建て直して再出発するのだろうか?
クマガイさんは、しばらく考えてから口を開いた。「これまでに大きな津波を何度も見てきた。もうたくさんだ。これからはもっと高台に住みたいと思う」
By David Pilling
© The Financial Times Limited 2011. All Rights Reserved. Please do not cut andpaste FT articles and redistribute by email or post to the web
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/5777?page=3
| 拍手はせず、拍手一覧を見る |
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常
|動画・ツイッター等
|htmltag可(熟練者向)
(タグCheck
|タグに'だけを使っている場合のcheck
|checkしない)(各説明)
(←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)
↓パスワード(ペンネームに必須)
(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
重複コメントは全部削除と投稿禁止設定
ずるいアクセスアップ手法は全削除と投稿禁止設定
削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告」をお願いします。 最新投稿・コメント全文リスト
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。