| Tweet |
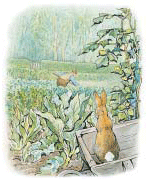
| 裁判員制度はこれまで「順調」に行なわれてきた。いずれの事件でも量刑は死刑ではなく懲役刑だった。だが事件は懲役刑で済むものばかりではない。そう遠くないうちに(一説では9月にも)過去の判例から考えて死刑が相当の事件が対象となるのは間違いない。 司法当局は裁判員制度の下での最初の「死刑判決」をできるだけ「スムーズ」に下したいと考えているはずである。いくら残酷な犯罪を犯した被告であっても彼は人間であることに変わりはない。裁判員制度で裁判員はその被告を目の前にする。彼の顔を見、彼の肉声を聞き、彼が間違いなく一人の人間であることを裁判員は肌で感じるだろう。これまで新聞などで死刑執行の記事が載ってもほとんど関心を払ってこなかった人が裁判員として被告を前にする。死刑判決を下すということは死刑執行への開始手続きを意味する。裁判員たちには、これまでのように死刑執行が新聞の片隅の一記事ではなく、被告とはいえ、一人の人間である被告を「殺す」ことであることをストレートに意識せざるを得ないに違いない。 被告が複数人を殺害し、その事実を認めており、過去の判例からすれば死刑相当であることが明らかな事件を担当する裁判員たちは、量刑を判断するにあたってどのような判断をするだろうか。一つは、過去の判例に依拠し、また裁判官の意見も受け入れ、「自分の意志」ではなく、これまでの司法の判断に自らの判断を預けるという、いわば「自己を没した」上で量刑を死刑とするだろう。一般的に言って「人を殺す」ということにはどのような理由があろうとも人は忌避するものである。だが、軍人と裁判官はそうではない。その社会的立場、職業上の責務によって人を殺すことを厭わない姿勢が求められており、本人もその責務を受け入れている特別な人たちである。 裁判官と異なり、職業上の責務を持たない一般人が抽選で裁判員に選ばれて、死刑が妥当と判断を下す。にわか裁判員には、「自らの意志」で死刑判決を下すことの重みには堪え難いものがあるかもしれない。そうした人たちは、過去の判例に従っただけであり、また裁判官の誘導に従っただけであり、自らの意志で死刑判決を下したのではない、ということで自分を納得させようとするだろう。そうでもしなければ自らの行為の重さに耐えられないからだ。「司法への市民参加」という裁判員制度の趣旨とはうらはらな結果となる。結局、司法の思惑通りに使われることになる。 裁判員の中には、秩序を重んじることに最大の価値を置く人もいるかもしれない。そうした人にとっては、重大犯罪を犯した人に死刑判決を下すことにそれほどの躊躇を覚えないかもしれない。むしろ「極悪人」に死刑判決を下すことによって「達成感」を感ずるだろう。また従来では死刑が適用されてこなかった事例について、死刑を適用しようする重罰化の傾向を持つと容易に推察できる。こうした人たちが一定の割合で存在することについては留意すべきことだ。今、進みつつある司法の厳罰化の先導役を果たすことになるからだ。 最後に、裁判員の中には過去の判例にいたずらに引きずられることなく、また裁判官の誘導に従わず、自らの考えで判断しようとする人も少数ではあるが一定の割合で存在すると思われる。そのような人は自らの判断で死刑の量刑に反対し、懲役刑を主張するかもしれない。いや、そのような人しか懲役刑を主張しないだろう。しかし、最終的な量刑は多数決できまる。自分は懲役刑を主張したのに死刑判決に名を連ねることになる。裁判員の中で誰が死刑判決に賛成で誰が反対だったかは裁判員の秘守義務であり、自分は死刑判決に反対だったとは言えない。自分が死刑に反対したのに結局、死刑が確定したとき、また死刑が執行されたとき、その人の受ける心理的な苦痛は想像に余りあるものがある。自らの力不足で結果的に被告を殺す一連のプロセスに手を貸してしまった。そうして自分を責めることになるかもしれない。それは一生背負い続ける重荷だ。 大勢に流されることなく、また自分をごまかさず、個を確立した人だけが受ける大きな苦痛である。それでも自らの主張を変えることはしないだろう。誰にも知られることのない重荷を背負いながら。 |
- 既に準備の、拒否出来ない徴兵制度と密接関係の 「裁判員制度」 AHR666Generation 2009/8/23 10:22:10
(0)
- 裁判員に選ばれないための方法はあるやに聞いております。 最大多数の最大幸福 2009/8/23 00:13:08
(4)
- そういう問題ではありません。 ダイナモ 2009/8/23 01:09:44
(3)
- では、わたしは少数派かもしれません。 最大多数の最大幸福 2009/8/23 12:09:49
(2)
- 騙されて [現実]を、無視すると・・ 誰でも後悔します。。 AHR666Generation 2009/8/25 12:33:21
(0)
- そうですか。 ダイナモ 2009/8/23 13:27:01
(0)
- 騙されて [現実]を、無視すると・・ 誰でも後悔します。。 AHR666Generation 2009/8/25 12:33:21
(0)
- では、わたしは少数派かもしれません。 最大多数の最大幸福 2009/8/23 12:09:49
(2)
- そういう問題ではありません。 ダイナモ 2009/8/23 01:09:44
(3)
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。