| 暗たんたる気分にとらわれた 読みながら、暗たんたる気分になった。「光市母子殺人事件」――広島高裁の差し戻し控訴審は今年四月二二日、弁護団の主張をすべて退け、被告の元少年に死刑判決を言い渡した。
衝撃的で象徴的な事件である。加害者の犯行行為そのものではなく、報道と裁判の経過がである。本書はこの判決の日に発行された。事件とその報道について検証する集会が三月、都内であった。この集会での弁護団の報告を中心に構成されている。
再控訴審で結成された新弁護団はまず、事実認定の違いを強調した。被害者母親の遺体頸部右側に残った蒼白帯は何を意味するのか。二mの高さから床に叩きつけられたとされる乳児に、その痕跡がなかったのはなぜか。弁護団が実験した写真やイラスト、法医鑑定人の結論が、真実へのアプローチを容易にしている。
警察の捜査のズサンさ。法廷で物証が点検されない理不尽さ。検察側に追随し、一体となって厳罰を下す裁判所の発想に、怒りと危機感を覚えずにはいられなかった。 被害者感情とメディアの演出 今回被告人に初めて面会した弁護士は、それまでの供述を翻し、殺人と強姦の意思を否定した発言に驚愕したという。捜査段階から弁護士がつかず、かつ小学生並みの精神年齢だと鑑定された少年が、警察の意のままに供述したとしても何ら不思議はない。悲劇的な冤罪を繰り返してきた代用監獄。自白偏重の捜査手法は、旧態依然、温存され続けてきた。
本件を「典型的な少年事件」だと弁護団は指摘する。だが公判には毎回傍聴を求める人々の長蛇の列ができた。これほど世間の関心が集まったのは、被害者感情のみがメディアによって繰り返し演出、増幅された結果だろう。
「私が加害者を殺す。――躊躇することなく極刑を求める遺族の姿。ネット上には被告少年の実名や顔写真が流布し、「殺せ、殺せ」の大合唱が始まった。それでも旧控訴審までは、司法の良心がかろうじて息づいていた。「無期懲役」という判決には、少年の極めて不幸な生育過程が酌量されていたのだ。
少年と母親は、父親のすさまじい暴力を受けていた。殴る蹴るはもちろん、逆さに水風呂に漬けられたりもした。包丁を突きつけられ何度も命の危険にさらされていた。それにより少年の精神の発達は著しく阻害され、家庭裁判所の鑑定には、「精神年齢は四、五歳で止まっている」との意見もあったという。
暴力におびえながら、少年と母親との依存、密着関係はさらに強くなっていった。それは実の母親をして、「結婚してお前に似た子供をつくろう」と言わしめるほどだった。しかしそんな母親は、少年が中学一年の時に首吊り自殺する。少年は自殺現場を目の当たりにし、このときの光景、すなわち縊死した母親の失禁、脱糞の衝撃が、深いトラウマとなって、今回の事件にきわめて重要な影を落としている、と考えられている。 事実を無視した不当死刑判決 〇二年三月の控訴審判決は「無期懲役」。これでは収まらない被害者と検察そして右派言論。「判例違反・量刑不当」を掲げ、「死刑」のみを求めて異例の上告をした。そして彼らによる被告、弁護団への総攻撃が始まったのだ。
あくまで「例外」として慎重に選択されたはずの死刑判決。今回の差し戻し控訴審判決は、それを事実上「原則」に一八〇度転換した。高かったハードルが一気に引き下げられた。「凶悪犯罪を起こせば、例外なく死刑になる」――歴史を塗り変える重い判断が下された。われわれはこの不当判決に、厳重に抗議する。
警察、検察、裁判所。国家権力は、少年法改悪・死刑拡大に向けて、こうした事件を最大限利用している。前法相鳩山邦夫は、就任以来十三人という、歴代法相のなかでも突出した数の死刑執行を繰り返してきた。来年五月の裁判員制度実施を見据えた布石が、着々と打たれている。即決・重刑極刑判決へむかう裁判の流れは、人権無視、問答無用の戦時司法へと逆行する流れである。
闇に葬られる真実に光を当てようとする弁護士たち。事件の真相が本書で、克明に明かされている。上告審の闘いは、始まったばかりだ。 (佐藤隆)
| 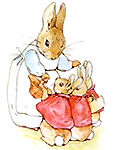
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。