�@�@�@�W���[�i���X�g�E��Ƃ̗��ԗ������@�I�@���L���e�[�}��ށ@�I
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԗ�����̃v���t�B�[���Ƃ́@�H
�iwww3.nhk.or.jp�F2021�N6��23�� 17��54���j
�c�����t�ސw�̂��������ɂȂ����ƌ�����u�c���p�h�����v���͂��߁A������Ȋw�A��ÂȂǕ��L���e�[�}�Ŏ�ނ�]�_�������s���Ă����W���[�i���X�g�Ńm���t�B�N�V������Ƃ̗��ԗ����A���Ƃ�4���A�}�����nj�Q�̂��ߖS���Ȃ�܂����B80�ł����B
���ԗ�����́A���a15�N�ɒ���s�Ő��܂�A������w�𑲋Ƃ������ƁA�o�ŎЂ̕��Y�t�H�ɓ��Ђ��܂����B
���Ђ���2�N�]��ŏo�ŎЂ𗣂ꂽ���Ƃ���ފ�����L���̎��M�𑱂��A���a49�N�Ɍ��E�̑�����b�������c���p�h���̋�������c��Ȏ����������ĒNjy�����u�c���p�h�����v�\���đ傫�Ȕ������ĂсA�c�����t���ސw���邫�������ɂȂ����ƌ����Ă��܂��B
���̌���s������_�ƓO�ꂵ����ނ����Ƃɂ������|���^�[�W�������X�Ɣ��\���A�����e�[�}�����������łȂ��A�Ő�[�̉Ȋw���ÁA�F����]���ȂǑ���ɂ킽��A�u�m�̋��l�v�Ə̂���܂����B
����7�N����͓�����w�̋q�������߂ă��j�[�N�ȍu�`�ő����̊w�������Ɋw�т̑����`���A�e�n�̑�w�ł��u������ȂǎႢ����̈琬�ɂ��͂𒍂��ł��܂����B
����19�N�ɂ͂ڂ������������������Ƃ����\���A�a�C�⎀���e�[�}�ɂ�����i�̎��M��h�L�������^���[�ԑg�̐���ɂ��g����Ă��܂����B
�Ƒ��ɂ��܂��ƁA���Ԃ���͓��A�a��S���a�Ȃǂ�����ē��މ@���J��Ԃ������Ƌ��m�̕a�@�œ��@�𑱂��A4��30���A�}�����nj�Q�̂��ߖS���Ȃ����Ƃ������Ƃł��B80�ł����B
�Ƒ���HP�ŏڍׂ����\
���ԗ����S���Ȃ������Ƃɂ��āA�Ƒ���23�����A���Ԃ���̋����q���^�c����T�C�g�ɏڍׂ����\���܂����B
����ɂ��܂��ƁA���Ԃ���͂��Ƃ�4��30���̌ߌ�11��38���A�}�����nj�Q�̂��ߖS���Ȃ�܂����B
�S���Ȃ�܂ł̂������ɂ��ẮA�u���N �ɕ��A���A�a�A�������A�S���a�A����Ȃǂ̕a�C���������A���މ@���J��Ԃ��Ă܂���܂����B��N�O��w�a�@�ɍēx���@���܂������A�{�l�������A���ÁA���n�r���������ۂ������߁A���m�̕a�@�ɓ]�@���܂����v�Ɛ������Ă��܂��B
���̕a�@�ŗ��Ԃ���́u�a��̉�ϋɓI�Ȏ��ÂŖڎw���̂ł͂Ȃ��A�����ł��S�g��Ԃ��ŁA��ɂ��Ȃ������ł���悤�Ɉێ����Ă����v�Ƃ����@���̍l���̂��Ƃœ��@�𑱂��A4��30���̖�ɊŌ�t���ُ�������ĉ@���ɘA�����Ƃ������̂́A������҂����ɋ}�������Ƃ������Ƃł��B
���V�͉Ƒ��݂̂Ŏ���s�����Ƃ������Ƃł��B
�����|���C�^�[�̊��c�d����u�ꎞ�����������C�^�[�v
�������C�^�[�Ƃ��Ďd���Ō𗬂̂��������|���C�^�[�̊��c�d����́u�G�b�Z�[�̘A�ڂ��Ȃ������̂ŕa�����Ȃ��Ă���̂��ȂƎv���Ă��܂������A���ɖS���Ȃ��Ă��܂����̂��Ƃ������S������܂��B��������������C�^�[�ŁA���ł͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����w���|���C�^�[�x�ƌĂ�鑶�݂�1�l�ł����v�ƐU��Ԃ�܂����B
���̂����ŁA���Ԃ���̌��тɂ��āu�Ⴂ������Â萫�ŁA���̐��i���c��ȗʂ̃f�[�^�̕��͂����w�c���p�h�����x�ݏo�������͂ɂȂ����̂ł͂Ǝv���܂��B
���L���W�������ɊS�������Ď�����O��I�ɒ��グ�A���ɂ͎�ރ`�[��������Ă��̗͂����W�����闧�Ԃ���̍D��S�Ƒ����͂͌��o���Ă���A�ނ̂悤�ȑ��݂͂���܂ł��Ȃ��������A���ꂩ����o�Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�܂��Ɉꎞ�����������C�^�[�ł����v�Ƙb���Ă��܂����B
���W���[�i���X�g�E�c������N����F�u�������̃W���[�i���X�g�v
���Ԃ���Ɛe�����������W���[�i���X�g�̓c������N����́A���Ԃ����Y�t�H�Łu�c���p�h�����v�\�������Ƃɂ��āu�����A�c���p�h�������������s���Ă������Ƃ͑��̕@�ւ��m���Ă��āA�c���p�h���g���A�ǂ������̂��Ƃ������Ȃ��Ǝv���Ă����B
���t�ŋL�����o�����Ƃ��A�ǂ��̐V�����������A���̌�A�c���p�h���J�����ƂɂȂ������{�O�����h������ł̉�����������ɁA���߂ē��{�̐V�������v�ƐU��Ԃ��������Łu����������������O�̎���ɑ̂��āA�������ŏ������B
���{�ɂ́A�Ȃ��Ȃ��������̃W���[�i���X�g�͂��炸�A���������炢�Ǝv���v�Ɨ��Ԃ�����������܂����B
�c������́A���Ԃ��u�c���p�h�����v�\���������A�e���r�̃f�B���N�^�[�����Ă��āA�����ɂ͂���قNJS�͖��������ƌ������Ƃł����A���Ԃ���̔��\�����������ŁA���̒����c���p�h�̃o�b�V���O��F�ɂȂ钆�A�c�����g���c���p�h�ɂ��Ē��ׁA�����ƂƂ��Ă̂��������L�����_�l��ɒ������_�Ŕ��\���邱�ƂɂȂ�A���������o�܂�������Ԃ���Ƃ́u�߁X�A�c���p�h�_���ꏏ�ɖ{�ŏ������v�Ƙb���Ă����Ƃ������Ƃł��B
���̂����ŁA���Ԃ����c���������Ă��������̐��E�ɂ��āu���̍��́A�����̎x������������Γ}�����}���牴�����Ƃ������[�h�����������A���܂͂��ꂪ��܂��Ă���B������ᔻ���邾���łȂ��A���{���ǂ�����̂��A�Ƃ����C�T�������������Ƃ�W���[�i���X�g���o�Ă��Ăق����v�Ƙb���Ă��܂����B�\�ȉ��ȗ��\
���}�����nj�Q�Ƃ́@�H
�iwww.msdmanuals.com ��蔲���E�]�ځj
�}�����nj�Q�́A���������ˑR�ӂ�����i�ǁj���Ƃɂ���ċN����܂��B�ǂ̈ʒu�Ɨʂɉ����āA�s���苷�S�ǂ��S������i�S�؍[�ǁj���N����܂��B
�}�����nj�Q�ǂ���ƁA�ʏ�͋����̈�������ɂ݁A����A��J�Ȃǂ��N����܂��B
�}�����nj�Q���N�����Ǝv������A�܂��~�}�Ԃ��Ă�ł���A�A�X�s�����̏��܂����ݍӂ��ĕ��p���܂��B
�a�@�ł͐S�d�}�����ƌ��t���̕����𑪒肷�錟���ɂ��A�}�����nj�Q���ǂ�����f�f���܂��B
���Ö@�͏nj�Q�̎�ނɂ���ĕς��܂����A�ʏ�͕ǂ��N�������ʂ̌����𑝂₷���u���s���܂��B
�i�����������̊T�v���Q�Ƃ̂��ƁB�j
�č��ł́A���N90���l�ȏ�̐l���S������܂��͐S���ˑR�����N�����Ă��܂��B�܂��A�}�����nj�Q�ɂ�薈�N��40���l�����S���Ă��܂��B���̂قڑS���Ɋ�b�����Ƃ��Ċ������̕a�C���݂��A��3����2���j���ł��B
�i�Q�l�����j
�����ԗ�����̃v���t�B�[���Ƃ́@�H
�i�E�B�L�y�f�B�A��蔲���E�]�ځj
���� ���i������ �������A�{���F�k ���u�@1940�N�i���a15�N�j5��28�����܂�B 2021�N�i�ߘa3�N�j4��30�����S�B80�B�j�Ƃ́A���{�̃W���[�i���X�g�A�m���t�B�N�V������ƁA�]�_�ƂŗL��B���M�e�[�}�́A�����w�A�����A��ÁA�F���A�����A�o�ρA�����A�N�w�A�Վ��̌��ȂǑ���ɂ킽��A�����̒������x�X�g�Z���[�ƂȂ�[1]�B���̗ނȂ��m�I�~���L������ɋy���Ă���Ƃ��납��u�m�̋��l�v�̃j�b�N�l�[��������[2]�B�܂��剺�p���ƕ��сu�m�̗������v�ƕ]���ꂽ�B
1974�N�A�����w���Y�t�H�x�Ɂu�c���p�h�����`���̋����Ɛl���v�\���A�c���p�h���r�̂������������A�W���[�i���X�g�Ƃ��ĕs���̒n�ʂ�z���B2007�N���A�N������̎�p���邪�A���̌�����E�̍őO���̌����҂�������ނ��A����̐��̂������I�Ɍ��ߒ��������𑱂���[3][
������
���������F1940�N�A���茧����s�ɐ��܂��B���͒���̏��w�Z���t�Ō�ɕҏW�҂߁A��͉H�m���Ǝq�̐M��҂ŁA�N���X�`�����̉ƒ�B��O�̉E���v�z�ƁE�k�F�O�Y�́A���̂��Ƃ��ɓ�����B1942�N�i���a17�N�j�A���������ȐE���Ƃ��Ėk���̎t�͊w�Z���Z���ƂȂ������߁A��ƂŒ��ؖ����֓n��B
1946�N�A�����g���œ��{�֖߂�A�ꎞ����̈��S�߉ϐ��ɏZ�݁A�̂��ɕ��̋�����錧���ˎs�Ɉڂ�B���t�͊w�Z�i����w�j�������w�Z�A���w�Z���o�āA1956�N�i���a31�N�j�ɐ��ˈꍂ�A����ɐ�t���Ɉڂ������ߓ����s����썂���w�Z�ւ̓]�����o��B���w�Z���ォ��Ǐ��ɔM�����A����̓Ǐ������L�������͂��c���Ă���[5]�B�܂��A���w����͗��㋣�Z�ɂ��M���B�o�D�̔~�{�C�v�E���[�^�[�W���[�i���X�g�̓��厛�L�P�͒��w����̐�y�ł���A�O�l�Ƃ����㋣�Z�I�肾�����B
1959�N�i���a34�N�j�A������w���ȓ�ނ֓��w�B�݊w���͏����⎍�������A�C�M���X�ŊJ���ꂽ�������֎~���E��c�ɎQ���B���Ƙ_���̓t�����X�̓N�w�҃��[�k�E�h�E�r�����B
���G���L�҂Ƃ���
1964�N�i���a39�N�j�A������w���w���t�����X���w�ȑ��ƌ�A���Y�t�H�ɓ���[2]�B��g���X��NHK�̎����������s���i�������Ƃ���[6]�B���Ќ�͊�]�ʂ�w�T�����t�x�ɔz�������B��i�ɒ�Ă������B��y�L�҂̓����ŁA���w�N���ォ���]�m���t�B�N�V�����𗔓ǂ��đ���ȉe�����邪�A�����Ƃ���肽���Ȃ��v���싅�̎�ނ�������ꂽ���Ƃ���3�N���炸�ŕ��Y�t�H��ގ�[7]�B
1967�N�i���a42�N�j�A������w���w���N�w�ȂɊw�m���w�B��68�N�ɓ��啴�����u�����x�Z�ƂȂ�B
�����|���C�^�[�Ƃ���
������w�x�Z���ɁA���t����̒��Ԃ̗U���ŕ��M�����ɓ��胋�|���C�^�[�Ƃ��Ċ������J�n����B�n�����̎G���w���N!�x�Ɂu�����w�v���v�A�u�F���D�n�����v�A�u�Ζ��v�Ȃǂ��e�[�}�Ƃ��ăm���t�B�N�V������]�_�������B1968�N�A�u���ԗ��v�̃y���l�[���ŕ��Y�t�H�������u�f��ł̂��オ�����j�����v�\�����B
�w���N!�x�̏���ҏW���c�����܁i��́w���Y�t�H�x�ҏW���j�Ƃ̌�F����́u�p�h�����v�Ɍq����B1969�N�A�w���Y�t�H�x��w�T�����t�x�Ɂu60�N���ۉp�Y�̉h���ƔߎS�v�A�u����Q�o���g�nj�^�v�A�u���̉ʂĂ��Ȃ��f��v�A�u�����E�R�{�`���ƏH�c����v�Ȃǂ\[8]�B1970�N�A���啴�����̊w��x�����������w�����ƏՓˁB����N�w�Ȃ𒆑ށB
�f�r���[��w�v�l�̋Z�p�x�ŁA�u�l�Ԃ͐i���Ƃ����T�O��ӖړI�ɐM�������Ă���v�Ƃ��āA���Ԋw�Ɋw�Ԏv�l�@���I�B�����̎��R�͏�ɋ�̓I�ŁA�����ɕ��G�����l�ŁA�����ɂ͑���s�\�̂��́A�܂萔�ʉ��ł��Ȃ��v�f�����������Ă���B�����̓��_�ƃ����ɖ��������Ă��邪�A����ɑ��āA�l�Ԃ̍�������̂́A�����Ȃ����_�Ȃ��A���ɃX�b�L���ƁA�����I�ɂł��Ă���B
���Ȃ���A���R�̍����̂��A�l�Ԃ̍�������̂̕����A�͂邩�ɏ㓙�Ȃ��̂ł��邩�̂悤�Ɍ����邪�A����͐l�Ԃ̉��l�ς̋����ɂق��Ȃ�Ȃ��B
���_�͏�ɏ����Ȃ��̂��������A�Z�p�͂��̂������ɑ��삷��K�v��A���Ȃ菃�x�̒Ⴂ���̂܂ň����B�����Ō����Ă���M���b�v���A�����闝�_�Ǝ��H�̃M���b�v�ł���A�Z�p�̖ʂł́A���Q�Ȃǂ̖��Ƃ��Č����B
���R�E�ɂ́A�����̂ɂ��A�����Q�W�ɂ��A����ɂ͐��Ԍn�S�̂ɂ��A�ڂɌ����Ȃ��z���I�X�^�V�X�ێ��@�\�������Ă���B�����ɂ������Ă���̂͂��̓_�ŁA�i���Ƃ����T�O���A�ӖړI�ɐM���Ă������䂦�ɐ��܂ꂽ���ׂł���A�Ƃ����{�I�ȍl���\���Ă���[9]�B
�u�K���K���`���A�v�̊Ŕi�E���j�i�ԉ���Ԓʂ�̌�������B�e�j
�����̗F�l�Ǝ������o�������A�V�h�S�[���f���X�Ƀo�[�u�K���K���`���A���ԁv���I�[�v��������[10]�B���̃o�[�ł͌o�c�����łȂ��A�o�[�e���_�[�Ƃ��ăJ�E���^�[�ɂ����������A�E�o�ŋƊE�̒m�荇�����q�Ƃ��ĖK���悤�ɂȂ�u����Ȃ�ɖׂ������v[10] �Ƃ����B�ҏW�҂̐��F����f����Ƃ̃u���X�E�y�h�����b�e�B����A�q�Ƃ��Ēʂ��Ă���[10]�B�̂��Ƀy�h�����b�e�B���V�h�S�[���f���X���e�[�}�ɂ���OV�w�t�F�X�N�E���h���x���B�����ۂɂ́A�o�[�̓X��Ƃ��ďo�����Ă���[11]�B�o�[���o�c���Ă����̂�1971�N�O�ゾ���A�X���̂͌��݂��c���Ă���[10]�B
1972�N�A�u�k�Ђ̐��F���i�̂��́w�T������x�ҏW���j�̏Љ�ŃC�X���G�����{�̏��҂�����2�T�ԃC�X���G���ɑ؍݁B���Ҋ��ԏI����͎���Œ����e�n�A�n���C�E�G�[�Q�C�𒆐S�Ƃ������[���b�p��������Q����B���Q���Ԓ��ɋ��R�e���A�r�u�����������B���啴���Ȍ㒆�f���Ă����W���[�i���X�g���������n�ōĊJ�����B�\�ȉ��ȗ��\
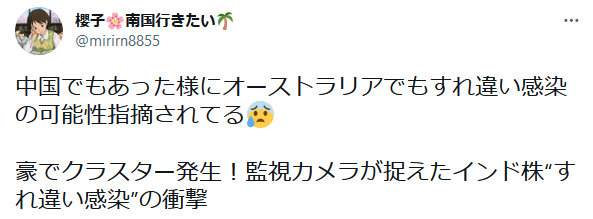
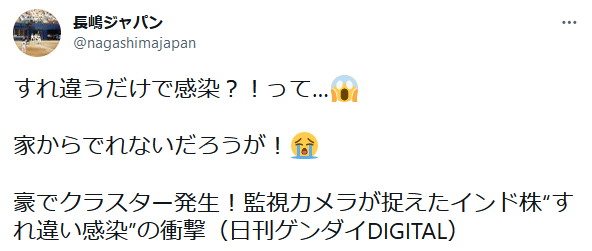


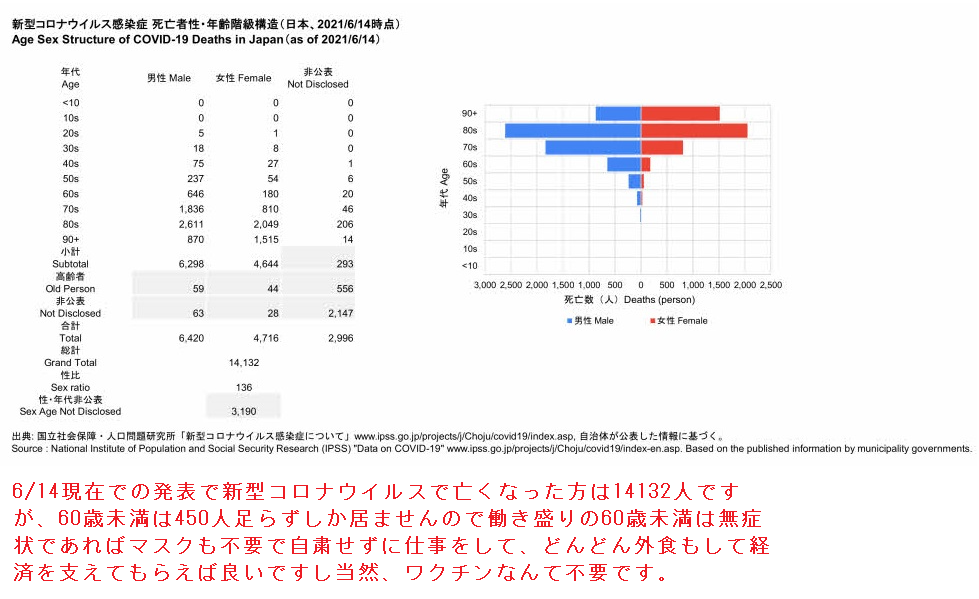



 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B