�߉q��t��
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%A1%9B%E4%B8%8A%E5%A5%8F%E6%96%87
�߉q��t���́A�����m�푈������1945�N�i���a20�N�j2��14���ɁA�߉q���������a�V�c�ɑ��ďo������t���B
�w�i
1945�N1��6���A�A�����J�R���t�B���s���E���\�����㗤�̏��������Ă���Ƃ̕���āA���a�V�c�͓���b�،ˍK��ɏd�b�̈ӌ������Ƃ����߂��B�،˂͗��C�������Ɗt���̏��W�����߁A�܂��A�߉q���،˂Ɉ��������߂Ă����B�،˂Ƌ{����b�̏����P�Y�Ƃ����c���A�d�b�炪�X�ɔq�y���邱�ƂɂȂ���[1]�B�����͖،˂��s���A�R�����h�����Ȃ��悤�ɔ閧���ɍs��ꂽ[2]�B�\�����͏d�b���V�@���f����Ƃ������ڂł���A�،˂��c�������L�ɂ��{���̖ړI�͋L����Ă��Ȃ��B
�d�b��͈ȉ��̏��ŏ��a�V�c�Ɉӌ����q�ׂ��B�d�b�̓��A�ē������i�C�R��b�j�A�����M�s�i���N���j�͌��E�ɂ��邽�ߏ��W����Ă��Ȃ�[3]�B
2��7�� - �����u��Y
2��9�� - �L�c�O�B
2��14�� - �߉q����
2��19�� - ����X���Y
���� - �q��L�� �i������b�j
2��23�� - ���c�[��
2��26�� - �����p�@
��t�̑O�A�߉q�͏����グ���u�߉q��t���v�������ċg�c�Γ@��K�ꂽ�B�g�c������ɋ������A�q��L���ɂ������邽�߂Ɏʂ����Ƃ������A�g�c�@�̏����Ƃ��̐e�ނ𖼏�鏑���̓X�p�C�ł���A�ʂ����������ɘR�ꂽ���߂ɋg�c�͍S������A���̑��߉q���ӂ̐l�������X�ƁA�߉q�������܂�z�����˂Ď撲�ׂ��邱�ƂƂȂ�B2�l�̃X�p�C�́A�g�c�S����͋߉q�@�̏����ɓ��蓐�����s���Ă����Ƃ����B
�߉q�̏�t�ƌ䉺��
1945�N2��14���̒��A�،˓���b�����]�����Ɏp�������A���c�������]���ɁA
�u���c����A�����̋߉q���̎Q���́A���Ɏ��������Ăق����B�߉q���́A���Ȃ����悭���������Ă��Ȃ��B����Ŏ��]���̎������C�ɂ��āA�b���\���ɂł��Ȃ��ƍ���B�ЂƂ�O�ŋ߉q���̎v���ʂ�ɘb�������Ă݂����v
�Ɨv�������B���c���]���͉������A�،˂Ƌ߉q�̓�l�����a�V�c�ɔq�y���A�ȉ��̏�t������悵��[4]�B
��ǂ̌������ɂ��l�ӂ�ɁA�ň��Ȃ鎖�Ԃ͈⊶�Ȃ���ő��K���Ȃ�Ƒ������B�ȉ��O��̉��ɐ\�ギ�B
�ň��Ȃ鎖�Ԃɗ����邱�Ƃ͉䍑�̂̈����������ׂ����A�p�Ă��o�_�͍������̏��������̂̕ύX�Ɩ��͐i���炸�i�ܘ_�ꕔ�ɂ͉ߌ��_����B���A�����@���ɕω������͑��f����j�����čň��Ȃ鎖�ԏ�Ȃ���̏�͂��܂ŗJ�ӂ�v�Ȃ��Ƒ����B���̌쎝�̗�����ł��J�ӂׂ��́A�ň��Ȃ鎖�Ԃ����V�ɔ����ċN�邱�Ƃ���ׂ����Y�v���Ȃ�B
���v���ɉ䍑���O�̏�͍��⋤�Y�v���Ɍ����ċ}���ɐi�s������Ƒ����B�������O�ɉ��Ă͑h���ُ̈�Ȃ�i�o�ɔV�Ȃ�B�䍑���͑h���̈Ӑ}��I�m�ɔc�������炸�B�ނ̈��O�ܔN�l�������p������i�v����p�̗p�ȗ��A��ɍŋ߃R�~���e�������U�ȗ��A�ԉ��̊댯���y������X�������Ȃ邪�A����͔瑊�����ՂȂ鎋���Ȃ�B�h���͋��ɂɉ��Đ��E�ԉ����̂Ă��邱�Ƃ́A�ŋ߉��B�����ɑ���I���Ȃ�����ɂ�薾�ĂƂȂ���鎟��Ȃ�B
�h���͉��B�ɉ��đ����ӏ����ɂ̓\�r�G�b�g�I�������A���]�̏����ɂ͏����Ƃ��e�h�e����������������Ƃ��Ē��X���̍H���i�߁A���ɑ啔�������������錻��Ȃ�B
���[�S�[�̃`�g�[�����͑��̍œT�^�I�Ȃ��̕\���Ȃ�B�g���ɑ��Ă͗\�߃\�����ɏ�������g�������җ����𒆐S�ɐV�������������A�݉p�S����������Ƃ������肽��B���n��A�u�嗘�A䎗��ɑ���x�����������ɁA�����s���̌����ɗ������q�b�g���[�x���c�̂̉��U��v�����A���ۏ�\�r�G�b�g�����ɂ��炴��Α��݂������邪�@�����v���B�C�����ɑ��Ă͐Ζ������̗v���ɉ�������̌̂��Ȃē��t�̑����E�����v����B�������\���Ƃ̍����J�n���c����ɑ��A�\���͐������{���ȂĐe�����I�Ȃ�ƂĈ�R���A�V���ׂߊO���̎��E��]�V�Ȃ������߂���B
�āE�p��̉��̃t�����X�A�x���M�[�A�I�����_�ɉ��ẮA�ΓƐ�ɗ��p���镐���I�N�c�Ɛ��{�Ƃ̊Ԃɐ[���Ȃ铬���������A���������͉���������I��@�Ɍ���������B�����ĔV�������c���w����������͎̂�Ƃ��ċ��Y�}�Ȃ�B �ƈ�ɑ��Ă͔g���ɉ�����Ɠ������A���ɏ������鎩�R�ƈ�ψ���𒆐S�ɐV��������������Ƃ���Ӑ}����ׂ��A�V�͉p�ĂɂƂ荡�͓��ɂ̎�Ȃ�Ǝv�͂�B
�\���͂����̔@�����F�����ɑ��A�\�ʂ͓����s���̗���������A�����ɉ��Ă͋ɓx�̓��������Ȃ��A����������e�\�I�����Ɉ������Ƃ�����B�\���̍��̈Ӑ}�͓����ɑ��Ă������l�ɂ��āA���ɉ����ɂ̓��X�R�[��藈��鉪��[5]�𒆐S�ɓ��{��������g�D�����A���N�Ɨ������E���N�`�E�R�E��p��(�ꎚ��)�����ƘA�g�����{�ɌĂт��������B�z���̔@���`����萄���čl�ӂ�ɁA�\���͂₪�ē��{�̓����Ɋ��������댯�\������Ǝv�͂�i�����Y�}���F�A���Y��`�ғ��t�|�h�S�[�����{�A�o�h���I���{�ɗv������@���|�A�����ێ��@�y�h������̔p�~���j�B
�ʂč���������ɋ��Y�v���B���̂�����������X��������s���ς���B���������̋��R�A�J���Ҕ������̑���A�p�Ăɑ���G���S�V�g�̔��ʂ���e�\�C���A�R�����ꖡ�̊v�V�^���A�V�ɕ֏悷�鏊���V�����̉^���A�y�A�V��w���葀�鍶�����q�̈Ö����Ȃ�B
���s�R�l�̑����͉䍑�̂Ƌ��Y��`�͗���������̂Ȃ�ƐM��������̂̔@���A�R�����v�V�_�̊���������ɂ���B�c�����̒��ɂ����咣�Ɏ����X�����������Ƙ������B
�E�ƌR�l�̑啔���͒��ȉ��̉ƒ�o�g�҂ɂ��đ��̑����͋��Y�I�咣�������Ղ������ɂ���B���ޓ��͌R������ɉ��č��̊ϔO��͓O��I�ɒ@�����܂ꋏ����ȂāA���Y���q�͍��̂Ƌ��Y��`�̗����_���ȂĔޓ����������Ƃ�������̂Ǝv�͂�B
�}�X���F���ρE�x�ߎ��ς��N���A�V���g�債�A���ɑ哌���푈�ɖ����������́A�����R�����ꖡ�̈ӎ��I�v��Ȃ肵���ƍ��▾�ĂȂ�Ǝv�͂�B
���F���ϓ����A�ޓ������ς̖ړI�͍����v�V�ɂ���ƌ�������͗L���Ȃ鎖���Ȃ�B
�x�ߎ��ϓ����u���ς͉i�������X���B���ω����������v�V�͏o���Ȃ��Ȃ�v�ƌ��������͍��̈ꖡ�̒��S�I�l���Ȃ肫�B
�����R�����ꖡ�̊v�V�_�̑_�Ђ͕K���������Y�v���ɔƂ�����A������Ƃ芪���ꕔ�����y���ԗL�u�i�V���E���Ɖ]�����A�����Ɖ]�����A�����E���͍��̂̈߂𒅂����鋤�Y��`�҂Ȃ�j�͈ӎ��I�ɋ��Y�v���ɖ������Â��Ƃ���Ӑ}��������A���q�P���Ȃ�R�l�V�ɗx�炳�ꂽ��ƌ��đ�߂Ȃ��Ƒ����B���̎��͉ߋ��\�N�ԁA�R���E�����E�E���E�����̑����ʂɘi���F��L�����s�т��ŋߐÂ��ɔ��Ȃ��ē��B�����錋�_�ɂ��āA���̌��_���ɂ����ĉߋ��\�N�Ԃ̓������Ƃ�����Ƃ��A�����Ɏv�Г���߁X���鑽���������鎟��Ȃ�B
�s�т͍��̊ԓ�x���g�t�̑喽��q�����邪�A�����̑������C������o����䂯�����v�V�҂̎咣���̂����ċ�����v�̎���������Əŗ����錋�ʁA�ޓ��̔w��ɐ��߂�Ӑ}���[���Ŏ悷��\�͂��肵�́A�S���s���̒v�����ɂ��āA���Ƃ��\��Ȃ��[���ӔC�������鎟��Ō�����܂��B
������ǂ̊�}��������Ƌ��Ɉꉭ�ʍӂ����Ԃ̐�����ɐ��͂����ւ���B������咣���Ȃ��҂͏����E���җ��Ȃ���A�w����V�����������́A�V�ɂ��č����������Ɋׂ�A���Ɋv���̖ړI��B����Ƃ��鋤�Y���q�Ȃ���ɂ����B
����ɉ��ēO��I�p�Č��ł����ӂ锽�ʁA�e�\��C�͎���ɔZ���ɂȂ����l�Ɏv�͂�B�R���̈ꕔ�ɂ͂����Ȃ�]���ЂĂ��\���Ǝ������ׂ��Ƃ��֘_������̂���B�������Ƃ̒�g���l������҂�����Ƃ̂��ƂȂ�B
�ȏ�̔@�����̓��O��ʂ����Y�v���ɐi�ނׂ�������D������������Ɛ���������B�����ljv�X�s���Ƃ��Ȃ���`���͋}���ɐi�W�v���ׂ��B
��ǂ̑O�r�ɂ����������~�ł��ŊJ�̗�����Ɖ]�ӂȂ�Ίi�ʂȂ�ǁA�ň��̎��ԕK���̑O��̉��ɘ_����A�����̌����Ȃ��푈��V�ȏ�p�����邱�Ƃ͑S�����Y�}�̎�ɏ����̂Ɖ]�ӂׂ��A�]���č��̌쎝�̗����肷��A��������ɐ푈�I���̕��r���u���ׂ����̂Ȃ�Ɗm�M���B�푈�I���ɑ���ő�̏�Q�͖��F���ψȗ������̎��Ԃɖ����ǂ𐄐i�����肵�R�����̔ނ̈ꖡ�̑��݂Ȃ�Ƒ������B�ޓ��͛߂ɐ푈���s�̎��M�����Ћ�����A�����̖ʖڏ�A�N����R�𑱂�����̂Ǝv�͂�B�Ⴕ���̈ꖡ����|�������đ��}�ɐ푈�I���̎��ł��́A�E�������̖��ԗL�u�ꖡ�Ƌ������č����ɑ卬������N���A�����̖ړI��B�����邱�Ɣ\�͂���Ɏ���|�ꂠ��B�]���Đ푈���I������Ƃ��A�悸���̑O��Ƃ��č��̈ꖡ�̈�|���̗v�Ȃ�B���̈ꖡ���ֈ�|������A�֏�̊����E�E���E�����̖��ԕ��q���e����ނ�Ȃ��B�W���ޓ��͖�����Ȃ鐨�͂����������炸�A�R���𗘗p���Ė�]��B����Ƃ���҂ɊO�Ȃ炴�邪�̂Ȃ�B�̂ɑ��{���ĂΎ}�t�͎���͂����̂Ȃ�Ǝv�ӁB
���V�͏��X��]�I�ϑ����͒m�ꂴ��ǂ��A���������ꖡ����|����鎞�́A�R���̑��e�͈�ς��A�p�ċy�d�c�̋�C�͈��͊ɘa����ɔ邩�B�����p�ċy�d�c�̖ڕW�́A���{�R���̑œ|�ɂ���Ɛ\��������A�R���̐��i���ς�A���̐����܂�A�ޓ��Ƃ��Ă��푈�p���ɂ��l������l�ɂȂ�͂�����Ǝv�͂�B
����͓e���p�Ƃ��āA���̈ꖡ����|���R���̌��������s���邱�Ƃ́A���Y�v�������{���~�ӑO��挈�����Ȃ�A���̌�E�f�������]�܂����������B
�ȏ�\��������_�ɂ��ԈႦ����_����Ή����䎶�����x���B
— �߉q�����A[6]
�،˓��{�̃��������ɓ��c�������]���͉��L�̂悤�ɒԂ��Ă���B
�߉q���͏I���O��Ƃ��ďq�ׂĂ������A�@���ɂ��ďI��Ɏ��ǂ��ڂ��̂��̋�̓I�ȕ���ɂ��Ă͐��Ă������Ă����Ȃ������悤���B�������Y�v���̋��Ђ��A���t��s�����ďq�ׁA���̎�͂ɂȂ��Ă���̂����Ȃ�ʌR���̈ꖡ�ł���Ǝw�E����̂ł���B�ꖡ�Ƃ͈�́A�N���w���̂ł��낤���B�É����A���̋߉q���̋c�_�ɂ́A���S�ł��̓��ق��ɋ����ꂽ���l�q���M����B
— ���c�����A[7]
���a�V�c�͂����ɋ߉q�䉺�₵�Ă���B
�i�䉺��j�䍑�̂ɂ��Ă͋߉q�̍l���Ƃ͈ق�A�R���́A�č��͉䍑�̂̕ϊv�����l����l�ϑ������邪�A���̓_�͔@���B
�i�䓚�j�R���͍����̐�ӂ��V�g�����ނ�ׂ߂ɂ������]�ւ�Ȃ��ƍl�ւ���B�O���[�̖{�S�͍��ɂ��炸�ƐM���B�O���[��g���C�̍ہA�����{�̌�g�ɑ����g�v�Ȃ̑ԓx�A���t�����݂Ă��A��c���ɑ��Ă͏[���Ȃ�h�ӂƔF����L���ƐM���B�A���č��͗`�_�̍��Ȃ�A�����ǂ̔��W�@���ɂ��Ă͏����ω��Ȃ��Ƃ͕ۏ������B�V�푈�I����̎��}�ɍu����̗v����ƍl�ӂ�d�v�Ȃ�_�Ȃ�B
�i�䉺��j����̘b�ɏl����K�v�Ƃ���Ƃ̂��Ƃł��������A����ڕW�Ƃ��ďl�R����Ɖ]���̂��B
�i�䓚�j��v�z����B�V��ڕW�Ƃ��B
�i�䉺��j�l���̖��Ɍ��ǂȂ邪�A�߉q�͂ǂ��l�ւċ��邩�B
�i�䓚�j����͕É��̌�l�ցc�c�B
�i�䉺��j�߉q�ɂ�����Ȃ��l�ł͒��X����Ǝv���B
�i�䓚�j�]���R�͉i����̎v�z�̉��ɐ��i���������̂ł���܂����A�V�ɑ��Ă͖���ɔV�ɔ������肵�҂�����܂��̂ŁA���̕����N�p���ďl�R�����ނ�������Ȃ�ƍl�ւ��B�V�ɂ͉F�_�A�����A�^��A�����A�Ό��̍��̎O�̗��ꂠ��B�V�����N�p����Γ��R���C�傷�B�l�֗l�ʼn������͖��C������̂Ƃ���A���۔V�������邱�ƂȂ��f�s���邱�Ƃ���Ȃ邪�A�Ⴕ�V��G�O�ɂĎ��s����̊댯���l������Ƃ��A����E�R�����叫�̒����N�p�������ĂȂ��B��ʕ����E���c���Ɖ�����ۂɂ����̘b�o����B��z�{�a���͌R�̌����ɂ͎R���叫���K�C�ƌ�l�ւ̗l�Ȃ�B
�i�䉺��j������x��ʂ������Ă���łȂ��ƒ��X�b�͓���Ǝv�ӁB
�i�䓚�j�����]����ʂ�������ΐ��Ɍ��\�Ǝv�͂�܂����A�����]��������������܂������B�V���߂������Ȃ炴��ׂ��炸�B���N�A��N��ł͖��ɗ��܂��Ǝv�Ђ܂��B
— �䉺��:���a�V�c�A�䓚:�߉q�����A[8]
���
���a18�N1���A�߉q�����͎Q�l�Ƃ��Ė،˂ɏ��Ȃ𑗂�u�R�����̈���c�ɂ��l�Ă���ꂽ�鏊���v�V����̑S�e���ŋߌ���@�����B�ܘ_�����S�e��I�悷��ɂ͎��炸��嫁A���X�ɍI���ɏ��o���ɒ��X�����̓�����i�݂��邪�@���v�ƍ�����[9]�B�����ē��N3��18���A�߉q�́A�����R���C�R�叫�����O���ɏ������B
�������Ƃ̍U����킪���E�ɒB���ĕ���������n�߁A����ɔ����������t�ɑ���M���������ނ��A�ꕔ���҂̊Ԃł́A�����p�@�̍X�R�̕K�v����������钆�A�g�c�Ƌ��ɑ����u�a����Ă������ё叫�́A������nj��̈�l�Ƃ��ĕ��サ�Ă����B
�߉q�́A��k�����ɗ��R�����w����������Ƃ����ȉ��́w���Ɗv�V�̉A�d�x[10]��ł������A���ё叫�ɁA��p��ǂ������u�Ԃɖ�����ꂽ�v���R�̊v�V�h�𑬂₩�ɏl�����邱�Ƃ�v�������̂ł���B
���B���ϔ����ȑO���Ό��Ύ��̓\�A�̕��w�T�����Y��`�̓쉺�����ꑁ���ɉ����ĔV�ɒɌ�����������ׂ��炸�ƍl���Ă����B�V���ׂɂ͉䂪���̌R�����Y������K�v�Ƃ���݂̂Ȃ炸�����̐������X�V��v���Ƃ��A�ނ̉e�̐l����{�萳�`�����ĎY�ƌ܃J�N�v��V�ɔ��������v�V��[11]����炵�߂��B���̓�Ă͒r�c���j�A����L���Y�N����ǂ����N���[���o����c�_���Ƃ��ċ����B
�Ό��͖��F���ςɂ͑��̑\�A�ς���傢�ɓw�߂����ꋤ�A�V���g�債�x�ߎ��ςɓ������@���l�����ɂ͔������B�V���ׂɒǂ��ĔӔN�s�U�ł��������A�ނ̍�炵�߂��Y�ƌ܃J�N�v��y�э����v�V�Ă͑��̘ԌR�ɕۊǂ���ċ����B�V���R�̐V�i�C�s�̓k���ǂ�ő傢�ɔV�ɋ����A���̏����V�l�T���v�V�h�̘A���ɋߕt���V�������̕������炵�߂��A�������̐V�l�̓��ɋ��Y��`�҂�����A�ޓ��͌R�𗘗p���đ��̗��z�������ƌ��ӂ���ɌR�̐V�i�Ɏ��������B������V�l�͓����悭���̗��_���ꉞ�𗝐��R�Ƃ��ċ���̂ŌR�̐V�i�͉����̊Ԃɂ��V�ɖ������A�����v�V��ڕW�ɁA�����đ��̎�i�Ƃ��Ē����푈����Ă�Ɏ������̂ł���B
���̖�����ꂽ�A���͎Q�d�{���������R�ȓ��ɑ����A���ɖk�x���ς̋N���������A�Q�d�{���͏�ɐ��{�̋ǒn�����ɓ��ӂ��A���̕��j�Ŏw�߂����̂����A���R�Ȃ��������v�V�h���o��̌R�ƒʖd���h���h�����ς��g�債���B�V�ɂ͗��h�ȏ؋�������B���A���@�ɋ���H�i�����̔@�����x�ߎ��ς𑁂����߂��Ă͍���Ɖ]���ė�����������B�v����ɗ��R�̐V�l�͍���̕K�v���S�����A�ƒf�Ő푈���g�債�A�V�Ɉ˂��č��Ɖ�����]�V�Ȃ������߂�ƌv�悵���̂ł���i�����j�B
�v����ɗ��R�̐Ԃɖ�����ꂽ�A���́A���{��R��]���̎w�������A���Âɐ�����g�債�p�A�ĂƂ̏Փ˂����݂炸���ɑ哌���푈�ɂ܂Œǂ�����Ŏd�������B���������̖ړI�͐푈���s��̕K�v���S�����A�䂪���̍����A������j�A�v�V�������Ƃ���̂ł���B���̈�h�̗����闤�R�ɏ������������Ă͍��Ƃ̑O�r�[�J�Ɋ����Ȃ��B
�|���ď����v�V�h�̒��j�ƂȂ��Ă闤�R�̘A���ׂČ���ƁA���������h�ɑ�����҂������r�A�^�蓙�̍c���h�̘A���͎�r�����͂��邪�����c���h�ō��̂̔j�͍l���ċ��炸�����̉]�������I�n��т��Ă�B�V�ɔ��������h�͖ړI�ׂ̈Ɏ�i��I���A���������X�Ɍ�p�҂�{���Ă���B�����ɔV���l�����Ȃ��ƍ��Ɗ낤���ł���B
���ё叫�́A�����̔��͂͑����̔C�ɂ��炴��|�������A���˂Ă�艪�c�[��C�R�叫���痤�R���Ɏz���̔@������ׂ������̂��鎖�𔖁X�����Ă���[12]�A�߉q������߂āu���R�����h�A�J�_�v������A�Ƃɂ��������푈���~�߂˂Ȃ�Ȃ��ƒɊ������̂ł�����[13]�B
���N4���A���쐳���Ƌ��ɓ�����ᔻ���Ă����O�c�����v��c�m�����O����K�₵�߉q�Ɖ�k�����B�O�c����1928�N�i���a3�N�j6����������Ȍx�ۋǁA�ȊǗ��ǂɋΖ����A�����^���̎���ɏ]�����Ȃ��獑�ۋ��Y��`�^���̒��������ɖv��������A�O�c�@��c�m�ƂȂ�A�掵�\�Z��鍑�c��O�c�@�̍��h�ۈ��@�Ĉψ���i���a16�N2��3���j�ł́A���{�̏�w�����펞�h���̐��̑傫�Ȕ������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��莋���ċ߉q�����B���A���Ԃ���댯������Ă����Ƃׂ̈ɓO��I�ɁA��O���̎v�z�d���A�o�ϖd���A�O��d���A�����d���A���ł��ł����낵���A���ӎ����ɔT���͑�O�҂̖d���̐��ɗx�炳�ꂽ�ӎ������钳��s�ׂɑ���x���Ǝ������������悤�ɐ��{�i��߉q���t�j�ɗv�����Ă���[14]�B
���O���̋߉q��K�₵���O�c���́A��ǂƐ��ǂ̏����ɂ��ė����Ȉӌ����q�ׁA�u���̐푈�͕K���s����B�����Ĕs��̎��ɗ�����̂͋��Y��`�v�����B���{������ȏ�Ԃɒǂ�����ł������݂̐ӔC�͏d�傾�I�v�Ƌ߉q���l�₵���Ƃ���A�߉q�͒��������݂��݂Ƃ������q�ŁA��ꎟ��߉q���t�����̂��Ƃ���z���A�u�Ȃɂ����������̍l���Ă������ƂƋt�Ȍ��ʂɂȂ��Ă��܂����B���Ƃ����Ɏ����ĐÂ��ɍl���Ă݂�ƁA���҂���Ɍ����Ȃ��͂ɑ����Ă����悤�ȋC������|�v�Əq������[15]�B
�߉q�����������R���ƎO�c�����v�ɍ����������Ƌy�юO�c���ƌx�����������ے��̐`�d��[16]���璮�悵�����ƂƓ�����|�̌x���Ɣ��Ȃ����a20�N2��14���ɂ͋߉q���珺�a�V�c�ɏ�t���ꂽ�̂ł���B
�O�c���́A�߉q��t�����u�߉q�������̌o���Ɣ��Ȃ��q�ׁA�������v����`�҂̃��{�b�g�Ƃ��Ė�炳�ꂽ�̂��ƍ���������́v�ƕ]��[17]�A�s���ɒ��N�ɂ킽�鎩���̒��������Ɛ����o���A�����Ď��������肵�����@�����A�߉q�����̃u���[���g���X�g���a������Ɍ��W���Ă������@�v�V��������ђ����V���Џo�g�̃\�A�X�p�C����G����O�ؐ��狤�Y��`�҂̐펞���̍D��I�Ȍ����Ǝv�z�A�]���Q�����A�\�A����уR�~���e�����̐��E�헪�Ɋւ��鑽���̏؋������Ɉˋ����āA�߉q��t���ɊY�������̓I��������U���A�߉q���t�̌R���O���������̔w��Ƀ\�A�̑Γ�����d�����������������Ƃ��w�E����[18]�B�O�c���̎����Ƙ_����1950�N3���Ɂu�푈�Ƌ��Y��`�|���a������^�v�i���吧�x���y��j�Ƃ��ďo�ł���A�n��P��i�ǔ��V���В��j�A�쌴�Ɂi���呍���j�A���c�F��i����c�呍���j�A����M�O�i���c���`�m��w�m���j�A�c���k���Y�i�ō��ٔ��������j�A�ђ˕q�v�i����R�@�����j�̎^���Ǝx�����B����͌�ɉ��R�i�v�ɂ���ĕ�������A�ӔN�̊ݐM��i���j�ɑ傫�ȏՌ���^����[19]�B
�T���t�����V�X�R�u�a�����̓��{�ł́A�߉q��t���ɑ���l�X�Ȍ��������\����Ă���B�߉q�͓�E��Z�����Ȃ�1930�N�㒆���̃e����N�[�f�^�[�̊ώ@�ɂ��R�����̋��Y����J�����Ă���A1940�N�i���a15�N�j�ɂ͓����푈�̒������Ŋv���K���Ƃ̔F���������Ă���A���̔F���͌R���̊v�V�h�����B���ψȌ�̐푈���v�悵���Ƃ���A�d�_�ւƓ]�����ꂽ�Ƃ�������[20]�A1941�N�i���a16�N�j9�����痂�N4���ɂ����Ĕ��o�����]���Q�������߉q�̑��Y�}����ւ̉e����^�����Ƃ�������[21]�A�u�}���N�X��`�҂ł������߉q�������}���N�X��`�҂ł͂Ȃ��Ƃ̋U�C���[�W����鎩�ȕٌ�̕���[22]�v�Ȃǂł���B
�Ȃ��A2013�N8��12���̎Y�o�V���̕ɂ��ƁA�߉q���u�R���̈ꕔ�͂����Ȃ�]�����Ă��\�A�Ǝ������ׂ��Ƃ����_������̂�����A�������Ƃ̒�g���l������҂�����Ƃ̎��Ɍ����v�ƌx�������ʂ�A�����h�𒆐S�Ƃ��闤�R�����̈ꕔ(�鏑���߂����J���卲��Q�d�{���푈�w���ǒ��̎푺���F�卲�Ȃ�)�́A�\�A�ɐڋ߂��A�V�c�������������ɐ��A�\�A�⒆�����Y�}�Ɠ��������сA�u�V�c���Ƌ��Y��`�𗼗��������Ɓv�̑n�݂�ڎw���u�č��ł͂Ȃ��\�A�哱�ɂ��I��\�z�v�������Ă����Ƃ����B�܂��A1945�N6���ɁA���X�C�X�����������{�i�Ӊ�ΐ����j�̗��R����(������������Ă������ߒ������Y�}���̉\��������)���A�č��̃A�����E�_���X(CIA�̑O�g�g�D�ł���헪����(OSS)���B���ǒ�)����̍ō��@�����Ƃ��āu���{���{�����Y��`�҂����ɍ~�����Ă���v�Əd�c�ɋ@���d��ŕ��Ă������Ƃ��A�����h���̉p�����������ُ����̍ō��@�������ɂ���Ĕ��������Ƃ���[23]�B
�r��
^ �� (1966)�A�㊪ �O��ŁB
^ ���c (1987)�A43�ŁB
^ ���c (1987)�A73�ŁB
^ ���c���� �w���]���̉�z�x �������_�Ёq�������Ɂr�A1987�N�A55-67�ŁB
^ �����A�����̉����Ŋ������Ă������Q�O�i�ϖ��E����i�j���w���B
^ �،˓��L�������\���`���@�� �w�،ˍK��W�����x ������w�o�ʼn�A1966�N�A495-498�ŁB
^ ���c���� �w���]���̉�z�x �������_�Ёq�������Ɂr�A1987�N�A64-65�ŁB
^ �،˓��L�������\���`���@�� �w�،ˍK��W�����x ������w�o�ʼn�A1966�N�A497-498�ŁB
^ �،ˍK��W����591�`592�ŁB
^ �߉q�����̍ő��߂̈�l�ł����厡�́A���a16�N5��6���ɁA�ē����t��|�������R�����w���u�吭���^���e�R�I�ꍑ��}�^���Ƃ��Ďx�����\�A�M�Ƃ̕�������}����v�V�E���v�ƌĂ�ł����i����j�������Ƒ������Q�A484�`488�Łj�B
^ �����v�V�ĂƂ́A���{�����Љ�}�ɂ��ꍑ��}�����A�������t���A��s�A�d�v�Y�ƁA���Ƃ̍����c���̎�����ڎw���u�����s���@�\�����āv�ł���B�Ό��Ύ��͏��a6�N5���ɁA�u�푈�͕K���i�C���D�]�����ނׂ�����푈�����ɘj��o�Ϗ�̍���r�������Ɏ����Ƃ��鎞�́A�����߉��ɉ����Ċe��̉��v���s���ׂ������ɉ����鏊�����������ɔ䂵ꡂ��Ɏ��R�I�ɔV�����s����ׂ��B�䂪����͍����̉�������Ƃ�������J�덑�Ƃ�����đΊO���W�ɓːi�����ߓr���ɂ�荑���̉�����f�s�����K���Ƃ��v �Əq�ׁA�Q�d�{���푈�w���ے��Ƃ��ď��a11�N�H���ɋ{�萳�`�Ɂu�Y�ƌ܃J�N�v��v�Ɓu�����s���@�\�����āv�𗧈Ă��������A��҂̈Ă͌����i�K�Œ��~�ɂȂ����i�Ό��Ύ��������h�_����76�`78�Łu���֖�莄���v�A�`��F�y�R�t�@�V�Y���^���j�z246�`247�ŁA�ɓ����y�߉q�V�̐��z59�`60�Łj�B
^ �C�R�ɂ͎x�ߎ��ς̖u���ȑO���痤�R�����h�A�J�_�����݂����B�C�R�叫�̎R�{�p��́A�ē������{�ɑ���̏��i���a10�N12��29���j�̒��ŁA���{������ɍr�A�^��̗��R�c���h�̗v�]�ɉ����Ȃ��ׂɁA�v�V���Z���u�ӋC�n���Ȃ���ɂ��A�ő��㊯���ނɑ��炸�A�����h�̕����}�V���v�Ƃ����A�䂪���̂Ɋӂݍc�R�̖{���Ɩ��_�������邱�ƂȂ��𗧂đO�Ƃ��A�匳���É��̌䖽�߂ɂ��炴��Γ����Ȃ��Ǝ咣����c���h��������A�����h�̐��͂��g�債���邱�Ƃ��w�E���A�u�n�߂͏������̗͂��S��đ��ړI��B����Ǝ��݂����e�Ղɉ������ꂸ�A�I�ɍŌ�̎�i�ɑi���Ė����ƍl������̌n�����t�@�b�V���C���ƂȂ�A�V�ɖ��ԉE���A�����̏��c�́A�����ƁA�I���̖���A�ԉ��^�����V�ɏ悶�ė��p����Ƃ�������ƂȂ�A�V�����������h�ƂȂ肵���̂ɂāA�\�ʂ͑�ϔ������ꋏ����A���I�ǂ̖ړI�͎Љ��`�ɂ��āA��N���R�̃p���t���b�g�͑��̐^�ӂ�I�킷���̂Ȃ�B�ёO�����A�i�c�R���ǒ����͔V��m��ĂȂ������m�炸���ď悺���ċ��肵���m�炴��ǂ��A���ŏI�̖ړI�_�ɒB����Ύ��{�Ƃ����A�}�Ă����ƓI�ɓ�������Ƃ�����̂ɂāA�\�A�M�̔@�����ʂƂȂ���̂Ȃ�v�ƌx�����Ă����i�،ˍK��W����257�`258�Łj�B
^ �I��H��̋L�^��67�`72�Łu�����R����ژ^�v
^ ��76��鍑�c��O�c�@���h�ۈ��@�Ĉψ���c�^��3�a16�N2��3���B
^ �哌���푈�ƃX�^�[�����̖d���|�푈�Ƌ��Y��`�A28�ŁB
^ ���a19�N6���A���O���ɏ����ꂽ�x�����������ے��̐`�d���́A�䂪���̋��Y��`�^���ɂ��āA�u�����̂킪���ɂ͋��Y�}�͂Ȃ��A�]���āA���Y��`�^���͓��ꐫ�������Ă���B����ǂ��A���Y��`�҂͐E��Ǝ��Ƃɑ������ĉ^�����s���Ă���A�푈�ɂ�鍑�����������̒ቺ�́A�����^���̉����ɂȂ��Ă���B���̉^���͐��ʂ��狤�Y��`��W�Ԃ����A�s��̏ꍇ�ɂ��Ȃ��ċ��Y��`�҂�{������Ƃ����ړI�łȂ���Ă�����̂������B�v����ɁA���݂̏�́w�͑���ς݂���L�l�x�ł��邩��A����Ƀ}�b�`�ʼn�����A�����ɔR���オ��B�x�����ł͍��̂�۔F������̂������A�����łȂ����̂��E���Ƃ��Ĉ����Ă�����̂́A���̉E���̒��ɂ͎��͍����̑������Ƃ́A�����ł���B�ŋ߂̎Y�ƕ�Ҙ_�̂��Ƃ��́A���̗ǂ���ł���B�܂�������]���҂̑啔���͐^�ɓ]�����Ă���̂ł͂Ȃ��v�Ƌ߉q�ɐ��������i���`���y�߉q�����z202�Łj�B
^ �哌���푈�ƃX�^�[�����̖d���|�푈�Ƌ��Y��`�A30�ŁB
^ �哌���푈�ƃX�^�[�����̖d���|�푈�Ƌ��Y��`�Q�ƁB�����{�ɂ����Ēn���w�̍ĕ]�����s�����O���j�����Ƃ̑]���ېM�́A�푈�Ƌ��Y��`�|���a������^�i�O�c�����v���^���吧�x���y��A1950�N�j���u�哌�����h���ƃ}���N�X��`�Ƃ̊ւ�����j�I�ɗ������{�v�ƕ]�����A����Ɉˋ����āA�u��O����ѐ풆�̓��{�ł͒n���w�͓��{�ɑΉp�ĊJ��𔗂鍑�ۋ��Y��`�̈��i�Ƃ��āA������������Ȃ킿�X�^�[�����̑ΊO��������̂��߂ɒm�炸�m�炸�̂����ɗ��p���ꂽ�Ƃ������܂荁�����Ȃ��ߋ��̉{���������Ă���v�Əq�ׁA�u���{�̑嗤����ɍł��傫�ȉe����^�����O���̎v�z�͎��̓}���N�X��`�ł����āA�{���̈Ӗ��̒n���w�ł͂Ȃ������悤�Ɏv����v�ƌ��_�Â����i�]���ېM�y�n���w����O��헪�̐����w�z130�`134�Łj�B
^ �哌���푈�ƃX�^�[�����̖d���|�푈�Ƌ��Y��`�A311�`322�ŁB�ݐM��͐푈�Ƌ��Y��`�|���a������^��ǂ݁A���̂悤�Ɉ⌾�����B �u�m�F�̃��W�I���{�В��A���R�i�v�N���A�^���A�w�ݐ搶�A��ςȖ{�����t���܂����B������lj������x�Ǝ��Q���ꂽ�̂��A���̎O�c�����v���̒����ł������B�ǂޒ��ɁA���́A�v�킸�A�E�[���ƚX�邱�ƎƁX�ł������B�x�ߎ��ς��������A���x�a���̉���Ԃ��A���{�����đ\�헪����A�Εĉp�����̓�i�헪�ɓ]�������āA���ɑ哌���푈�������N�����������{�l�́A�\�A�̃X�^�[�������w������R�~���e�����ł���A���{�����ōI���ɂ����U�������̂��A���Y��`�ҁA����G���ł������A�Ƃ������Ƃ��A���ɐԗ��X�ɕ`�ʂ���Ă���ł͂Ȃ����B�߉q�����A�����p�@�̗����͂��߁A���̎��܂Ŋ܂߂āA�x�ߎ��ς���哌���푈���w��������X�́A�����Ȃ�A�X�^�[�����Ɣ���ɗx�炳�ꂽ����l�`�������Ƃ������ƂɂȂ�i�����j�B ���̖{��ǂ߂A���Y��`���@���ɉE���A�R�������Ɩ��Ē��̂��̂ɂ��������悭����B���̂��ꂪ�o�����̂��A�N�����^��Ɏv���Ƃ���ł��낤�B�R���A�l���Ă݂�A�{�����̗��ҁi�E���ƍ����j�A���ɑS�̎�`�ł���A��}�ƍفE�v��o�ς���{�Ƃ��Ă���_�ł͓��ނł���B�����A�푈���s�̂��߂ɌR�����Ƃ��������́A�܂��Ɉ�}�ƍفi���^�����j�A�v��o�ρi���Ƒ������@�����Y�����Ɣz�����j�ł���A�����ׂ����A�����̃\�A�̐��Ɨގ����Ă���B�����ɁA��q�̋^���������������悤�Ɏv����B ���ۋ��Y��`�̖ړI�́A���̒����ł��w�E���Ă���悤�ɁA�哌���푈�̏I���ȍ~�͋؏��ǂ���ɂ͂������A���{�̋��Y���͎���Ȃ��������̂́A���ۋ��Y��`�̐��E�ԉ��헪�����́A��O���獡���܂ň�т��āA�Ԓf�Ȃ������Ă��邱�Ƃ�m��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���N�̃��X�g�{���t�����A���A�ŋ߂̃��t�`�F���R�����Ȃǂ́A�ق�̕X�R�̈�p�ɂ����Ȃ��̂ł��낤�B�����H���~�߂�ɂ́A���R��`�̐������邷�ׂĂ̍��Ƃ��A�т��āA���R�Ɩ����`����������Ǝ��A�G�̈�}�ƍفE�v��o�ςɑ���ɁA�������}�E�s��o�ς̎Љ�����炷�邱�Ƃł���B ���́A�����g�̔��Ȃ����߂āA�ȏ�̂��Ƃ������������B�܂��A���̃V���b�L���O�Ȗ{���A�����Ƃ����Ƒ����̐l�X�ɓǂ܂�邱�Ƃ�S����]�ގ���ł���B�v
^ ���i (1995) �u����ł͉��́A��t���̂Ȃ��ʼnߏ�Ƃ��v����v���ւ̋��|�ƁA����ɂ���Ă����点��A�d�����W�J���ꂽ�̂��낤���B�����߉q�����̂悤�ȌX���������A�]���Q������R�������ɂ�葝�����ꂽ���Ƃ͔ے肵���Ȃ����A�ُ�Ƃ���������e�����ł���B�ނ���߉q�̖{���Ƃ������A�B�c��̉e���ƂƂ��ɁA�����߉q��̃O���[�v���͍����Ă����A����ɂ͓�E��Z�����ȍ~�̏h��ł���c���h�̕����E�g�t�̂��߂ɁA�c���h�ɗ�W�ȓV�c��������悤�Ƃ��鐭���I�ȈӖ����������Ɛ��������B���̂��߂ɂ́A�֒����ꂽ�\�����K�v�ł������v
^ ���c (1987)�A58�ŁB
^ �u�w�{�y����x�w�ꉭ�ʍӁx�����s��v���_�҂����v�i���ԗm��u�������Y�}�@��]�Ɩd����90�N�v�w�ʍ����_�x����23�N6�����j ���씪�m�́u�߉q�������Ήp�Đ푈��`�҂łȂ��������̂悤�ȋU�C���[�W�A���邢�͋߉q�������}���N�X��`�҂łȂ��������̂悤�ȋU�C���[�W������A�߉q���g�ɂ�鎩�ȉ��Z�̍ł�����̂����̗L���ȋ߉q��t���ł��낤�B����͓����푈�Ɠ��Đ푈�̔��N�푈�̂��ׂĂ̐ӔC���R���ɓ]�ł���ɐ▭�ʼnؗ�ȉ��Z�̓T�^�ł������B���̏�t���������ċ߉q�������]�O����p�Ăɑ���푈�̉��_�҂ł������ƁA���̏؋��Ƃ��Ă�������̂��������A����͗]��ɂ��Z���I�ł���B�܂��lj�͂Ɍ��ׂ���Ƃ��킴������Ȃ��i�����j�B�߉q��t���́A���{�̔��N�푈�Ƃ͓��{�̋��Y����ړI�Ƃ��ċ��Y��`�ҁi�}���N�X��`�ҁA�Љ��`�ҁj�����ɂ���Đ��s����Ă������ƁA���l�l�N������̃X���[�K���ꉭ�ʍӂ̓��[�j���̔s��v���_�ɏ]�����A���Y�v�������Ղ��r�p�������{�Љ�����邽�߂̂��̂ł��邱�ƁA���m�E����̏G�ˑg�̂��镔�����\�A�R����{�ɓ������Ă̓��{�̋��Y�������d���Ă��邱�ƁA�Ȃǂ̍ł��[���ȏ��ɂ��čł����m�ɉs���j�S���Ղ��Ȏ@���Ȃ��Ă���B�������ɁA���̋߉q�̎w�E�́A�}���N�X��`�ɂ��Ԃꂽ���m�E���呲�̐Ԃ��R�l�����ɑΉp�Đ�Ƃ��̌p��̓����̂��ׂĂ̐ӔC��]�ł���_���ł���̂͒N������ǂ���Η����ł��悤�B�v�Ƌ߉q��t�����]���Ă���i�߉q�����ƃ��[�Y�x���g�哌���푈�̐^��76�A81�Łj�B
^ �I����Y���ƍ\�z�@���R�����u�V�c�������ł���v1/42/43/44/4 �Y�o�V��2013�N8��12��
�Q�l����
�I��H��̋L�^�㉺���i�]���~�ďC�A�g���쐟�Y�ҁA�u�k�Е��ɁA1986�N�j
�s��̋L�^�i�Q�d�{���ҁA�����[�A1967�N�j
��{�c���R���푈�w���Nj@���푈�����i�R���j�w��ҁA�ѐ��ЁA1998�N�j
����G������W�P�`�T���i����G�����^�������[�A1979�N�j
�哌���푈�ƃX�^�[�����̖d���|�푈�Ƌ��Y��`�i�O�c�����v���A���R�I���A1987�N�A�푈�Ƌ��Y��`�|���a������^�̕����Łj
�߉q�����ƃ��[�Y�x���g�i���씪�m���A�o�g�o�o�ŁA1995�N�j
����E���Ɠ��ƈɎO�������\�C�R�ƃR�~���e�����̎��_����i���ԗm�꒘�A�ѐ��ЁA2007�N�j
�߉q���L�i�����ʐM�ЊJ���ǁA1968�N�j�@ASIN: B000JA68IO
���z���E�����땽�E�������j�w�߉q�����u�Z���I��v�̃V�i���I�x���������Y �A2006�N�@ISBN: 4901622153
�،ˍK��w�،ˍK����L�x�㊪�A�،˓��L������Z���A������w�o�ʼn�A1966�N�BISBN 9784130300117�B
���`���w���x�A1966�N�A��Ł|�l�\�O�ŁB
�w�،ˍK��W�����x�A�،˓��L������ҁA������w�o�ʼn�A1966�N�BISBN 9784130300131�B
�u���ǃj�փX���d�b�^�v �l��ܕŁ|�l�㔪��
�߉q��t�������^�B
���c�����w���]���̉�z�x�������_�Ёq�������Ɂr�A1987�N�BISBN 4122014239�B
�����A���a�V�c�̎��]���߂Ă������c�������猩����t�̌o�܂ƁA��t���̌����Ƃ��L�q����Ă���B
�u�V�c�̏I��閧�H��v43�Ł|54��
�u�z�̖ڂ������߉q��t���v55�Ł|67��
�u��ӎv�ɉ����d�b�̑t��v68�Ł|85��
���i����Y�u�w�߉q��t���x�̍Č��� ���ۏ���͂̊ϓ_����v�w���ې����x109�� �I��O���Ɛ��\�z�A���{���ې����w��A1995�N5���A 54�Ł\69�ŁA ISSN 0454-2215�B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%A1%9B%E4%B8%8A%E5%A5%8F%E6%96%87
http://www.asyura2.com/20/reki4/msg/1126.html

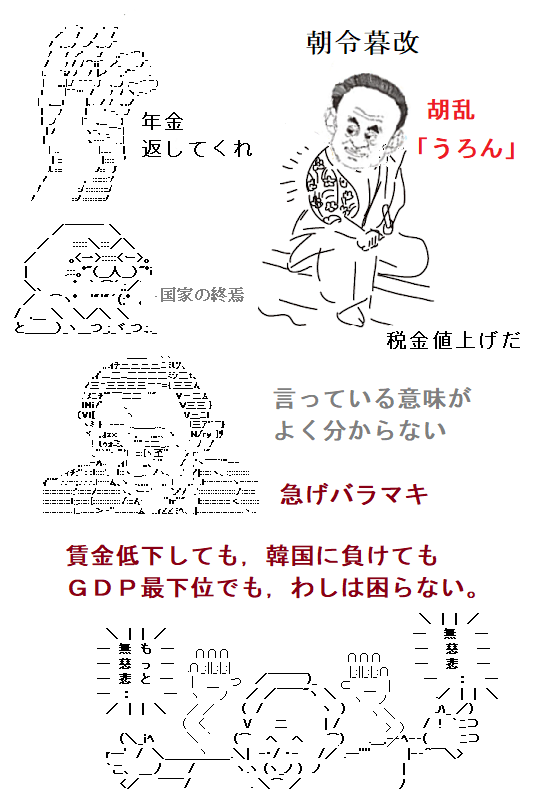
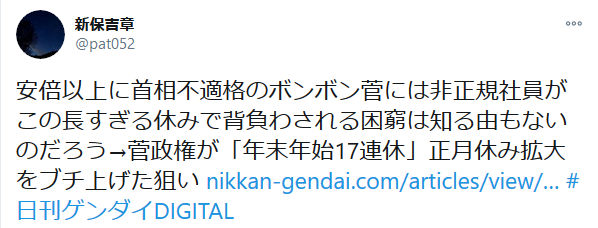

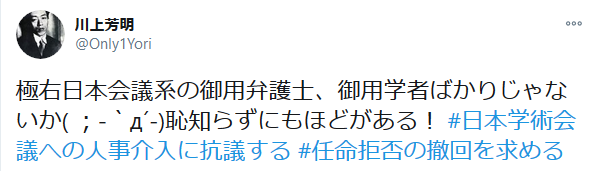
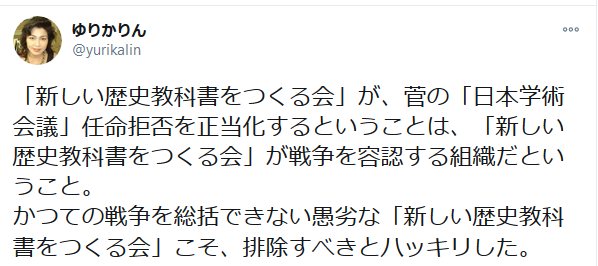


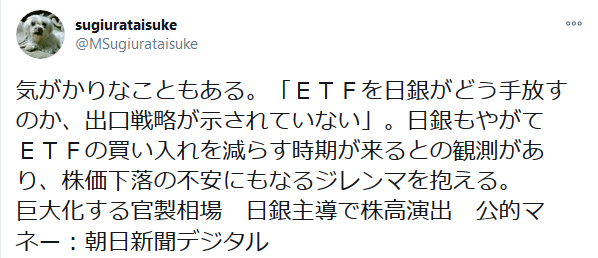
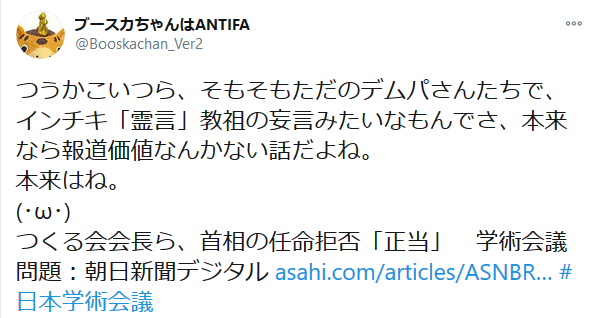



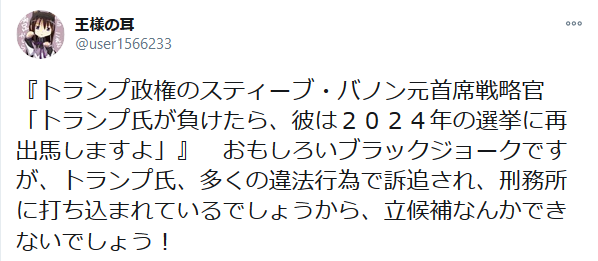


 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B