�P�ꂽ�����Z�b�g�i���j�ƃj���[�E�C���O�����h�E�W���[�i���E�I�u�E���f�B�V���̘_���B�P�ꂽ�iRETRACTED�j�ƒ��L����Ă��遁2020�N7��6���ߌ�4��36���A���c�_��B�e
�u�V�^�R���i�E�C���X�����ǃp���f�~�b�N�v���̂��̂��A���Ґ��␢�E�I�Ȋg�U�ɏƂ点�u�X�P�P�v��ꡂ��ɗ��������I�ő�̍��ۓI�d�������Ȃ̂�����A�������E���Ö�E���N�`���ȂǂɊւ��錤���⌾���̂Ȃ��ɖ��d�s�v�c�œ��̂̒m��Ȃ����̂��������Ƃ��Ă����R�̂��Ƃ��낤�B
�u�V�^�R���i�E�C���X�v������ނ̊��ő�ʐ������ꂽ�\�����������Ƃ₻�̎U�z�����́g�����h�����������āg�������ʁh�Ƃ��ďo�Ă��Ȃ����Ƃ́A��w�E�̈ł̐[���������͖��\�Ԃ��@���Ɍ����Ă���B
���{�ł́A�U�����{�ȍ~�̊����g�傪�u��O�g�v�ł���Ƃ̔F�������Ȃ��Ȃ��ŁA�����}�����ǂ�����̂��A�o�ϕ����̂��߂̂f�� �s���g���x���L�����y�[���̐���Ȃǂ��߂����āA���Ԍ��Ƃ������q�ǂ������̋c�_���^��ōs���Ă���B
�i�����𐄂��ʂ�j�l���l�Ă�������w�̒��삳��́u��O�g�v�ƔF���j
�u���\�O�t���i���{�E�����E�����j�v�Ɓg�S�}�J�V�Ɛ�h�̓s�m���ɑ�\�����ߎS�����铝���\�͂Ɉ��R�Ƃ��邾���ł���B
�����s�[�N�������炭�V�����{�i�����m�F�҂̃s�[�N�͂W�����{�ɂ��ꍞ�ނ����j�ƂȂ�ł��낤�u��O�g�v�i�R���E�S���́u���g�v�������j�ɂ��ẮA�č�����́g����e�h�ł��邱�Ƃ������ł��Ȃ���Ί����}�����ł��Ȃ��ƌ��������ɂƂǂ߁A�ڍׂ͌���ɏ��肽���B
�����ł͍�N�W������V�^�R���i�E�C���X�����ǂ��������Ă����\��������Ƃ����K�Z�l�^�������n�[�o�[�h��̕ʂ̌����҂ł���}���f�B�[�v�E���t�������́A�u�g�p����f�[�^���K���\���Ɋm�F���Ȃ������B���ړI�ɂ��ԐړI�ɂ��A���������������Ƃ�S���\����Ȃ��v���v�ƎӍ߂��鐺�����o�������������A���݂��Ȃ��f�[�^�x�[�X�Ȃ�A�f�[�^���K���ǂ����������Ȃ��͂Ȃ����B
���t�������́A�u���t��������N���������ۑ�ɑ��āA���Ёi�T�[�W�X�t�B�A�j���ۗL����Ƃ����f�[�^�͂������ʂ�����A�������ɘ_�������M�����v�Ɛ������Ă���悤�����A����Ȃ�A���f�[�^���m�F���Ȃ��܂܂Ř_���\����Ƃ������\�I�s�ׂ��Ӗ�����B
�i�R�}�����A��q�h���L�V�N�����L���̓��^�����S�������߂�Ƃ����g�_���h�́A���̎g�p�����ɂ��Ă����g�����v�哝�̂��Ȃ߂�i�o�J�ɂ���j�ړI����f�V�r�������̂��߂����ŏ����ꂽ����������j
���@�u�T�[�W�X�t�B�A�Ђ́A�V�^�E�C���X�̗��s���L����O�܂Ŗڗ��������������Ȃ������̊�Ƃ������B�z�[���y�[�W�ł́A���E1200�̈�Ë@�ւƋ��͂��č\�z�������E�ő勉�̊��҃f�[�^�x�[�X��l�H�m�\�iAI�j�ŕ��͂���Ɛ������Ă������A�p���K�[�f�B�A���͏]�ƈ��Ɉ�w��@�B�w�K�Ɋւ���o��������l���͂قƂ�ǂ��Ȃ������ƕĂ���B�v
�m�֘A�Q�Ɠ��e�n
�u�V�^�R���i�E�C���X������ł̗��s�J�n�͍�N8���̉\�����n�[�o�[�h��F�W���ł͂Ȃ��P�O���A������ł���N���ɐ��E�I�����̂͂��I�v
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/319.html
���e�� �������� ���� 2020 �N 6 �� 10 �� 04:37:44: Mo7ApAlflbQ6s�@gqCCwYK1guc
====================================================================================================
���E�h�邪���R���i�����s���^�f�@�������_���P��@�����ރf�[�^���
�����V��2020�N7��7�� 18��03��(�ŏI�X�V 7��7�� 18��17��)
�@�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̎��ÂɊւ�錤���ŁA�ꗬ��w����ɂ��������s���^�f���g����L���Ă���B�č��̃g�����v�哝�̂����������݁A���ۓI�ɑ傫�Ȓ��ڂ��W�߂������̃f�[�^�́A���݂�������܂�鎖�ԂƂȂ��Ă���B�J��Ԃ����s����h���藧�Ă͂���̂��B�y���c�_��i�u�����b�Z���j�A�n�ӗȁz
������Ƃ��u���E�ő勉�f�[�^�x�[�X��AI���́v�@������z�[���y�[�W��
�@�p��w�������Z�b�g�ƕĈ�w���j���[�E�C���O�����h�E�W���[�i���E�I�u�E���f�B�V���iNEJM�j��6��4���A������𗘗p�����V�^�E�C���X�̎��ÂɊւ��錤���_����P���B�ǂ���̌������A���E�e�n�̈�Ë@�ւœ��@���Â������҂̓d�q�J���e���W�߂ĕ��͂����Ɛ������Ă������A�����Ƃ���f�[�^�ɋ^�`���������B
�@��̌����������ăn�[�o�[�h��̃}���f�B�[�v�E���t�������́A�����V���̎�ނɁu�g�p����f�[�^���K���\���Ɋm�F���Ȃ������B���ړI�ɂ��ԐړI�ɂ��A���������������Ƃ�S���\����Ȃ��v���v�ƎӍ߂��鐺�������B
�@�_���͂��ꂼ��5���ɔ��\���ꂽ�B�Ƃ�킯�R�}�����A��q�h���L�V�N�����L�����V�^�E�C���X�̎��ÂɗL�����������������Z�b�g���̘_���́A�����K�͂̑傫�����璍�ڂ��W�߂��B�V�^�E�C���X�ւ̗L�������m�F�ł��Ȃ����肩�A���S���X�N�����܂�\��������ƌ��_�Â�����e�������B��������Ɍ����҃R�~���j�e�B�[�ŋ^�`�����シ��B�_���͐��E�e�n�̖�9��6000�l�̊��҃f�[�^�͂����Ɛ������Ă������A�_���Ŏ����ꂽ���Ґ��Ȃǂ̃f�[�^�Ɗe�����{�̔��\�ɐH���Ⴂ���������̂��B
�@NEJM���Ɍf�ڂ��ꂽ�_���́A�A�W�A�Ɖ��Ă̊���8910�l�̃f�[�^����ɁA�~���܂̕��p���V�^�E�C���X�������̏d�lj����X�N���u���߂Ȃ��v�Ƃ�����e�������B���{�̌����J���Ȃ�5���ɉ��������u�V�^�R���i�E�C���X�����ǁ@�f�Â̎�����v�̒��ŁA�_���Ɍf�ڂ��ꂽ�}����{��ɖĂ��̂܂܈��p���Ă���B�����A���̘_���̊��҃f�[�^�̐M�҂傤���ɂ��^�`���������B
�@��̘_���̃f�[�^���W�ƕ��͂́A�ăV�J�S�ɋ��_��u���T�[�W�X�t�B�A�Ђ��S���Ă����B
�@���t�����̐����ɂ��ƁA�V�^�E�C���X�̗��s���āu�^�C�����[�ȃf�[�^�̒��s���v�ƍl���Ă����Ƃ���A�������Ԃ�ʂ��ē��Ђ��Љ�ꂽ�Ƃ����B���t��������N���������ۑ�ɑ��āA���Ђ��ۗL����Ƃ����f�[�^�͂������ʂ�����A�������ɘ_�������M�����B
�@�^�`�����シ��ƁA���t�����͓Ɨ�������O�ҋ@�ւɒ������ϑ������B�����T�[�W�X�t�B�A�Ђ́u�@�������܂݁A�҂Ƃ̍��Ӂv�ɔ�����Ƃ��Č��f�[�^�̊J�������B���t�����́u�f�[�^�̏o����M�҂傤���v�Ɋm�������Ȃ����Ƃ��ė����ɓP���\�����ꂽ�B
�@�T�[�W�X�t�B�A�Ђ́A�V�^�E�C���X�̗��s���L����O�܂Ŗڗ��������������Ȃ������̊�Ƃ������B�z�[���y�[�W�ł́A���E1200�̈�Ë@�ւƋ��͂��č\�z�������E�ő勉�̊��҃f�[�^�x�[�X��l�H�m�\�iAI�j�ŕ��͂���Ɛ������Ă������A�p���K�[�f�B�A���͏]�ƈ��Ɉ�w��@�B�w�K�Ɋւ���o��������l���͂قƂ�ǂ��Ȃ������ƕĂ���B
�@�œ_�́A�f�[�^�̐M�҂傤������A�T�[�W�X�t�B�A�Ђ��ۗL���Ă���Ǝ咣����f�[�^�x�[�X�������������݂��Ă��邩�Ɉڂ��Ă���B�V�^�E�C���X���҈Ђ��ӂ�������B��č��e�n�ɂ����v�Ȉ�Ë@�ւ͌����݁A���f�B�A�̎�ނɓ��Ђւ̃f�[�^��ے肵�Ă���B�����V���͓��ЂƑn�Ǝ҂Ƀ��[���ŃR�����g�����߂Ă��邪�A7��6�����_�ŕԓ��͂Ȃ��B���Ђ̃z�[���y�[�W�͘_���P���ɕ����ꂽ�B
�^�f�_���A�e���傫���@�g�����v���͕��p�P��@�p���Տ����������f
�@�^�f�̌����͊w�p�E���Đ��������A�܂������ɗ��p����Ă���B
�@�����Z�b�g���̘_���Ō����ΏۂɂȂ����q�h���L�V�N�����L���́A�g�����v�đ哝�̂��V�^�E�C���X�̎��ÂɌ��ʂ�����Ǝ咣���A5�����̋L�҉�Ŗ������p���Ă���Ɩ������Ĕg����ĂB�V�^�E�C���X���u�����̕��ׁv�ƌy������u���W���̃{���\�i���哝�̂����p���Ă���B�V�^�E�C���X�̗\�h�⎡�ÂɗL���ł��邱�Ƃm�Ɏ����������ʂ͂Ȃ����A�g�����v���͓d�b��莆�ōm��I�Șb�����ȂǂƐ������Ă����B
�@�Ƃ��낪�A����Ƀ����Z�b�g���Ŕ��\���ꂽ�_���́A�ނ��뎀�S���X�N�����܂�\��������Ǝw�E�B�g�����v���̎咣��ے肷�鐬�ʂ��Ƃ��ĕč����O�ő�X�I�ɕ�ꂽ�B���t�����������͉p���f�B�A�Ɂu��X�̌����̌��ʂ��ǂ����͒m��Ȃ����A�哝�̂̓q�h���L�V�N�����L���̕��p����߂��ƕ������v�ƌւ炵���Ɍ���Ă����B���E�ی��@�ցiWHO�j��p���ł́A���S�ւ̌��O���瓯����g�����Տ��������ꎞ�I�ɒ��f����Ȃǂ̉e�����L�������B�����f�[�^�ւ̋^�`�ŁA�_���̍������h�炢���B
�@�g�����v���ᔻ�Ɏg��ꂽ�u�G�r�f���X�i�Ȋw�I�����j�v�͘_�����̂��P�ꂽ���̂́A�哝�̂̎咣���x�����錤���͂��̌�����\����Ă��Ȃ��B�q�h���L�V�N�����L����V�^�E�C���X���Ö�̌��Ƃ��ėՏ��������s���Ă����p�I�b�N�X�t�H�[�h���WHO�́A���ꂼ��u�V�^�E�C���X�ɑ�����ʂ͔F�߂��Ȃ������v�ƌ��_�Â���6�����܂łɗՏ�������ł������B
�@�^�f�̌����͓P�ꂽ2�_�������ł͂Ȃ��B���t����������4�����{�A�R����C�x�����N�`�����V�^�E�C���X�̎��ÂɗL���Ƃ����������ʂ���A���ǑO�̘_���Ȃ��獑�ۓI�ɒ��ڂ��W�߂��B�C�x�����N�`���̓m�[�x����w�����w��҂̑呺�q�E�k����w���ʉh�_�������J���ɍv�����A���������̔M�ъ����ǂ̓�����Ƃ��ăA�W�A��A�t���J�ő����̐l�̖����~���Ă����B
�@�������A���̘_���ɂ��T�[�W�X�t�B�A�Ђ̃f�[�^���g���Ă���A�f�ڃT�C�g���獐�m�Ȃ��ɍ폜���ꂽ�B�ĉȊw���T�C�G���X�ɂ��ƁA���̌����́u���ʁv���āA�y���[�ł͐V�^�E�C���X�̎��Îw�j�ɃC�x�����N�`����������ꂽ�ق��A�{���r�A�ł��V�^�E�C���X���Ö�Ƃ��Ďg�p���F�߂��A�����z�z���v�悳�ꂽ�Ƃ����B�����́u�i�_���͓P��Ă��j���e���A�����J�ł͖S�삪���������Ă���v�ƌ��O������Ƃ̐���`���Ă���B
��������f�[�^��͊�Ɓ@���ǂŐ^�U���������@�u�������ʂ��v�ɗ��Ƃ���
�@�ꗬ����ɂ��������s���^�f�́A2014�N�ɉp�Ȋw���l�C�`���[�Ɍf�ڂ��ꂽSTAP�זE�_�����͂��ߌ��₽�Ȃ����A������Ș_���̌f�ڂ�h������I�ȕ��@�͂Ȃ��̂�����B
�@���ǁi�R���j�͘_���̌f�ڂ����߂�ۂ̃`�F�b�N�@�\�̈���B�_���̃e�[�}���ƂɁA���т��镡���̐��Ƃ����̂��B���čs�����A�_���������т��Ă��邩�Ȃǂ��m�F����̂������ŁA�s�������������Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��B
�@���ɋߔN�́A�W�߂��f�[�^����V���Ȕ������o���u�f�[�^�Ȋw�v�����݊��𑝂��A�f�[�^�̎��W�⏈���A��͂��s����Ƃ��������Ă���B�����Ҏ��g���f�[�^���Ǘ���������A��O�҂������������f�[�^�̎��ⓧ�������m�ۂ��邤���Ŗ]�܂����Ƃ����l�������L�܂�A��������������������ƂɈˑ�����X���͋��܂��Ă���B���̔��ʁA���f�[�^�̐^�U�����������Ƃ͂܂��܂�����Ȃ��Ă���B
�@NEJM�̍L��S���҂ɂ��ƁA����̓P��_���͌f�ڑO�A���v������܂�4�l�̊O���̐��Ƃ����ǂ��s�������A���f�[�^�̊m�F�͂��Ȃ������B��K�͂ȓd�q�J���e�̃f�[�^�������������͔�r�I�V�����Ƃ����A�����͍���̌����Čf�ڂɊւ���K�C�h���C������ɒ���B�u��K�͂ȃf�[�^�̐M�������m�����邽�߁A�ǂ̂悤�ȐV�������@���K�v�����l����_�@�ɂȂ����v�Ƃ��Ă���B
�@�����ł�18�N4���{�s�̗Տ������@�ŁA�������������s���Ă��邩�Ȃǂ��m�F���郂�j�^�����O��č��������ӔC�҂ɋ`���Â����B�������A���̎�@�͌����ɒ�߂��Ă��炸�A���@�ɏڂ������Ƃ́u�����ɕs������������Ƃ͌�����Ȃ��v�Ǝw�E����B
�@�����Ȋw�Ȃ̃K�C�h���C���́A�s���i�˂����j�Ɖ�����A���p���u����s���s�ׁv�ƒ�߂�B15�`19�N�x�ɓ��Ȃ̗\�Z���g���������̂����e8�`16���ŕs�����������B�ĉȊw���T�C�G���X��18�N�A�_���P�������E�̌����ҏ��10�l�̂������{�l���������߂��ƕB�_���̓P�����Ď�����C�O�̃E�F�u�T�C�g�u���g���N�V�����E�I�b�`�v�ɂ́A���{�̈�w�n�_���̓P�ڗ��B
�@�����ϗ��ɏڂ�����ʎВc�@�l�u�Ȋw�E����ƎЉ�����v�̉|�؉p���\�����i�a���w�j�́u�V�^�E�C���X�֘A�̘_���͓��X���E���Ŕ����I�ɔ��\����Ă���B���Ö@�m���ւ̊��҂�����A���ǂ��ȗ������ꂽ��A�Z�k���ꂽ�肵�ĎG�ɂȂ��Ă���B���Ɛ��m���̃o�����X��������A����͂��̈����ʂ��o���v�Ǝw�E�B�u���ǂ̂Ƃ���A�w�Ȋw�Ƃ͑S�ĉ����ł���x�Ɨ�ÂɎ~�߂邵���Ȃ��B�Ӑ}�����s���͖h������̂ł͂Ȃ��v�Ƙb���B





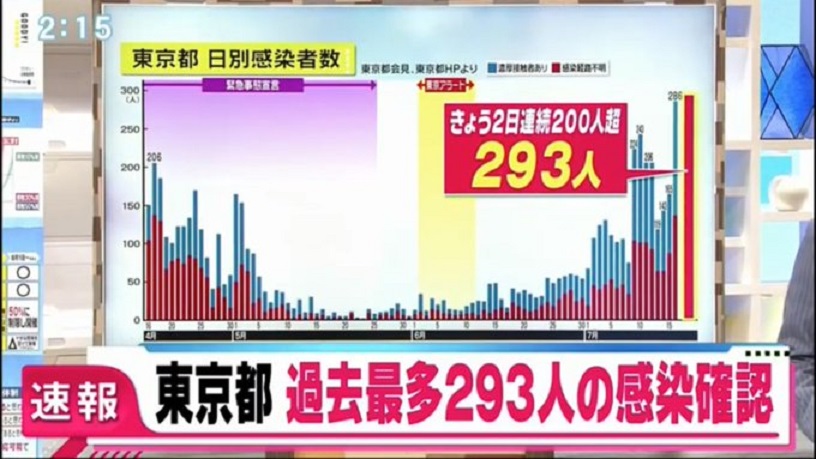


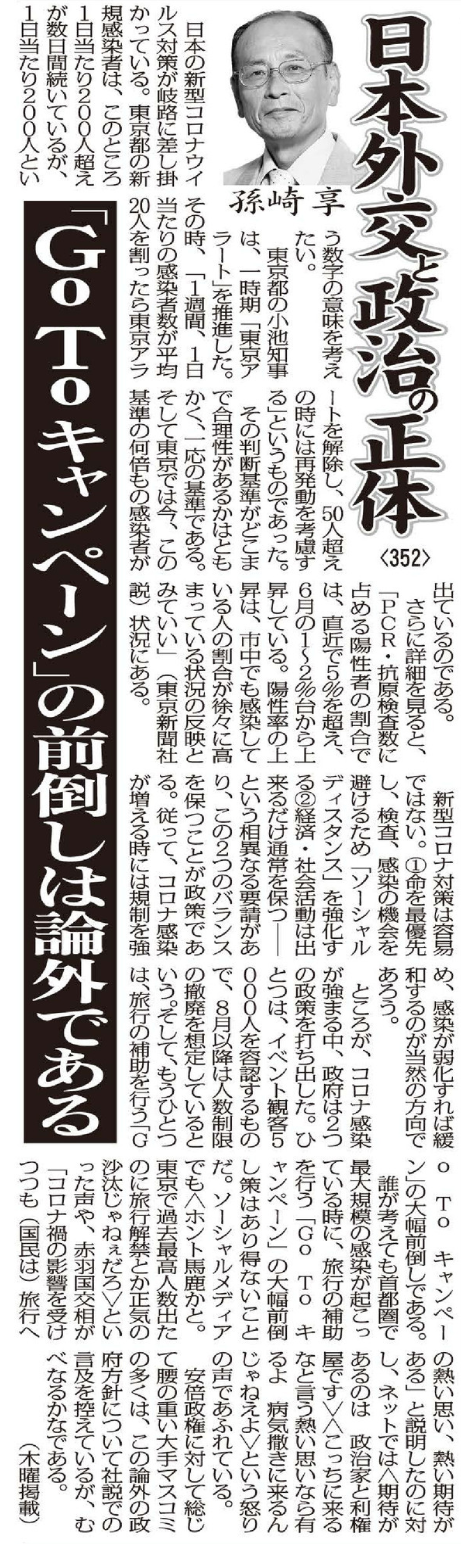


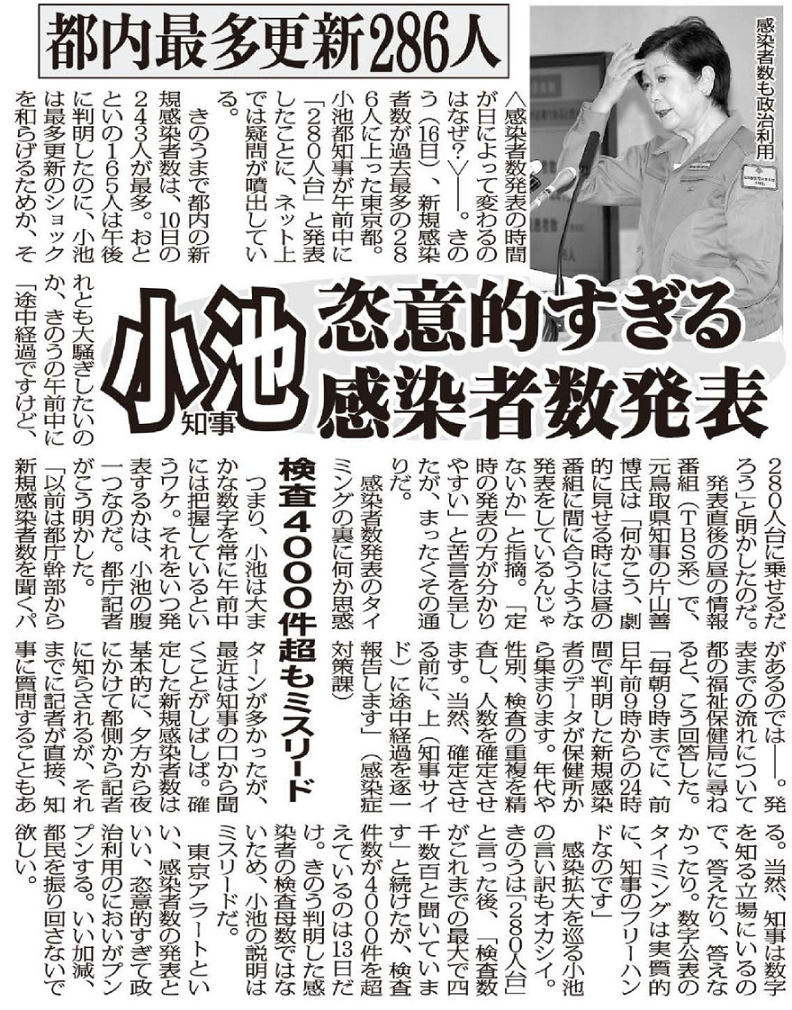


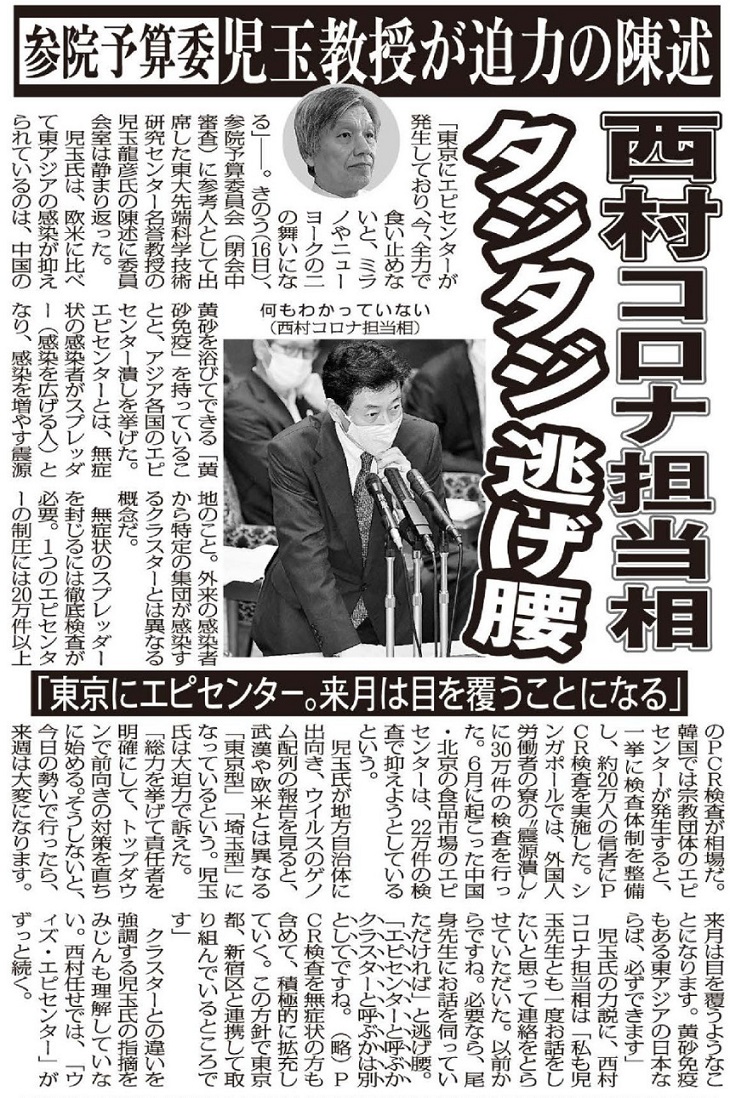

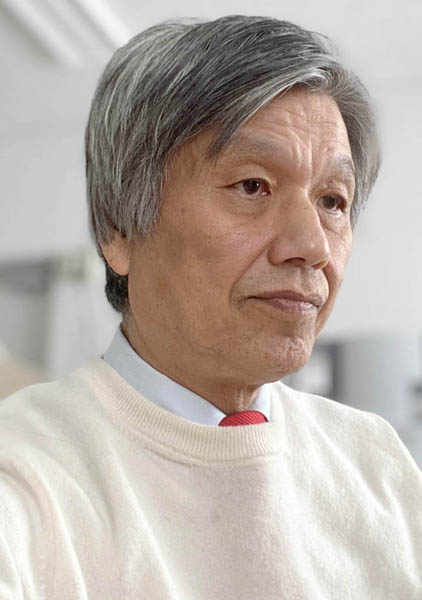
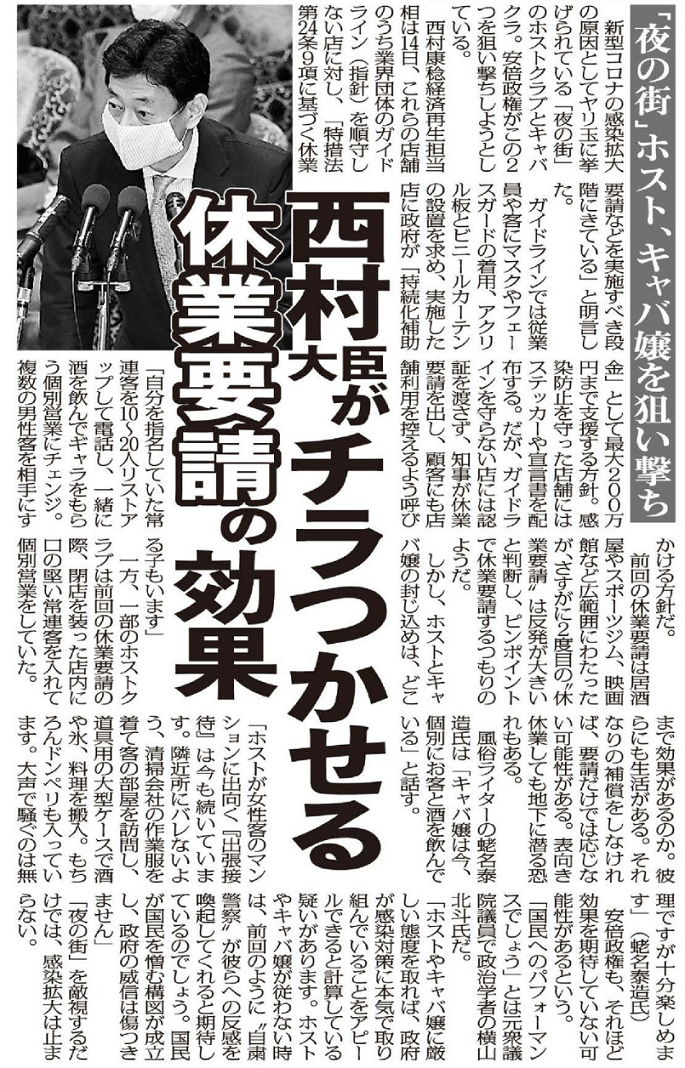

 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B