������ ����
�Ď����Ƃ̌��� 2020�N02��04��
http://tokaiama.blog69.fc2.com/blog-entry-1019.html
�@�@�������w���ɂȂ邱��A��y�Ƃ����e���r�������̂����A�Q���Ėʔ����ԑg���������B
�@�u�v���Y�i�[6�v�Ƃ����B
�@ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%8A%E3%83%BCNo.6
�@���̃h���}�̖ʔ����́A�Ō�܂Ŏ�l�����Ď����A�S������g�D�̐��̂�������Ȃ����Ƃ������B���������N���H�@���̖ړI�ŁA��l�̒�������S�����A�\�͓I�ɊĎ���������̂��H
�@�X�g�[���[�́A�ɂ߂ēN�w�I�Ȏ����ɕx���̂Ŏ����҂��䂫�����B
�@���̔ԑg�́A�C�M���X�Ő��삳�ꂽ���̂��������A���̃C�M���X�́A�������Y�}�̊Ď��Љ��������܂ł́A���E��̊Ď����Ƃ������B
�@2��2���A�����h���ʼn��ߕ����́A�C�X�������v�z�̉e�������e�������Ƃ��P�Ƃ�3�����h�����A����ɁA�Ď����������x���ɎˎE���ꂽ�B
�@https://www.bbc.com/japanese/51352236
�@�e�^�҂́A���E��Ƃ����閧�x�̊Ď��J�����ŒǐՂ���A�e���s���Ɠ����ɋ߂��ɂ����x�����삯���ĎˎE�����̂����A���̑Ή��̑����ɋ������ꂽ�B
�@
�@�����N���Ɍ����Ă���A���Ď��Љ���h��
�l��1�l������̊Ď��J�����̑䐔�ŁA�����h���͐��E�g�b�v���Ƃ���
�@https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/18/032300130/
�@���̃j���[�X�����āA�v���Y�i�[6���v���o�����̂́A����l�ł͂Ȃ����낤�B
�@�C�M���X�́A�I�[�E�F���́u1984�N�v�Ď��Љ�����������A�ŏ��̍��������B
�@https://ja.wikipedia.org/wiki/1984%E5%B9%B4_(%E5%B0%8F%E8%AA%AC)
�@�Ȃ��A�C�M���X���A���قǂ̊Ď��̐���K�v�Ƃ��鍑�������̂��H
�@����́A���j�I�ȁA���̐����i���Љ�ł���A�Љ�{��l�I�����̗��������Ȃ��A�l�X�́A�x�z�K���Ɣ�x�z�K���i�z��K���j�ɗ��j�I�ɌŒ肳��A�̐��ɑ��镮����Ԃ��܂����i���A�e�������c����Ă��Ȃ��������炾�낤�B
�@����́A�ŏ��ɖ����I�Η��̂Ȃ��ŋN���Ă����B
�@
�A�C�������h���a�R
�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%85%B1%E5%92%8C%E8%BB%8D
�@�C�M���X�͢�e���Ƃ̕S�N�푈��̍Œ��ɂ���@�����h���ͤ�����Ɖߌ��h�̕W�I������
�@https://toyokeizai.net/articles/-/96503
�@���̐���́A�C�M���X��IRA�ɂ���āA�������e���̕W�I�ɂ��ꑱ���A���傤�ǁA�����̖����ʎ����e���̃��f���ɂȂ��Ă����悤�Ȏ��オ�������������Ƃ�m���Ă���B
�@������A�����h���Ńe�����J��Ԃ���Ă��A�C�M���X�����́A����I���i�Ƃ��đ傫�ȋ����������Ȃ��̂ł���B
�@�C�M���X�͖����`���ƂȂǂƌ����邪�A���Ԃ́A�����Ɠ����K���ɂ��ƍَЉ�ł���B
�@�l�X�̐g���́A���܂ꂽ�Ƃ�y�n�ɂ���Ē�܂�A�y�n�̏��L������A�p�����ƒn���̎�M�����唼��Ɛ肵�A�قƂ�ǂ̉p����������l���_�z���Ȃ߂��Ă���B�@
http://www2.ashitech.ac.jp/civil/yanase/essay/no07.pdf
�@���Y��i�������Ȃ�����l�̉Ƃɐ��܂ꂽ�Ȃ�A�Љ�S�̂̍d���������l�ςɂ���āA��ӂ̘J���ҊK���Ƃ��Ă̐l���ȊO�̑I�����͂Ȃ��B
�@����͈ږ��ɑ��ẮA���Ս��ł���A������A�ږ��Ńe���ɑ����҂������̂ł���B
�@����ɑ��āA�x�z�K���͊Ď��Ɩ@�I�Ȓe���őR���Ă����B
�@�C�M���X�ɂ�����Ď��Љ�Ƃ́A�Œ肳�ꂽ�̎傪�A���R�����߂��ӏ����̓{������߂邽�߂̃V�X�e���ł������B
�@���݁A�̐��̗������Œ肵�A�����̓{������߂邽�߂̃V�X�e�����A���E�ł����Ƃ��K�v�Ƃ��Ă���̂��A�������Y�}�Љ�ł���B
�@�V�^�x����Ƀh���[���A�������֎�����Ď����Ƃ̎p�@���C�^�[2��3��
�@https://jp.reuters.com/article/column-apps-idJPKBN1ZY0CI
�@�ȉ����p
�@��T�̂�����A�����E���s�s�̘H��ɏZ�����l���W�܂��č����Ă����B�����ȃh���[�����߂Â��ċ�~����ƁA�b���n�߂��B
�@�@
�u�����ǂ��L�����Ă���Ƃ��̉��O�����͋֎~����Ă��܂��v�h���[�����琺������B�u�������Ă��܂���B��������߂č����������𗣂�Ȃ����v�A�u�q�ǂ�����A�h���[�������Ă͂����܂���B��������ɍ����������悤�Ɍ����Ȃ����v�B
�@�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��}�~�Ɍ������h���[���́u�n���I�Ȋ��p�@�v���ƒ������Y�}�n�p�����O���[�o���E�^�C���Y�������̓���́A�C�O�̑����̐l�X�ɂƂ��Ă͖����̃f�B�X�g�s�A�i�Í����E�j�̂P�V�[���ɉf�邩������Ȃ��B
�@�������������{�w�������A������ւ�ׂ����Ƃƍl���Ă���͖̂��炩���B����͒����̃\�[�V�������f�B�A�Ŋg�U����A�p�ꃁ�f�B�A�ŊC�O�ɂ��Љ�ꂽ�B
�@���̈ꌏ�́A�Q�̏d�v�Ȃ��Ƃ������Ă��������B��P�ɁA�����͂������i����g���ĐV�^�R���i�E�C���X�̊����g���H���~�߂悤�Ƃ��Ă��邾���łȂ��A������@�ɐ��E�ꍂ�x�ȊĎ����Ƃł��鎩��̔\�͂��������A�֎�����\�����\���ɂ���Ƃ������Ƃ��B
�@��Q�̓_�͌����܂ł��Ȃ����A���^�Ŗ��l�̔}�̂�v���b�g�t�H�[�����A��O�̊Ď������łȂ��A���ړI�ȎЉ���̎�i�Ƃ��Ă��}���ɕ��y�����邱�Ƃ��N���ɂȂ����B���̌X���͓ƍَ�`�I�ȍ��X�ȊO�ɂ��L����\���������A�����`���Ƃ͂��̓_�ɂ��āA����܂œw�͂��Ă�����肸���ƌ��J���Q�����₷���c�_��ϋɓI�ɍs���Ă����K�v������B
�@���@�̎��s��
�@�@�̎��s��x���̐����肢���ς��̍��X�͊��ɑ������߁A���������@�킪���p�����͖̂ڂɌ����Ă���B�����h���łQ���A�ŋߎߕ����ꂽ����̃C�X�����ߌ��h�v�z�̒j�ɂQ�l���n���Ő����ꂽ�����ł́A�댯�ƌ��Ȃ����l����ǐՂ��铖�ǂ̔\�͂ɋ^�₪�����|����ꂽ�B��F���\�t�g�E�G�A�Ȃǂ̎������Z�p���g���ΒǐՂ͂����Ɨe�ՂɂȂ邪�A�����̐l�X��s���ɂ�����̂��ԈႢ�Ȃ��B
�@�č��ł̓J���t�H���j�A�B�̃I�[�N�����h��o�[�N���[�ȂǁA�������̎s�⒬���@���s�@�ւɂ���F���Z�p�̗��p���ւ��Ă���B���ɂ��Ǘ����������Ă���B��n�悪���邪�A�č�����ѐ������E�̑唼�̒n��ł́A�قڋC�t���ꂸ�A�c�_������Ȃ��܂܂ɐV���ȊĎ��Z�p�����X�Ɠ�������Ă���B
�@�����n��Ȃǂł̕ČR�̊����ł́A����𓋍ڂ����^���l�h���[�������N���O�������������Ă���B�č����n�߂����ƂɁA�����͂����Βǐ����邽�߁A�T�E�W�A���r�A��A���u���A�M�i�t�`�d�j�ȂǁA�č�����̃h���[���A�o����������s����������X�ɂƂ��āA�����͕����h���[���̎�ȋ������ɂȂ��Ă���B
�@�č��h���������v��ǁi�c�`�q�o�`�j�͍�N�W���A�W���[�W�A�B�t�H�[�g�E�x�j���O�̕ČR�P���{�݂ŁA�h���[���̏W�c���g���ē���̌����������̏ꍇ�͎s���ɂ̑z�肾�������̓���̑Ώۂ������A�Ď�����Ƃ����ŐV�Z�p���I�����B�Q�T�O���̃h���[�����������P�l�̃I�y���[�^�[�ɃR���g���[������A���邢�͋@�̂��X�ɓƗ����ē��삷��Ƃ��������Ƃ��\�ɂ���̂��_���B�������������̈ړ����Ď��͈ȑO�Ȃ�s�\�������B
���h���[���Z�p��
�@�����͐��\�N�O����h���[���ƊĎ��Z�p�Ɏ����𓊓����Ă����B�Q�O�P�W�N�A���`�̉p�����T�E�X�`���C�i�E���[�j���O�E�|�X�g�́A�����ڂ⓮���Ȃǂ̒��Ɏ��������l�h���[���ɂ��Ă��A�������J�������ƕ��B�����n�т�A�C�X�������k�ւ̒e���Œm����V�d�E�C�O��������Ŋ��Ɋ��p�����Ƃ����B
�@�����ɂ��ƁA���̃h���[���͗r�̌Q��̏�����Ă��r��������s���̂ɑ����Ȃ��قǂ̐��\���ؖ�����Ă���B�r�͒ʏ�A��s�@�ɔ��ɕq���ɔ�������B�������{�����̋Z�p���J�������F���f�[�^�x�[�X�ȂǁA���̊Ď���i�Ƒg�ݍ��킹�Ďg�����ƍl���Ă���̂͂قڊԈႢ�Ȃ��B�����͑��ɁA�������̕ȂŐl��F������V�X�e���Ȃǂ��J�������ƕ��Ă���B
�@�����A�`���̃O���[�o���E�^�C���Y��������́A���炩�ɐl�Ԃ��R���g���[�����Ă���A���͊g���킩�痬����Ă����B�]�h�Ȃ̕ʂ̓���ł́A�w�l�x�@�������f�����Ńh���[�����g���A�ʍs�l���}�X�N�𒅗p���Ă��邩���`�F�b�N���Ă����B�u�d�b���̃n���T���Ȃ��Z����A�}�X�N�͂ǂ����܂������B�����ĉ�������v�Ɗg���킩��Ăт�����B�u�H�ו������̂��삳���A�}�X�N�𒅂��ĉ������ˁB�������ɋA��ΐH�ׂ��܂���v�B
�@�����������i������ƁA�����h�C�c�̂悤�ȁA���Ă̊Ď����Ƃ̂悤�ɁA�������܂��l�Ԃɂ��l�Ԃ̊Ď��ɗ����Ă���悤���B�������͋}���ɕς�����B�l�H�m�\�i�`�h�j�̃A���S���Y���ƁA�ߋ��ɒ~�ς��ꂽ�c��ȃf�[�^�̑g�ݍ��킹���^�[�Q�e�B���O�L������ς������͎̂��m�̎������B
�@�O���[�o���E�^�C���Y�ɂ��ƁA�t�߁i�������j�̍Â������~�ɂȂ�A����ɂ����钆���̐l�X�ɂƂ��āA���s�s�̓���͊i�D�̌�y�ƂȂ��Ă���B���悪�{�����ǂ����͕ʂ̖�肾���A���E�����v������葁���A�����悤�ȉۑ�ɒ��ʂ��邩������Ȃ��B
*****************************************************************
�@���p�ȏ�
�@���������h���[���Ď��Љ�́A������A���{�≢�B�ɂ��g�傷�邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��������B�Љ�S�̂Ɋi���ƍ��ʂ̌Œ肵���Љ�ł́A�K����ӂ̐l�X�ɖ������������A����̂Ȃ�������܂��Ă䂭�B
�@�������i�ŁA���������s���E����}�������Ȃ�A�Ŋ��͕K���e���\���Ɍ������̂��l�ԎЉ�̖@���ł���B
�@�Œ肳�ꂽ�����K�����ꋉ�����́A�����|�����Ƃ����e�����|���B���ځA�l���_����e�����Y���ł́A�����K���ɂƂ��ē��������Ȃ��̂��B
�@������A�Љ�̌l�I�\����h�����߂̊Ď��ƒe���ɁA���Ă�ő�̗͂𒍂����ƂɂȂ�B����́A���E���œ������ƂȂ̂��B
�@�����A�m���Ă����Ă��炢�������Ƃ́A�{���́A�u�����ʃe���v��헪�Ƃ��ėp���鐭���v�z�͑��݂��Ȃ��B�Ⴆ�A�����≢�B�ʼn��s���Ă��閳���ʎ����e���́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�C�X���G�������T�h���w��ɂ���ƍl����ׂ����B
�@�C�X���G���́A�����n���L�ɋL���ꂽ�u�C�X���G���l�ɖ̒n��^����v�Ƃ��������ɋ�������āA���[�t���e�X�ƃi�C���̊Ԃ̍L��ȓy�n���C�X���G���ɂ���V�I�j�Y���^���i��C�X���G����`�j���s���Ă��āA���̂��߁A���̒n��̐l�X�������e���ɂ���Ēǂ��o�������������Ă���̂ł���B
�@�C�X�����̎�҂��A���T�h�̉A�d���ɂ���Đ��]����A�����e���ɗ��p����Ă���̂��^���ł���B
�@�{���̖����e���Ɏ������͑��݂��Ȃ��B����IRA�̂悤�ȃe�������݂��邾�����B
�@�������A�ǂ���ɂ���A�����K�����e����Q��h�~���悤�Ƃ���A�d�q�@��ɂ��Ď����������A�Z�������x�z��AI����������ɐi�ނ̂͊ԈႢ�Ȃ��B
�@���������d�q�Ď����N�ɗ��v�������炷�̂��Ƃ����A���Ȃ��Ƃ����O�ɂ͗��v�͂Ȃ��B���Y�Ɠ�������낤�Ƃ�������K���ɑ傫�ȗ��v�������炷�����Ȃ̂��B
�@�������A�����������z�ɂ́A�傫�ȗ��Ƃ���������B
�@�Ď��Љ����������A�܂��܂��l�̐l���͂��тɒe������A�Z���̐����͋ɒ[�ɑ��ꂵ���Ȃ��Ă䂭�B
�@����ȋꂵ���Љ��A�l�Ԃ�������悤�Ƃ���v�z���N���オ���Ă���̂����R�̐���s���ł���B
�@������A�����ł��p���ł��A�Ď��Љ�̊�������������Љ�̒������ł��������Ă䂭���Ƃ��������Ȃ��B
�@���Ă̒����̎���́A��E�g��ɑ�\����闠�Љ�̔閧���Ђ������B�Ⴆ�A��O�́A��͍����}�R�Əd�Ȃ��Ă��āA�Ӊ�́A�ǂ�����̓��ڂ������B
�@�ʏB�����E�싞�����̑�s�E�̖��ߎ҂͏Ӊ�������B
�@�Ď��Љ�̔w��ł́A�ĂсA�Ӊ�̂悤�Ȑl�����̂��オ���Ă���K�R��������A�����l�́A�\�̊Ď��Љ�ɏ]���t�������Ȃ���A���́A���̔閧���ЂɋA�˂���Ƃ����悤�Ȑl���𑗂�҂��������邱�Ƃ��낤�B
�@
�@����ɁA�Ē��R���Փ˂��N����A�ŏ��ɁA�����Ƃ��ɁA�K��EMP�j���e�����400Km�Ŕ��������A����̓d�q�@������ׂĔj��Ƃ��납��푈���n�܂�̂ł���B
�@�������A���{���ł�EMP���������邱�Ƃ��낤�B
�@EMP�����̏u�Ԃ���A�R���s���[�^�@��AAI�@��A�Ď��@��́A���ׂĔj���B�{���ɐ��g�̐l�Ԃɂ�����E���ȑO�̐푈�ɖ߂邱�ƂɂȂ�B
�@���̂Ƃ��A�͂����Ē������Y�}�́A�ǂ̒��x�̎��͂��ł���̂��A�ɂ߂Ėʔ��������ł���B
�@�����炭�A���Y�}���R���A�����ɂ���Ċ��S�ɕ��s�������Ă���̂ŁA�������Ƃꂸ�ɑ卬���Ɋׂ�̂ł͂Ȃ����낤���H
�@���݂̒����̐푈�V�X�e���́A��l���q����ŁA�����̒j�q�����Ȃ��Ȃ����Љ�̂Ȃ��A�قڃR���s���[�^�Ɉˑ��������Ă��āA�R���s���[�^��Ď��@�킪�j�ꂽ�Ƃ��A�����N����̂��H�@�l���Ă݂�����B
http://tokaiama.blog69.fc2.com/blog-entry-1019.html
http://www.asyura2.com/18/reki3/msg/888.html



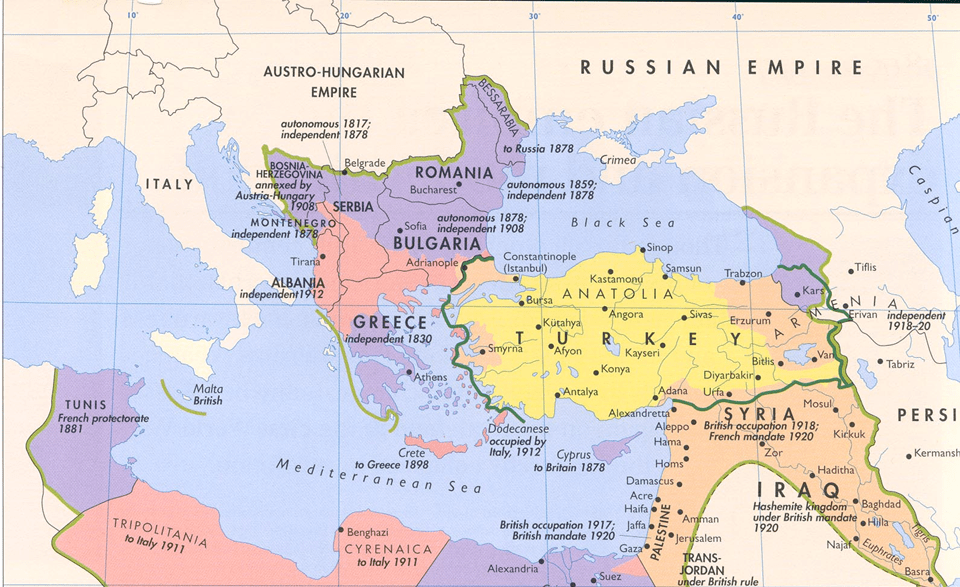
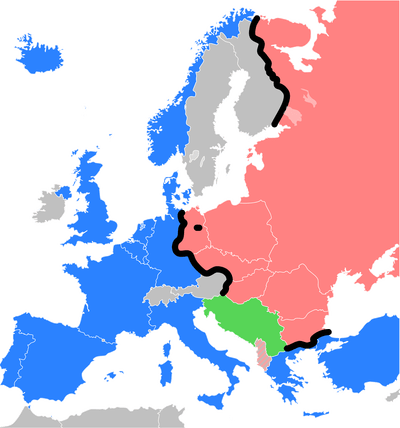

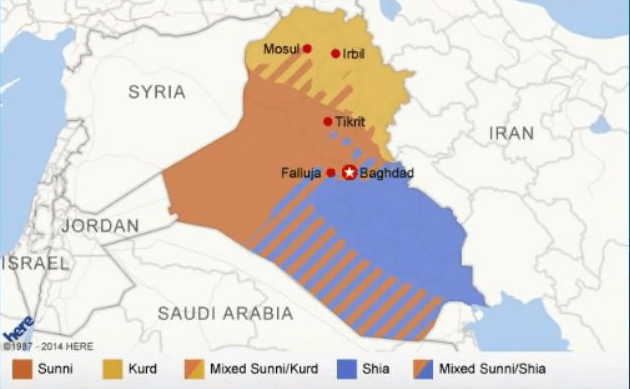

 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B