�p���X�`�i�̌����߂��ނT���P�W���́u�z�{�L�̒n���V�v
http://kenpo9.com/archives/3755
2018-05-21�@�V�ؒ��l�̃u���O
�@���N�̓C�X���G�������V�O�N�ł���A���̓����j���ăg�����v�哝�̂͂T���P�S���ɕč���g�ق��G���T�����Ɉړ]�����B
�@�Ƃ��낪���̓��̓p���X�`�i�l�ɂƂ��Ă͕s�K�̓��������B
�@�p���X�`�i�̍R�c�f�����N����]���҂��o���B
�@�������A���̍R�c�͒e������A�C�X���G���͍R�c�҂Ɏ��e���������ޖ\���o���B
�@�]���҂̌��t���ɁX�����B
�@�u�������̓C�X���G���̃I���ɕ����߂��Ă���B�R�c����p�𐢊E�ɒm�点�����v�i��w�j
�@�u�C�X���G���̕s���`�͋����Ȃ��B������Ď���ł��\��Ȃ��v�i�e�����ď��t��ōR�c���鏭�N�j
�@���̃p���X�`�i�̌�����A�����V���̕z�{�L���ҏW�ψ����T���P�W���̎��ʁu�z�{�L�̒n���V�v�ŗJ���A�߂��B
�@�u�C�X���G���̎x�z���ɐ�����p���X�`�i�l�́A���킢�����ɁA�ƌ������t�����Ȃ��v�ƁB
�@������������Ŕނ͑�����B
�@������������ăg�����v�����̓p���X�`�i���������ƊJ������B
�@�C�X���G���̉ߏ�ȕ��͍s�g�𐢊E�����ɂ��Ă���̂ɁA�č������͕ʂ��ƁB
�@�č��̑I���̓��_���c�̂ɂɂ�܂��Ɠ��I���낤���Ȃ�B
�@������ł܂イ�ł��H�ׂ��悤�ɁA�I���ɃC�X���G����i�삷�鐭���Ƃ��ڂɂ��̂��ƁB
�@���ꂪ���卑�ł���č��̔߂������i���ƁB
�@�����Ă���ɑ�����B
�@�V���A�֘A�̍��A���ۗ����c�ĂɃ��V�A�͂P�Q������ی����g�����ƕč��͔��邪�A���̕č��̓C�X���G���֘A�̌��c�ɂS�O��ȏ㋑�ی����s�g���ė����ƁB
�@���{�̑��V���Ђ̊����W���[�i���X�������ł����܂ŕč��E�C�X���G���̃p���X�`�i�����ᔻ����̂������̂͏��߂Ă��B
�@����قǃp���X�`�i�̌���͍����Ƃ������Ƃ��B
�@�������A�������̃����}�K�œǎ҂Ƌ��L�������̂́A���̌�ŕz�{�L�҂������Ă��ꂽ�V�O�N�O�̖����V���̎А��̎��ł���B
�@�C�X���G���̓Ɨ�����P�X�S�W�N�T���P�U���̖����V���̎А��͂��������Ă����Ƃ����B
�@���_���l���p���X�`�i�Ɍ̍��Č����߂����̂͂����Ƃ������A���̒n�̐l���̑啔�����߂�A���u�l����������Ɛ��͊g������߂Ă���A�u���j�I�Ɍ��āA�p���X�`�i�ɑ���咣�́i���_���A�A���u�j�������ɂ��ꂼ�ꂠ�肤��̂ł���v�ƁB
�@�܂�A�P�X�S�W�N�ɐ��������C�X���G�����F���c�i�p���X�`�i�������c�j���̂��̂��A�C�X���G���E�p���X�`�i�Η��̌��������o�������Ƃ��V�O�N�O�̖����V���̎А����F�߂Ă����̂��B
�@���̐V���̎А��͂ǂ������Ă������A����Ƃ������Ȃ������̂��A����͒m��Ȃ����A�����V�����������̌��c�ɔᔻ�I�������͂����Ȃ��B
�@�݂ȁA���̂P�X�S�W�N�̍��A���c�����̌�̒�����ɂƂ��Ė����͂���c�ł���������m���Ă����͂����B
�@�����ĕz�{�L�L�҂͏����Ă���B
�@���ꂩ��V�O�N�o���������́A�u���a�����v�ǂ��납�C�X���G���������V�O�N���j���A�ŁA��Ɖ������p���X�`�i�l�͂V�O�N�O����u��Ж�i�i�N�o�j�v�̋��Ɣ߈��̂V�O�N�������ƁB
�@���̐�]�I�Ȋi���͕č��̉��S�Ȃ��ɂ͉����ł��Ȃ��ƁB
�@�Q�O�O�P�N�̕ē��������e���̎�d�҃E�T�}�E�r�����f�B���e�^�҂́A���@�̈�ɕāE�C�X���G���̃p���X�`�i�e���������Ă����ƁB
�@�ǂ�ȗ��R�ł��e���͋�����Ȃ����A�č��͉䂪�g�����ɉf���悤�ɂ��āA�Ȃ��������������܂��̂��l�����ق��������ƁB
�@�����p���X�`�i���Ō����������̂��ׂĂ��A���̕z�{�L�L�҂̌��t�̒��ɂ���i���j
�z�{�L�̒n���c�F�߂����u�t�]���E�v - �����V�� https://t.co/fTd8hotKDO
— ��� �@�� renzo eaux (@renzaux) 2018�N5��18��
�z�{�L�̒n���c�@�߂����u�t�]���E�v
https://mainichi.jp/articles/20180518/ddm/005/070/019000c
2018�N5��18���@�����V��
�@���킢�����ɁA�Ƃ������t���������Ȃ��B
�C�X���G���̎x�z���ɐ�����p���X�`�i�l�ł���B�đ�g�ق̃G���T�����ړ]�ɔ��������ŁA���҂͂U�O�l�����B
�@������������ăg�����v�����̓p���X�`�i���������ƊJ������B�C�X���G���̉ߏ�ȕ��͎g�p�𐢊E�����ɂ��Ă���̂ɁA�č������͕ʂ��B�����Ȃ���A�P���␥��̉��l�ς��t�]�����p���������[���h������悤���B
�@�t�Z�C�������̃C���N���v���o���B�P�X�X�P�N�̘p�ݐ푈�Ŕs�k�����C���N�͗��N�A�u�č��ɂ��N���v�P���N�̋L�O�s�����s�����B�ČR�Ȃǂ��N�E�F�[�g����������u���`�̐푈�v�̓C���N�ɓ���Ɓu�N���v�ւƋt�]����B
�@�t�Z�C���哝�́i�̐l�j���e���r�ɏo�āA�����^�X�L�̂悤�ȉh�_�M�͂����B������ƏƂꂭ�������Ȃ̂́A���ۏ펯�ɔ����������̉��o�Ə��m���Ă��邩�炾�낤�B
�@�����A�Đ��E�ɂ͂���Ȓp���炢�����̒ɂ݂��Ȃ��悤���B�č��̑I���̓��_���c�̂ɂɂ�܂��ƁA���I���܂܊낤���Ȃ�B������A�ł܂イ�ł��H�ׂ��悤�ɁA�I���ɃC�X���G����i�삷�鐭���Ƃ��ڂɂ��̂��B
�@���̌X�����A�H�̒��ԑI�����T���ĉߔM���Ă���̂��낤�B���卑�́A�����A�߂������i���B�V���A�֘A�̍��A���ۗ����c�ĂɃ��V�A���P�Q������ی����g�����ƕč��͔���B�����A���̕č��̓C�X���G���֘A�̌��c�ĂɂS�O��ȏ�A���ی����s�g���Ă����B
�@�V�O�N�O�A�C�X���G���̓Ɨ���������V���i�S�W�N�T���P�U���j�̎А��͂��������Ă���B
�@���_���l���p���X�`�i�Ɍ̍��Č����߂����̂͂����Ƃ������A���̒n�̐l���̑啔�����߂�A���u�l����������Ɛ��͊g������߂Ă���A�u���j�I�ɂ݂āA�p���X�e�B�i�ɑ���咣�́i���_���A�A���u�j�������ɂ��ꂼ�ꂠ�蓾��̂ł���v�ƁB
�@���̒ʂ肾�B�������A�����ɂ̓C�X���G�����Ɨ��V�O���N���j���A�ŁA��Ɖ������p���X�`�i�l�͂V�O�N�O����u��Ж�i�i�N�o�j�v�̋��Ɣ߈������݂��߂Ă����B���̐�]�I�Ȋi���͕č��̉��S�Ȃ��ɂ͉����ł��Ȃ��B
�@�Q�O�O�P�N�̕ē��������e���̎�d�҃E�T�}�E�r�����f�B���e�^�҂́A���@�̈�ɕāE�C�X���G���̃p���X�`�i�}�����������B�ǂ�ȗ��R�ł��e���͋�����Ȃ����A�č��͉䂪�g�����ɉf���悤�ɂ��āA�Ȃ��������������܂��̂��l�������������B�i���ҏW�ψ��j



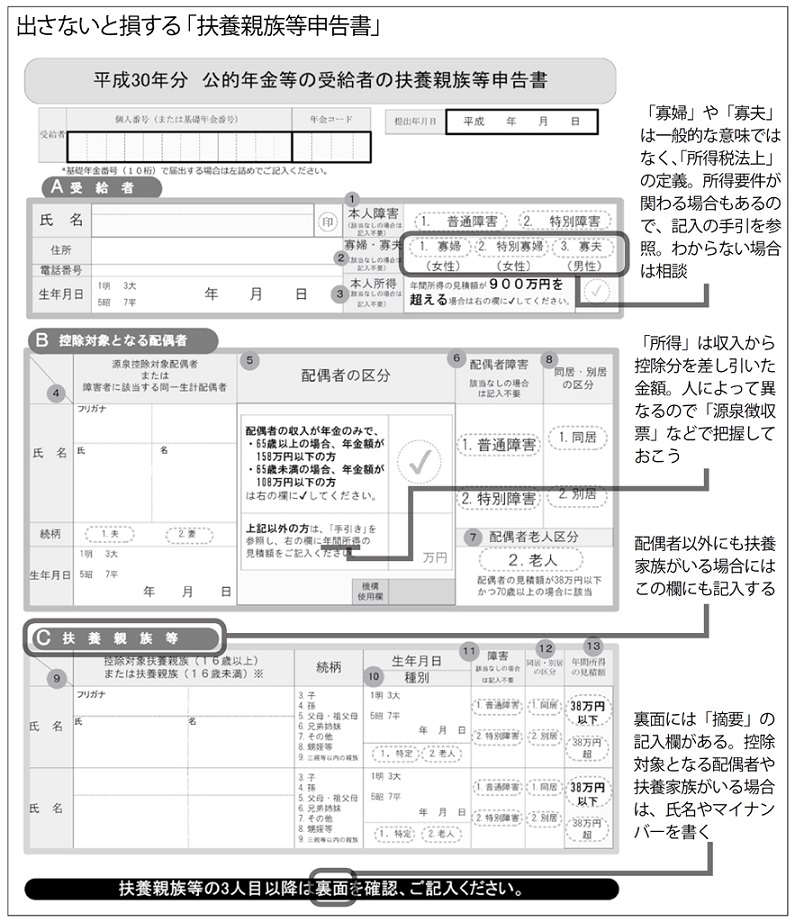
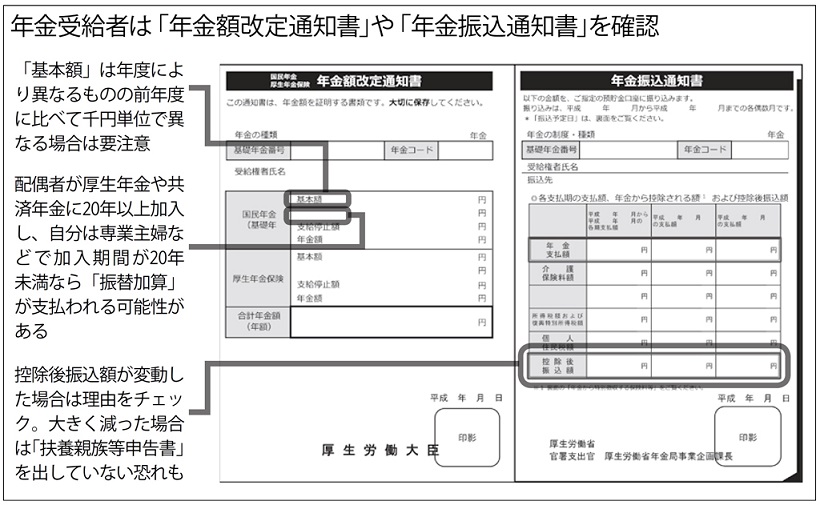

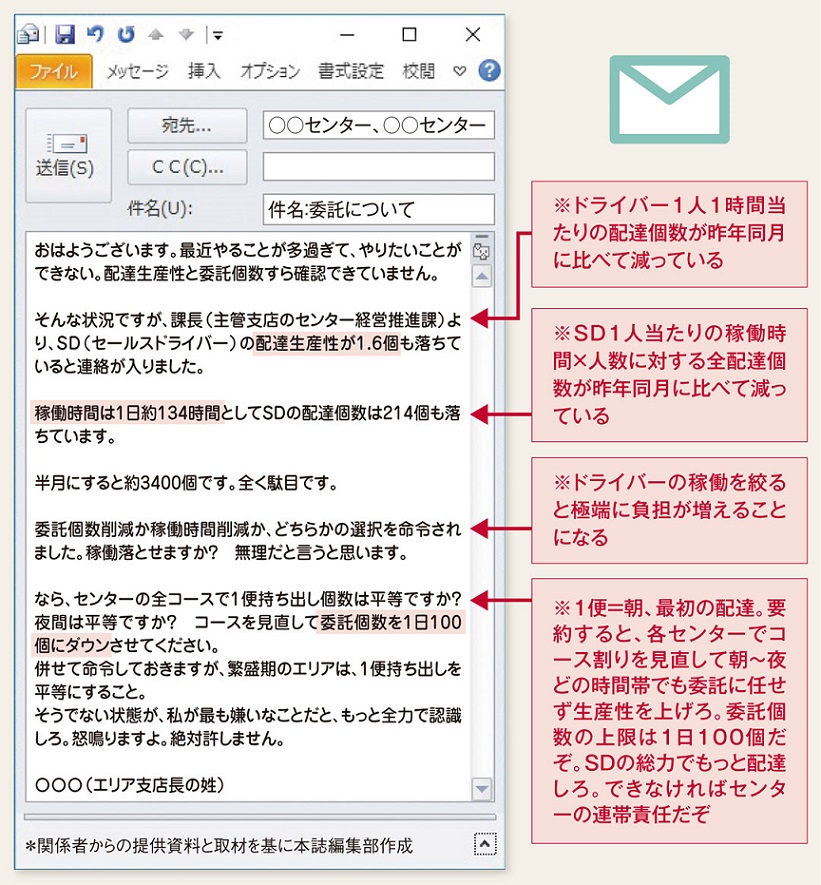

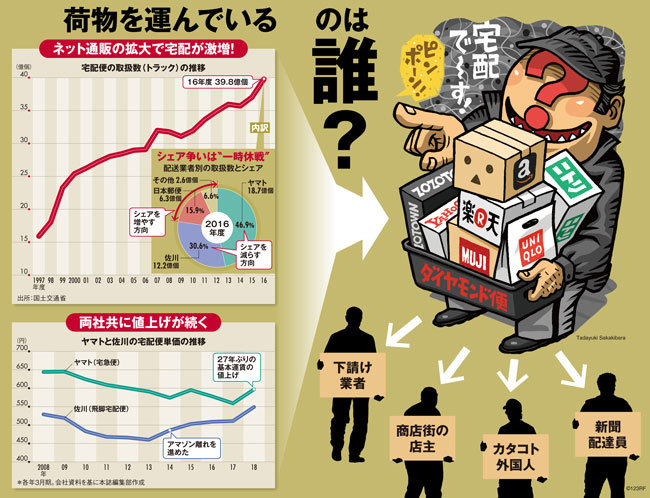
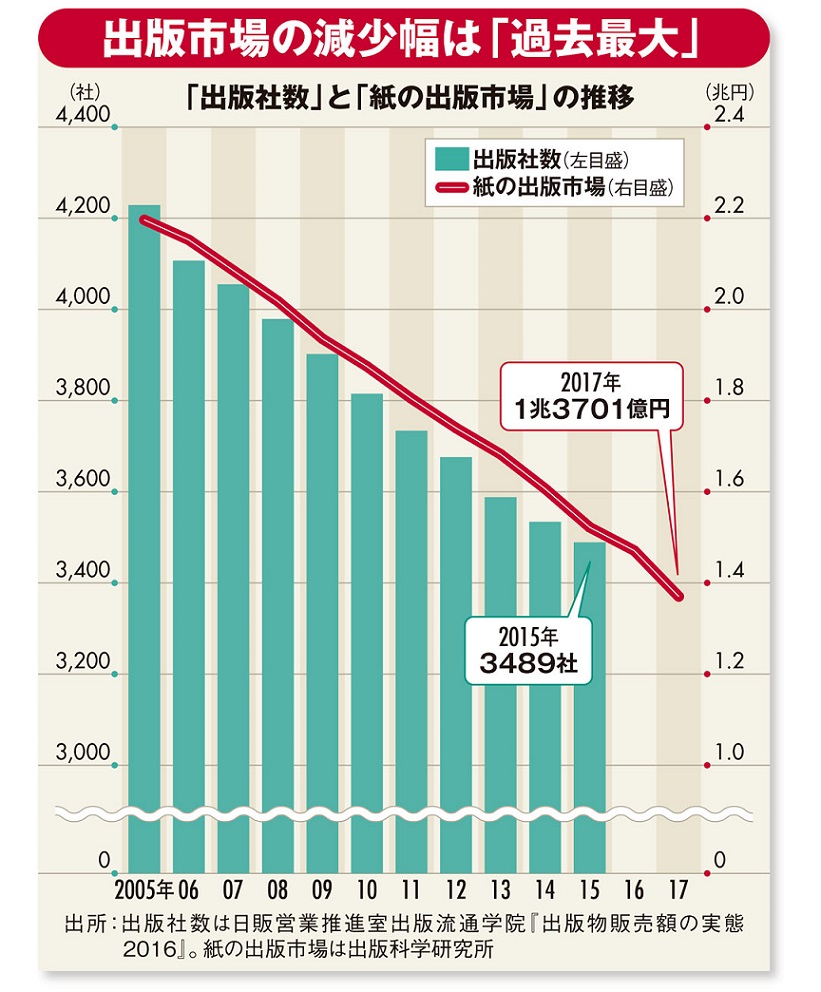


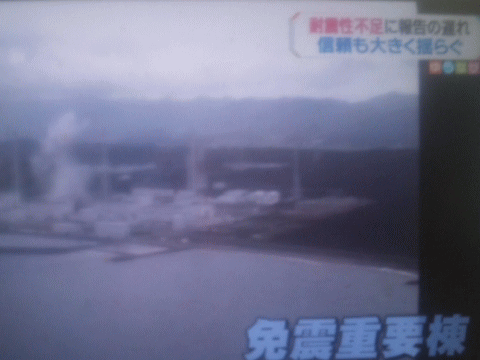
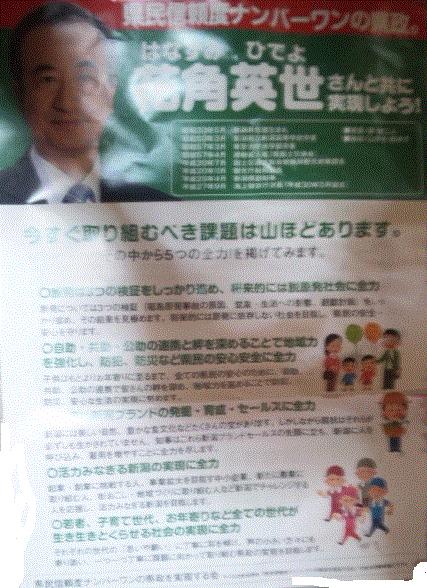
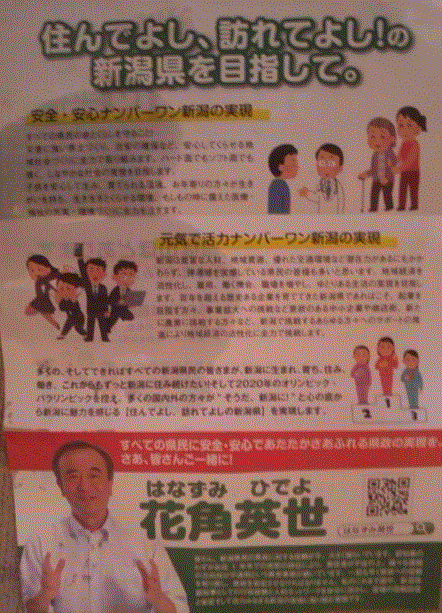
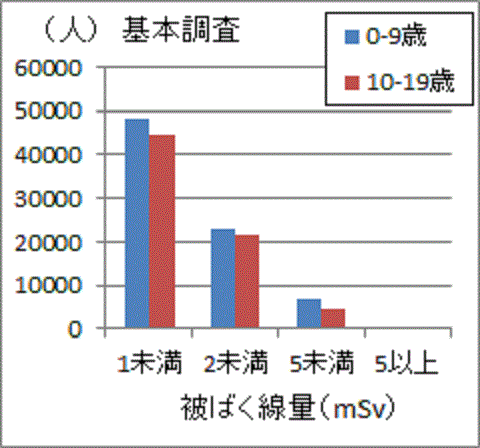
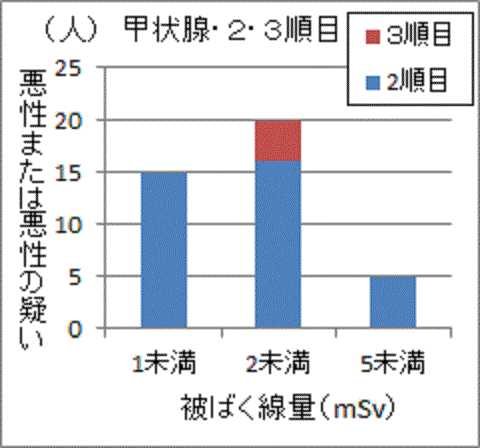
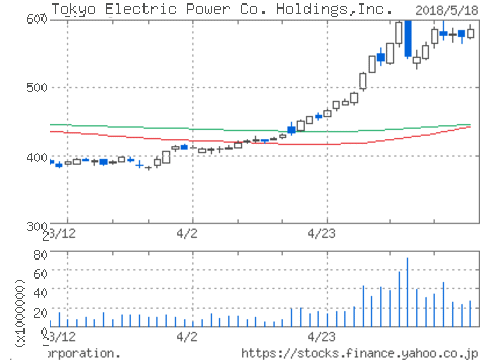

 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B