�o�u���Ƃ͉��������̂��H�@�`���I�L�҂̑����ƃA�x�m�~�N�X�ւ̌x���@���{�̎��s�͂�������n�܂���
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50281
2016.11.24�@�ɓ� ���q�@�W���[�i���X�g�@����r�W�l�X
���o�u���Ƃ͉��������̂�
�����}������1989�N���o�u������̕���ƈʒu�Â���A���łɎl�����I�ȏオ�o�߂����B�߂������Ă��܂��u�ߋ��v�����A����23��̓y�n�̒l�i���S�đS�y�ɕC�G����悤�ȕ��O�ꂽ�M�p�n���̔j��͐��܂����A���{�͈�ߐ��̉ߋ��ɏI���Ȃ��u����ꂽ20�N�v���o������B
���̃o�u��������A��X�͔��Ȃ̂����Ō��������Ă��Ȃ��\�\�B�����f���ĕM��������̂��A���{�o�ϐV���L��OB�̉i�쌒�ł���B
1949�N���܂�B���s��w�@�w���𑲋Ƃ��ē��o�ɓ��Ђ��A�،����L�ҁA�ҏW�ψ��A���o�r�W�l�X�A���oMJ�e�ҏW���Ȃǂ߁A�o�c�T�C�h�ɐg��u���Ă���́A���{�Б�\�A���É��x�Б�\�ABS�W���p����\�Ȃǂ��C�����B
���̉i�쎁���������w�o�u���@���{�����̌��_�x�B�{�l���u���Ƃ����v�ŁA�u�i�삳��́A1987�N����92�N��5�N�Ԃ͂����L�҂ł����ˁv�ƁA��y����g��ώ���h�Ȗ₢���������Ƃ����G�s�\�[�h���Љ�Ă���悤�ɁA�m���Ƀo�u�����A�u���o�̉i��v�́A�G�X�^�u���b�V���ɂ��o�u���a�m�ɂ�������u���A����̗�������������A�X�N�[�v�����ĂA���@�͂ɗD�ꂽ������������̂ł���煘r�L�҂Ƃ��Ēm���Ă����B
��������ɁA�t���[���C�^�[�Ƃ��ăo�u���o�ς̎�ނ𑱂��Ă������́A��q����Ђ��Ȃ����������炻��撊P�ɐڂ��邱�Ƃ��ł����̂����A���̉i�쎁�ɂƂ��āA�����́u�o�u�����ؖ{�v�́A������Ȃ����̂����������Ƃ����B
������́A��s�̋~�ύ�ł�������A���Z������߂��鐬���E���s�̕]���ł�������A�o�u���������I�ɁA���邢�͎���I�ɁA���邢�͊O�����猩�Ă�����̂������悤�ȋC���������炾�B�u�C�~�y�Ȃ̂ł��遄
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@11��18���ɔ������ꂽ�w�o�u���x�B�e���ʂŘb��ɂȂ��Ă���
����y�n�ȂǓ���̎��Y���A���Ԃ���|������ď㏸����o�u���o�ς́A���E�̂�����Ƃ���Ŕ����A�����悤�ȗl����悷����̂́A���̔w�i�́A���̍��̕����E���j�ƕ��G�ɂ���ݍ����Ȃ��琶���邾���ɁA���ꂼ��ɈقȂ�Ƃ����B
�ł́A80�N��㔼�A���{�ɐ������o�u���͉��������̂��\�\�B
�i�쎁�́A�������̕����ƍ��x�o�ϐ������x�������{�Ǝ��̌o�σV�X�e����m�邱�ƂȂ��ɂ͗����ł��Ȃ��Ƃ����A���̃V�X�e�����u�a�{��`�v�Ƃ������炪���o��������Ő�������B�a��Ƃ́A���{�̎��{��`�̕��A�a��h��̂��Ƃł���B
���a�{��`�Ƃ́A���{��`�̋��~������{�I�ɗ}�����A�C�O����̌��������{�ƕ����̍U���������A���{�Ǝ��̃G���[�g�V�X�e����������
���̃V�X�e���́A��㕜�����x���A���x�o�ϐ������ɂ́A�呠�i�ȁj�A����i���{���Ƌ�s�j�A�V���S�i�V���{���S�j�̃G���[�g�������A���{�o�ς̎i�ߓ��ƂȂ��Č����A�u�W���p���E�A�Y�E�i���o�[�����v��搉̂����B
�����A80�N��㔼�A�ϗp�N�����߂��ċ@�\���Ȃ��Ȃ�A�G���[�g�������O���[�o�����Ƌ��Z���R���̔g�ɏ��x��A�\�����v�Ɏ��g�܂��A�c���ꂽ�͂�y�n�Ɗ��ɐU����������ʁA�������̂��o�u���������B
�i�쎁�́A�o�u�������������܂ł̃h���}���A�ׂ����ׂ��Ȃ��w�����킦�Ă������E�A���ʂ��̊Â����N���������G�R�m�~�X�g�A���ӔC�ɏI�n���āu�����Ƃ����v�����͔M�S��������������Z�G���[�g�A�Ƃ������e�w�ɕ��L����ނ��A���̃o�u���ɗx��������オ��҂����ɂ��ڂ������A������T�����B
���A�x�m�~�N�X�ɂ��x����炷
�u���Ȃ��́A���o�̉i�삳��ɉ�ׂ����v
���ɂ������߂��̂́A�{���Łu�Z�F��s�̑�߂̓C�g�}�����������J��肩�v�ƁA�ꍀ�������ďЉ�Ă���o�u���a�m�E���J���_���̑��߂������B
���J���Ƃ����A�u1����2000���~������̑���t�v�Ƃ���ꂽ�d��ŁA�����́A���ۍq�ƁA�ւ̖ڃ~�V���H�ƁA���c�ό��ȂǑ����̏���Ƃ̊�����߁A�o�c�ɂ��Q���A�ꐢ���r�����B
���́A�������̑��߂Ƃ������Ă���̂����A�ނ̌����Ƃ��邱�Ƃ́A�i�쎁�ɉ���Ĕ[���ł����B�u�d���x������s�v�Ƃ����^�C�g���ʼni�쎁��1�ʊ��̋L���������A�u���̐S�̂ӂ邳�Ƃ͏Z�F��s���v�Ƃ������J���̌��t���Љ�Ă���̂��A89�N6��22���t�Ȃ̂ł��̑O��̂��Ƃ��B6�N��̉i�쎁�͎�������A���M�ɖ����Ă����B
���Z�E�ɂ����Z����ɂ��ʂ��Ĕ����B���������J���̂悤�Ȏd��ɂ��߂Â��M���Ă���B
���̂����ŁA���J�������Ђ��̏���Ƃ����������݂ƂȂ����w�i���A�������Ԏ��̂Ȃ��ňʒu�Â��A�g�����h��T��_��Ȕ��z�ƁA�v�l�\�͂������Ă����B����ɖ��͓I�������̂��`��Řb�肪�L�x�Ȃ��ƁB�ꏏ�ɂ��ĖO���邱�Ƃ��Ȃ������B
��3�́u�����v�̂Ȃ��ŁA�i�쎁�͏��J���̑��A���{�����M�p��s�j�]�̌�������������������A�s���Y���ƌ���ꂽ���Ƃ����閃�������̓n�ӊ쑾�Y�A���ʋƍĕ҂��d�|�����G�a�̏��іƂ������o�u���a�m������������Ă��邪�A���傤�Ǔ���89�N�A���́A�ʐ^���wFRIDAY�x�Ɂu�����j�b�|����忂��w���l���x��`�v��11��ɂ킽��A�ڂ��Ă����B
�܂����������A���J�A�����A�n�ӁA���ю�������グ�Ă��鎞�����������ɁA�i�쎁�́u���Ղ����v�Ɓu���㐫��T��v�l�v�͎h���I�ŁA�ȍ~�A���́A����Ɂu�t���v�ƌĂсA�s�т̒�q�̂���ł���B
�o�u����`�������i�쎁�́A���A�o�u�������o����悤�ȃA�x�m�~�N�X�ɔᔻ�I���B�s����I�ɃR���g���[�����邱�ƂȂǂł��Ȃ�����A�Ƃ����̂����̗��R�ŁA�����{�����̑匩���ɂ́A�i���͎҂ɂƂ��ĕK�v�ȁj�u�������v���s�����Ă������Ə����B
�u����ꂽ20�N�v���o�āA���{���u�a�{��`�v����E���āA��O�ȋ��Z���{��`�̍r�g�ɑ����o�������Ƃ����A�K�����������ł͂Ȃ��B���܂��ɋK���Ɗ������v�̎c�����_�u���X�^���_�[�h�𑱂��Ă���A�A�x�m�~�N�X�̊낤���͑�O�̖���u���v���u�V�v�����ĂȂ����Ƃɂ���B
����Ȏ��A���{�̌�����ǂ��l�[�~���O���Ăǂ�ȏ���Ⳃ����������̂��B���ꂩ��́u�t���v�̖����́A�����ɂ���B


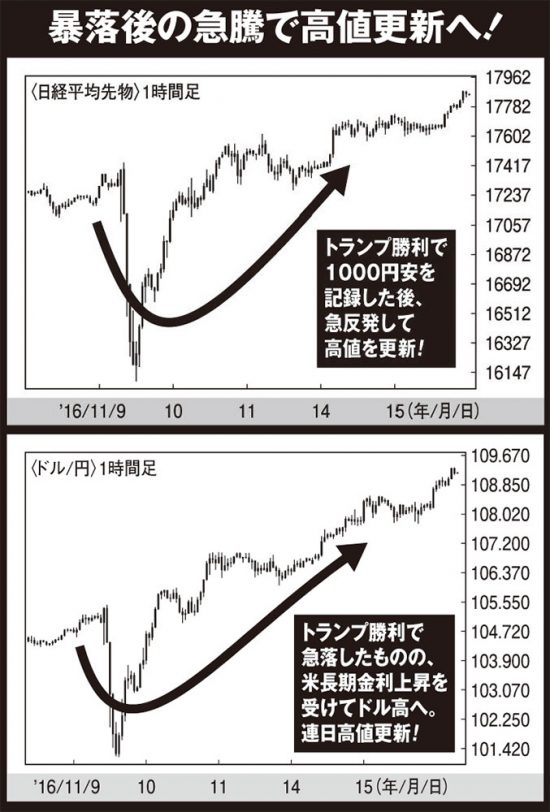
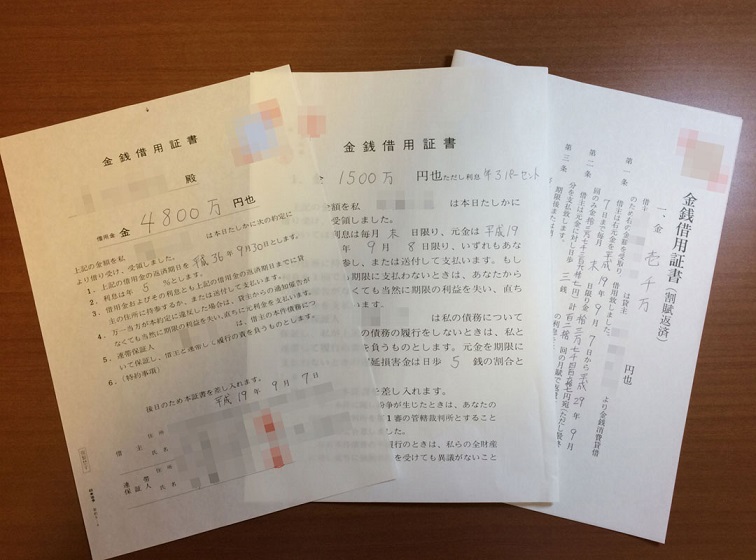

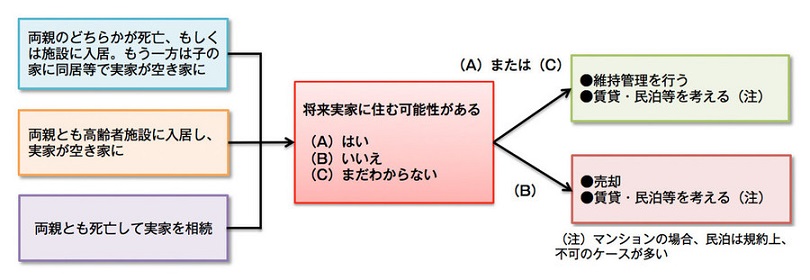
 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B