ƒgƒ‹ƒR‚جƒGƒ‹ƒhƒAƒ“‘ه“—جپi‰Eپj‚ئ‰ï’k‚·‚éƒAƒپƒٹƒJ‚جƒoƒCƒfƒ“•›‘ه“—جپBˆêٹر‚µ‚ؤ—Gکa“I‚بژpگ¨‚ً•غ‚ء‚½پkPHOTOپlgettyimages
‹‹C‚جƒgƒ‹ƒR‚ة•½گg’ل“ھپcƒAƒپƒٹƒJ‚ج"—Gکaگچô"‚ھŒؤ‚رٹo‚ـ‚·ˆ«–²پ@–_‚ب‚«‘خکb‚إگ¢ٹE’پڈک‚ح•غ‚ؤ‚é‚©
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49562
2016”N08Œژ31“ْپiگ…پj ٹ}Œ´ •q•Fپ@Œ»‘مƒrƒWƒlƒX
پ،پuڈlگ³پv‚ھ‘±‚ƒgƒ‹ƒR‚ة‘خ‚µ‚ؤپc
ƒAƒپƒٹƒJ‚جƒoƒCƒfƒ“•›‘ه“—ج‚ھ24“ْپAƒgƒ‹ƒR‚ً–K–₵‚½پB
7Œژ15“ْ‚ة‹N‚«‚½ƒNپ[ƒfƒ^پ[–¢گ‹ژ–Œڈ”گ¶ŒمپAƒGƒ‹ƒhƒAƒ“گŒ ‚ح‚·‚³‚ـ‚¶‚¢ڈlگ³‚ً‘±‚¯‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚¤‚µ‚½ڈَ‹µ‰؛پAƒoƒCƒfƒ“•›‘ه“—ج‚ھ‚¢‚©‚ب‚éƒپƒbƒZپ[ƒW‚ً”‚·‚é‚ج‚©‚ھ’چ–ع‚³‚ꂽپB‚»‚µ‚ؤپA‚»‚ج—Gکa“IپAڈ÷•à“I‚ب“à—e‚ةœ±‘R‚ئ‚µ‚½پB
ƒoƒCƒfƒ“•›‘ه“—ج‚حƒ†ƒ‹ƒhƒDƒ‹ƒ€پEƒgƒ‹ƒRژٌ‘ٹ‚ئ‚ج‹¤“¯‹Lژز‰ïŒ©‚إ‚±‚¤Œê‚ء‚½پB
پgƒAƒپƒٹƒJ‚ح“¯–؟چ‘ƒgƒ‹ƒR‚ئ‚ئ‚à‚ة‚ ‚éپB‰نپX‚جپiƒGƒ‹ƒhƒAƒ“گŒ ‚ض‚جپjژxژ‚حگâ‘خ“I‚إ‚ ‚èپA—h‚邬‚ب‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚éپh
پ–پ@پ–پ@پ–
‚±‚±‚إپAƒoƒCƒfƒ“•›‘ه“—ج‚ج”Œ¾‚ھژ‚آˆس–،‚ًچl‚¦‚é‘O‚ةپAƒgƒ‹ƒR‚إ‹N‚«‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ً‚ـ‚¸‰ں‚³‚¦‚ؤ‚¨‚«‚½‚¢پB
ƒNپ[ƒfƒ^پ[–¢گ‹ژ–Œڈ‚حپAƒGƒ‹ƒhƒAƒ“‘ه“—ج‚ج‹Œ “ژ،پAگ‹³•ھ—£‚جچ‘گ¥‚ة”½‚µ‚ؤگi‚ك‚ç‚ê‚éƒCƒXƒ‰ƒ€‰»گچô‚ً—J—¶‚·‚éˆê•”‚جŒRگl‚ة‚و‚èٹé‚ؤ‚ç‚ꂽپB”½—گŒR‚حژٌ“sƒAƒ“ƒJƒ‰‚جچ‘‰ï‹cژ–“°‚ً‹َ”ڑ‚·‚é‚ب‚ا‚µ‚½‚ھپA–I‹N‚حˆê–é‚ة‚µ‚ؤ’ءˆ³‚³‚êپAƒGƒ‹ƒhƒAƒ“‘ه“—ج‚ح‚·‚©‚³‚¸پg”½‘ه“—ج”hپh‚جژو‚è’÷‚ـ‚è‚ةڈو‚èڈo‚µ‚½پB

‹َ”ڑ‚³‚ꂽچ‘‰ï‹cژ–“°‚ًŒ©ٹw‚·‚éƒoƒCƒfƒ“•›‘ه“—جپkPHOTOپlgettyimages
•ٌ“¹‚ة‚و‚é‚ئپA”ٌڈيژ–‘شگ錾‰؛پAŒRگl‚ً’†گS‚ة‚µ‚½‘ك•كپEچS‘©ژز–ٌ4–œگlپAچظ”»ٹ¯‚⋳ˆُپAٹ¯—»‚ç‚جŒِگE’ا•ْژز–ٌ8–œگlپA•آچ½‚³‚ꂽƒپƒfƒBƒA130ژذپA•آچ½‚³‚ꂽٹwچZ‚â•a‰@‚ب‚ا–ٌ2300ژ{گف‚ة‹y‚ٌ‚إ‚¢‚éپB
ƒGƒ‹ƒhƒAƒ“‘ه“—ج‚حپAچف•ؤ‚جƒCƒXƒ‰ƒ€‹³ژw“±ژزƒtƒFƒgƒtƒbƒ‰پ[پEƒMƒ…ƒŒƒ“ژt‚ًژ–Œڈ‚جپuچ•–‹پv‚¾‚ئ‚µپA‚»‚جژxژژز‚ًژو‚è’÷‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئژه’£‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
ٹwچZ‹³ˆç‚ة—ح‚ً“ü‚ê‚ؤ‚«‚½ƒMƒ…ƒŒƒ“ژt‚جژxژژز‚حƒgƒ‹ƒRگ•{‚ة‚©‚ب‚èگZ“§‚µ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚¾پB‚µ‚©‚µپAƒMƒ…ƒŒƒ“ژt‚جژxژژز‚ًƒNپ[ƒfƒ^پ[–¢گ‹ژ–Œڈ‚ة—چ‚ك‚ؤڈlگ³‚·‚邱‚ئ‚حپu–‚ڈ—ژë‚èپv‚إ‚ ‚èپA–¯ژهژه‹`‘جگ§‚ة‚¨‚¢‚ؤ‹–—e‚³‚ê‚邱‚ئ‚إ‚ح‚ ‚蓾‚ب‚¢پB
–ˆ“ْگV•·‚ج14“ْ’©ٹ§‚ةŒfچع‚³‚ꂽپƒƒgƒ‹ƒRپ@ڈlگ³‘±‚پ^چ‘–¯پu‚¢‚آژ©•ھ‚ھپvپ„‚ئ‚¢‚¤‹Lژ–‚حƒgƒ‹ƒRچ‘“à‚جƒ€پ[ƒh‚جˆê’[‚حˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ة“`‚¦‚ؤ‚¢‚éپB
پuپwژ©•ھ‚ھگ•{‚ج‚ا‚ٌ‚بƒٹƒXƒg‚ةچع‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©•ھ‚©‚ç‚ب‚‚ؤ•|‚¢پxپBŒ»چفٹOچ‘‚ة•é‚炵پAژ–Œڈ“–ژ‹Aڈب’†‚¾‚ء‚½30‘م‚جƒgƒ‹ƒRگlڈ—گ«‚حپAڈoچ‘ژ‚ة‹َچ`‚إچS‘©‚³‚ê‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚ئ’…‘ض‚¦‚â‰؛’…‚ً‚½‚‚³‚ٌژژQ‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤پBژہچغ‚ةپAƒMƒ…ƒŒƒ“ژtژxژژز‚¾‚ئ‹^‚ي‚ê‚ؤ—·Œ”‚ًژو‚èڈم‚°‚ç‚êچS‘©‚³‚ê‚éژs–¯‚ھڈo‚ؤ‚¢‚é‚©‚炾پv
ƒgƒ‹ƒR‚إگi‚ٌ‚إ‚¢‚邱‚ئ‚حپA”½گŒ ‚ج‰è‚ًˆê‘|‚·‚éپg‹°•|گژ،پh‚ج‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚éپBƒGƒ‹ƒhƒAƒ“‘ه“—ج‚حژ–Œڈ‚ًپuگ_‚©‚ç‚ج‘،‚蕨پv‚ئŒؤ‚ٌ‚¾‚»‚¤‚¾‚ھپA‚±‚جƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO‚إژ€ŒYگ§“x‚ج•œٹˆک_‚ھڈo‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚حژہ‚ة•s‹C–،‚إ‚ ‚éپB
پ،ƒzƒڈƒCƒgƒnƒEƒX‚جپu‘إژZپv
ƒoƒCƒfƒ“•›‘ه“—ج‚جƒgƒ‹ƒR‚ض‚جپu—h‚邬‚ب‚¢ژxژپv‚ح‚±‚¤‚µ‚½ڈَ‹µ‰؛‚إ•\–¾‚³‚ꂽ‚à‚ج‚¾پB
•›‘ه“—ج‚جƒgƒ‹ƒR‘طچف’†پi12ژٹشپj‚جŒ¾“®‚حˆêٹر‚µ‚ؤ’لژpگ¨پA—Gکa“I‚¾‚ء‚½پB
ƒgƒ‹ƒRچ‘“à‚ة‚حپAچ،‰ٌ‚جƒNپ[ƒfƒ^پ[–¢گ‹ژ–Œڈ‚حƒAƒپƒٹƒJ‚ة‚¨‚¯‚铯ژ‘½”ƒeƒچپi2001”Nپj‚ة•C“G‚·‚é‚à‚ج‚¾‚ئ‚جژv‚¢‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤پB‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸‰¢•ؤڈ”چ‘‚جƒgƒ‹ƒR‚ض‚جکA‘ر‚جˆسژv•\–¾‚حٹة‚·‚¬‚éپA‚»‚ٌ‚ب•s–‚ً•ه‚点‚éƒGƒ‹ƒhƒAƒ“‘ه“—ج‚ة‘خ‚µپAƒoƒCƒfƒ“•›‘ه“—ج‚حپu‚à‚ء‚ئ‘پ‚ƒgƒ‹ƒR‚ً–K–₵‚½‚©‚ء‚½پv‚ئژك–¾‚µ‚ؤ‚³‚¦‚¢‚éپB
“¯–؟چ‘‚إ”ٌ“‚ê‚é‚ׂ«ژ–‘ش‚ھ‹N‚±‚ء‚½‚ئ‚«پAٹOŒً‚إ‚حپAپudual messageپi“ٌڈd‚جƒپƒbƒZپ[ƒWپjپv‚ً”‚·‚é‚ج‚ھˆê”ت“I‚¾پB“¯–؟‚جٹî–{“I‚ب‰؟’l‚ب‚ا‚ًژ‚؟ڈم‚°‚éˆê•û‚إپA”ل”»‚·‚ׂ«“_‚ة‚حŒ¾‹y‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚â‚è•û‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپAƒoƒCƒfƒ“•›‘ه“—ج‚حŒِ“I‚بڈê‚إڈlگ³پAگlŒ ’eˆ³‚ة‚آ‚¢‚ؤŒ¾‹y‚ًچT‚¦‚½‚ئ‚¢‚¤پB
‚±‚جژ–ژہ‚ح‰½‚ًˆس–،‚·‚é‚ج‚©پB•ؤژ†ƒEƒHپ[ƒ‹پEƒXƒgƒٹپ[ƒgپEƒWƒƒپ[ƒiƒ‹پi“dژq”إپj‚حژں‚ج‚و‚¤‚ة•ھگح‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
پgƒoƒCƒfƒ“ژپ‚جژpگ¨‚حƒzƒڈƒCƒgƒnƒEƒX‚ج‘إژZ‚ًژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚éپBڈd—v‚بگي—ھ“I“¯–؟چ‘‚إ‚ ‚èپA–k‘هگ¼—mڈً–ٌ‹@چ\پiNATOپj‚جƒپƒ“ƒoپ[‚إ‚ ‚éƒgƒ‹ƒR‚ئ‹ظ–§‚بٹضŒW‚ًˆغژ‚·‚邱‚ئ‚حپAƒGƒ‹ƒhƒAƒ“گŒ ‚ج–¯ژهژه‹`‚©‚ç‚جˆي’E‚ة‘خ‚µ‚ؤŒµ‚µ‚¢ژpگ¨‚ًژو‚邱‚ئ‚و‚èپA•ؤچ‘‚جچ‘‰v‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚و‚èڈd—v‚¾‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپh
ƒgƒ‹ƒR‚حƒMƒ…ƒŒƒ“ژt‚جˆّ‚«“n‚µ‚ً‹‚ƒAƒپƒٹƒJ‚ة‹پ‚ك‚ؤ‚¢‚éپBƒIƒoƒ}گŒ ‚حŒ»ژ“_‚إ‚حپuƒNپ[ƒfƒ^پ[–¢گ‹ژ–Œڈ‚ئƒMƒ…ƒŒƒ“ژt‚ًŒ‹‚ر•t‚¯‚éڈط‹’‚ھ•K—v‚¾پv‚ئ‹‘”غ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
‚±‚ê‚ة‘خ‚µپAƒGƒ‹ƒhƒAƒ“‘ه“—ج‚حپuƒAƒپƒٹƒJ‚حƒgƒ‹ƒR‚ئƒMƒ…ƒŒƒ“‚ج‚ا‚؟‚ç‚©‚ً‘I‚خ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پv‚ئ‹‹Cˆê•س“|‚¾پB‚ـ‚é‚إپg“¥‚فٹGپh‚ً”—‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©‚ج‚و‚¤‚إ‚ ‚éپB
پ،ƒgƒ‹ƒR‚ج’nگٹw“Iڈd—vگ«
‚»‚ê‚إ‚ح‚ب‚؛پAƒgƒ‹ƒR‚حƒAƒپƒٹƒJ‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚±‚±‚ـ‚إ‹‚¢‘ش“x‚ةڈo‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚ج‚©پB
‚»‚جچإ‘ه‚ج——R‚حپAƒgƒ‹ƒR‚ھگ¢ٹE‚جƒoƒ‰ƒ“ƒXپEƒIƒuپEƒpƒڈپ[پi—ح‚ج‹دچtپj‚جچs•û‚إƒLƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒOپEƒ{پ[ƒg‚ًˆ¬‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ً—‰ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB
‚ـ‚½پAƒgƒ‹ƒRچ‘“à‚ة‚حپAƒAƒپƒٹƒJ‚ھƒNپ[ƒfƒ^پ[ٹéگ}‚ج”wŒم‚ة‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‰A–dگà‚ھ—¬•z‚µپA”½•ؤٹ´ڈî‚ھگ·‚èڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚à‹چdژpگ¨‚ًژx‚¦‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚¾پB
ƒgƒ‹ƒR‚حپAƒAƒپƒٹƒJ‚جƒVƒٹƒA“àگي‚ئ‰كŒƒ‘gگDپuƒCƒXƒ‰ƒ€چ‘پiISپjپv‘خچô‚إ•K—v•s‰آŒ‡‚بچ‘‚إ‚ ‚éپB‚ا‚؟‚ç‚ج–â‘è‚à’†“Œ‚ج’پڈکپAگ¢ٹEŒoچدپAچ‘چغژذ‰ï‚جˆہ‘S•غڈلٹآ‹«‚جڈ«—ˆ‚ةژ€ٹˆ“I‚بڈd—vگ«‚ًژ‚آپB
‚¾‚©‚çپAƒAƒپƒٹƒJ’†گS‚جچ‘چغ’پڈک‚ة‹‚¢•s–‚ًژ‚آƒچƒVƒA‚âƒCƒ‰ƒ“‚ب‚ا‚جپuƒٹƒrƒWƒ‡ƒjƒXƒgپiŒ»ڈَ‘إ”jپjچ‘‰ئپv‚ھ‰î“ü‚µپAƒAƒپƒٹƒJ‚ة“G‘خ‚·‚éŒ`‚إƒVƒٹƒA‚جƒAƒTƒhگŒ ‚ًژx‚¦پAژه“±Œ ‚ًژو‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
ˆê•û‚إپAƒAƒپƒٹƒJ‚حƒgƒ‹ƒR“ى•”ƒCƒ“ƒWƒ‹ƒٹƒN‚ج‹َŒRٹî’n‚ةٹj•؛ٹي‚ً”z”ُ‚µپA’†“Œ‚جˆہ‘S•غڈل‚جڈdگخ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚«‚½پBŒ»چف‚حISچUŒ‚پAƒVƒٹƒA‚ج”½ƒAƒTƒhگ¨—حژx‰‡‚جڈoŒ‚‹’“_‚ئ‚µ‚ؤ‚³‚ç‚ةڈd—vگ«‚ً‘‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

ƒgƒ‹ƒR‚جƒCƒ“ƒWƒ‹ƒٹƒNٹî’n‚ةŒf‚°‚ç‚ꂽ‹گ‘ه‚بچ‡ڈOچ‘ٹّپkPHOTOپlgettyimages
پ،ƒgƒ‹ƒR‚ج‘I‘ً‚ھگ¢ٹE‚ًچ¶‰E‚·‚é
ƒgƒ‹ƒR‚ئƒAƒپƒٹƒJ‚جٹش‚ة‚حپAپuچ‘‰ئ‚ًژ‚½‚ب‚¢چإ‘ه‚ج–¯‘°پv‚ئ‚³‚êپAƒgƒ‹ƒR‚âƒVƒٹƒAپAƒCƒ‰ƒ“‚جچ‘‹«’n‘ر‚ةڈZ‚قƒNƒ‹ƒhگl‚ً‚ك‚®‚éçaç€‚à‚ ‚éپB
ƒAƒپƒٹƒJ‚حIS‘|“¢‚ج‚½‚ك‚ةƒVƒٹƒAچ‘“à‚ج”½گ•{ƒNƒ‹ƒhگl•گ‘•گ¨—ح‚ًژx‰‡‚µپA‚±‚جگ¨—ح‚حژہŒّژx”z’nˆو‚ًٹg‘ه‚µ‚ؤ‚¢‚éپBˆê•û‚إپAƒgƒ‹ƒRچ‘“à‚ة‚ح“ئ—§‚ً–عژw‚·ƒNƒ‹ƒhگlگ¨—ح‚ھ‚ ‚èپAƒgƒ‹ƒR‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حچ‘‹«‚ً‰z‚¦‚½ƒNƒ‹ƒhگlگ¨—ح‚جکAŒg‚ح‹؛ˆذ‚إ‚ ‚éپBƒGƒ‹ƒhƒAƒ“گŒ ‚ة‚حپAƒAƒپƒٹƒJ‚جƒNƒ‹ƒhگlگ¨—حژx‰‡‚ح‹ة‚ك‚ؤ‹êپX‚µ‚¢ژ–‘ش‚ئ‰f‚éپB
‚±‚¤‚µ‚½ڈَ‹µ‰؛پAƒGƒ‹ƒhƒAƒ“‘ه“—ج‚حچإ‹كپAƒچƒVƒA‚ئƒCƒ‰ƒ“‚ة‹}گع‹ك‚µ‚ؤƒVƒٹƒA–â‘è‰ًŒˆ‚ض‚جکg‘g‚فچى‚è‚ًژژ‚ف‚é‚ب‚اپAƒAƒپƒٹƒJ‚ض‚ج—h‚³‚ش‚è‚ً‹‚ك‚ؤ‚¢‚éپB
ƒgƒ‹ƒR‚ھƒAƒپƒٹƒJگw‰c‚ة—¯‚ـ‚é‚ج‚©پAƒٹƒrƒWƒ‡ƒjƒXƒgچ‘‰ئ‚ضŒX‚‚ج‚©‚إگ¢ٹE‚جچف‚è•û‚ح‘ه‚«‚•د‚ي‚邾‚낤پB
ƒAƒپƒٹƒJ‚ھƒGƒ‹ƒhƒAƒ“گŒ ‚ةژ¦‚·—Gکa“I‚بژpگ¨پBگ¢ٹE‚ج–¯ژه‰»‚ةŒü‚¯‚½پu“”‘نپv‚ًژ©•‰‚µ‚ؤ‚«‚½ƒAƒپƒٹƒJ‚¾‚ھپA‚»‚جژpگ¨‚ةٹ_ٹشŒ©‚¦‚é‚ج‚حپA’†کI‚ب‚ا‚جچUگ¨‚إ‘ه‚«‚“]ٹ·‚µ‚آ‚آ‚ ‚éچ‘چغ’پڈک‚ً‘O‚ةپA—‘z‚ًŒf‚°‚é—]—T‚ً‚ب‚‚µ‚½—Bˆê‚ج’´‘هچ‘‚جژp‚إ‚ ‚éپB
پ،–_‚ئ‘خکb‚ج‚ ‚¢‚¾‚إ
‚»‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپAƒgƒ‹ƒR‚ج’eˆ³‚ھچ‘چغژذ‰ïڈO’m‚ج’†‚إ•½‘R‚ئگi‚ٌ‚إ‚¢‚邱‚ئ‚ح‹ء‚‚ׂ«‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
ƒgƒ‹ƒR‚حNATO‰ء–؟چ‘‚ئ‚¢‚¤‚¾‚¯‚إ‚ب‚پA‰¢ڈBکAچ‡پiEUپj‚ج‰ء–؟Œَ•âچ‘‚إ‚à‚ ‚éپB‚»‚جƒgƒ‹ƒR‚إگi‚قڈlگ³پi‚¨‚»‚ç‚21گ¢‹I‚ة“ü‚ء‚ؤچإ‘ه‹K–حپj‚ةژ–ژہڈم’¾–ظ‚·‚éچ‘چغژذ‰ï‚جچف‚è•û‚حپA‚ـ‚³‚ة—Gکaگچô‚ئŒؤ‚ش‚ׂ«‚à‚ج‚¾‚낤پB
ƒVƒٹƒA‚©‚ç‚ج“ï–¯‘خچô‚âƒeƒچ‘خچô‚إƒgƒ‹ƒR‚ج‹¦—ح‚ھ•K—v‚بEU‚àƒgƒ‹ƒR‚ً‹‚”ٌ“ï‚إ‚«‚ب‚¢‚ج‚ھژہڈپBEU‚ئƒgƒ‹ƒR‚حچ،”N3ŒژپAƒMƒٹƒVƒƒ‚ض‚جƒVƒٹƒAگl–§چqژز‚ç‚ًƒgƒ‹ƒR‚ض‘—ٹز‚·‚邱‚ئ‚ب‚ا‚إچ‡ˆس‚µ‚½پB
ƒgƒ‹ƒRچ‘–¯‚جEU‚ض‚ج“nچqƒrƒU–ئڈœ‚ًŒ©•ش‚è‚ة‚µ‚½چ‡ˆس‚¾‚ء‚½‚ھپA“ï–¯‘—ٹز‚ئ‚¢‚¤‘[’u‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚حپAچ‘کA‹@ٹض‚âگlŒ ’c‘ج‚©‚çپu“ï–¯•غŒى‚جŒ´‘¥‚ة”½‚·‚éپvپuچ‘چغ–@ˆل”½پv‚ب‚ا‚ج”ل”»‚ھ•¬ڈo‚µ‚½پBEU‚à”w‚ة• ‚ح‘ض‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢ڈَ‹µ‚ة’ا‚¢چ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
ˆہ”{گWژOژٌ‘ٹ‚ئƒGƒ‹ƒhƒAƒ“‘ه“—ج‚ھ–؟—FٹضŒW‚ة‚ ‚é“ْ–{‚à“¯‚¶‚¾پBƒgƒ‹ƒR‚ح“ْ–{‚جژ©“®ژشƒپپ[ƒJپ[‚ب‚اگ»‘¢‹ئ‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‰¢ڈBپA’†“ŒپAƒچƒVƒA‚ض‚جڈd—v‚ب—Aڈo‹’“_‚إ‚ ‚é‚ظ‚©پAŒ´”‚ب‚اƒCƒ“ƒtƒ‰—Aڈo‚ض‚جٹْ‘زٹ´‚ھ‹‚¢چ‘‚¾‚©‚炾پB
‘خٹO—Gکaگچô‚إ‹³‰بڈ‘“I‚ب‹³ŒP‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپAƒCƒMƒٹƒX‚جƒ`ƒFƒ“ƒoƒŒƒ“ژٌ‘ٹ‚ة‚و‚éƒqƒgƒ‰پ[‚ض‚ج—Gکaگچô‚¾‚낤پB
1938”N‚جƒ~ƒ…ƒ“ƒwƒ“‰ï’k‚إ‚ج—ج“y“Iڈ÷•à‚ھƒiƒ`ƒXپEƒhƒCƒc‚ج‘’·‚ًگ¶‚ٌ‚إ‘و2ژںگ¢ٹE‘هگيٹJگي‚ج—vˆِ‚جˆê‚آ‚ئ‚ب‚èپAƒ`ƒƒپ[ƒ`ƒ‹‚ً‚µ‚ؤ‘خ“ئ—Gکaچô‚ھ‚ب‚¯‚ê‚خپuƒzƒچƒRپ[ƒXƒg‚à‚ب‚©‚ء‚½‚¾‚낤پv‚ئŒ¾‚ي‚µ‚ك‚½‚±‚ئ‚ح—L–¼‚إ‚ ‚éپB
ƒgƒ‹ƒR‚ض‚ج—Gکaگچô‚حƒGƒ‹ƒhƒAƒ“گŒ ‚ً‚و‚è‘ه’_‚ة‚·‚邾‚낤پB‚»‚ج‚±‚ئ‚ھگ¢ٹE‚ة‰½‚ً‚à‚½‚ç‚·‚ج‚©پBچs•û‚ً’چژ‹‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB
پ–پ@پ–پ@پ–
گ¢ٹE‚ًŒ©“n‚·‚ئپA—Gکaگچô‚ـ‚ھ‚¢‚جچ‘چغژذ‰ï‚جژpگ¨‚ھ‘خڈغچ‘‚ً‚و‚è‘ه’_‚ة‚µپA‚ـ‚·‚ـ‚·ژ–‘ش‚ًˆ«‰»‚³‚¹‚ؤ‚¢‚éƒPپ[ƒX‚ھ–ع—§‚آپB
“ىƒVƒiٹC‚جٹاٹچŒ ‚ً‚ك‚®‚éچ‘چغ’‡چظچظ”»ڈٹ‚جچظ’è‚ً–³ژ‹‚µ‚ؤ’§”“Iچs“®‚ً‹‚ك‚é’†چ‘پA‰»ٹw•؛ٹي‚جژg—p‚â•a‰@‚ض‚ج‹َ”ڑ‚ًŒJ‚è•ش‚µ‚ب‚ھ‚çژ¸’n‚ً‰ٌ•œ‚·‚éƒVƒٹƒA‚جƒAƒTƒhگŒ پAƒEƒNƒ‰ƒCƒi‚جƒNƒٹƒ~ƒA”¼“‡•¹چ‡Œم‚³‚ç‚ةŒRژ–“I–`Œ¯ژه‹`‚جژpگ¨‚ً‹‚ك‚éƒچƒVƒAپcپcپB
‹ك”NپAپuƒjƒ…پ[پEƒmپ[ƒ}ƒ‹پvپiگV‚µ‚¢ڈي‘شپj‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚ً‚و‚ژ¨‚ة‚·‚é‚ھپA‹Œ ‘جگ§‚ض‚ج—Gکaگچô‚حچ‘چغگژ،‚جƒjƒ…پ[پEƒmپ[ƒ}ƒ‹‚ة‚ب‚ء‚½ٹ´‚ھ‚·‚éپB
‚»‚جŒ´ˆِ‚ًƒAƒپƒٹƒJ‚ة‚¾‚¯‹پ‚ك‚é‚ج‚حƒtƒFƒA‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚µ‚©‚µپAƒAƒپƒٹƒJ‚ھچ،‚à—Bˆê‚ج’´‘هچ‘‚إ‚ ‚èگ¢ٹE‚جچف‚è•û‚ة‘ه‚«‚ب‰e‹؟—ح‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚حژ–ژہ‚¾پB
پu‘ه‚«‚ب–_‚ًŒg‚¦پA‰¸‚â‚©‚ةکb‚¹‚خپAگ¬Œ÷‚·‚邾‚낤پv‚ئٹOŒً‚ج—v’ْ‚ًŒê‚ء‚½‚ج‚حƒZƒIƒhƒAپEƒ‹پ[ƒYƒxƒ‹ƒg‘ه“—ج‚¾‚ء‚½پB
گU‚è•ش‚ê‚خپA‘خکb‚ً‘¸ڈd‚¹‚¸پAƒCƒ‰ƒNگي‘ˆ‚ب‚ا‚إ–_‚ًگU‚è‰ٌ‚µ‚½‚ج‚ھƒuƒbƒVƒ…‘OگŒ ‚¾‚ء‚½پBŒمŒpژز‚جƒIƒoƒ}‘ه“—ج‚ح‹t‚ةپA–_‚ًژè‚ة‚µ‚½‚ھ‚ç‚ب‚¢‘ه“—ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚µ‚ؤپAگ¢ٹE‚حچ¬–ہ‚ج“x‚ًگ[‚ك‚ؤ‚¢‚éپB
پu–_پv‚ئپu‘خکbپv‚جƒoƒ‰ƒ“ƒX‚ً‚¢‚©‚ةگ}‚é‚©پBƒAƒپƒٹƒJ‚ئگ¢ٹE‚ح‹ة‚ك‚ؤ“‚¢ڈَ‹µ‚ة’u‚©‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
ٹ}Œ´•q•F پi‚©‚³‚ح‚çپE‚ئ‚µ‚ذ‚±پj
1959”N•ںˆنژsگ¶‚ـ‚êپB“Œ‹ٹOچ‘Œê‘هٹw‘²‹ئپB1985”N–ˆ“ْگV•·ژذ“üژذپB‹“sژx‹اپA‘هچم–{ژذ“ء•ت•ٌ“¹•”‚ب‚ا‚ًŒo‚ؤٹOگM•”‚ضپBƒچƒ“ƒhƒ““ء”hˆُ (1997پ`2002”N)‚ئ‚µ‚ؤ‰¢ڈBڈîگ¨‚ج‚ظ‚©پAƒAƒtƒKƒjƒXƒ^ƒ“گي‘ˆ‚⃆پ[ƒS•´‘ˆ‚ب‚ا‚ً’·ٹْژوچقپBƒڈƒVƒ“ƒgƒ““ء”hˆُ(2005پ`2008”N)‚ئ‚µ‚ؤƒzƒڈƒC ƒgƒnƒEƒXپAچ‘–±ڈب‚ً’S“–‚µپAƒuƒbƒVƒ…‘ه“—ج(“–ژ)ٹO—V‚ة“¯چs‚µ‚ؤ20ƒ•چ‘‚ً–K–âپB2009پ`2012”N‰¢ڈB‘چ‹ا’·پB‘ط‰p8”NپBŒ»چفپA•زڈWˆدˆُپEژ†–تگRچ¸ˆدˆُپB’کڈ‘‚ةپw‚س‚µ‚¬‚بƒCƒMƒٹƒXپx‚ھ‚ ‚éپB




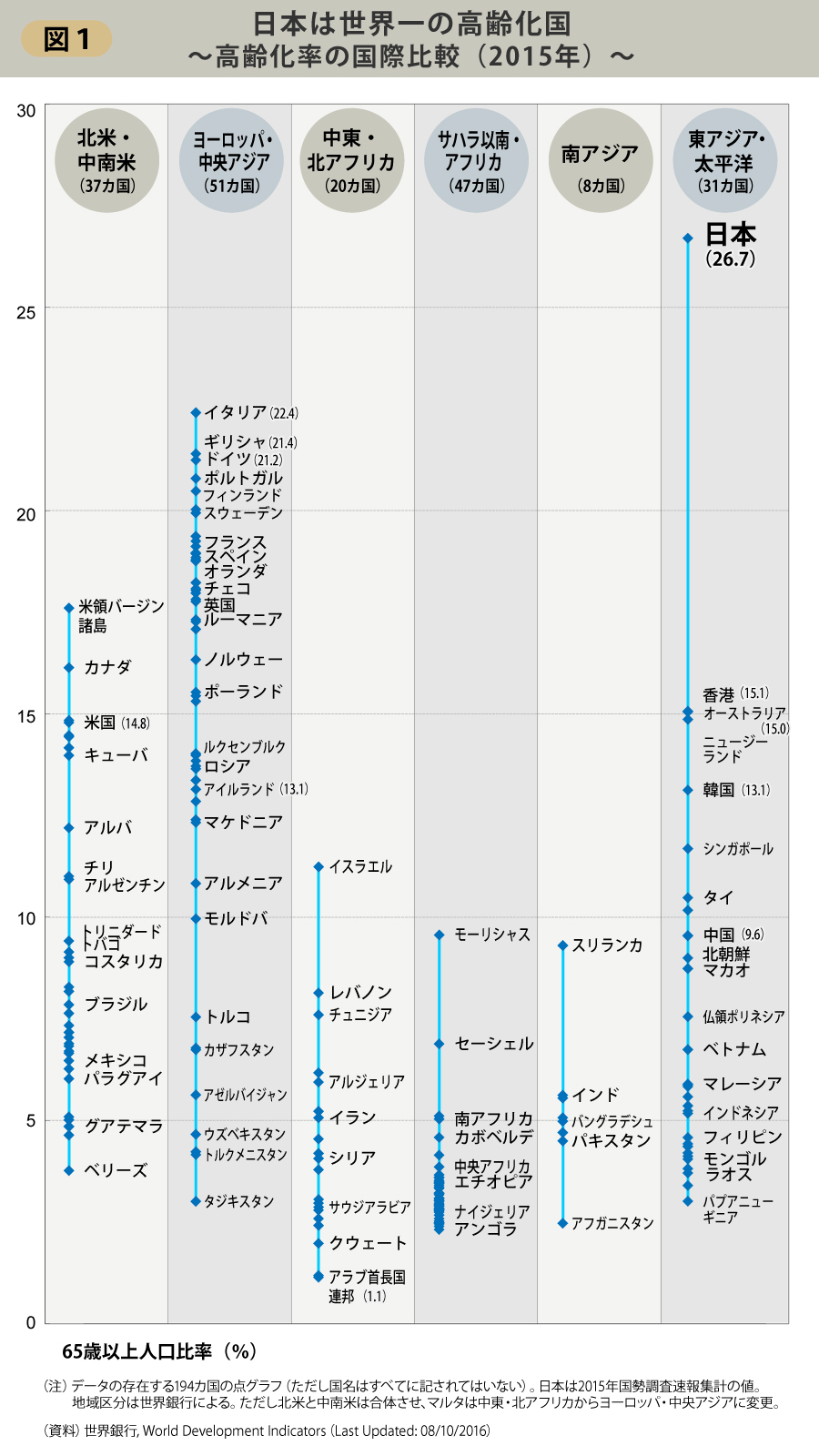
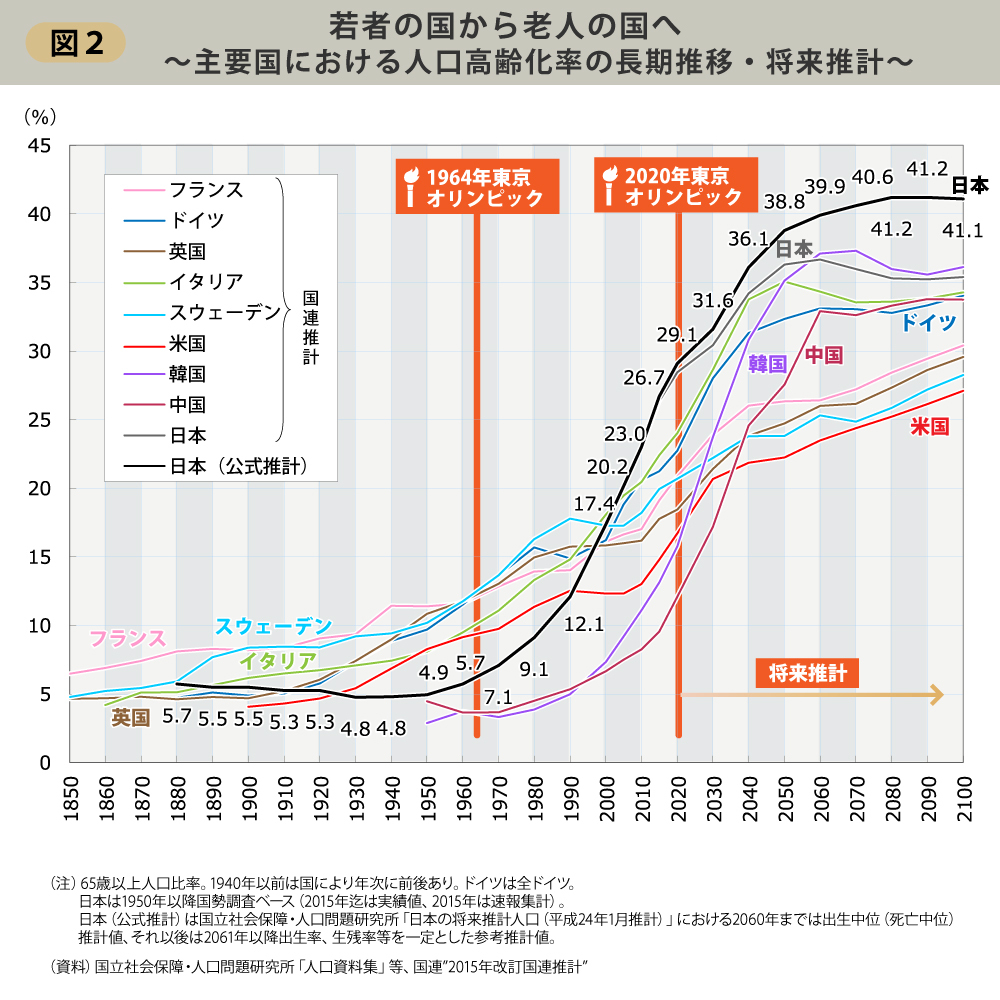
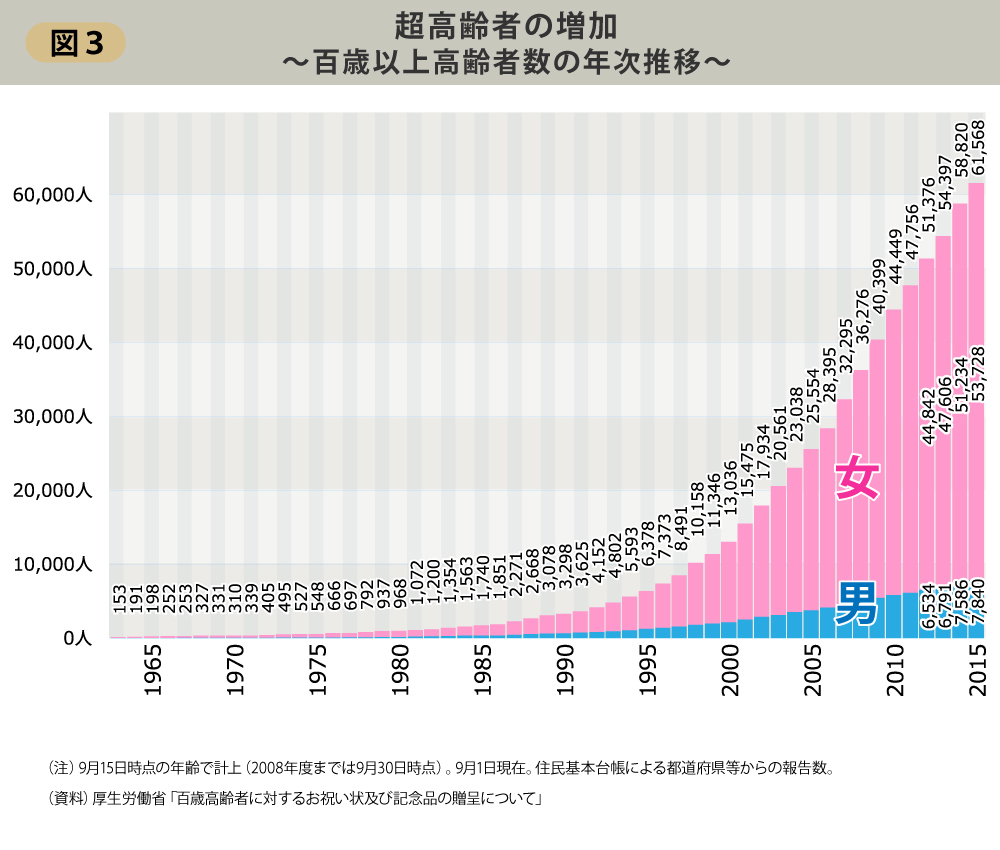
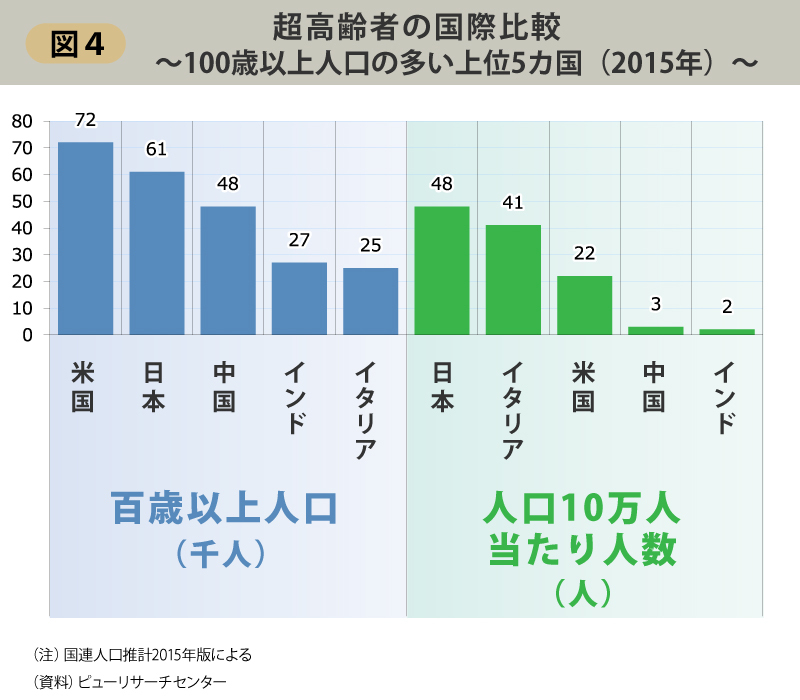


















 پ@‘è–¼‚ة‚ح•K‚¸پuˆ¢ڈC—…‚³‚ٌ‚ضپv‚ئ‹Lڈq‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ@‘è–¼‚ة‚ح•K‚¸پuˆ¢ڈC—…‚³‚ٌ‚ضپv‚ئ‹Lڈq‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB