�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�𑲋Ƃ��A�D�y�s���̈����Ђɐ��Ј��Ƃ��ďA�E�����q���V����i29�A�����j
����13���~�őς�������29�̉ߍ��̌��@������[�������܂�ɂЂǂ��J���̎���
http://toyokeizai.net/articles/-/129359
2016�N08��03���@���c �a�b :�W���[�i���X�g�@���m�o��
����̓��{�́A�K�ٗp�̊g��ɂ��A�����i�����}���ɍL�����Ă���B�����ɂ���̂́A��������n���̃��i�Ɋׂ�Ɣ����o�����Ƃ�����ȁu�n�������Љ�v�ł���B�{�A�ڂł́u�{�N��̕n���v�A�܂�j���̕n���̌ʃP�[�X�Ƀt�H�[�J�X���Ă����B
�t���Z���Ȃ�n�߂��^�Ă̎D�y�ŁA�ŏ��ɕ������͓̂�����悤�Ȑ^�~�̑̌��k�������B
��Ј��̃q���V����i29�A�����j�͐[��ɋA���ƁA�^����Ɍ���̃_�E���W���P�b�g�𒅍��ށB�}�C�J�[�ʋŔ���̃W���P�b�g�������Ă��Ȃ��̂ŁA�{�i�I�Ɋ�����������̂͂ނ��뎩��ɋA���Ă��炾�B2���ɓ���ƁA�����̉��x���X�_��������邱�Ƃ��������Ȃ��B�{���Ȃ�A�����t���̓����X�g�[�u�̃X�C�b�`����ꂽ���Ƃ��낾���A�g�[���ߖ邽�߁A�X�g�[�u������̂͒���30�������ƌ��߂Ă���B
�����āA�R���r�j�Ŕ��������p����2�A�H�ׂ�B�J�b�v���[�����Őg�̂����߂邩�A�h�{�ʂ��l����Ȃ点�߂ĕٓ��ɂ�������̂ɂƎv�����A���������Ԃ��ɂ������A�ٓ��͍����Ƃ����B�Ƃɂ����u�����H�ׂāA�����Q�����v�B�����͂Ƃ����ɗ뎞���߂��Ă��邪�A�������莞���1���ԑ���7�����ɂ͏o���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B��������Ńp���̋܂��S�~���Ɏ̂Ă�ƁA�_�E���W���P�b�g�𒅂��܂܃x�b�h�ɂ����荞�ށB
���Α�10�N�Ŏ����13���~

���̘A�ڂ̈ꗗ��������
���w�Z�𑲋Ƃ��A�D�y�s���̈����Ђɐ��Ј��Ƃ��ďA�E�����B�p�[�g�]�ƈ������킹�Ă��\���l�قǂ̏����ȉ�ЂŁA�q���V����̖����̎���͖�13���~�B�Α�10�N�A���̊Ԃ̏����z�͂킸��5000�~�قǂ��B�����A�c�Ƃ͌���30���Ԃ��������A�c�Ƒ����������L���͂Ȃ��A�L���x�ɂ�����̂��Ɛq�˂��Ƃ��́u�����ɂ͂��������́A�Ȃ�����v�ƌ���ꂽ�B

�C���N���w���ŐL���Ƃ����d�J���Ɍg����Ă������߁A�E�r���������Ȃ���
���Јȗ��A�X�L�[�W�[�Ƃ����w����̓���ȍH��𑀍삵�Ĉ�����ɃC���N��L���d����C����Ă����B�C���N�̔S�x��ʂɂ���čH��̏d����4�`5�L���ɂȂ邱�Ƃ����邵�A�w���̊p�x�₩���鈳�͂ɂ���ăC���N�̏o��ʂ�����Ă���B�d�J���̂����A�_�o���g���d���ł���B�X�L�[�W�[��فX�ƈ����ẮA�����߂����X�B�אg�̑̌`�̃q���V�����A�����r�̉E�r�͍��r�ɔ�ׂĂЂƉ�葾���A�����Ȃ����B
���̉�Ђł̓~�X�������Ј����由�������銵�K���������B�q���V��������А��N�ڂ̂���A�C���N��ɋC�������ɍ�Ƃ�i�߂Ă��܂��A���i�̈ꕔ��p������������Ȃ��Ȃ������Ƃ�����B�ނ͎����̃~�X���ƔF�߂������ŁA���̂Ƃ��͐V�l����ɒǂ��Ă����Ƃ�����A�[���ɊԂɍ��킹��悤�ɂ�������A���C���N�̎c�ʂ��m�F����̂�Y��Ă��܂����Ƃ����B
���̂Ƃ��ɐ������ꂽ��������25���~�B�C���N��ɂ͔�r�I�����C�������͂��������̂ŁA�����牽�ł���������̂ł͂Ȃ����Ƒi����ƁA�����ɂ͂��̊Ԃ̃p�[�g�]�ƈ���̐l������܂܂�Ă���̂��Ɛ������ꂽ�B���̌サ�炭�́A�������̂��тɔ����Ƃ���1���~���x�����������Ƃ����B
�J���҂̃~�X�ɔ������Ȃ����Ƃɂ��ẮA�J����@�Ȃǂŋ�������̈���I�ȓV�����͋ւ����Ă���ق��A���z�ɂ����̏�����݂����Ă���B�������A���Ј��ɗL�x���Ȃ��ȂǂƂ��������ɂ������Ă�100%��@�ł���B�q���V����́u�w�����ȁA�w�����ȂƂ͎v���Ă��܂����B�ł��A�����ȉ�ЂŁA�В����璼�ځg�����͂����������܂肾����h�ƌ�����ƁA�g�͂��h�ƌ�����������܂���ł����v�ƐU��Ԃ�B
��������ߖĂ������͕s�\
����13���~����A�Ƃ��炵�̃A�p�[�g�̉ƒ���Ԃ̃��[���A���M��A�g�ї����Ȃǂ��x�����ƁA�茳�ɂ͂�������c��Ȃ��B�����ł́A�~��̓_�E���W���P�b�g�𒅂ď��邪�A�ď�͉ď�ŁA100�ςŔ������ۗ�܂���̌��ɓ��ĂĂ��̂��B���ݐ��͋߂��̑�^�X�[�p�[�ɍs���Ɩ����Ŏ�ɓ���������ł܂��Ȃ��A�����Ȃǂ͂ł��邾���ܖ������������Ċ���������ꂽ���̂��B���H�ɂ͕ٓ������肵�A���ׂ��Ђ��Ă��a�@�ɂ͍s�����Ɏ��͂Ŏ����B������m�b���i���Đߖ����A�����͂قƂ�ǂł��Ȃ������B
�q���V����̉�Ђ͂�����u���b�N��Ƃ������킯�����A���̂Ђǂ��ɔ��Ԃ����������̂́A���N�ɓ����Ă��炾�Ƃ����B
��Ђ̎�Ȏ����͖k�C�����̎����̂�����c�̂ŁA�����������d���̈ꕔ�𒆍��ȂNJC�O�̈����ȋƎ҂ɊO�����Ă����̂����A�C�O�������̐��i�̎�����������ƁA����悩��N���[�������̂��B���Ƃ����āA�����̑����_����z����悹���Ă����킯�ł͂Ȃ��B���I�ȑg�D����̎d���Ȃ�A���肵�Ă��Ĉ��ȏ�̎��v���ۏႳ���Ǝv��ꂪ�������A�n��������n���Đ��Ƃ͖�����̍��̐���̉��A�����̎����͍̂�����ɂ������ł���A���≺�����Ǝ҂̑��������Ĕ����������̂́A���Ԋ�Ƃ����A�s���{����s�����Ƃ������n�������̂̂ق����Ƃ�������B
���ǁA�l�ߕ���炳�ꂽ�̂͌���̓�����ł���q���V�����������B�C�O�Ǝ҂ɔC���Ă����d���̕��S����C�ɔނ�ɂ̂������邱�ƂɂȂ�A����ɂ��A�����̎c�Ǝ��Ԃ�120�`130���Ԃɋ}�������̂��B���N�ɓ����Ă����2�T�ԋ߂��A���ŏo�������Ƃ����������A���ׂ�38�x�̔M���o���Ƃ����o����悤������ꂽ�B���x�e��15���قǂ�����ꂸ�A�g�C���ɍs���̂��͂������C�̒��A���ς�炸�A�c�Ƒゾ���͕����Ȃ������Ƃ����B
�u�����A�g�̂����邭�āA�d�����������Ďd������܂���ł����v
���t���ς�����[��ɋA��āA���o�c�Ƃ����Ȃ�����7�����ɏo������X�����N�߂������ƁA����Ɂu�ߘJ���v�Ƃ������t�������悬��悤�ɂȂ��Ă����B
���В�����v�����ꂽ�̂́u�����[���v
�^�Ă̎D�y�ʼn�����q���V����͍��F�̃X�[�c�p�Ō��ꂽ�B�����A�A�E�����̐^�����������Ƃ����B�����Ђ�6�������ς��Ŏ��߂��B
�����̏��Ȃ��q���V���A���߂����R���ۂ�ۂ�Ƙb���Ă��ꂽ�B
�ߘJ�����O�̏�Ԃœ����Ă�������Ƃ��A�В����炱������ꂽ�̂��Ƃ����B
�u�����܂ł������Ă���������B�Ƃɂ����[���ɊԂɍ��킹��悤�Ɂv
����10�N�ԁA���߂����Ǝv�������Ƃ͉��x���������B�������A�������y��1�N�������Ɏ��߂Ă������A�q���V�����͓��݂Ƃǂ܂��Ă����B���̗��R���u�����������ȂƂ��낪���邩��v���Ɛ������邪�A����Łu���A�����Ă���V�l���Ƃ藧�������玫�߂悤�v�ƌ��߂Ă����̂ɁA���̐V�l�ɐ�Ɏ��߂��Ă��܂��A���̂܂܂ł͉�Ђɖ��f���������畏����Ă��邤���ɋ@����킵�����Ƃ��������Ƃ�������A�ӔC���̋����Ƃ��������̂��낤�B
�Ȃ��ƌ����āA��Ђʼn߂������Ԃ������̂��ׂĂ��������A���ɂ��̔��N�Ԃ͖������v���œ����Ă����̂ɁA������ꂽ�̂́u�����[���v�ƌ�������̌��t�������B���̂Ƃ��ɁA�����̒��̉����������ꂽ�̂��Ƃ����B
�����ЂƂ̂��������́A�V���ŘA�����m�����J���g���u�����ۂ�N���j�I���v�ɑ��k���������Ƃ������B��Ђ̂�邱�ƂȂ����Ƃ���@�ł��邱�Ƃ��킩�����Ƃ��A�����̂��������悤�ȋC�����ɂȂ����B
���̂Ƃ��A���k���������j�I�����s�ψ��̍��ꐳ�傳��̓q���V����̑���ۂ��u�b�����Ă��Ă��\��قƂ�ǂȂ��āA���_�I�ɂ����낤���Ƃ����ւ�S�z���܂����v�ƐU��Ԃ�B���̂����ŁA�q���V����̓������������͂���ȎЉ�̕��i�������Ă���Ƃ����B
�u�������Ƃقǂ��܂��܂Ȃ�����W�����Ă��āA���[���Ȃ��̖��@�n�тɂȂ��Ă��܂��B�Ǝ���킸�A����Ƃł���A�\���ł͂Ȃ��Ƃ͂����L�x���c�Ƒ���܂������Ȃ��Ƃ������Ƃ͂��܂肠��܂���B����ŁA�i������Ƃ́j�o�c�҂��@���̒m�����Ȃ��Ƃ������́A�g�����ɂ͐l����J�l���Ȃ��B�ł��Ȃ����̂͂ł��Ȃ�����A�d���Ȃ��h�ƊJ�������Ă���߂�����B���ǁA�{���ɂ����H���Ă���̂͂����œ����l�������Ƃ������Ƃł��v
�������ő̏d��4�`5�L��������
�ĂсA�A�����̃q���V����ɘb��߂��B
���ł�ʂ��̂́A���w�Z�̎��ȗ����Ƃ����X�[�c�̓E�G�X�g�⌨��肪�������Ԃ��Č�����B�q���V����́u�����ƍ̐����č�����͂��Ȃ̂ɁB���̔��N�ő̏d��4�`5�L���͗������̂Łv�Ƌ������B
30��ڑO�ɂ����A�E�����͗\�z�ǂ���Ɍ������B5�Ђقǖʐڂ܂ł������������A�����Ԏ��͂��炦�Ă��Ȃ��B����ł��A���������邱�Ƃ��D���Ȃ̂ŁA���x�͈��H�ƊE�œ��������Ɩ������B�K�v�Œ���̉Ƌ���Ȃ�����ɁA�Ȃ������͓炪���������Ƃ��v���o���A���_���������B
�q���V����̂܂��߂��ɕt�����悤�ɂ��������Ȃ����̉�Ђɂ��āA�u�l�ԊW�͌����Ĉ����Ȃ�������ł��B�y�������Ƃ�����܂����v�ƃt�H���[����悤�ȁA�D�����Ƃ��낪����B�В����n�Ǝ҂̈����Ђ́A�������܂߂ă����}���Ȑl�����������������A�l�|���ꂽ��A�\�͂�U���ꂽ�肵���킯�ł͂Ȃ������B�����A������O�̂悤�ɁA�c�Ƒオ����ꂸ�A�L�x�͂Ȃ��ƌ����A���������ꂽ�������A�Ƃ����B
�Љ�l�ɂȂ��Ă�����l���ł������Ƃ͈�x���Ȃ����A�����s���Ɏv���]�T���Ȃ������B�C���炵�ɗ��s�ɍs�������Ǝv�������Ƃ͂��������A���Ԃ��A���J�l���Ȃ������B���܂ň�x���C�O�ɂ͍s�������Ƃ��Ȃ�����A�p�X�|�[�g�͎����Ă��Ȃ��B�������s���A�l���Ă݂�ƒ��w���ƍ��Z���̂Ƃ��ɏC�w���s�ŋ��s�E�ޗǂƓ����ɍs�������肾�B
�ǂ����s���Ă݂����Ƃ���͂���܂����H �Ɛq�˂�ƁA�����l���Ă���A�����������B
�u�s�������Ƃ̂Ȃ��Ƃ���Ȃ�A�ǂ��ł��v
�����������[���A�h���X�Ɂudreams-come-true�v�Ƃ����t���[�Y�����������Ƃ��A�����Y����Ȃ��B
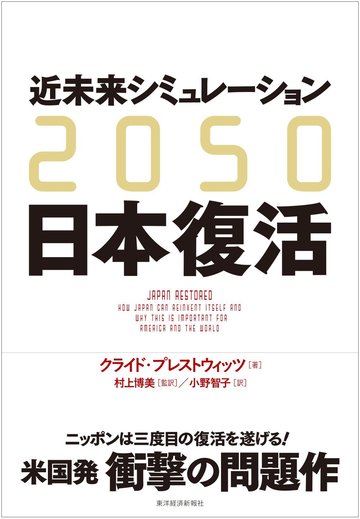
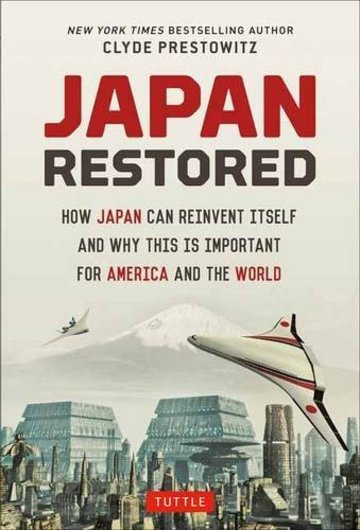

 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B