島野製作所とアップルの争いは「ダビデ(左)とゴリアテ(右)」の戦いか?(iStock)
日本の中小企業がアップルを提訴 裁判ができるのはアメリカだけ?
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160305-00010001-wedge-bus_all
Wedge 3月5日(土)12時20分配信
本年2月15日に、東京地方裁判所で、国際裁判管轄に関する興味深い中間判決が下された。しかも、その被告は、iPhoneやiPadなどで有名な米国のアップル社(Apple, Inc.)である。
■日本の中小企業と世界企業の戦い
「国際裁判管轄」と言われて、読者の中には自分には縁がなさそうだと思った方もいるかもしれないが、そうとは限らない。気付かないうちに、国際裁判管轄についての合意を締結していたり、同意していたりすることがある。
「裁判管轄」とは、ある紛争を、どこの裁判所で解決するか、という問題である。一般には、合意という形で現れることが多い。契約書の終わり近くの条項を注意深く読むと、「本契約に基づき生じた一切の紛争は、XX裁判所を第一審の専属管轄裁判所として解決される」などと規定されていることがある。これが、裁判管轄に関する合意である。
こうした裁判管轄に関する合意は、契約書に限られているわけではない。オンライン・ショッピングを利用する際などに、「注文は規約に同意したものとみなされます」といった文言が書かれているのを見たことはないだろうか。そうした規約の中に、先のような裁判管轄に関する合意が規定されていることがよくある。購入者は、注文を行うことで、ほとんど意識しないうちに、裁判管轄に関する合意を締結しているのである。
こうした(国内的)裁判管轄を国際的な問題に発展させたものが、「国際裁判管轄」である。すなわち、「どこの国の」裁判所で紛争を解決するのか、というのが国際裁判管轄の問題である。もし機会があれば、グローバル企業のウェブサイトなどを訪問し、規約を探してみると面白いかもしれない。国際裁判管轄に関する条項を、多くの場合に見つけることができるであろう。
なお、裁判管轄は、必ずしも1カ所や1カ国にのみ決まるわけではなく、複数の裁判所で裁判を起こすことができる場合がある。この場合には、原則として、裁判を起こす原告が、その複数の裁判所のうちどこで訴えを提起するか選択するのである。
■島野製作所VS アップル社の概要
さて、アップル社が被告となった事件とは、一体どのようなものであったのだろうか。2014年、株式会社島野製作所(「島野製作所」)は、アメリカのアップル社に対して、2件の訴訟を東京地方裁判所に提起した。一方は、アップル社が独占禁止法に違反したということを根拠に、損害賠償を求め、他方は、アップル社が島野製作所の特許権を侵害したということを根拠に、一部のアップル社製品の販売差止と損害賠償を求めた。本稿に関わるのは、このうち、前者の独占禁止法違反に関する訴訟である。
島野製作所は、東京都荒川区に本社を置く、プローブピンという精密部品を製造するメーカーである。訴状によれば、島野製作所は、06年にアップル社のサプライヤーとなり、継続的な取引を行ったが、12年になって発注が停止され、これを再開するため、翌年には減額やリベートにやむなく応じるに至ったとのことである。島野製作所の主張では、こうした取引の停止や減額、リベート要求などが、独占禁止法に違反した、というわけである(なお、訴状の閲覧に際しては、裁判所に赴き、所定の手続きを踏む必要がある。筆者は、本稿執筆のため訴状を閲覧したが、営業秘密にかかわるような部分は大幅に閲覧が制限されている)。
■カリフォルニア州で行われるべき裁判と 主張するアップル
これに対し、アップル社は、独占禁止法違反を否定しただけでなく、この訴訟が、日本ではなく、米国のカリフォルニア州で争われるべき訴訟である、と反論したのである。島野製作所はこれを否定し、日本の裁判所でも解決できる紛争であると主張し、ここに国際裁判管轄の問題が争われることとなった。
カリフォルニアで訴訟追行することになれば、基本的にすべての手続きが同地で行われることになる。カリフォルニアの裁判所に出頭する必要があり、日本企業が手続きを進めていくには、費用も手間もかかる。ここで、割に合わないと判断すれば訴訟を取りやめる可能性も出てくる。相手に負担が大きいことは、裏返せばアップルにとって有利な事情といえる。さらに、地元企業と日本企業が戦っているとなれば、陪審員や裁判官は、地元企業を事実上贔屓するかもしれない。
■「どの国の裁判所で解決するか」国際裁判管轄
冒頭でも述べたが、国際裁判管轄とは、ある紛争を、どの国の裁判所で解決するか、という問題である。多くの場合、それぞれの国の法律に、国際裁判管轄に関する規定が設けられており、日本では民事訴訟法3条の2以降がこれにあたる。この民事訴訟法3条の2以降は、11年の民事訴訟法改正で盛り込まれた条項である。
改正以前はどのように解決されていたかというと、これは「条理」によって解決されていた。条理とは、平たく言えば、社会通念や公序良俗、物事の道理などである。もっとも、全くのフリーハンドで裁判官が判断するわけではなく、過去の判例や類似の規定、外国の裁判例などを駆使して解決することになる。
管轄合意には、「ある国の裁判所に訴えを提起できること」を(単純に)規定する管轄合意と、「ある国の裁判所にのみ訴えを提起できること」を規定する専属的管轄合意がある。後者の専属的管轄合意は、「ある国の裁判所に訴えを提起できること」+「他の国の裁判所に訴えを提起できないこと」の合意と分析できる。以下では、便宜上、前者を「単純管轄合意」、後者を「排除管轄合意」、そして両者を併せて専属的管轄合意と呼ぶことにする。
■「一定の法律関係に基づく訴え」
さて、民事訴訟法3条の7第1項によれば、当事者は、合意によって、いずれの国の裁判所に訴えを提起できるか、を定めることができる(つまり、国際裁判管轄について合意できる)。ただし、こうした合意は「一定の法律関係に基づく訴え」に関して、「書面」でしなければならない(同条第2項)。
民事訴訟法3条の7第1項は、あくまで「いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるか」と規定するのみであり、「いずれの国の裁判所に訴えを提起することができないか」には言及していない。つまり、単純管轄合意ができることだけを定めた規定のようにも見える。
しかし、民事訴訟法第3条の7第4項では、「外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意」(つまり専属的管轄合意)が無効となる場合について言及している。そうすると、排除管轄合意を含む専属的管轄合意を締結することも、民事訴訟法は許容しているようである。そこで、このような専属的管轄合意も、先の「一定の法律関係に基づく訴え」に関して、「書面」でしなければならない旨の要件を満たし、かつ訴えを提起できると定められた国の裁判所が法律上、または事実上裁判ができないような事情がない限り(民事訴訟法第3条の7第4項)、有効と考えられる。
ところで、「一定の法律関係に基づく訴え」とは、どういう意味なのだろうか。平たく言えば、当事者間での紛争について、一定の範囲に限定しなければならないという趣旨だが、それ以上に明確に定義することは、なかなか難しい。ある訴えが「一定の法律関係に基づく訴え」なのかどうかは、具体的な事件を見たうえで、当事者の公平やどのような紛争を対象とするかの当事者が予測できるかどうか、といった事情を考慮して、判断されることになる。
一般的には、「当事者間の全ての紛争」を対象とする合意は、当事者間での紛争に対する限定がないので、「一定の法律関係に基づ」いてはいないと考えられている。一方で、「本契約に関連して生じた紛争」を対象とする合意は、一般的には「一定の法律関係に基づ」いていると考えられている。
最後に、改めて注意喚起しておきたいが、ここで説明した民事訴訟法の条項は、11年改正で盛り込まれたものであり、それ以前は条理によって解決されていた、ということである。
■原告と被告の主張の違い
さて、改めて島野製作所とアップル社の事件に戻ってみたい。島野製作所とアップル社は、部品を供給するに際し、09年にMaster Development and Supply Agreement(「MDSA」)を締結した。MDSAには契約書の一部を構成するいくつかの附属条項が存在しており、そのうちの1つの条項において、当事者間の紛争解決手段が定められた。
当該条項によると、次のように紛争は解決される。
(1) 両社が1名ずつ上級管理職を選出し話合いを行う。
(2) 苦情を申し立てから60日経過しても、(1)で解決できない場合、カリフォルニア州サンタクララ郡又はサンフランシスコ郡の調停での解決を求める。
(3) 調停開始後60日以内に解決できない場合、カリフォルニア州サンタクララ郡の州又は連邦裁判所で訴訟を提起できる。
この(3)は、専属的裁判管轄を定めたものと明記されている。また、この条項全体は、他の書面で合意しない限り、紛争がMDSAから生じた場合や、関係する場合かどうかに関わらず、適用されると規定された。
被告の主張の骨子は、明快である。
(a) MDSAを締結したのは11年の改正以前であり、民事訴訟法第3条の7第2項は適用がない。
(b) 条理あるいは民事訴訟法上、仮に合意を「一定の法律関係に限定する」必要があっても、これは当事者の予測可能性を担保するためのものである。今回の訴訟は、国際裁判管轄が定められたMDSAに基づき生じたもので、契約書とは無関係に起きた訴訟ではないので、予測可能性はあり、この限りで有効である。
一方、原告は、次のように反論した。
(a) 民事訴訟法第3条の7第2項は、新たに何かを作った規定ではなく、元々存在していたルールを明文化したに過ぎないものである。したがって、改正前の合意であっても適用されるものである。
(b) 仮に、適用されないとしても、条理上、国際裁判管轄に関する合意は、一定の法律関係に限定しなければ無効である。
(c) 今回の合意は、一定の法律関係に限定せず、当事者間の全ての紛争に及ぶものだから無効である。
論点は、次の3点に集約できる。
1つ目は、法改正前に結ばれた合意に対して、民事訴訟法第3条の7第2項が適用されるのか。
2つ目は、民事訴訟法第3条の7第2項が適用されないとしても、条理上、国際裁判管轄に関する合意については、一定の法律関係に限定しなければならないのか。
3つ目は、条理上、一定の法律関係に限定しなければならないとしても、MDSAによって生じた紛争については、予測可能性があるとして、例外的に合意が有効なのか。
■中間判決での裁判所の判断
中間判決での裁判所の判断は次のとおりである。
1つ目の論点については、民事訴訟法第3条の7第2項を法改正前の合意に適用することは、法的安定性を害するので、認められないと判断した。つまり、被告の主張を採用した。
2つ目の論点については、国内での裁判管轄に関する合意では、法改正以前から「一定の法律関係に基づく訴え」に関するものである必要があり、この趣旨は国際裁判管轄に関する合意でも同様だと指摘して、条理上は「一定の法律関係に基づく訴え」に関するものでなければならないと判断した。したがって、この点は原告の主張を採用した。
3つ目の論点については、合意を今回の紛争に限って有効とすれば、逆にそれこそが当事者の予測可能性を害する。それゆえ、あくまで合意は全体として無効であると判断した。したがって、この点においても原告の主張を採用した。民事訴訟法の規定は適用できない、としながら、結局、「一定の法律関係に基づく訴え」という民事訴訟法と同じ規律が当てはまる、と結論付けたわけである。
今回の訴えは、合意が無効であれば、日本で裁判を起こすことが可能な訴えであった。中間判決に対し、独立して争う方法はないため、日本で裁判が続けられることが決定したのである。
■中間判決後の実務への影響
さて、中間判決は、重要な2つの判断を行った。1つは、11年の民事訴訟法改正前の国際裁判管轄に関する合意であっても、条理上、現行条文と同様の「一定の法律関係に基づく訴え」に関するものでなければならないと判断したことである。
もう1つは、「紛争がMDSAによるもの、あるいは関係するものかどうかに関わらず」と定めたことを問題視し、「一定の法律関係に基づく訴え」に関するものではないと判断したことである。
契約書などでは、「本契約に関連して甲乙間で生じた紛争」について定めることがごく一般的である。もし、アップル社が、「紛争がMDSAによるものあるいは関係するものかどうかに関わらず」ではなく、「紛争がMDSAによるものあるいは関係する場合には」と限定を付していれば、「一定の法律関係に基づく訴え」だと判断された可能性が高い。他に有効な抗弁がなければ、国際裁判管轄の合意は、おそらく有効であったであろう。カリフォルニア州で裁判を起こさなければならないので、東京地方裁判所に提起された今回の訴訟は却下されることになる。しかし、アップル社は、いわば「欲張って」、そうした限定をせずに規定したことにより、かえって足元をすくわれる結果となってしまったのである。
アップル社がこれまで締結してきた合意には、同じような条項が含まれている可能性が高い。そうした合意全てが、日本での裁判を排除できないということになれば、アップル社にとっての影響は多大なものとなるであろう。アップル社と類似の合意を締結してきたグローバル企業は、自社の国際裁判管轄に関する合意が、日本での裁判を排除できるように規定されているか、一度確認してみる必要があるかもしれない。また、今後の合意締結においては、今回の中間判決を受けて、見直す必要があるだろう。
一方、日本で裁判ができないように規定されている国際裁判管轄条項を見て、裁判を起こすことをあきらめたような日本の企業や個人は、今一度当該条項を確認してみてもよいかもしれない。「一定の法律関係に基づく訴え」でないものであれば、今回の中間判決のように、少なくとも日本の民事訴訟法ではその効力を排除できる可能性がある。
さらに進んで考えると、自分たちに不利な国際裁判管轄条項が、今回のように無限定に定められていた場合、あえて契約交渉時に放置するのも、一手段と考えられる。これが「一定の法律関係に基づ」かないとされれば、無効とできるからである。ただし、これが失敗すれば、きわめて広範な範囲の紛争が、全て日本で解決できなくなるリスクもあり、慎重に対応する必要があるだろう。
なお、本稿は、一切の法的アドバイスを含むものではなく、具体的事件に当たっては、必ず弁護士等法律専門家のアドバイスを求めていただきたい。
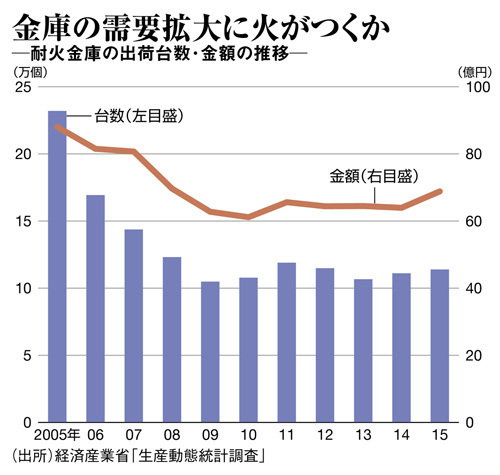
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。