�������u�A�����J�̋��Z�e���v�ɖ{�C�Œ��ݎn�߂��I ���E�̃��[�������߂�̂͒N���l�����̃h���nj��̐��͐�������
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47197
2016�N01��03���i���j �}���q�F�@����r�W�l�X
���A�����J�̊�@��
���ێЉ�̃��[���͒N�����߂�̂��H�@2016�N�͂��̑�e�[�}�̍s����肤��ŏd�v�ȔN�ɂȂ肻�����B
���̉ΊW��邩�̂悤�ɁA�����哱�̃A�W�A�C���t��������s�iAIIB�j���N����25���ɐ������������B�A�����J�x�z�̏ے��ł��鐢�E��s�E���ےʉ݊���iIMF�j�̐��A�h����̐��ւ̒����̒���̑������낤�B
����̃A�����J�ł�11���ɐV���ȑ哝�̂��I�o�����B�A�����J�̓u�b�V���A�I�o�}���������Ŏ��Ă������ێЉ�ł́u�АM�v�����߂���̂��B�����āA���x�����Ȗ����`�w�c�̎w���҂Ƃ��āA���Ȏ咣�����߂郊�r�W���j�X�g�i����ϊv�j���Ƃւ̔��]�U���ɑł��ďo��_�@�ƂȂ�̂��B���N�͂��̕���_�ƂȂ肻���ł���B
���@���@��
�N�̃��[���A�s���l�����u���E�W���v�Ȃ̂��B���̖����߂���U�h�́A�A�����J�Ɖ��B�̑��ΓI�ȉe���͒ቺ�ƁA������V�A�Ȃǃ��r�W���j�X�g���Ƃ̑䓪�ł܂��܂��M��ттĂ���B
���̎���́A�I�o�}�đ哝�̂���N10���A�ē����哱���������m�p�[�g�i�[�V�b�v����iTPP�j��؍��ӂ��ďo�������̐������[�I�Ɏ����Ă���B
�u�O���[�o���o�ς̃��[���𒆍��̂悤�ȍ��ɍ�点��킯�ɂ͂����Ȃ��B�V�������[���͉�X�����ׂ����v
���̔��������Ƃ��A�䂪�����^�����B�哝�̂����R�Ƃ����܂Ō���Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǁA�A�����J�̊�@���͍��܂��Ă���̂��Ƃ����Ӗ��ł��B�o�σ��[�����߂���A�����J����́u���z���v�B�������������~�߂Ă��d���Ȃ����e�ł���B
���{�ł́u��������_�v���r���𗁂тĂ���悤�����A�z���C�g�n�E�X�ɂ���������F���͑S���Ȃ��A�����̌����ɔ����Ă���悤�ł���B
����A�U�߂鑤�̒����̘H���͖������B�K�ߕ��E���Ǝ�Ȃ�2014�N11���A8�N�Ԃ�A�j���x�ڂ́u�����O���H���c�v�ł̏d�v�k�b�ł����i���Ă���B
�u���ۃV�X�e���ƃO���[�o���K�o�i���X�̉��v�𐄐i���A�䂪���ƕ��L���r�㍑�̔����������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��v
�K���̔����̓I�u���[�g�ɕ�������Ȃ���A�ĉ����z���グ�Ă������ۃ��[���𒆍��̍��v�ɉ����悤�ɕς��Ă����Ƃ����錾�ł���A���̎p������s�����Č���Ă���̂���V�i�C���낤�B�����͂����ō��ۖ@�����A�l���������ēƎ��̃��[���Ɋ�Â��u�̊C�v���咣���Ă���B
�������A���̖��͍��ۃ��[�����߂��邹�߂������̓_���猩���ꍇ�A�X�R�̈�p�ł����Ȃ��B�����I�ɂ��d��ȈӖ������̂́AAIIB�̐ݗ��ɂ��A�������č��̋��Z�e���ւ̒�����n�߂����Ƃł���B
�����Z�e���Ƃ����p���[
AIIB�͑n�݃����o�[57�����ŃX�^�[�g�����B���{����1000���h���ŁA�����͂��̂���297���h�����o�����A�c������26.06��������B�r�㍑�𒆐S�ɑ��傷��C���t���������v�ɉ����邱�Ƃ��\�����̐ݗ��ړI�����A�A�����J�̋��Z�e���̊�Ղ�����Ƃ����헪�I�ȑ_���������ɂ��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�O���[�o�����o�ς̈�̓����́A���ێ���̑���ɔ����A���ې����ɂ�������Z�e���̉e���͂�����I�ɑ��債�Ă��邱�Ƃ��B
�A�����J�́A��ʉ݃h�����O���E���ق̓���Ƃ��Ďg�����Ƃ��\���B�h���͍��ێ���̎�v�Ȍ��ϒʉ݂ł���A���̍��ێ���͕ċ��ʂ�����Ȃ����炾�B����A�A�����J�͍��ێ���́u�֏��v�ł���A���̖�����A�܂�h�����σV�X�e���ւ̃A�N�Z�X���ւ��邱�Ƃɂ��A�_�����߂����ƁE�g�D�E�l�ɐ��ق��ۂ����Ƃ��ł���Ƃ��������ɂ͂Ȃ��p���[�����B
�ŋ߂ł́A�Ďi�@�Ȏ哱�Ői�ލ��ۃT�b�J�[�A���iFIFA�j�̉��E�E�����悢�Ⴞ�낤�B���̎����ł́A��č��l��FIFA����炪�����f�����߂���d�G���Ȃǂőߕ߁E�N�i����Ă���B�A�����J���A�����Ƃ͒��ړI�ȊW���������̎����������@�œE�������̂́A���K�̎n���ŃA�����J�̋�s�������g���Ă������炾�B
�܂��A2005�N�ɔ��������k���N�ւ̋��Z���ق͂��̌��ʂ��[�I�Ɍ��ꂽ��ł���B�č����Ȃ́A�U�h���D�̗��ʂȂǂŖk���N�̃}�l�[�����_�����O�i�������j�ɉ��S�����Ƃ��ă}�J�I�̋�s�u�o���R�E�f���^�E�A�W�A�iBDA�j�v�ƕċ�̎�����֎~�����B
���̃P�[�X�ł́A�A�����J�ȊO�̋�s���A�A�����J�̋K���ɐG��ăh�����σV�X�e���ւ̃A�N�Z�X�𐧌�����邱�Ƃ������BDA�Ƃ̎�������l�B�����𓀌�����A���ƍU�߂ɂ������k���N�͌������������A2006�N10���ɂ͍ŏ��̊j���������{����Ɏ������B
�����A�M�҂̓��V���g�����h�����������A����Đ��{���ǎ҂́u���Z���ق͂����܂ňЗ͂�����̂��v�Ƌ����Ă������̂��B
�k���N�j�����߂���6�������c�̋c�����ł��钆���́A���̖��̉����Ɋ֗^�����o�܂�����A�č��̋��Z���ق̌��͂��Ԃ��ɖڌ������͂����B
���l�����̃h���nj��̐��͐�������
���j��A�p�ĈȊO�̍������Z�e�������������Ƃ͂Ȃ��B�A�����J�́A�����I�A�o�ϓI�ȉe���͂͑��ΓI�ɒቺ�����Ă�����̂́A�h����̐��̉��ŋ��Z�e���͂�������ƈ����Ă���B����A�A�����J�����卑�ł��葱���邽�߂̍Ō�̍Ԃ����Z�e���Ȃ̂ł���B
�����āA�������č��ƕ��ԃO���[�o���p���[�ƂȂ�A���̂��u�V���ȑ卑�W�v��z���ɂ́A���Z����ł̎��w�n�g�傪�������Ȃ��̂ł���B
������A��N�A�l�����̍��ۉ����傫���O�i�������Ƃ̈Ӗ��͏������Ȃ��B
IMF��11���̗�����Ől���������ےʉ݂̈��ł���u���ʈ����o�����iSDR�j�v�̍\���ʉ݂ɉ����邱�Ƃ�����B�ܑ�ʉݑ̐��̈�p���߂邱�ƂɂȂ�ASDR�̍\���䗦�ł͉~���ĕăh���A���[���Ɏ�����3�ʂ̒ʉ݂ɗx��o�邱�ƂɂȂ����B
�܂��A�����h���ł̐l�������č����s�A�h�C�c�E�t�����N�t���g�ł̌������i�������V�s��̊J�݁A���I�ȂǐV��5����BRICS�ɂ��u�V�J����s�v�̐ݗ��������ɍ��ӂ��ꂽ�B�����̊O�ݏ�������3��5000���h���O��ɋy�ԁB�l�����̃h���nj��̐��͏��X�ɐ�������悤���B
�� ���ے����Ƃ́u�����̑n�����v
�����ŁA���X�����~�܂�A�u���ے����v�Ƃ͉��Ȃ̂����l���Ă݂����B
�ߔN�A�������鐢�E���w�i�ɂ��̌��t���悭���ɂ���悤�ɂȂ������A���̒�`���������ƌ�����Ƃ����ȒP�ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�����ŁA�����ȃC�M���X�l���ې����w�ҁA�d�E�g�E�J�[���̒����u��@��20�N�v����ȉ��̉��߂����p���Ă����B
�u�w���ے����x�Ɓw���ۘA�сx�͂˂ɁA�����𑼍��ɉ����t����قǂ̋����ł���Ƃ݂�����������鍑�X�̃X���[�K���ɂȂ�̂ł���v
�u19���I��ʂ��ăC�M���X�������I�D�ʂɗ������̂́A���E�̋��Z�Z���^�[�Ƃ��Ẵ����h���̒n�ʂƖ��ڂɊW���Ă���c�����I�i20���I�j�A�����J�������卑�ւƏ㏸���Ă����̂́A�������܂��̓��e���A�����J�ւ́A������1914�N�ȍ~�̓��[���b�p�ւ̑�K�͂ȑݗ^���Ƃ��Ďs��ɓo�ꂵ�����Ƃɑ傫���N�����Ă���v
�܂�A���ے����Ƃ͋����̑n�����ł���A���Z�e�������̃x�[�X�ɂ��Ă���Ƃ������Ƃł���B�����̋��Z����ł̓����ɓ��ɒ��ڂ��ׂ����ƍl���闝�R���A�����ɂ���B
�����E���u�[���E�T���v�Q�[���̃����^���e�B
�O��ٍ̐e�i12��19��http://gendai.ismedia.jp/articles/-/46961�j�ł́A���E������̒n���w�I�J�I�X�Ɏ������o�܂�R�������B����ł́A���̃J�I�X����V���Ȓ����̉�͐��܂��̂��B���̓_���l����ہA���ڂ������L�[���[�h���upivot�i���ς��g�j�v�ł���B
���̌��t�̓I�o�}�������ŃA�����J�O���̊�����B�E��������A�W�A����i��pivot to Asia�j�������Ƃ��w���̂Ɏg��ꂽ���A�p���G�R�m�~�X�g����N10��24�����̋L���ŁuWe can pivot too�v�Ƃ������o�����f���Ă����̂��ڂ��������B
�L���������p�����͍�N�A�u���ʂȊW�v�ɂ���A�����J�̔����������Ă�������AIIB�ւ̎Q����\������Ȃǐe���H���ֈ�C�ɌX�����B�G�R�m�~�X�g���̌��o���́u�A�����J���A�W�A�ɐ���Ȃ�A��X�����Đ��Ă���������Ȃ����v�Ƃ����j���A���X�ł���B
�L��������������2010�N�̔�����������u���Ǝ�`�O���v���f���A�O���ɂ�����o�ϓI���v��D�悷��p�����т��Ă���B���̃C�M���X��AIIB�Q���\���́A�����̐l���y����n���w�I���Ђɖڂ��ނ���̂����A�ƕ��ȂǑ��̉��B�������C�M���X�ɒǐ���AIIB�ɎQ�������B
���̎��Ԃ������Ă���̂́A���ې����ɂ�����o�ς̔�d�����܂钆�A���x�����ȗ��z���f���鉢�B�����ł��炻�̊O���p���ɂ����āu�}�l�[�E�x�[�X�h�E�A�v���[�`�i�����{�ʎ�`�j�v�����߂Ă���Ƃ������Ƃł���B
�O���[�o���o�ς͂����āA���E�Ɂu�E�B���E�E�B���i�S�������ҁj�v�̊W�������炷�ƌ��`���ꂽ�B�������A���̌��t�͍ŋ߁A�Ƃ�ƕ�����Ȃ��B����́A�������낤�B��i�e���Ƃ����������A�o�ς̎����I�Ȉ��萬���ȂǒN���m�M�ł����A�i���g��ɔ��������͕s���艻���������B
������������Ŋe�����Ă���̂��A�N������������A�N������������Ƃ����u�[���E�T���v�Q�[���̃����^���e�B�ł���B�e���Ƃ����E�̐����I�����D�悷��]�T�ȂǂȂ��A�ꍑ�̌o�ϓI�ɉh��ǂ����߂Ă���̂�����ł���B���ۏ�����������钆�A�O���̊�����A�������鍑�͍����w�����邱�Ƃ��낤�B
�����āA���B�����̐e���H��������A�o�ϓI�ɉh�����߂�p���������I�s��������[����������Ƃ����t���I�Ȏ��Ԃ������Ă��邱�ƂɋC�t�����낤�B���m�ȃ��[�_�[�����������E�́A���H�ɓ��荞��ł��܂������̂悤�ł���B
���A�����J�哝�̑I�����Ӌ`
�����������E�̒���������A���N11���ɍs����A�����J�哝�̑I�̎��Ӌ`�̑傫���������ł���̂ł͂Ȃ����낤���B
����A���a���}�Ƃ�2��1������n�܂钆�����A�C�I���B�}���W�����Ɍ��ґI�т��{�i�����A7���Ɍ��҂𐳎��Ɏw������B
�����ł͏ڂ����G��Ȃ����A����}���̓q�����[�E�N�����g�������������łقڌ��܂�̂悤���B����̋��a�}�́A�ߌ������ŕ��c�������s���Y���A�h�i���h�E�g�����v�������_�����Ńg�b�v���s���A���ґI�т͍�����[�߂Ă���B
���ې����̐��E�ɂ́u���_����ɐÂ��Ɍ��v�i��26��đ哝�̃Z�I�h�A�E���[�Y�x���g�j�Ƃ������t������B�R���͂�w�i�ɂ��Ȃ�����A������g�����ƂȂ��A������������A�Ƃ����Ӗ��ł���B������`�h���\���闧�ꂾ�낤�B
�U��ւ���A�P�ƍs����`��ᔻ���ꂽ�u�b�V���O�哝�͖̂��łɁu���_�v��U��A�I�o�}�哝�̂́u���_�v����ɂ��Ȃ��哝�̂��B�����āA�A�����J�̈АM�͎��Ă��A���ے����͗��������A�����̓A�����J�Ƃ́u�V���ȑ卑�W�v�X�Ǝ咣����悤�ɂȂ����B
�A�����J�́A���x�����Ȗ����`��J���ꂽ�o�ς̎��҂Ƃ��Ď��R���E���Ăь��������A���I�Ȃǂ̃��r�W���j�X�g���Ƃ̒���������߂��A���ێЉ�������肳���邱�Ƃ��ł���̂��B���N�̑哝�̑I�̍s���ɒ��ڂ������B
�}���q�F�i�����͂�E�Ƃ��Ђ��j
1959�N����s���܂�B�����O�����w���ƁB1985�N�����V���Г��ЁB���s�x�ǁA���{�Г��ʕ��Ȃǂ��o�ĊO�M���ցB�����h�����h�� (1997~2002�N)�Ƃ��ĉ��B��̂ق��A�A�t�K�j�X�^���푈��[�S�����Ȃǂ���ށB���V���g�����h��(2005~2008�N)�Ƃ��ăz���C �g�n�E�X�A�����Ȃ�S�����A�u�b�V���哝��(����)�O�V�ɓ��s����20������K��B2009~2012�N���B���ǒ��B�؉p8�N�B���݁A�ҏW�ψ��E���ʐR�� �ψ��B�����Ɂw�ӂ����ȃC�M���X�x������B
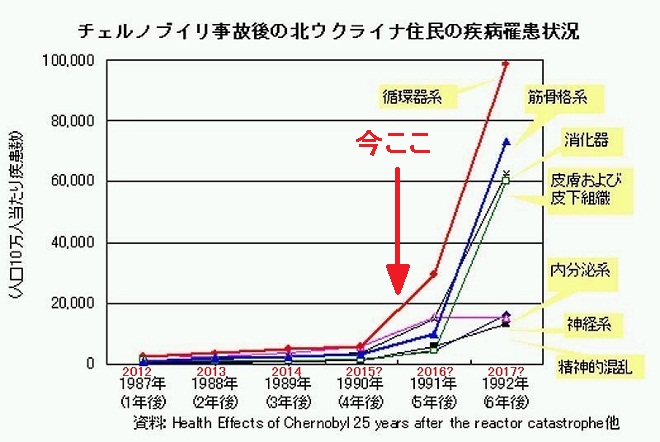
 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B