賃金伸び悩みの背景には、高齢者や主婦などの再雇用で賃金水準が低い労働者が増えていることもある(写真:xiangtao/PIXTA)
日本で賃金上昇がなかなか進まない根本理由 デフレに慣れ切った企業は簡単に変われない
http://toyokeizai.net/articles/-/94398
2015年11月30日 村上 尚己 :アライアンス・バーンスタイン(AB) マーケット・ストラテジスト 東洋経済
名目賃金の上昇率の伸び悩みが話題になっている。これに対して、企業の利益が過去最高水準まで増えているのに、人件費や設備投資になかなか回らない企業行動を問題視する見方がある。
企業が蓄積した内部留保を人件費等に使うのが望ましいとの考えで、政府から大企業に対する働きかけが続いている。
■影響大きかった2014年の消費増税
この政府の対応の是非について多様な見方があるだろうが、実際には政府からの要請があっても、民間企業の行動(=お金の使い方)に大きな影響を及ぼすには至らないのが実情だろう。厳しい競争にさらされる民間企業の行動は、さまざまな要因が影響するので、法的拘束力がない声掛けにはおのずと限界がある。効果が不確かな声掛けよりも、企業が人件費や設備投資への支出を増やすインセンティブが自ずと強まる経済環境を地道に整える対応が、最も効果があるのではないか。
2015年に期待された賃金上昇が遅れている一因を考えると、2014年に消費増税によって実質GDP成長率が停滞したことがあげられる。現段階で判明している2014年度の実質GDP成長率はマイナス0.9%と大きな落ち込みで、実際にはこれほど大きなマイナス成長ではなかったとみられるが、個人消費が失速して急ブレーキがかかり需給ギャップの縮小が止まった。
企業利益は円安効果で増益になったが、前政権の「負の遺産」である尚早な消費増税の後遺症は大きく、脱デフレと相反する政策を採用した政策への不信から、企業は賃上げに慎重にならざるをえなかったのではないか。
脱デフレに向けた中途半端になってしまった総需要安定化政策が、企業による賃上げへのインセンティブを弱めたということである(第2の矢が逆噴射を起こした)。つまり、脱デフレにブレーキをかける政策手段には徹底して慎重に対応することが、回り道のようにみえて賃金上昇の実現の近道だと思われる。また、賃金が伸び悩んでいることには、団塊世代など高齢者の再雇用などが進み、またこれまで非労働力化していた女性の就業拡大、などの労働供給側の変化が一因になっている。
賃金水準が低い労働者が増えれば、一人当たりの賃金は抑制される。これらの労働者の新規採用を優先し、迅速に(手っ取り早く)かつコストを抑制して労働力を確保することが依然合理的と判断する企業が多いのかもしれない。人手不足時代到来と言われるが、2014年に景気回復にブレーキがかかる中で、建設業など一部を除けばコスト抑制の制約を最優先にしながら、労働者を確保する余裕が多くの企業にあるのではないか。
すでに日本は完全雇用に近いと言われることが多い。ただ、日本の失業率は3%台前半と低いようにも見えるが、1990年代半ば以前の安定したインフレ期には失業率は2%台で推移していた。過去20年で、日本の労働市場において摩擦的失業率が上昇したとの分析もみかけるが、これらは推計誤差が大きい可能性がかなりあると筆者は考えている。
■企業は労働市場がタイトだと判断していない
本当に完全雇用といえるほど労働市場が逼迫していれば、企業は、将来の事業拡大あるいは企業価値を保つために、他社との競争との観点から、正社員化促進を含め高めの賃金を支払うなど、人的資本を拡充することが合理的な行動になるだろう。賃金の伸びが高まらないのは、多くの企業は、雇用戦略を変える必要性を認識するほど労働市場がタイト化していないと判断していることが一因ではないか。
このことは、脱デフレが道半ばであるとともに、2012年以前よりは大分少なくなったとはいえ、労働市場にスラック(余剰)が残っていることを意味する。実際に、賃金の伸びの低さ以外にも日本の労働市場にまだ余剰が残っていることを示すデータがある。男性の現役世代の労働参加率(=労働市場に存在する人/総人口)が、依然低下し続けていることである。
女性の労働参加率は過去20年いずれの世代でも上昇しており、これは景気動向とはほぼ関係なく起きてきた。一方で、現役世代(20~50歳代)の男性の労働参加率は低下が続いている。例えば30-34歳男性の労働力率は1995年98%だったが、2014年には95%台まで低下した。
労働者の非労働力化にはいくつか要因があるが、就職氷河期を経て不本意ながらも労働市場から退出を余儀なくされた方も相当含まれるだろう。景気回復が長期化してインフレが安定することで労働市場が引き締まり、こうした現役世代に就業の機会が訪れることで、労働市場の余剰が縮小する余地があるだろう。
■賃金上昇が明確になりつつある米国
上記を含めた労働市場の余剰が更に小さくなり、また不本意に短時間の非正規労働の職にある現役世代の正社員化が進む過程で、今後名目賃金が上昇すると予想される。脱デフレの進展とともに起こるこのプロセスが道半ばにあるため2%インフレ実現にコミットして金融緩和強化を徹底するという、現在の日本銀行の政策姿勢は望ましいと評価できる。
なお、賃金の伸び悩みは、日本だけではなく一足早く金融政策の正常化を始めた米国でも議論になっていた。もちろん、デフレには陥らなかった米国では、日本ほど賃金の伸びは低くないが、失業率低下が続いた一方名目賃金上昇率は2010年から2%前後でほとんど伸びない状況が続いた。
ただ11月初旬に判明した10月の米雇用者の平均時給は前年比2.5%とほぼ6年振りの高さの伸びを示し、リーマンショック後の緩やかな景気回復局面でようやく賃金上昇が明確になりつつある。
米国でも伸びない賃金を巡り、失業率と賃金の関係が崩れたなどの議論が聞かれた。しかし、量的金融緩和強化解除後も慎重に出口政策を進めるなど、米FRBのねばり強い政策対応が功を奏して名目賃金が上昇し始めた。日本に先立ち量的金融緩和政策を拡大させた米国において、ようやく賃金加速の兆しが見え始めたわけだが、金融緩和など総需要安定化政策の徹底が賃金上昇にいずれはつながるということだろう。過去20年続いたデフレ環境に慣れきった日本企業の行動を変えるには、より時間を要するのかもしれない。
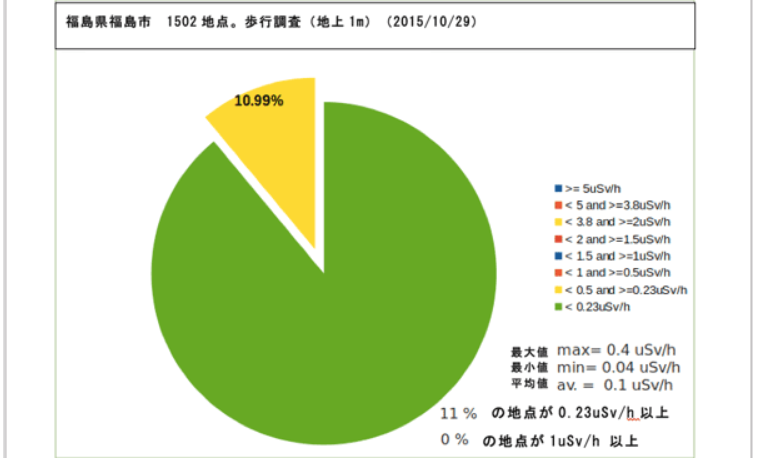



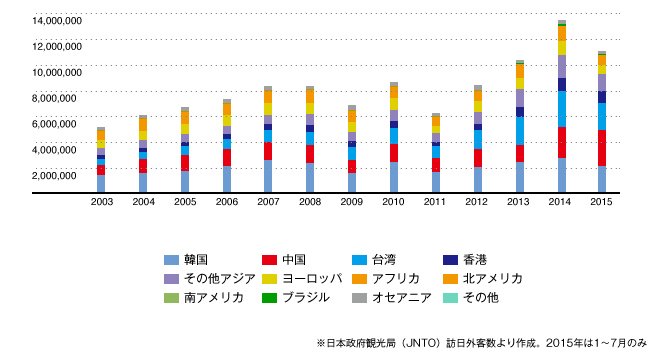
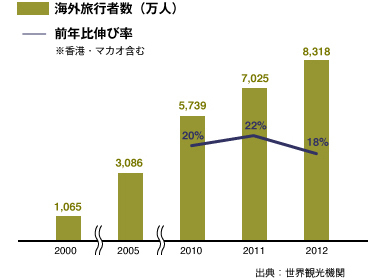
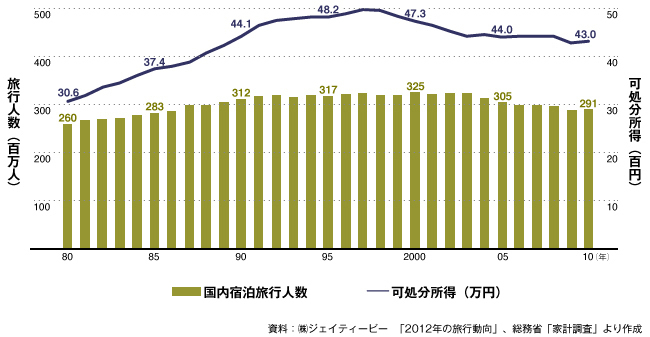






 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。