Gショックの販売戦略を語る田中氏
一旦ブームが去ったGショック 再び売れ始めた販売戦略とは
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150809-00000002-pseven-bus_all
SAPIO2015年9月号
今年誕生から32年を迎えるカシオ計算機株式会社の腕時計・Gショックが順調な売れ行きを維持している。出荷台数は730万個(2014年度)と過去最高を更新中で、2015年度は800万個(目標値)、カシオ全体の連結純利益も330億円が見込まれている。この好調の秘密はどこにあるのか? 作家の山下柚実氏がリポートする。
* * *
「17歳に火を点けろ」
ストリート系の若者を中心にアメリカでGショックブームが燃え上がったのは今を遡ること18年前、1997年のこと。その勢いが日本へ逆輸入され国内でも人気が爆発した。3万個売れればヒットという時計業界において、1997年の出荷個数は国内外あわせて600万個に達した。
「たしかにかつてのブームは凄まじいものでした。しかし、その後の沈み方もまた、すごいものがありました」と同社コーポレートコミュニケーション統轄部・宣伝企画担当部長の田中秀和氏(52)は振り返る。お祭り騒ぎは長くは続かなかった、と。
「4年後、一気に出荷個数が三分の一まで落ち込んだのです。ファッション性に依拠しすぎたために、飽きられるのも早かったのでしょう」
ブームが沈静化した社内には重苦しい空気が漂った。
「営業から研究開発現場までこの先どうしたらいいのか悩みました。もう一度原点に立ち戻り、Gショックのコア・アイデンティティとは何なのか、議論を尽くしました」
浮かび上がったのは、やはり「タフネス」という一語。Gショックの内部は中空構造をしていて、衝撃に強い。gravity(重力)の「G」とshock(衝撃)からその名は付けられている。
「これまでのように『壊れない』だけでなく、さらに『狂わない』『止まらない』という、いわば時計としての『究極の強さ』を追い求める方向性が固まりました」
そこで、電波で自動的に時刻を合わせ、太陽光で充電するという「電波ソーラー」機能をGショックに載せた。腕時計としての「アブソリュート(絶対的)・タフネス」を追求し始めた。第一次ブームから5年ほどが過ぎていた。
絶対的なタフネスを目標に定めた新商品を、ではどうやって市場へアピールしていけばいいのか。
「時はちょうど携帯電話ブームの頃で、若者の関心はまったく腕時計にありませんでした。広告を打っても振り向いてもらえない。これまでとは全く違うプロモーション方法を探っていくしか、道はありませんでした」
2005年頃から同社はユニークな方法に着手し始めた。憧れのキーマンやリーダーにGショックの魅力を語ってもらうという方法だ。音楽ライブ、アートイベント、セレクトショップなどとコラボして、Gショックファンのミュージシャン、スポーツ選手、アーティストといった媒介者を通じて若者と対話を重ねていった。新規取引が飛躍的に増えた。店頭に並んだ商品を、対話の相手である若者が買っていった。新鮮な手応えがあった。
「この手法を2008年頃から欧米、アジア、中東と世界十数都市で展開していきました。『SHOCK THE WORLD TOUR』というプロモーションイベントには基本の型があります。前半は開発ストーリーや機能を伝えるカンファレンス。後半はライブやパーティーを通してエモーショナルにGショックの魅力を表現していくのです」
「タフネス」という機能の上に、各国の土地柄と響きあう若者カルチャーを重ねていく。そんなプロモーションが大成功し、世界各地で出荷数が伸びていった。だが、周到に形作られたこのプロモーションは、いったい誰によって、どのように生まれてきたのだろう?
「イベントの中身は自分たちで企画して練り上げていきました。また、Gショックのファンではない有名人にお金を払って出演していただくことは、決してありません」
Gショックを本当に愛しているコアなファンが、次のファンを作っていくという「ファン作りマーケティング」が世界を舞台に展開されていたのだ。ヒップホップのエミネム。レディー・ガガ。ネイマール。俳優、アーティストらが語る「間接的話法」が世界の若者たちの心を揺さぶった。
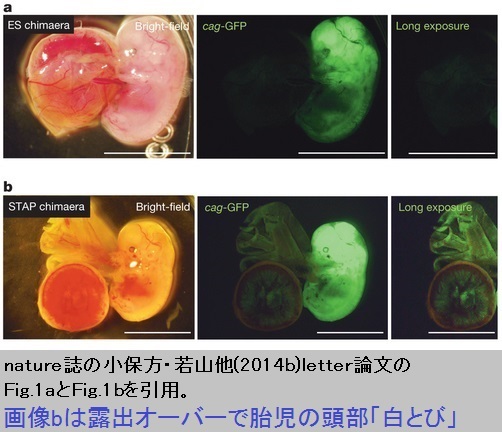
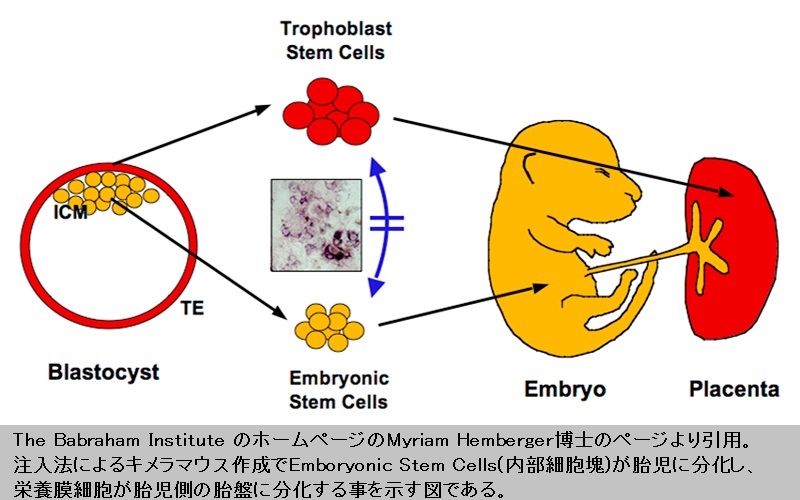

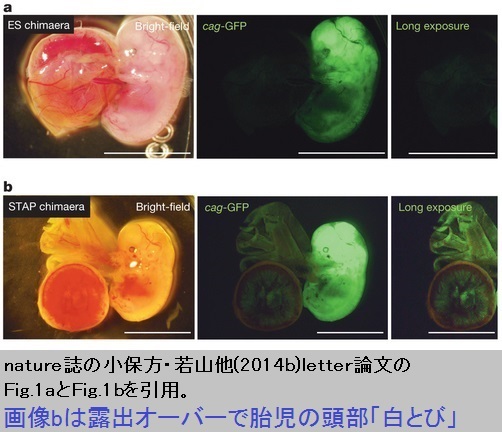
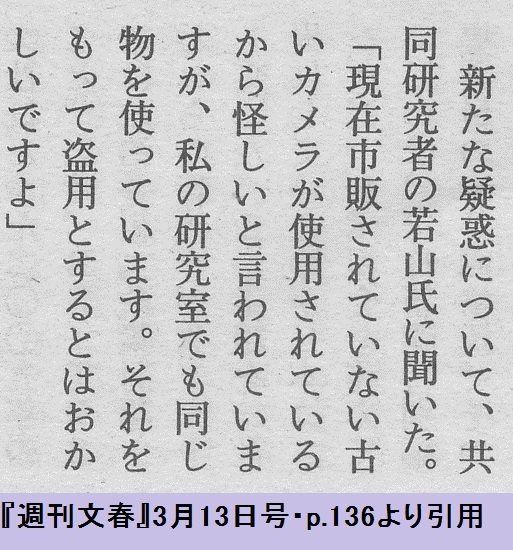
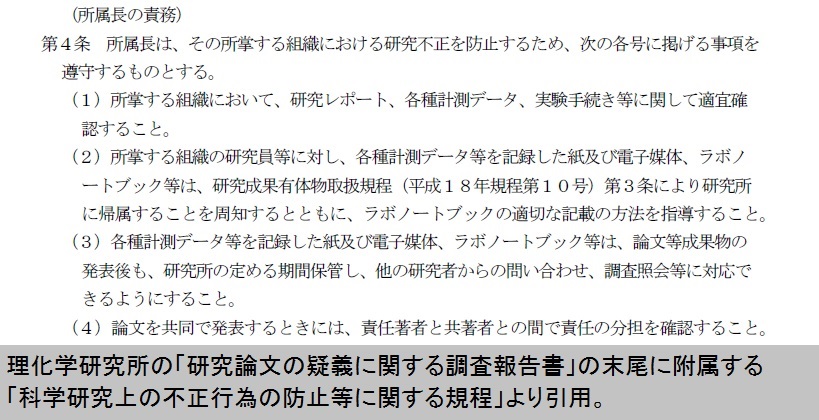

 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。