�R�����F��i���Ő��Y������́u��v������
2015�N 05�� 14�� 13:40 JST
Edward�@Hadas
�m�����h���@�P�R���@���C�^�[�@BREAKINGVIEWS�n - �o�ϋ��͊J���@�\�i�n�d�b�c�j�̓��v�ɂ��ƁA��i���̐��Y���L�ї��͒ቺ���Ă���B�����̃G�R�m�~�X�g����Ƃ����̌X����J�����Ă���A���ɉp���ł͔Y�݂��[���B�p�C���O�����h��s�i������s�j�͂P�R�����\�����C���t���Ő��Y���L�ї��̎����������K�{�Ƌ����������A�����Y�ޕK�v�͂Ȃ��B
�ނ炪�z�肵�Ă���ۑ�͘J�����Y�����B���\���ꂽ�����ɂ͊m���ɋC���œ���B�n�d�b�c�̕ɂ��ƁA�P�X�X�O�N��O���ɂ͓��{�A�h�C�c�A�t�����X�A�p���A�C�^���A�̐��Y���͔N���Q�����̃y�[�X�ŐL�тĂ���A�č��͂P�D�R���������B����ɑ��ĂQ�O�O�X�N����P�S�N�܂ł̂T�N�Ԃł́A�����U�J�����ׂĂŐL�ї����P�D�P���ȉ��ƂȂ�A�č��ł͂O�D�X���܂ʼn��������B
���������Y���L�ї��̒ቺ�́A�Z�p�v�V�y�[�X������������A�ݔ������̗L���������ꂽ��A���C�t�X�^�C�����قƂ�nj��サ�Ă��Ȃ����Ƃ������Ă��Ȃ��B
���Y���̒P���Ȍv�Z���@�́A�唼�̘J���������H��ōs���Ă��鎞�ɈӖ������B�@�B���l�͂Ɏ���đ������ۂ̐��Y�������c���ł��邩�炾�B
���������݁A�܂������������i����葽������悤�ɂȂ������琶�Y�������シ��A�Ƃ����͂܂ꂾ�B�ނ��닌���̐��i�����ǂ�����A���S�ɐV�������i���J�����邱�Ƃɂ���Đ��Y���͌��サ�Ă���B���������萫�I�ȕω��͒�ʓI�ω��Ɩ{���I�ɈقȂ�A�v���ł��Ȃ��B
��M��Ԃ��ň��������Q�f�^�̌g�ѓd�b�P�@������̂ɗv���Ă����J�����ԂŁA�ŐV�^�X�}�[�g�t�H���P�@���ł���悤�ɂȂ����ꍇ�A�J�����Y���͂ǂ�قnj��サ���̂��낤���B���m�ȓ����͂Ȃ��B���v���Ƃ͎������l���r���悤�Ɖʊ��ɒ���ł��邪�A�ނ炪���ݏo���������I�ȕt�����l�̌v���@�͂܂����������Ď������肾�B
�T�[�r�X�ƂƂȂ�ƁA���Y���̌v���͂���ɂ��������ɂȂ�B��i���̍��������Y�i�f�c�o�j�ɂ����āA�T�[�r�X�Ƃ͍����R���̂Q���߂�B������ÂƂ������d�v�ȃT�[�r�X�Ƃł́A���Y���������Ӗ�����̂������͂����肵�Ȃ��B�l�X�����X�ɂ��ċ��߂�̂́A�l�I�Ȏw����P�A�ȂǁA��ʂɐ��Y�����Ⴂ�Ƃ����T�[�r�X�Ȃ̂��B
���邢�́A�t�@�X�g�t�[�h�ɑ����ăJ�W���A���_�C�j���O���䓪���Ă��邱�Ƃ��l���Ă݂悤�B�J�W���A���_�C�j���O�X�������Ɍ����I�ȃT�[�r�X����Ă����Ƃ��Ă��A�J�E���^�[�z���ɗ�����n���t�@�X�g�t�[�h�X�ɔ�ׂ�����Ƒ����̘J����K�v�Ƃ���B�������ǂ̂悤�ȏ펯�I�Ȋ�Ō��Ă��A���l�Ŏ�����鐶�Y�����ቺ��������Ƃ����āA�o�ς̐��Y�����������Ƃ͍l�����Ȃ��B���H�X�ŘJ���̑Ή�����葽���x������悤�ɂȂ������Ƃ́A�Љ�L�����𑝂����؋����낤�B
�o�ϊ����ɐ�߂�T�[�r�X�Ƃ̊����͑����Ă��邽�߁A�W���I�Ȑ��Y���w�W�̗L�p���͒ቺ���������B����������A��i���o�ς̓|�X�g���Y������Ɉڍs�����B
�ٗʓI�Ȑ����ł͂Ȃ����ۂ̌o�ςɖڂ�������ƁA�J�����Y���̒ቺ�͓ǂݎ��Ȃ��B�J���҂̋��琅���͏オ��A�Z�p�͐i�����Ă���B�ݔ������A���ɐ��{����̂��ꂪ�������Ă���\���͊뜜�����B�������o�L�ڂȐ��Y���v���́A������i�݁A���ɗT���Ȍo�ςɂ����Ăǂ�قǂ̓����K�͂��K�������߂���c�_�����������邾�����B
�������C���O�����h��s�̌��O�����L����҂͂ق��ɂ�����A�Ⴆ�A�����h���̃C���y���A���E�J���b�W�E�r�W�l�X�E�X�N�[���́u�p���Y���̓�v�Ƒ肷��R�R�y�[�W�̘_���\���Ă���B
��������ȂǑ��݂��Ȃ��B���\����鐶�Y���L�ї����ቺ���Ă���̂́A�o�ςɐ�߂�䗦���ǂ�ǂ�k�����Ă��镪��̐������W�v���Ă��邩�炾�B
���Y�����߂���I�O��Ȍ��O�́A��{�I�����ւ̓����g��Ƃ������ǂ�����ɂȂ��蓾��B�������ڂɌ�����`�łf�c�o�Ɋ�^���Ă��Ȃ��ٗp�팸���㉟�����Ă��܂����������B���������ٗp���팸����ΐ��Y���̐����͏㏸���邪�A���Ƃ𑝂₵����ߏ��ٗp�ݏo�����ƂɂȂ�B�����������Ԃ̕����K������������ł͂Ȃ����Y�����A��i���ɂ����Ă͖��炩�ɐ[���Ȗ�肾�B
�J���s��ȊO�ɂ��A�������Ƃ̃R�X�g�̍�������Z�s��̋@�\�s�S�A���E�I�ȕn���ȂǁA�������ׂ����͖ڔ��������B�X�J�Ɏ��ԂƃG�l���M�[���₵�Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��B
���w�i�ƂȂ�j���[�X
���C���O�����h��s�̃C���t���͈ȉ��̃A�h���X���N���b�N���Ă������������B
bit.ly/1zZG7y5
���C���y���A���E�J���b�W�̘_���͈ȉ��̃A�h���X���N���b�N���Ă������������B
bit.ly/1QJaVHJ
�����E��s�̎w���͈ȉ��̃A�h���X���N���b�N���Ă������������B
���N�@bit.ly/1G6g2Pg
����@bit.ly/1IAYrPN
http://jp.reuters.com/article/jp_column/idJPKBN0NZ09C20150514
�R�����F�z��ƈႤ���B��v���̐������A���Ȑ������ł��闝�R
2015�N 05�� 14�� 12:26 JST
Edward�@Hadas
�m�����h���@�P�R���@���C�^�[�@BREAKINGVIEWS�n - ���B�e���̌o�ϓ����́A���B�S�̂Ɣ�r����Δc�����ɂ����B�����Čo�ςɂƂ��ĂR�J���͒Z�������B���ꂪ�P�R���ɔ��\���ꂽ���[������P�E�l������������Y�i�f�c�o�j����l���瓾��ꂽ���P���B
�قƂ�ǂ̎�v���̌o�ς͑z��ʂ�ɐ��ڂ��Ă��Ȃ��B�h�C�c�̂f�c�o�͑O����O�D�R�����Ń��[�����̂�������Ɗ��҂���Ă������ɂ͎ォ�����B���Ƀt�����X�ƃC�^���A�̂f�c�o�͂��ꂼ��O����O�D�U�����ƂO�D�R�����ɒB���A�����ƒ�����܂܂Ƃ̕]���ɂ͂�����Ȃ����e�������B
�S���ɔ��\���ꂽ�p���̑�P�E�l�����f�c�o�͑O����O�D�R�����Ɨ\�z�O�ɒᒲ�ƂȂ������A����͔�r�I�����ȘJ���s��֘A�̎w�W�Ƃ͐��������Ȃ��悤�Ɍ�����B�Ⴆ�P�R���̏T�ԕ��ϒ����̑O�N��łP�D�X�����L�тĂ���B
�����������ŏ��Ȃ��Ƃ��X�y�C���͍ŋߏo���オ�����Œ�ϔO�𗠐��Ă��Ȃ��B�f�c�o�͑O����O�D�X�����ƁA���v�哱�Ő����𐋂��鉢�B�̊��҂̐��Ƃ��������������ɉ����Ă���B
��v���̑唼���z��ƈ���Č����闝�R�̂قƂ�ǂ́A�P�l�����i�R�J���j�Ƃ������Ԃ̒Z���ɂ���Đ����ł���B�e���̂f�c�o�͑�G�c�ŕs�\���ȃf�[�^�Ɋ�Â��ĎZ�o����Ă���A���炭�͎���x��ɂȂ��Ă���G�ߒ�����������ꂽ��ɁA�ٗ�̃C�x���g�ł䂪�߂��Ă���B�Q�O�P�T�N���i��ł����ƂƂ��ɁA���ׂĂ̍����{���̎p�ɗ����߂��Ă����\�����傫���B
�����ň�������Ă݂�A���B�S�̂̏͂킩��₷���B���[�����f�c�o�̑O����O�D�S�����Ƃ��������́A�i�C���{����������肪�x�����Ƃ������Ă���B
���[�����̐������́A�č������O�D�O�T���|�C���g���������Ƃ͂����A���C�^�[���܂Ƃ߂��G�R�m�~�X�g�\�z�̂O�D�T�����ɂ͓͂��Ȃ������B���[�����ƌ������i�������N���Ă��鎞���ŁA�Q�O�O�X�N�̌i�C��ނ̑�K�͂Ȍٗp�r������̉��n�܂�������̒n�_�ɂ���Ƃ����ʂ���݂Ă��A�ᒲ�Ԃ肪���炩���B
���B�S�̂́A�X�y�C���Ɠ����悤�Ȍo�ϓI���𑽂������Ă��邪�A�X�y�C�������o�ς̐���������i�K�ɂ͂܂��قlj����B������Ƃ�����Q���厸�s�̌����ƂȂ��Ă��܂��B���������s���肳�̂䂦�ɁA���ŗ����ɋꂵ�ނ悤�ȍޗ����o�Ă���̂͑�P�E�l�������Ō�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��������B
���w�i�ƂȂ�j���[�X
�@�E���B�A���i�d�t�j���v�ǂ��P�R�����\������P�E�l�����̃��[�����f�c�o����l�͑O����O�D�S�����ƂȂ����B�h�C�c�A�t�����X�A�C�^���A�̂f�c�o�O����͂��ꂼ��O�D�R�����A�O�D�U�����A�O�D�R�����������B
�@�E�p�������v�ǂ��P�R�����\������P�E�l�����J�����v�ɂ��ƁA�T�ԕ��ϒ����̑O�N������̓{�[�i�X���܂ރx�[�X�łP�D�X�����A�{�[�i�X�������ƂQ�D�Q�����������B
http://jp.reuters.com/article/jp_column/idJPKBN0NZ06220150514
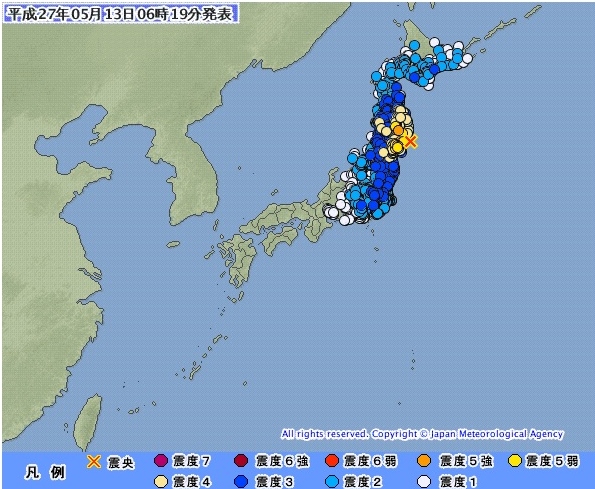

 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B