�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Photo:takashikiji-Fotolia.com
�����}�͈��ۖ@���́u���~�߁v���u�G�}�v��
http://diamond.jp/articles/-/70206
2015�N4��16���@��v�ې��l [�����ّ�w����Ȋw���y����]�@�_�C�������h�E�I�����C��
�����}�A�����}�̘A���^�}��4��14���A���{�W�O�́u��肽������v�i��101��j��1�ł���u�V���Ȉ��S�ۏ�@���v�����鋦�c���ĊJ�������B���̋��c�́A���{��������N7���ɁA�W�c�I���q���s�g��e�F���A���q���ɂ�鑼���̌���x�����g�[����t�c����i��85��j�����������ƂɊ�Â��A���N2�����玩���}�ƌ����}���{�i�I�ɃX�^�[�g���������̂ł���B�����A���q���̊C�O�ł̊����͈͂��ł��邾���g�債���������}�ƁA����Ɂu���~�߁v���������������}�̊Ԃɂ͂��܂��܂Ȉӌ��̊u���肪����A�������Η��������Ă���B
�����ۖ@��������U�h�F�u�O�̂߂�v�����}�Ɓu���~�߁v�����}
���{�A�����}�́A���ۖ@���̎����ɋ����v������������Ă���B���q���̊C�O�ł̊����͈͂��ł������g�債�����ƍl���Ă���B�����}�Ƃ̋��c�ł́A��t�����ɕ������͂��㗤����ȂǁA�푈�Ƃ܂ł͌����Ȃ����x�@�������ł͑Ή��ł��Ȃ��u�O���[�]�[�����ԁv�A���{���ӈȊO�ł́A�ČR�Ȃǂւ̕⋋�E�A���A��ÂȂǂ́u����x���v�A���A���a�ێ������iPKO�j�ȊO�́A�����ێ��⑼���������~�ς���u�삯���x��v���܂ށu���ۓI�ȕ��a���͊����v�ւ̎Q���A�u���{�̑�������������閾���Ȋ댯�v�Ɏ��q�����h�q�o�����đ����R�����u�W�c�I���q���v�̍s�g�ȂǁA���܂��܂ȕ���Ŏ��q���̊����͈͊g����Ă����B
����A�����}�́A�k����Y����\���A���q���h���ɂ������āi1�j�����̗����Ɩ���I�ȓ����A�i2�j���ۖ@��̐������A�i3�j���q�����̈��S�m�ۂ������Ƃ���u�k���O�����v����A���ۖ@�������Ɂu�O�̂߂�v�ɂȂ��Ă��鎩���}�́u���~�ߖ��v�ƂȂ낤�Ƃ����B
�����}�́A�푈�����Ă��鑼���̌R���ɑ����q��������x�����邱�Ƃɂ��āA�P�v�@�u���ە��a�x���@�v�̐����ڎw���Ă���B�]���A���q���̊C�O�h���́A�A�t�K���푈���Ɂu�e�����[�@�v�𐬗������āA�C���h�m�ł̎��q���ɂ�鑽���ЌR�ւ̋����x�������������悤�ɁA���̓s�x�u���[�@�v������Ď��s���Ă����B����ɑ��āA���ł����q����h���ł���u�P�v�@�v���ł���Ȃ�A�ČR�Ȃǂ̋��߂ɑf�����Ή��ł���悤�ɂȂ�B����́A�����}�́u�ߊ�v�Ƃ�����B
�����A�����}�͎��q���h���ɍۂ��A�u�k���O�����v�i1�j�ɂ�����u��O�Ȃ�����̎��O���F�v�������v�����Ă���B����́A�u�O�@���U�⍑���őf�������F���ł��Ȃ��ꍇ�́A��O�I�Ɏ��㏳�F��F�߂�ׂ��v�Ɣ��_���鎩���}�ƁA�������Η����Ă���B
�܂��A�����}�͎��q���h���̗v���Ƃ��āA���B�A���i�d�t�j�ȂǍ��ۋ@�ւ̗v����A���A�̎�v�@�ւ́u�x���v������Δh���ł���Ƃ��������������Ă���B���q���h���́u�������v�́A�ł��邾���ɂ₩�ɂ��āA�h�����₷���������Ƃ������Ƃ��B�������A�����}�͔h���́u�������v����茵�i�ɍl���Ă���B�u�k���O�����v�i2�j�Ɋ�Â��u���ۓI�Ȑ��������s�\���v�Ƃ��āA���q���h���ɂ́u���A���S�ۏᗝ����c�v���`���t����ׂ��Ƌ����咣���Ă���̂��B
�����}�́u�k���O�����v�i3�j�ɂ��Ă��A�u�e�������ȂǂɊ������܂ꂽ�M�l�̋~�o�v�ȂǁA���q�����̊C�O�ł̔C���͋ɂ߂Ċ댯�����̂ɂȂ�Ǝw�E���A���ۂɓ������q�����̈��S�m�ۂ��ǂ̂悤�ɖ@�I�ɒS�ۂ��邩���A��̓I�ɒ���悤�����}�ɋ��߂��B�����}�͂��������A���q�����̈��S�ۏ�ւ̔z����h�q���ɋ`���t����K����e�@�Ă̐��荞�ނ��Ƃ͌��߂��B�����A��̓I�ȑ[�u�̒��g�͂܂��l�܂��Ă��Ȃ��B
�u�W�c�I���q���v�̌���I�s�g�̗v�����A�����}�ƌ����}�̘_���_���B�����}�́u���ӎ��Ԗ@�v���������A�u�킪���̕��a����ш��S�ɏd�v�ȉe����^���鎖�ԁi�d�v�e�����ԁj�v���K�肵�A���{���ӈȊO�ł��n���I����Ȃ����͍s�g�ł���u�d�v�e�����Ԗ@�v�̐����ڎw���Ă���B���́u�d�v�e�����ԁv���Ȃɂ��Ӗ�����̂��Ƃ������Ƃ����}�̑��_�ƂȂ����B
�����}�́A���{�̗A��������8�����ʂ钆���̃z�����Y�C���ɋ@�����܂����P�[�X��Ꭶ�����B�u�Ζ��̗A�����~�܂�A���������Ɏ����I�ȉe�����o��v�Ƃ��āA�d�v�e�����Ԃɂ��Ă͂܂�Ǝ咣���Ă���B����A�����}�́u�o�ϓI�ȑ��������̏ł͐V���Ԃɂ��Ă͂܂�Ȃ��v�Ƃ̌����������Ă���B�u�z�����Y�C���̋@���Ƃ��������ō��̑��������������ԂƂ݂Ȃ��Ȃ�A�g����߂����s�����˂Ȃ��v�Ǝ����}�̍l�������x�����Ă���B
�����}�ƌ����}�́A���q���̊C�O�ł̕��͍s�g��e�F���邽�߂́u�V����3�v���v�����肵���B�i1�j���ڂȊW�������͍U�����A�u���{�̑�������������A�����̐����A���R����эK���Nj��̌��������ꂩ�畢����閾���Ȋ댯������i2�j���ɓK���Ȏ�i���Ȃ��i3�j�K�v�ŏ����x�̎��͍s�g�A�ł���B�����}�͂���3�v���̒��Ɂu���ɓK���Ȏ�i���Ȃ��v���Ƃ荞�ނ��ƂɓO��I�ɍS�����Ƃ����B�܂��A�u�����̐����⎩�R�Ȃǂ����ꂩ�畢����閾���Ȋ댯�v���Ȃɂ��w���̂��A���̔��f��m�Ɏ����悤�A�����}�ɋ����v�������B���̂悤�ɁA�����}�͈��ۖ@���̋��c�ɂ����āA�l�X�Ș_�_�Ō������w�E���J��Ԃ��A�u�O�̂߂�v�����}�́u���~�ߖ��v��O��I�ɖ��߂Ă����̂ł���B
���u���~�ߖ��v�����}�����ۖ@����O�i�����Ă���
�������A���ۖ@�������鎩���}�E�����}�̍U�h���悭�ώ@���Ă݂�ƁA�ʂȑ��ʂ������Ă���B�����}�́u���~�ߖ��v�߂�Ƃ����Ȃ���A���͈��ۖ@���̑O�i�ɑ傫�ȍv�����ʂ����Ă���悤�ɂ݂���̂��B
���{�́A�Ƃɂ������ۖ@���ɑ��Čl�I�v�����ꂪ��������B�܂��A�����}�����q���̊����͈͂��ی��Ȃ��g�債�����Ƃ����v�����I���ɕ\�ɏo�����ł���B���̂��ߎ����}������ẮA�e���ۂ������ۂ��B�����炭�A�����}�����~�߂Ȃ��u�\���v�����Ƃ�����A���ۖ@���͍����̔ᔻ�ɑς����Ȃ����̂ɂȂ������낤�B�����}���u���~�߁v���ʂ������ƂŁA���ۖ@���̂��܂��܂Ȗ��ɑ��āA����Ɍ����I�ȋ�̍l�܂��Ă��Ă���̂ł���B
�M�҂́A���̓��{�����ŁA�������h���}���ϋɓI�Ɋ֗^�������Ɉ��S�ۏᐭ�i�W���Ă������j���w�E�������Ƃ�����i�O�A�ڑ�29��j�B�ȉ��ɂ����[�I�ɂ܂Ƃ߂Ă݂����B
����ŗ^��}�̋c�Ȑ��ɍ������鎞�A��}�͐����̍����ӎ����邱�Ƃ��Ȃ��A���S�ۏ���ɂ��Ă͔��ɓO�����B�����}�͖�}�̔����傫�����Ɉ��S�ۏᐭ����ɐi�W�����悤�Ƃ͂��Ȃ������B����A�^��}������Ԃ�A�������h���}���A�������ɎQ�����鎞�ɂ́A�^��}�̊W�͕ω�����B�������h���}���A��Δ��̗��ꂩ��A��茻���I�ȑΉ���͍�����悤�ɂȂ����̂��B���̌��ʁA�����}�Ƃ̊Ԃɘb�������̗]�n�����܂�āA���S�ۏᐭ�O�i�����̂ł���B
��̓I�ɐU��Ԃ��Ă݂悤�B�^��}������Ԃł̑啽���t�i1978�N12���|1980�N6���j�ł́u�������S�ۏ�\�z�v�����������B�����}�ƎЉ�}�E���������̘A�����������R���t�i1994�N6���|1996�N1���j�ł́A�Љ�}���}����p�~���u���q�������A���Ĉ��ی����v�ɐ����]�������B�����A���̏������t�i1998�N7���|2000�N4���j�ł́u���ӎ��Ԗ@�i���ăK�C�h���C���j�v�u���@��������v�u��������Ɩ@�v�u�ʐM�T��@�v�u�������w�ԍ����v���������A�����������A���̏�����t�i2001�N4���|2006�N9���j�ł��u�e�����[�@�v�u�L���֘A�O�@�v�����������B���{�����̗��j�ł́A�������h���}�́A���S�ۏᐭ��Ŏ����}�́u���~�߁v�ɂȂ�Ƃ��������A�ނ��됭���S���\�͂��������߂ɐϋɓI�Ɉ��S�ۏᐭ���O�i�����Ă����Ƃ�����̂ł���B
����̈��ۖ@���ł��A�{���u���a��`�v�̒������h���}�ł�������}�́A�A���^�}�̈�p�Ƃ��āu���~�ߖ��v�߂Ȃ���A���{�⎩���}�̎v�����ꂪ�o�����Ă���e���ۂ��Ă��A���{�̂���܂ł̗��j�I�o�܂⍑������ɔz�������A�����I�ȂƂ���ɗ��Ƃ����ޖ������ʂ����Ă����Ƃ����Ȃ����낤���B
�������}�́u���~�߁v�̖�����������˂Ȃ����ăK�C�h���C���̉�����
���ۖ@��������A����̎����}�ƌ����}�̋��c�̔g���v���ƂȂ�̂��A�������s�I�ɍs���Ă���u���Ėh�q���͂̎w�j�i�K�C�h���C���j�v��18�N�Ԃ�̉����Ƃ��낤�B
1997�N�ɍ��肳�ꂽ���s�̃K�C�h���C���́A���{�̈��ۊ����u�����v�A���{�ɏd��ȉe�����y�ԁu���ӎ��ԁv�A���{�����͍U������u�L���v��3�ɕ����Ă����B�V���ɉ��肳���K�C�h���C���ł́A�u�����v�u�L���v�̊T�O�ɉ����āA�����̌R���I�ȑ䓪��O���ɂ����A�����̕s�@�苒�ȂǑ�������̕��͍U���ł͂Ȃ��u�O���[�]�[���v���Ԃ�V���ɉ�����B�܂��A�u���ӎ��ԁv��n���I�Ȑ���̂Ȃ��u�d�v�e�����ԁv�ɕύX����B�����āA�W�c�I���q���̍s�g��e�F����u�V���ԁi���j�v�����邱�ƂɂȂ��Ă���B
���ė����{�́A4��27���Ƀ��V���g���ŊO���E�h�q�S���t�����c�i2�v���X2�j���J���A���ăK�C�h���C���̉���ɂ��č��ӂ��邱�ƂɂȂ��Ă���B�����āA28���Ɉ��{�ƃI�o�}�đ哝�̂���k���A���ē����̐[�������߂Ċm�F����Ƃ����i��肪���Ɍ��܂��Ă���B
�����A�V�������ăK�C�h���C���ɂ́A���ۖ@���̋��c�Ŏ����}�ƌ����}�̌���������Ă�����e���܂܂�Ă���B�Ⴆ�A���q���̒����z�����Y�C���ł̋@���������u���O�v�ł��\�ɂ��邽�߁A�u�V�K�C�h���C���v�ł͒n���I������O�����ƂɂȂ��Ă���B�������A����͌�������F�������Ă�����̂ł���B
�^�}���̋c�_����������O�A�����Ė{�i�I�ȍ���_�킪�n�܂�O�́u�ΕČ���v�͖�肪����B���ꂩ��n�܂�@�č쐬�ɉe��������͕̂K�������炾�B�����}���ɂ́A�u�č����爳�͂�������A�����}�͐܂�邵���Ȃ��v�ƍl����҂�����Ƃ����B�������A����Ȉ��Ղȍl�������A�������痝������邾�낤���B
�������A���ăK�C�h���C���͗����{�́u���������v�Ƃ����ʒu�Â��ł���A���x��A����F�͕K�v�Ȃ����̂ł���B�����A����������Ƃ����āA�����n���̂悤�ɁA���ăK�C�h���C���ł��ΕČ�������ɁA�����̔ᔻ�ɑ��āu�葱���I�ɖ��Ȃ��B�l�X�Ɛi�߂�v�Ƃł��������肾�낤���B�����}���A�����}�́u���~�߁v���������A�����̔ᔻ��}���邽�߂Ɂu�O���v�𗘗p���悤�Ƃ���Ȃ�A���ۖ@���̂���܂ł̋c�_�ɐςݏグ�͈ꋓ�ɕ��邾�낤�B
���{���I���͈��ۖ@�����}�~�͂�{���ɍ��߂�̂��ǂ���
�Ō�ɁA���ۖ@���ɑ���u���~�߁v�̕K�v�����̂ɂ��čl���Ă݂����B�J��Ԃ����A�����}���A���^�}�̈�p�Ƃ��āA���ۖ@��������O��ɁA���q���̊C�O�h���̍ی��Ȃ��g��Ɂu���~�߁v�������悤�Ƃ���̂́A�]�����ׂ����Ƃł���B�����A�u���~�߁v���̂��̂ɖ��͂Ȃ����낤���B�u���~�߁v�������������߂ɁA�ނ�����{�̈��S�ۏ�̐��Ɍ��������āA�G�����u���{���U�߂₷���v�ƍl����悤�Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ����낤���B
���S�ۏᐭ��̖{���́u������g��Ȃ����߂ɁA����𑵂��邱�Ɓv�ł���A�u������g�����ƂɂȂ����玸�s�v�Ƃ������Ƃł���i��85��j�B�܂�A�u���~�߁v�����ʓI�ɓ��{�ɕ�����g�p�����邱�ƂɂȂ�A���{��푈�Ɋ������ނ��ƂɂȂ�Ȃ�A����͖��Ӗ����Ƃ������Ƃ��B�ɒ[�Ɍ����A�u���{�̗}�~�͂������Ȃ܂łɍ��܂�Ƃ����̂Ȃ�A���q���̊C�O�h�������~�߂Ȃ��������Ɋg�傷�邱�Ƃ��e�F���ׂ��v�Ƃ����l���������蓾��̂ł���B
���݂́A���{�����̈��ۖ@��������c�_�́A���q���̊C�O�h���̊g��ɂǂ̂悤�Ɂu���~�߁v�������邩�Ƃ������ƂɏW�����Ă���B�������A�{���I�ɏd�v�Ȃ̂́A�u���q���̊C�O�h���̊g�傪�A���{��G���Ƃ݂Ȃ����E���͂��o�������Ă��܂��A���ʂƂ��ē��{���푈�Ɋ������܂�郊�X�N�����܂��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������O���A�����I�ɓ˂��l�߂ċc�_���邱�Ƃł͂Ȃ����낤���i��85��j�B
���̋c�_�́A�A���^�}�̈�p�Ƃ��āA���ۊW���l�����Ȃ��猻���I�Ȑ����^�c�Ɍg���Ƃ��˂Ȃ�Ȃ������}�ɂ͂ł��Ȃ����Ƃł���B�u���~�ߖ��v�́A�����}�ɂł�����E�M���M���̂��ƂȂ̂ł���B�ނ���A�ȑO�w�E�����悤�ɁA�{���I�ɂ́u���x�����h�v�̖����ł���͂����i��95��j�B
���x�����h�́u���a�v��ڎw���l�����ł���B������{���́A�u���a�̈ێ��v�Ƃ����ϓ_����A���ۖ@�������{�̗}�~�͂����߂邩�ǂ������I�ȋc�_�����[�h���ׂ��l�����ł���B�����A���x�����h�͌���A���ԈˑR����u�쌛�v�u���a�v��i����݂̂ł���B���S�ۏ��_���邱�Ǝ��̂��u���v�ł���Ƃ����Â��Œ�ϔO�ɑ����A���S�ۏ�̌������̂��̂�ے肷��l������B���S�ۏᐭ�����I�ɘ_���邱�Ƃ��ł��郊�x�����h�̕s�݂��A���{�ɂƂ��Ă̕s�K�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B



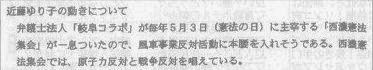
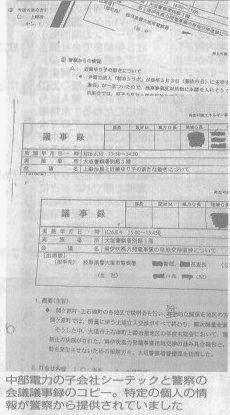



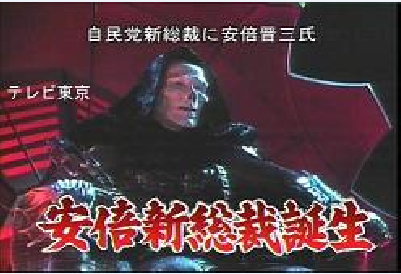










 �@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�@�薼�ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B