|
����354�s���炢���E�́��N���b�N�Ŏ��̃R�����g�ɃW�����v�� >>76 �̓�����N��������Ă�T�C�g������܂����B
��������Ȃ����̂��߂ɁA���̕������R�s�y�B���Ă̊O���ɂ���ĕ������{�̐H�̈��S�Ɣ_�Ɓ@(2024/5/6)
https://ameblo.jp/sherryl-824/entry-12850889980.html�@
(��)
����͊��S�ȕ����N�����ł͂Ȃ��A�r�f�I�����Ȃ��玄���d�v�ȓ_���������Ă��������̂����Љ�����Ǝv���܂��B
�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q �P�D���{�́h�^�́h�H���������ɂ��� ���{�̐H����������37%�ł͂Ȃ��A����10%�ƂȂ��Ă���B
37%�Ƃ����̂̓J�����[�x�[�X�ł̐����ŁA�{�Y�ł̉a�̎������������Ȃ��Ƃ����̂͂��������l�����Ă���B �������A�엿�̌����͂قƂ��100%�A���ɗ����Ă���B�엿�̗A�����~�܂�Ύ��ʂ͔����ɂȂ�B��̎������͂W������Ƃ������A��͂��̂P�����������ł��Ă��Ȃ��B������ł͂Ȃ��A�Ă⑼�̂��̂̎���C�O�̑��Ƃɍ����o���Ă����悤�Ȑ��x���肪�i�߂��Ă���B �ň��̏ꍇ�͖�Ɠ����悤�ɂ��ׂĂ̔_�Y���̎�̂X�����C�O�Ɉˑ�����Ƃ������ƂɂȂ�A������������9.2%�ɂȂ�B
���엿�͂��Ƃ��ƍ]�ˎ���ɂ�100%�������Ă������A��������ŕ����O��������Ă��Ȃ��������œO��I�ɏz�����āA���Ă̓��{�͔_�Əz�o�ς����グ�Ă����B ���ꂪ�A�����J�̐�̐���œ��{�͗A���ɗ���Ȃ����Ƃ������ƂŁA�A�����J�̔_�Y������ʂɗ]�����̂������`�ɂȂ��Ď��������������Ă����B
�E�N���C�i�V���b�N�ɉ����āA���͐��E�ł̒����̐H���̔����������ЂɂȂ�A���{�������ɍs���Ă��Ȃ��Ȃ����̂��c���Ă��Ȃ��Ƃ������ԂɂȂ��Ă���B
�����͗L���ɔ����ĂP�S���l�̐l�����P�N���ς����邾���̐H������~���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƁA�������Y�̋��������ł͂Ȃ��A���E�����獒�������W�߂Ă���B ����ɉ����Ĉُ�C�ۂ̒ʏ킩�œ��{����N�͖ҏ��ɂ��ꂽ���A���E���Ŋ���^����������O�̂悤�ɋN�����Ă��āA�o�Y�Ȃ́u�����ԓ����ĐH�Ƃ͐��E�Ŕ��������A�H�Ƃ͂��ł������A���ł���v�ƍl���Ă���Ă����̂���X�̂���Ă������ł���B
�A�����J�����{�ɂǂ�ǂ��ŗ]�������̂��āA���{���R���g���[������@�Ƃ����������X�͎~�߂Ă����B ��(��؋���)�͔_���ȂɂP�T�N�����̂ŁA�_���Ȃƌo�Y�Ȃ������̒��ŁA�����Ȃ͔_���ȂɂȂ��Ȃ������o���Ȃ��̂ŁA�o�Y�Ȃɂ����悤�ɂ���Ă����B ���̂悤�Ȓ��ʼn�X�͗A���ɗ����Ă������A���ꂪ��������Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł͂Ȃ����A�ƍl����ƐH�Ƃ��ʓI�ɂ����I�ɂ���@�ɂȂ��Ă���B �Q�D�������̂ɂ͕K�����P������ �A�����������Ƃ݂�Ȃ���т��Ă��邪�A�H���́@�A�����J�ł̓G�X�g���Q���Ƃ��������z�������𒍓����đ��点��S�����炢�������Y�ł���B���̂悤�Ȍ`�ň����Ȃ������̂���X�͗A�����Ă��邪�A����͓�����̑��B���q�Ƃ��������������āA���{�̍����ł͂�����������̓��͋֎~�B
���{�̓A�����J�ɜu�x���ē��{�̍����ł͋֎~�Ȃ̂ɁA�A�����̌������U���ɂ��Ă���B��X�͋����̎������͂R�������Ȃ��킯������A�����ŋ֎~�����Ă��Ă��A�A���Ŕ������^����z�������̓��������S���Ɍ��O��������̂�����Ă���B
�ʓI��(�s���)�����Ă���̂Ŏ��ꂴ��Ȃ��Ȃ��Ă���B
�����玿�I�ɖ�肪�����Ă����ꂴ��Ȃ��B
�ʂ�������A���I�Ȉ��S�ۏ�������Ƃ����\���ɂȂ��Ă���B ����AEU�̓A�����J�����ƌ��������A��Ȃ����̂̓_�����Ƃ������ƂŁA�G�X�g���Q���̋����͋��ۂ��Ă���B
�A�����J�����łȂ��A���̍���EU�ɔ���Ȃ��ƂȂ�ƁA���{�����ɁA���{�l�ɐH�ׂĂ��炤�@�Ƃ����b�ɂȂ��Ă��āA�I�[�X�g�����A�Ȃ�EU�ɔ���Ƃ��ɂ͋֎~������z�������͎g��Ȃ����A���{�����ɂ͑��v������ƁA��������g���Ă���B
�_���Ȃɂ��m�F�������A�u�I�[�W�[�r�[�t�Ȃ���v�v���Ǝv���Ă���l���������A�_���ȂɊm�F������A�I�[�W�[�r�[�t��������Ɓu�z�������͎g���Ă��Ȃ��v�Ƃ��f���Ă��Ȃ�����͎g���Ă���@�Ƃ͂����茾���Ă����B
�֎~���Ă���EU�ɂ͎g��Ȃ����A���{�ɂ͎g���邩��B
����Ӗ��A���E�̍����t�Łu��Ȃ����͓̂��{�ցv�ƂȂ��Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����悤�ȏ�����B���{�̓A�����J�ɜu�x����(�K����)��邭���Ă����Ă���킯������A�����Ȃ�B 3.BSE�̌����ɂ���
BSE�̌����ɂ��Ắ@�S�������A�Ⴂ24�����܂ł̋���������Ȃ��Ƃ������Ƃōŏ��͂��Ȃ肫�т���������A�������A�A�����J����{���āu��������Ȃ��Ƃ�߂�v�ƌ����āA�ǂ�ǂ��߂Ă������B
���Ėf�Ջ��肪�ߔN���܂������A�A�����J�̋�����S�ʓI�Ɏ����Ƃ����̂ŁA����ɍ��킹�Č�����P�p�����B �A�����J�ł�BSE�͏o�Ă��Ȃ��Ƃ������n�t���ɂȂ��Ă��邪�A���̗��R�͌��������P�`�Q��������B�������A�A�����J��BSE�ɂ������Ă��鋍�͖��炩�ɂ���A �u�w�^�����v�Ƃ��ăr�f�I��f���ŕ����邪�A�����������̂��j�{��ɉ^��Ă���悤�ȉf���������Ă��A�������Ă��Ȃ���u���퍑�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B
���{�͂��̂悤�Ȓ��ŁA�A�����J�́u���퍑�v������S�ʓP�p����@�ƌ����Ăǂ�ȋ��ł��A�����J�������邱�Ƃɂ����B BSE�ɜ늳���Ă��鋍�̓������R�ɓ����Ă��Ă����ԂɂȂ��Ă���B�{���͐H�����H��Ŋ댯���ʂ�������Ǝ�菜�����Ƃ��o���Ă���悢���A���{�͂��ꂪ�ł��邪�A�A�����J�͂������܂��ł��Ă��Ȃ��炵���B
��������Ɗ�Ȃ��ُ�ȃv���I�����~�ς����Ґ������������܂܂̓������{�ɓ����Ă��Ď��ۂɖ��ɂȂ��Ă�����������B
������BSE�ɂ��Ă��ŏ��͌������������A�A�����J�x�̊W�ł����S�ʓI�Ɏ���邱�ƂɂȂ��āA�����ɂ��Č����ƁA�G�X�g���Q���̖��Ƌ����a�ɜ늳���Ă���\���̖��Ɠ�d�̈Ӗ��Ŏ��̈��S�Ɍ��O���o�Ă���B 4.�H�i�Y�����̖��
������A�����J�Ƃ̊W�ŁA���{��1500�̐H�i�Y����������܂ŔF�߂Ă����B �A�����J�ł���2000�ʔF�߂Ă�����̂����邪�A����͓��{�ŔF�߂Ă��Ȃ�����Ȃ����@�ƂȂ��ď����F���Ȃ����Ƃ����v�����@���������ɏ�����Ă���B ��������ƁA���{��1�N��2000����C�ɔF�߂�̂͑�ςȂ̂ŁA���N�͂���50��F�߂�Ƃ��A���Ԃ����߂āA�����F�߂Ă����B ��������{�̓A�����J����̗v�������S�ɋ��ۂ���I�������Ȃ��̂ŁA�ł��邾�������Â��ԂɂȂ��Ă����@�Ƃ����̂����{�̗B��̊O��헪�B
1500�������Ƃ����2000����������ꂾ����3500�Ƃ��ɂȂ��ċC���t��������{����ԁA���E�ŐH�i�Y������F�߂Ă��鍑�ɂȂ��Ă��܂����@�Ƃ������Ƃ��N�����Ă���B�A�����J���猾���邪�܂܂ɒlj��������Ă�������ł���B 5.�Ȃ����{�̓A�����J�ɑ��Ă���ȂɎア�̂�
�s���̐�̐���ŃA�����J����̗]�萶�Y���������Ƃ������ƂŊœP�p��������ꂽ�B
���{�����A�����J������邱�ƂŁA�_�Y���������ɂ��ɂ��āA����ɓ��{�͎����ԓ��̐����Ƃ̐��i���悤�ɂ�������ł͂Ȃ����@�Ə�肭�A�����J�̌������Ƃ��āA���̑���Ɍ��Ԃ�Ƃ��Ď����ԓ��̗A�o�𑝂₷�̂����{�̐����c�铹���Ƃ������Ƃœ��{����肭�Ή��������ʂ�����B �_���Ȃ͖f�Վ��R����j�~���邱�Ƃɂ���Ȃ�ɒ�R�͂��ATPP�ɂ���Ƀ_�����ƕK���ɒ�R�������A���@���o�Y�Ȃ������Ȃ��݂�Ȃ���͐i�߂���Ȃ��Ƃ������Ƃœ����Ă�������A�_���Ȃ̗��ꂪ�@���@�ł̔鏑���������A�o�Y�A�_���Ƃ����āA����Ȃ�ɔ����ł��Ă�����������������A�u�_���Ȃ��]�v�Ȃ��Ƃ��邩��A�N��̌������Ƃ͕����Ȃ��v�݂����Ȋ����ɂ���ƂȂ��Ă��āA�݂�Ȃŏ���Ɍ��߂����Ƃ�_���Ȃ͂�炳��邾���@�Ƃ������ƂɂȂ�A�H����_�Ƃ������o�����ƂɂȂ����B �́E���쏺��_����b�����{�ŒE�������̍ɂ��]���Ă��邩��ƌ������ƂŎ��͂̔������������ĊC�O�����Ɏg�������A���ꂪ�A�����J�̎s���D�����Ƃ������Ƃŋt�ɐG�ꂽ�B���ꂾ���ł͂Ȃ����A�ނ̓A�����J�ɂ��������Ƃ͌����Ƃ������ƂŊ撣�������A���̂悤�Ȃ��ƂɂȂ����B �����琭���s���̊F����̂��Ȃ�̕����k���オ���Ă��āA�u�A�����J�ɋt�炤�ƁA�����������Ȃ��v�ƁB�����獑�����H�ׂ���̂��Ȃ��Ȃ낤�ƁA�_�Ƃ��ׂ�悤���A�����̒n�ʂ̕ېg���悾�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���Α�ςȂ��Ƃ��B
�����Ƃ��s���̊F����������̗������낤�Ƃ����͕̂�����B ��l�Ő������ׂ����@�Ƃ����\���������Ƒ����Ă���B
�A�����J�ɕK�������Œׂ���Ă��܂��Ƃ����\���������āA�A�����J�ɑ��Č������Ƃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
���A���{�̐H������ς��������Ă��܂����@�Ƃ����̂�����B
�A�����J�́@�����]�萶�Y������{�l�ɖ������H�ׂ����邾���ł͂Ȃ��A���{�l������Ɉˑ�������Ȃ��悤�ɁA�H��������]�����B
�u�R����H���Ɣn���ɂȂ�v�Ƃ����{���w�̈�w���̋����ɏ����Ă�����āA�A�����J�̏�����H�ׂȂ��Ɠ��{�l�̓A�����J�l�Ƃ܂Ƃ��ɘb�̂ł��铪�]�ɂȂ�Ȃ��Ƃ����܂Ő��]������Ă����B ����ƁA�q������ς��Ă��܂��Ƃ������ƂŁA���H�ŃA�����J�̂܂��������̃p���ƒE��������H�ׂ������B�E�������͔��������Ă����Ƃ����b�����邪�A�{���͑S�������Ă����B�^��ł���Ƃ���1�������̂����߂Ă����������@�Ƃ������̂������B ���{���H�������P�^���Ƃ����낢���������A�S���A�����J�̂����B
�w�Z���H���������̂�GHQ�ŁA�H������ς��邱�Ƃœ��{�l���A�����J�̔_�Y���Ɉˑ�������Ȃ��悤�ȏ�����Ă����B �A�����J�͂����P�I���������̂��@���{�̒{�Y�͐U������Ƃ������ƂŁA�x�������B��ʂ̗]��̉a�̍������g�E�����R�V�Ƒ哤�J�X����{�ŏ�������ɂ͋���ɐH�ׂĂ��炤���߂ɓ��{�ɗA�o���āA���{�͂���Ɉˑ����Ă��܂�����A���̗��_�{�Y�͂������ɔ��W�ł������A�A�����J�̉a�A�������Ȃ��Ɨ����s���Ȃ��Ȃ�悤�ȍ\�����A�����J�ɏ�肭���ꂽ�B 2008�N�ɃA�����J���g�E�����R�V������Ƀo�C�I�G�^�m�[���ɂ���Ƃ������n�߂ĉ��i��݂�グ�A�ʂ������Ă���Ȃ��悤�ȏ�Ԃɂ��ꂽ��A�����ł���グ�ɂȂ�A���{�̗��_�{�Y�_�Ƃ��o�^�o�^�|��n�߂�Ƃ����A���ꂾ�������A�����J�Ɉˑ�������Ȃ��悤�ɂ���Ă����B �����P���R���ʂł̊W�ŁA�A�����J�Ɏ���Ă�����Ă���Ƃ������z������Ă���̂ŁA�A�����J�̌������Ƃ��Ȃ��Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ�@�Ƃ������ƂŎv�l��~�ɂȂ��ăA�����J�ɏ]�킴��Ȃ��Ƃ����\���ɂȂ��Ă���B�����Ă��̍\�����������Ă��܂����̂��ߔN�ɂ����鐭���s���̐��B �A�����J�̂����P�̐헪�́@���{�l�̓��̍\����V���R��`�Ƃ������A�s�ꌴ�����`�A�O���[�o�������邱�ƂłƂɂ����K���P�p�Ɩf�Վ��R������ΊF�K���ɂȂ�Ƃ������ƂŁA�A�����J�ɗ��w�����݂�ȌĂэ���ł����ēO��I�ɋ�������œ��{�ɕԂ����B���������l�����������ɂȂ����肵�Ă���B �F����郋�[����j��A�A�����J�́u�������A�������A���������v�̃O���[�o����ƂƂ����{�̂����ƂȂ����Ă���悤�Ȑl���������������ɗ��v���W���ł���悤�Ȍo�ώЉ������Ă��邱�ƂɂȂ邩��A�_�Ƃ��ꂵ���Ȃ�A��ʂ̐l�X��������������A������������A���NJi���Љ�ł����B ���ꂪ�u���v�v�ƌ������̂��Ƃ�30�`40�N����Ă��đ厸�s��������Ȃ����ƌ����Ă��邪�A�ނ�ɂƂ��Ă͑听���������B
���̂悤�ȍ\���̒��ŁA���Ă̂��F�B��Ƃ��ׂ�����悤�ɂ��Ă����̂��A�����J�̐��]�����{�l�̓��]�����̂悤�ɂ��Ă��܂����B 6.�H�ǖ@�ɂ���
�̂͂��������Ȃ����Ă��܂������A���̍��͂���Ă��邵�A����ɋ߂����̂�����Ă���B
�����Ȃ���u��������H���₪���āv�Ƃ����b�ɂȂ��āA�����������Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ������A�H�ǖ@�͗D�ꂽ���Ǝv���̂́@�_�Ƃ̕������Y�𑱂�����悤�ɁA1�U60kg��2���~�Ŕ����āA����҂̊F����͂����Ɣ�����悤�ɂƁA1���~�Ŕ���@�ƁA���̂悤�ɗ����������Ă��̍��߂�Ƃ����̂�����̖������ƁB �������S�������邩�炻����������̓_�����Ƃ����đS�Ĕp�~���Ă������B���̍��͌`�͏�������Ă��A���Y�҂̘J����V���܂߂��R�X�g�Ɍ��������i�Ɣ����Ă��鉿�i�ɍ����o����A������A�����J���@100%�s�����͕����܂��@�Ƃ��A���[���b�p�͑����̍��̓X�C�X��t�����X�Ȃǂ͔_�Ƃ̏����̂ق�100%���ŋ��ŕ����Ă���B �����Ȃ��炷��A����Ȃ��Ƃ����ėǂ��킯���Ȃ����낤�Ɠ��{�ł͌�����悤�Ȃ��Ƃ����E�ł͋N�����Ă���B
���ꂾ���A�H���������Ŋm�ۂ��邱�Ƃ������Ƃ������ɍ����̖�����邩�Ƃ����F���ł���B ���ǁA���i�̔_�Ƃ���邽�߂̃R�X�g���@���Ƃ��N�Ԃ��̐H�ǐ��x�݂����Ȍ`��1���~�]�v�ɂ�����Ƃ��Ă��A���낢��ȕs���̎��ԁA������A�����~�܂������ɐH�ׂ���̂��Ȃ��Ȃ��Ă݂�Ȃ��Q�����ɂ���悤�Ȃ��ƂɂȂ�����A����͎��Ԃ��̂��Ȃ��R�X�g������ł���B
�����������X�N�������܂��Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�����̖�������Ԃ̈��S�ۏ�A�܂��ɍ��h�A���h�͂܂��ɕs���̎��Ԃɍ����̖�����邱�ƂȂ̂ŁA���̃R�X�g�i���炫����ƕ��S���Ă����@�Ƃ����̂��܂��ɖh�q�B
7.�H�����S�ۏ�ɂ��� �h�q���ł������43���~���g�����Ƃ��Ă��邪�A���̂悤�Ȃ���������̂�������A�A�����J�̍ɏ����̃~�T�C�������̂ɉ��\���~�g���킯�����A�܂Ƃ��Ɏg���Ȃ��悤�ȕ����43���~�����������̂���������̂�������A�H�ǖ@�݂����Ȃ��̂����āA����Ŗ��N1���~�H���ɂ����邱�Ƃ��{���̍��h�ł͂Ȃ����B �����Ƃ����Ƃ��ɍ����̖������̂����h�Ȃ�A�H���������Ő��Y�ł���悤�ɁA�������݂�Ȃō����I�ɂ����S����Ƃ������Ƃ����h�̈꒚�ڈ�Ԓn�ł͂Ȃ����B �������������̎g����������������A�h�q�̂ق��ɂ̓A�����J����̗v�������邩��A�����Ȃ��_���\�Z�������āA1970�N�ɂ��ł�1���~�߂����������̂�50�N�ȏソ���Ă��܂�2���~�ŁA����ȏ�͏o���邩�@���Č����Ă���B
�h�q�\�Z�͂ǂ�ǂ�c���Ŗ��N10���~�K�́B�R���A�H���A�G�l���M�[�����Ƒ�����3�{���Ɛ��E�I�ɂ���������ǂ��A���̒��ł���Ԗ�����邽�߂ɕK�v�Ȃ̂��H���B
�H�����Ȃ�������ɂ��ĕ��킾��43���~�������āA�U�߂Ă������A�Ȃ�Č��������āA�키�O�ɒ����ɃV�[���[�������ꂽ��A�Q�����ɂ��ďI��肶��Ȃ��ł����B���ɂ��тȐ���ɂȂ��Ă���B 8.�O���[�o���X�g�����i���Ă��鐭��ɂ���
����ł͂܂Ƃ��ȐH�Ɛ��Y���ǂ�ǂ��Ă��@�R�I���M��H�ׂ��������Ȃ����݂����Șb�������āB���[���b�p�̔_���Ꝅ�ƊW���Ă���B
�v����ɁA���Ɉ����̂��_�Ƃ⋙�Ƃ��Ƃ����b�ɂȂ��āA�������������̂���߂ăR�I���M�Ɛl�H���ƃo�C�I���ɂ��܂��傤�@�Ƃ����������_�{�X��c�ɏW�܂��Ă���悤�ȋ���ȃO���[�o����Ƃ̊F�����̃r�W�l�X�Ƃ��čl���Ă���B ���{�ł��_�Ƃ͂ǂ�ǂ�ׂ�Ă���̂ɁA�R�I���M��H�ׂ��������Ȃ����Ƃ����c�_�ɂȂ��Ă���B�n�����g���̈�Ԃ̈��҂��@�c��ڂ̃��^���K�X�Ƌ��̃Q�b�v���Ƃ����b�ɂȂ��Ă���B�c��ڂ�����N���O���炠�邵�A���������ƑO����Q�b�v���Ă���̂�����A�H�Ɖ��������牷�g�������Ƃ����͖̂��炩�����A�����͔̂_�ƁA���_�A�{�Y���ƌ����n�߂��B�����炻�������l�H�I�Ȃ��̂�H�ׂ��������Ȃ����@�Ƃ�������Ɏ����čs�����Ƃ��Ă���B �͖쑾�Y���e���r�ŃR�I���M��H�ׂ�p�t�H�[�}���X������Ă������A���ʃR�I���M�͐H�ׂȂ�����Ȃ��ł����B�C�i�S�Ƃ��I�̎q�͐H�ׂĂ��A�R�I���M�͐H�ׂȂ������Ƃ����̂͂���Ȃ�̗��R������B��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B ������킴�킴�������̍��Z�̋��H�ŏo���Ă݂���A���͂����݂�ȐH�ׂĂ����ł���B�\�������Ȃ��Ă��A�u�R�I���M�p�E�_�[�v���ď����Ȃ��Ă�������@���Ă��ƂŁA�����u�A�~�m�_�v�Ƃ�����Ȃӂ��ɏ����āA���̃p�E�_�[���ǂ�ǂ���{�l���H�ׂĂ���H�i�ɍ����Ă��Ă���B�m��Ȃ������Ɉ�ʂ̐l���H�ׂĂ��܂��Ă���B ���[���b�p�ł́@���������A�_�Ƃ͈��҂��@�Ƃ����������낤�ƍ����Ă��āA�⏕����啝�ɃJ�b�g����Ƃ������Ƃ������n�߂��̂ŁA�_�Ƃ��N�����ăg���N�^�[��l�C��p�œ��H�����āA���S������H���������Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ܂ł���Ă���B�h�C�c�ł̓g���b�N�ɋ���̕��A��ςݍ���ō���c�����ɂ܂��U�炵�Ă��邪�A�����́u�������A�݂�ȂŊ撣�낤�B�H������낤�v�ƌ����Ĉ�̉����Ċ撣���Ă���B���̂��炢���E�͓{���Ă��邪���{�̊F����͉䖝�����B
���{�l�������͂��������悭�l���āA�����������ǂ̂悤�ȏɒu����Ă��邩�A�l����ׂ��B 9.������������l��l���ł��邱�Ƃ́H
�����Ȃ��Ȃ������Ȃ��̂ŁA���������̗͂Œn�悩�痬���ς��Ă������Ƃ����Ȃ�������Ȃ��B����҂Ƃ��Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂́u�������̂ɂ͖���v�Ƃ������ƂŁA�A�������S�������Ƃ͌���Ȃ����A���X�N�̂�����̂������̂�����A�����������̂��ł��邾��������B ������������ȂɒႢ�Ƃ����̂́@�݂�Ȃ�����ɔ�т��Ă���Ƃ������Ƃł�����B���X�ł��������ėA�������炷���Ƃ͂ł��Ȃ����A������������u�����Ă���A�����Ă��܂��Ă���Ƃ������Ƃ��傫�ȗv���Ȃ̂ŁA���������̖��A�q�������̖������ɂ́@���X�N�̂���A�����Ɉˑ�����̂ł͂Ȃ��A�ł��邾���n��n��Ɉ��S���S�Ȃ��̂�������������Ă���Ă���l����������킯������A���������l�����̂��̂��o���邾�������u�n�Y�n���v���x�[�X�ɂȂ�B���������Ӗ��ł̏���s���ƒn��Œn�Y�n���Ŕ_�Ɛ��Y���Ă���������̂����������̂Ƃ���ł�����������悤�Ȏd�g�݂Â�����L���Ă����邩�ǂ����Ƃ����̂���Ԃ̃J�M�ɂȂ�B
���H�̌������B�A�s���⒬���������āA�A���̏����͈�������ǂ����n��_��Ǝ��n�O�̔_��̖��Ƃ���������̂ŁA���X�N������B�n���̏�����ł��邾���R���������̑���Ɏg�����肵���肵�āA�ł��邾���n���̈��S���S�ȐH�ނ��q�������ɏo����悤�Ɏs�⒬���������@�Ƃ����������B�ŁA���I�[�K�j�b�N���H�Ƃ��̓������L�����Ă��Ă��邪�A���ꂪ�傫�ȃJ�M�ɂȂ�B �悭��ɏo��̂͐�t�������ݎs�̎s�����L�@�č���Ă��ꂽ��1�U24000�~�Ŕ������܂�����撣���Ă��������ƌ�������A�L�@�Ĕ_�Ƃ�1�����Ȃ���������ǂ��A���s����Ŋ撣���āA4�N�ʂŎs���̋��H�S���L�@�ĂɂȂ����B ���ꂩ�������Ȃ�L�@�ɂȂ��Ă����A������S�L�@�ł͖����ł��A�����w�엿�A���_����ʍ͔|�Ăł���������n�߂Ă������킯�����A����ɐG�����ꂽ�������{���ɍL�����Ă��āA���s�̋T���s�̎s������́u�����ݎs��24000�~�Ȃ玄�͂��̔{�A48000�~�Ŕ������܂��v�Ƃ������ƂŁA���傤�ǎ����Z�~�i�[�ł��b�����Ă��������ɋT���s�̎s�����錾�����̂ŁA�_�Ƃ̊F���甏�肪�N�������B
�����炻�̂��炢�A�����Ȃ��������o���Ă���Ȃ��Ă��A�s�������������������Ă��q���̌��N�����\�Z�͉����������Ƃ�����@�Ƃ������Ƃł���Ă����A�_�ƂɂƂ��Ă��@��������Ƃ����o�����v���ł��āA���i�����肷��A �q�������C�ɂȂ�ƁA��肪��������@�Ƃ݂�Ȃ��n�b�s�[�ɂȂ�B
�������n��ŕ����z����킯������A���Ƃ��A�����ݎs�ł��������͂������H���o���Ă���Ďq�����������C�ɂȂ��Ă���@�Ƃ����̂����āA�ڏZ�҂������Ă���B��������Ɛl���������Ă���B ����������������Ƃ����āA���ł���Ƃ��A�x�o�����炷�Ƃ��A����Ȃ��Ƃ������Ă���ƌo�ς��Љ���ǂ�ǂ�k�����邾���B
�u���[�J���������v�ƌ����āA�n��̎�������āA����łł������̂��݂�Ȃŏ���ĉĂ����Ƃ����d�g�݂����B
���Ύs�̐�s�����\���Ƃ��Ŏ��߂�ꂽ���A���ꂾ���̐Ԏ������̒��ő��ł���Ȃ��Ďq������鋋�H�̖������Ƃ��A���������\�Z��2�{�ɑ��₵���킯�ŁA�u������Ăv�ƌ���ꂽ����ǂ��A���ʓI�Ɏq�������C�ɂȂ��āA���X�X�����������ďo�����������Đl���������ĐŎ��͑����Ă����B
�q���▽�����H�Ɋւ�鐭��������Ƃ��A���Ǎ��������S������B 10.���{�l�Ƙa�H
�ԈႢ�Ȃ��B�R���𒆐S�Ƃ����H���������{�l�ɂƂ��Č��N�����̂ɓK���Ă���B�n��̓y������A�����ň�������̂�H�ׂ�̂����̐l�ԂɂƂ��Ĉ�ԓK���Ă���B���{�͓c��ڂ����������Ă����łł����R���𒆐S�ɐH���������Ă����Ƃ����̂��n�Y�n���ł���A�ł��邾���n��ŁA���Ȃ��Ƃ������ŁA�����Ăł��邾���������Z��ł���n��łƂ����̂𒆐S�ɂ��ĐH�ׂĂ����݂�Ȃ̌��N������B
�y��ɂ���ۂƂ����݂ɂ������Ă����肵�āA�y��̍ۂ��l�X�̒����ۂƂ��֘A���Ă���̂ŁA�n�Y�n���I�ȓ��{�̕��y�ɍ��������̂���������Ǝx����̂���Ԃ̃x�[�X�ɂȂ�B���{�l�̒����ۂƑ��̍��̐l�̒����ۂ͈Ⴄ�ƌ����Ă���B���Ƃ��Γ��{�l�̓��J���͐H�ׂ��邪�A���m�l�͐H�ׂ��Ȃ����A��`�I�ɂ��������ӂ��ɂȂ��Ă���̂͂����̕��y�Œ��N�����Ă����̂����������ӂ��ɂȂ����B
���ꂪ�����Ȃ�A�����J�̐H�������P�^�����n�܂����B�u�R����H���Ɣn���ɂȂ�v�ƌ����āA�ǂ�ǂ�p���Ɠ���H�ׂ�����ꂽ���A���{�l�ɂ͂���Ȃɍ����Ă��Ȃ��B���{�l�͋��������ނ����ł��Ȃ����S���S������l�����Ƒ������A�����ɂ��Ă͐F�X�ȕ]�������邪�A���͉h�{�f���l�܂������ݕ��A�P�d�v�ȐH���Ƃ��Ă��Ă����K�v������Ǝv�����A�ł��邾�����{�̕��y�ɂ����`�Ō�����H�������l���邱�Ƃ��厖�B
�_���Ȃ�����18�N�ɐH�Ǝ��������|�[�g�Ƃ����̂ŁA�H�����������������Ē��S�̘a�H�ɂ���A�H����������63���܂ŏグ����Ƃ����������o���Ă���B �u����͂�������Ȃ����A����Ɋ�Â��Ă݂�Ȃōs���v��A�\�Z�����Ă�����Ċ撣�낤�v�Ǝv���Ď������ׂ���A�Ȃ�ƁA�l�b�g�ŃA�N�Z�X�ł��Ȃ��Ȃ��Ă���B
������s�v�c�Șb�Ƃ������A������O�̘b�Ƃ������A�v����ɓ��{�̐H�����������a�H���S�ɂȂ���63%�܂ŏグ��Ƃ����̂͂����Ă͂����Ȃ��A�������m���Ă͂����Ȃ��@�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B
�F�X�Ȍ`�Ō��������[�����~����Ă��邪�A�����͒n��A�n��ŕς��Ă��������Ȃ����ȂƎv���B
�݂�Ȃ������̒n��ő厖�ȍݗ��̎�A�Œ�����������Ǝ���ďz�ł���悤�ɂ��āA���Y���Ă��ꂽ���̂��݂�Ȃŋ��H�Ŏx���AJA���͂����Ă��邪�A�}���V�F�Ƃ��������̂悤�Ȏd�g�݂�����������Ɗg�債�Ă����A���݂��ɐ��Y�҂�����҂��v���X�ɂȂ�̂ŁA�����������Ƃ��܂߂Ēn��̎킩����z�^�H���������A���[�J���������A�����n��ʉ݂Ƃ������������̂Ń��[�J���������A�n��ʉ݂��Z�b�g�ɂȂ�Βn�悩��ǂ�ǂ���{���ς���Ă����Ƃ�������A����Ɏ����̂̐����s������������Ɗւ���ăT�|�[�g���Ă����A���ꂪ���˂�ƂȂ��āA���̐����s�����@���������������ꂴ��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��č��̐������ʓI�ɂ��������l�����������Ă����A�ߋ��̗�̂悤�ɁA��l�ŃA�����J�ɑR���悤�Ƃ��Ēׂ���Ă����������l�������邪�A����c���̊F��������������������悤�ɂȂ�Ες���Ă���Ǝv���B
�n�悩��̎��������̎��g�݂�n��̐����s����������~�߂đS���I�ȍL����ō��̐������ς��Ă����Ƃ����A���˂���N������Ǝv���B
�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�ȏオ�@��؋����̘b�̃|�C���g�������Ƃ������̂ł��B �F�X�Ƒ厖�Ȃ��Ƃ�b����Ă��܂����A���{�̐H����������37%�ł͂Ȃ��A��܂ōl������A����10%��邭�炢�ɂ܂łȂ��Ă���@�Ƃ����̂́@�_�Ə]���҂̕��ϔN�68�Ƃ��A70�߂��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��܂߂āA�����Ɛ[���ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B ���{�͂܂��ɁAGHQ�̐�̐���ŁA�o�ϐ����A���Ɏ����ԃ��[�J�[���̐��E�i�o�A����g��ƈ��������ɔ_�Ɛ������ɋ]���ɂ��Ă����̂ł����āA���̌��ʂƂ��� �H�ǖ@�̔p�~�A���R�f�Ղׂ̈̊ł̓P�p�A�����̐��i�A�_�Ƃւ̕⏕���k���A�A�����J�̔_�Y���������ׂɐH�i�Y�����̋K���𐢊E�ň����x���ɂ܂Ŋɂ����邱�Ƃ������Ƃ���Ă��܂����B ���������O��������A�_�Ƃ�ی삷�邽�߂ɕ⏕���Ŕ_�Ƃ��_�Ƃ𑱂�����悤�ɂ���A������O���������낤���A�����ׂ̈ɐH�̈��S�����@�Ƃ����̂́@����������O�̂��Ƃł��̂ŁA�_�Ƃւ̕⏕�������炻���Ƃ�����ACO2�팸�ׂ̈ɔ_�n�����炻���Ƃ�����A�E�N���C�i����̈��S���ɋ^�O��������������Ɋł�P�p������AEU�̑����̍��Ł@��K�͂Ȕ_�Ƃ̃f�����N�������킯�ł��B ����ƁA�����H��o�C�I���Ȃǂ̐��i�́@�܂��Ƀ_�{�X��c�ɏo�Ă���悤�Ȑ��E�̂����ꈬ��̃G���[�g���������i���Ă��鐭��ł����āA�������A�u���X�̎ҁv�ɂ� CO2�����炷���߂ɒ{�Y�̓����H�ׂȂ��悤�ɂ��܂��傤�A������o�C�I����H�ׂ܂��傤�@�ƌ����Ă����Ȃ���A����Ŕނ�G���[�g�́@�v���C�x�[�g�W�F�b�g�Ń_�{�X��c�ɏ��t���A���ʂɒ{�Y�̓����H�ׂāA�r���E�Q�C�c���̂悤�Ɂ@�����A�푈��H����@���N���������ׂ̈ɂƁA���E���ɔ_�n�������Ă���킯�ł��B --------------------------�R�s�[�I��
|
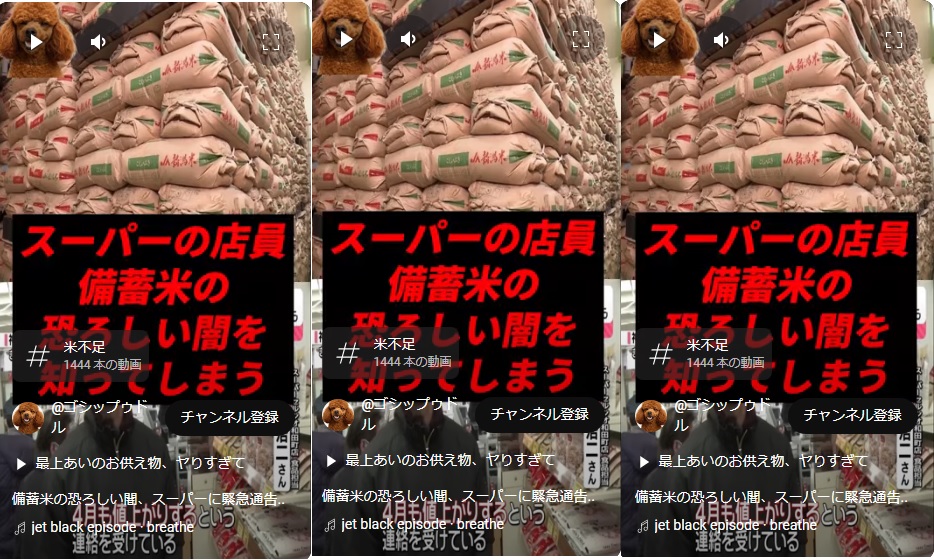
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B