|
���c����͂��ݎ������ɏo���̂͂��������d�|���l�������悤�ŁB ���c�����c���͂Ȃ��u�l�b�g�E���E�v�̒����ɂȂ����̂��H���̌����u�o�Ŏ�X�l���v��T��
�ÒJ�o�t | ��Ɓ^���M�Ɓ^�]�_��9/30(��)
https://news.yahoo.co.jp/byline/furuyatsunehira/20200930-00200742/ ��L�L�����A�ȉ��ꕔ����
������̓}�x�́A�ێ�E�G�E�l�b�g�E���֑i�����A�O���l�ɂ����鐶���ی�s���̖��Ȃǂ����ʂɋ��������A���ۂɂ͐����ی�s���̗�͋ɂ߂ď��Ȃ��A�l�b�g���_�ɑi������s�����������咣���L���҂ɖ�������Ĕj�ł����B��������2014�N11������A���c���͋c���o�b�W���O���A�ݖ�̊����ƂƂ��Ă��̕������L�����B
�@���̎��A���c���ɂ����������ڂ����̂��A�����s�a�J��ɖ{����u���o�ŎЁE�ѓ��ł���B���c���̏��̒���́A�w�Ȃł������� �\���������Ƃ��ł��邱�Ɓ\�x�ł���A�Ō��͂��̐ѓ��ł������B���m�Ɍ������̐��c���̏��̒���㈲���A���́w�ېV�x�ɏ������Ă��āw������̓}�x�c���ł͂Ȃ��������̂́A���̏�����̏o�ł���킸�����N���o�����Đ��c���͋c���o�b�W���O���A�����ݖ�̊����ƂƂ��Ă��̊����̕����c���ݖ�ɍL���邱�ƂɂȂ�B���̔ޏ��́u�l�b�g�E���Ƃ��Ă̍ˁv�����������������A�����Ē�������s�����ނ�Ɏ������̂��ѓ��ł���B����A�Ƃ������A�L�[�p�[�\���ƂȂ�̂͐ѓ���\������В��ł���'�I�]���F�i���ɂ��݂��Ђ��j���̒߂̈ꐺ�ł������B �@�M�҂��琄�@����ɁA���c���̕ێ�E�G�E�l�b�g�E���E�G�ւ̑i���́A�ނ���w�ېV�x���w������x���o�Ă���̐ѓ��ɂ�銧�s���̃l�b�g�E���E�G�ł��Y�t�i��������j�ɂ��`�����ꂽ�ƌ����ĂقڊԈႢ�͂Ȃ��B���̎�����A�v����ɉ��쎞��ɂ����Đ��c���͕ێ�E�G�E�l�b�g�E���E�G�ł̔F�m���}���Ɋg�傳���Ă������B�܂萙�c���́A�w�ېV�x����͒m��l���m��E�h�_�q���������A���̊E�G�ł̖{�i�I�F�m�́A�ނ��뎁����c�m�̃o�b�W���O���Ă����2014�N�ȍ~�̉�����Ԃɂ�����A�o�ŎЁE�ѓ��𒆐S�E�}��Ƃ����u�I�o�v�ɂ����A���̊j�S������Ƃ�����B �@�Ȃ��M�҂����̂悤�Ȓf��I����������̂��ƌ����A�����g���A���̎���������̐ѓ��Ɛ[���������������Ă�������ł���B��̓I�ɂ́A2012�N�`2013�N�ɂ����āA�ѓ������s���Ă����E�h�n�E�l�b�g�E���n�̃I�s�j�I���G���A�w�W���p�j�Y���x�̕ҏW�����߂Ă�������ł���B����Ă��̎����̑O��ɂȂ��A���c���������ێ�E�G�E�l�b�g�E���E�G�Ŋ���悤�ɂȂ����̂��B���̌o�܂��M�҂ɂ͂܂�Ŏ�Ɏ��悤�ɔ������邩��ł���B �E���c�������A��t��q���A�͂��݂Ƃ��������u���@�v�����ѓ� 2012�N�A�܂�����}�����̖����ł���������A���c��������SNS�w�c�C�b�^�[�x���g�p���Ă������A���̃t�H�����[���͕M�҂̋L���ɂ��Ƃ���2�����x�ł������i2020�N9�������݂ł͖�19���j�B�����A�ێ�E�G�E�l�b�g�E���E�G�̋C�s�̐V�l�Ƃ��ĔF�m����Ă����M�҂ł���A���̃t�H�����[����1�����炠�������Ƃ��l����ƁA�s��̃��C�^�[�ł������M�҂ƁA���������O�c�@�c���ł��鐙�c���̂���́A�����I�Ɍ���ΊT�ˑ卷�Ȃ��B��͂肱�̎��_�ŁA���c���́u�ێ�E�G�E�l�b�g�E���E�G�v�̓_�i�ɉ߂��Ȃ������̂ł���B �@�Ƃ��낪���c�����O�f2014�N�̏O�@�I�Ŕs�ꉺ�삷��ƁA�������ăl�b�g�E�G�ł̐��c���̕]���͂ɂ킩�ɁA�������x�I�ɏ㏸�����B����͓e�ɂ��p�ɂ��A�E�h�I�E�l�b�g�E���I���l�ς������Ĝ݂�Ȃ����c�����A�ѓ����u�~���グ���v���ʂɂق��Ȃ�Ȃ��B�����ƌ����A���̍єz�͓��ЎВ��̊I�]���F���̒߂̈ꐺ�ƌ����Ă��悩�����B �@���̎����A���͐ѓ��̎В��E�I�]���Ƌٖ��ȊW��z���A�O�f�w�W���p�j�Y���x�̔��s�Ɩ���簐i���Ă����B���������ѓ��ƊI�]�����A�����ێ�E�G�E�l�b�g�E���E�G�Ɛړ_�����悤�ɂȂ����̂́A�[���N�㒆�Ղɓ��Ђ����s��������M�҂̒������A�E�h�nCS�����ǁw���{�����`�����l�����x�i���݂�CS��������P�ށj�ɏЉ�����˂ĉc�Ƃ����̂����[���Ƃ����i�|���Ȃ݂ɓ��{�����`�����l�����{�ЂƁA�o�ŎАѓ��͓����a�J��̖ڂƕ@�̐�Ɉʒu����j�B �@���̕ӂ�͏ڂ����Ȃ肷����̂ŏڍׂ͏Ȃ����A�Ƃ�����ҏW���Ƃ��Ă̎��̈ӎv�ɊW�Ȃ��A�I�]���͕ێ�n�E�l�b�g�E���n�ɑi������u���_�l�v��u�����l�v�̔��@�ɗ]�O���Ȃ������B�����Ō��������ꂽ�̂����c�������ł���A�u�����i�p���N�j����E���ɓ]�������v�Ǝ��̂��錳�A�C�h���̐�t��q���A�̂��ɃW���[�i���X�g�̈ɓ����D���ւ̖��_�������Ŗ����i�ׂ̔퍐�l�ɂȂ閟��Ƃ̂͂��݂Ƃ������炪���̌n��ł���B �@���c�A��t�A�͂��݂�3���́A�T�˂��̎����ɁA�ѓ����Ƃ����̑�\������ł���I�]���ɂ���Ď��X�ƕێ�E�G�E�l�b�g�E���E�G�ł̃f�r���[�����邱�ƂƂȂ�B�I�]���͂��łɏq�ׂ��ʂ�w�ېV�x����̖����A2014�N�ɐ��c�������ď���������s������ƁA��t��q���́w����Ȃ�p���N �\�`�o���C�����������̎��ԁ\�x�i2016�N�j�A�͂��݂Ƃ������́w����������悤! �͂��݂Ƃ����̐��E�x�i2015�N�j�ƁA�ێ�E�G�E�l�b�g�E���E�G�ɑi������P�s�{�𑱁X���s������Ɏ���B��������������̊��s�ƁA����Ɍĉ�����SNS�ł̊g�U���_�@�ƂȂ��āA���c�E��t�E�͂��݂�3���́A�ێ�E�G�E�l�b�g�E���E�G�ł����܂������Ƃ��Ď��Ě������悤�ɂȂ�B �@�����l����ƁA���c��c�m�͂��Ƃ��A��t��q���A�͂��݂Ƃ�������̃f�r���[�̐��|����������̂́A�����܂ł��Ȃ��o�ŎЁE�ѓ��ł���A���Ђ��犧�s����銧�s���̎�����̑S�Ă̍єz�������Ă����I�]���̃v���f���[�X�̎����ł���B �@�M�҂́A�ҏW���j���̈Ⴂ����2013�N���ՂɂȂ�Ɛѓ�����ъI�]���Ƃ͑a���ɂȂ肪���ł��������A�����M�҂̏��Ɗ��s�{���鏈�����2012�N�ɓ��Ђ��犧�s����Ă���A�I�]���ɂ͕��X�Ȃ�ʉ��`�������Ă���̂ł���i�|�����ĊI�]���̃~���^���[���ʂł̒m�����w�̐[���ɂ��h�����Ă���A���̒m���ʂ͕��̃I�^�N��y���ɗ��킷��ƌ��݂ł��v���Ă���j�B�����ōm����ے���r�������]���������ƁA�I�]���͏����ɓ�������̐M��ێ�E�G�E�l�b�g�E���E�G�̐M��u���E�����E�������V���E�������i��}�j�v�Ƃ�������`�ɐ��c���E��t���E�͂��ݎ��炪���v����ƌ�����ł̎v�f���������悤�Ɏv���A�����ɉ��炩�̎הO������Ƃ͎v����B�P���ɁA�I�]���̌o�c�҂Ƃ��Ă̚k�o���A�����A�ێ�E�G�E�l�b�g�E���E�G�ȊO�ł͂قږ����ɓ������������c�����f�r���[���炵�߂��̂ł��낤�B �@����������̓W�J�́A�ѓ��ƊI�]���̎v�f��傫���������W�J��������B���c���͐ѓ��ł̏����씭�\�̌㉺�삵�A���쎞��Ɂu���A���Ԉ��w�^���v�Ŗ���y���A�����ɕێ�E�G�E�l�b�g�E���E�G�̐M�p�����������B�ǂ̎��_�ł��͔��R�Ƃ��Ȃ����A���̊����Ɏ����}���ڂ����A2017�N�ɒ������ł̌��F�邱�ƂɂȂ������B �@��t���A�͂��ݎ����c���ɂȂ�Ƃ�������H��Ȃ���Γ����ŁA����{�������������Ă��炵�炭�A2013�N�`2014�N�ɕێ�E�G�E�l�b�g�E���E�G�Ƀf�r���[���邱�ƂŁA�u�����l�v�Ƃ��Ă̒n�ʂ��ł߂��B���������̎O�҂̑匳��H��ƁA���ׂĐѓ��ƊI�]���F���ɍs�������B�܂萙�c���́A�����}���痧����Őf����͂邩�ȑO����l�b�g�E���̑O�q����ѓ��ƊI�]���Ɍ����܂�Ă������炱���A���݂̒n�ʂ�����B�����}���A�����̍ݖ슈���Ƃ���������}�Ɉ�{�ނ肵�Ă����킯�ł͂Ȃ��̂ł���B �q�ȉ����r ���̍��ɐ����鏗�Ƃ��ẮA�܂��͂��������\���œ��{�Љ�o���Ă��邱�Ƃɓ���Ă����܂���B
|
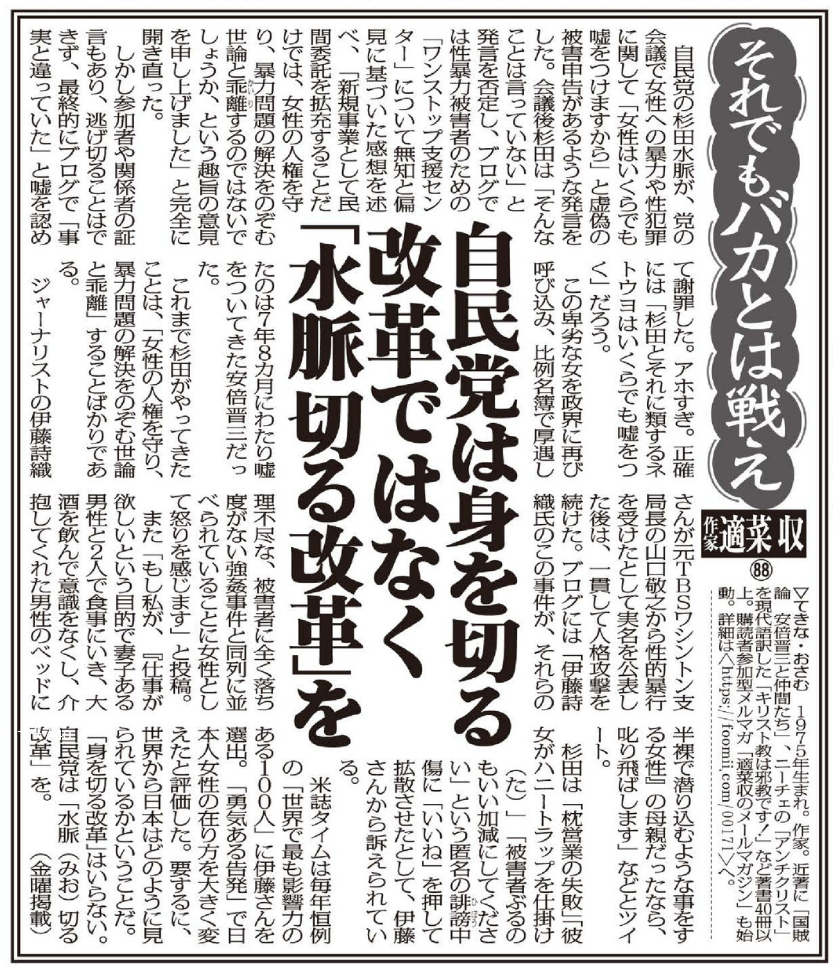


 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B