http://www.asyura2.com/20/ban8/msg/821.html
| Tweet |
(回答先: 少子化は技術の進歩で、日本人全員が必要とするすべての物を少数の人間で簡単に作れる様になったのが原因 投稿者 中川隆 日時 2021 年 1 月 30 日 12:05:48)
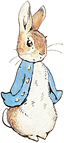
大西つねきさんが10年前から言い続けている事だよ、NHKが エンデの遺言 を放映してから有名になった話だけどね:
エンデの遺言 〜根源からお金を問う〜
https://www.youtube.com/watch?v=Hh3vfMXAPJQ
民間銀行はもうこの世に必要ない(Live配信2021/1/12)
https://www.youtube.com/watch?v=a3y34SLGKlo
米国のMMT政策は日本を破壊(Live配信2020/11/17)
https://www.youtube.com/watch?v=nYgXByuRzMU&feature=emb_title
いま220兆円を配らなければいけない理由:大西つねきからの緊急告知と拡散のお願い
https://www.youtube.com/watch?v=dawE3Kjgmbg
- 新型コロナウィルスの世界的流行によって世界経済は未曾有の景気後退にさいなまれ、日本やアメリカなどの先進国政府は紙幣印刷… 中川隆 2021/1/31 00:13:18
(3)
- ハイエクvsケインズ〜経済学を変えた世紀の対決 中川隆 2021/1/31 00:33:03
(2)
- 日銀当座預金には利子がつくし、たとえ国債がマイナス金利でも日銀が民間企業が買った値段より高く買い取ってくれるので、国債… 中川隆 2021/1/31 11:19:36
(1)
- 所得税最高税率 90%で所得再分配できるというのは妄想だ。 所得税の累進課税では所得再分配は不可能 中川隆 2021/1/31 20:49:40
(0)
- 所得税最高税率 90%で所得再分配できるというのは妄想だ。 所得税の累進課税では所得再分配は不可能 中川隆 2021/1/31 20:49:40
(0)
- 日銀当座預金には利子がつくし、たとえ国債がマイナス金利でも日銀が民間企業が買った値段より高く買い取ってくれるので、国債… 中川隆 2021/1/31 11:19:36
(1)
- ハイエクvsケインズ〜経済学を変えた世紀の対決 中川隆 2021/1/31 00:33:03
(2)
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。