|
原発なしでも平気などというのは現実が分かっていない。 2016.8.9 21:17更新
太陽光事業者の倒産急増 電気買い取り価格引き下げ、安易な参入… 今年は過去最悪ペース
http://www.sankei.com/economy/news/160809/ecn1608090033-n1.html
太陽光発電に関連する企業の倒産件数が今年、過去最悪のペースで推移していることが分かった。1~7月の累計倒産件数は前年同期比7件増の37件、負債総額は同比15.7%増の179億1300万円に上る。再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)が生んだ“太陽光バブル”の収束で市場は縮小を始めており、事業者の淘汰(とうた)が加速する恐れがある。(田辺裕晶) 東京商工リサーチが太陽光発電パネルの製造や卸売り、施工、売電など関連企業を対象に調査した。既に倒産件数は年間ベースで20件台後半だった24~26年を上回り、過去最多を記録した27年に次ぐ水準だ。 住宅リフォームの東海住宅サービス(愛知県)は、太陽光発電パネルの卸売り・施工の事業に参入後、一時は同事業が売上高の約7割を占めたが、今年4月に負債総額4億3800万円で倒産した。倒産企業の負債総額は同社のような1億円以上5億円未満の企業が多いという。 FITは東京電力福島第1原発事故後、民主党政権が原発依存を減らそうと24年7月に導入した。再生エネで発電した電力を一定期間、大手電力に全量買い取るよう義務付けている。 ただ、太陽光は買い取り価格が他の電源より高く、環境影響評価(アセスメント)が原則必要ないなど発電設備の設置も容易とあって参入が殺到した。発電事業の認定を受けた事業者の約9割を太陽光が占める。
こうした官製市場に踊った一部の企業が、実現性に乏しい安易な事業計画で参入した結果、業績の見込み違いから倒産が増加した。 太陽光の急増で買い取り費用は27年度に約1兆8千億円まで増加し、電気料金への転嫁で家庭や企業の負担が重くなった。政府は段階的に買い取り価格を引き下げた上、29年4月施行の改正再生エネ特別措置法で事業用の太陽光に発電コストの安い事業者の参入を優先する入札制度を導入するなど制度自体も見直した。 政府は今後、地熱など太陽光以外の再生エネに力を入れるとともに、太陽光は「FITに頼らない自立した事業者を増やす」(経済産業省幹部)方針だ。 優遇措置の見直しを受け太陽光の事業環境は急速に悪化しており、東京商工リサーチは「倒産の恐れがある信用不安の企業も増えている。今後は売電事業者など事業規模が大きな企業が破綻するケースも出てくるだろう」と分析している。 「原発なしでも大丈夫」というウソ 2016年4月 再生可能エネルギー、太陽光発電・・・それで本当に日本の電力を賄えるのか 5年前の2011年3月11日以来、国民は突如として重大な問題に向き合うことになった。東日本大震災による東京電力福島第1原子力発電所の事故をきっかけに、原発が容易に稼働できなくなった今、生活に欠かせない電力をどうやって賄うのかという問題である。 震災前、日本全国では総電力の4分の1以上、28.6%を供給してきた原子力発電所は、2年後の2013年にはゼロになった。それでも、私たちは震災前と変わらない、電気に”あふれた”生活を送っていた。そのため、「原発がなくても何とかなっている(=だから原発はいらない)」という感覚に陥った国民が多い。しかし、本当にそうだろうか。「原発がなくても何とかなっている」のだろうか。 私はこれまで、福島第1、第2、柏崎刈羽原発(新潟県)、浜岡原発(静岡県)、敦賀原発(福井県)、高浜原発(福井県)、伊方原発(愛媛県)、川崎火力、大井火力、大井川水系の水力(静岡県)、武豊火力(愛知県)、メガソーラーたけとよ(同)、本川水力(高知県)の13発電所を取材し、発電の現場を見てきた。私たちの生活の基盤であり、また国力の源ともなるエネルギー政策の在り方を、冷静に考えてみたい。 太陽光発電で安心というウソ 「日本全国、全て太陽光で電力は間に合います」 テレビを見ていると、こんな発言をするマスコミ人がいる。福島第1原発事故以後、太陽光発電は再生可能エネルギーの筆頭格として注目を集めている。太陽光パネルを設置すれば家庭でも導入できることから、太陽光こそが原発の代替エネルギーとなり得ると認識している人も少なくない。震災当時の民主党、菅直人政権時には、太陽光パネルを設置して電力事業を行う事業者に対して、送電網を持つ大手電力事業者は国が定めた固定価格で買い取らなくてはならないという「固定価格買取制度」も導入され、太陽光発電事業に参入する事業者も一気に増えた。しかし、太陽光発電がいかに不安定な発電か、その技術的限界を知る人は実は意外なほど少ない。いや、それどころか基本的な原理すら完全に誤解している人が多いのである。 大きな誤解の1つは、太陽光が強く照りつけさえすれば発電量は大きくなるという認識である。この認識に立てば、太陽がさんさんと照りつける真夏の発電量が最大ということになるが、実際はそうではない。太陽の高さによって、入射角度も変わってくることや、広く普及しているシリコン型のパネルは温度が高くなると効率が下がるため、ゴールデンウィークあたりの初夏が発電量のピークになる。つまり、太陽光パネルは雲の影さえなくなれば、十分に発電できるというような単純な理解は誤りなのである。 加えて、雲の影が及ぼすマイナスの影響も想像より遥かに大きい。例えば、10枚の太陽光パネルのうち、1枚に雲などによる影ができたとしよう。そうすると、10枚全てに太陽が当たっている時と比べて発電量は1割減、つまり9割の発電量だと考える人は多いだろうが、これはとんでもない誤解で、実際には発電量は1~2割程度まで落ちる。なぜなら、太陽光パネルは1枚当たりの電圧が低く、パネルを直列につないで必要な電流電圧を確保しているため、1枚でも影によって発電しないとそのパネルが抵抗になり、発電量が大幅に低下する場合があるのだ。 「乾電池の仕組みと同じです。テレビのリモコンが切れて電池を交換する時に、1本だけはなく全ての電池を交換しないといけないのと、原理としては基本的に同じです」 「メガソーラーたけとよ」を持つ中部電力武豊火力発電所所長、永崎重文氏は、こう解説する。 電気事業者は日々、電気の需要予測をたて、需要に応じ電気が滞らないよう発電量を瞬間瞬時コントロールするが、太陽光発電は、需要に応じて発電するのではなく天候に応じて発電するので、このコントロールが極めて難しい。気象予測の技術が発達したとはいっても、ピンポイントで雲の流れを、それも秒単位で予測することなどできないからだ。 激しく発電量が下がった時に、その分をカバーする電力を供給するなど、太陽光発電の不安定を補ってコントロールしているのは、大手電力会社が以前から持っている火力発電と水力発電である。電力会社の自前の太陽光発電だけではなく、新規事業者の太陽光発電による増減も、大手電力会社がコントロールしている。太陽光による発電量が多くなれば、火力や水力の発電量を減らし、少ない時はそちらを増やす。これを雲の流れに合わせて瞬時に対応しているのだ。コンピューターにより自動化されているが、このコントロールを抜きに、太陽光発電を一般的な電源にすることは不可能なのである。 当然、新規事業者による太陽光発電の電力の買い取りもこのコントロールの範囲内でしかできない。これまで何度か「大手電力会社が太陽光発電の買い取りをしない」と、あたかも大手電力会社が意地悪をしているかのような報道もあったが、その多くにはこうした原理への無理解がある。 国民の負担は年々、大きく 太陽光発電がここまで増えた理由の1つが、「固定価格買取制度」である。新たに再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱)の発電事業を行う事業者に対し、大手電力会社9社は、定額で発電分を買い取るという制度である。その費用は電気利用者が等しく負担させられている。つまり、実際に太陽光で発電した電気を使っていてもいなくても、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として全ての国民が負担しているのだ。その負担額が積み立て方式となっているところに、この制度の最大の問題がある。仕組みは次の通りだ。 制度が始まった2012年7月当初の大手電力会社の事業者からの買取単価は1kWh当たり40円だった。今は27円(2015年7月から)まで下がっているので、一見すると負担額が下がっているように思われる。しかし、新規事業者は発電を始めた年の単価が20年間適用されるので、2012年に始めていれば40円のまま、2013年に始めていれば36円のままであるのだ。それぞれの単価にその年の発電量を掛け、それを使用電力量で割ったものが、1世帯当たりの負担額となる。このままこの制度を続けていくと、2032年には、負担額は最大で4.1兆円、1世帯当たりでも月額1,146円になるという試算もある。 再生可能エネルギー発電促進賦課金 標準的な家庭の負担(月額)
2012年度83円
2013年度117円
2014年度225円 2032年度1,416円 太陽光発電を含む再生可能エネルギー事業の促進は公益に適うことは言うまでもない。ただ、一方で国民の負担は年々上がっていく。同時に、新規事業者にとっては、発電分は電力会社が買い取ってくれるのだから、とても「美味しい」事業である。これもまた現実なのである。 「震災翌日に、当時の菅直人総理大臣がヘリで福島原発の視察に行ったのを見て、あ、これは浜岡(原発)も止まるなと直感したのです」 こう述懐するのは、愛知県知多半島にある武豊火力発電所所長の永崎重文氏である。この直感から、同発電所では、1年8か月の間、運転停止をしていた、40年超の老朽火力発電所を再稼働させ、原発が止まった場合の代替電力として活用するために準備を始めた。 実際、永崎所長の予想は的中し、震災から約2か月後の2011年5月6日に、何の法的根拠もないまま、浜岡原発の停止要請が、当時の菅直人総理大臣によって出された。一旦止められた火力発電を使用可能にするには、メンテナンスなどで最低でも3か月程度かかるため、すぐには動かなかったが、13%もの電力不足が予想されていた夏には何とか間に合った。計画停電することなく、危機を免れることができたのだ。 「浜岡が止まって需要のピークである夏を迎えたら大変なことになると思ったので、震災の翌日からすぐに対応して、3月末には、復旧計画が出来上がっていました。それでもギリギリ、7月末に運転開始ができましたが、古いものだと、補修すると言っても部品がないことも多く、日本中の部品メーカーに当たって、何とか調達したのです」 永崎氏は話す。そこには「何としてでも電力の供給を滞らせてはいけない」という、電気事業者としての高い使命感があったことは否定すべきではないだろう。思い返してみると、福島第1原発事故以後、計画停電が行われたのは、震災直後の計10日間、延べ32回だけであった。それ以後は首都圏のみならず、日本全国で1回もない。原発事故の反省は何より重要としても、事故の余波を乗り越えた電気事業者の努力も正当に評価すべきではないだろうか。 電気というのは公共的な事業であり、電力が供給できないと生死に関わる事態も起きる。電気の安定供給のために、そしてトラブルが起きないように、起きた場合には速やかに解決できるように常に考え、訓練し、事業に当たらなくてはいけない。電力事業は、単に「発電装置を置いて送電する」ということだけではない。その使命を自覚し、人材の育成、技術の開発、安全の確保などに高い意識と能力、そして鍛錬が必要なのだ。事故以降、大手電力会社への批判が絶えない一方で、再生可能エネルギーばかりが過大評価されている現状は、そうした電気事業の根本を見えなくしているという意味で問題だと言わざるを得ない。 火力発電頼みでいいのか 原子力発電は、2011年東日本大震災の前、37基が動いていた。その後、順次定期検査に入り、2012年5月に北海道泊原発3号機が定期検査に入ったことによって、国内50基(福島第1の4基を除く)が停止をした。2か月後の7月、民主党政権下で当時の野田佳彦総理の判断により、福井県の大飯原発3、4号機が稼働。しかし、1年2か月後の2013年9月に同機が定期検査のため停止したのを最後に、2015年8月、鹿児島県にある川内原発が再稼働するまでの約2年は、国内で1基も原発が動いていないという状態が続いた。原発による発電が全くなかった期間である。 そこで大きく依存することになったのは、火力発電だ。2010年度は62%だった火力発電への依存度が、2013年度には88%まで増えた。特に40年以上前に整備された老朽火力発電の稼働は大幅に増加した。東日本大震災前は53基だったものが、2013年度には75%増の95基まで増加。稼働中の火力発電に占める老朽火力の割合も、機数ベースでは2010年度には15.4%だったものが2013年度には26.2%となり、特に石油火力が急増した。武豊火力発電も、その1つである。川内原発、福井県の高浜原発の計4基が再稼働した現在(その後、高浜原発は運転差し止めの仮処分)も、この状況は変わっていない。 「火力発電は、決まった耐用年数はなく、点検・補修を行いながら、簡単に言えば、『使えるまで使う』というものです。補修や機器の性能等を総合的に考え、使用継続や廃止を判断しています」(東京電力大井火力発電前所長・山崎賢一氏) 補修箇所などが多くなれば、それだけ費用もかさむし、また新しいものとでは熱効率も違う。川崎火力発電所のMACCという最新鋭の機種の熱効率は60%に迫るのに対して、昭和46年に運転開始した大井火力発電所1号機は40%程度だ。老朽火力は原発と比べると、出力が小さいものも多い。原発1基当たり概ね100万kWに対し、35万kW程度の老朽火力発電もある。 しかも、火力発電の燃料である石炭、石油、LNG(液化天然ガス)は、ほぼ全て輸入である。全原発が停止し、火力発電が増加した2013年度の燃料費の増加分は3.6兆円。これは2015年度の我が国の補正予算額とほぼ同規模である。例えば中部電力では、火力発電のためのLNG輸入は、2013年度では総量1,302万トン。これは、9万トン級タンカーでカタールから2~3週間かけて運んできたLNGを2日半で使い切るというペースである。今や、どの電力会社でも、経常経費に占める燃料費の割合は、約50%に迫る。当然のことながらCO2排出量も増えた。2012年度は、東日本大震災前の2010年度に比べ、29.9%増加。電気事業者以外の事業によるCO2排出量は減少しているため、全体では7.5%増にとどまっているが、発電のためのCO2排出量が大幅に増加したのは事実だ。 水力発電に期待するなら では、燃料費がかからず、CO2の排出量もない水力発電はどうだろうか。日本の大規模発電は、そもそも水力から始まっている。そのため水力発電も、老朽化その他の課題を抱えるところは少なくない。 国内に水力発電は大小合わせ、約2,000か所あるが、そのうちの静岡県大井川水系の計13の発電所、30のダム・えん堤(ダムより小さいもの)を例に挙げて考えてみたい。例えば、ダムの中に土砂がたまるという問題だ。大井川水系で現存する一番古い湯山発電所は昭和10年に運転開始した水力発電所だが、水源となる千頭ダムのダム湖内の堆砂率は98%にも上っている。 「ほとんど水は溜められない状況ですが、土砂が取水口を塞ぐと困るので、出水時には土砂を流下させたりしています。また別のダム(井川ダム)では土砂を袋に詰めてダム湖内の別の場所に移動させたりしています。河川は国や県の管理になるのでダムの中の土砂も公共の財産ということになり、勝手に掘削して外に出すということがでいないのです」(中部電力大井川電力センター所長・石黒幸文氏) ダムは本来水を貯める所だが、ダム湖の中は、ほとんど土砂なのだ。古いダムでは特に堆砂率が高くなっているが、全体的に見ても、堆砂率は平均40~50%程度である。近年、場所によっては、取り除いた土砂を道路整備資材等として使用するなど有効利用が拡大されているようだが、土砂の量が多いため、依然としてその多くが土捨場へ運ぶなどの対応にとどまっているという。 水力発電の維持管理に労力や費用がかかるのは土砂だけではない。全国の水力発電所では無人化が進み、平時はダム管理所にある制御室で遠隔でダムのコントロールを行っているが、天候の状況によっては、社員や作業員がダムまで足を運ばなければならない。一般の人は立ち入り禁止になっている奥地にあるような千頭ダムへ行くには、建設時に使用したトロッコの線路跡を舗装し車が通れるようにしただけの、かなり小さな軽自動車でないと通行できないような道を進む。左右は急こう配の崖で、雨の後には路上にもところどころ、岩ほどの大きな石や倒木があり、通行を妨げるものとなっている。いつ落ちてくるか分からないような岩や倒木を警戒しながら、少しでもハンドル操作を誤れば崖下まで一直線という6kmの道をひたすら進む。 「夜間であれば、車のライトを頼りに無線を持って2人1組で駆け付けます。天候も荒れる中を行くことになる場合もあるので、社員や作業員の身は本当に心配です」(石黒氏)
まさに命懸けである。 そもそも、ダムの土砂が増えたのも、発電所までのアクセス道が荒れ放題なのも、周辺の山の地質変化も大きな要因だが、ダムがある山林で国が間伐などの手入れを怠ってきたこと、さらには林業が産業として衰退したことに大きな原因がある。国土保全の観点からの抜本対策が欠けているのだ。 水力発電が電源構成に占める割合は、2013年度で8.5%。新たなダム建設も容易ではない中、究極の自然エネルギーとして水力発電を活用するのなら、まず山の手入れから始めなければならない。それは国が国土保全をどう考えるかということも含め、政策としてどう位置付けるかということに関わってくる。電気事業者が考える範疇を超えているのだ。 「反原発」を言える立場か 東日本大震災から5年、原子力発電所の、避難を擁する大事故を初めて体験した我が国において、今、私たちは何を考えるべきであろうか。 原発のメリットは何より、「国産」電力が安定的に供給されるということである。原料のウランこそ輸入だが、ウランから作る燃料棒は国産である。日本のエネルギー自給率は原発が止まった今、わずか6%。エネルギー消費量では世界第5位であるにもかかわらず、だ。そもそも、戦後、原子力発電を日本で導入したのには、安定的な電力の供給こそが、敗戦からの復興する上で欠かせないものであったからであり、また原子力の平和利用は、重要な国策でもあったはずである。もちろん、核という危険物を扱う以上、より慎重な運用は必要だが、福島の事故が起きたからといって、もう原発を使うべきではないというのは、あまりにも短絡的な発想に過ぎない。まして、多少の節電意識の向上はあっても事故前とほとんど変わらない電気の使い方をしている国民に、「反原発」などと言える立場かと言いたい。 事業者も、そして私たちも「まさか原発が爆発することはないだろう」と思い込んでいたことは事実であり、それは過ちであった。たとえ想定外の津波があったとしても、そこは反省すべきことである。しかし、電力をどのように作っていくかということには、国家の安全保障という観点からも考えなくてはいけないのだ。また安全で効率的な運用のための知恵の結集や技術の研究・開発が国力を向上させていくのである。 原発だけにこだわればいいというのではない。日本では景観や音の問題などから、欧米に比べ普及が進まず0.5%にとどまる風力発電についても、海に囲まれた地形を生かせば、洋上風力など将来性はかなりあるものだという話も聞く。シェールガスやシェールオイルの開発など、新エネルギーの可能性に期待も集まる。メタンハイドレードやレアアースなどの海底資源の研究や開発にも力を注ぎ、安定した良質の電力をつくる原料となるのなら、こんなに素晴らしいことはない。昨今の技術開発の速さを考えると、そんな時代もあっという間に来るかもしれないということも、常々感じる。 ただ、今すぐにそれが可能かといえば、どれをとっても不可能だ。火力発電の原料となる原油や石炭、LNGが世界情勢の変化の中で、もし運ばれなくなったらと考えると、恐ろしい限りである。この5年間は実は綱渡りの状況であって、とても「原発がなくても何とかなっている」ということではなかったのだ。電気を安定的に得るためには、原発を安全に運用しながら、他のエネルギー源をバランスよく構成し、そして将来へ向けた研究・開発を行うという冷静な判断こそが必要である。
|
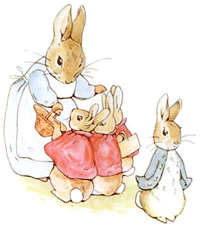
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。