http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/465.html
| Tweet |
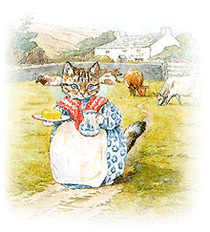
政府、もんじゅ廃炉で最終調整
http://gansokaiketu.sakura.ne.jp/20160913-seifu-monjyu-hairode-saishuuchosei--kyogakutuika-hiyoude-seifu-handan.htm
もんじゅ廃炉で最終調整
巨額追加費用で政府判断
政府は12日、原子力規制委員会が運営主体の変更を求めている日本原子力研究開発機構の高速増殖炉もんじゅ(福井県)を廃炉にする方向で最終調整に入った。再稼働には数千億円の追加費用が必要となり、国民の理解が得られないとの判断に傾いた。核燃料サイクル政策の枠組みの見直しは必至で、関係省庁で対応を急ぐ。
所管の文部科学省は、規制委から運営主体の変更勧告を受け、原子力機構からもんじゅ関連部門を分離し、新法人を設置して存続させる案を今月に入り、内閣官房に伝えた。しかし、電力会社やプラントメーカーは協力に難色を示しており、新たな受け皿の設立は困難な情勢。
- 高速増殖炉“もんじゅ”廃炉を視野に検討:再処理やプルトニウム保有が認められなくなった状況では存続はムリ あっしら 2016/9/13 20:12:16
(0)
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素46掲示板 次へ 前へ
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。